皆さん、こんにちは。
終活カウンセラー協会の講師をしている小川朗です。
終活カウンセラーとして活動していると、よく耳にするのが「介護には、終わりが見えない」という言葉です。
日常生活のなかで介護をするという重いテーマを一人で抱え込むことの大変さを、言い表している言葉のようにも思えます。
誰もが自分の死を予測できないのと同じように、介護される側にもする側にもそれは、当てはまるのです。
そのこと自体に悩み、疲れ果ててお母さまとの心中を考えた元同僚のケースを、私は第93回で書きました。
しかし、1対1ではなく複数で、その思いを分け合い、負担を少しでも軽くできるケースも世の中には存在します。
先日、出版社勤務のAさんにお父さまの介護について取材したときに、そのことを痛感しました。
今回は、お父さまの介護を3兄弟で協力して行った、Aさんとそのご家族の話をいたします。
介護をするAさんご家族の状況~3県にまたがる3兄弟と一人暮らしのお父さま~
三男のAさんには4歳上の長兄と、2歳上の次兄がいます。
Aさんは埼玉県在住で、長兄は千葉県在住、次兄は栃木県在住です。
3兄弟のお母さまが63歳で亡くなったとき、10歳上のお父さまは元気でした。
悲しみのなか、お父さまは栃木の自宅で一人暮らしをスタートさせました。
最も近くに住んでいたのは自営業の次男で、市内で歩いて10分、車なら数分の距離でした。
3兄弟にとってお父さまは、どんな父親だったのでしょうか。
食品関連の大手企業で経理を担当。
戦時中は中国大陸のトラック隊に召集され「俺は人を殺したことがない」というのが自慢だったそうです。
最近の朝ドラでも流行りの「ちゃぶ台返しも良くやった」そうです。
激動の昭和を駆け抜けた24時間働く男、そんなイメージでしょうか。
国内の転勤も多く、Aさんは福岡勤務時代に誕生しています。
お父さまは「考え方が進んでいる」タイプであり、絵が好きで、海外旅行にも1人でよく出かけていたといいます。
またボランティアとして、市の活動にも参加していました。
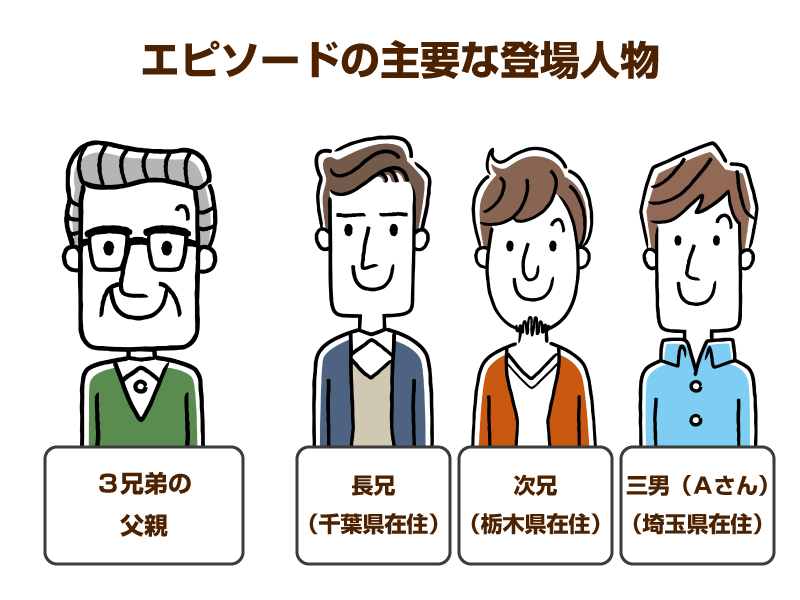
お父さまが認知症に。そして介護がスタート
そんな暮らしが10年ほど続いた頃、Aさんはお父さまとの会話のなかに、ある種の違和感を感じます。
「あまりにも場違いな、ピントが外れた話を始めたんです。これはおかしいな、と思いました」
85歳のお父さまは軽い認知症を発症していました。
介護認定を受けたときは、最軽度の要支援1でした。
徘徊などの問題行動はなかったものの「一人にしておくわけにはいかんだろ」となり、3兄弟は本格的に介護について話し合いました。
最初は長兄とAさんが1週間、それから次兄が近くに住む自宅で2週間 、という半介護的な生活がスタートします。
お父さまはAさん宅にいるとき、体力低下を予防するため週に3回はリハビリセンターのデイサービスに参加していました。
残りの4日は家で留守番をしながら「新聞の同じところをずっと読んでいたり、漢字パズルをしたりの生活」を送っていました。
しかし90代に入ってから排尿が困難になり、尿道にカテーテルを挿入するようになって、認知症もさらに進行していきます。
そこで2週間ごと順番に、3兄弟の自宅で介護することとなりました。
「1週間ごとならそれぞれの負担は軽くなるかもしれないが、親父の方も落ち着かない、ということもありました」(Aさん)
順番が中2週間で回って来るよりは、中4週間の方が旅行などのスケジュールが入れやすい、という側面もあるでしょう。
介護の負担も、老老介護などの場合にくらべ大きく減らされているように見えます。
関東エリアの隣り合う3県の、そう遠くない距離に3兄弟が住んでいて連携を取りやすかった地の利も見逃せません。
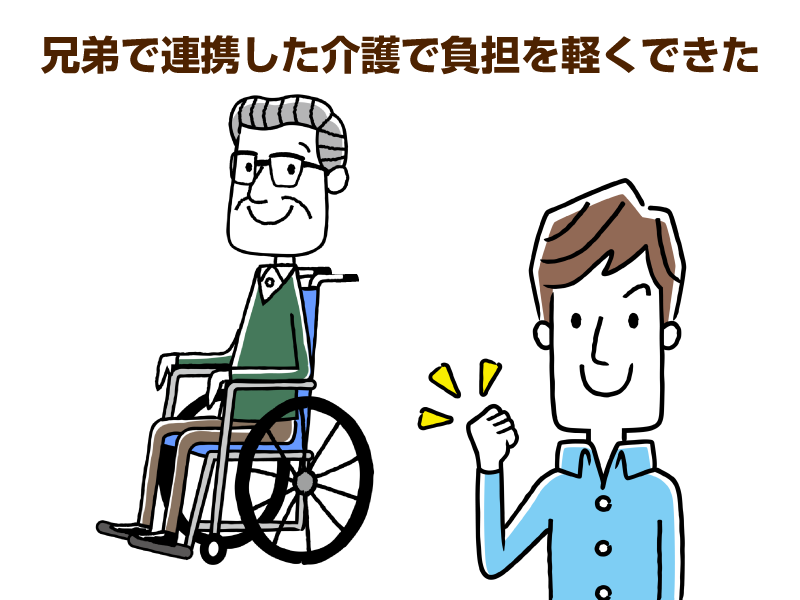
3兄弟はまだ現役で働いています。
介護に専念するわけにもいかず、3兄弟の奥様方へと、介護のウエイトがかかっていくことにもなります。
Aさんの家にも、数週に一度、父親がやってきます。
日中はAさんの奥さんもパートに出ており、義理のお父さまはデイサービスへ。
認知症もそれほど進行せず、平穏な生活が続いていたと言います。
しかしこの後、足がむくみ始め足を患い、あまり動けなくなってしまいます。
Aさんもカテーテルを入れているお父さまと、一緒に入浴することも多くなります。
大変なのは、1ヵ月ごとにやってくるカテーテルの入れ直し。
尿道に差し込む際の激痛に、お父さまは痛みのあまり大声で叫んでいたと言います。
認知症の進行と入院、最期
認知症が進行し、お父さまはAさんのことも、わからなくなっていきます。
「やはり介護で一番大変なのは、下の世話ですよね。下痢をしてしまい、気付かぬままにベッドを汚してしまうことも多くなりました」(Aさん)
お父さまの頭がしっかりしているときにそうしたことが起きると、おむつや汚れたものを隠したりしていたそうです。
そのため、大型犬用のトイレシーツをベッドに2枚敷いておくなどの工夫をするようになりました。
その後、元々エアコンが嫌いで使わない方だったお父さまは、熱中症になったことをきっかけに入院生活となってしまいます。
長兄の自宅に近い千葉県内の病院で、リハビリ生活を送るようになりました。
結局お父さまは101歳まで長生きし天へと召されました。
今のAさんの思い
Aさんから見せていただいたスマホの写真の中で、お父さまは笑っていました。
一緒に散歩したときに撮った、在りし日の1枚です。
Aさんは、今も時々、この画像を開いて見るそうです。
「関東3県にまたがる3兄弟の奇跡」。
取材の途中、こんな言葉が思い浮かんでいました。
お父さまが亡くなった今、Aさんの思いについて聞きました。
Aさんは、介護の当初は「それまでの父親との関係があるために腹立つことがあると、怒鳴ってしまうこともあった」そうです。
しかし、介護をするうちに考えが変化します。
「そのうちこっちも悟りを開かされる。極力笑顔で対応すれば、親父も笑顔で返してくれる。最後の方は、そういう関係になれたと思う」とおっしゃっていました。
スマホのなかのお父さまは、今日も笑っています。
その視線の先にあるのは、Aさんの笑顔。
悩みや苦労を分かち合う理想形が、ここにある気がします。




















