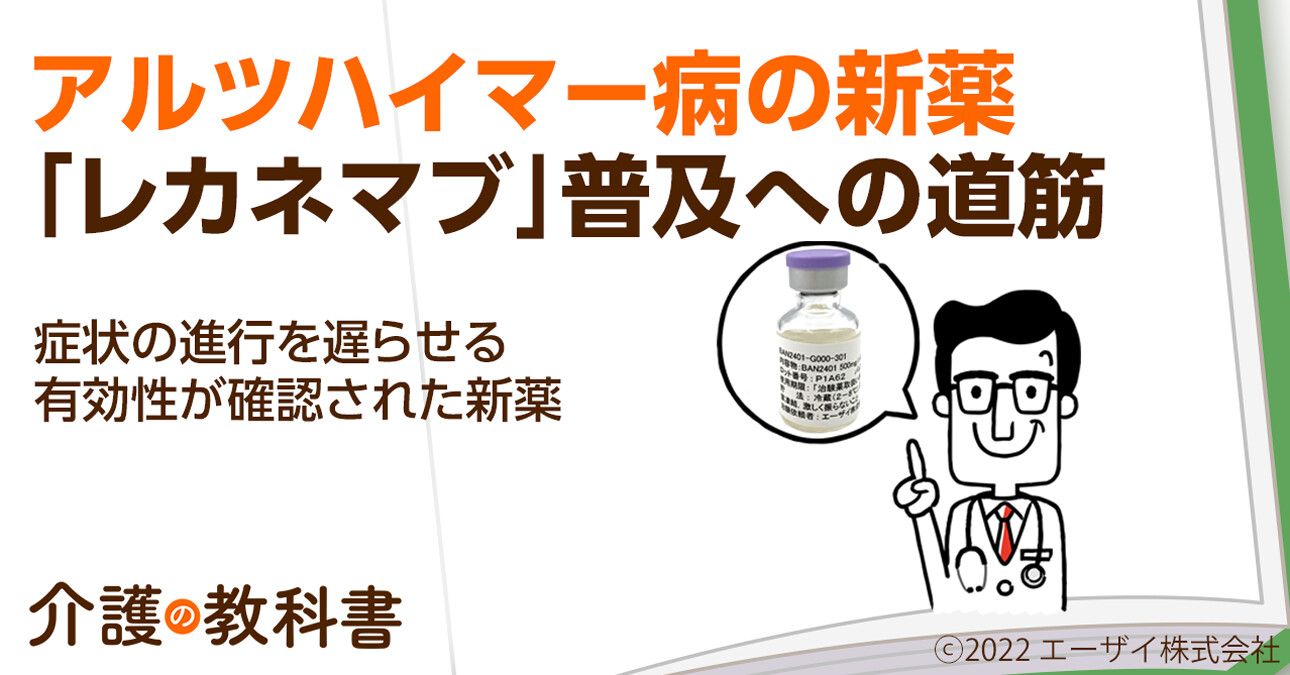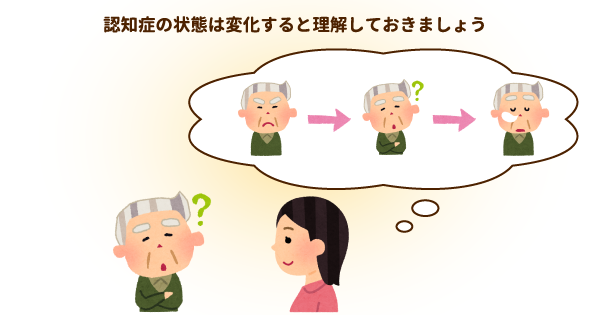こんにちは。一般社団法人元気人の向川 誉です。
今回は「認知症予防と睡眠」がテーマです。
日本人の睡眠時間が世界的に短いことはよく知られていますね。
現代社会では忙しさで生活習慣を乱しやすく、そのしわ寄せの多くは「睡眠」にきています。
「国民健康・栄養調査(平成29年、厚生労働省)」によると、40代の半数ほどが「6時間未満の睡眠」というのが現状です。
また、「睡眠で休養が十分にとれていない者」の割合も、2009年以降から増加傾向にあります。
睡眠の質と量が悪い状態が続いてしまうことで、脳の働きが低下することは誰もが実感していると思うのですが、最近の研究では“認知症の発症リスクを高めること”も明らかになっているのです。
40代以降は「睡眠」が最優先課題に!
認知症の半分近くはアルツハイマー病によるものが占めているので、認知症予防はアルツハイマー病の予防からスタートします。
アルツハイマー病の原因物質として考えられているのがアミロイドβというタンパク質です。
このアミロイドβは脳の活動によって生産されるため、高齢者だけでなく、若い人の脳内にも存在しています。
通常は脳内のゴミとして排出されていますが、アミロイドβが集まって塊になることで神経細胞が破壊され、記憶障害などの症状を引き起こしてしまうと考えられているのです。
アメリカの研究によると、健常な人とアルツハイマー病の人とでは、アミロイドβの“生産量”にはさほど違いがなく、“排出する力”に差があることがわかりました。
つまり、このアミロイドβを排出する力がアルツハイマー病の予防では重要なポイントだと言えそうですね。
人が起きているときも脳内の老廃物は排出されていますが、アミロイドβの排出が促進されるのは「睡眠時」であることも、同じ研究から明らかになっているのです。
また、アメリカの別の実験では、「一晩眠らないだけでもアミロイドβが増える」という報告があります。
なお、アミロイドβが一時的に増えても、それで認知症のリスクが一気に上がるわけではないので、一晩うまく眠れないからといって心配になる必要はありません。

ただ、不眠や睡眠不足が慢性的に続くと、アミロイドβが排出されず蓄積していく。
つまりアルツハイマー病を発症しやすいことになるのです。
アミロイドβは特に40代以降から蓄積しやすくなると言われています。
人生100年時代では、認知症の発症時期をいかに遅らせられるかが大切になってきますが、40代以降の人にとっては、「睡眠」は最優先の課題と言えるでしょう。
孤独感が認知症の発症リスクが増大する可能性も!?
人が孤独を感じているときと、痛みを感じているときに働く脳の部位は同じだと言われており、孤独感は精神面だけでなく、身体の健康にも影響を与えるのです。
孤独感を抱えていると、早死や依存症、ストレス関連の病気につながるリスクがあるほか、将来の認知症リスクを高めてしまうことが指摘されています。
認知症予防では、人との交流で充実感を得ること、すなわち孤独感の解消が大切になってきますが、アメリカの研究によると、人が孤独を感じる要因のひとつに「睡眠不足」があるとわかりました。
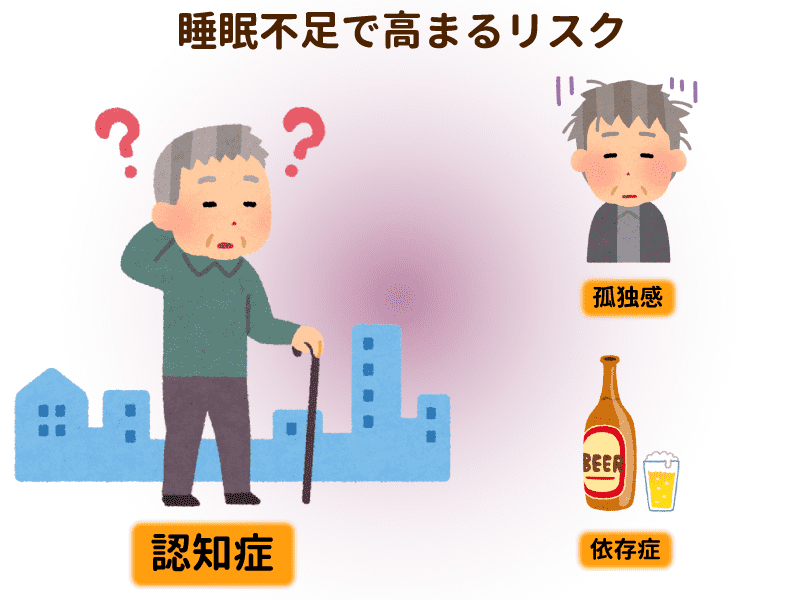
その人の価値観で孤独を好んでいる場合は別ですが、「何となく人を遠ざけたい」と感じる人は、寝不足が原因でそのように感じている可能性があるのです。
しかし、人を遠ざけてばかりの状態が続くと、閉じこもりや社会的な孤立に陥りやすく、死亡リスクや認知症の発症リスクを高めることになります。
最低でも6時間以上眠るようにしよう
アルツハイマー病に次いで多い認知症の原因は脳血管障害ですが、中年期の肥満、糖尿病、高血圧などの生活習慣病が影響しています。
睡眠不足は生活習慣病の発症リスクを高めることがわかっており、この生活習慣病は40代~50代にかけて急増しています。
認知症の原因物質と考えられているアミロイドβが蓄積し出すのも40代以降ですので、睡眠による認知症予防を考えるのであれば、この年代から手を打ちたいところですね。
まずは自分でできることから改善していきましょう。
睡眠は人として最も基本的な欲求のひとつですが、その大事な睡眠をきちんと確保するために、時間の使い方から見直す必要があります。
つまり、睡眠の優先順位を最優先にし、そのとおりに実行するのです。
例えば、スマホ操作や読書は脳を刺激したり、興奮させたりします。夜の時間になったら、それらを控えて睡眠を優先しましょう。
福岡県の久山町で行われた調査研究によると、高齢者(日本人)において認知症の発症リスクを高めるのは、「睡眠時間5時間未満、もしくは10時間以上」だとわかりました。
厚生労働省が2014年に発表した「睡眠指針」によると、健康な人の睡眠時間は「40代で約6.5時間」、「60代で約6時間」が目安となっており、別の研究報告も踏まえると、最低でも6時間以上は眠るようにしましょう。
また年をとると、睡眠時間が少し短くなるのは自然であることと、必要な睡眠時間は人それぞれで、日中の眠気で困らない程度の自然な睡眠がその人にとっての最適であることは、知っておくとよいでしょう。

忙しい現代人が自分にとって最適な睡眠時間を確保するには、どうしても最初はかなりの努力が必要になります。
しかし、その努力も続けているうちに習慣となり、習慣となれば、それだけ効果が期待できるのです。
習慣化のためにも睡眠改善の取り組みを早めにスタートすることが望ましいですね。
よく眠るための7つの習慣
以下に「よく眠るための7つの習慣」を記載していますので、参考すると良いでしょう。
よく眠るための7つの習慣
- 昼間は日光を浴びる
- 昼間の日光で、眠りを導く「メラトニン」というホルモンの分泌が増える
- 夕方以降、コーヒー、紅茶、緑茶を飲まない
- カフェインの目覚まし作用の影響を避ける
- 夕食時のアルコールは適量にする
- 飲酒していると、浅い眠りになりやすいため、飲み過ぎないようにする
(グラス1杯程度がのぞましい)
- 夕方の運動をする・ぬるめのお風呂に入る
- 身体が温まって、その後下がるときの放熱で眠気が強くなる
- 眠くなってから布団に入る
- 「寝なければならない」という焦りは逆効果、眠れないなら起きてしまうのも手段のひとつ
(数日うまく眠れなくても、気にする必要はありません)
- 朝は決まった時間に起きる
- 夏でも冬でも同じ時刻に起きる、休日の寝だめ(遅起き)も避ける
- 午後の決まった時間に30分ほど昼寝をする
- 30分ほどの昼寝は認知症の発症リスクを抑える研究報告がある
(1時間以上だと、逆に高まるおそれあり)
睡眠の悩みがあれば医師に相談
自分の睡眠状態に悩んでいる場合、医師に相談することも大切です。
睡眠時無呼吸などの眠りの質を損ねる病気がないか、常用している薬の影響はないかチェックしてもらうと良いでしょう。
不眠は認知症の危険因子なので、不眠の悩みが続く場合、睡眠薬やCBT-I(薬を使わない認知行動療法)を検討するのもひとつの手です。
病院で処方される睡眠薬については、動物実験や臨床試験を経て安全性が確認されていますので、短期間の服薬であれば、睡眠薬で認知機能の低下が進むおそれはありません。
また、60代以降の方にとっては、現時点までのアミロイドβの蓄積量を考えると、睡眠の改善だけで認知症を予防するのは難しいと思われます。
睡眠の改善と同時に、頭を使って神経ネットワークを強化すること、すなわち「認知力の蓄え」を増やすことも心がけたいところです。
アメリカのある修道女の事例では、萎縮がみられるなど脳はアルツハイマー病の状態でしたが、生前は認知症を少しも感じさせない生活をされていた方がいらっしゃいました。
その方はアルツハイマー病に打ち勝ったといえますが、その理由のひとつは認知機能を使う生活を日頃からされていたからと考えられています。
新しいことにチャレンジしたり、たくさんの人と交流したり、五感を刺激して感情豊かに過ごしたりすれば、脳の神経ネットワークは強化されます。
また、このような活動的な生活は心地よい疲れとなって、自然と良質な睡眠に導いてくれることでしょう。