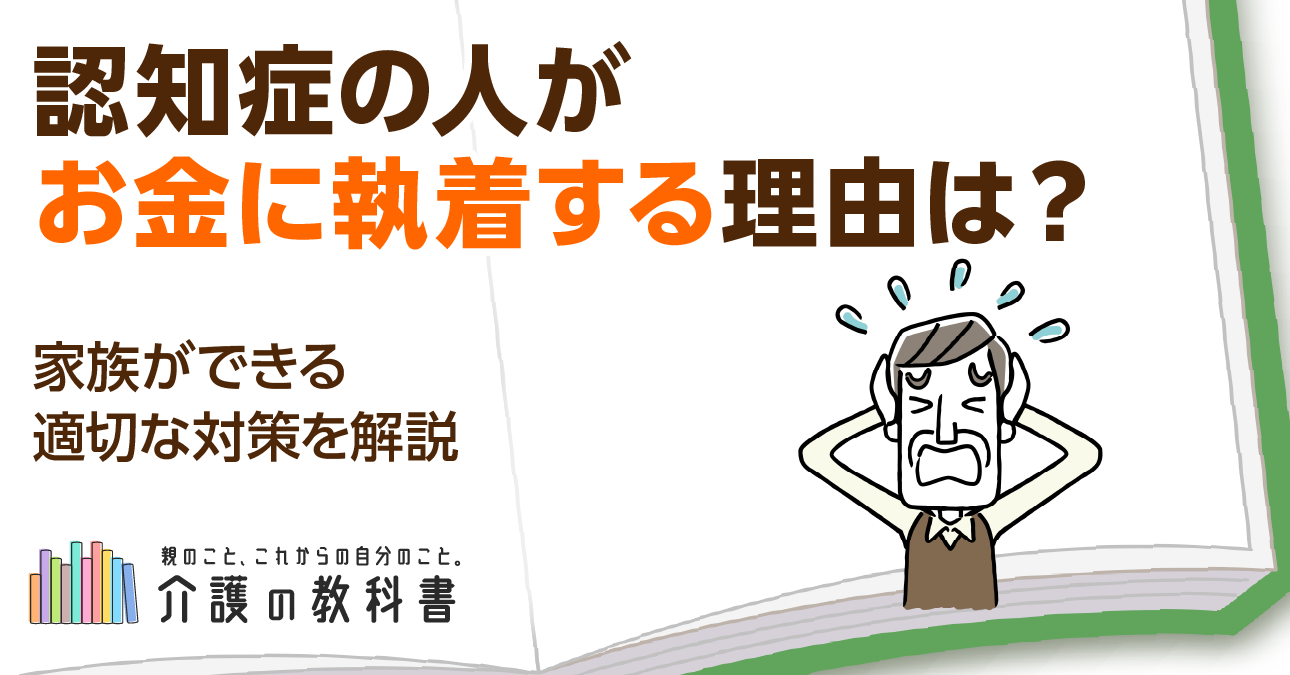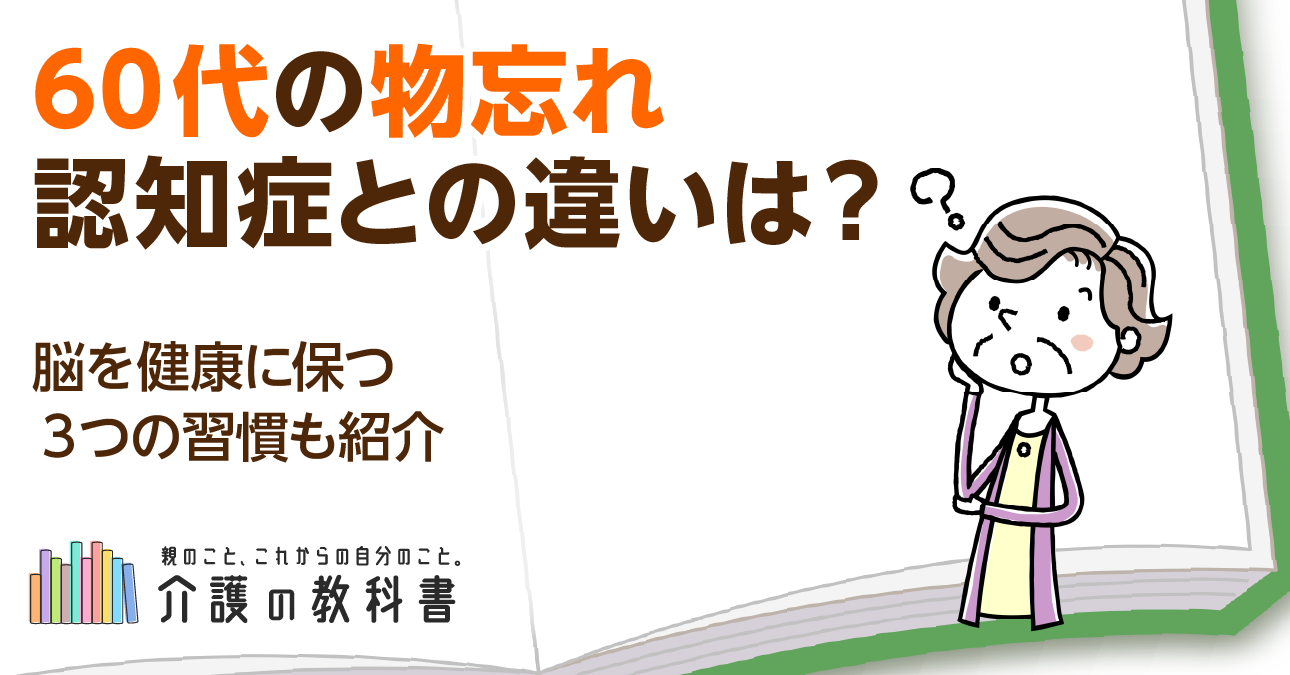こんにちは。介護老人保健施設「総和苑」で介護課長をしている高橋秀明です。「介護の教科書」では引き続き「認知症」だけに焦点をあてるのではなく、「人の想いを考えていくことの重要性」についても触れていきます。
今回は「認知症と徘徊」を考えていきます。今年3月、ある全国紙が「徘徊と呼ばないで」というコラムを掲載し反響を呼びました。高齢になるほど認知症になるというデータがあるように、認知症の最大の発症リスクは加齢と言われています。長寿化が進むこの国では、認知症は特別なものではありません。私たちは認知症と共に歩むときを迎えています。
そんな中、避けては通れない社会的課題が「認知症と徘徊」です。認知症の状態にある方が外出したまま行方不明となったり、電車の事故にあったりと心を痛めるできごとがこの国では起きています。このテーマは一概に答えが出せるものでもないですが、読んでいただくことで考えるきっかけにしていただけるとうれしく思います。
認知症の状態でも判断することはできる

認知症の状態にある方が「道に迷い自宅などに戻れないこと」や「施設内をウロウロと歩きまわること」を"徘徊"と表現している記事やニュースをよく目撃しますが、みなさんは徘徊という言葉の意味を知っていますか?
徘徊を辞書で調べると「目的なく、うろうろ歩き回ること(大辞林)」とあります。私が思うに、認知症の状態にある方は何もわからない人、困ったことをする人と捉えられてきた時代がありました。そういった歴史的背景があり「目的なく、ウロウロ歩き回る」のが認知症状と捉えられ、「徘徊」と表現されてきたのだろうと考えます。
以前、アルツハイマー型認知症の状態であるフユコさんが病院に入院する際に、病院の看護師さんが僕に「この方は徘徊しますか?」と質問をしてきたのですが、それがフユコさんご本人に聞こえてしまい「馬鹿にしないで。徘徊なんてしません!」と間髪入れずに答えたことがあります。
認知症の状態は「何もかもわからなくなっているわけではなく、わかりづらくなっているだけ。わかることもたくさんある」が正しい認識です。私たちが何気なく使っている徘徊という表現に心を痛め、傷ついている方がいることを忘れてはなりません。
徘徊=認知症の症状ではない
専門職の皆さんに考えていただきたい事例があります(専門職以外の家族の方も参考にしていただければと思います)。
僕が施設に入職をして1年が過ぎた頃、こんな場面がありました。アルツハイマー型認知症状態にあるナオコさんが不安そうな顔つきで眉間にしわを寄せ廊下を歩いていたのです。そこにたまたま通りかかった相談員と僕のやり取りが以下です。
- 相談員「ナオコさんは何かあったのかなぁ?ずっと歩き続けているけど…」
- 高橋「ナオコさんは徘徊しているだけですよ。だって認知症ですから。いつもだから大丈夫です」
- 相談員「……」
それからしばらく経ったある日、認知機能にまったく問題がないヨシコさんが、不安そうな顔つきで眉間にしわを寄せ廊下を歩いていました。僕は「何かあったのかなぁ?」と心配になり、「ヨシコさん、どうされました?」と声をかけました。
2つの対応に、皆さんは何か感じませんか?僕は認知症状態のナオコさんが歩いている=徘徊と決めつけてかかわろうとすらしなかったのに、認知機能に支障のないヨシコさんには「何かあったのだろう」と考え関わりを持っている。「徘徊は認知症の症状」と捉えることにより、まったく同じシチュエーションでもこのように考え方や関わりに差が生まれてしまうのです。
認知症の状態の方に対して介護者ができること
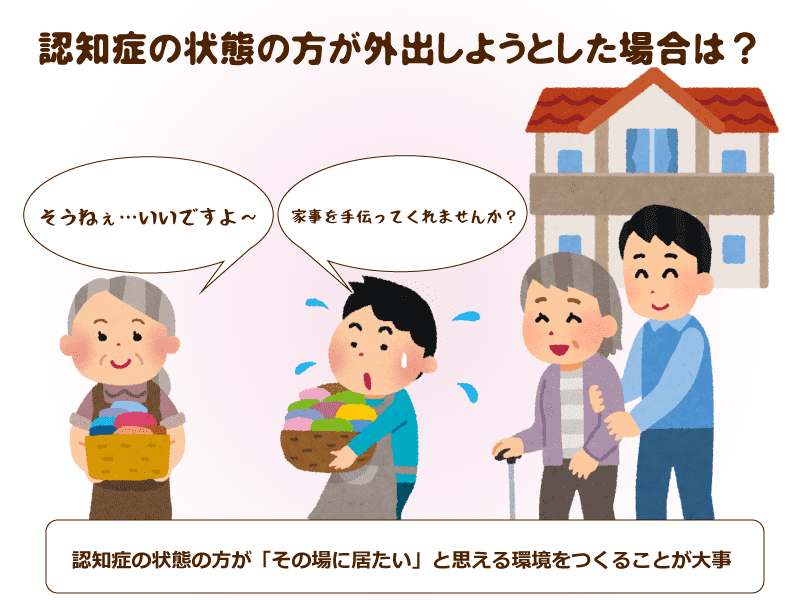
私たちは「今日は6時に起きて、8時に会社へ行き、14時に会議室で〇〇さんと会って、18時に退社して自宅に帰る」というように、時間・場所・人の中に自分を位置づけ、記憶しながら生活を送っています。時間や場所の把握、人の認識力、記憶、理解・判断力などの低下がないために日常生活に支障はありません。
しかし、認知症になると中核症状(第20回参照)という状態になってしまいます。これによって、見当識障害で「今がいつで、ここがどこで、目の前の人が誰か」がわかりづらくなり、さらに記憶障害で「何を目的に行動をしたのか忘れてしまう」ことがあるのです。これによって、以下の事象が起きてしまうことがあります。
- 施設に入居したことを忘れ、自分の家に帰ろうとして歩いている
- おしっこをしようとしてトイレを探している最中に、自分がおしっこをするという目的を忘れ歩き回る
- 家事をしていないのに、家族にご飯を作らなきゃいけないから帰ると言って歩いている
- (過去に農業を営んでいた方で今は引退しているのに)「田んぼの様子を見に行かなきゃ」と言って外に行こうとする
- 「会社で重要な会議があるから」と言って、歩いて外に出ていこうとする
他にもあるでしょうが、挙げるとキリがありません。
理由は違えども、必ず本人なりの意味や目的があるということは共通して言えること。しかし、目的自体を忘れる(記憶障害)、今どこにいるかがわからなくなる(見当識障害)、赤信号を渡ってしまう(理解力、判断力の低下)などが考えられるために、道に迷ってしまったり、少し間違えると交通事故につながるリスクを抱えています。
だから、認知症の状態の方を介護する人は、常に監視(見守り)の目を持ち続けなければならず、精神的負担や疲弊感から心に余裕がなくなるのだと思います
認知症の状態の方が外出したときに介護者ができること
本人と一緒に外を歩いてみる(後ろからこっそりと見守る)
認知症の状態の方が外出することを止めた場合、本人が怒ることがあります。なので、本人がしたいことを否定せずに、付き合うことが大事です。しばらく歩くと「そろそろ帰るか」と穏やかに話してくれるでしょう。
専門職の皆さんはこのとき、ただ一緒に歩くことが目的となってはいけません。一緒に歩きながら「なぜこの人は外を歩きたいと言ったのか、どこを目指して歩いているのか、しばらく歩いたら「戻ろうか」と言ったのはなぜなのか」を本人の視点に立って考えながら一緒に歩くことが大事です。
本人がその場に留まろうと思える目的や意思をつくる
本人が「その場に居たい、居よう」と思える環境をつくることも、認知症の状態の方の外出を防ぐ行為の一つです。例えば、家事が得意だった方に「今、お天気が良いので洗濯物を干すのを手伝ってもらえませんか?」とお願いしてみることで、「そうねぇ」と言ってその場に留まってくれたことがありました。人によって興味があることが違いますし、そのときに抱えている感情も違います。これを正しく理解するには、その人のことをよく知っていないとできることではありません。
一方で、介護者が本人を叱責、否定するなどして本人が「ここから逃げ出したい」「こんなところに居たくない」「不安でしょうがない」といった感情から、外に歩き出すということもあります。適切な環境設定やかかわりというのは大切なことです。
突然の行動・心理症状はお年寄りからのSOSサイン

認知症の状態であるキヨシさんは妻と二人で自宅での生活を送っていて、近くに住む長女さんがキヨシさんご夫婦の様子を定期的に確認しています。
キヨシさんは日課で散歩に出かけますが、ときどき自宅に戻れなくなり、長女さんから僕の知り合いの事業所に「父がいない」とSOSの電話があるそうです。その事業所の職員さんたちは、キヨシさんの生活史をヒントに探しに出かけます。そのときは、「毎日のように将棋を指しに行っていた」という情報をもとに将棋クラブ付近を探し、本人を発見することができたそうです。
別のケースでは、夫と二人暮らしの認知症の状態であるタマコさんの行方がわからなくなりました。タマコさんが以前犬の散歩に近所の公園に行っていたことを思い出し、夫が公園付近を探したところ、タマコさんを発見することができたのです。
認知症の状態は「不安と恐怖」道に迷ったときを想像しよう
10年前の話です。僕は、海外に行き滞在先のホテルから買い物をするために外出をしました。 目的地にはタクシーで行ったのですが、そんなに遠いところではなかったので、「歩いて帰ろう」と滞在先のホテルに向かいました。しかし、いくら歩いても滞在先のホテルにたどり着けず、道に迷ってしまったのです。焦りと不安な気持ちが募りました。
1時間ほど歩きましたが、今自分がどこを歩いているのかがまったくわからない。徐々に陽が落ちてきて、周辺が暗くなったときには、「これはマズイ」と心臓の鼓動が激しくなり、「このまま帰ることができなかったら…」と大きな不安感と恐怖感から身震いが止まりませんでした。認知症の状態にある人も、もしかしたら僕が海外で経験したような不安感と恐怖感を持ち続けながら歩いているかもしれません。
認知症の状態の方がとる行動には意味がある
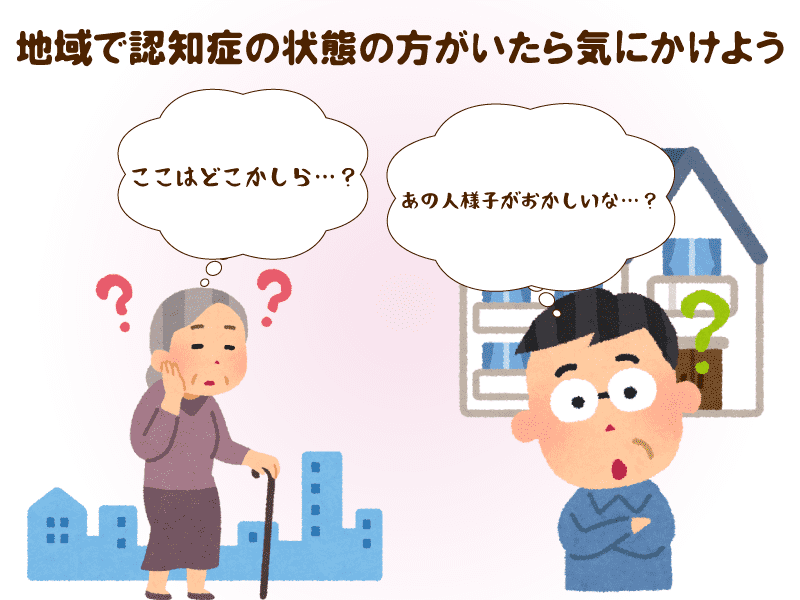
不自然な様子が窺える
- 左右チグハグの靴を履いている
- 服装がチグハグ(例えば上パジャマ・下ジーンズで服装バランスがおかしい、パジャマで歩いている、季節感に合わない服装など)
- ボサボサの髪型
- キョロキョロ辺りを見渡し歩いている
- あまり人が通らない場所を歩いている
- 夜に一人で歩いている
危険認識に疑問を感じる
- 車道を歩いている
- 炎天下にもかかわらず日よけせずに歩いている
- 道端に座り込んでいる
- 雨の中、雨具を使わずに歩いている
困っている様子が窺える
- ウロウロと同じ場所を歩いている
- 質問に戸惑いが多く「わからない」と答える
- 交差点などで戸惑っている
以上のような人は、道に迷って困っている方かもしれませんので、気にかけて様子を見てあげてください。そして声をかけるときもポイントがあります。
- 相手の視野に入ったところで声をかける
- 大勢で囲まない
- 相手の目線に合わせて穏やかなトーンで、でもゆっくりはっきりした口調を心がける
- こちらが一方的に話すのではなく、相手の話にも耳を傾ける
声をかけるときは、以上のようなことを意識してみてください。
認知症の状態にある方の「徘徊」といわれるものは、家族だけで対処するのではなく、地域で見守るものだと考えます。認知症になっても安心して過ごせる地域を創ることは簡単なことではありません。
しかし、一つひとつは小さな力でも、それが積み重なると大きな力となることがあります。認知症は他人事ではありません。難しいからと言って割り切る・あきらめる・嘆くに終始するのではなく、地域の方々や行政、専門職などが語り合い知恵を出し合って考えていくことが、安心して過ごせる地域づくりの第一歩になると考えます。