こんにちは。一般社団法人元気人の理事・向川 誉です。当法人では、認知症ゼロ社会の実現を目指して、地域の認知症予防活動をサポートする「認知症予防活動支援士」の育成と支援に力を入れております。
私は仕事柄「認知症予防」と名のつくものがあれば、目を通すようにしています。最近では「認知症予防には〇〇が効く」「〇〇を食べて認知症予防」など、認知症予防を扱ったテレビ番組や特集記事を、よく見かけるようになりました。
認知症予防について国民的に関心が高まるのは良い傾向なのですが、いくつか誤解が生まれているのも感じます。誤解したまま認知症予防を実践する人が増えることで、かえって混乱が生じることも考えられます。今回は、「認知症予防にまつわる誤解」をテーマに、認知症予防の理解を深めていきたいと思います。
認知症=アルツハイマー型認知症…ではない!
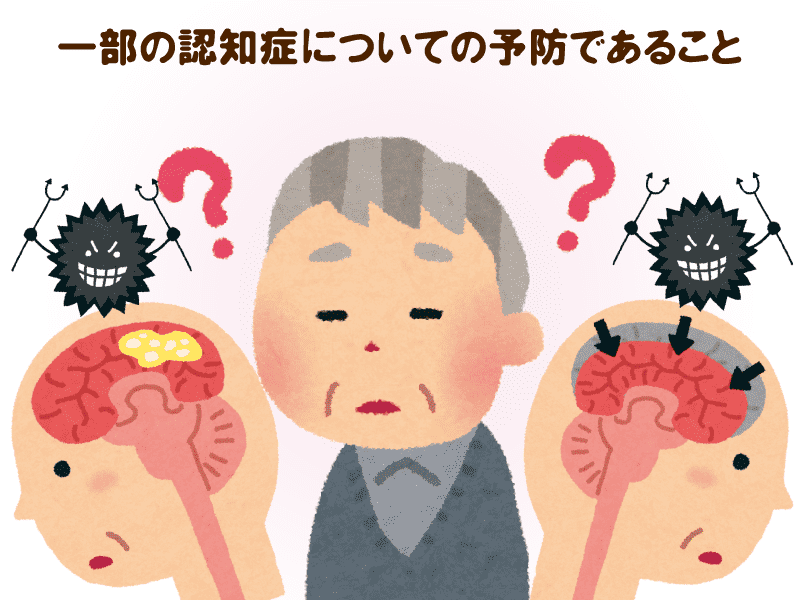
「認知症」は、病名ではなく何かの病気によって引き起こされる症状や状態を総称したものです。認知症の原因となる病気は70種類以上あると言われています。また、認知症は一つの原因によってもたらされるだけでなく、ときには複数の原因が組み合わさっている場合もあります。
認知症を引き起こす病気の中でも、アルツハイマー病が割合の半数近くを占めています。また認知症と言えば、一般的に加齢とともにもの忘れが酷くなり、だんだんと日常生活ができなくなるというイメージがあります。これはアルツハイマー病による認知症の症状とよく合致しています。
そのためか、メディアや一般の人々が「認知症」という表現を使うときは、「認知症=アルツハイマー型認知症」と読み替えているケースがみられます。つまり、適切には「アルツハイマー型認知症」と表現すべきところが、「認知症」となっている場合があるのです。
これは認知症予防においても同様です。発症する人が多いアルツハイマー病は研究対象になりやすく、その予防法が明らかになってきています。脳血管性認知症では、生活習慣病との深い関係が指摘されています。しかし、レビー小体型認知症のように、発症のメカニズム自体が未解明のものもあります。
「認知症予防につながる〇〇」とあっても、それは研究で明らかになった一部の認知症(アルツハイマー病など)についての予防であって、それが”すべて”の認知症に効果的だとは限らないのです。
例えば、アルツハイマー病の予防に積極的に取り組んでいたとしても、別の原因による認知症(レビー小体型認知症)になる人はおり、また、加齢は最も知られているアルツハイマー病の危険因子でもあります。原因となる病気が異なれば、予防も治療も異なるため、日常生活で何か違和感を感じたら、早めに専門機関に受診することが大事になってきます。
認知症予防に100%はない!

認知症予防につながる四大原則として…
- バランスのとれた食事
- 適度な運動
- 知的活動
- 人とのつながりを保つこと
が推奨されています。
これらは脳の健康に限らず、長生きにつながる健康習慣でもあります。ですが、80歳を超えると5人に1人、85歳を超えるとおよそ2人に1人が認知症というデータがあり、長生きをすればするほど、認知症になる可能性も高くなります。
つまり、認知症予防に取り組むことで、長生きもするが、長生きしたあとには認知症が待っている可能性が高くなるのです。皮肉なことではありますが、いつかは朽ちていく肉体をもった人間の性(さが)なのかもしれません。
もちろん、認知症予防に取り組むことが無駄というわけではありません。取り組みが長く続くほど、その分認知症の発症時期を遅らせることができます。また、健康的な生活習慣が確立されていれば、認知症の発症後もその進行スピードが抑えられる可能性が高くなります。
認知症予防において大事なことは、積極的に認知症予防に取り組むものの、100%の予防という"確実さ"までは求めないことです。情報収集や環境整備、諸手続きなどを済ませておくことも大切になります。そうすることで、いつの日か認知機能が低下し、認知症になったとしても、QOL(生活の質)を維持したり、少しでも高めたりすることは十分に可能となります。
認知症になったら人生の終わり!は勘違い
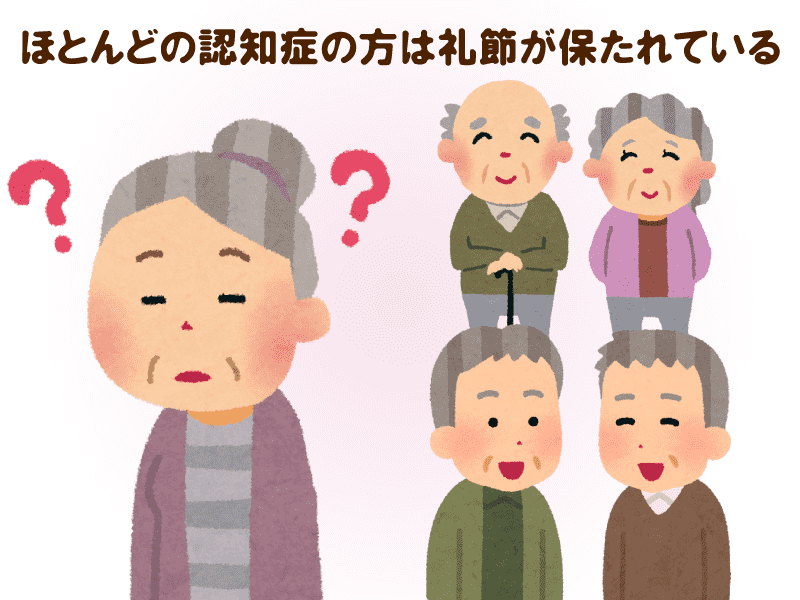
「できることなら、認知症にはなりたくない」は誰もが思うことで、人を認知症予防に駆り立てる原動力になります。ですが、この意識があまりにも強すぎると、認知症になった場合、「人生の終わりだ」と絶望して、途方にくれてしまいがちです。
認知症がもたらす社会問題の大きさから、認知症予防が強調されています。ただ、成果ばかり強調すると、「認知症を予防できなかった=失敗した」と考える人も出てきます。認知症予防に努めなければ、予防の効果は期待できませんが、健康的な生活を送り、脳を一生懸命に鍛えている人でも認知症になるときはなります。
認知症になるのは、本人のせいでも、家族のせいでもありません。まして、やる気がないからでもなく、病気になった結果なのです。人は必ず老い、いつかは病気になるものです。認知症になったからと、本人や家族を責めることも、なったことを悔やむ必要もありません。「認知症になったら人生の終わり」は誤解です。
認知症になったら、症状は悪化するだけで何もわからなくなり、暴力と徘徊が増えていく、一方で介護する家族は疲弊し、追い込まれていく…。認知症には、こうした悲惨なイメージが付きまとい、ここから「認知症になったら人生の終わり」という認識が生み出されています。ですが、これは認知症が重度まで進行し特殊な状況で起きたケースで、ほとんどの認知症の方は至って普通で、礼節も保たれています。
また、介護の負担も認知症の症状も軽くする方法が確立されてきているのに、本人も介護者もそれらをあまり知らず、わざわざ症状を悪化させたり、介護の負担を増やしたりしてしまっているケースもあります。つまり、認知症自体が問題なのではなく、認知症への対処の仕方が問題の場合もあるのです。
認知症に対する認識を変えて、正しい知識を身につけていくことで、認知症になっても本人や家族が笑顔で暮らせて、前向きに生きていきやすくなります。
「認知症予防の誤解」まとめ
認知症予防については、自分ができる確かな予防法を長く続けると同時に、100%という確実さは期待せず、認知症の発症を想定した準備もしておくことが大切になります。
ちょうど車を運転するとき、常に安全運転を心がけるも、万が一のときに備えて自動車保険にも入っておくようなものです。
また、長寿大国となった日本では、誰もが認知症になる可能性を抱えており、認知症とはうまく折り合って生きていく必要があります。
自分にあった予防法をみつけるときにも、認知症の発症を想定した準備をするときにも、認知症に関心をもって情報を集め、人と会って話をし、向き合い続けることがその手助けになると思います。




















