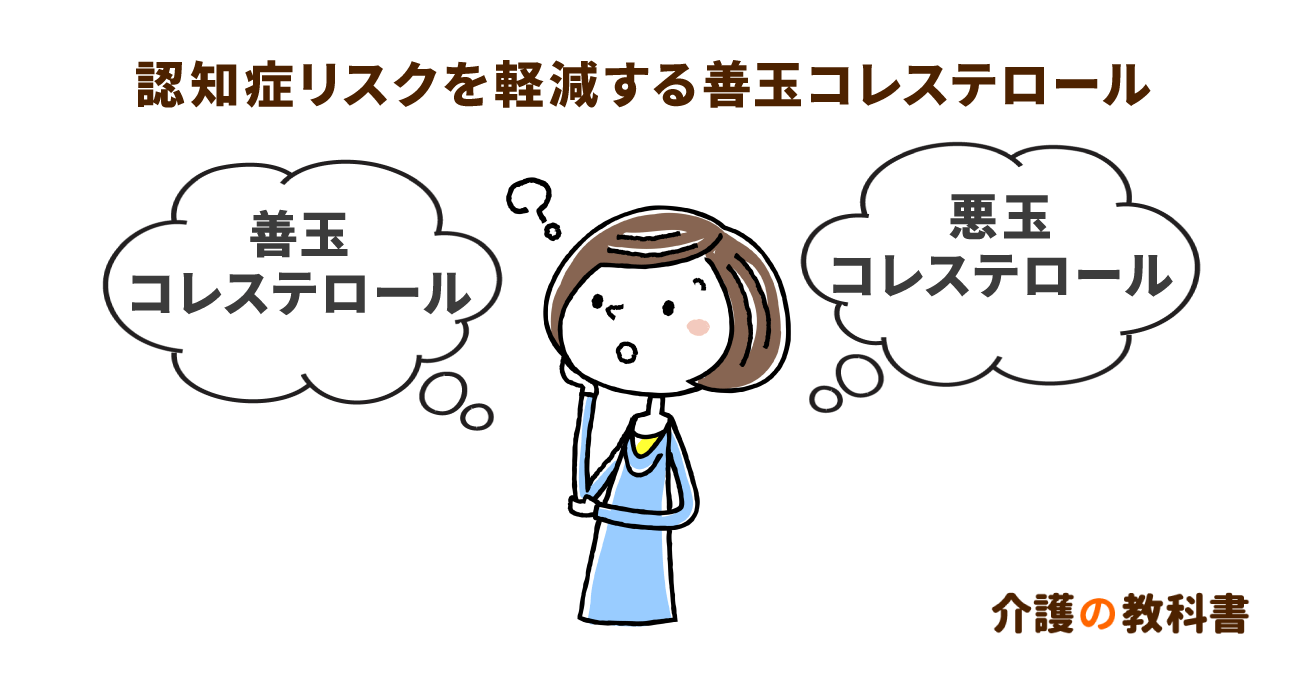こんにちは。一般社団法人元気人の理事・向川 誉です。当法人では、認知症ゼロ社会の実現を目指して、地域の認知症予防活動をサポートする「認知症予防活動支援士」の育成と支援に力を入れております。
日本人の平均寿命(2016年)は男性が80.98歳、女性が87.14歳と世界でもトップクラスですが、これがさらに伸びて日本は人生100年時代に突入していくと話題になっています。ただ、認知症患者の8割近くが80歳以上で、100歳を超えるとほとんどの人が認知症というデータもあり、認知症は長生きをすればするほど発症する可能性が高まります。
人生100年時代でもなるべくなら、ならずに済ませたい認知症。これまでになった数多くの研究成果をまとめたところ、認知症の発症には生活習慣が大きく影響していることがわかりました。今回は、そうした研究成果を踏まえながら、認知症の予防や発症遅延につながる予防対策を見ていきたいと思います。
認知症になりやすい9つの生活習慣リスク

認知症になりやすい要因があれば、その要因の対策から認知症予防が始まることになります。まずは認知症になりやすい要因を確認していきましょう。
2017年7月に、世界五大医学雑誌のひとつである『THE LANCET(ランセット)』に次のような主旨の論文(※文献1)が掲載されました。「認知症の発症リスクに影響する生活習慣を改善することで、世界中の認知症の3分の1以上が予防可能である」複数の専門家が認知症に関する研究論文を分析し、総合的に評価を行い、十分に信頼性の高い要因だけをまとめて発表したもので、ライフステージ別に認知症の発症に影響する”9つの生活習慣リスク”が指摘されています。
9つの生活習慣リスクがかかわっている
- 1.少年期
-
- 15歳までの教育
- 2.中年期
-
- 高血圧、肥満、難聴
- 3.中年期~高齢期
-
- うつ病、糖尿病、身体不活動(運動不足)、喫煙、社会的孤立
世界中の研究者が、長年の研究と多額の費用を費やして検証した結果の集大成といえ、この発表に対する信頼性は、十分に高いものです。そのため、認知症予防を考える際はこれらの生活習慣リスクに対してぬかりなく手を打つことが大切になります。もし、これらすべての要因を軽視した生活を送り続けるのであれば、認知症とは隣り合わせといえるでしょう。
例えば、喫煙は認知症の危険因子ですが、「90歳を過ぎた親戚のおじいさんは、長年たばこをぷかぷかと吸っているが、いまだに頭も体も達者だよ」などと嘘ぶいて、積極的にたばこを吸っている人がときどきいます。
ですが、そのおじいさんと自分の健康との間には何の関係もありませんし、そのおじいさんは統計データ上だと例外的なケースです。その例外的なケースに目を向けて、健康を損なう習慣(喫煙など)を続けることを正当化するのではなく、それらの習慣を素直に手放して、新しい習慣を選ぶことが大切になります。
また、ライフステージごとに生活習慣リスクが分けられていることから、認知症予防は高齢者だけが行うものではないこともわかります。中年期から対策を必要とする要因がいくつかありますし、生活習慣は一回ずつの影響は小さなものであっても、長年にわたり蓄積され続けるとその影響は大きくなるため、40代以上の人は今日からでも対策を始めたいところです。
義務教育制度が整った日本では、「15歳までの教育」は満たしている人がほとんどで、この点については安心されても大丈夫です。ただ安心して終わるのではなく、学びについては心がけてほしいことがあります。それは「もう歳だから」と言い訳せずに、何事にも興味をもって新しいことにチャレンジすることです。新しいことにチャレンジしている人は、総じて心身ともに健康的ですし、実際に認知症予防につながるとする研究成果もあります(※文献2)。
そして、高血圧、肥満、糖尿病については、生活習慣病を招く要因そのもので、生活習慣病に注意して健康習慣を維持することは、将来の認知症予防や発症の遅れを実現します。割と見過ごされがちですが、難聴も認知症の発症リスクとして注目されています。
難聴予防のためには、日頃から大音量で音楽を聴かないことを心がけ、生活習慣病の改善に努めること(高血圧や糖尿病などの疾患は難聴になるのを早めるため)が大切になります。難聴を放置していると、脳への刺激が減ったり、コミュニケーションに行き違いが生じたりして、認知症予防にはあまりよくありません。現在のところ、加齢による難聴を治す治療法はありませんが、補聴器を装用することで、聞こえの悪さを改善できます。
なお、認知症との関連が指摘されている食事や睡眠については、研究の数がまだ少ないという理由からこの論文では取り扱っていないと思われます。ですが、生活習慣リスクをまとめた今回のリストに含まれていないからといって、食事も睡眠も軽視して良いわけではなく、今後研究が進めばこのリストに加わる可能性は十分にあります。
食事も睡眠も、認知症との関連性が昔から指摘されており、QOL(生活の質)にもかかわってくるので、しっかりと抑えておきたいところです。今後の連載では、これらの生活習慣リスクを回避するには何をすれば良いのかを具体的に紹介していく予定です。
運動は今すぐ取り組んでほしい予防法

これまで健康をあまり意識したことがない人が生活習慣を改善しようと決めたとします。ただ、習慣を身につけるコツ自体がつかめていないため、新しい習慣を一度にたくさん身につけようとしてもなかなか大変です。習慣化のコツをつかむためにも、まずは習慣にしたいものを一つ選んで、それを一点突破で取り組むのが良いでしょう。
その際、何をしようかなと迷ったら、特に身体的な制約がなければ、わたしは「運動」をおすすめします。その理由は、認知症の危険因子の中でも特に危険度が高いとされているのが「運動不足」だからです。
アルツハイマー病の危険因子の危険度を調べた米国の調査研究から、高血圧や喫煙、うつ以上に運動不足が大きく影響していることがわかりました(※文献3)。運動不足は認知症の大きな危険因子になると同時に、運動は防御因子としても働くため、認知症予防については一石二鳥の効果が見込めます。
また、体力や筋力はあらゆる活動を行う際の土台となっており、運動することで体力や筋力を鍛えることができます。また、多くの人が感じているように、脳も体も楽をしたがる傾向にありますが、その声にずっと聞き従うことは運動不足を招き、運動不足は認知症促進の原因にもなります。運動は主体的に行動を選択するという心の筋肉も鍛えられますので、他の健康習慣が身につきやすくなります。
認知症予防につながる運動といえば、有酸素運動が良いといわれていますが、高齢でも筋力を維持するために筋トレにも取り組まれると良いでしょう。
認知症のまとめ

私たちの生活はほとんどが日々の小さな積み重ねからできていますが、それが長年にわたり積み重なりますと、「雨垂れ石を穿(うが)つ」のことわざのように、いつかは大きな影響を及ぼします。認知症になりやすい要因を回避する”生活習慣”を心がけるところから認知症予防はスタートするといえます。
そして、認知症予防の実現性を高めるには、「今したいこと」ではなく、最終的に「どうなりたいか」、さらにいえば「どのように人生を終わりたいか」を決めることが大切になります。自分が求めているものが明確であれば、自分が今取るべき行動が、何なのかが見えてきます。今の行動と将来の状態とはトレードオフです。自分が今している行動が求めている将来につながるのかどうかと日々自問することも、認知症予防では大切な習慣のひとつと思います。
※文献1 Livingston G, et al. "Dementia prevention, intervention, and care" Lancet (2017)
※文献2 Park DC, et al. "The impact of sustained engagement on cognitive function in older adults: the Synapse Project" Psychological Science (2014)
※文献3 Barnes DE, et al. "The projected effect of risk factor reduction on Alzheimer's disease prevalence" Lancet Neurol (2011)