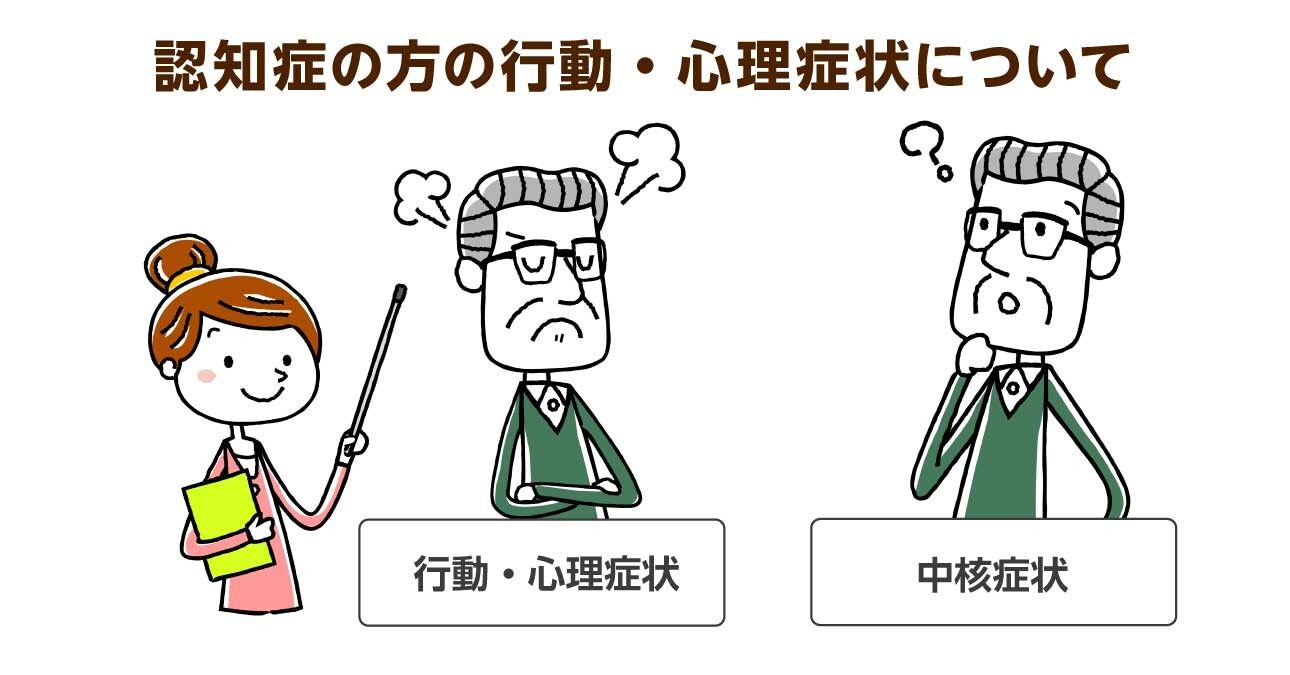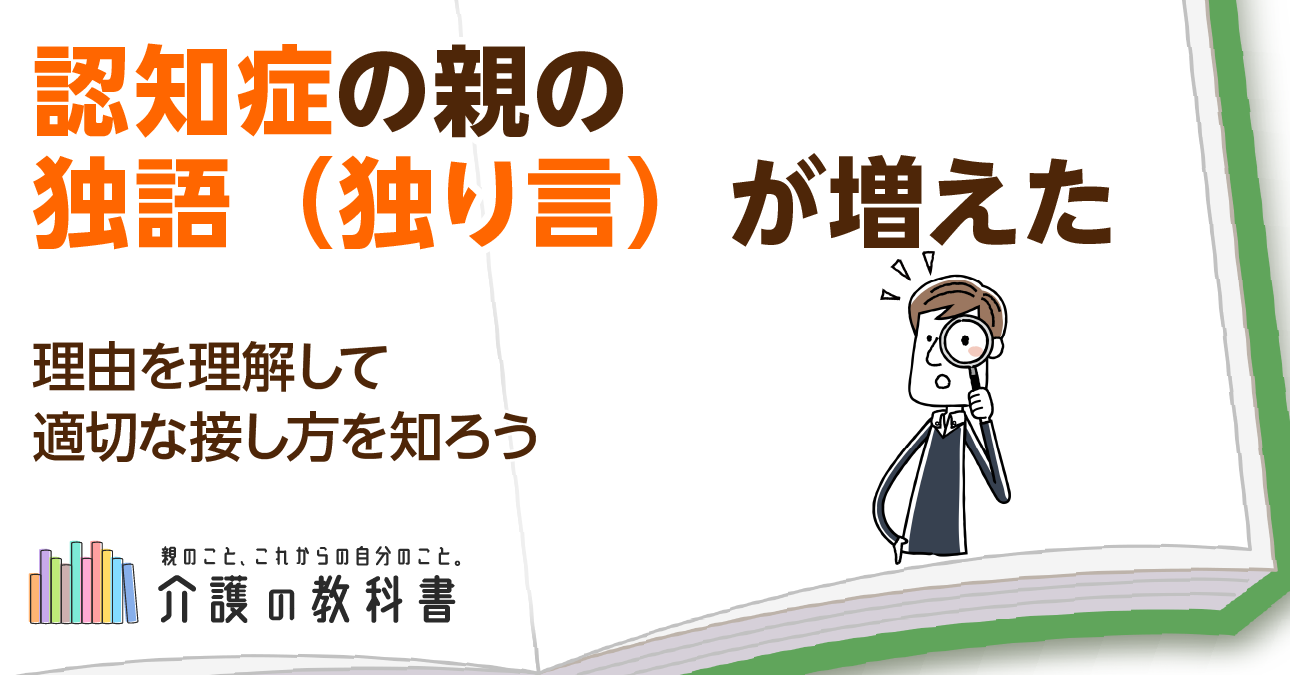こんにちは。介護老人保健施設「総和苑」で介護課長をしている高橋秀明です。「介護の教科書」では引き続き「認知症」だけに焦点をあてるのではなく、「人の想いを考えていくことの重要性」についても触れていきます。
今回は「身体的不調がもたらす行動・心理症状」についてです。医学的観点ではなく、僕が現場での経験を通して学んだことや、感じたことを皆さんにお伝えし、考えるきっかけにしていただけるとうれしく思います。
介護をする上で、自宅で介護をしているご家族だけではなく、職業として介護をしている専門職にとっても難しいのが「認知症の行動・心理症状」です。
ご家族や職業として介護をしている専門職とお話をしている中で、「認知症が進行した」という言葉を聞くことがあります。認知症は進行性の難病だと言われていますが、何をもって認知症が進行したと感じるのかを、家族や介護職員の声を聞き深めていくと、「行動・心理症状の変化(悪化)」を言っている人が多いのです。
行動・心理症状の変化は記憶障害などを主症状とした中核症状に、「不快、不安などの心理的要因」「介護者の関わりなどの人的環境要因」「身体的不調などの身体的要因」が加わることで起こります。このとき、僕は本人に何か困ったことがあったと判断しています。僕が経験した出来事をお伝えします。
「私の痛みや異変に気づいてほしい」行動・心理症状はお年寄りからのSOSサイン

事例①:大声を発したり、机を叩いて痛みを表現
長女さんの手助けを受け、アルツハイマー型認知症と診断されながらも自宅で生活を送っていたマサコさんは、自身で判断できることや、できなくなることが増え、当施設に入所となりました。
入所してしばらくは落ち着きのない行動はありながらも穏やかに生活をしていたのです。ところが、しばらくすると大きな声で「うー、うー」と声を荒らげたり、テーブルをバンバンと叩いたり、髪を自ら掻きむしるなどの行動が目立ち始めました。
私たちは原因を考えて、マサコさん本人が安心できるようなさまざまなことをしましたが、行動は治まるばかりか激しさを増すばかりでした。「認知症の進行なのか?」と原因がわからず途方に暮れた私たち。食べる量が減ってきたときに「内科的な問題ではないか」ということに気づきました。
病院にお連れして、精密検査を受けさせた結果は胆管結石(たんかんけっせき)で、お医者さんは「大きな声やテーブルを叩くことは痛みの表現でしょう」と言っていました。その後、入院治療で胆管結石は改善し、大きな声やテーブルを叩くことはなくなったのです。
マサコさんはずっと、「私は痛くて困っているからなんとかしてほしい」という声なき声を発信していたにもかかわらず、そのことに気づけなかったことを専門職として反省しています。10年前の出来事ですが、この出来事は僕の心の中にいまだに留まっており、忘れることができません。
事例②:急に会話が噛み合わなくなったり、物忘れが激しくなったら頭部に異常があった…
テツジさんは2009年にアルツハイマー型認知症の診断を受けました。自宅での妻と長男、長女と暮らしていたとき、テツジさんは78歳でしたが、年齢を感じさせないほど活発な方で、周囲を笑わせて和やかな雰囲気にする方でした。
そんなテツジさんが急に歩くことがおぼつかなくなり、言葉を発することができなくなりました。加えて話がかみ合わず、物忘れが著しくなってしまったのです。長女さんは「急に認知症が進みました。自宅介護は難しいので施設入所したいのですが…」と僕に相談。話を伺っていると、3ヵ月前に自宅で転倒をして頭を打ったということを長女さんは言いました。
僕はその情報から「もしかして頭の中に異常があるかも」と思い、長女さんにすぐにかかりつけのお医者さんへの受診を勧めました。長女さんはすぐに受診をしてくれ、かかりつけのクリニックで頭部CTを行ったところ、「硬膜下血腫」(こうまっかけっしゅ)が発覚し緊急入院となりました。病院で血腫を除去する治療をしたところ状態は改善し自宅に退院することができました。
高齢の方は私たちよりもリスクが高く、転倒をすることがよくあります。その際に頭をどこかにぶつけているときは要注意です。頭をぶつけた直後に異常はなくても、数ヵ月後に血腫がたまり、そのことが原因で認知症状が現われることがあります。
「頭の中に血腫がたまる硬膜下血腫」が原因疾患となって起こる認知症は、治療によって治る認知症と言われています。認知症になったら治らないというイメージを持っている方が多いですが、治る認知症もあるということを知識として持っておくことが大切です。言葉がうまく出てこない、足元がおぼつかなくなることや麻痺、排せつの失敗や認知症状などを見逃さないこと。「頭をぶつけたり打ったりした後3ヵ月くらいは本人の状態に変化がないか経過を追うことが重要」だと話すお医者さんもいます。私たちの意識と気づきで救えるということです。
事例③:夜中突然でかけようとする父。検査をしたら末期の状態…
セイジさんは妻が入居する僕の施設に、週に1回程度のペースで車を運転して面会に来てくれる旦那さん。毎回ジャケットにスラックスで来られるおしゃれな方でした。セイジさんは90歳を超えていましたが、身体・認知機能にも問題ありません。2月に入り、長男さんとセイジさんが一緒に施設に来られました。「車の運転止めちゃったよ。俺も高齢だし何かあってからでは遅いからさ」セイジさんは僕に言いました。
そのときに気になったのが、セイジさんの服装がいつものジャケットとスラックスではなかったことと、若干やつれたような表情であることでした。
それから2週間くらいして長男さんがやってきて、「高橋さん聞いてよ。親父がおかしくなっちゃたよ。時間の感覚がなくなっちゃたのか、夜中に電気をつけてガタガタ音をたてるんだよ。こっちも目が覚めるし困っちゃった」と僕の所に相談に来ました。
長男「親父、今何時だと思ってんの?夜中に何しているんだよ?」
セイジさん「これから出かけるんだよ」(と言って鍵を開けて外に行こうとする)
長男「出かけるって言ったってこんな時間にどこに行くんだよぉ…」
長男さんはセイジさんとのやり取りを僕に話してくれました。「親父、認知症になっちゃったのかな。急に(症状が)進んじゃった。サービス利用(入所)できないかな?」長男さんは困り顔で言いました。
僕は、今までの経験から身体的不調を直感的に疑い、長男さんに「もしかしたら、セイジさんのおかしな言動は、身体の不調のサインかもしれません。介護サービス利用にあたっての健康診断も兼ねて、早めに診察を受けてみるのも良いかもしれません」と言いました。
僕の話を聞き、長男さんは思い出したように「そういえば最近ハアハアと息切れするようなこともあったなあ。病院も最近行っていないし、今日これから連れて行ってみるよ」
翌日、長男さんは受診結果の報告のために僕の所に来ました。「高橋さん、親父、精密検査することになったよ。脳や心臓は大丈夫だったけど、腫瘍がみつかった」と…。
その後の精密検査では、全身が腫瘍で侵されている末期の状態であるとわかりました。入院治療後、僕が勤務する施設のショートステイと、自宅を行ったり来たりした2ヵ月後にセイジさんは旅立たれました。
事例④:椅子から立ち上がろうとしたり、大声を出して体調不良を表現
通所リハビリテーションに通うミズエさんは、2013年にアルツハイマー型認知症の診断を受け、僕が出会った1年前にはすでに会話もままならなくなっていました。介護者の手引き歩行でなんとか歩くことはできますが、自ら立ち上がることは普段ありません。
しかし、稀に椅子から立ち上がろうとする素ぶりがあったり、「何すんだよー!」とフロアに響き渡るほどの声を出すことがあります。そういった言動があるときは、38℃を超える発熱と尿臭があります。
お医者さんからは膀胱炎と脱水と言われ、点滴などの水分補給や一時的な抗生剤の服用で状態は改善します。長女さんやケアマネージャーとのサービス担当者会議では「何すんだよー!」や「椅子から立ち上がる素ぶり」などは、体調不良のサインかもしれないと共有することになりました。
不安定な行動・心理症状の裏側には、身体の内側に異常が起きている可能性が

事例①~④に書いた通り、行動・心理症状の裏側には、身体の内側に異常(疾病による身体的不調)が起きている可能性があります。認知症の状態にある方は、自分の身体不調や不快、不安といった困りごとを言葉で表現がしづらくなっている状態です。
自分の困りごと(かゆい・痛い・苦しい・気持ち悪いなど)を言語で表現できずに、自分ができる行動と言葉で表現していると考えることが大事。行動・心理症状は「私は困っています。この困りごとを解決するために手助けしてほしい」という本人からのSOS信号だと考えましょう。