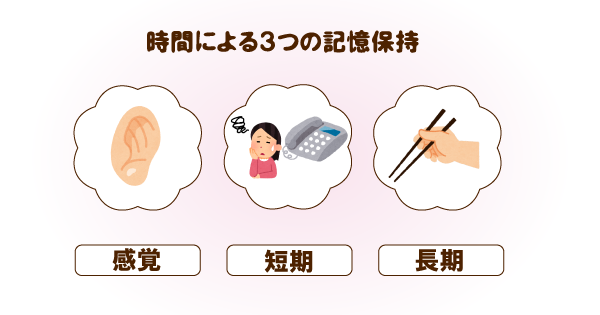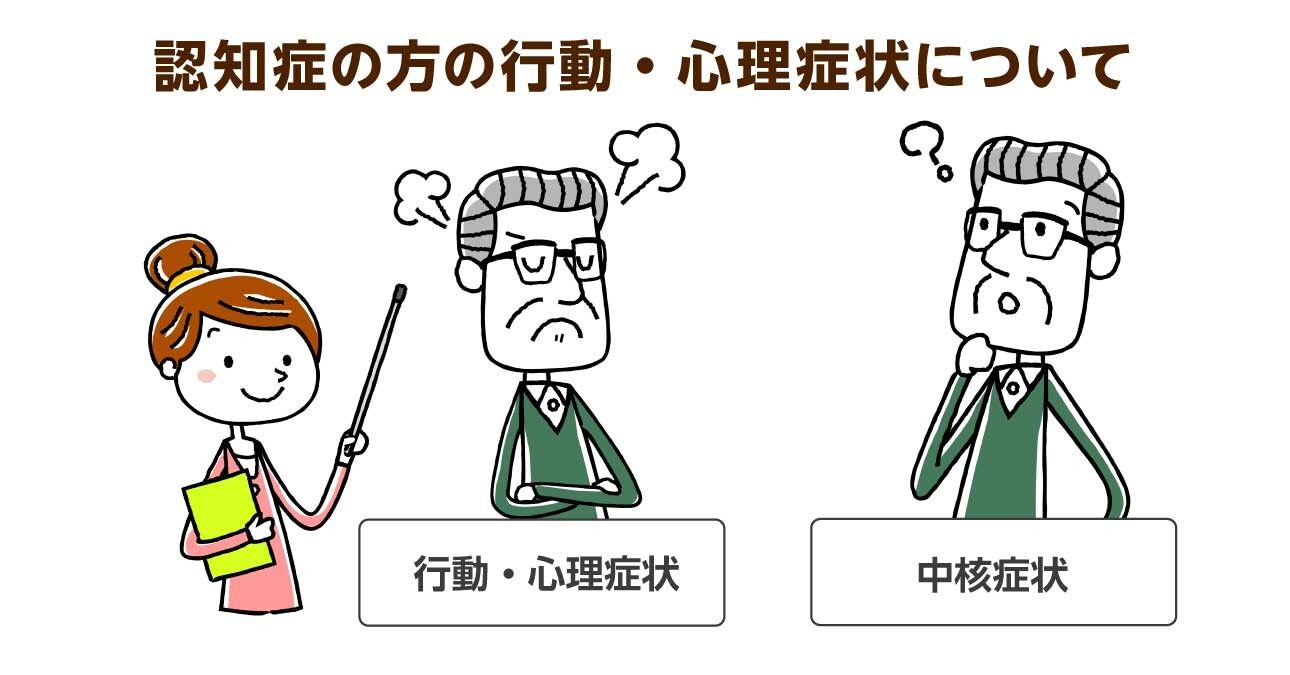こんにちは。介護老人保健施設「総和苑」で介護課長をしている高橋秀明です。
介護の教科書では引き続き「認知症」だけに焦点をあてるのではなく、「人の想いを考えていくことの重要性」についても触れていきます。
認知症の状態であっても、自宅では自分のことを自分で行うほど元気であったのに、肺炎治療のため入院している間に介護が必要なほど生活機能(身体・知的能力)が低下したトミ子さんのケースを紹介します。
今回は「入院などをきっかけにして本人の生活機能(身体・知的能力)が大きく低下したときに家族はどうしたら良いか」についてお話ししますので、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。
状態変化による介護は突然やってくる

トミ子さんは、肺炎の治療として点滴や酸素吸入を受けていましたが、「自分が今、入院していて治療が必要であること」を認識することができず、点滴や酸素マスクを自ら外してしまうことを繰り返しました。病院側はやむを得ず、"身体拘束"という手段を使い、両手にミトン型手袋(指が曲がらない専用品)を着けさせた上、両腕を左右のベッド柵に縛りつけたのです。トミ子さんはその状態でも必死に抵抗を続け、認知症の症状は進行していきました。
トミ子さんは長引く入院生活で、体力面での低下ばかりでなく知的機能も大きく低下してしまいました。会話のつじつまが合わず、寝たきりでおむつ交換が必要。食事はペースト状にして、食事介助も必要となりました。数ヵ月後、肺炎治療は終了し病状は安定したため、お医者さんから退院を告げられました。
ご家族は、入院中にどんどん変化してゆくトミ子さんに戸惑いと不安を感じていました。それに加え「退院」という一言がご家族の不安をさらに大きくなることに…。入院前のトミ子さんは自宅に住み、若干の物忘れはあるものの、自分の身の回りのことを全部自分でできるだけでなく、家族のご飯を作り、洗濯や掃除も行うなどの家事の中心を担っていました。
このトミ子さんの状態が入院中に変化。寝たきりで介護が必要な人になってしまったのですから、ご家族の不安が募るのは当然です。
「介護や認知症のことは何となくテレビや新聞で知っていました。でも実際に介護が必要になった本人を目の当たりにして、このままの状態で退院して自宅に帰ったときのことを考えると、どうしたら良いかわからないんです。頭も体も、もっとしっかりしてから退院になるものとばかり思っていました。今は、本人との話もよく通じないし。寝たきりの人のおむつのお世話や食事介助などは、やったことがないので介護の方法がわかりません。」
突然突きつけられた介護という難題に不安はどんどん大きくなり、ご家族は夜も眠れないほど精神的に追い詰められていきました。
想定外から「できる限り想定内に」

ご高齢の方が入院となる原因疾患で代表的なものは、
- 心疾患(心筋梗塞・狭心症・心不全など)
- 肺炎、脳卒中(脳梗塞・脳出血など)
- 大腿骨頚部(足の付け根)・大腿骨(太もも)・骨盤・膝等の下半身の骨折
といったような種類があります。これらの疾患は、医療機関での治療が必要で、早期の受診が重要となります。若い私たちが、これらの疾患で入院治療したとしても、身体や知的機能が衰えて歩けなくなったり認知症を発症したりすることはまずありません。多少の体力低下はあっても入院前の身体・知的機能を保って退院します。この「体力低下」はどのご家族にとっても「想定内」でしょう。
しかし、ご高齢の方の場合はそうはいきません。僕の14年間に及ぶ経験では、長引く入院生活によって、病気は良くなったけど「歩くことがおぼつかなくなった」「普通のご飯が食べられずお粥を食べるようになった」「寝てばかりいて寝たきりになってしまった」などの身体機能の低下ばかりでなく、「急に物忘れが酷くなり、さっき話したことをまったく覚えていない」「話のつじつまが合わなくなった」などの知的機能の低下をよく耳にします。
使える機能を使わないと人は衰えると言われています。入院中は、寝ている時間が長い、自分で考えて判断する機会が少ない、一日のスケジュールは病院任せ、人と話す機会が少ないなど、受動的で脳への刺激が少ない生活です。自宅とはまったく違う環境で、ご高齢の方は環境の変化に弱く対応できません。介護にあまり縁のなかったご家族にとっては入院中の知的機能の低下は「想定外」かもしれません。想定外であったために、変わりゆくご高齢者目の当たりにして慌てふためくことになります。
記憶力の低下があったとしても生活に大きな支障がなければまだ良いのですが、これがBPSD(行動・心理症状)の出現となると話は変わります。入院し治療が必要な状態を理解できず
- 「家に帰りたい!なんでここにいなきゃいけないの!」と怒ること。
- 昼間に寝ていることが多く夜になると、目が冴えてゴソゴソと動き出すこと。
- オムツに排泄したことが本人は不快でオムツを自ら外したり、オムツの中に手を入れて便を触り、便がついた手であちこちを触りベッドまわりを汚すこと。
これら以外にもさまざまなことが起こり得ますが、こういったことが入院中に出てくるとご家族は大きな焦りや不安を覚えます。このときにお医者さんから「退院です」と告げられると、トミ子さんのご家族のようにお先真っ暗状況に陥りかねません。
ご高齢の方は、入院をきっかけに身体機能の低下だけでなく、知的機能の低下もありうることを想定内ととらえてあれば、少しは慌てずに済むのではないでしょうか?
入院後の状態変化時に、困らないよう相談できる窓口を知っておく

超高齢社会の今、認知症や介護という言葉を聞いたことがある方は多いはずです。しかし、実際にその状況(認知症や介護)に直面するまでは、「聞いたことはあるがよくわからない」「知っているけど理解はしていない」というのが実態なのかもしれません。僕の施設にも「病院から退院という話が出ているけれど、どこに相談したら良いのか、どうやったら介護のサービスを利用できるのかがわからない」と途方に暮れて電話や来訪し相談に来る方が多いです。
そういった不安を払拭するためには、相談できる窓口を知っておくことが大事です。今回はトミ子さんの事例に沿って、病院に入院して「認知症のような症状が出てきた、認知症の記憶障害など中核症状が進行してしまった、BPSDが強く出てしまっている」ときに家族(介護者)はどこに相談すれば良いのか?を具体的にお伝えします。
入院先の医療相談室の医療ソーシャルワーカー(以下、MSW)に相談する
病院にはさまざまな部門がありますが、相談窓口として「医療相談室」という部門があります。病院によっては医療相談室以外にも「地域連携室」とか「地域医療連携室」などその病院によって呼称はさまざまですが、機能としては同じです。
その部門には「社会福祉士」「精神保健福祉士」という相談援助の国家資格を持った方や「看護師」や「介護支援専門員(以下、ケアマネージャー)」などの有資格者が相談に乗ってくれます。僕が介護の仕事に就いた14年前に比べると、医療相談室のスタッフ数は増えていますし(以前は1~2名程度だったのですが、現在は(病院の規模にもよりますが)複数名いますし、多いところでは5名以上いる病院もあります)、ほとんどの病院に医療相談室が設置され充実しています。
MSWは、お医者さんをはじめ看護師さんやリハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)など医療専門職と連携を図り、今現在の本人の心身状態と本人・家族の意向に沿ったこれからの生活(自宅や施設など)について相談や具体的提案をしてくれます。また、ケアマネージャーや介護保険施設(例えば特別養護老人ホームや介護老人保健施設など)との橋渡し役にもなってくれます。
ケアマネージャーに相談
入院前から担当してくれているケアマネージャーがいた場合は、ケアマネージャーに相談するというのも選択肢の一つです。退院をして自宅で暮らしたいというのが明確なら担当ケアマネージャーに相談するのが良いと思います。
施設に直接問い合わせ相談
介護保険制度の創設と制度の成熟とともに、さまざまな形態の施設(サービス)ができ、選択肢が広がりました。しかし数ある事業内容や事業形態から自らの意向に合う施設を選ぶことは大変です。
特別養護老人ホームなどは入居待ちが長期であったり、他施設も利用料金や施設の支援内容(医療行為など)や入居期間など条件が施設によってさまざまで、施設に直接相談に行くと得られるメリットも。施設でも相談員という相談援助の専門職がいます。介護保険サービスのさまざまな情報を得られるだけではなく、相談員は他施設との繋がりもありますから、自施設以外のサービスを紹介してくれるでしょう。
役所や地域包括支援センターに相談
近くの各市町村窓口や地域包括支援センターという公的なところへ、電話や直接訪問して相談をするという方法もあります。
以前介護をしていた方や今介護をしている方に相談
介護の経験値が豊富な先輩ですから、さまざまな情報を持っている可能性があります。経験をしている方同士のつながりは大きな力になるときがあります。ただ、そういった方が周囲にいるとは限りません。
これら以外にも選択肢はありますが、僕の経験からかいつまんでご説明しました。「いざとなってから」ではなく、「今」から意識を向けておくこと、関心を寄せておくことが大事だと思います。
そうは言っても悩むことやつらくなることもあるかもしれません。しかし、備えておくことで、自分の心の置き所がしっかりとして気持ちのバランスが取れ、悩みやつらさを少し軽減できるかもしれません。「備え」というものは「いざ」というときに、あなたの大きな味方になってくれるはずです。