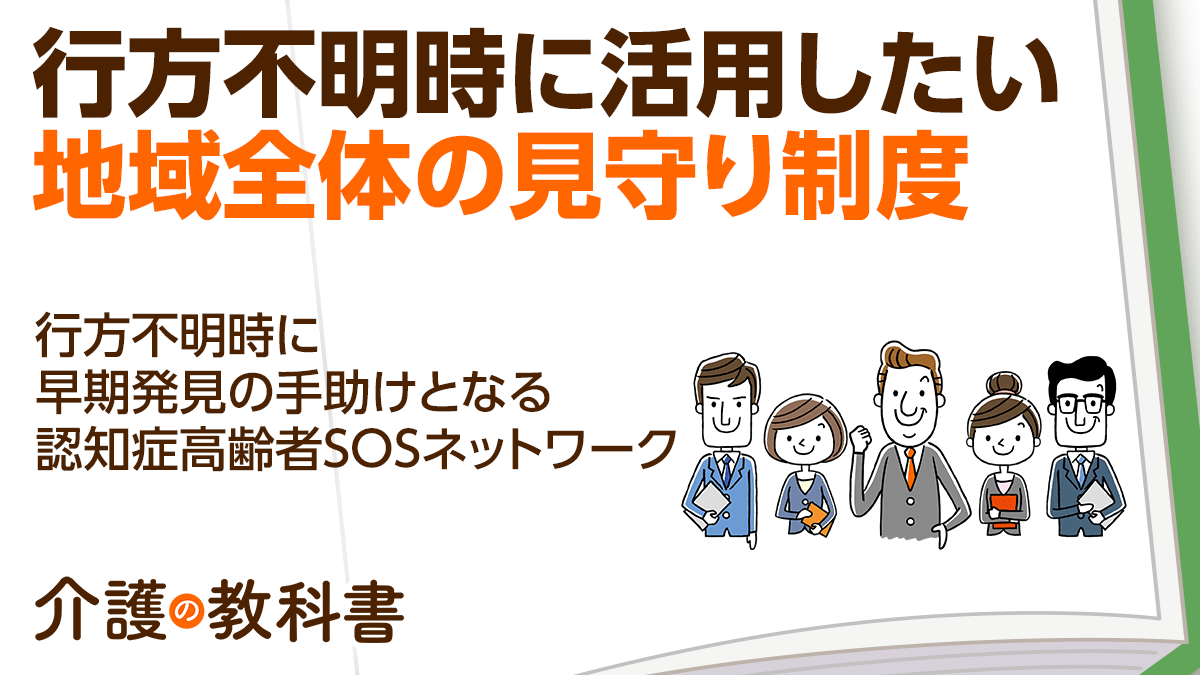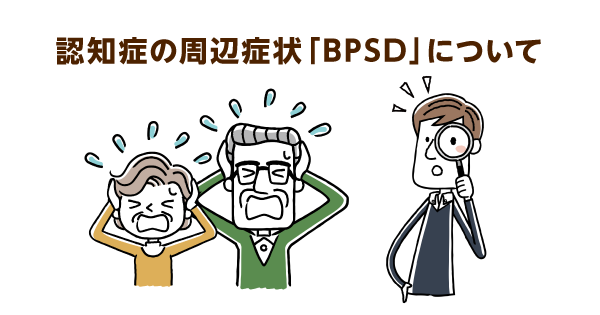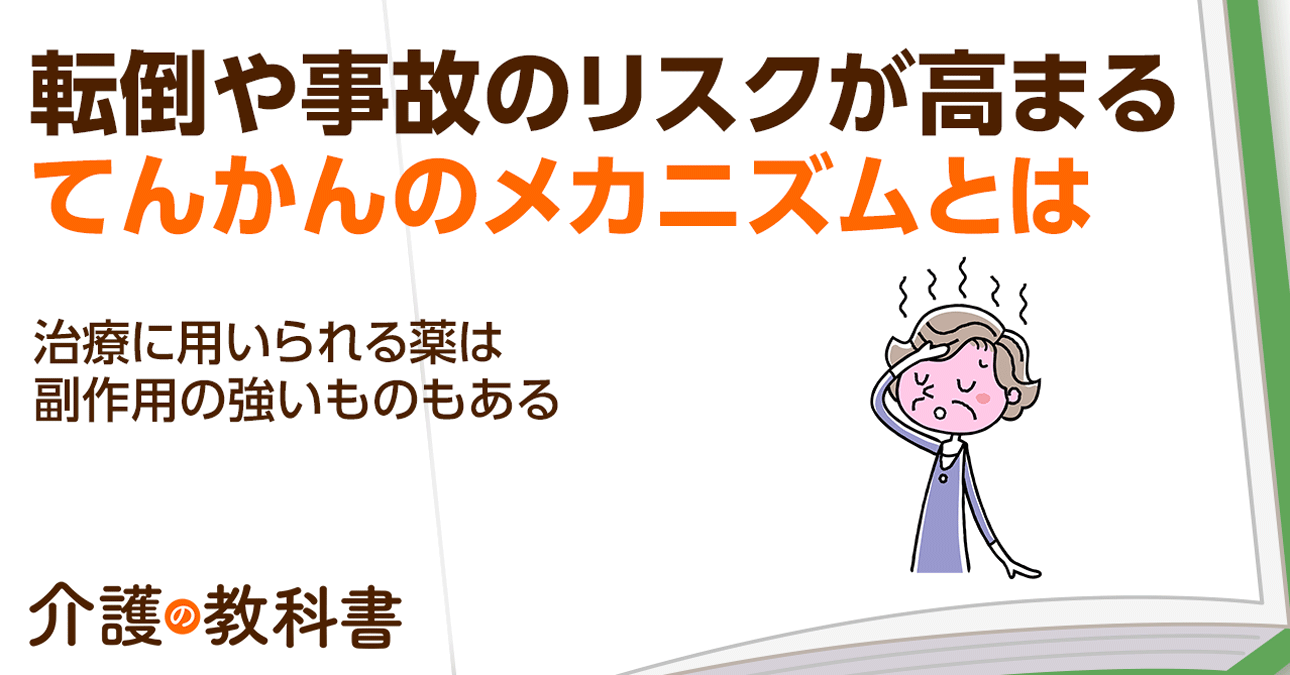「認知症の親が近所に出かけたが、家に帰ってこない」
「行方不明になって家族中で探し回った」
認知症高齢者を介護している家族の中には、このような経験を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
認知症高齢者は、さまざまな理由で行方不明になることがあります。また、思いがけず遠くまで行ってしまうことがあるので、家族だけで捜すことは大変難しい場合もあります。
そこで助けになるのが、認知症高齢者SOSネットワークです。
この記事ではSOSネットワークについて詳しく解説していきます。
認知症高齢者SOSネットワークとは?
認知症高齢者SOSネットワークは、外出して家に戻れなくなり、行方不明になった認知症高齢者を一刻も早く発見するためのネットワーク事業です。
さまざまな理由で行方不明になった認知症高齢者を、早く・無事に発見するために組織され、警察や消防、市区町村役場・地域包括支援センターといった公的機関の他、タクシー会社・地元のラジオ局・公共交通機関・宅配業者などの関係機関が捜索に協力します。
平成6年に北海道釧路市で初めて設立され、現在は全国に拡大しています。
認知症高齢者は記憶力や空間認知能力の低下によって、外出しても家に戻る道が分からず、そのまま歩き回り行方不明になることがあります。

また、過去の記憶が強く残っており、昔住んでいた家に帰ろう・子どもを迎えに行こうという本人なりの理由で外出して行方不明になることもあります。
警察庁生活安全局生活安全企画課の記録「令和2年における行方不明者の状況」によると、認知症が原因での行方不明者は17,565人であり、この人数は年々増加してきています。
詳しい人数は、下記の表をご覧ください。
| 年度 | 人数 |
|---|---|
| 平成28年 | 15,432人 |
| 平成29年 | 15,863人 |
| 平成30年 | 16,927人 |
| 令和元年 | 17,479人 |
| 令和2年 | 17,565人 |
SOSネットワークの利用方法
SOSネットワークの基本的な利用方法をご紹介します。
事前登録
SOSネットワークを利用する場合、対象になる認知症高齢者の情報を事前に登録することが望ましいでしょう。事前に登録することで、SOSネットワークがより早く動けるというのが、その理由です。
認知症高齢者の情報とは、名前・住所・年齢・身体的特徴といったことがあげられます。
行方不明に気づいたとき
認知症高齢者が行方不明になったと気づいたら、すぐにも最寄りの警察署に連絡してください。そのときには、SOSネットワークに登録していることも伝えましょう。
その後、警察が協力機関にメールやファックスで捜索を依頼します。
依頼を受けた協力機関は、自分たちの業務と並行して捜索活動を行います。
地元のラジオ局を例に挙げると、捜索依頼が届いたら番組の途中で行方不明者情報を流し、地域住民にも捜索に協力してもらうといった形です。
無事発見されたら警察に連絡が入り、家族が迎えに行くことになります。
SOSネットワークの事例紹介
ここではSOSネットワークを実施している自治体のうち、2つの事例をご紹介します。
1.北海道釧路市
平成6年、日本で初めてSOSネットワークを立ち上げた自治体です。認知症高齢者が行方不明になり、遺体で発見されたことがネットワーク立ち上げのきっかけになりました。
30年近くたった現在もSOSネットワーク活動は続いており、釧路市及び周辺の自治体では年間約50名の高齢者が警察に保護されています。
2.神奈川県横浜市
神奈川県横浜市では、SOSネットワークのほかにも、「横浜市認知症高齢者等見守りシール事業」を実施しています。
SOSネットワークの事前登録を行った高齢者に対して、QRコード(※)の付いたシールを配布し、認知症高齢者の持ち物や衣類に貼っておきます。
シールを身に着けた認知症高齢者が行方不明になった場合、発見者がシール上のQRコードを読み取るとコールセンターにつながります。
そしてコールセンターから家族に連絡が届き、無事保護されるという仕組みです。
これは、認知症高齢者の個人情報を守りながらも、行方不明の際には早く保護できるように作られました。
家族の方へ
家族が認知症になった場合、「恥ずかしい」というイメージを持ち、隠してしまう方もいるでしょう。
しかし、勇気を出して周囲の人に打ち明けて、助けを求めることが大切です。住み慣れた地域の方に状況を理解してもらうことで、見守りの目が増えるという利点があります。
顔見知りの関係になっておくと、近所を歩き回っていた場合に声をかけてくれたり、自宅に送り届けてくれたりといった協力を得られる可能性もあります。
家族が行方不明になった場合
家族が行方不明になったら、まずは速やかに警察に連絡しましょう。
慣れ親しんだ場所に行く場合もあるので、友人や親戚の家、昔住んでいたところなど思い当たる場所も探すのも1つの方法です。
交番やコンビニエンスストアなどで目撃情報を訊くのもよいでしょう。
頭に入れておきたいのが、認知症高齢者も「恥ずかしいという気持ち」は残っていることです。
そのため、道を歩いている方に突然、「ここはどこですか」などと訊くのはためらうことが多いのです。
その点、交番やコンビニエンスストアなら比較的中に入りやすく、道を尋ねやすいでしょう。
無事保護された後の対応
無事保護された後は、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに介護保険サービス利用、今後の介護生活について相談しましょう。

特に、今まで介護保険サービスを利用していなかった方であれば、可能な限りサービス利用を勧めることが必要です。
介護保険サービスの中には福祉用具の貸与があり、要介護2以上の方であれば認知症老人徘徊感知機器をレンタル可能です。
認知症老人徘徊感知機器は、高齢者がベッドから離れたときや、部屋を出たときなどにセンサーが感知して、音や光で家族に知らせる福祉用具。
認知症の方自身が発信機を持つタイプなどもあり、1人で外出し行方不明になることを予防できます。
介護の悩みを抱え込まないようにしよう
介護の悩みは家族だけで抱え込まないようにすることが大切です。
悩みを抱え込みすぎると、介護ストレスが増大し、介護うつや高齢者虐待などにつながる可能性があります。
最悪の場合、介護疲れによる心中や殺人などに発展することもあるでしょう。
そうならないためにも、悩みを抱えないことが大切です。
お住まいの地域に、認知症家族同士の交流の場がある場合は積極的に参加してみましょう。
つらい気持ちを打ち明けたり、家族同士で情報交換したりすることで、介護者の気持ちはいくらかでも楽になります。
行方不明になっている高齢者を見かけたら
道に迷っている・疲れている・周囲をキョロキョロ見ていて不安そうな様子といった高齢者を見かけたらやさしく声をかけてみてください。
その際は、正面から手を振りつつ、目線を合わせながら声をかけるとよいでしょう。
相手から見えないところで声をかけると、逆に驚かせてしまいます。
名前や住所、電話番号などの連絡先が分かればそこに連絡し、分からない場合は警察に連絡しましょう。
また、行方不明になってから時間が経っている場合は、思いがけないほど長距離を歩いていることもあります。
疲れきっていたり、のどが渇いていたりする場合もあるので、お茶や水などを差し上げるとよいでしょう。
まとめ
この記事では、認知症高齢者SOSネットワークや高齢者が行方不明になった際の対処法について解説しました。
認知症高齢者が行方不明となってしまうのには、さまざまな理由があります。
大変悲しいことですが、行方不明になって数日後遺体で発見されるということもゼロではありません。
そのような悲しい出来事を減らしていくためにも、SOSネットワークの役割は大きいものです。
認知症高齢者を介護しているのであれば、できる限りSOSネットワークの利用(事前登録)をおすすめします。
家族以外にも見守りの目を増やしていき、介護負担やストレスを軽減していきましょう。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です