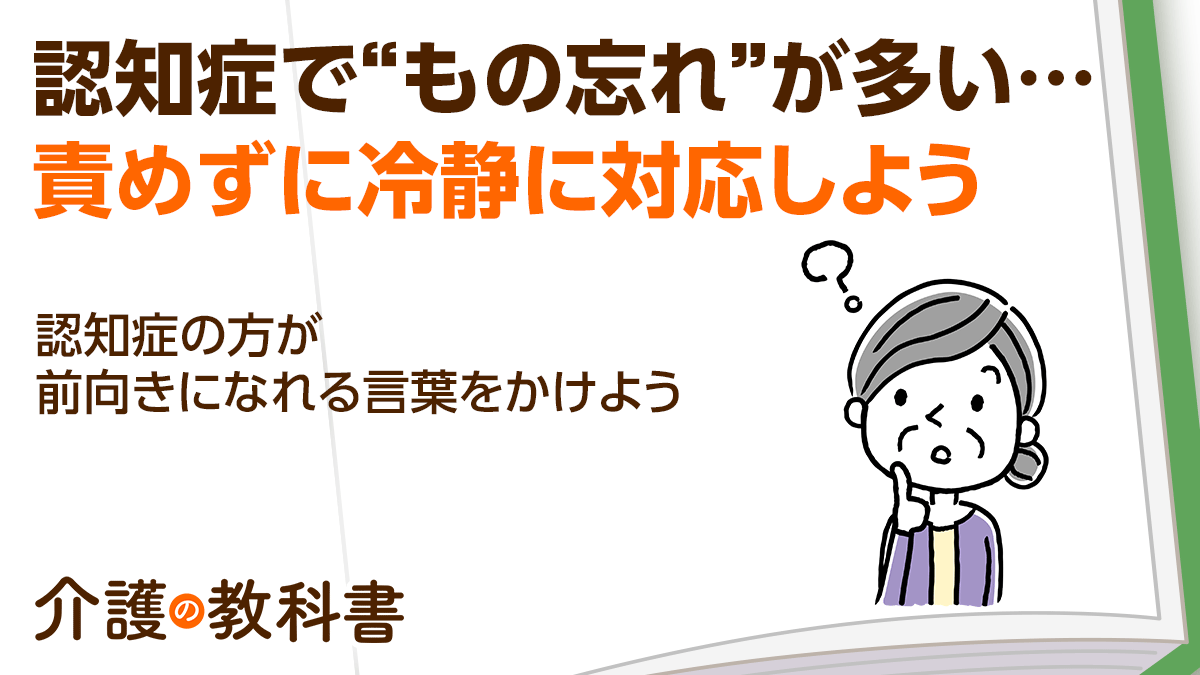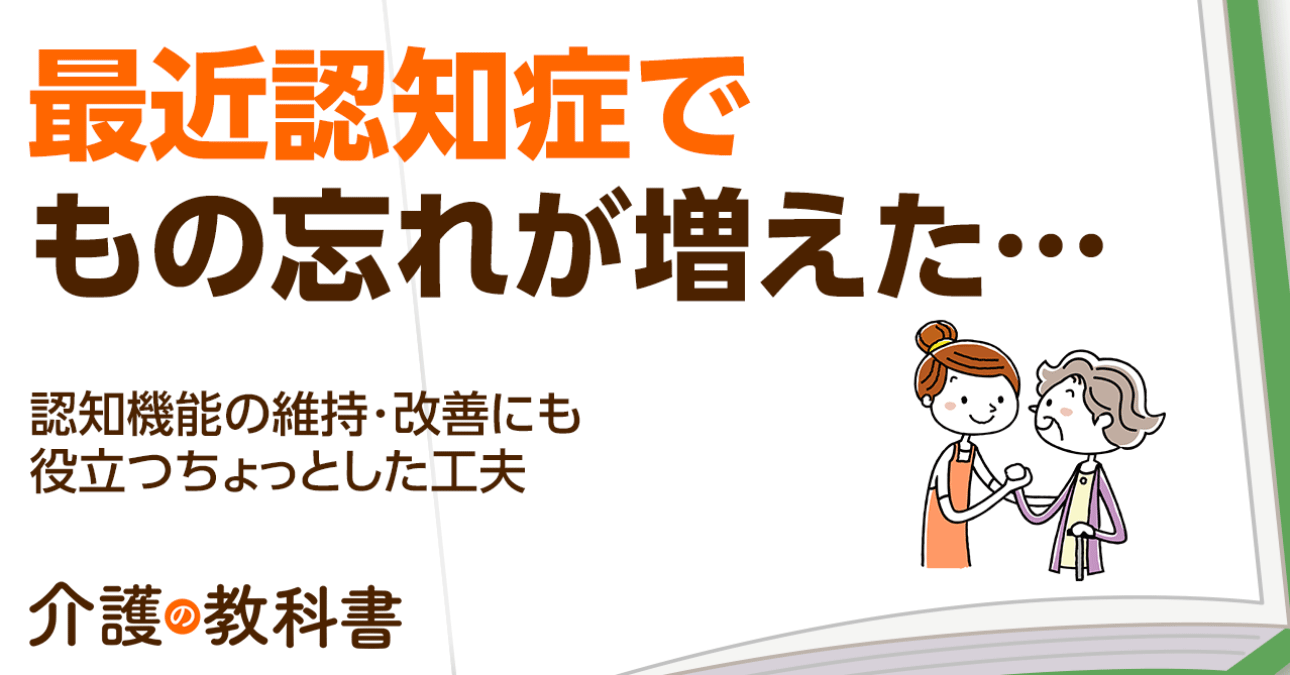認知症の代表的な症状が記憶障がいです。わかりやすく言えばもの忘れですが、一般的なもの忘れと認知症によるもの忘れ(記憶障がい)は違います。
今回は記憶障がいの特徴を一般的なもの忘れとの関係で見ていくとともに、周りの方が感じる兆候、またその対応についてお話します。
「記憶障がい」と「もの忘れ」の違い
記憶障がいの特徴は、認知症の方自身が忘れているという自覚がないことです。認知症の初期段階で多く見られます。
中には「この前こんなことを忘れてしまって…」と心配をされる方がいますが、記憶障がいの方からは聞くことがありません。
また、忘れる回数が増えたり、忘れる事柄が多くなることも、もの忘れでは見られません。
忘れた自覚がなくなっている場合は、いわば認知症が進行している状態で、人の助けが必要になります。その自覚がないことが、周囲の方の対応を難しくさせてしまうのです。
そして、忘れているといっても、何もかも忘れているわけではないことがあります。最近のことは忘れてしまうのですが、昔に体験したことや思い出といった体で覚えたことは覚えていることが多いのです。
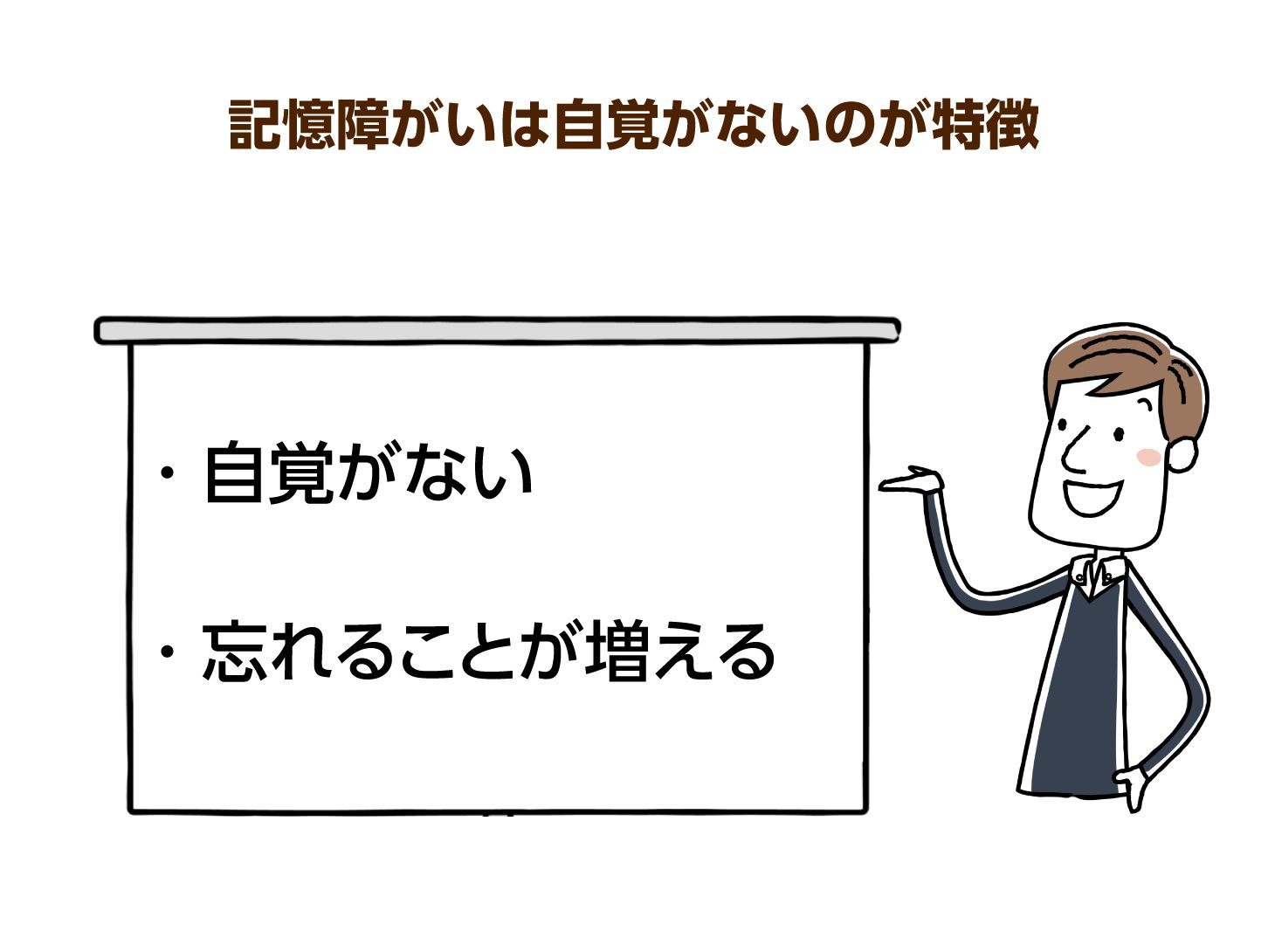
認知症による記憶障がいの兆候
本人に自覚はなくても周りの方が気づく変化、兆候があります。
例えば、同じことを何度も聞く行為です。わからないことを人に尋ねたとき、その答えをしばらく経って忘れてしまうことは誰でもあるかもしれません。
しかし、さほど時間の経たないうちに、初めてかのように何度も聞いてくることがあれば、記憶障がいの兆候といえるでしょう。
また、一緒に体験した内容について話をしていても、「その体験をしていない」などと言って話がかみ合わなくなったら注意してください。思い出せないのであれば、それも一つの兆候です。
忘れたことを決して責めない
最後に、よくある例を通して、対応について考えてみます。
食事をすませて間もないにもかかわらず、食べていないと話す方への対応です。
このとき、すでに食べ終わったことをわかってもらおうとするのは誤りです。「食べたでしょ」と繰り返し言ったり、食べ終わった食器を見せたりして思い出させるようなことをしても効果はありません。
少しでも食べたことを覚えている方であれば、思い出すきっかけにはなるかもしれませんが、食べた記憶自体がない方には、いくら言って聞かせようとしても意味がないのです。
では、本当に食べていない方を前にしたとき、どのように声をかけるかを考えてみてください。
例えば「つくるから待って」と声をかけたりします。こんなことを言うと「またつくらなくてはいけないのか」と思うかもしれませんが、実際につくる必要はありません。
食べたことをわからせる言動で相手の気分を害するより、ウソで構わないので少しでも食べられるとの気分になってもらう方が良いのです。
また「つくるから待って」と声をかけつつ、ちょっとした物を食べてもらうことも一つの方法です。少しお腹が満たされることで落ち着く方もいるのです。
また、タンスのある引き出しを開けてはいけないと話をしていても、忘れて何度も開けてしまう方がいました。介護者の奥さんは「言っても仕方のないこととわかってはいるものの、当初は言うことしかできなかった」とのことです。
そこで、話をすることに疲れたこともあり、「開けてはいけない」と張り紙をしたそうです。これが効果てきめん。一切開けなくなったそうです。言われたことが理解できなくなっている方には、目で確認してもらうことで理解される場合もあるのです。対応の発想を変えてみることも対処法の一つとして覚えておくと良いでしょう。
記憶障がいのある方に対して大切なのは、忘れていることを決して責めないこと。そのうえで、忘れていることに対して、対応する側が先に前向きになれる言葉をかけたりして働きかけることが必要です。