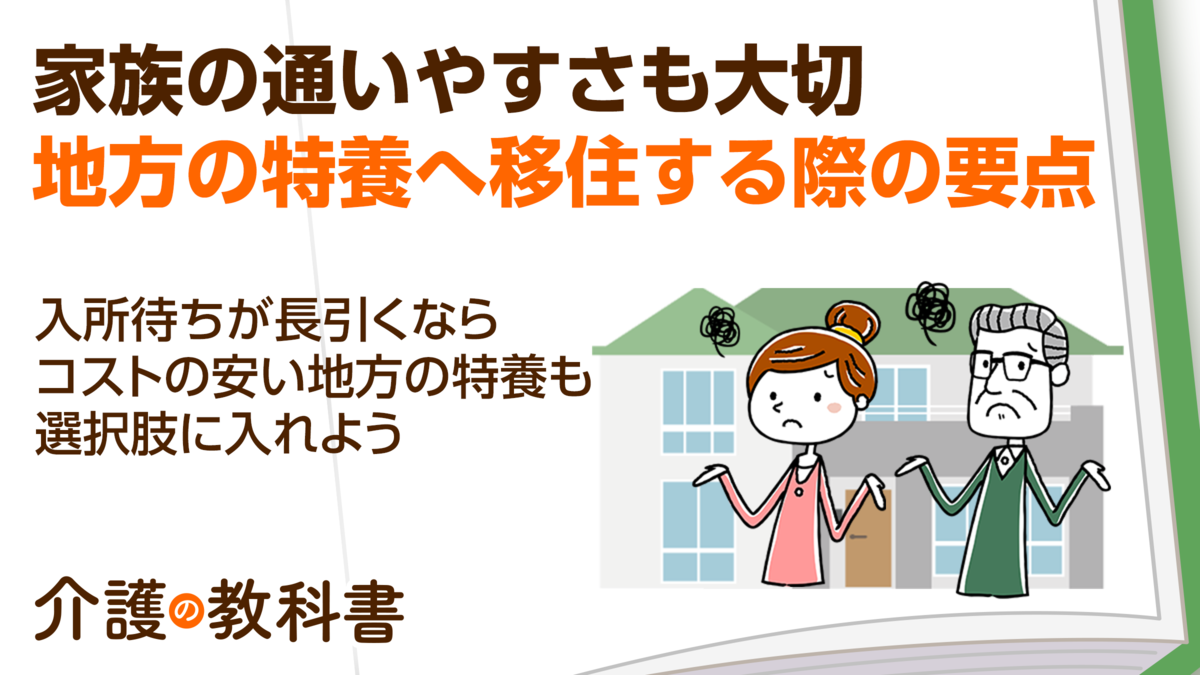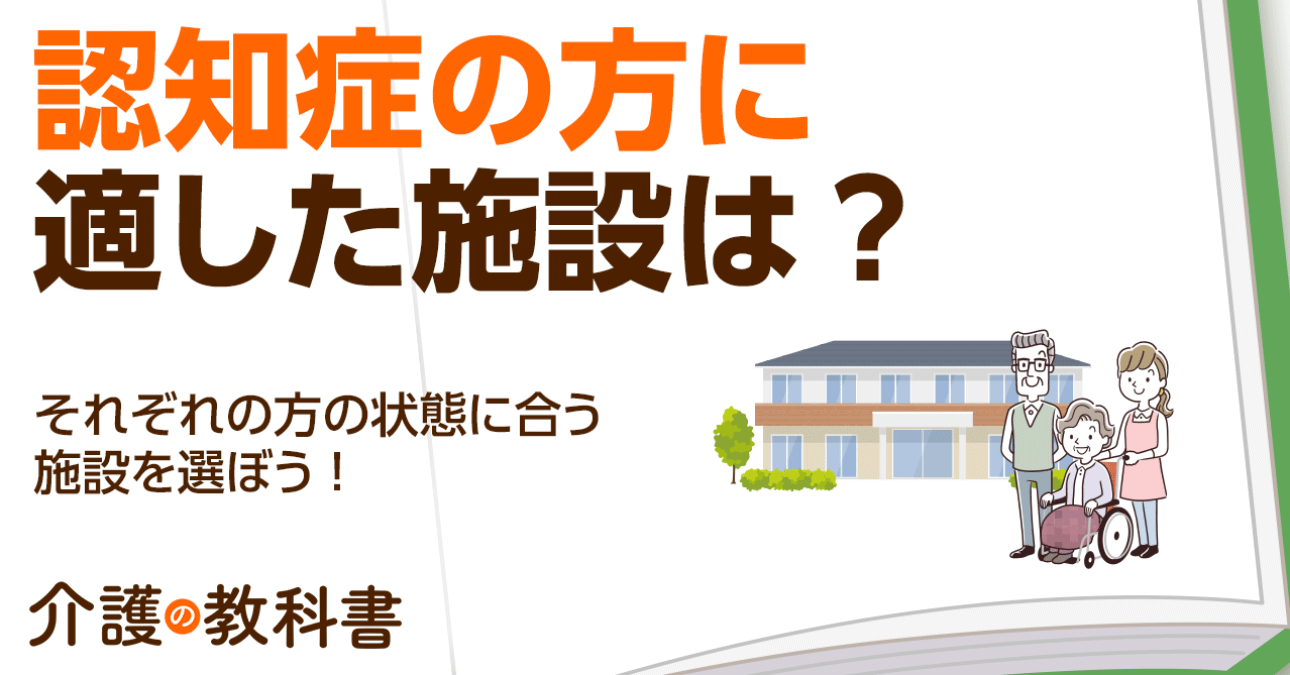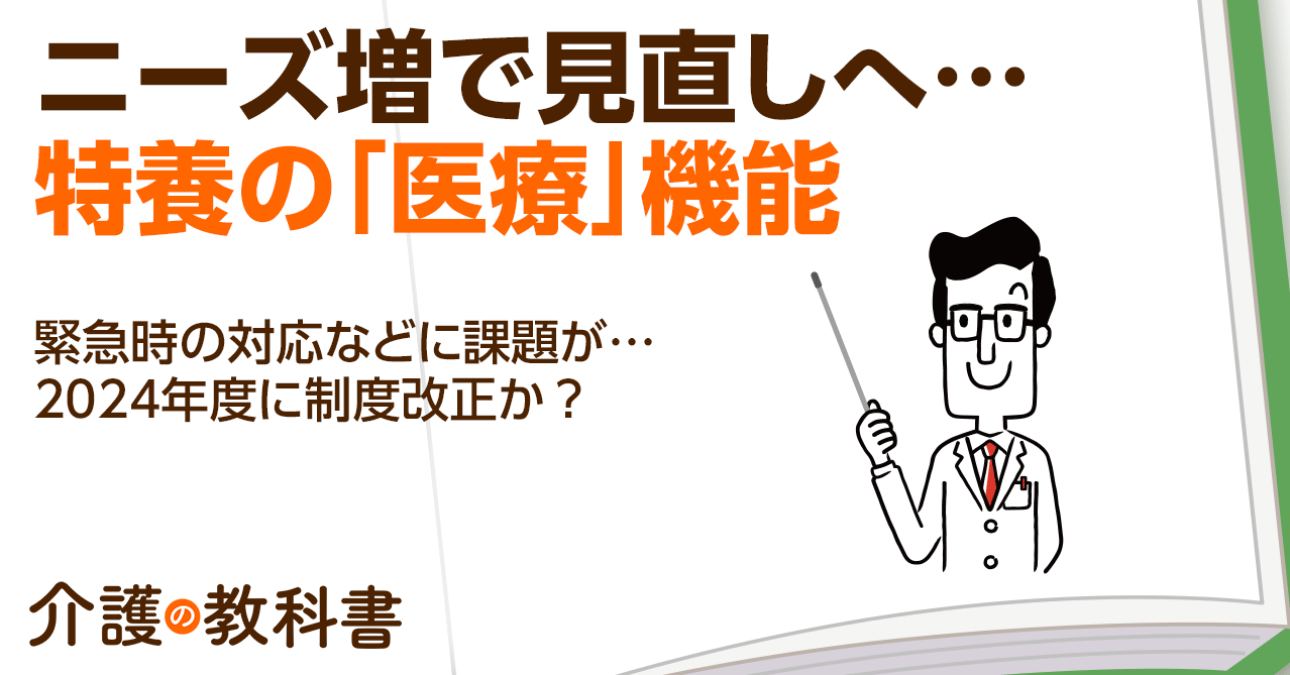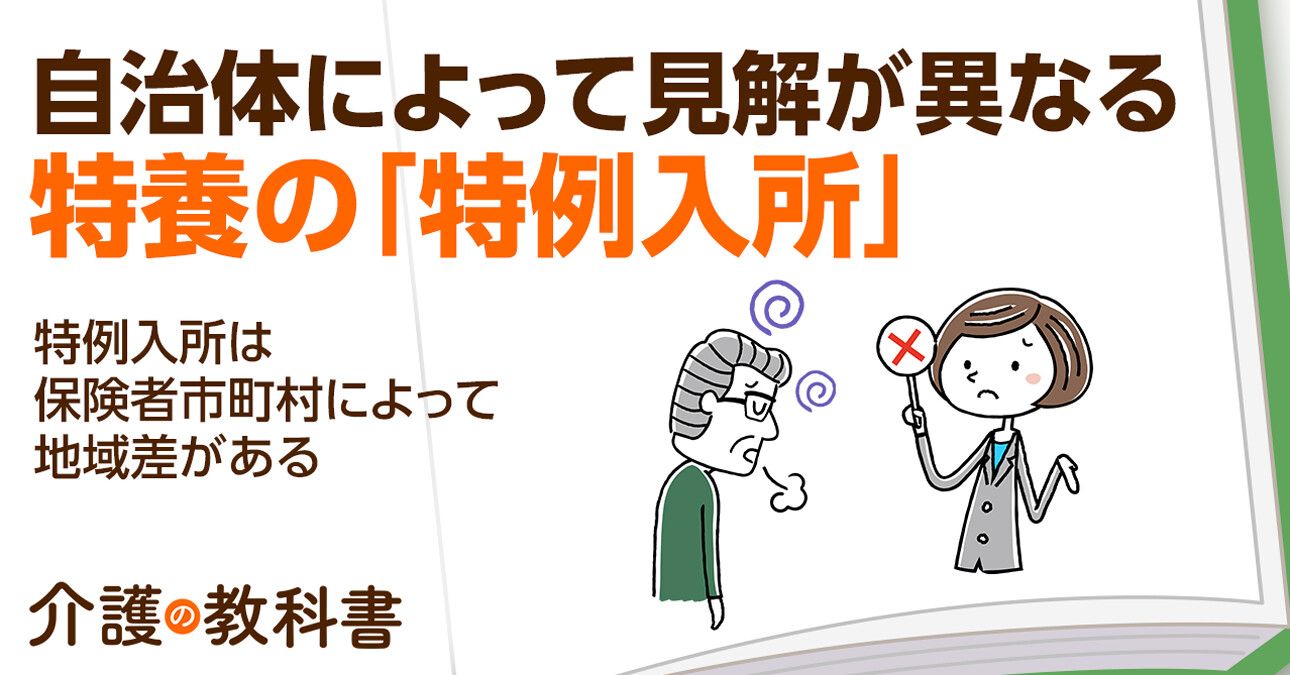日本は超高齢社会のピークを迎えようとしています。厚生労働省の発表では、2025年に認知症高齢者数は700万人を超えると推計されており、国は認知症に関するさまざまな施策を打ち出しています。
認知症の方が、できる限り住み慣れた地域で生活を送るためには、家族への支援の充実も必要です。また、在宅介護が困難になった際には、施設入所も選択肢のひとつです。
さまざまな種類の施設がある中で、一般的に浸透しているのが、特別養護老人ホーム(以下、特養)です。しかし、特養は待機者が多く、入所がしにくい施設ともいわれます。
2019年12月25日、厚生労働省老健局高齢者支援課が発表した「特別養護老人ホームの入所申込者の状況」によると、特養(地域密着型を含む)に入所を申し込んでいるものの、調査時点で当該特養に入所していない人は、約29万人とされています。
さらに同資料では入所申込者の都道府県別の状況も示しており、都市部の特養ほど申込者数は多く、都市部を離れた地方は申込者数が少ないことがわかります。
そこで今回は、地方の特養に移住する際のポイントを解説します。
着地点を探す発想が必要
国は2010年代から「地域包括ケアシステム」を推進しています。地域包括ケアシステムとは、要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みです。
一方、地方創生とセットで、都市部から地方へ高齢者が移住する政策が政府主導で推進されてもいます。これは、都市部よりも高齢化のピークを早く迎える地方圏の介護施設が利用できるうえ、生活コストも抑えられるというメリットがあります。
国が進める地域包括ケアシステムと地方への移住は相反するものに映るかもしれませんが、「こうあるべき」「これが絶対」と固執するのではなく、着地点を見出す発想が必要だと思います。
つまり、都市部の施設から地方の介護施設へ移り住むことも選択肢として持っておくことがおすすめです。
ただし、むやみにどこでも良いというわけではなく、着地点を見つけて折り合いをつけて考えることが大事です。

都市部から地方の介護施設に移り住む際のポイント
1.家族の通いやすさ
介護施設を選ぶ際に、考慮したいことは家族の通いやすさです。入所する本人に定期的に会いに行くためには、家族の住まいと施設の距離も重要なポイントになります。
また、高齢者は状態が変化する可能性もあり、医療機関受診や緊急時等など、家族がすみやかに駆けつけなければならないこともあります。
家族の住まいと離れてしまうと面会に行きにくい、緊急時にすぐに駆けつけにくいなどのデメリットもあるので、慎重に検討しましょう。
2.本人にゆかりのある地
まったく見知らぬ地ではなく、本人にゆかりのある地であるかどうかも選定のポイントです。都市部で生活していたが、生まれや育ちが地方という方も多く、その方に馴染みある場所であれば、不安感も少しは軽減されることも考えられます。
3.より良い施設・事業所を選定する
都市部・地方に限った話ではありません。人生のラストステージを託すわけですから、より良い施設・事業所を選ぶことが大事です。選ぶ際に最低でも次の2つは行ってください。
- 1.施設のパンフレットや資料を取り寄せる
- パンフレットや資料には基本的な情報が記載されています。ただ、この情報だけを鵜呑みにするのではなく、見学したいと思える施設を選ぶつもりで取り寄せましょう。
- 2.電話をかけて相談や施設見学のアポイントをとる
-
コロナ前は、見学の予約なく、施設に飛び込み相談が可能でした。しかし、今は多くの施設が感染対策のために、施設内での相談・見学に事前予約が必要となっています。
事前予約は電話が一般的ですので、その際に窓口となる相談員の電話応対を確認します。
外部の方への応対がていねいで適切か、家族の不安を解消できる、または家族の視野を広げられるような対応ができているかなど、電話応対でもわかることもあります。
- 3.施設見学をする
- 見学の際は、施設設備(居室・リビング・浴室など)や職場の雰囲気を確認します。
- 4.職員の人数と質
-
利用者の生活の質を大きく左右するのは、そこで働く職員の知識・技術・意識です。まずは人員配置がどのようになっているのか確認しましょう。
具体的には、日中は利用者数に対して何人の職員が配置されているのか、夜間帯はどうかなどを聞いておくと良いでしょう。
また、施設・事業所が大事にしている実践の考え方、それをどのように具現化しているのかを確認することも重要です。
- 5.入居者の生活風景を確認する
- 窓口となる相談員の話だけではなく、実際の生活場面を確認し、入所後の生活をイメージしてみましょう。
- 6.家族連絡の頻度や受診対応の実際、緊急対応時の体制などの確認
- 施設・事業所が家族に対して、どのような内容を、どのくらいの頻度で連絡がもらえるのか、を確認します。
- 7.面会などの方針を確認する
- コロナ禍では、その施設・事業所がある地域の感染者数などによって、直接面会を制限する場合もあります。直接面会が可能であっても、面会は予約制で人数制限を実施しているところもありますから、忘れずに確認しておきましょう。
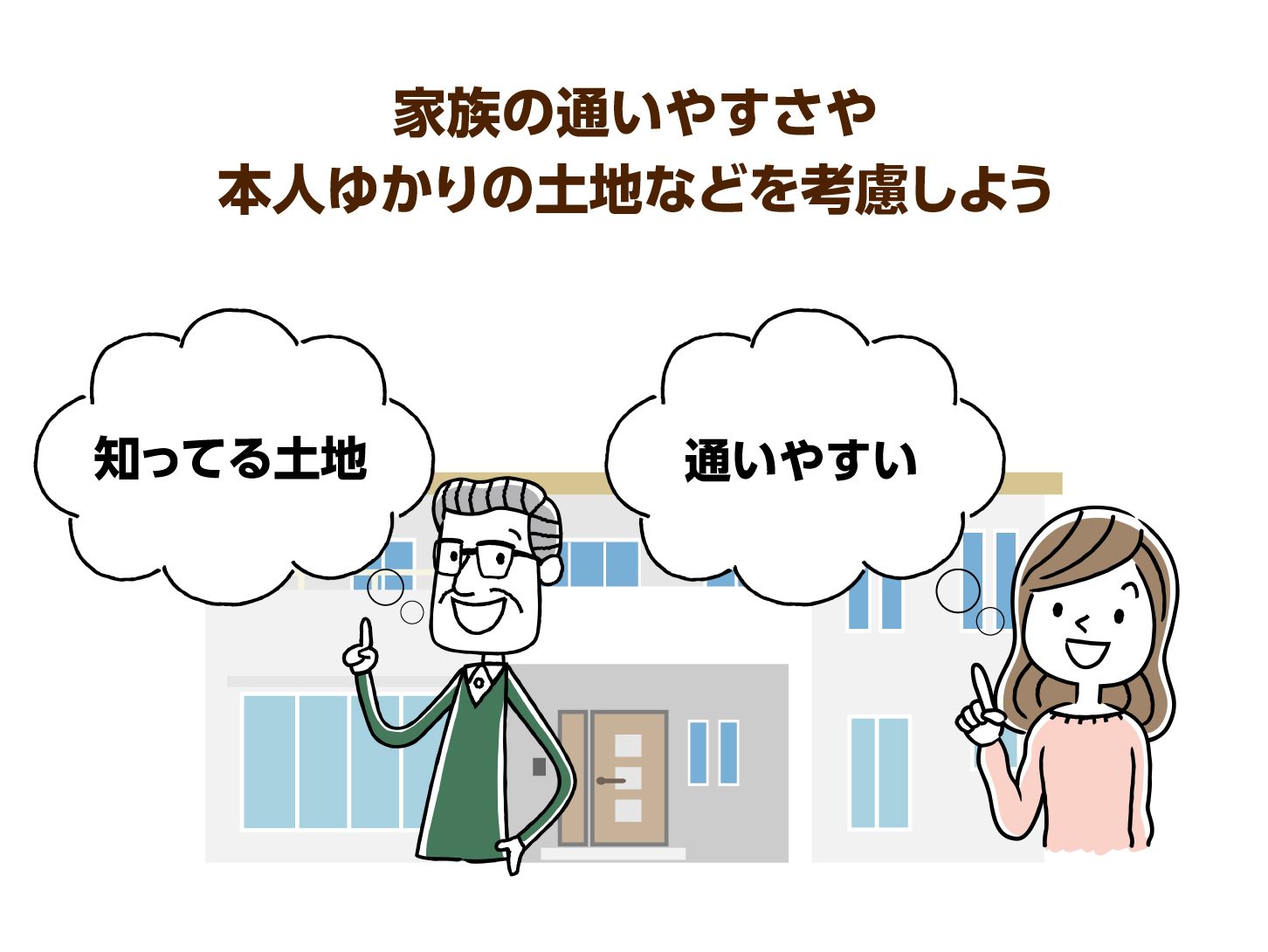
高齢者にとっては、住み慣れた場所から馴染みのない場所に転居することがストレスになり、心身に弊害を与えてしまうと言われます。
そのため、環境の変化や移住は良くないとマイナスに思われがちです。確かに環境の変化によって、本人の不安感が増して混乱することはありえます。
しかし、環境変化によるストレスは、人として生きている以上、避けては通れないものです。
例えば、新しい職場の入社初日、または人事異動で部署が変わったときを思い返していただきたいのですが、人は新しい環境にさらされたときにストレスを感じます。
しかし、日時が経つにつれて、仲間と打ち解ければ、環境に慣れてストレスは軽減していきます。環境そのものは何も変わっていないにもかかわらず、ストレスは減っていくのです。
環境の変化が悪いという考えにとらわれすぎると、認知症の状態にある方とその家族が共倒れになる可能性があります。
本人の状態や家族状況によっては、環境を変えざるも得ない、つまり施設入所という選択肢もあるということです。そのときに、今回紹介した施設選定のポイントを参考に検討してみてください。