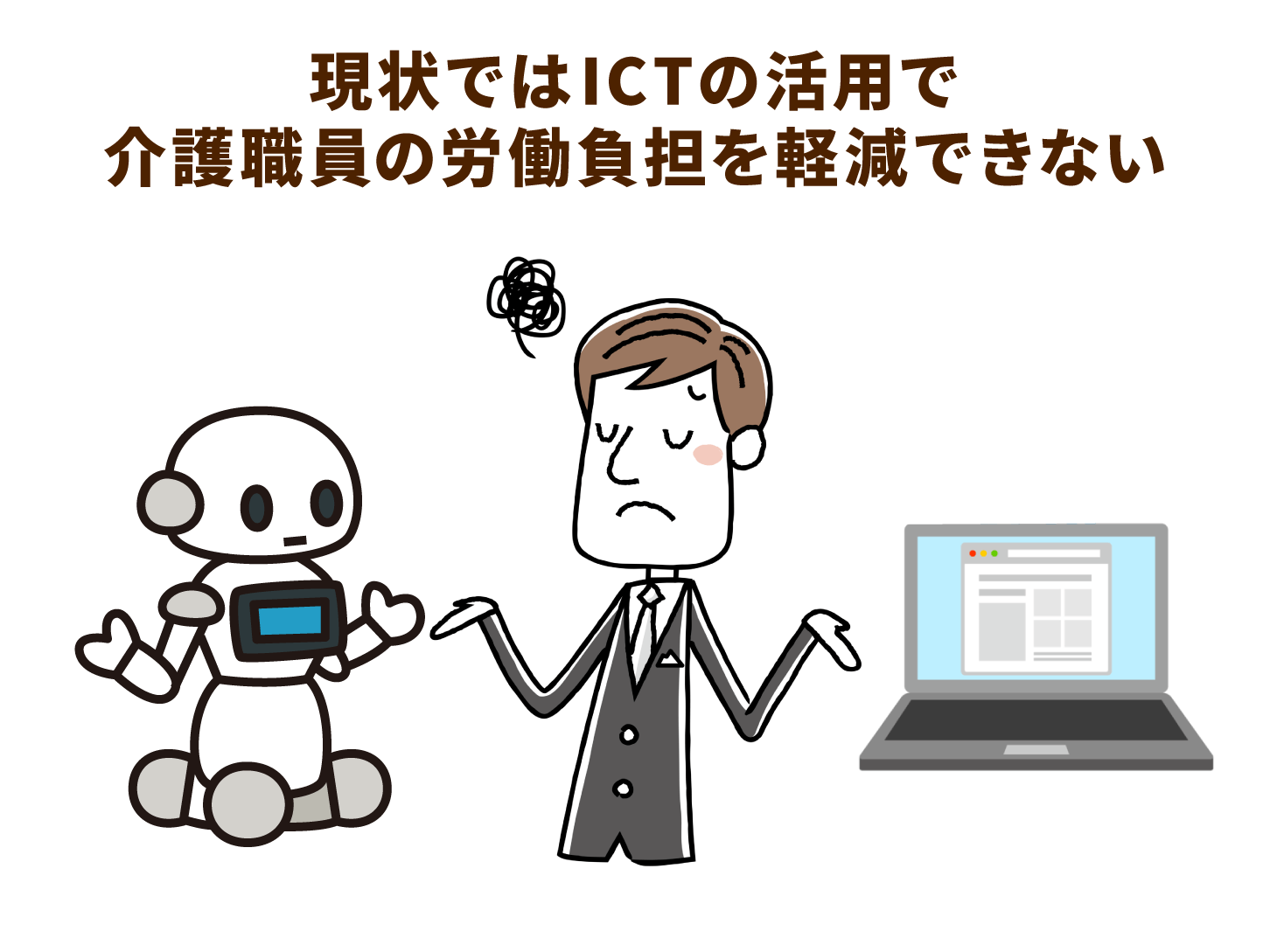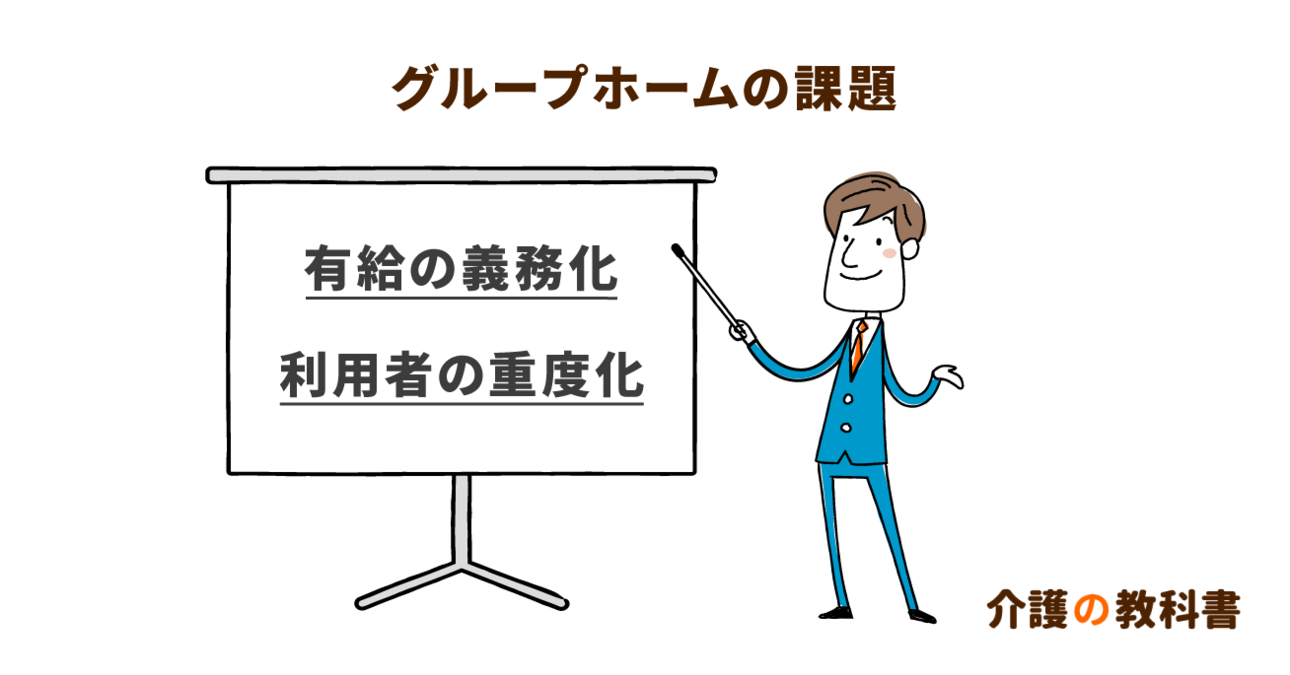株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
第206回・209回・212回・第215回に引き続き、介護保険法にもとづく運営基準(省令)や解釈通知などから、特別養護老人ホーム(特養)の特徴や基本事項を確認していきます。
今回は「人員に関する基準」です。
特養における現行の人員配置基準
2022年1月に日本経済団体連合会(経団連)が、「現行で3対1と定められている介護施設の人員配置基準を見直すべき」と提言したことが話題になりました。効率的な介護記録システムや情報連携ツールの導入、見守りセンサー・ロボットといったICT(デジタルテクノロジー)などの活用を前提とした人員基準緩和策です。
また、2月には厚生労働省が介護職員の配置基準を緩和する方向で検討に入ることがわかりました。その検討に向け、「介護現場でICTを活用した際の業務効率化を数値化する実証事業を2022年度に実施」する予定です。
この議論は2024年度に予定されている介護報酬改定に向け、今後も取りざたされていくと思います。では、現行の特養の人員配置基準はどうなっているのか、確認してみましょう。
特養に必要な人員配置基準を以下にまとめてみました。
| 管理者(施設長) | 常勤1人以上 | |
|---|---|---|
| 医師 | 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 | |
| 介護職員または看護職員 | (1)総数 | 常勤換算方法で入所者3人に対し1人以上(3:1) |
| (2)夜間及び深夜 | 入所者25人以下:1人以上 入所者26人~60人:2人以上 入所者61人~80人:3人以上 入所者81人~100人:4人以上 入所者101人以上:4人+(入所者数25増毎に1人)以上 |
|
| (3)ユニット型特養 | 日中:1ユニットに1人以上 夜間及び深夜:2ユニットごとに1以上 ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 |
|
| (4)看護職員 | 入所者30人まで:常勤換算方法で1人以上 入所者30人超50人未満:常勤換算方法で2人以上 入所者50人超130人未満:常勤換算方法で3人以上 入所者130人超:常勤換算方法で3+(入所者数50増毎に1人)以上 ・1人以上は常勤 |
|
| 生活相談員 | 入所者100人に対して常勤1人以上(100:1) (入所者の数が100またはその端数を増すごとに1以上) |
|
| 栄養士 | 1人以上 | |
| 機能訓練指導員 | 1人以上 | |
| 介護支援専門員 | 入所者100人に対して常勤1人以上(100:1) (入所者の数が100またはその端数を増すごとに1を標準とする) |
|
| 宿直 | 夜勤者とは別に必ず配置 (最低基準を上回る数の夜勤者を配置していれば配置無しでも可) |
|
人員配置基準のポイント
緩和が提言、検討されている介護職員の人員配置基準ですが、特養の場合、ポイントが2つあります。
まず1つ目は、特養に配置すべき介護・看護職員の人数は「定員あたりの総数」であることです。
「定員あたりの総数」というのは、「1日あたりの人数」ではありません。なので、365日毎日、入所者3人に1人の介護・看護職員が配置されることでも、常時(24時間)配置されるということでもないのです。
現実はというと、介護・看護職員はシフト制勤務で休日もありますから、日によって人数にバラつきが生じます。
2つ目のポイントは、「介護職員または看護職員」と規定されていることです。
例えば、定員100人の特養の場合、「介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で入所者3人に対して1人以上」で34人、このうち看護職員は、「入居者50人以上130人未満の場合は、常勤換算方法で3人以上」なので最低3人となります。
つまり、最低基準の人員配置であれば、「介護職員31人+看護職員3人」で良いということです。
ICT活用で介護職員の負担は軽減できない!?
厚生労働省が公表している「令和2年介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、特養の1施設あたりの定員は平均69.3人となっています。
この結果を踏まえて定員を70人とした特養の場合、介護職員または看護職員24人、このうち看護職員は3人の配置が必要なので、「介護職員21人+看護職員3人」が最低基準の人員配置となります。
では、この人員配置の場合、1日あたり何人の介護職員を配置することが可能なのか試算してみます。
| 根拠とする数字 | 左記数字の求め方 | |
|---|---|---|
| 1 | 年間休日数108日 | 1ヵ月単位の変形労働時間制で最低限必要とされる休日数 |
| 2 | 年次有給休暇を年間12日取得 | 特養の平均勤続年数7.8年(令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果より)。 労働基準法上、当該勤続年数の有給休暇付与日数は年20日となるので「有給休暇を1ヵ月平均で1日取得」とした |
| 3 | 年間120日の休日 | (1)108日 + (2)12日 =120日 |
| 4 | 1ヵ月の勤務日数20日 | 年365日-(3)年間休日数120日=245日 245日÷12ヵ月=20.4日 ※端数の0.4日は余剰分としてシミュレーション |
| 5 | 施設全体で1ヵ月420勤務が発生 | 介護職員21人×(4)勤務日数20日=420勤務 |
| 6 | 1ヵ月に必要な夜勤・夜勤明けの勤務数は180勤務 | ※1日あたり夜勤3人×30日=90勤務 ※1日あたり夜勤明け3人×30日=90勤務 ※90勤務+90勤務=180勤務 |
| 7 | 施設全体で日中の配置が可能な勤務は月240勤務 | (5)月420勤務-(6)夜勤・夜勤明け勤務:月180勤務=240勤務 |
| 8 | 1日あたり日中配置できるのは8勤務(人) | (7)日中配置:月240勤務÷30日=8勤務(人) |
定員を70人とすると、1日あたり日中8人の介護職員が配置される計算になります。これだけを踏まえると、日中の介護職員1人あたり8.8人の入所者の方を介護することになりますが、現実はそれ以上の人数を介護しています。
介護職員はシフト勤務のため、日中常時8人の介護職員が配置されるわけではないからです。介護給付費分科会の資料によると、特養入所者の平均要介護度は3.95ですから、要介護度4の入所者10人程度を1人で介護しているのが現実です。
これでは仕事がまわらない・休憩もとれない・シフトがまわせない状況になるため、多くの特養は3対1基準以上の人員を配置しているのです。
また、この試算は、夜勤を介護職員の負担が大きい16時間配置とすることで成立させています。さらに、ユニット型の場合は1日あたり8勤務では介護職員が足りません。定員70人の場合、最低でもユニットの数が7になりますので、この最低基準の人員配置による試算では、日中1ユニットに1人の介護職員しか配置できないからです。
高性能の見守りセンサーで介護職員が巡回しなくて済む時間はつくり出せても、センサーの反応に対応するのはロボットではなく、人(介護職員)です。配置する介護職員の人数を減らせば、介護職員の労働負担は今よりも増えます。
また、作業のような食事介助ではなく、噛む・飲み込むこと・姿勢などに注意しながら、美味しく感じたり、食事の時間を楽しんでもらえることを心がけた食事介助ができる介護ロボットも存在しません。
利用者の心情や反応を見ながら対応を変えて、会話することができる介護ロボットもありません。介護の知識・技術・意識を持った専門職に代わる介護ロボットが存在しない現状では、特養の介護職員にかかる負担はかなり重いと言わざるを得ません。
デジタルテクノロジーなどは現状、残念ながら人員配置基準の緩和(人を減らす)の根拠にはならないと考えます。
介護保険制度は、「心身の状況に応じて、要介護者の自立を支援する」ことを目的としています。人手を減らすためのデジタルテクノロジーではなく、介護職員の負担を減らして本来やるべきこと(介護保険制度の目的)に集中できるようにしたり、離職防止と定着率向上という目的のために使ったりすることをが大切ではないでしょうか。