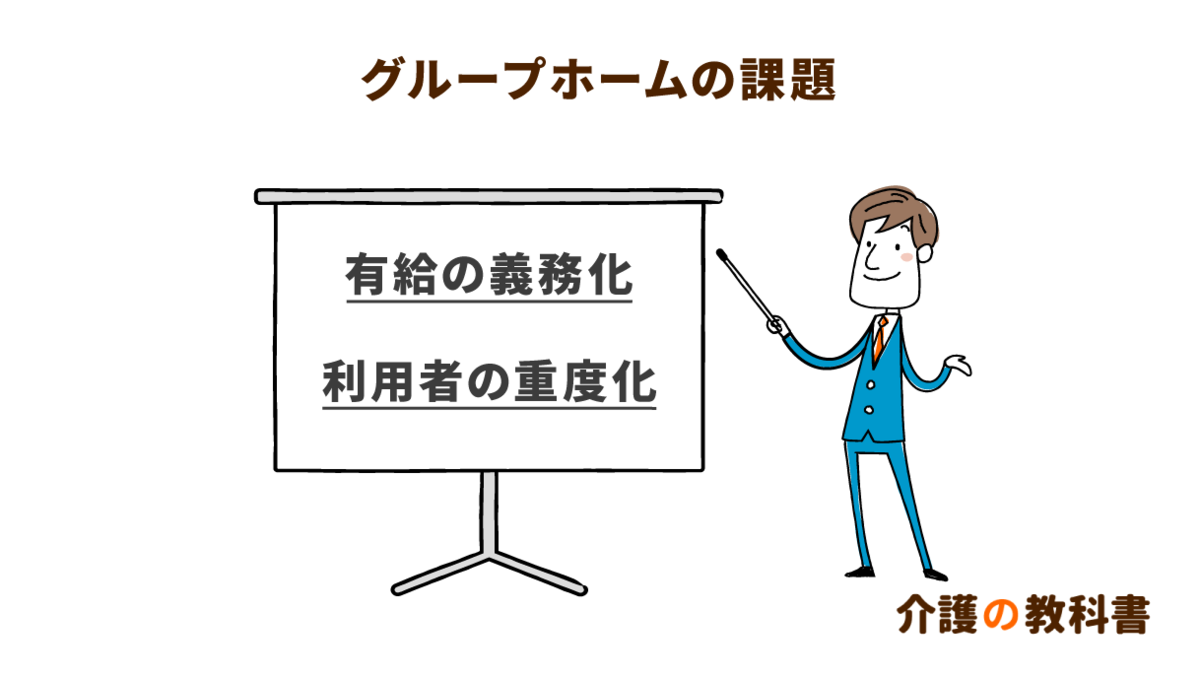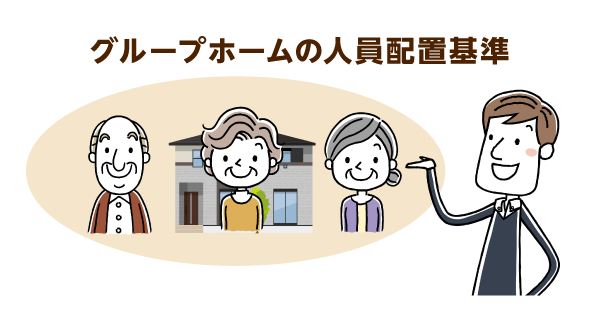株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
前回に引き続き、私の10年半に及ぶグループホームのホーム長の実務経験を交えつつ、運営基準などの法令を基に、グループホームの特徴や現状での課題などを改めて考えていきたいと思います。
前回同様、ここで取り上げるグループホームは、介護保険法上の「認知症対応型共同生活介護」事業です。
有給休暇年5日取得の義務化が事業継続に与える影響
前回の終わりに、グループホームには、労働基準法改正による「年次有給休暇が10日以上発生した従業員に年5日以上の年次有給休暇を取得させること」の義務づけによって生じる課題があることをお伝えしました。
その課題を確認するにあたり、まずはグループホームの人員配置基準から、実際に必要となる介護職員の人数を計算してみます。
1ユニット9名定員の場合
●日中:介護職員3名×8時間=24時間
●夜間・深夜:夜勤(介護)職員1名×16時間=16時間
よって、1日あたり40時間分(24時間+16時間)の介護職員が必要
●40時間×365日=1万4,600時間
よって、年間1万4,600時間分の介護職員が必要
●1万4,600時間÷12ヵ月=1,216.6時間
よって、1ヵ月あたり1,216.6時間分の介護職員が必要
●1,216.6時間を168時間(職員:1月の勤務日数21日×8時間)で割ると7.24
つまり、1ユニット約7名の(常勤)介護職員が最低必要
単純計算で、介護職員1名に年間5日の有給休暇を取得させれば7名×5日=35日となります。1ヵ月の総公休数63日(7名×公休9日)に、約3日(35日÷12ヵ月=2.9)の有給休暇取得数が加わります。1ユニット約7名の(常勤)介護職員の体制では、この月3日を捻出するのは苦しいのが現状です。
その理由として、この約7名配置は人員配置基準をクリアするギリギリの人数なので、余剰人員分がほとんどないことにあります。そもそも余剰人員分がないため、介護職員を外部の研修に参加させる余裕も、慶弔休暇なども取得しにくいのです。また、職員自身や子どもの体調不良などによる急きょの休みに脆い体制でもあります。
そうであれば解決策として、基準以上の介護職員を配置することが考えられますが、介護職員の給与の原資である介護報酬は人員配置基準を上限に設定されています。基準以上の介護職員を配置(雇用)すれば、職員一人あたりの給与が下がってしまうため、余剰人員分をつくりにくい事情があるのです。
また、グループホームは、前回もお伝えしたとおり、「1日あたりの最低限の定量(介護職員数)」が基準化されています。
ということは、介護職員の休みが増えれば、その分を穴埋めする人手が必要となります。しかし、多くの事業所が、現状の人員配置基準を満たすために必要な人手を確保することにさえ苦労しています。また、人手を増やせたとしてもコスト高になります。そのため、有給休暇年5日取得の義務化は、事業者にとってグループホームの運営を続けていくうえで大きな課題なのです。これが、求人を出してもなかなか雇用に結びつかず、派遣職員を使ったり、職員の残業でやりくりしている事業所であればなおさらです。
有給休暇年5日取得の義務化は、職員には良いことでも、事業者にとっては事業を継続していくうえで大きな課題であると言えるでしょう。

利用者の重度化への対策
そのほか、グループホームの課題とされているのが、利用者の重度化への対応です。
介護報酬のことなどを審議する介護給付費分科会でも、たびたびグループホームにおける利用者の重度化対応について議論が交わされています。
グループホームはそもそもの制度設計において、身体的自立度の高い要介護1・2・3の認知症の状態にある方が利用することを想定されていたと思います。現に、2020年10月9日に開催された介護給付費分科会の資料によると、グループホーム利用者の平均要介護度は2.74で、利用者の割合は70.8%が要介護1~3の方となっています。しかし、利用者の入居期間の長期化とともに、老化や認知症の進行により、徐々に心身機能が低下してくるわけです。
私がホーム長を務めていたグループホームも、ほとんどの入居者の方が室内では歩行による移動が可能で、見守りや声がけなどによって買物や炊事、掃除などに取り組むこともできました。それが開設から7年、8年と経過する頃には、移動手段は車椅子になり、食事や着替えなど生活全般に介助が必要な方が増えていきました。
いわゆる「入居者の方の重度化」です。しかし当時、課題と感じていたのは重度化への対応ではなく、「状態に差のある入居者の方への支援」でした。
例えば、家事への取り組みです。
当初は、入居者の方9名対職員2~3名(9対2~3)で、グループホームだからこそ実践しやすい掃除・洗濯・炊事・買物といった家事に取り組んでいました。しかし、開設7~8年目になると、家事で能力を発揮することが難しくなった入居者の方もいて、調理の場にいるだけになっていました。それは、妙な平等感から9名全員が同じでなければと考える職員が、9名が集まっている(だけの)調理に固執したために起きたことでした。
そのような状況に疑問を持つ職員もいたことから、入居者の方の状態差が生じた調理への取り組みについて職員会議で話し合いました。その席で私からは、「9名それぞれが、それぞれの能力や状態に応じた生活を送ることが大切であること」、だからこそ「職員が支援する・介助する場面や内容、その際に要する時間は一人ひとり違うこと」、「違うことは不公平ではないこと」を伝え、そのことを理解してくれた職員は、入居者の方「それぞれの暮らしの再構築」を行ってくれました。
そのほかには、支援の仕組み(現状)を定期的に点検し、課題が見つかれば工夫を施して解決していきました。
例えば、このグループホームは1ユニット9名の入居者の方に対し、7時から20時の時間帯に2~3名の職員が勤務していました。「9対2~3」や「1対1と8対2」の組み合わせであれば、職員同士の助け合いが可能になりますが、「1対1と1対1と7対1」では職員が分断され、助け合うことはできません。
そのため、職員の分断が固定化されないように、「入居者の方1名に対して職員1名の組み合わせとなる入浴支援や受診が重ならないようにする」「重ならないようにするために職員の勤務時間を変更する」といった取り組みを行ったのです。
また、状態に差のある入居者の方への支援のために、次のような職員一人ひとりのスキルを上げることにも取り組みました。
- 「一人でできること」を増やす
- 例えば、自分一人で見守り支援ができる入居者の方の人数を増やすことや、自分一人で買い物や散歩などに連れていける入居者の方の人数を増やすなどです。
- 「一人で一度にできること」を増やす
- 例えば、食器洗いをしながらリビング全体の見守りができる、歩行支援をしながらその方の顔や口の中の汚れ、洋服の乱れや汚れ、口臭や尿臭などといったことを確認して次の支援につなげたりするなどです。
「状態に差のある入居者の方への支援」は「重度化への対応」とイコールです。課題であるからこそ、このような「今できること」を探し、取り組んでみることが大切だと思います。次回もグループホームの特徴などについてお伝えします。