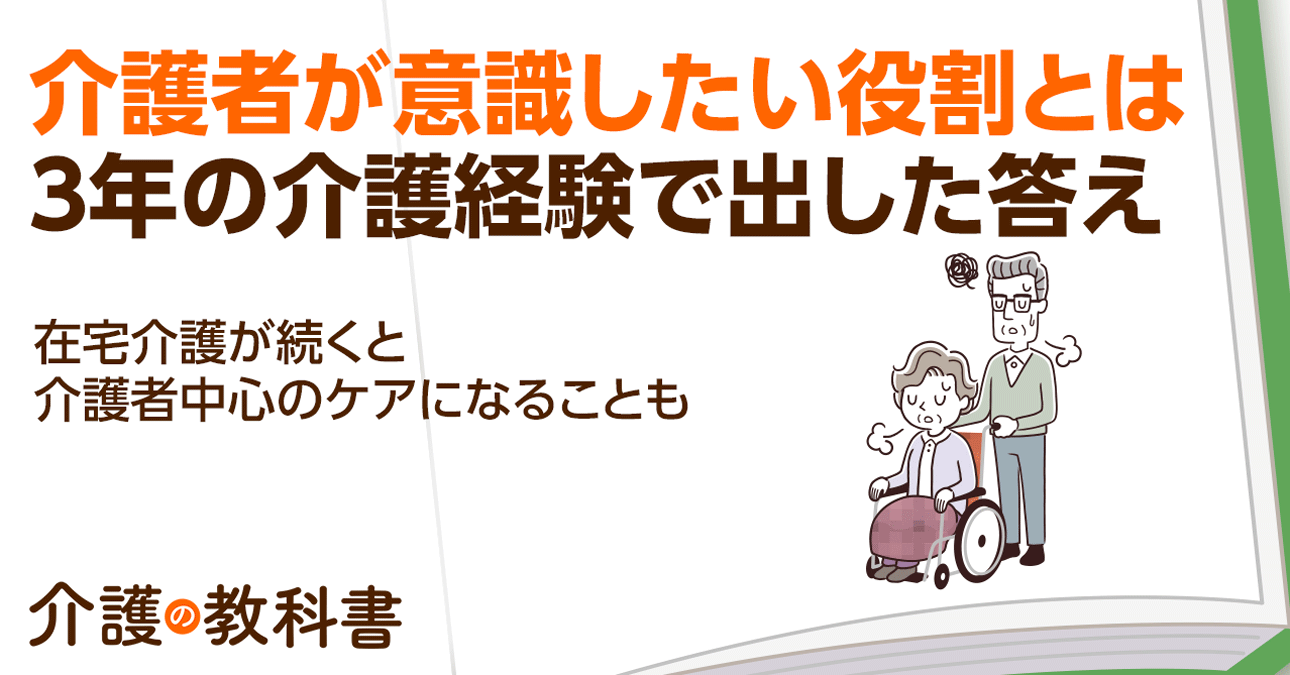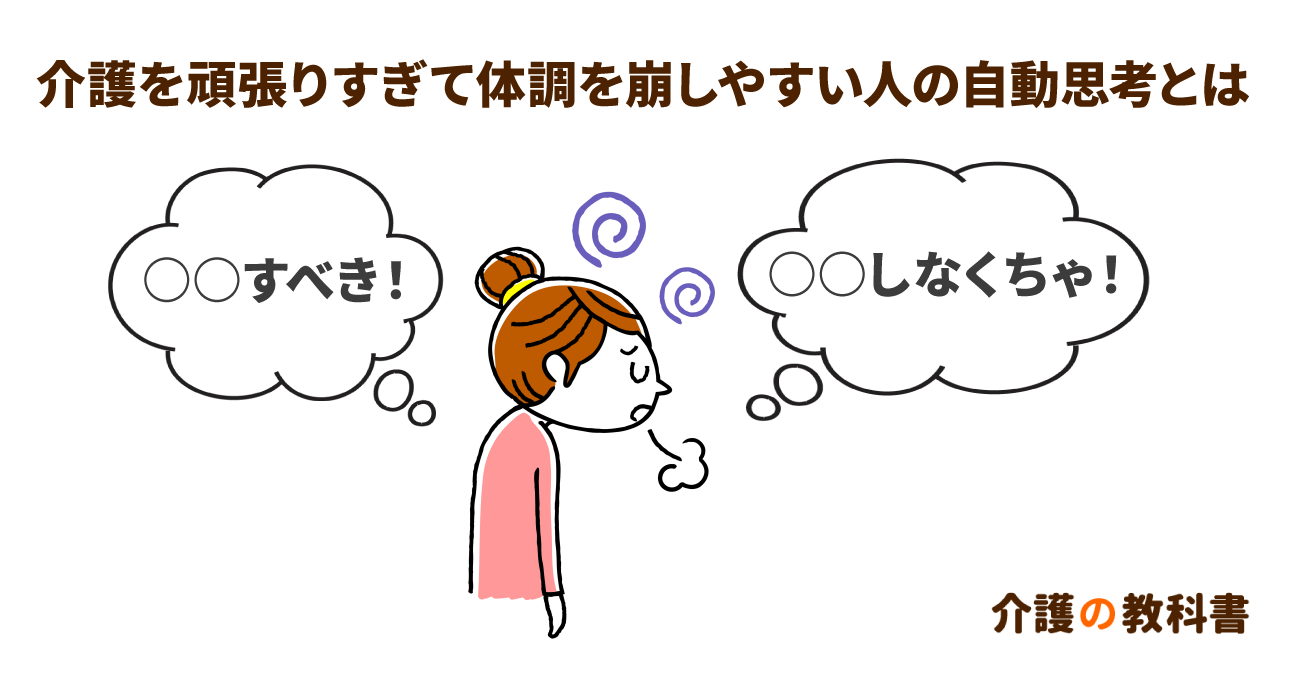株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
今回は、Mさんという方の事例を通じて、利用者の方の一方的な要望に応じることについて考えてみたいと思います。
Mさんの事例
Мさん(女性)は通所介護と訪問介護を利用しながら、アパートで一人暮らしをしていました。甘いものが大好きで、自宅にいるときは、三度の食事以外に訪問介護員さんに買ってきてもらったお菓子などを間食する生活を送っていました。
別々に暮らしている息子さんがMさん宅を訪ねる前に連絡をすると、必ず食べもののオーダーがあるそうです。その内容は、カロリー高めなハンバーグや唐揚げのお弁当、甘いものだとプリンやアイスクリームなどです。息子さんは、その内容もそうですが一度のオーダーが多いのではないかと感じても、母親の希望通りに買ってきていました。そんな息子さんは、「お母ちゃんの好きなようにさせているので」とケアマネージャーに伝えていたそうです。
しかし実際は、Mさんは干渉されるのが大嫌いな方で、人の言葉に耳を貸さないことを息子さんは知っているため、何も言わないだけでした。それは担当のケアマネージャーも同じで、Mさんの食生活や体のことが気になってはいても、何か言えば怒るMさんが苦手で、何も言えない関係性だったのです。
さらにMさんは人一倍訴える力が強く、一度言い出したら聞かないので、息子さんもケアマネージャーも「要望をのまざるを得ない」という状況だったようです(要望をのんでいる方が楽という気持ちもある)。
Mさんは、左半身に軽い麻痺がありましたが、杖を使いながらの自力歩行は可能でした。しかし、もともと動くのが嫌いなうえに依存心も強いため、アパートでの暮らし全般を訪問介護員さんに代行してもらい、移動の際も車椅子を要求していました。通所介護の利用も他利用者との関係を持とうとせず、食事を自力で食べること以外は「あれやって」「これやって」の状態でした。
太りすぎて転倒事故が発生
さて、皆さんでしたらMさんにどのような支援をしていこうと考えますか?
介護においては、「本人の意思や希望、気持ちに応じる(尊重する)ことが大切」だと言われます。また、そのためには傾聴・受容・共感などのコミュニケーション技術が必要だとして、介護職員初任者研修のカリキュラムにも取り入れられています。
本人の意思や要望に応じる観点から考えれば、「Mさんが食べたいものを好きなように食べさせてあげよう」「動くのが嫌いなのだから無理はさせず、介護者がやってあげよう」「暮らしの継続が大事なのだから、これまでと同じような暮らし方をさせてあげよう」となるのではないでしょうか。
その後、動くことが嫌いで依存心も強いМさんは運動量が少なくなっていました。そこに輪をかけて食事は偏食、甘いものが大好きで間食を続ける毎日でした。その結果、Mさんの体重はみるみる増えていったのです。
太ったMさんは、お尻に手が届かなくなってしまい、排便後にトイレットペーパーでお尻を拭くことができなくなってしまいました。拭ききれないために下着が便で汚れてしまい、彼女の体と自宅からは常に便臭が漂うようになりました。
太った体が、自分の屈曲や伸展の邪魔をするようになりました。そのため、介助なしでは着替えられなくなり、入浴では体を隅々まで洗えなくなりました。自分で靴を履くこともお腹の肉が邪魔をしてできなくなってしまいました。
そして、動きづらい体になったMさんは、一人暮らしのアパートでついに転倒してしまいました。転倒したМさんは太りすぎて一人では身動きがとれず、たまたま訪ねてきた民生委員さんに発見されて、救急車で病院に運ばれたのです。幸い、骨折や裂傷はありませんでしたが、転倒時に体を相当強くぶつけたようで痛みがひどく、入院することになってしまいました。さらに検査の結果、糖尿病を患っている可能性が高いことも判明。体の痛みがひいても、糖尿病の治療が必要ということで長期入院せざるを得なくなったのです。

専門性を発揮して利用者と向き合うことが大切
この経緯を踏まえると、改めて入院前のMさんに対し、どのように支援していこうと考えますか?
介護において大切とされる「本人の意思や要望、気持ちに応じる(尊重する)こと」のみでMさんの望むことを実現していけば、本人の満足度は高くなり、気分も良いことでしょう。そのため職員は、本人が望むことを実現できたという充実感や、優しさを発揮できる(できた)心地よさを感じられるかもしれません。
また、何を言っても人の言葉に耳を貸さず、言い出したら聞かないMさんのような方であったら、本人の望むことに応じていくのが無難な対応であり、介護者が嫌な思いをすることも少ないでしょう。
でも、それが本当に支援専門職の仕事だといえるのでしょうか。というのも、本人の意思や要望に応じるだけが仕事なら、そこに専門性は必要ありません。専門性が必要ないのであれば専門職は不要ということになります。
本人の意思や要望に応じることだけを仕事とするなら、お手伝いさん(と化した介護職)であればよく、そこに必要なのは優しさだけになります。優しい人であれば「誰でもいい」のです。
支援・介護を提供するうえで、本人の意思や希望、気持ちを確認することは大切です。しかし、その意思や希望を聞き入れるだけではなく、理解をしたうえで専門性(知識や経験値)をフル稼働し、このままだと「この人はどうなってしまうのか」を予測することが必要です。
そして、その予測に至らないように、「有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを支援する」という専門職の仕事(求められていること)を基にして、支援内容や支援量を考え、実践していくことが大切だと僕は考えます。ときには、その実践のためにご本人やご家族とぶつかり合わなければいけないこともあるでしょう。しかし、そこを調整していくことも僕たち専門職の仕事なのです。
誰もが「病気にはなりたくない」と思うのは当然です。「いつまでも自分のことが自分でできるようにありたい」とも思っています。そんな「人としての本位」も織り交ぜながら、支援内容を立てていくことも大切ではないでしょうか。
「本位」とは、「判断や行動をするときの基本となるもの」という意味を持っています。つまり、「利用者本位」とは、「利用者の言うことに何でも従うこと」ではないのです。