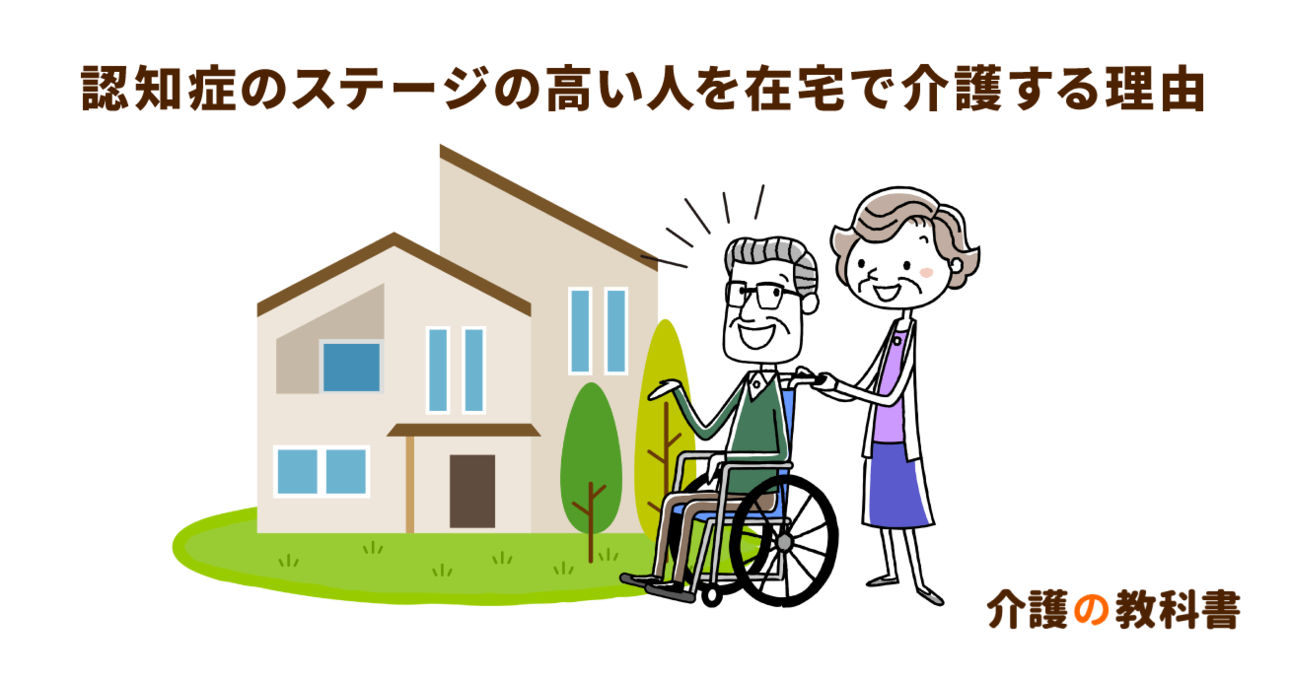皆さん、こんにちは。認知症支援事業所 笑幸 代表の魚谷幸司です。
私は本業とは別に、公益社団法人「認知症の人と家族の会大阪府支部」の世話人をしています。世話人としてはまだ数年ですが、会の集まりに参加して約10年が経ち、これまで多くのことを学んできました。そこで、今回はこの集まりに参加する中で学んだことを中心に書いていきます。
在宅介護での本当の苦労
まず知ったのは在宅介護をされている方の大変な苦労でした。参加した当初、私は施設に勤めていたのですが、ご家族が在宅介護においてさまざまな苦労をされていることを知りませんでした。
ケアマネージャーがいても介護保険など制度の内容についてよく知らない方がいる現状に対して、今でも疑問を抱いています。また、想像をはるかに超える、在宅介護の大変さを痛感したのです。
施設に勤めていた私は、介護に苦労している利用者と接すると、思わず「なぜこんな人が」と口にしてしまうこともありました。しかし、家族の会で在宅介護をしているご家族の話を聞いていると、何も言えなくなりました。
デイサービスを利用されている例を考えてみてください。施設の職員が対応するのは長くてもせいぜい8時間です。困ったらほかの職員に代わってもらうことができます。一方、残りの16時間は家族が、場合によっては1人で介護しているケースも少なくないのです。私は、職業として勤めている介護職員として簡単に「大変」という言葉を使ってはいけないと強く感じました。
感謝の言葉に隠されているご家族の真意
次に、今なお学んでいる「ご家族の本当の思い」についてです。施設で勤めていると、利用者さんのご家族から「ありがとうございます」という言葉をよくいただきます。しかし、その言葉の裏には、また別の思いがあることも忘れてはいけません。
ご家族からいただく「ありがとう」には、もちろんお礼としての意味があります。しかし、その言葉の裏にある真意を考えたことはあるでしょうか。家族の会に参加していると「介護職員の方に感謝はしているけど、本当はこうしてほしい」という話がよく出てきます。ご家族は、「お世話になっている」という気持ちが強いだけに、内心で思っていることをなかなか言い出せないのです。また、口に出して、今後の対応が悪くなっても困るというのが本音のようです。

ですから、介護職員の皆さんには「専門職だから正しい」という思い込みを捨ててほしいと願います。「今やっている対応は本当に正しいのか」という観点から、自らの介護サービスを振り返る謙虚な姿勢を持ち続けてほしいと思います。
同じ立場の人と苦労を共有する意義
最後は、吐き出すことの大切さです。介護をしていると、良いこともありますが、多くの方は苦労して悩んでいます。そうなったとき、絶対に1人で抱え込んではいけません。
1人で抱え込んでしまうと、考えや行動が悪い方向に向かってしまい、介護者と要介護者の双方にとって悪影響を及ぼします。そんなときは、家族の会のような同じ立場にある人が集まる「場」に参加してみてください。
そして、その場で自らが体験している苦労や大変さを話してみてはいかがでしょうか。はじめて参加される方が発言をするのは勇気のいることだと思います。しかし、はじめのうちは下を向き、暗い表情だった方が、上を向いて「少し楽になりました。また明日から頑張れる気がします」といった言葉を残して帰られるケースが多くあります。これは同じ境遇にある者だからこそ、わかり合えることがあるという強みなのです。
こうした悩みは緊急事態宣言下にあっても変わらず、常に介護者の前に横たわっています。介護をしている人は「話をしたい」「聞きたい」「仲間をつくりたい」と考えるものなのです。なぜなら、そうすることで大変な介護でも頑張る気持ちが生まれるからです。
私は、こうした場で話されるエピソードこそが認知症の現実であり、その現状を知るための良い教材であることも学びました。これは介護をしている家族だけでなく、専門職にも通じることだと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの人が密集してはいけないとされています。しかし、そんな状況でも介護している人たちのために「場」は開け続けています。介護者に寄り添い、学び、集まることの意義は確かなものです。感染対策はもちろん重要ではありますが、より良い介護生活のためにも、こうした「場」を継続することが必要だと私は思います。