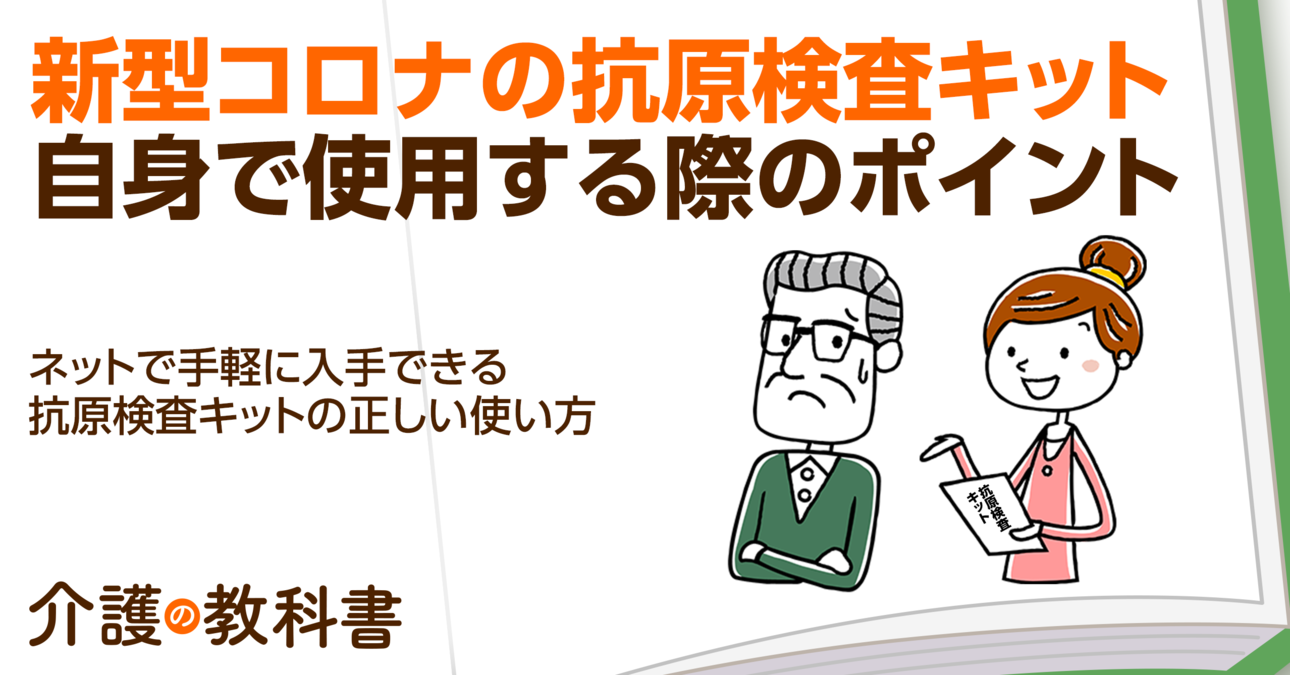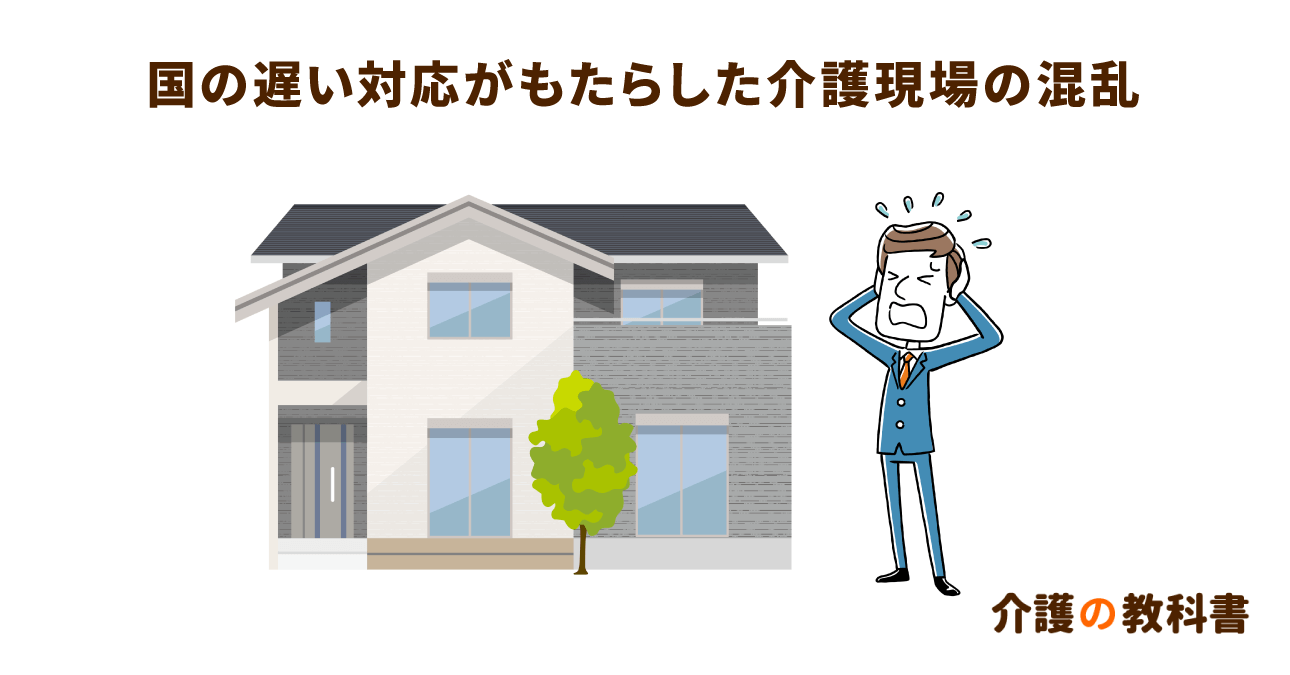特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。
介護施設で働く職員は、新型コロナの感染予防のための作業が増え、ほかにも「風評被害」というプレッシャーを抱えています。そのため、国は3月24日に『新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのサポートガイド等について』を発出し、介護施設等で働く職員のメンタルヘルス対策をとりまとめました。
今回は「新型コロナ対応で疲弊する介護職員の現場のメンタルヘルス対策」についてお話いたします。
感染対策にかかる職員への負担
介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないものです。緊急事態宣言下であっても休業等ができず、サービスの継続が求められます。そのため、介護現場で働く職員たちは、第174回、第177回の記事でも書かせていただいたように、日々感染予防策に力を尽くしています。
もちろん感染予防対策に追われている仕事は、何も介護だけではありません。しかし、サービスの継続性が求められている介護施設などでは、高齢かつ基礎疾患を抱え、集団生活を送っている利用者を支えています。
ひとたび施設にウイルスが持ち込まれると、クラスター(集団感染)や命に直結するリスクが高く、介護の現場は高い緊張感を1年以上保ち続けています。感染対策にまつわる業務でスタッフたちには身体的・精神的な負担が重くのしかかっているのです。
新型コロナの感染拡大が始まった1年前から、感染対策にまつわる以下の業務が加わりました。
【感染対策による負担】
- アルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる環境消毒業務
- 常時不織布マスクやフェイスシールドを着用することによる身体的負担(夏季など暑い時期にも着用をしなければならない)
- 職員や利用者のエリア分け(行動分離)による業務制限
- 感染が疑われる利用者への感染防護対応
- PCR受検者に対しての接触状況確認作業
- 面会制限に伴う調整(面会予約等管理業務)など
これら感染対策の業務負担に加え、「職員自身が感染する可能性」「職員自身が媒介となり利用者や同僚に感染を拡げる可能性」なども、職員がストレスを感じる要因として挙げられます。

実際に設けられている自宅待機基準
筆者が働く施設では、職員自身に体調不良があるとき、同居者に体調不良等があるときは、原則自宅待機するというルールを設けています。参考までに当施設での自宅待機基準の詳細を例示しましょう。
【自宅待機基準Ⅰ(一つでも該当した場合は自宅待機)】
- 37.5℃以上の発熱がある
- 前日までにはなかった風邪症状がある(咽頭痛、頭痛、倦怠感、咳、鼻水、味覚・嗅覚障害等)
- 発熱者と長時間接触した
- PCR検査を受検した
- 濃厚接触者に該当するもの(またはその可能性が高いもの)に該当
- 同居者に37.5℃以上の発熱または風邪症状がある
- 同居者がPCR検査を受検した
- 同居者の職場や学校で感染者が発生した
- 同居家族が濃厚接触者に該当するもの(またはその可能性の高いもの)に該当
【自宅待機基準Ⅱ(原則として複数該当したら自宅待機)】
- 検温の結果、平熱より高い
- 花粉症や喘息などの持病に基づく風邪症状が悪化している
- 発熱者と接触があった
以上の自宅待機基準を設定し職員に周知。自宅待機基準を明確化することで、「この状態で出勤してもいいのか不安」「判断に迷う」という職員の精神的ストレスを軽減できるように配慮しました。
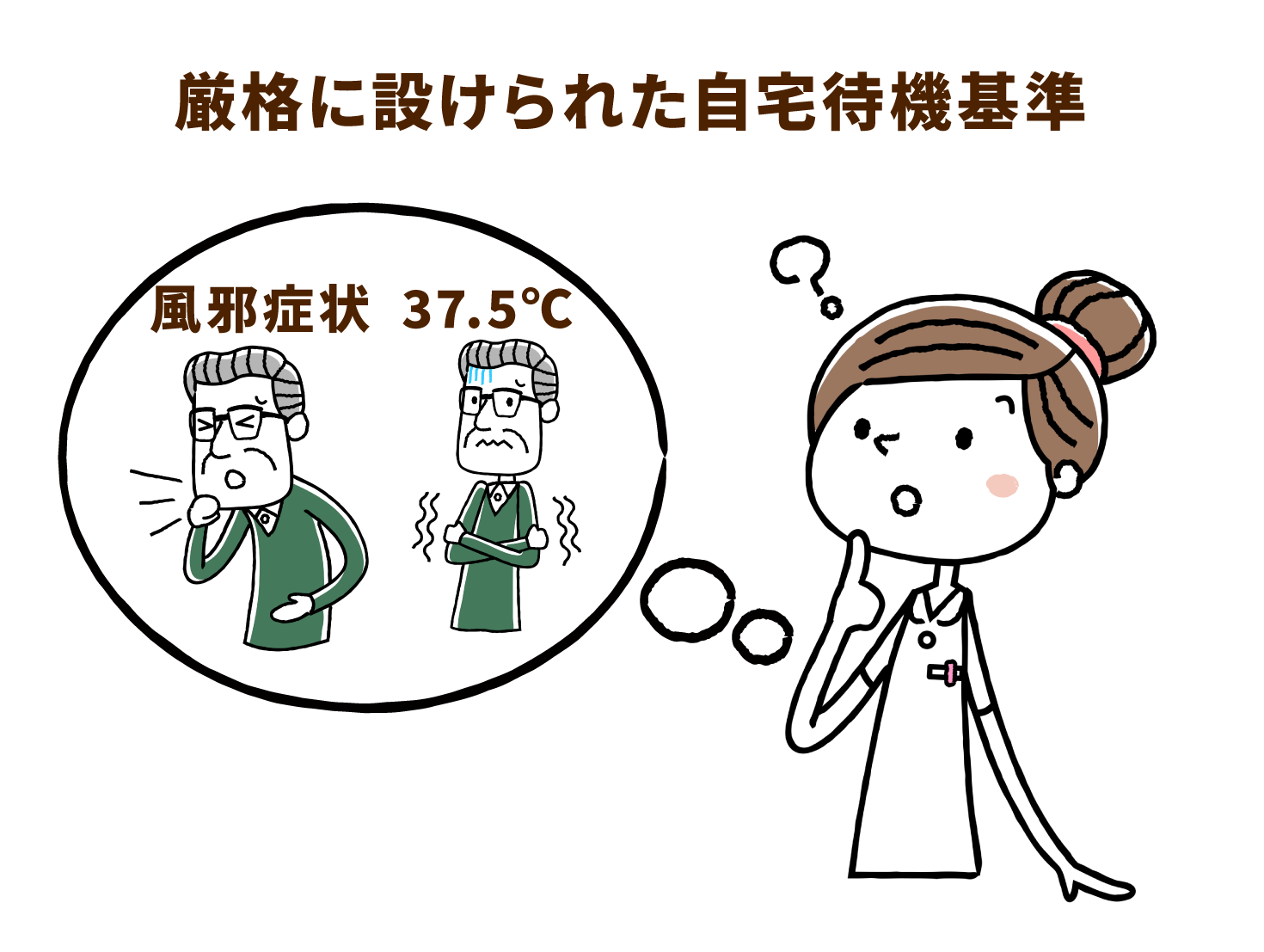
先述した自宅待機基準に該当した場合、部署長に報告し、自宅待機となります。仕事に復帰する場合は、原則医療機関を受診し、医師の判断のもとで出勤が可能になります。体調不良があった場合や体調不良者と接触した場合、自己判断に委ねるのではなく、仕組み化することで職員の迷いや不安などを軽減できると感じていました。
自宅待機している職員に1日1回の状況報告をしてもらっていますが、「自身が感染しているのではないか」「私がウイルスを持ち込んだらどうしよう」という不安があるそうです。
不安をぬぐう職員間のコミュニケーション
連日テレビや新聞、ネットニュース等では新型コロナに関する情報が流れています。不安を煽られるような内容や感染者に対する社会的な偏見・差別的な内容も目にします。職員も当然そのような情報に触れますから、不安を感じることも理解できます。
このような状況下で、職員の不安やストレスをゼロにすることは難しいかもしれません。しかし、体調報告の電話の際に職員の不安が少しでも緩和するよう、話を聞いて不安を受け止めることや情報に必要以上に振り回されないこと、元気になって仕事に戻ってきてくれることを待っていることなどを伝えるようにしています。
当たり前ですが、人は人とのつながりの中で、お互いに助け合って生きています。不安や緊張感を和らげるためにも些細なコミュニケーションが大切なのではないでしょうか。そして、自宅待機となっていた職員が職場に復帰してきたときは、リーダー職員が率先して声をかけることも大事なことだと思います。

2015年12月に「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回、ストレスチェックをすべての労働者に対して実施することが義務付けられました。
このストレスチェックなどを活用して、自分自身のストレス状態を客観的に観察することも肝心。高ストレス状態にあるなどと判定された方は、産業医と面談してアドバイスをもらうことも選択肢の一つです。
風評被害や誹謗中傷にさらされながらも意識高く働いている職員
感染リスクを考えて、旅行や会食、コンサート鑑賞といったプライベートの行動を自粛している職員の方も多くいます。そのように意識を高く持って介護施設で働いている職員が大勢いることを知っていただきたいのです。
そんな中、高齢者施設で感染者が発生したという情報があると、地域を含めて大きなうわさになったりすることがあります。人のうわさは止めることはできませんが、介護従事者や医療従事者を「避ける」「嫌がる」「遠ざける」「攻撃する」などの行為は控えてほしいと思います。
また、感染者が発生した施設が誹謗中傷されたという話も聞きました。どんなに感染対策を実施していても、リスクをゼロにはできません。感染対策に尽力をしている施設の現実、緊張感や不安を抱えながらの利用者の生活を懸命に支えている実情を知っていただければと思います。
今まで利用者に会いたいときに会いに来て、利用者と時間を共有していた家族も、新型コロナ感染拡大に伴う面会制限等によってストレスや不安などを感じているはずです。
私たち介護施設で働く職員に対して利用者の家族や関係者の方々は、温かい言葉で応援してくれています。そうした温かい視線を持っていただければと思います。