【特別寄稿】新型コロナウイルス感染症と介護施設
2020年4月20日現在、新型コロナウイルス感染症が世界的に感染拡大を続けています。
感染予防が進められる中で、「介護」の現場では、入居者・利用者の感染後の重篤化や集団感染のリスクを抱えながら、日々支援が行われています。
今回は「特別編」として、介護の最善線で起きている変化と現場の対応について、髙橋秀明さんに教えていただきました。
皆さんこんにちは。特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。
「新型コロナウイルス感染症」という見えない敵との戦いに、日々尽力している介護事業所関係者の皆さま、本当にお疲れ様です。
「不要不急の外出を控える」「3密(密集・密接・密閉)を防ぐ」「テレワーク」など、連日のように報道で感染症拡大防止への呼びかけが行われています。
しかし、私たちの生業である介護は、入居者に「密接」にかかわらなければ成り立たないため、国が推奨するテレワークへの移行は不可能です。
この状況の中で、介護事業所で働く職員の方は、かなりの緊張感を保ちながら毎日出勤していることでしょう。
今、僕にできることは、現場の最前線で実践している内容をご紹介して、全国で新型コロナウイルス感染対策に日々尽力している介護事業所の「仲間」と共有することだと考えました。
今回お伝えするのは、「正解」が見えない中で、日々情報収集・分析、企画・立案をして生み出した施設での介護現場目線の内容です。
現場は常に変化するため、明日には状況が変わっているかもしれませんが、ぜひ読んでいただけるとうれしいです。
「新型コロナ対策」で、入居者・家族のストレスが高まっている
僕が働く特別養護老人ホームでは、200人近い要介護状態の高齢者の方が暮らしを営んでいます。
施設の構造はユニット型ではなく、従来型の施設で、居室の大半が多床室です。
そして、多くの入居者は糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの基礎疾患を抱えています。
新型コロナウイルス感染症は、高齢者や基礎疾患を抱えている方が感染すると重篤化するといわれています。また、特別養護老人ホームでは集団生活を送っているため、感染拡大というリスクも抱えています。
そのため、日々国から発出される介護保険最新情報などを根拠に、感染症を「持ち込まない」「感染症を拡げない」ための対策が必要です。
しかし、感染症対策は、入居者の暮らしに少なからず影響を与えています。
今まで“当たり前だった日常”が制限されています。
【新型コロナ感染症対策による入居者への制限】
- 外出制限
- 家族・親族との面会制限
- 施設内でのボランティアなどによる催し中止
- 訪問歯科や訪問美容、訪問販売の中止
中でも「外出制限」「家族・親族との面会制限」は大きなストレスになっていると感じられます。
家族と会えず、コミュニケーションが取れないことは、入居者のみならず、家族にも影響を与えていることがわかりました。
「施設では感染症が流行っていませんか?」「うちの父(母)は元気ですか?」「面会に行けないので心配です…」など不安を抱えた家族から施設に電話がかかってくるようになりました。

ストレス・不安解消のための3つの取り組み
「オンライン」で面会を可能に
私たちは、「面会ができないことは感染症対策だからやむを得ない…」と感じつつも、「どうしたら家族の不安を解消できるか」試行錯誤を重ねました。
そこで生み出したのがオンライン面会です。
「オンライン面会」では直接面会はせず、スマホ画面越しに面会をしてもらいます。
では、オンライン面会の具体的方法について説明します。
オンライン面会の方法
- 施設所有のスマートフォンに「LINE」アプリをダウンロード
- 家族などに施設のQRコードを貼り付けた手紙を送付
- QRコードを読み取ってもらい、友達登録をしてもらう
- 「オンライン面会予約」をしてもらう
- オンライン面会予約時間に施設からLINEのビデオ通話をかけて、スマホ画面越しに面会(15分程度)
この方法であれば、設定も比較的容易。
何より、入居者も家族も顔が見えるだけで表情がとたんに明るくなります。
「不安」から「安心」に風向きが変わる光景を見ると、僕ら職員の胸に迫るものがありますし、「今が踏ん張りどきだ」「力を尽くして乗り越えよう」というモチベーションにもつながります。
耳が遠い入居者にも有効で、家族が画面越しに「元気か?」「こっちは元気だから心配いらないよ」など、筆談形式でコミュニケーションを図ることもできます。
オンライン面会はLINEだけではなく、ZOOMやスカイプなど方法もあります。
まだ取り組んでいない施設はぜひ実践してみてください。
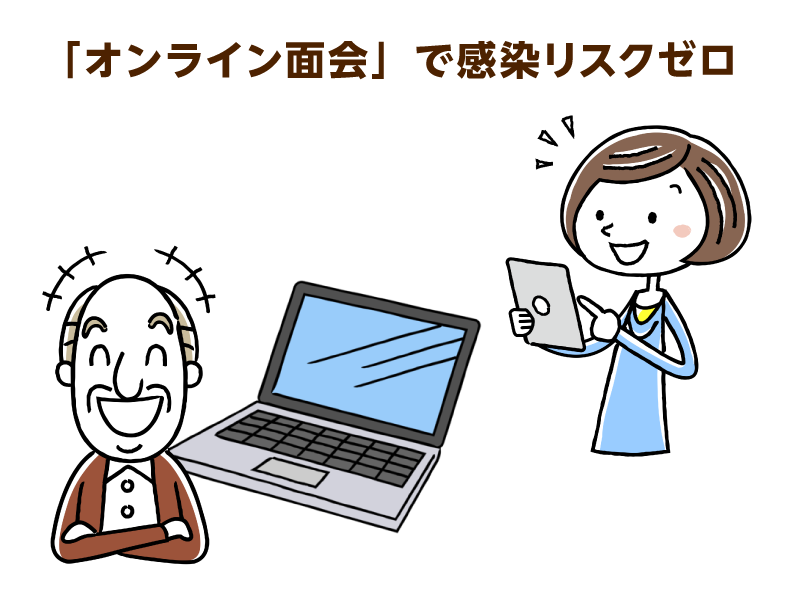
家族宛に手紙で様子を伝えて、不安を解消してもらう
また、僕は入居者一人ひとりの様子を書いた手紙をご家族に送りました。
手紙を見たご家族から「髙橋さんからの手紙を読んで、うちの父が元気でいることがわかって良かったよ」と言っていただけました。
こんなときだからこそ、生活相談員・介護支援専門員など相談援助職の方々は、家族の不安を少しでも解消できる手立てを考えることも必要だと考えます。
施設内で散歩や日光浴をすることで、緊張をほぐす
感染症対策の観点から、2月末より入居者が家族や職員と街に繰りだす機会がなくなりました。
そんな入居者のストレスを感じ取った介護職員から「入居者を散歩に連れ出し、外の空気を吸ってもらいたい」という声が。
「外出制限」という言葉を拡大解釈すると、入居者を一歩も外に出さないことと捉える方もいるかもしれません。
しかし、外出制限の本質は「大勢が集まる場所へ出かけるのを避ける」ことです。
施設の外を入居者が職員とともに散歩すること、陽の光を浴びることは問題ないでしょう。
この状況がいつまで続くかわからず、現場ではピリピリした空気が漂っていますが、冷静に目の前の入居者のことを考え、行動に移せる職員はすごいと感じました。
そんな些細なひとときが、入居者そして職員の緊張を解きほぐす時間になるのではと考えます。
感染予防や感染拡大をための4つの取り組み
次に、「感染を予防する」「感染を拡げない」具体的取り組みについてご紹介します。
職員の健康状態に応じて、出勤を制限する基準を設ける
僕の施設では、職員の健康状態をA~Cの3つの項目を設定します。
その項目のうち、「△」が1つ以上ある場合は自己判断せず、上司に相談し指示をもらい、上司の指示があるまで自宅待機となります。
多くの介護事業所はシフト制で交代勤務となっています。
入居者の生活の質を担保するために、職員は多少の体調不良があっても、「ほか職員に迷惑を掛けたくない」という思いから出勤してしまうケースも少なくありません。
しかし、その誠実さと熱意により、感染症が持ち込まれる可能性も考えられます。
そのため、施設を運営する法人が、基準を設けて職員に発信し、職員が順守・徹底する必要があります。
また出勤時には、全職員が健康チェックシートに検温結果と自己問診結果を記入する仕組みにしています。
このほか施設には業者など、外部の方が施設へ立ち入ることもありますが、職員と同様に検温・自己問診結果を記録しています。万が一、発熱や風邪症状などがある場合は、入館を断る必要もあるでしょう。
ショートステイ利用者には、同居家族や利用者の検温を数日前から行ってもらい、当日も送迎職員が利用者の検温や風邪症状の有無を問診して問題がなければ利用をしてもらうよう徹底しています。
席の間引きや職員出入口の分割などによる、「3密」を防ぐ
食堂や休憩室では密集・密接する環境が生まれやすい場所です。
施設では、食堂席の間引きをして対面や隣に密接しない環境にしました。
また、ロビーなどを開放し、食事・休憩場所を確保しています。
さらに、職員出入口の分割や更衣室を新たに設置するなど、可能な限り職員が密集しない環境に改善しています。

施設内消毒の強化
新型コロナウイルス感染症は飛沫感染だけではなく、接触感染によって感染が拡大しているといわれています。
施設の中でいえば、タイムレコーダー、コピー機、共有パソコン・タブレット、テーブル、椅子のひじ掛けや背もたれ、ドアノブ、手すり、自動販売機、トイレなど、多くの人が触れる場所がたくさんあります。
次亜塩素酸ナトリウム0.05%(水500mlに対して、衣料用漂白剤5ml)希釈液で1日4回消毒清掃を実施しています。
僕の施設では、次亜塩素酸ナトリウムの取り扱いについては注意点がありますので、取り扱いについては必ず事前に確認しましょう。
今までにも増して消毒清掃に力を入れていますが、消毒清掃業務が増えるということは、職員の入居者への支援時間が剥ぎ取られるということにもつながります。
そのため、業務の優先順位を決めて取り組むなど創意工夫が求められます。
施設をユニット化して、職員を専属に変更
大勢の入居者が生活を営む施設では、一度新型コロナウイルス感染症が発生すると、たちまち集団感染に発展するリスクがあります。
特に、ユニット型ではなく「従来型」といわれる施設で働く皆さんは、緊張感とストレスを抱えながら仕事をされていることでしょう。
僕の働く施設も従来型の施設ですが、予防・拡大防止の取り組みとして、一定箇所を間仕切りして「空間分離」を実施しています。
わかりやすくいえば、従来型施設をユニット化するということです。
可能な限り、ユニットごとに職員も専属で対応をする方法を試みています。
この方法が確実に効果があるとは言えないかもしれませんが、毎日頭を悩ませながら試行錯誤を続けているのが現実です。
入居者の自立した生活を支えるには、臨機応変に対応することが重要
今回ご紹介した内容は実施している取り組みのごく一部ですが、現場で働いている全国の仲間に少しでも参考になればと考えます。
ほかの介護事業所では、新型コロナウイルス感染症が発生し対応に追われていたり、地域で新型コロナ感染症が発生したために、事業所を休業・自粛したり、規模を縮小して営業をしている事業所もあります。
早く事態が収束し、上記のような状況にある事業所には「日常」を取り戻してほしいと願って止みません。
そして同時に考えることは、現場の最前線で奮闘する職員のこと、入居者のこれからのことです。
現場では、高い緊張感を保ち続けながら支援をしている職員、感染症予防のために不自由さや違和感を抱えながら暮らす入居者がいます。
日々支援をする専門職の仲間たちは、この有事に立ち向かいながら、支援の本質である入居者の「尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援」しています。
上司に「考える、考え続ける、考え抜く」「実行に移す」「取り組みながら修正し改善する」ことが大事だと言葉をかけられました。
見通しが見えない中で、状況も日々変化をします。
これは支援にも言えることですが、一度決めた取り組みをいつまでも続けるのではなく、状況の変化をしっかりと見極めながら、臨機応変に対応を判断することが私たちには求められています。
このような場を通じて全国の皆さんと情報共有をしたり、知恵を出し合いながら、この状況を乗り越えていきたい!と僕は思います。





















