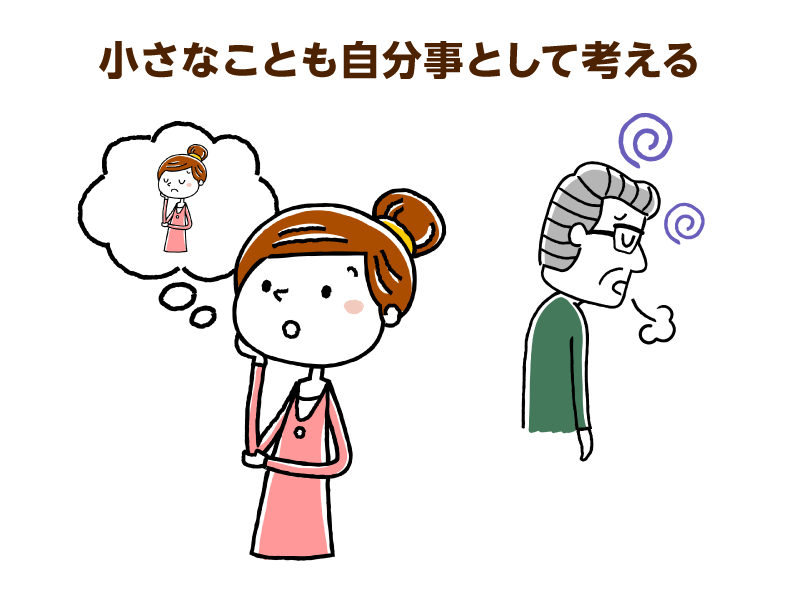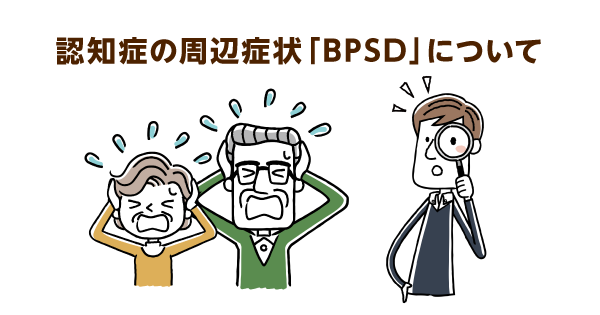こんにちは。デイサービスで看護師として勤務している、認知症LOVEレンジャーの友井川愛です。
今回は、「認知症ケアで大切な倫理観」についてお話します。
介護職員に求められる公平な立場と倫理観
私は常々、認知症ケアとは「人間学」だと考えながら認知症の方と接しております。
なぜそう考えるのかというと、これまでたくさんの認知症の方と出会い、接するたびに多くの学びを得てきたからです。
認知症ケアをするにあたって忘れてはいけないと思っているのは「すべて見抜かれている」ということ。
認知症の方はそうでない方に比べると感受性が高く、言葉ではうまく伝えられない場合でも行動ではっきりと示します。
もちろん、その行動の本当の意味を介護者が理解しなければならないので力量が試されますが、認知症の方は自分が不快に感じたことを覚えていらっしゃいますし、その場その場の付け焼刃的な言葉ではぐらかそうとすればそのことを見抜かれます。
このことにきちんと気づけなければ、勘違いケアをしてしまうことになるのです。
私はこれまでさまざまな医療や介護の現場でケアをしてきましたが、どの現場でも聞かれる言葉があります。
介護者、病院の看護師、施設の職員からよく聞かれる「○○してあげる」「○○しちゃだめ」などの言葉です。 もし自分が同じような言葉を使われたら、皆さんはどう思いますか?私なら子ども扱いされたとか、馬鹿にされたと不愉快に思います。
認知症がどういうものなのか正しい知識がない方は、認知症の症状がどれも同じと思っていたり、専門職の言葉や態度が症状を進行させていることに気づかないのです。
皆さんは現場で自分の業務を優先にしていませんか?
私たち、専門職は自分の利益ではなく利用者の利益を優先に考えなければなりませんし、介護の現場で一番、不利益を受けているのは認知症の方です。
認知症の方は社会的に弱者と言われる立場にいます。そんな方々の弱みに付け込むことができ、自分の思うようにできる怖い立場に専門職はあります。
こうしたことに理解や意識をせずにいると、いつのまにか介護する者が上の立場になったような勘違いを生むことになります。
専門職としての倫理観が重要なポイントになってきます。

倫理的な2つのポイント
- 認知症の方はやさしい方が多く、そのやさしさに付け込むような自分本位なケアをしない
- 認知症の方の弱さに付け込まない、不利益になるようなことをしない
病識がある認知症の方も多い
認知症の方は常に、「不安」「混乱」「焦燥感」を抱えています。
昔は認知症の方は呆けているから病識がなく、何もわからないと考えられていましたが、現在では病識がある場合の方もいらっしゃいますので、病識があるという考えが広まっています。
病識とは、病的な状態にある方が、「病気である」ことを自覚していることをいいます。
私は、混乱期まっただなかの認知症の方と幾度となく接し「私、なんでこうなっちゃったの?」「頭がおかしくなったの」「すぐに忘れるんだ」などとご自分の変化に戸惑い混乱されている姿を見てきました。
認知症の症状に自分が最初に気づかれる方も多くいらっしゃいます。
また、症状が進行していく過程で不安が強くなり一定の場所に落ち着く事ができず、そわそわすることがよく見られますが、こうした際も専門職の些細な発言がさらに不安や焦燥感を増大することもあります。
認知症の方は漠然とした不安を抱えていますので、そんな方に「どこに行くの」「ここに座っていて」「まだ帰れませんよ」などと言ったとしても伝わりません。
逆に不安がさらに高まり、不安を解消できないので混乱が始まります。
そんななかで「まだ、帰れません」などと言われてしまったら「もう、ここから逃げ出せない」と感じて恐怖心や猜疑心が生まれる場合も考えられます。

自分に置き換えて考えることで不安を解消できる
医療・介護の世界で仕事をするようになってからいつも思うのは、この世界の常識は世の中の非常識であるということです。
はじめてこの仕事についたときには、皆さん違和感を何かしら感じていたはずです。
しかし、仕事に慣れ業務に追われ始めると違和感を感じなくなり、当たり前になってしまいます。
認知症の方は常に違和感を感じており、その違和感を理解してもらえないと、不安がBPSDとして出てきます。
専門職は小さいことでも「自分だったならどう思うのか?どう感じるのか?」という視点で考えることが大事であり「こんな風に言われたらどう思うのだろう」「この言い方で正しいのか?嫌な思いをしないだろうか?」と問いかけ、その答えが正しいなら良いですよね。

認知症ケアには倫理観が重要
今回、最初の冒頭で私は言いましたが、認知症ケアとは人間学です。
認知症ケアを行う専門職には人間力、倫理観が必要とされますし、だからこそ座学だけの知識だけではケアができません。
以前と比べると認知症ケアは進化していますし、認知症の方に対しての理解も進んできてはいますが、それでもいまだに認知症の方に対して「面倒な人」というレッテルを貼っていたり、虐待が行われている残念な現実もあります。
こうした現状を改善するためにも、正しい認知症の知識を得て倫理観を育てる啓蒙活動も重要になってきますね。