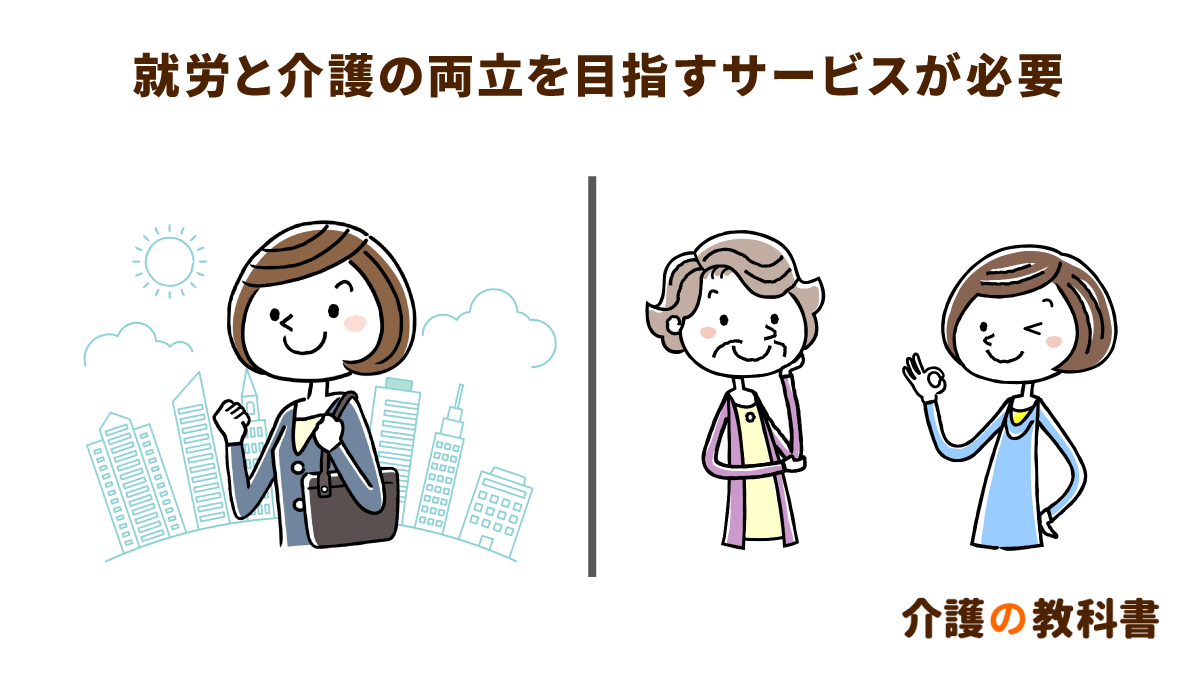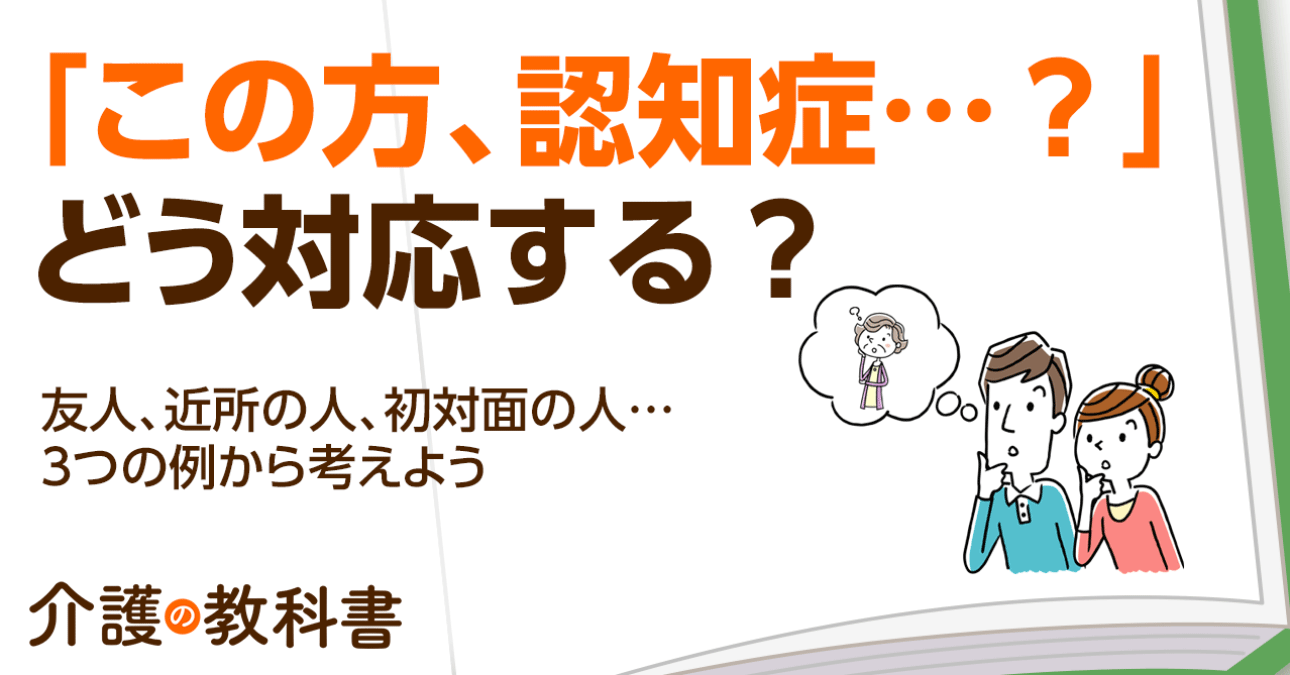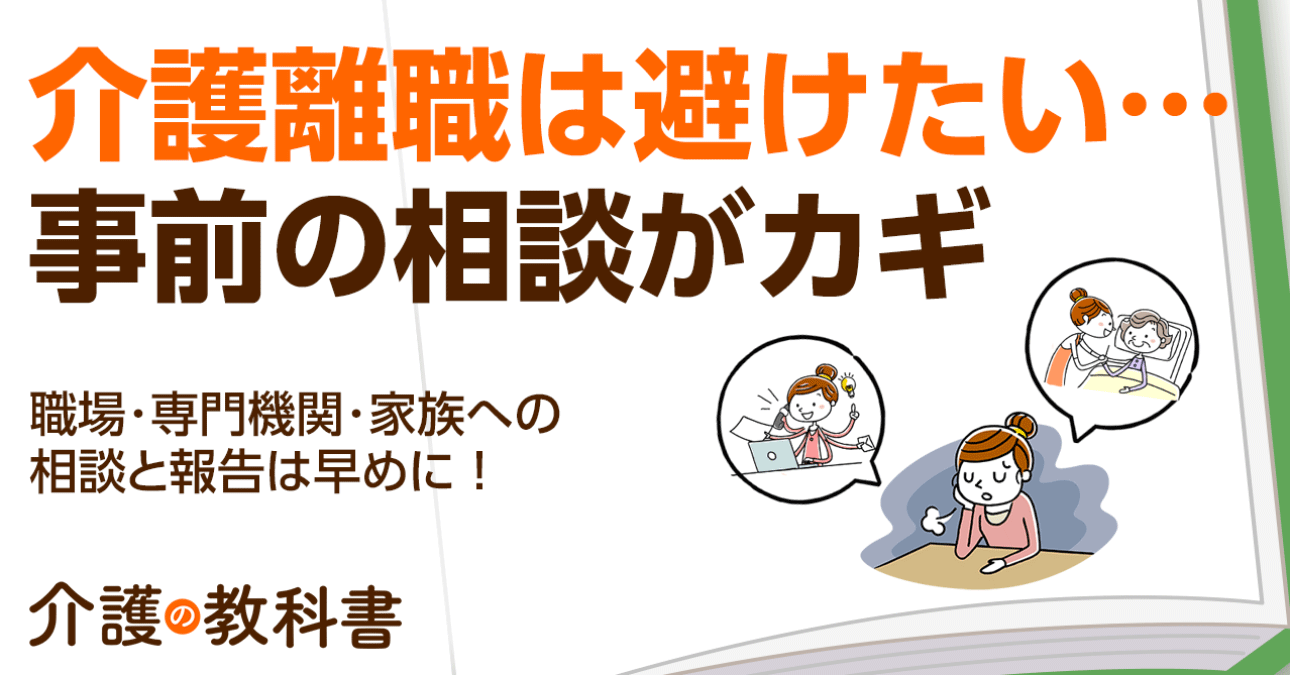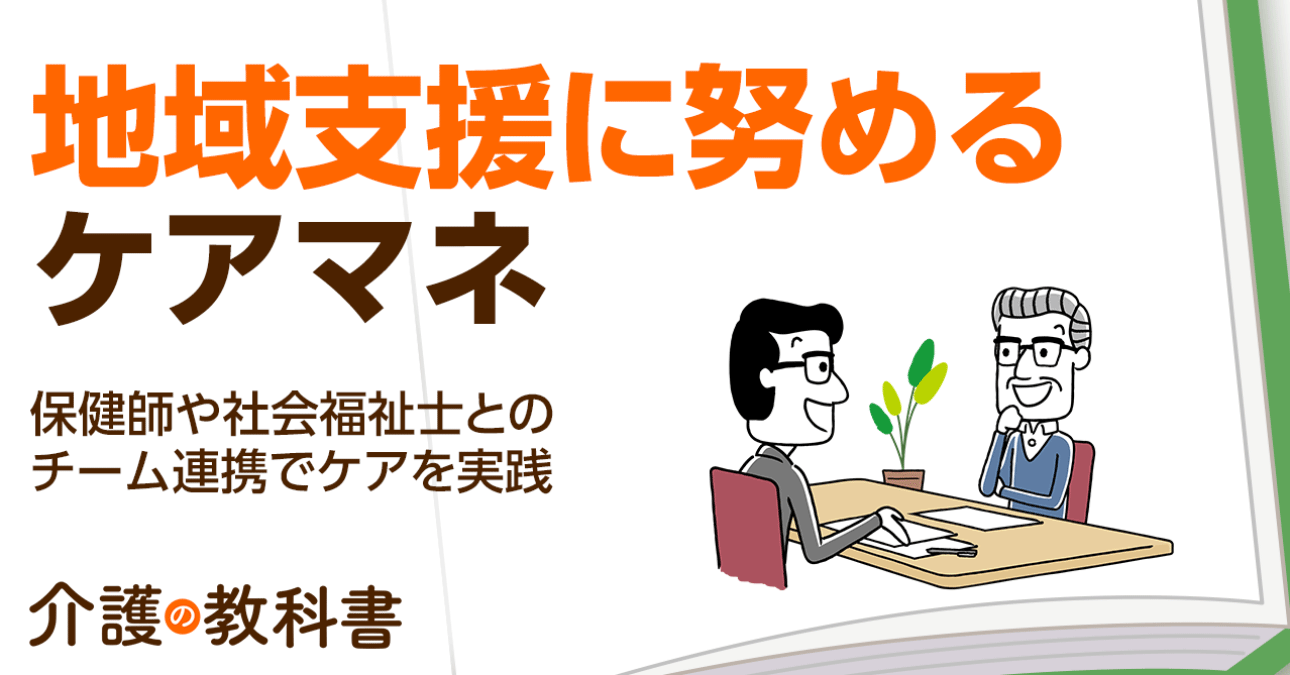介護と仕事の両立が求められる理由
日本の人口は少子高齢化に伴い、今後どの職場でも慢性的に働き手不足が発生する可能性があります。
2018年に発表した総務省の『平成 29 年就業構造基本調査結果』によると、全国に家族や近親者の介護をしている方は約628万人。そのうち、6割近くの約346万人が働きながら介護を行っています。
さらに、過去1年間に「介護・看護のため」離職した人は約9.9万人。実に10万人近い人が介護を理由とした離職を選択しているのです。
介護サービスは、介護が必要な人に向けたものであり、介護者が心身の疲労やストレスを溜めることがないよう支援してくれる公的なサービスではありません。
無償で介護を行う介護者が、仕事を続けながら健康で文化的な生活を営めるような支援が、今後迎える高齢化社会の課題となっています。
一般企業では業務効率を上げるため、さまざまな施策を講じ、ICTの活用などが行われています。介護福祉業務においても同様であり、業務効率化やスリム化を果たすべく見直しが行われています。
介護保険が施行されて約20年が経過し、排泄介助や入浴介助などは専門職が行うことで、実務としての介護負担の軽減が図られました。しかし、日常的に同居して介護する家族にとって、劇的に軽減したとはいえないでしょう。
そのほか、医療・介護サービスの利用開始や変更時における同意や契約が、ご家族の負担になっているとも感じています。
介護保険の申請とサービスの利用を例にしてみましょう。
- 介護保険の申請
- 書類の申請代行は、地域包括支援センターやケアマネジャーが行えますが、原則的には本人や家族に記載してもらう必要があります。本人や家族が記載できないような事情があれば相談は可能です。
- 介護保険の調査や主治医意見書の依頼
- 介護保険を利用する際は、調査員から調査を受けることと、主治医からの意見書が必要となります。
継続のケースであればケアマネジャーなどが代行で依頼することも可能ですが、新規の場合は調査時の家族(その方の生活状況がわかる方)の同席が必要です。また、主治医意見書は本人かご家族から主治医に依頼してもらう必要があります。 - サービスの調整
- 介護認定がでると、介護保険のサービス調整を行います。その際に本人・家族へ自立支援、重度化防止の観点を踏まえ、受けたいサービスについての聞き取りを行います。そのうえでケアマネジャーはサービスを調整します。
- サービスの契約
- サービスの調整が済むと契約になりますが、この契約は利用される方と事業所での契約になります。
その説明と契約における手続きは本人と家族が行います。この契約は事業所ごとになりますので、利用するサービス事業所の数だけ契約を行うことになります。なお、ケアマネジャーとも契約が必要です。 - 緊急時の対応も必要
-
サービスを利用中に急変や体調不良などが発生し、病院への受診が必要となった場合も家族対応が必要です。介護保険事業所での対応は、原則的にサービス利用中となっているためです。
ただ、体調不良時や急変時の対応については契約の際に取り決めをされている事業所が多くあるように見受けられます。また、緊急時に入院や治療のため手術が必要な場合は、家族に入院申込書や手術への同意書など記載いただく書類は多岐にわたります。
このように、介護サービスを利用時は家族対応が必要な場面が多くあります。介護保険事業所のなかには、お互いの負担軽減のために、電子契約や郵送でのやり取りによって簡素化し、家族負担を少なくしている例もあります。

とはいえ、常々介護を必要とする場合にお休みを取ったり、本人の体調不良時に急遽お休みを取ったりするなど、就労中の方にとっては非常にハードルが高いと感じられると思います。
地域包括支援センターやケアマネジャーの現状
地域包括支援センターやケアマネジャーは、介護サービスを利用する本人だけではなく、介護をする家族も支援することを念頭に置いています。
介護が始まると、その介護力についても確認して生活上の負担を検討します。本人が年金を月額いくら支給されているか、家族が就労しているかどうか、介護に対してどれぐらいの金銭的負担を担えるかなどです。
その際、家族が就労しないと療養生活を維持できないとなれば、家族が就労しながら介護できるように支援を行います。
例えば、以下のような項目をチェックします。
- 介護休暇や介護休業を利用できるのか
- 時短勤務など会社との交渉は可能か
- 親族からどれぐらいの直接的支援(排泄や食事などの日常的な介護や受診・施設利用時の契約代行)や金銭的支援を受けられるのか
- 地域で手伝ってもらえる友人や知り合いやいるか
- 上記を加味したうえでの実際に介護を担える部分はどれぐらいか(量・時間など)
介護はいつまで続くのか先行きが見えづらいため、家族が疲弊しないように支援を行うことが求められています。
とはいえ、地域包括支援センターやケアマネジャーは介護保険でのサービスがメインですので、介護休暇や介護休業の取得、会社との交渉は完全に専門外です。
私自身が以前対応したケースでも、「就業規則を社外の人に閲覧することが原則できません」と言われ、口頭で内容確認を行ったこともありました。
また、家族の中には所属する会社に対して介護休暇や介護休業・時短勤務など言い出しにくい方や、自営業の方などは仕事も介護も一日の中で区分けできないとお話された方もいました。
これから少子高齢化がますます進む中で、就労しながら介護される方への支援方法はまだ熟成されていないかもしれません。
今後ニーズが高まる産業ケアマネジャー
そこで、現在注目されている新たな資格が産業ケアマネジャーです。産業ケアマネジャーの最大の目的は、年間10万人にのぼる介護での離職を防ぐことです。
介護は、産休育児休暇とは異なり、突然始まりいつ終わるのかもわかりません。それは本人だけでなく、企業側にも大きなリスクになっています。
そのため、介護のために離職するか、仕事を続けるか迷ったとき、社内に介護の専門家がいることはとても心強いことでしょう。
今後ニーズが間違いなく上がっていく資格だと感じていますが、まだまだ認知度も低く、資格を取得した人も多くはありません。

これからの日本は少子高齢化がますます進み、医療や介護福祉の担い手も減少します。その中で、家族の支援は切り離すことが難しい状況になるでしょう。
仕事を辞めることなく、介護ができるかを地域包括支援センターやケアマネジャーは一緒に考えることができます。
もし身近な方の介護が突然必要となった際は、本人の状況や今後についてお話していただくのはもちろんですが、介護をする家族もどのようにこれからの人生を考えていくことが大切です。