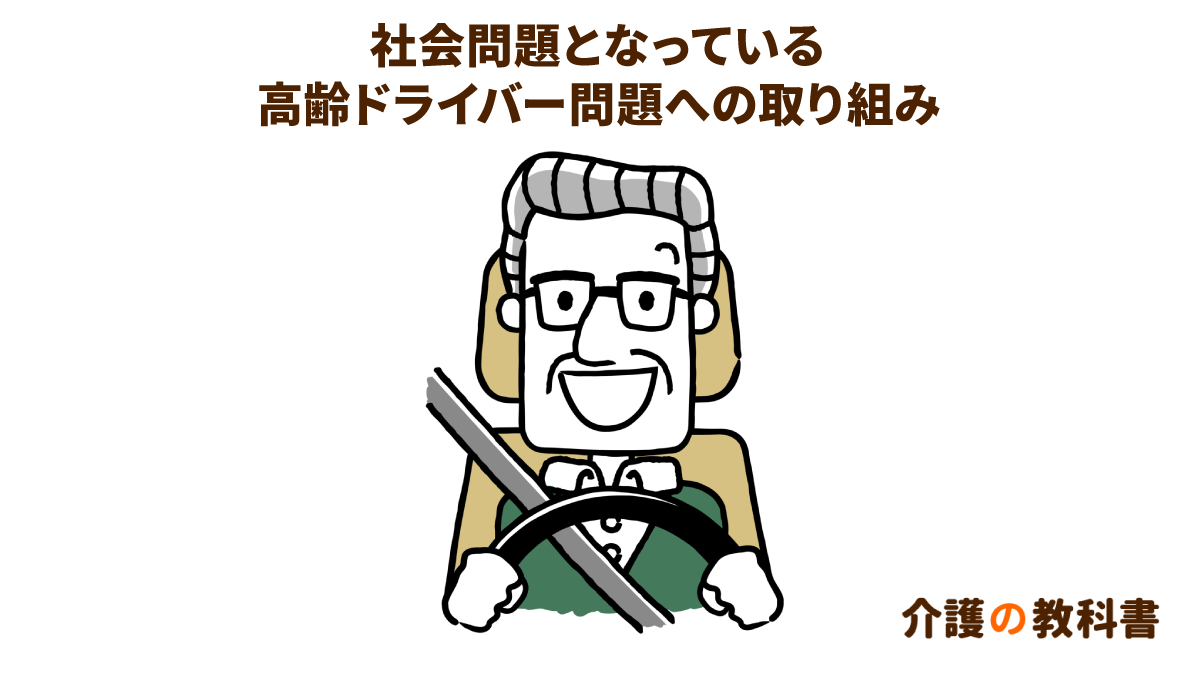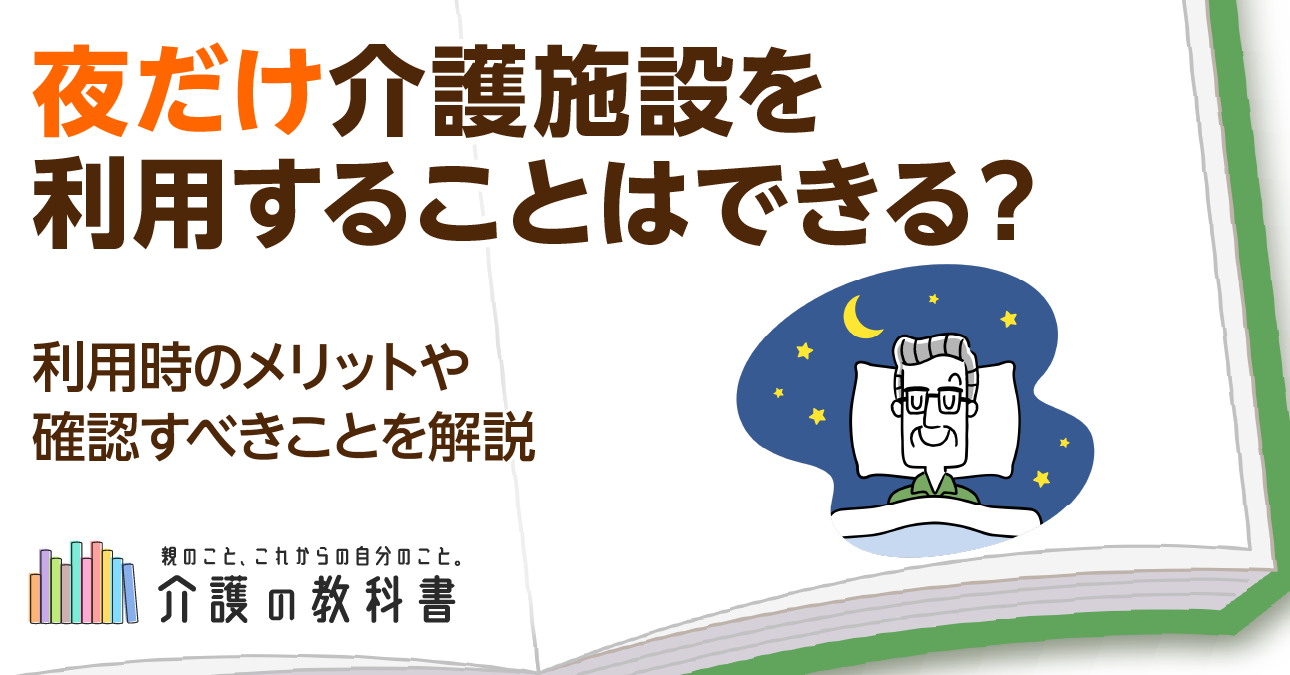医療と介護の連携支援センター長谷川です。
今回は、問題視されている高齢者の交通問題について解説し、町田市で取り組んでいる交通についてもご紹介します。
高齢者の免許更新が改定される
道交法改定のポイント
まず最初に高齢者の運転免許に関する問題を考えてみましょう。75歳以上の方が免許を更新される際、現行制度では認知機能検査を行うことになっています。
本人の判断力や記憶力の状態を判断するために以下の簡易検査を行います。
- 時間の見当識:検査時の年月日、曜日及び時間を回答する
- 手がかり再生:16種類の絵を記憶し、何が描かれていたかを回答する
- 時計描画:時計の文字盤に、指定された時刻を表す針を描く
この検査が終了した後、その点数に応じて3つの段階に認定され、次のような処置を受けます。
- 1.記憶力・判断力が低くなっている(認知症のおそれがある)
- 医師の診断を受けることが義務付けられ、その結果によって運転可能という診断結果が出れば、個別指導を加えた3時間の高齢者講習を受けて更新できます。
- 2.記憶力・判断力が少し低くなっている(認知機能の低下のおそれがある)
- 医師の診断が不要で、3時間の高齢者講習を受けるだけで更新できます。
- 3.記憶力・判断力に心配がない(認知機能の低下のおそれがない)
- 2時間の講習を受けることで更新できます。
この現行制度が2022年5月(令和2年改正道路交通法)から、さらに厳格化される予定です。
75歳以上で、過去3年間に一定の違反歴がない場合、新しい認知機能検査を受けます。
その結果による分類では、これまでの3つではなく、「認知症のおそれなし」と「認知症のおそれあり」のいずれかになります。
今回の改正で最も注目されるのは、75歳以上の方で誕生日の160日前までの過去3年間に「一定の違反歴(違反行為)」がある場合、実車を使った運転技能検査(運転技術)が義務付けられた点です。
この「一定の違反歴(違反行為)」には、以下が当てはまります。
- 信号無視
- 通行区分違反
- 速度超過
- 横断歩行者妨害
- 安全運転義務違反等複数
こうした改定が行われる背景には、統計データによる裏付けがあります。
普通免許を所持している75歳以上のドライバーの中で、過去3年間に何らかの違反歴がある人の重大事故率は約1.8倍。また、違反内容が重大事故であった場合、事故率は2.1倍になることがわかっています。
実際に、対象となる高齢ドライバーは警察庁によると、2022年に212万5,000人に上ると予測されており、そのうち、過去3年間に「一定違反歴(違反行為)」がある人は7.2%の15万3, 000人に達するとされています。
改定の背景にあるのは認知症の人の増加
高齢者の運転免許が厳格化される背景には、認知症者の増加が挙げられます。
日本における65歳以上の認知症の人は、2020年時点で約600万人ですが、2025年には約700万人にまで増え、高齢者の約5人に1人にまで達すると見込まれています。
おのずと運転免許を取得されている高齢者の中にも、認知症の人が増加していくと考えられ、認知症の一歩手前の状態とされる軽度認知障害(MCI)の方も多く存在することになります。
一方で、社会事情に合わせた制度の改定は必要だと思いますが、高齢者の免許の返納は、また別問題として考える必要があると思います。
確かに認知機能に問題があり、運転能力が低下している高齢者については、更新できないなどの措置は必要でしょう。それは高齢ドライバーによる事故が、重大な事態を招く可能性が高いことからも明らかです。
しかし、高齢者になったというだけで、一律に免許返納を迫るのはその人の権利を侵害することにもなりかねないとも考えています。
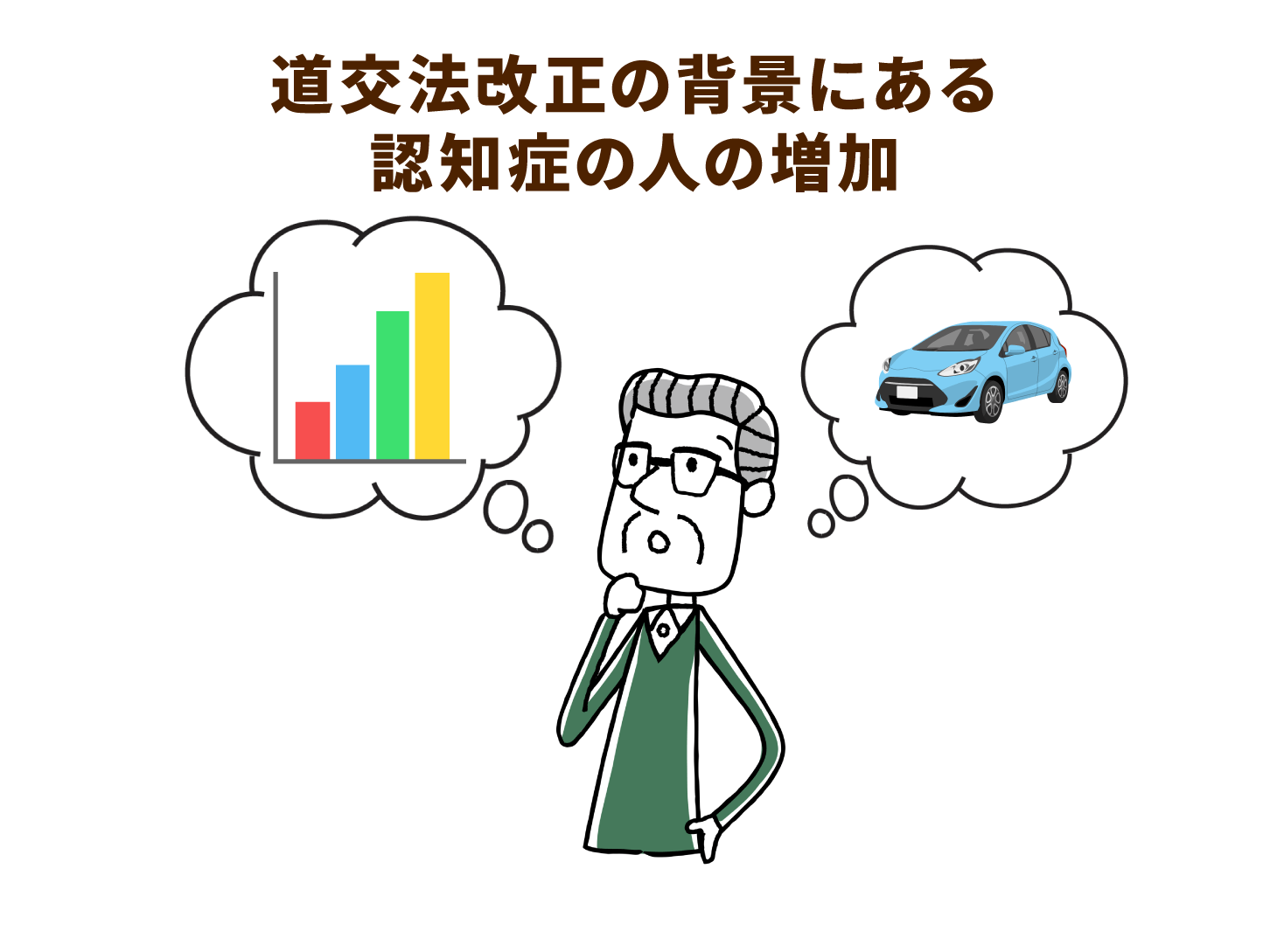
地域包括支援センターに寄せられた相談事例
地域包括支援センターでも運転免許に関する相談が寄せられることがあります。
【運転の荒さに近隣住民からクレームがあったケース】
私が相談を受けたことがあるケースでは、近隣の方から「Aさんの運転が荒く困っている」というものでした。
詳細を確認したところ、住宅街の中でもスピードを出したり、自宅の駐車場への出し入れの際に塀やポールにぶつけていたりしているとのことでした。
そのため、いつか大きな事故を起こすのではないかと周囲が心配になっていたのです。その当時は直接関わりがなかったのですが、相談をきっかけに自宅へお伺いしました。
訪問したときには、玄関横に車が止められており、バンパーの部分は前も後ろもへこみや傷があり、車体にも擦ったような傷が見られました。
Aさんの話を聞いていくうちに地域特有の問題がわかってきました。その地域は坂の中腹にあり、近くにスーパーやクリニック・銀行や郵便局といった生活に必要な施設がありませんでした。
そのため、用事を済ませるためにはその都度車を利用する必要があったのです。車の傷についても「人に迷惑をかけてはいない」と話していました。
近隣の方はAさんが車を手放すか免許返納を望んでいましたが、免許返納はあくまで自己判断によるものであり、市役所や警察でもその権限がないことを説明しました。
Aさんにとって、車は自身の生活を支えるために必要なものであり、長年乗ってきた愛車でもありました。
いくら周囲が危険だと思っていても、取り上げる権利は誰にもありません。
また、Aさんは更新まで期間もあり、更新時の検査なども当面受ける予定はありませんでした。
とはいえ、車や自宅の損傷を見る限り、運転能力に支障をきたしている可能性を感じざるを得ませんでした。
警察に相談し、Aさんと地域包括支援センターと警察の三者で話をする場を設定しました。
警察にも実際に車を見てもらい、現状について共有を図りました。警察から、免許の返納ではなく、車を手放してみて不便がなければ返納も考えてみてはどうかと提案したところ、Aさんは「車がないと買い物や通院が不自由になる」と主張しました。
そこで地域包括支援センターでは、地域の交通インフラを紹介するとともに、買い物についての支援策について説明しました。
Aさんが普段利用しているスーパーでは一定金額以上の買い物で自宅への配送サービスがありました。また、生協の宅配や配食弁当、地域で行っている巡回型の移送サービスについても紹介しました。
こうして少しずつサービスを活用することに慣れてもらった結果、Aさんは最終的に車を手放すことを選びました。
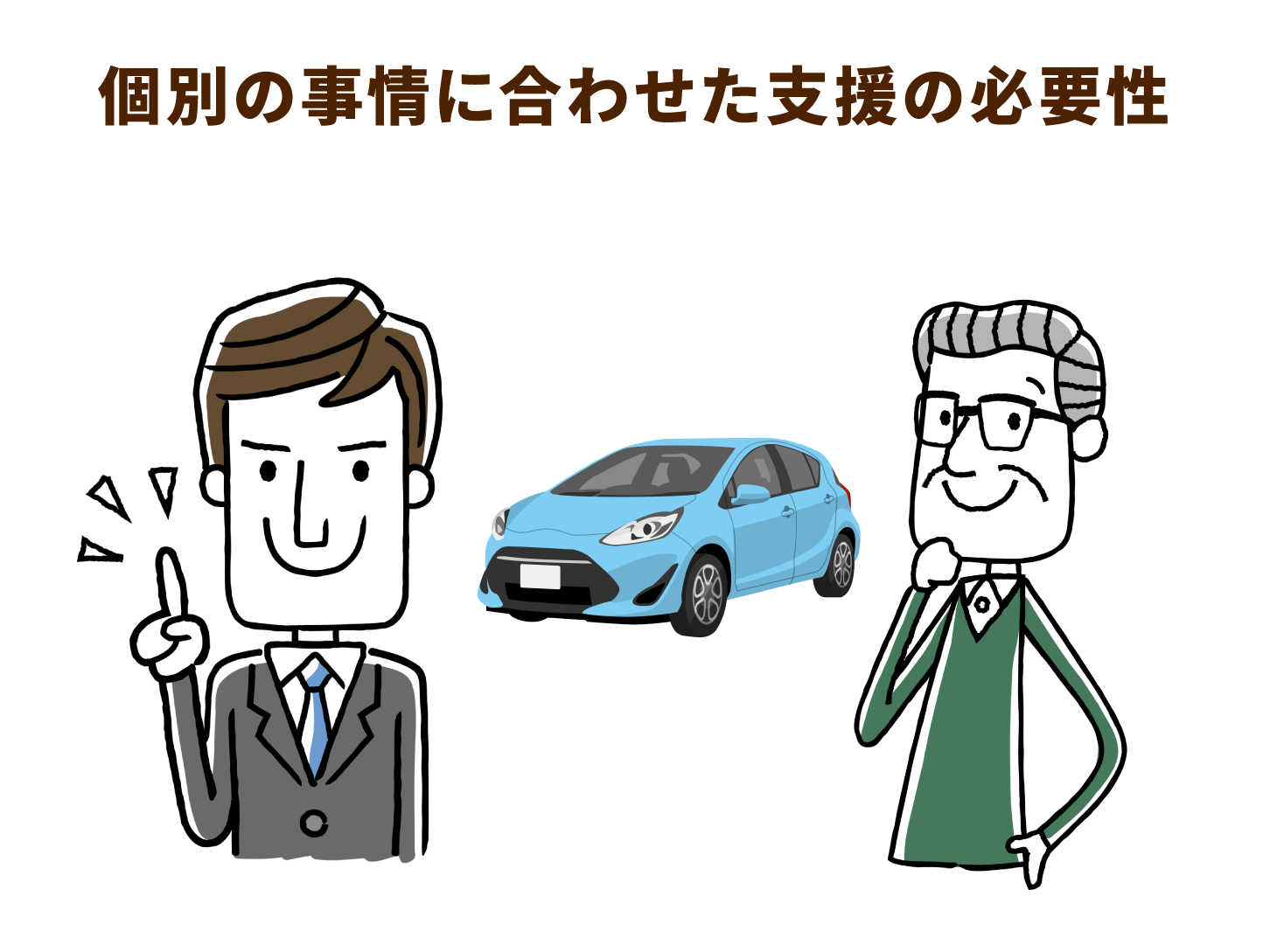
試験的に開始された交通弱者に対するサービス
バスや電車などといった交通手段の少ない地域において、自家用車が貴重な移動手段になっているケースもあるでしょう。
この場合、生活を車以外の手段で支えることができれば、糸口が見い出せるように思います。
まずは住んでいる各地域で、どのような公共交通や移動サービスがあるかなど、地域包括支援センターや社会福祉協議会・行政などに相談することが大切です。
私が勤める町田市は人口42万人の都市です。町田市内をJR横浜線と小田急線が通っていますが、利便性の高い地域は駅周辺に偏っています。
駅から離れた地域においては坂や狭い道など交通網が非常に脆弱です。その中で課題となったのが、移動手段がないために買い物や通院などに行けない高齢者でした。
私が経験したAさんのようなケースが市内で散見されていたのです。そこで、町田市では、第51回でも紹介したように、次のような支援を行っています。
- 地域住民と高齢者支援センター、高齢者施設や障がい者施設と行政が取り組んでいる「くらちゃん号プロジェクト」を実施。
- 団地に住んでいる方を中心に、買い物や外出に困っている高齢者に、電動カートを利用して団地内の各店舗までの送迎するサービスを実施。
こうした事業は、地域の社会福祉法人と団地の「地域支えあい連絡会」や企業、行政、国土交通省などからのサポートを受けています。
その後、市内の団地を中心に小田急電鉄とJR東日本の連携による「シームレスに移動できる社会の実現」に向けた少人数・定員制のオンデマンド交通サービス「E-バス」の実証運行を試験的に行っています。また、団地内にあった診療所の閉鎖に伴い、病院と団地を結ぶバスの運行が試験的に開始された地域もあります。
車の使用もそうですが、交通や移動は生活に密接にかかわっています。高齢者だからといって、一方的に免許の返納などを周囲から強要するのではなく、本人の想いをしっかり聞いて、それに代わるサービスを提供できる状況かどうかを判断する必要があるかと思います。また、地域のみんなで支えていく視点を共有できればいいとも感じています。