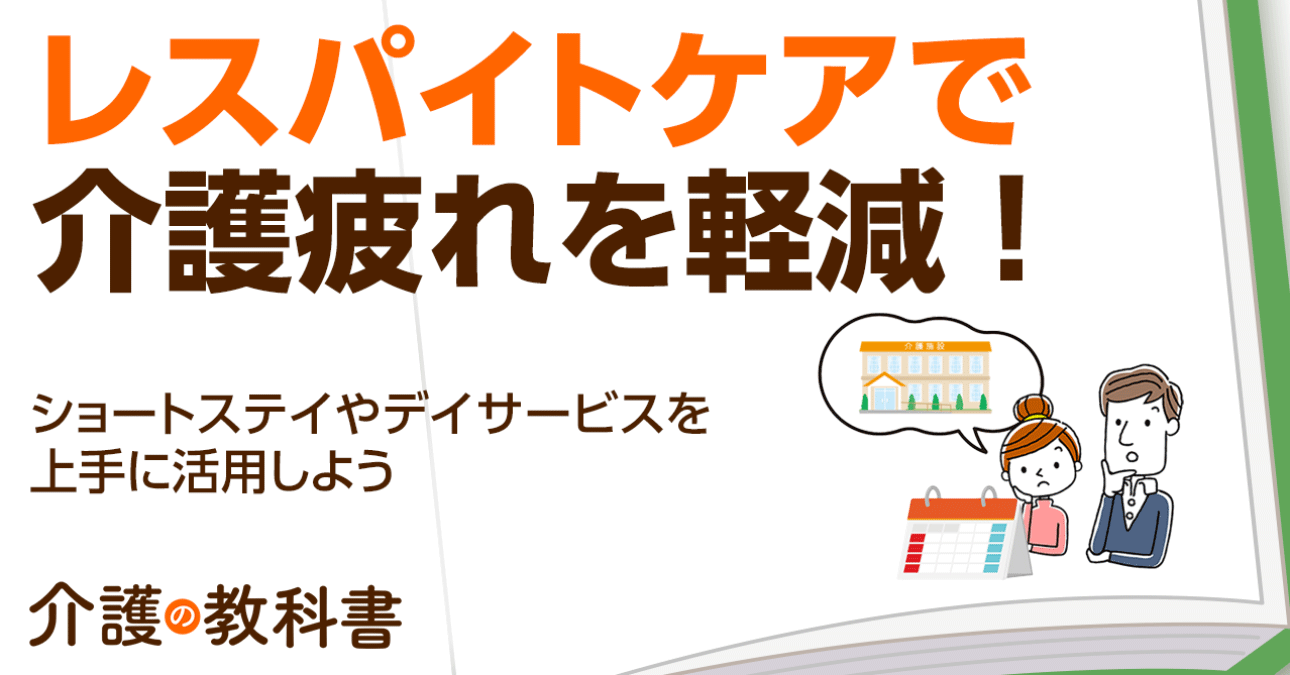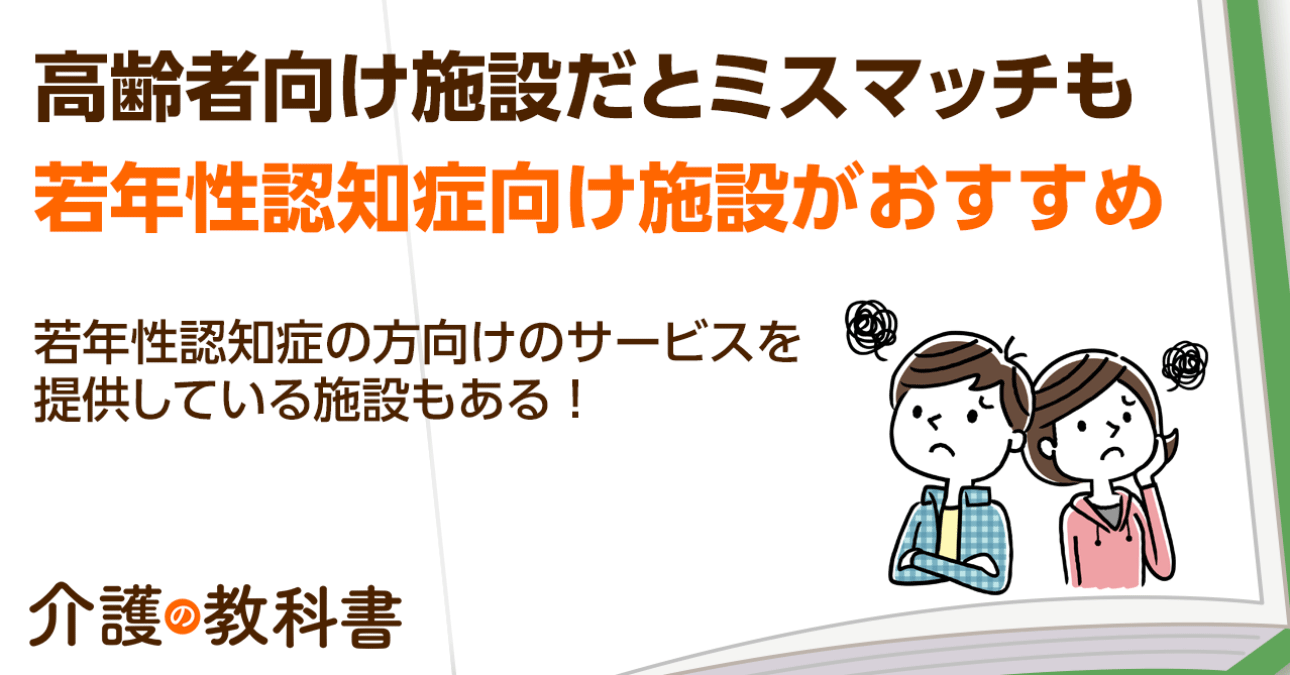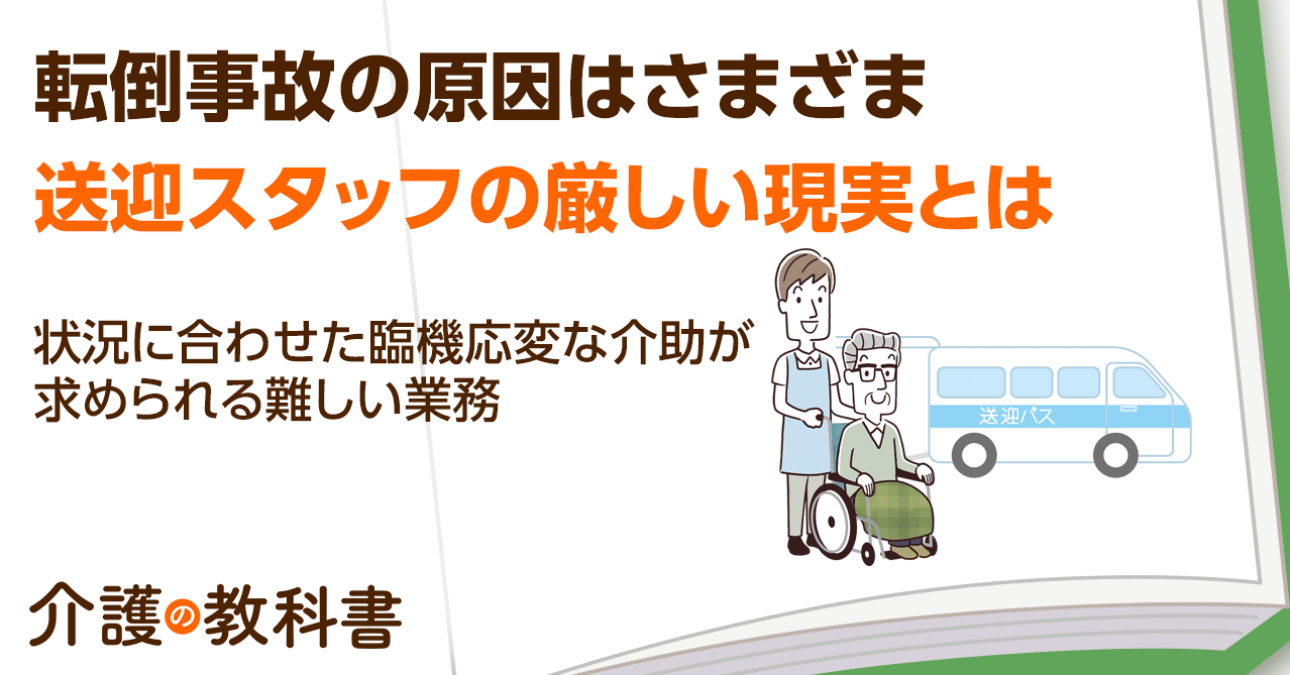医療と介護の連携支援センター長谷川です。
今回は「介護する人が病気や怪我などのドラブルにあってしまい、介護する人が居なくなってしまった」といった事態に陥った際の対処法についてお話します。
緊急時に介護保険サービスを利用する条件
ご家族が急な病気や怪我などによって介護ができなくなってしまった場合は、介護されている人が「宿泊を伴う介護保険サービス」を利用しているかが、重要なポイントです。
例えば、以下のようなサービスです。
- 短期入所生活介護(介護保険での利用可能)
- 短期入所療養介護(介護保険での利用可能)
- デイサービスに付随するお泊りデイ(介護保険外での自費サービス)
これらサービス事業所の利用実績があれば、緊急時にも利用することが可能です。
しかし、サービスとつながりがなかったり、施設に空きがなかったりする場合は、時間と手間を要することがあります。
なぜなら、介護保険制度では新たなサービスを利用する際、事前にサービス担当者会議を行う必要があります。その後、利用者に対してサービスの必要性を検討します。
緊急性がある場合について、短期入所生活介護・短期入所療養介護は、次の条件をクリアすれば、緊急での利用が認められています。
- 担当しているケアマネージャーが立てた「居宅サービス計画」に該当しない緊急的な受け入れであること
- 担当しているケアマネージャーが緊急の必要性や利用を認めていること
- 緊急の利用者における「利用する理由、期間、受け入れ後の対応」の記録を行うこと
- 緊急の利用を希望している方の受け入れが困難な場合は、別の事業所を紹介するなど適切な対応を取れること
- 受け入れ後の適切な介護の方策について、担当しているケアマネージャーと密接な連携を行い、相談を行うこと
お泊りデイについては、通所デイサービスに付随する制度なのでデイサービスを利用する具体的な検討が必要とされています。お泊りの部分だけを受け入れることは困難です。
このように急な病気や怪我などの理由でも、緊急時の受け入れの際、介護保険の利用が難しいケースもあります。
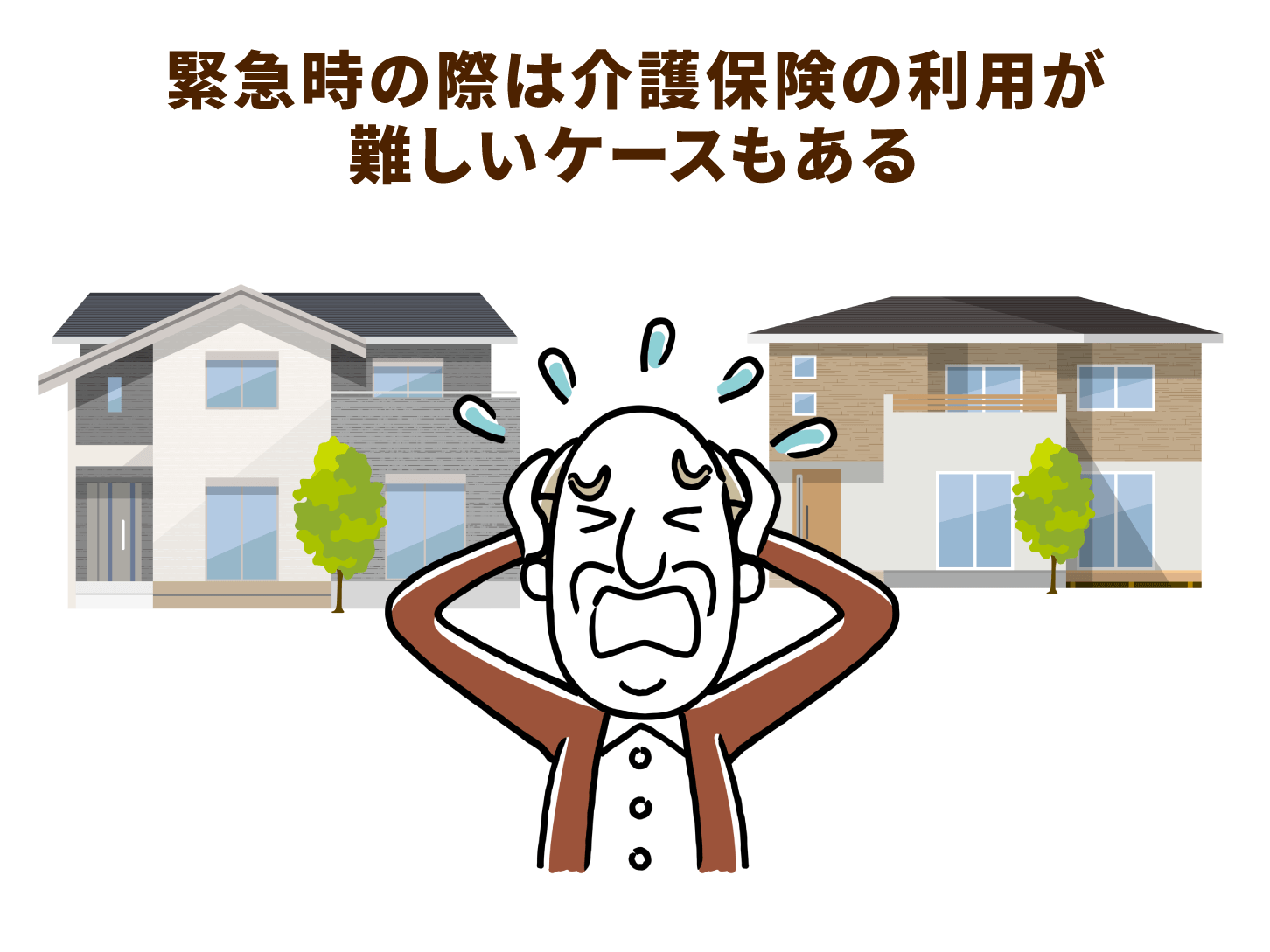
地域包括ケア病棟を活用する
認知症グループホームや小規模多機能型居宅・看護小規模多機能型居宅においても、定員を下回る場合の緊急時の受け入れは可能です。しかし、専門職の中でも制度としてはまだまだ理解が進んでいない面があり、在宅介護者には活用されていない現状があります。
そこで活用したいのは、介護保険ではなく医療保険における地域包括ケア病棟や病床です。
一般の病院にはさまざまな基準があり、病院ではベットの数を○○床といいますが、厳密にはベットの種別は詳細に分かれています。主な区分としては、以下の3つがあります。
- 急性期病床
- 急速に病状が悪化する時期の患者を治療する病床
- 回復期病床
- 容態が安定したり、リハビリが必要な患者を治療する病床
- 慢性期病床
- 病状が比較的安定し、再発予防や体力回復を図るための病床
例えば、100床の病院があったとしましょう。そのすべてが急性期病床の病院もあれば、100床のうち急性期病床50床、回復期病床30床、慢性期病床20床などに振り分けられている病院もあります。
その中で、2014年に新設された地域包括ケア病棟は、「在宅医療を支えるための入院」として、利用者の家族を支援するレスパイト入院の受け入れという大きな特徴があります。
レスパイト入院とは在宅介護を担う家族が、日々の介護に疲れを感じ、限界を超えてしまうことなどを予防するための入院を指します。家族の急病や怪我だけでなく、介護者の休息、旅行、冠婚葬祭などの事情により、一時的に介護が困難となった場合も利用できるようになっています。

また、介護保険ではなく医療保険の対応となることから、利用前の担当者会議などが不要です。
このように急な病気や怪我などの場合は、介護保険だけではなく医療保険での対応も可能となるので、緊急時には心強い味方になると思います。
ただ、この場合も病院の空き状況に左右されるので、利用できない場合もあります。近隣の地域包括ケア病棟や病床がどこにあるかなど事前に確認しておくと良いでしょう。自分や家族がかかっている病院に、地域包括ケア病棟や病床があるかもしれません。
ほかにもケアマネージャーや地域包括支援センター、行政の窓口などに相談してみてください。
日頃から「もしものとき」を想定して準備しておく
病気や怪我の具合が悪く、その後も継続的な治療や入院が必要になった場合について紹介します。
在宅介護をされている人の中には、いわゆる老々介護(高齢の方が高齢の方を介護する状況)などのケースも考えられます。
老々介護の場合、介護をされている方も通院や入院のリスクが高くなります。そうなる前に、担当のケアマネージャーに相談をしておいたほうが良いでしょう。
また、介護している人が休めるように、普段から介護保険の宿泊サービスなどを利用しておくことをおすすめします。要介護者の方も、何も知らない場所より、通い慣れている場所の方が安心しやすいのではないでしょうか。
介護保険では、家族が介護で疲弊しないよう積極的に宿泊サービスを活用しながら、在宅での生活をより充実したものにできるよう支援を行っています。
先述した地域包括ケア病棟も、レスパイト目的であれば(最大60日※ほか条件あり)入院での利用も可能となります。
レスパイト入院は、事前予約が可能ですので、各事業所や病院へ問い合わせしておいた方が良いかと思います。
介護保険の短期入所であれば、概ね2ヵ月前から予約を開始するところもあるので、定期的に家族の負担軽減のために利用できます。
このように「何かあったら、いざというとき、もしものとき」ということを想定して、日頃から介護保険サービスを利用することが大切です。
ケアマネージャーは介護を受ける方だけではなく、介護をされる家族も含めて支援をしています。しかし、介護される方の健康状態までチェックすることはなかなかできません。
そこで、在宅で介護をしているという方は、何か健康上の気がかりができた段階でケアマネージャーに報告してください。ケアマネージャー自身も、そのような事態に向けて備えておくことは非常に有意義です。
さらに、緊急のトラブルに備えて、要介護者を任せられる人を決められるのであれば、ケアマネージャーも対応がしやすくなります。子どもや親族など、万が一に備えて誰に任せられるかを事前に決めておくと良いでしょう。
病気や怪我で介護ができなくなる事態は、なかなか想定できないかもしれませんが、事前に備えがないと緊急時に選択肢が狭まるうえに判断を急かされることになります。この記事を参考に、そういった「もしも」を事前に考えておいていただければと思います。