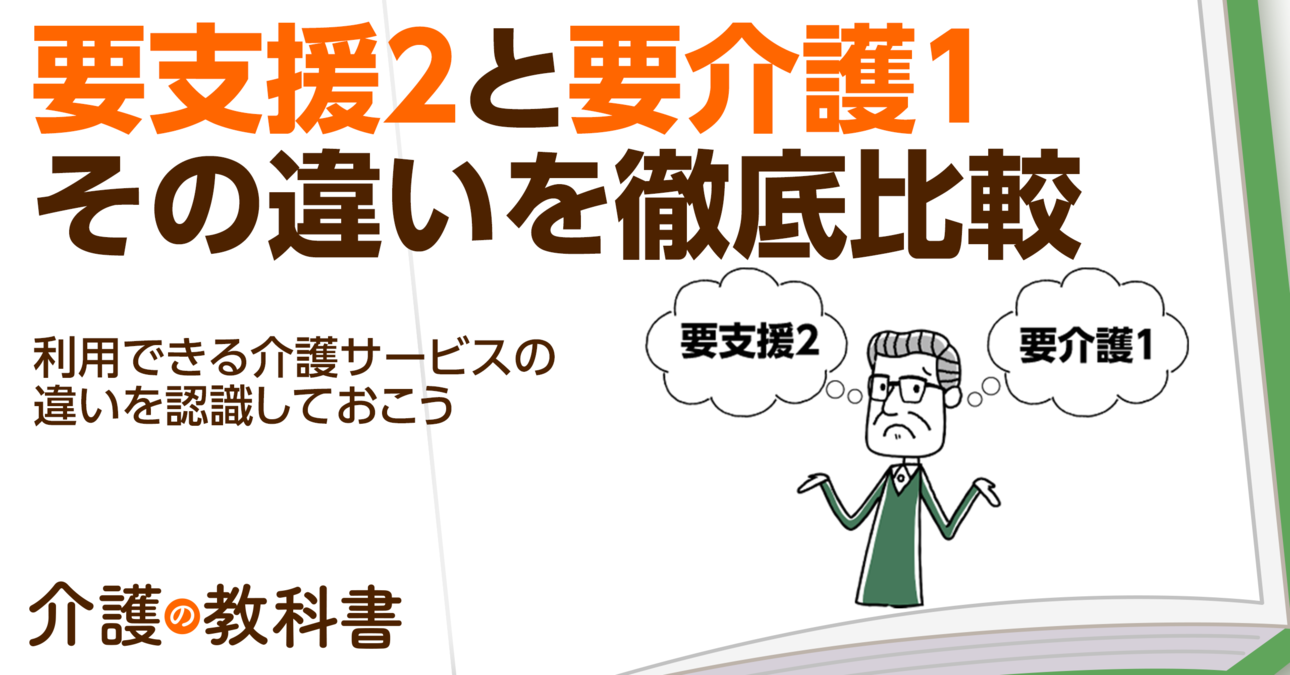医療と介護の連携支援センター長谷川です。今回は要支援の方が受けられるサービスについてお話させていただきます。
2000年に介護保険が施行されて、早20年。制度として定着してきた一方で、要支援という言葉を聞き慣れない方もいるかもしれません。
要介護度は7つの区分に分けられています。要支援1・2、要介護1~5です。本来の区分の意味合いは、介護の手間を図るものです。その方の心身の状態を表すものではありませんが、「要支援1」が区分の中では一番軽度で、要介護5が一番重度の状態と考えていただいて構いません。
区分の中でも一番介護の手間がかからず、心身の状態も軽度の判定となる要支援1で、どんなサービスが利用できるかをご説明いたします。
認定申請の主な流れ
介護認定を受ける際には以下のような困りごとがあるため、認定申請を行います。
- 足腰の衰えを感じて、主治医に相談したところ介護保険の利用を勧められた
- 散歩中に段差につまずき、転倒してしまった。杖などを借りて安全に散歩したい
- 家の片付けや買い物を一人で行うことが難しくなってきた
- 家で入浴するのが困難になっている
介護保険制度では、介護サービスを利用する本人またはご家族が申請を行います。その結果、非該当・要支援1・2、要介護1~5となります。非該当になっても、その方のお困りごとの解決に至らない場合は、各市町村独自の取り組みやお住まいの支援センターでの支援を受けられます。簡単に申請から認定までの流れをご紹介します。
要介護・要支援認定の流れ(町田市の場合)
- 要介護・要支援認定申請にあたり「介護保険認定申請書」を町田市に提出。後日、受理通知と資格者証(提出した介護保険被保険者証の代わりになるもの)が届きます
- 心身の状態を確認するため、次のような調査を行います。まずは「認定調査」です。町田市の認定調査員または町田市から委託を受けた認定調査員から調査日時の連絡があります。その後、認定調査員が被保険者本人やご家族にお会いして、聞き取り調査を行います。さらに、介護保険認定申請書の「主治医」欄に記載された主治医に、町田市から直接「主治医意見書」の作成を依頼します。なお、医療機関から被保険者の受診を求められる場合がありますので、あらかじめ受診が必要か主治医に確認をします
- 要介護度は、「認定調査結果」と「主治医意見書」をもとに、保健・医療・福祉の専門家が集まる「介護認定審査会」の判定で決まります
- 町田市から被保険者本人の住所に「認定結果通知」が郵送されます。認定結果通知が届いたら、要支援1・2、要介護1~5に認定された方は、介護保険のサービスを利用できます

要支援1の認定を受けた後の流れ
要支援の認定を受け、介護保険サービスを利用するには、住んでいる圏域の包括支援センターと契約を行う必要があります。包括支援センターは、地域にお住まいの方の介護予防サービスを担当しています。例えば「散歩中に段差につまずき、転倒してしまった。杖などを借りて安全に散歩したい」というお困りごとを解決してみましょう。
介護保険では福祉用具のレンタルや購入することが可能です。その方の心身の状況に合わせて、福祉用具貸与サービスに定められた物品から選択することになります。まずは、その方がなぜ転倒してしまったかを検討します。そのうえで「杖の使用が適当なのかどうか」「その杖を使用することにより、ご自身で自立した生活(散歩)を行えるようになるか」を検討します。また、杖を使用するだけでなく、筋力の衰えなど何かしらの要因があれば、それを分析しながら訪問リハビリや通所サービスでの機能訓練などを検討して、その方のプランを検討します。
要支援の方でも、その方の困りごとの解決や自立支援に資するサービスには支援センターと相談のうえ、下記サービスの導入が可能です。
- 訪問介護
- ホームヘルパーがご自宅に訪問して、食事などの介護や日常的なお世話をします。
- 訪問入浴介護
- 浴槽を積んだ入浴車でご自宅に訪問して、入浴の介助やお手伝いをします。
- 訪問看護
- 看護師などがご自宅に訪問して介護予防を目的として、療養上の世話や助言を行います。
- 訪問リハビリテーション
- リハビリの専門職がご自宅に訪問して、ご利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
- 居宅療養管理指導(医師・歯科医師・薬剤師など)
- 介護予防を目的とした療養上の管理・指導を行います。
- 通所介護
- 食事や入浴などのサービスや体操・筋力トレーニングなどを日帰りで行い、生活機能を向上させます。
- 通所リハビリテーション
- 食事や入浴などの日常生活上の支援や、リハビリ専門職などがリハビリテーションを行います。
- ショートステイ
- 食事・入浴などの介護サービスや、生活機能維持向上訓練を宿泊しながら行います。
- 福祉用具
- 心身の機能低下により日常生活に支障がある方に向けて、福祉用具のレンタルや購入の補助を行います。
- 住宅改修
- 住んでいる方が日常生活動作(ADL)が自分で行えるようになり、本人の自立意欲の向上につながるよう自宅内の改修を行います。
これ以外のサービスも利用可能ですが、この10種類が一般的かと思います。要支援でもこのサービスを利用できますが、介護と違う点もあります。例えば、通所介護では、要介護であれば複数の通所介護を利用することが可能ですが、要支援の場合は1ヵ所しか利用が認められなかったり、回数に制限が発生したりします。
要介護→月・水・金は〇〇デイサービス。火・木は△△デイサービスといったように、給付限度額内であれば複数事業所や回数に制限はありません。
要支援Ⅰ→月は〇〇デイサービス(要支援Ⅰの方はおおむね週1回程度のサービス利用)とされています。このことから要支援の方はサービス上制限を受けるようにみえますが、そのうえで要介護状態にならないように介護保険のサービスを利用したり、ご自身でできる体操を行っていただいたりします。
その方の困りごとを解決するために、介護保険を申請していただき、専門職(包括支援センターなど)とプランを検討してもらいます。必要であれば、サービスを給付限度額内で利用することが可能です。

要介護度認定は再申請ができる
要介護度認定は、基本的には定められた一定期間、サービス給付管理を行います。ただ、認定の期間中に本人の状態などに変化があった際や、認定結果を不服とするときには「区分変更の申請」が認められています。
この区分変更については、おおむね1ヵ月程度かかります。しかし、その間もサービス提供については、現在認定を受けている介護度で対応できます。必ずしも状態悪化だけではなく、状態が改善された場合も「区分変更の申請」は行うことも可能です。
要支援だと、サービスの利用方法に制限はありますが、サービスそのものを制限されることはありません。介護保険は、あくまでも本人により自立支援を目指すことと、重度化防止を目的としています。その方のしたいことや支援してほしいことを、すべて介護保険での支援でまかなうわけではなく、その方自身のできる能力を充分に活かして、不足する部分を支援していきます。介護保険での過不足を感じた際は要支援の方は包括支援センター、要介護の方は担当のケアマネジャーさんに相談してみてください。今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。