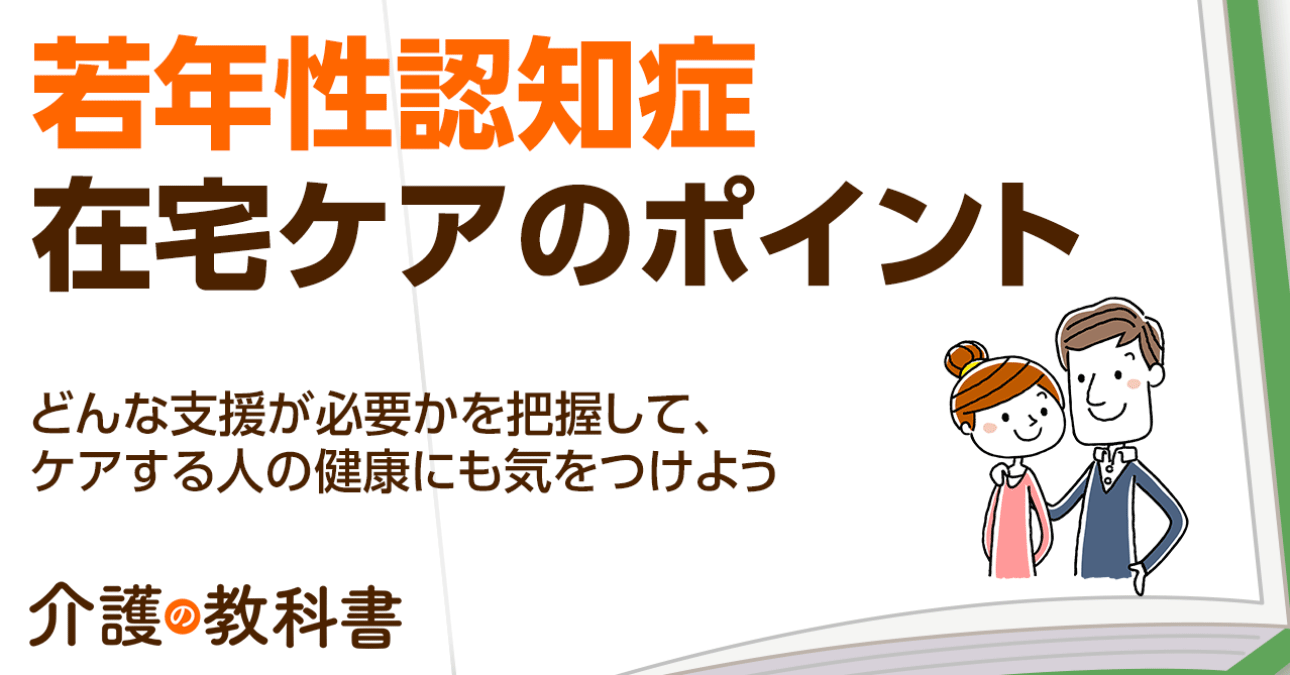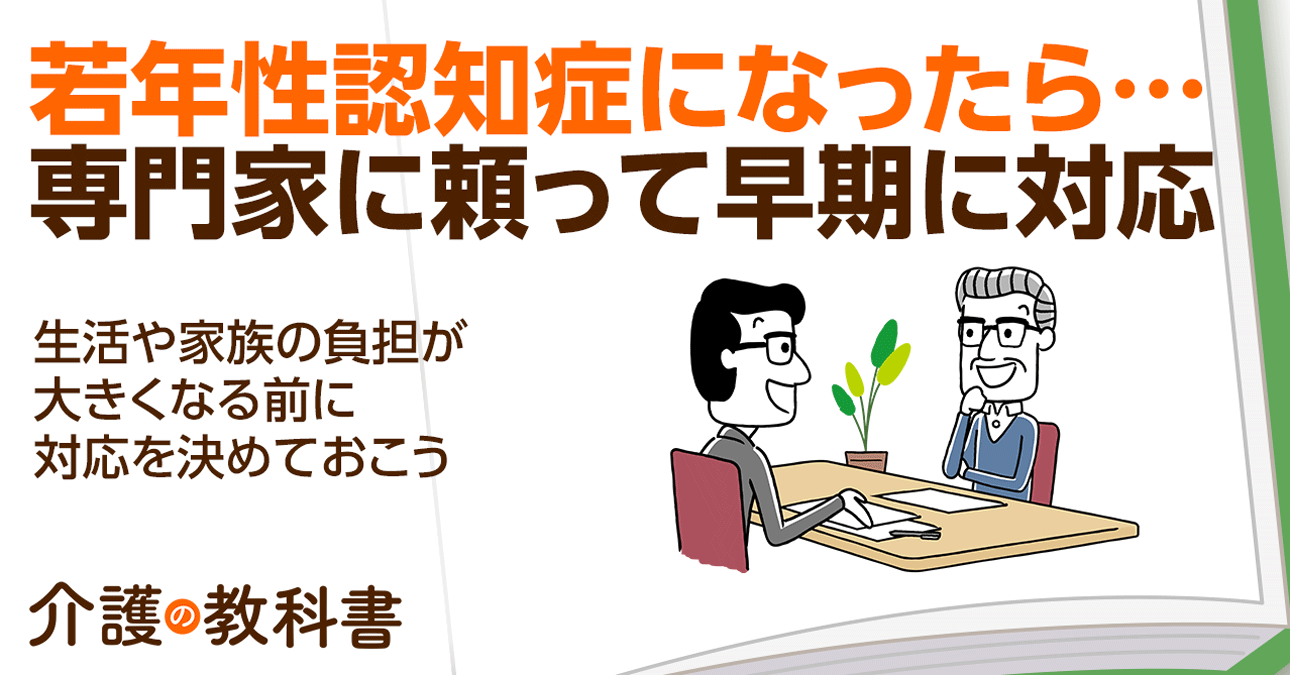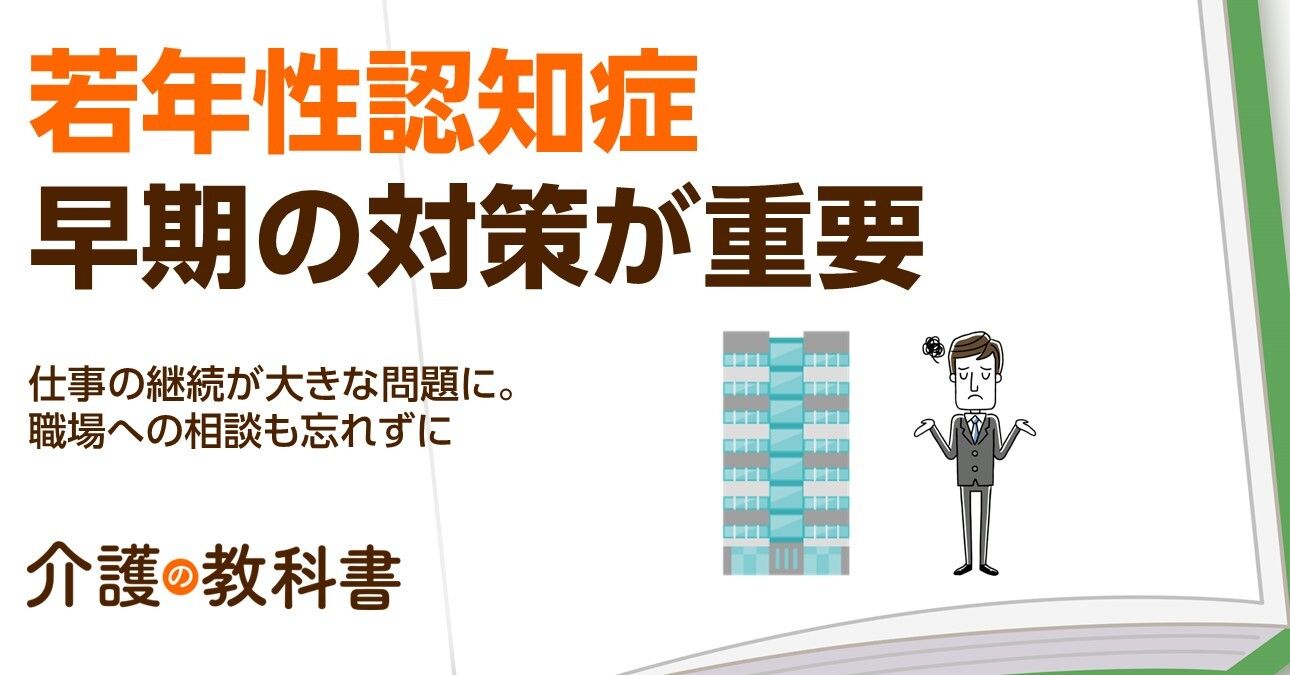皆さんこんにちは。医療と介護の連携支援センター 長谷川です。
今回は「市区町村による若年性認知症の方への支援例」についてお話しします。
若年性認知症は2つの認知症の総称
「若年性認知症の方」と聞いて、皆さんはどのような想像をされるでしょうか。東京都福祉保健局が運営している「とうきょう認知症ナビ」では、東京都のさまざまな支援について掲載されています。それには若年性認知症の対象となる方について、「40歳から64歳に発症した初老期認知症に、18歳から39歳までに発症した若年期認知症を加えた認知症の総称」とされています。若年性認知症という独立した病気があるわけでなく、発症年齢で区分した概念であるとされているわけです。

そもそも認知症が発症する原因はさまざまです。そのため、若年性認知症の方は、高齢者における認知症とは異なった独自の問題・課題が見受けられます。実際に私が支援に携わった方も、40~60代と年齢にばらつきがありました。
この若年性認知症とされる方の総数はどれぐらいいるのでしょうか。2017~2019年度に実施した日本医療研究開発機構が実施した調査においては、若年性認知症者の総数は3.57万人 と推計されています。
この数をどう捉えるかは人それぞれですが、この調査はあくまで診断がついた方のみを記録したものです。そのため私自身は、若年性認知症について悩みを抱えている人は、この数より多く存在しているのではないかと思っています。
東京都における5つの支援
若年性認知症の方への支援として、東京都では下記のような取り組みを行っています。
- 「東京都若年性認知症総合支援センター」の設置
- 「若年性認知症コールセンター」の設置
- 「若年性認知症マニュアル」の作成と運用
- 「若年性認知症ハンドブック」の作成・運用
- 「若年性認知症の方への通いの場をつくるガイドブック」の作成・運用
それぞれ詳細の説明をさせていただきます。
専門機関からの相談も請け負う「東京都若年性認知症総合支援センター」
専門の「若年性認知症支援コーディネーター」が、ご本人やご家族からの多岐にわたる相談に対応する窓口です。地域包括支援センターや医療機関などの専門機関からの相談については、必要な助言を行うとともに、相互に連携しながら若年性認知症の方への支援を行っています。東京都には「東京都若年性認知症総合支援センター」と、「東京都多摩若年性認知症総合支援センター」の2ヵ所存在しています。
国の相談窓口である「若年性認知症コールセンター」
国の電話相談窓口で、本人や家族、支援者などからさまざまな相談を受け付けています。ほかにも、以下のような内容の相談にも対応しています。
- 生活を支える制度や支援
- 医療、障がい者手帳・年金
- 就業中の方への支援
- 症状がすすんできたらどうしたら良いか

専門職に向けた「若年性認知症に関するマニュアル」
多様な原因疾患と社会的課題の多い若年性認知症の個別ニーズに対応した相談支援(マネジメント)を目的に、地域包括支援センターなど地域で若年性認知症の相談支援を行う専門職に向けたものです。医療機関の相談員や、企業・団体等の人事・労務担当者の方も参考とすべき内容となっています。
アセスメントシートや若年性認知症支援連携シートなど、実務で使用できるものが掲載されていることもポイントの1つです。
企業や事務所の人事・労務担当者が対象の「若年性認知症ハンドブック」
65歳未満で発症する若年性認知症は就労時期と重なります。よって、その方の異変に最初に気づくのは職場が多く、そこでの正しい理解と支援が大切と考えられています。企業や事業所の人事・労務担当者などを対象に職場において若年性認知症の方を早期に発見し、支援に繋げていただくことを目的としたものが若年性認知症ハンドブックです。2010年度に初版が作成され、2012年3月、2017年11月に改訂版が作成されました。
若年者のための「若年性認知症の本人の通いの場をつくるガイドブック」
こちらは2021年3月に作成されたものです。若年性認知症の方は介護保険サービスや障がい福祉サービスを利用することが可能になります。しかし、介護保険は高齢者の方に向けた位置づけなので、若年者の方にとってサービスの一般的なメニューがなかなか馴染みにくい面があります。
その方に対して必要なのは、サービス事業者の正しい理解と支援です。この「若年性認知症の本人の通いの場をつくるガイドブック」は「本人の居場所づくり」に主眼を置き、実際にサービスを提供してプログラムづくりを検討している介護保険サービスや、障がい福祉サービスの事業者の皆さまに活用していただくことを目的に作成されています。内容については、若年性認知症の原因疾患や支援の考え方、通いの場をつくるための実践的ポイントと実践事例などです。
高齢の方と若年の方を分けて通いの場を設定
町田市においては、若年性認知症に限ってではありませんが「本人の通いの場をつくる」ことに力を入れて行っております。ここで、医療と介護の連携支援センターが会場を提供して関わっている取り組みについて、ご紹介します。
医療と介護の連携支援センターでは、支援者の方と協力して毎月1回、日曜日に「若年性当事者研究会」を開催しています。この研究会は、若年性認知症と診断された方々で、「認知症と診断されてこれからどうしていきたいか」「どんなことをしていきたいか」などを語り合う場となっています。認知症の制度や参加者同士の生活のこと、困りごとや楽しかった出来事を共有して、自分のことを自分自身で考えていく会です。
ある男性の経験談をきっかけに開催される
この取り組みのきっかけは、ある認知症をお持ちの男性からの言葉でした。その方は当初のもの忘れや、自身の次の行動を考えてしまうことなどを「疲れているのかな」「ストレスかな」と考えていたそうです。ある日、自身で「最近どこかおかしいな」と思いはじめ、クリニックを受診され認知症と診断を受けました。
そのときは「病気なのか」「この先自分がどうなっていくのか」「何もわからなくなってしまうのだろうか」などとさまざまな不安に駆られたそうです。こんな気持ちを誰かに話したいと思ったとき、「実は自分も認知症だと医者に言われ途方にくれた」と言う方と知り合うことができ、時間を忘れたように話をしたとのことでした。不安を抱えているのはお互い同じで安心されたそうです。
この件がきっかけで、最初は若年性認知症の方に限らない当時者さん同士が話し合う場が町田市にできました。そのことにおいて、やはり高齢の認知症の方では分かり合えないところも出てきたために、若年性認知症の方がより語りやすい場を検討した結果、「若年性当事者研究会」が誕生したのです。
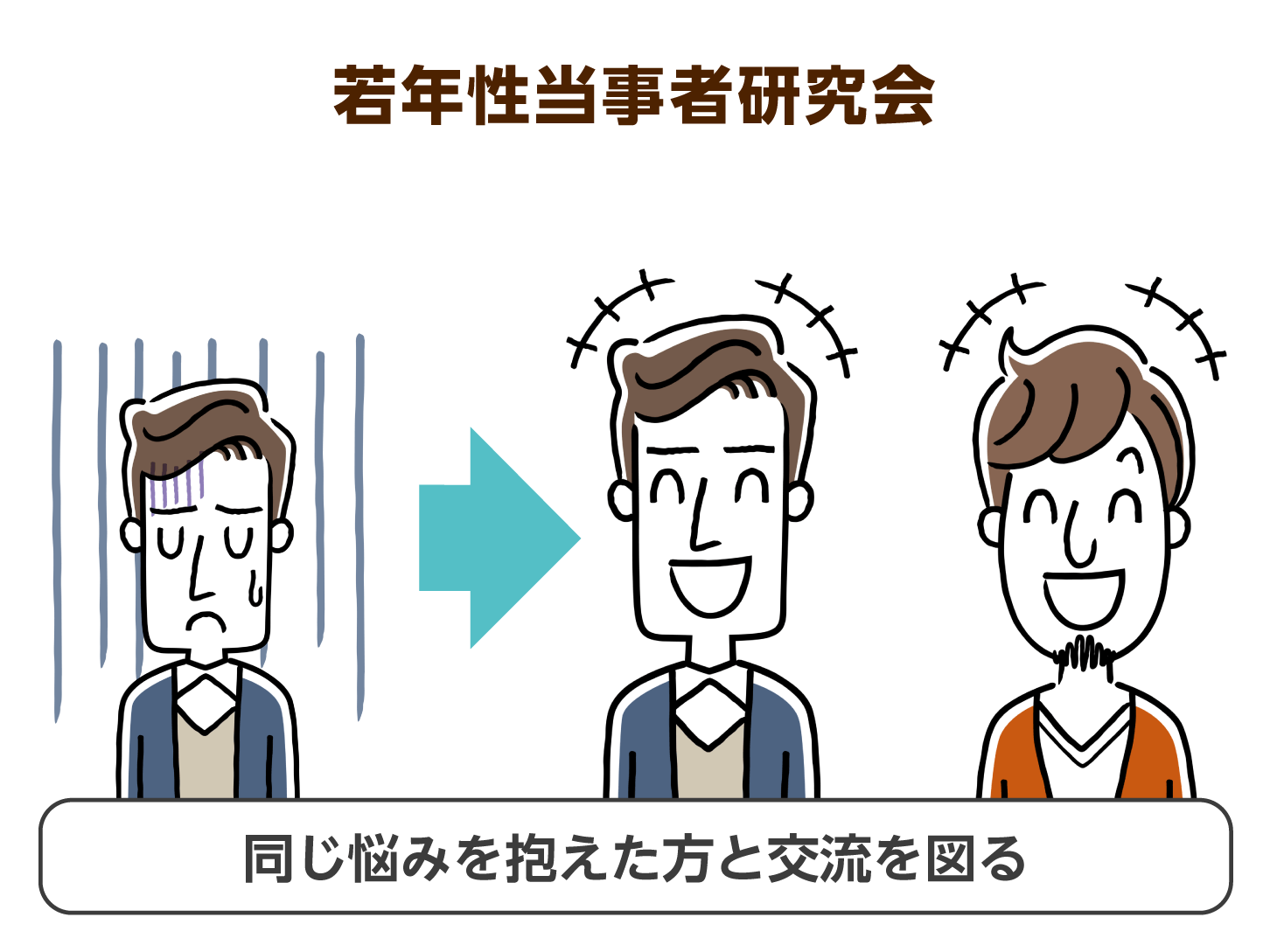
この研究会は月1回開催ですが、10~15時を目途に、昼食を食べながらさまざまな話し合いなど行っています。例えば、楽器を持ち寄って音楽を皆で聞いたり、会議アプリを使って日本各地の若年性認知症の方と話したりなどです。
国や都道府県・区市町村など、それぞれの単位で支援のための整備が進んできてはいますが、そうでない地域も存在します。お住いの支援センターや役所に問い合わせてみてください。
同じ認知症でも年齢によって抱えるニーズが異なる
今回、「認知症の本人の通いの場」をつくるにあたり、高齢の方と若年の方を分けたのは、それまでの場は高齢の方が多かったためです。高齢の方と若年の方では認知症という同じ症状がベースにあっても、抱えるニーズには年齢的要素で違いがあります。例えば、聞きたい音楽でも趣味・趣向は変わってきますよね。
個人それぞれの多様性を大切にすることは当たり前ですが、参加する方はすべて平等であり対等です。第13回でも書かせて頂きましたが、他人事ではなく自分事に捉え「町」や「地域」の一員として、これからの介護や福祉を考えるが大切であることを皆さんと共有できればと思います。