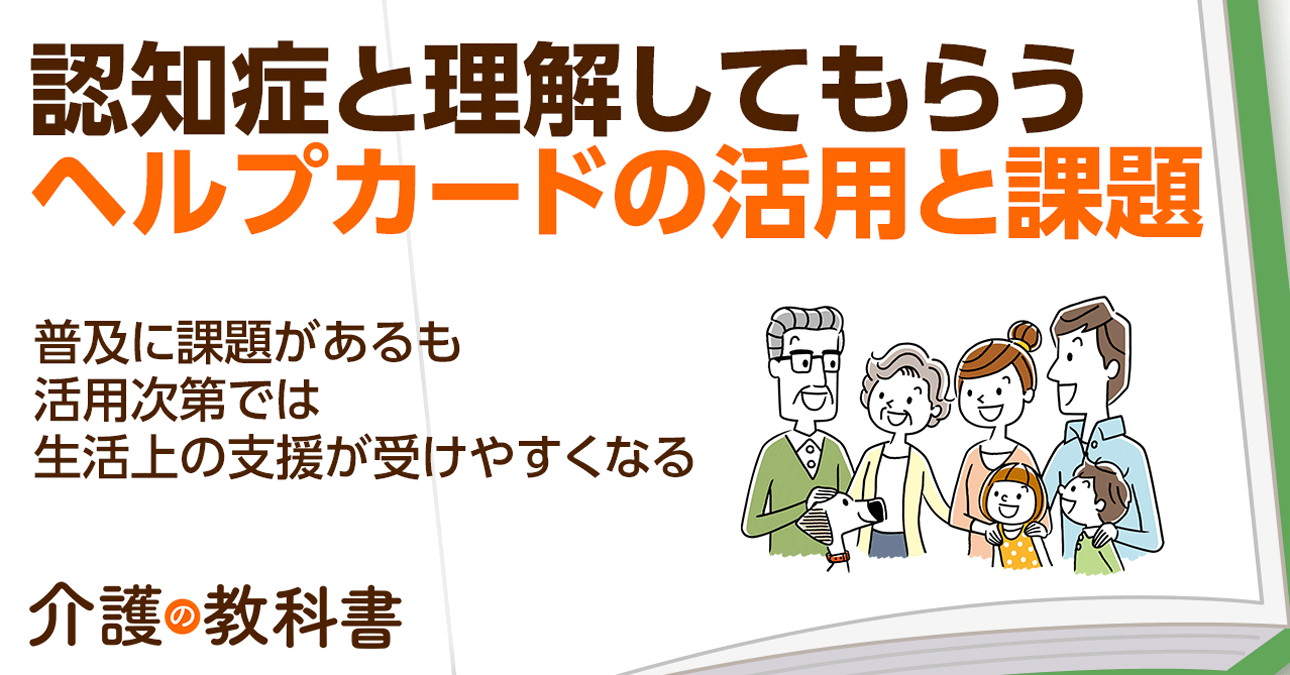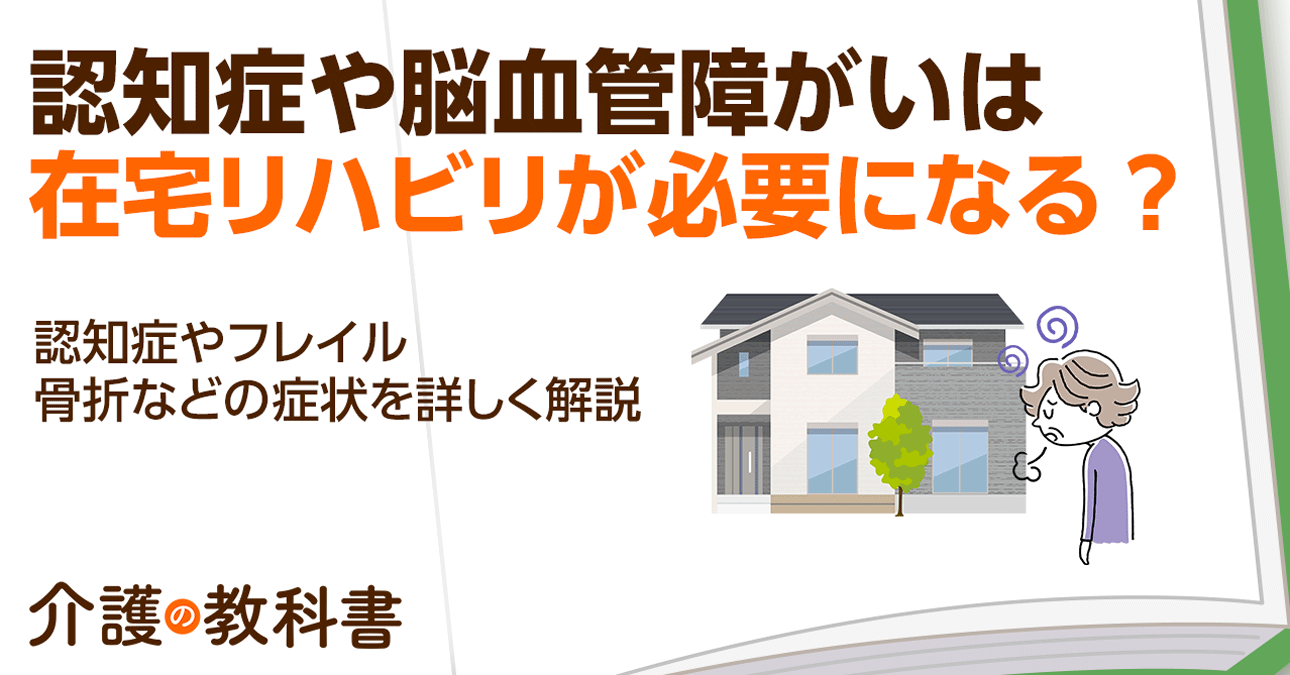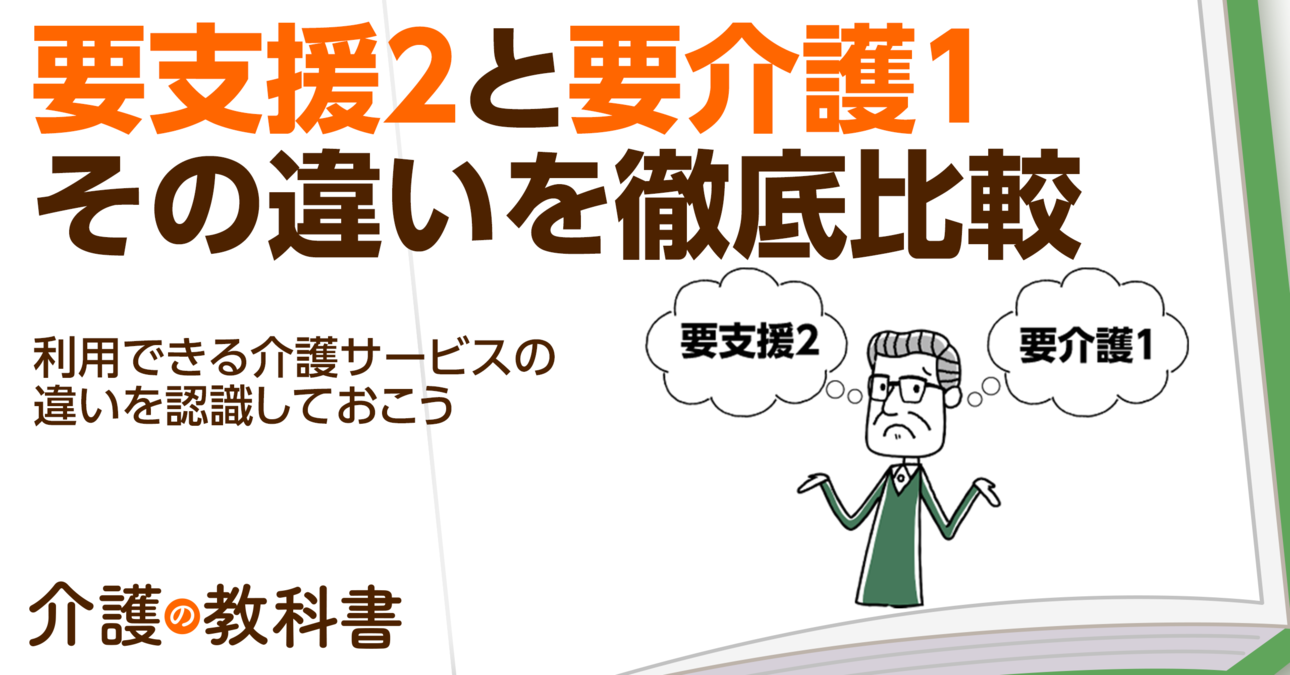皆さんこんにちは。(医)創生会町田病院地域連携課の長谷川昌之です。
今回は、「人生の最終段階」を在宅で過ごす場合の費用についてお話いたします。
終末期ではなく、「人生の最終段階 」
「終末期」はどの時期を指すのか?
おそらく人によっては、もう予後が見込めない場合を想像される方が多いのではないでしょうか。
私の職場にいる事務員さんに聞いてみたところ、余命3ヵ月ぐらいかな?と回答がありました。
個々によってさまざまな捉え方がありますが、今回の「終末期」とは、厚生労働省が出している『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』から読み取らせていただく形を取りたいと思います。
このガイドラインでは、「終末期医療」から「人生の最終段階における医療」へと名称変更がなされました。
ガイドライン内の「人生の最終段階」とは、回復の見込みのない疾患のために死が避けられない状態を指しているようです。
回復の見込みのない疾患とは、各種悪性腫瘍、非がん性疾患である臓器障害系疾患(慢性心不全、慢性呼吸器疾患、透析困難)、神経難病(ALSなど、)、認知症、多発性脳梗塞など多種多様な疾病を含んでいます
「人生の最終段階」かどうかの判断には、客観的視点が必要
そして、「人生の最終段階にある」という判断には、客観性が求められるため、ご本人や家族の意見だけではなく、医師・看護師など、多職種から構成されるチームによって確認される必要があります。
ご本人・家族だけではなく、その方を取り巻くチーム全体にとっても悩ましい問題でもあります。

いつか訪れるときに備えておく
ほとんどの方にとって在宅での療養生活は突然始まります。
あらかじめ万端に準備をしていたわけではなく、事前にまとまった金額を準備することはあまりないと思います。
ただ、いつか自分自身や家族に起こり得ること可能性は多いにあります。
ぜひ今から知っておくことの大切さを理解していただけたらと思います。
訪問診療と往診の違い
ここからは、「人生の最終段階」を迎えようとしている方が自宅療養で訪問診療を導入した場合について、3つの事例に基づいてご説明したいと思います。
そもそも、訪問診療と往診の違いをご存じですか?
訪問診療も往診のどちらも医師に診療を受けることには変わりありませんが、意味がまったく異なる医療サービスです。
「訪問診療」は24時間体制で在宅療養をサポート
「訪問診療」とは、計画的な医療サービス(お住まいを訪問して診療する)を指しています。
例えば1・3週目の火曜日(月2回)の午前中にお伺いするなど、定期的かつ計画的にお住まいを訪問し、診療・治療・薬の処方・療養上の相談や指導を行います。
また、状態の急変時には緊急訪問に伺ったり、入院の手配を行ったりするなど、臨機応変に対応することから「かかりつけ医」としての役割を持ち、多くの場合、24時間体制で在宅療養をサポートするのが、訪問診療です。
なお、訪問診療は患者と医療機関との契約に基づいて行われます。

「往診」は困ったときの臨時の手段
一方、「往診」とは、通院できない方の要請を受けて、医師がその都度診療を行うことです。
突発的な病状の変化が見られても救急搬送が必要でない場合には、普段からお世話になっている「かかりつけ医」にお願いして診察に来てもらうものです。
そのため、「診療」は基本的には困ったときの臨時の手段とお考えください。
かかりつけ医師側に必ず対応しなければならないという義務はありません。
在宅での訪問診療にかかる費用
在宅で訪問診療を導入した場合にかかる費用について、ご説明させていただきます。
要介護度1~2程度で通院が困難なケース(Aさん)
Aさんは比較的軽度(要介護1~2程度)ではありますが、通院は困難な方です。
この場合、月1回程度の訪問診療が必要となるため、医療費は概ね下記の通り算定されます。
ただし、医療費はあくまでも主治医となる先生の見立てになります。
3,133点×10円=3万1,330円⇒1割負担の場合…約3,200円/月
- 在宅時医学総合管理料:2,300点(月1回の訪問診療と緊急時の待機+療養上の相談)
- 訪問診療料:833点(実際にお住まいの場所への訪問診療料)
要介護度3~5度で通院が困難なケース(Bさん)
Bさんは比較的中重度(要介護3~5程度)で、通院困難な方です。
月2回程度の訪問診療が必要と主治医が判断された場合の医療費は、下記の通りです。
6,266点×10円=6万2,660円⇒1割負担の場合…約6,300円/月
- 在宅時医学総合管理料:4,600点(月2回の訪問診療と緊急時の待機+療養上の相談)
- 訪問診療料:1,666点(833点×2回)※実際にお住まいの場所への訪問診療料に依拠する
要介護4~5程度で在宅酸素を使用している通院困難な方(Cさん)
Cさんは比較的重度(要介護4~5程度)で、在宅酸素を使用している通院が困難な方になります。
主治医の方の見立てで月2回程度訪問診療が必要な医療費用として概ね下記の部分が算定されます。
13,646点×10円=13万6,460円⇒1割負担の場合…約1万4,000円/月
- 在宅時医学総合管理料:4,600点(月2回の訪問診療と緊急時の待機+療養上の相談)
- 訪問診療料:1,666点(833点×2回)(実際にお住まいの場所への訪問診療料)
- 在宅酸素管理料:7,380点(在宅で酸素療法を行うための物品や管理する費用)
ここまで3つのケースでご説明しましたが、各々の保険区分によって負担割合は変動しますので、負担割合が2割または3割の方はその分負担も増えることになります。
また、緊急で往診が発生した場合や処方が発生した場合、検査(採血など)は別途料金がかかるので、その分負担金額も上がります。
今回は皆さんにわかりやすく知っていただけるようにある程度区分けさせていただきましたが、本来介護度や病名が同一でもサービス内容は人それぞれで、一律ではないことをご理解ください。
人生の最終段階を迎える前に家族・専門家と話し合おう
どこで生活を望まれるかによってかかる費用は変わります。
もし施設(特別養護老人ホームや老人保健施設、有料老人ホームなど)での生活を望まれた場合、かかる費用も変わりますので十分に検討いただくことが必要となります。
併せて、医療費と介護保険費用については別ですので、忘れずに考えていく必要があるでしょう。
いざとなってからではなく、「人生の最終段階」をご自身やご家族がどうされたいかを事前に話し合うことが必要です。
そのために、厚生労働省では「A・C・P(アドバンス・ケア・プランニング)」を2018年11月から「人生会議」と名称変更し、医療・ケアについて、ご本人が家族や医療・ケアチームと繰り返し話し合う取り組みを推奨しています。
ぜひ大切な方と話し合うことから始めてみてください。