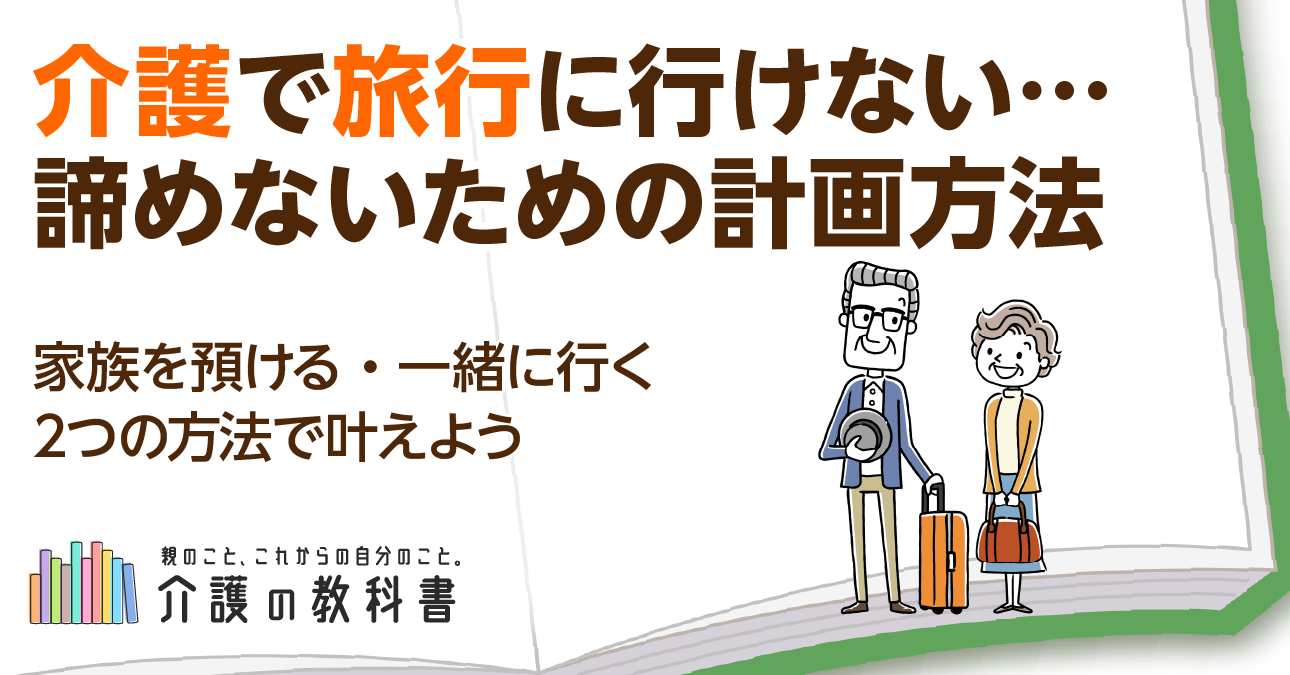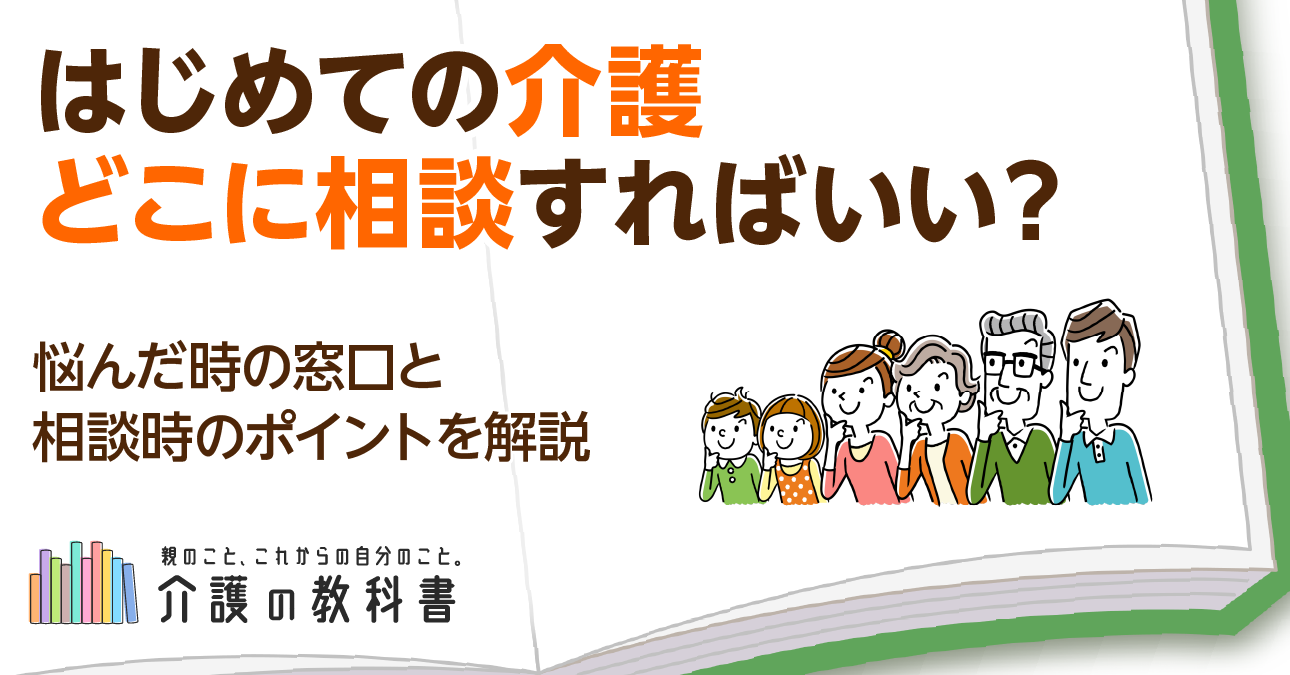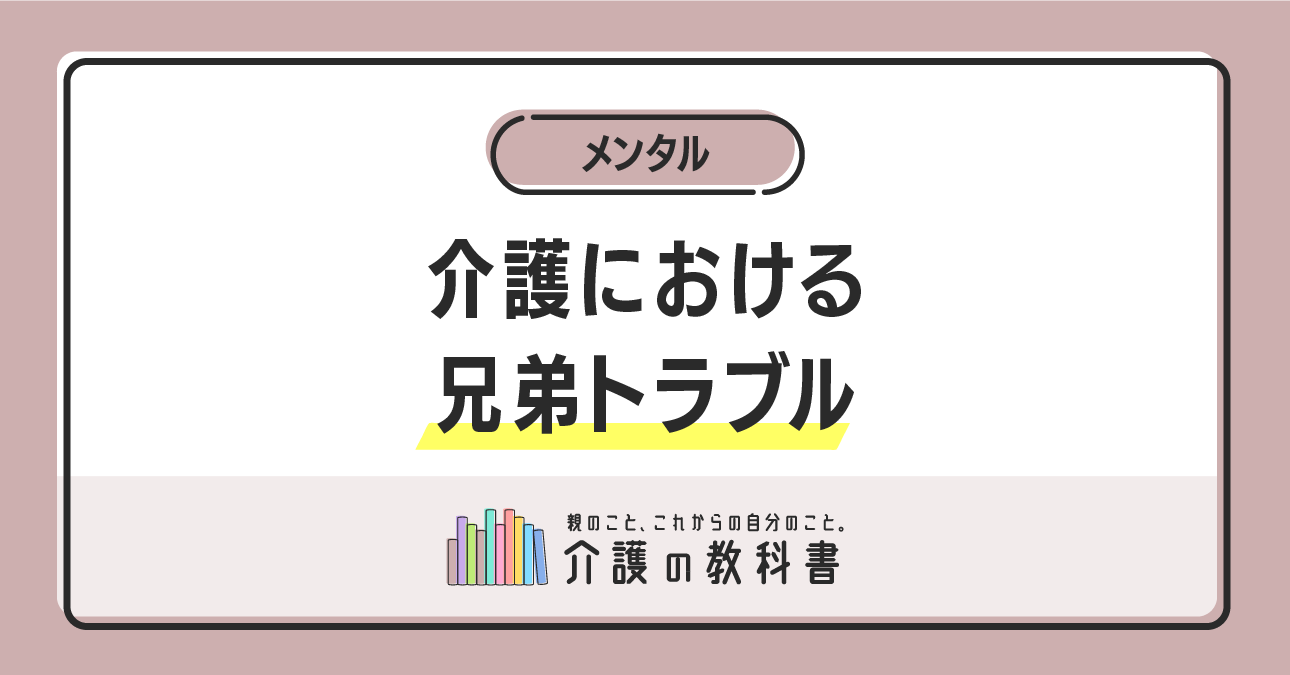町田病院長谷川です。第15回では入退院支援について説明し、急性期病院の入院期間が短縮する傾向にあることをお話ししました。
「病院から追い出された」「たらいまわしにされた」…と言いながら患者さんが途方に暮れて退院することがないように、病院には安心して早期退院・早期転院していくための体制が必要です。
今回は在宅医療コーディネーターとして、医療と介護がどのように連携していく必要があるのかについてお話しします。
医療と介護は連携する必要がある!
患者さん自身やご家族が安心して退院・転院できるように、入院前や外来時からサポートしていくことを入退院支援と言います。
ただ、退院して在宅介護を受けることにした方の場合は、入退院支援は病院側が積極的に推し進めれば良い、というわけではないため、受け手側である患者さんの在宅介護の準備が必要です。
退院や転院は否応なく押し迫ってくるので、準備が間に合わない患者さんは、病院から追い出された、たらいまわしにされた、と思う方も少なくないと思います。
そんなとき、医療と介護・福祉がしっかりと連携し、その方の望まれた生活(残された時間が短いとしても自宅に戻りたい・施設で過ごしたい・ホスピスなどの医療機関で過ごしたい…etc)を支援するために協働できたら、状況は変わると思います。
医療と介護が連携するための取り組み
入退院支援を行うにあたり、2015年から在宅医療・介護連携推進事業を整備するように求められました。
在宅医療・介護連携事業とは、医療と介護を必要としている高齢者の方に対して、関係機関が連携して継続的なサポートをすることで、住み慣れた地域で生活を続けてもらえるようにするための事業です。
地域包括ケアシステムなどは、みなさまにもなじみのある言葉だと思います。

この事業は2018年までに各市町村で行わなくていけない事業なので、みなさまの地域にもあると思います。
厚生労働省が定めた具体的な取り組みとしては下記の(ア)~(ク)の8項目となります。
在宅医療・介護連携推進事業の事業項目
- (ア)地域の医療・介護の資源の把握(地域の医療機関などをリスト・マップ化することなど)
- (イ)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
- (ウ)切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進(地域の在宅医療・介護サービスにおける提供体制を構築すること)
- (エ)医療・介護関係者の情報共有の支援
- (オ)在宅医療・介護連携に関する相談支援
- (カ)医療・介護関係者の研修
- (キ)地域住民への普及啓発 (パンフレットの活用やシンポジウムの開催など)
- (ク)在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携(必要に応じた隣接している市町村の連携など)
ここで注目すべきは(ウ)の切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進です。
2015年の段階では医療と介護の間の連携にはまだ切れ目があり、それを改善していく必要性があったということですね。
この切れ目に陥りがちだったのは、特に病院から退院をされた方です。
医療と介護は密接な連携が必要になる分野ですが、実際にはこの部分の連携がうまくとれていない状態でした。
つまり、病状は安定しているのに、在宅で介護するだけの準備や住宅環境の整備などが整わず退院に至れない方が多くいたのです。
そのため、本来であれば退院できる方も自宅に戻ることができず、入院が長期化する不幸が発生していました。

患者さんが自宅に戻れない状況だとしても病院のベットは不足しているため、患者さんが望まない場所へ退院したり、他の病院へ転院したりといった事態に発展していました。
このような事態を防ぐためにも、医療と介護が切れ目なく支援できる体制を構築する必要があるとはっきり表明したことを私は重要だと思っています。
町田市の取り組み事例
それでは、実際はどのように医療と介護・福祉は連携しているのか、私の勤める町田市を事例に用いて説明します。
町田市は上記の(ア)~(ク)に該当する8つの取り組みを行うために、町田市の医師会とタッグを組みました。
この事業を行うためには、行政・医師会・歯科医師会・薬剤師会や他介護保険事業所団体、地域のかかりつけ医がともに行う必要があると考えたからです。
8つの項目のなかで最初に取り組んだのは、多職種からなる主体の協議会を設置すること、そして(カ)医療・介護関係者の研修でした。
協議会は「町田安心して暮らせるまちづくりプロジェクト協議会(以下:町プロ協議会)」として設置され、医療介護連携などについて市に提言を行うものです。
この町プロ協議会の構成団体は、医師会・歯科医師会・薬剤師会・包括支援センター・ケアマネージャー連絡会、そして介護保険事業所団体・行政を含めた18団体で構成されました。
研修の内容は、共通のテーマをグループワークで話すことにより、医師やケアマネージャー、支援センターの困りごとや課題、そして強みを理解できるもの。

よく顔の見える関係づくりと言いますが、顔見知りになった程度ではお互いにしっかりと役割や課題を把握し、提携することは難しいと思います。
そのため、お互いの理解を深めることができる研修会になるように工夫されました。実際のテーマを紹介しますね。
- 第1回 多職種協働の必要性を学ぶ
- 第2回 口腔ケアと誤嚥性肺炎の研修を踏まえたうえでの地域の連携について
- 第3回 認知症高齢者への早期支援のあり方~多職種による有機的連携
- 第4回 高齢者の尊厳が守られ、人生の豊かさが実感できるまちを目指して
- 第5回 救急車の適正利用について
- 第6回 市民向けの発表会「みんなで知ろう 町田の医療と介護」
- 第7回 介護現場における感染症対策
- 第8回 高齢者の運転免許について考える
- 第9回 市民向け研修会「住み慣れた家で自分らしく生きたい」みんなで支える在宅医療
- 第10回 消化器がんについて
- 第11回 市民向け研修会「在宅療養とおかねの話」
このように、連携が必要だと思われることをテーマとした研修会に、多数の専門職・市民の方の参加を頂きました。
在宅で過ごすための備えをする必要がある
このような取り組みにより、町田市ではお互いの課題や強みを知ることで、お互いの専門性が明確化され始めました。
入退院支援に関して言えば、病院で働いている方は、在宅医療・介護支援の方に対して病院の制度や専門性、現状の医療について伝えることができました。
一方で在宅医療・介護支援の方は、病院で働いている方に対してさまざまな在宅支援サービスを伝えることができました。
もちろん、他の全ての地域と同じとは限りません。どこがリーダーシップをとるかで違いはありますし、各地域の高齢化率なども影響します。
ただ、以前の医療と介護は、近いフィールドにあるのに、あまりにもお互いを知らない状態でした。その状態をクリアしていかない限り、医療と介護の切れ目はなくならないと思います。
みなさんのなかには、病院へ入院すると在宅には戻れないのかも…と不安になってしまう方が多いかと思います。
もちろん、病院や関係機関も一生懸命にサポートします。
しかし、みなさまが自分事として考え、病気やケガで入院したときに相談できる場所(包括や市役所の担当窓口・病院の連携室など)を事前に知っておくことがとても大切だと思います。