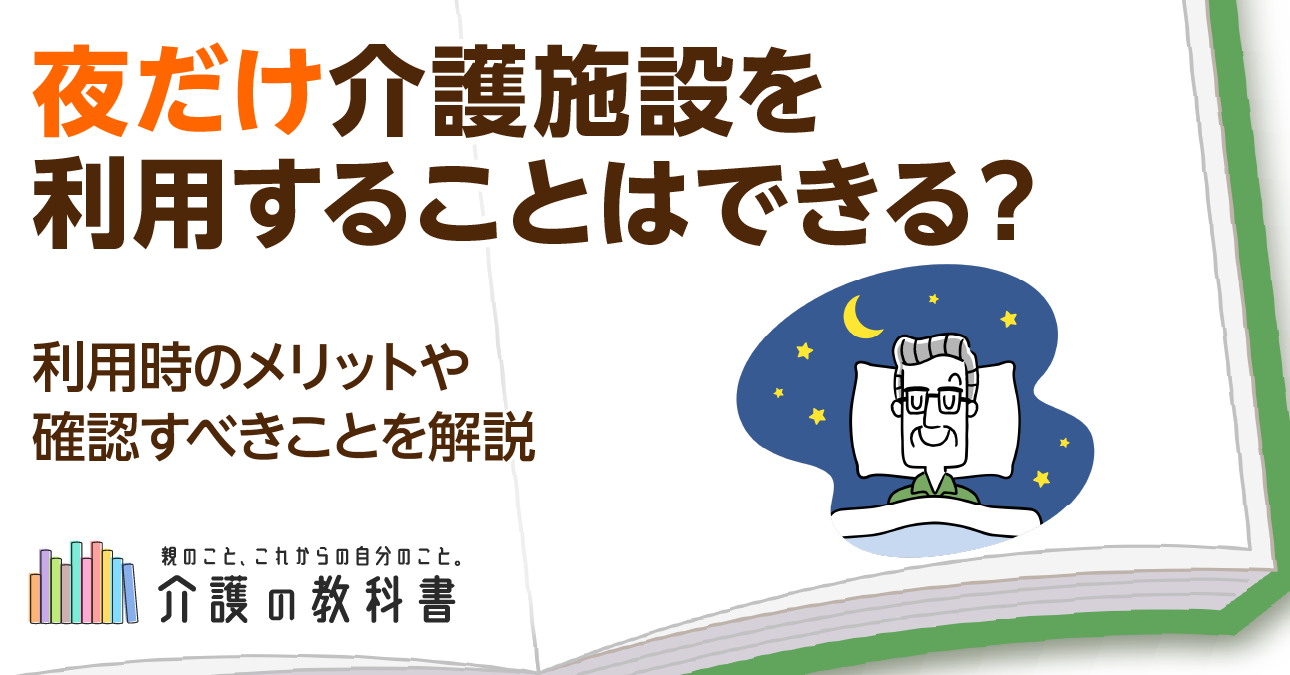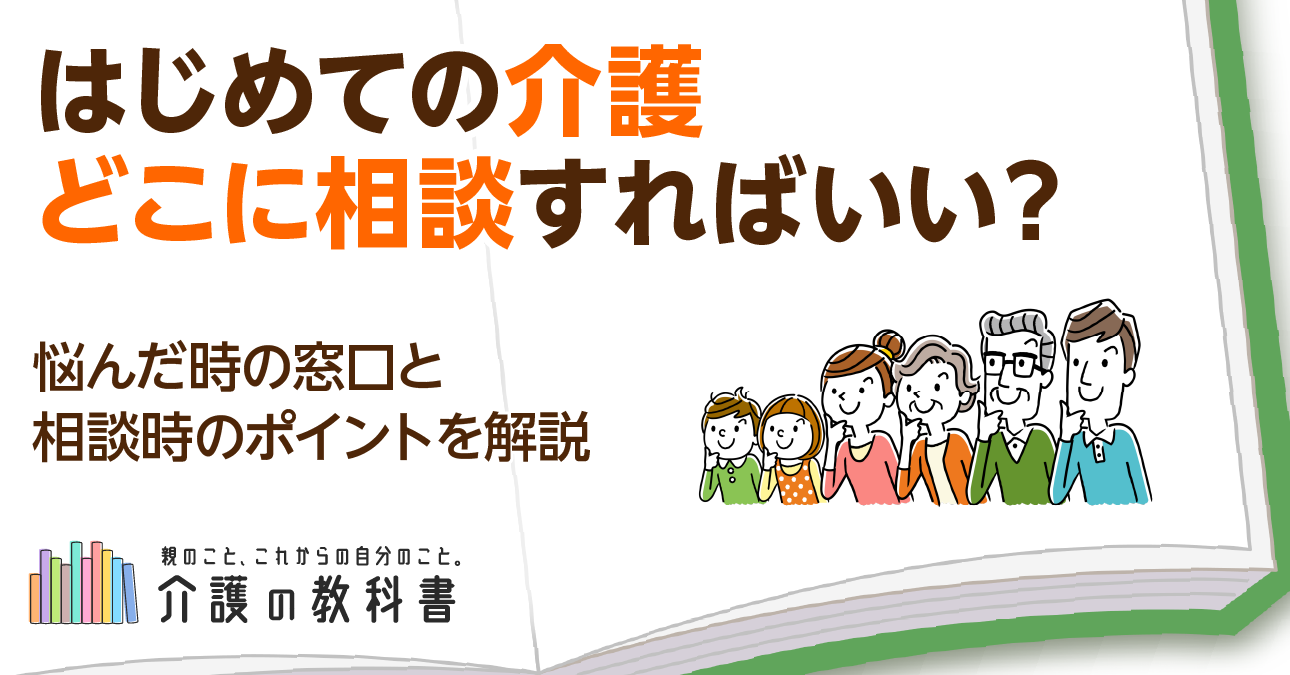要支援の場合もケアマネを利用できるのか?
要支援の場合にはケアマネジャーがつかない?
要支援1・2の認定を受けた方には、基本的にはケアマネジャー(介護支援専門員)が直接つくことはありませんでした。現在は、法改正により居宅介護支援事業所も届を出せば予防給付が直接できるようにはなっていますが、ほとんど申請はされていないのが現状です。
代わりに、地域包括支援センターが介護予防支援を担当するケースが多く見られます。
これは要介護1〜5の方とは異なる仕組みとなっています。要介護認定を受けた方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが専任で担当しますが、要支援の方は地域包括支援センターが窓口となり、介護予防ケアプランの作成や各種サービスの調整を行うのです。
ただし「支援を受けられない」というわけではありません。地域包括支援センターには保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)といった専門職が配置されており、これらの職員がチームとなって支援にあたります。 実質的には、ケアマネジャーがつくのと同等の専門的な支援を受けることができるでしょう。
要支援の方への支援は「介護予防支援」と呼ばれ、現在の生活機能を維持・改善し、要介護状態への移行を防ぐことに重点が置かれています。単に介護サービスを提供するだけでなく、運動機能の向上や栄養改善、口腔機能の向上など、予防的な観点から総合的な支援を行うことが特徴といえます。

地域包括支援センターが担う介護予防支援とは
地域包括支援センターが提供する介護予防支援は、要支援者の自立した生活を支える重要な仕組みです。
介護予防支援の中核となるのが、介護予防ケアプランの作成です。 センターの専門職は、要支援者の心身の状態、生活環境、本人の希望などを総合的に評価し、一人ひとりに適したプランを作成します。
このプランには、デイサービスやホームヘルプサービスといった介護予防サービスだけでなく、地域の通いの場への参加や、ボランティア活動など、幅広い社会資源の活用も含まれます。
2024年3月時点で全国に5,404か所の地域包括支援センターが設置されており、約1万9千人の専門職が配置されています。
介護予防支援の特徴的な点は、予防の観点を重視していることです。要介護状態への移行を防ぐため、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症予防、閉じこもり予防など、多角的なアプローチを行います。
実際の支援では、定期的なモニタリングも重要な要素となります。センターの職員は、サービス利用開始後も継続的に利用者の状態を確認し、必要に応じてプランの見直しを行います。
状態が改善すればサービスを減らし、自立度を高める方向で調整することもあれば、状態の変化に応じて新たなサービスを追加することもあるでしょう。
このように、地域包括支援センターの介護予防支援は、要支援者が可能な限り自立した生活を送れるよう、専門的かつ継続的な支援を提供する仕組みとなっているのです。
要支援認定後からサービス利用までの流れ
要支援認定を受けてから実際にサービスを利用するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。この流れを理解しておくことで、スムーズに必要な支援を受けられるようになるでしょう。
要支援1・2の認定結果が届いたら、まず地域包括支援センターへ連絡します。 連絡先は認定結果通知書に記載されていることが多く、不明な場合は市区町村の介護保険課で確認できます。
センターへの連絡後は、以下の流れで進行します。
- 初回面談
- 介護予防ケアプランの原案作成
- サービス担当者会議
- 正式なケアプランが作成
- サービス利用が開始
- 最初の評価
以降はサービスの提供状況や改善の有無を確認し、必要に応じてプランを見直していきます。これにより常に最適な支援を受けられる体制が整えられているのです。
認定結果通知からサービス利用開始まで通常2~3週間程度かかりますが、緊急性が高い場合はより迅速な対応も可能です。
ケアマネがいない時はどこに相談すればいい?
地域包括支援センターの探し方と初回相談のポイント
要支援認定を受けたものの「どこに相談すればいいのか分からない」という方は少なくありません。ケアマネジャーが直接つかない要支援の場合、地域包括支援センターが相談窓口となります。
地域包括支援センターの紹介は、自治体の介護保険課や高齢者福祉課、長寿社会課といった名称の部署に「要支援の認定を受けたので、担当の地域包括支援センターを教えてほしい」と伝えれば、住所に応じたセンターを案内してもらえます。
初回相談の際は以下のものを用意しておくとよいでしょう。
- 要支援認定の結果通知書
- 介護保険被保険者証
- お薬手帳
- かかりつけ医の診察券
また、相談時に伝えるべきポイントは以下の通りです。
- 現在の生活状況
- 「買い物に行くのが大変になった」「掃除が思うようにできない」「入浴時に不安を感じる」など、日常生活のどの部分に支援が必要かを明確に伝えましょう。
- 家族構成や家族の支援体制について
- 「息子は仕事で忙しく、週末しか来られない」「娘は遠方に住んでいる」といった事情があれば、それも含めて相談してください。
- 経済的な不安がある場合
- 介護保険サービスの利用料は原則1割負担(所得により2~3割)ですが、負担軽減制度もあります。
初回相談は緊張するかもしれませんが、地域包括支援センターの職員は高齢者支援のプロフェッショナルであるため、安心して相談してみてください。
居宅介護支援事業所への委託の可能性
要支援の方の介護予防支援は地域包括支援センターが担当しますが、実際の業務を居宅介護支援事業所に委託するケースもまれに存在します。
地域包括支援センターが業務を委託する背景には、センターの業務負担の軽減と、利用者により身近な場所での支援提供という二つの側面があります。
委託が行われる場合でも、利用者側の手続きに大きな違いはありません。まず地域包括支援センターに相談し、センターが適切な居宅介護支援事業所を選定します。
その後、委託先の事業所のケアマネジャーが実際の介護予防ケアプラン作成や定期的なモニタリングを担当することになるのです。
委託のメリットとして、地域の事情に詳しく、地元のサービス事業者とも連携が取りやすい自宅から近い事業所のケアマネジャーに担当してもらえる可能性があるため、きめ細やかな支援が期待できます。
しかし、現実的には報酬制度や利用者の要求水準との兼ね合いにより、予防給付はあまり行われていないのが現状です。
相談後~ケアプラン作成までの流れ
地域包括支援センターへの初回相談を終えた後、実際に介護予防ケアプランが完成するまでには、いくつかの段階があります。
初回相談の後、担当職員による詳細なアセスメント(評価)が行われます。 これは通常、自宅訪問の形で実施され、生活環境の確認と併せて行われることが多いです。
アセスメントでは、身体機能、認知機能、生活状況、社会参加の状況、住環境など、多角的な視点から現状を把握します。歩行能力のチェックや、実際に家事動作を見せてもらうこともあるかもしれません。
アセスメントの結果をもとに、担当職員は利用者と一緒に目標設定を行います。「3か月後には一人で買い物に行けるようになりたい」「趣味の園芸を再開したい」といった具体的な目標を立てることで、支援の方向性が明確になります。 目標は現実的で達成可能なものにすることが大切です。
目標が定まったら、それを達成するために必要なサービスの選定に入ります。サービスの頻度や期間も、目標達成に向けて適切に設定されます。
プランの原案ができあがると、先述の通りサービス担当者会議の準備が始まります。会議には本人・家族、センター職員、各サービス事業者が一堂に会し、プラン原案について説明を受けた後、それぞれの立場から意見交換を行います。
「リハビリの頻度をもう少し増やしたい」「送迎の時間を調整してほしい」といった要望があれば、この場で調整することができるのです。
会議での合意形成を経て、正式な介護予防サービス計画書が作成されます。内容を確認し、同意のサインをすることで、プランが確定となります。
プラン確定後は、各サービス事業者との個別契約を結びます。全ての契約が完了すれば、いよいよサービス利用開始です。焦らず、詳細な情報共有を行いながら一つひとつのステップを確実に進めていくことが、より良いケアにつながるといえるでしょう。

要支援・要介護の違いとケアマネジャーの探し方
要支援1・2と要介護1~5が使える制度の違いを知ろう
要支援と要介護では、利用できるサービスや支援体制に大きな違いがあります。
認定区分の基本的な違い
- 要支援1・2:日常生活の基本動作はほぼ自立しているものの、一部の生活行為に支援が必要な状態。
- 要介護1~5:日常生活の基本動作にも介助が必要な状態。 その必要度に応じて5段階に分類されています。要介護5が最も重度の状態となります。
利用できるサービス
- 要支援:「介護予防サービス」を利用 機能の維持・改善を目的として要介護状態への移行を防ぐことに重点を置いて提供されます。
- 要介護:「介護サービス」を利用 要介護3以上になると、特別養護老人ホームへの入所申請も可能となります。
ケアプラン作成の担当者
- 要支援は地域包括支援センター(または委託を受けた居宅介護支援事業所)が担当
- 要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが専任で担当
状態の変化により要支援から要介護へ、または要介護から要支援へと認定が変わることもあります。その際は、支援体制も切り替わることになりますが、引き継ぎはしっかりと行われ、継続性のある支援が受けられるよう配慮されているのです。
要介護になった時のケアマネジャーの探し方
要支援から要介護に認定が変わった場合、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所のケアマネジャーへと担当が切り替わります。
ケアマネジャーを探す一般的な方法は、市区町村の介護保険担当窓口で居宅介護支援事業所のリストをもらうことです。多くの自治体では、地域ごとの事業所一覧を用意しており、所在地や連絡先、特色などが記載されています。
地域包括支援センターに相談するのも有効な方法です。 要支援時代からの経過を知っているセンターの職員は、状態や希望に合った事業所を紹介してくれることもあります。
病院や診療所から紹介を受けることもできます。特に退院後に介護が必要になった場合、病院の医療ソーシャルワーカーが適切な事業所を紹介してくれることが多いでしょう。

信頼できるケアマネの見分け方と上手な相談のコツ
良いケアマネジャーとの出会いは、充実した介護生活を送る上での重要な鍵となります。
- 傾聴力の高さ
- 初回面談で一方的に説明するのではなく、利用者や家族の話をじっくりと聞いてくれるケアマネジャーは信頼できる可能性が高いといえます。
- 生活の困りごとだけでなく、趣味や生きがい、これまでの人生についても関心を持って聞いてくれる人なら、その人らしい生活を支援するプランを作ってくれるはずです。
- 提案力があるか
- 「このサービスしかありません」と断定的に話すのではなく、複数の選択肢を示しながら、それぞれのメリット・デメリットを説明してくれるケアマネジャーは信頼できるでしょう。
- 連絡の取りやすさや対応の迅速さ
- 緊急時にすぐ対応してもらえるかどうかは、在宅生活を続ける上で非常に重要な要素となります。
- 合わせて医師、看護師、リハビリ専門職、ヘルパーなど、様々な専門職と円滑にコミュニケーションを取れる体制が整っている場合はなおよいでしょう。
上手に相談するためのコツとして、まず準備が大切です。相談したいことをメモにまとめ、優先順位をつけておくと、限られた時間で効率的に話ができます。
また、遠慮せずに本音を伝えることも重要です。「家族に迷惑をかけたくない」という思いから、本当は必要な支援を断ってしまう方も少なくありません。経済的な不安、家族関係の悩み、将来への不安など、何でも相談してみてください。
定期的な情報共有も心がけましょう。月1回の定期訪問時だけでなく、状態に変化があった時は早めに連絡を入れることが大切です。
最後に、感謝の気持ちを伝えることも忘れないでおきましょう。「おかげで助かっています」という一言が、より良い関係構築につながることもあります。
まとめ
要支援認定を受けた方には通常のケアマネジャーは直接つきませんが、地域包括支援センターが介護予防支援を担当し、専門職チームによる手厚いサポートを受けることができます。
センターへの相談から2~3週間程度でサービス利用を開始でき、必要に応じて居宅介護支援事業所への委託も可能です。制度の違いを理解し、適切な相談先を把握しておくことで、状態に応じた最適な支援を受けることができるでしょう。