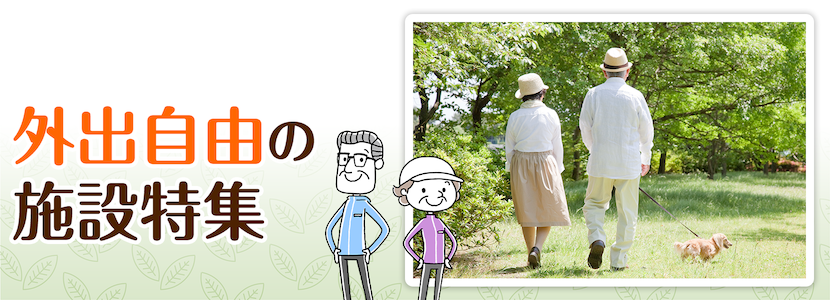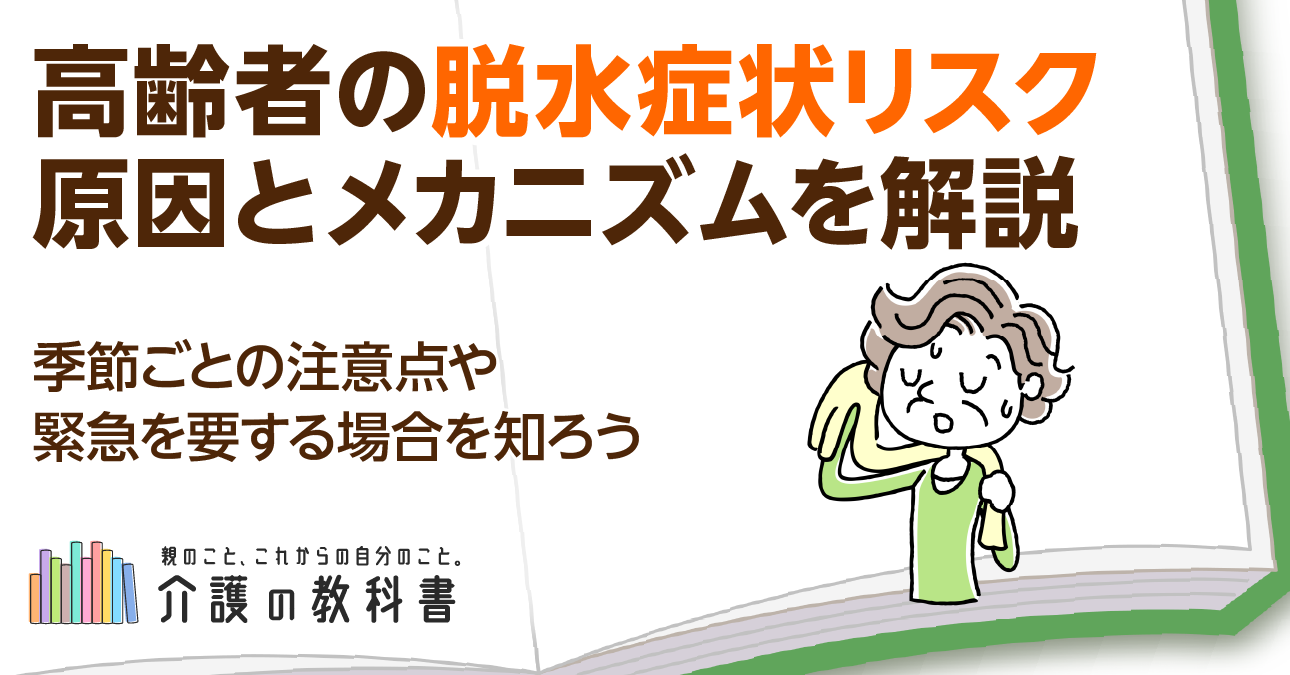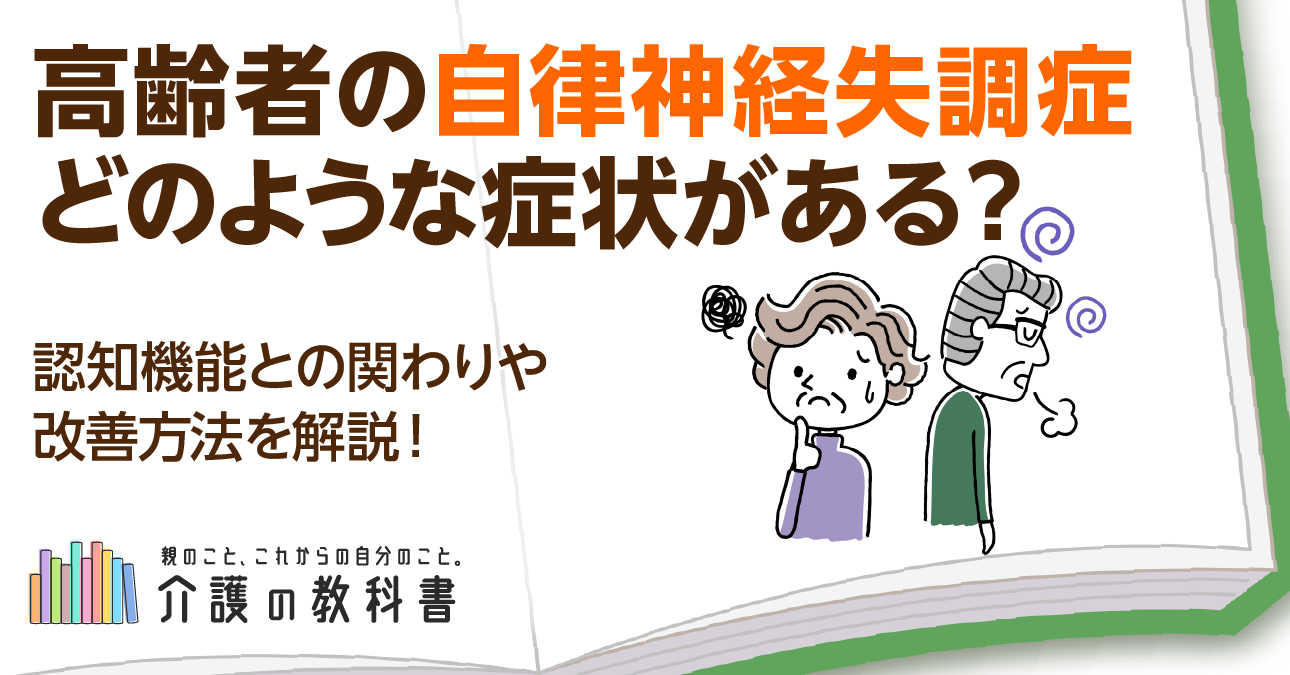皆さんは、日々の暮らしの中でご自身の幸せを感じられることはありますか?
幸せと感じることは人それぞれ異なるのが当たり前なのかもしれませんが、世界では何が人の幸せにあたるのかの研究が進められています。
国連が2022年3月に発表した「世界幸福度ランキング2022」において、日本の順位は54位と、先進諸国の中で最下位に位置していることがわかりました。
この結果を詳しく見ると「人生の選択の自由度」と「他者への寛容さ」の数値が目立って低く、そのほか「一人当たりの国内総生産(GDP)」「社会的支援」「健康寿命」に関しては、ランキング上位国とさほど大差がありませんでした。
今回はこうした幸せについて、エビデンスと取り組み事例をもとに考えていきたいと思います。
高齢者の幸福度を示す「つながり」
皆さんはどんなときに幸せを感じるでしょうか? 一般的には次のようなことが幸せの要素と考えられます。
- 家族や親しい友人と良好な関係が築けていること
- 犯罪や自然災害から身を守ることができる安心・安全な環境があること
- 地域住民同士が(プライバシーにも配慮した)適度な距離感を持ちながらも交流があり、コミュニティが形成されている
- 学校や病院、スーパーなど生活に必要な施設がある
では、高齢の方はどのようなことを幸せと感じるのでしょうか?
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所は『令和2年度高齢期の幸福度に関する報告書』を公表しています。
この調査は、京都府亀岡市において高齢者の福祉やその増進を行っていくため、2016年度から2018年度までの3年間にわたって、70歳以上の自立している高齢者2,680人と、要支援高齢者に対して「幸福感調査」を実施。調査項目には、次のような指標が用いられています。
- 主観的健康感
- 精神的健康感(幸福感)WHO-5-J
- 厚生労働省 基本チェックリスト
これらに加えて、聞き取りアンケートなどを行った日本国内でも非常にめずらしい調査となっています。
この調査内容からは、新型コロナウイルスの流行による活動・行動の自粛が、高齢者の要介護リスクを増加させており、また幸福感の低下につながる可能性があると推測されています。
さらに、日中の過ごし方では、次のようなことをしている人の方が幸福感が高いことも報告されています。
- 収入のある仕事
- ボランティア
- 田畑の仕事
- 孫の世話
- 運動
- 学習・教養
このように社会とつながりを持てる活動が、要介護リスクの減少や幸福感の向上につながるとしています。

また、2019年度では幸福感の悪化要因だった「介護」が、2020年度では幸福感の促進要因になっているということも注目すべきポイントです。
同報告書では、新型コロナウイルスの流行によるさまざまな社会活動の制限により、社会とのつながりが薄くなる状況が多くあったと指摘。介護を行うという行為が他者に対しての重要な役割をできることが、心身の健康や幸福感に繋がっていたと推測されています。
このように、幸せとは個人で感じるものではありますが、幸福感を高めることは個人ではなく、さまざまな人や社会とのつながりの中で培われるものと推測することができます。
多様に広がる地域活動
ただ、難しいのは地域や社会とのつながりをどうやって構築していくかという点です。
現在、70代以上の男性は定年まで就労されていることが多く、なかなか地域でのつながりを構築することが難しい場合もあります。
その世代は専業で主婦をされている方が多い時代だったので、女性は地域活動や、近隣のスーパーなど、さまざまな場所において近隣との交流がされていて、男性よりもつながりが深いと感じます。
ただ、現在30代ほどの方だと夫婦共働きなどの家庭も多く、この世代が高齢化すると、また別の課題が生まれるのかもしれません。

時代によって違いはあるかと思いますが、今まで地域とつながりを持ってこなかった高齢者の方がどうやって地域とつながっていくか、私の働く町田市での現在を例にとってご紹介させていただきます。
介護予防支援を目的に創設された有償ボランティア制度なども一つの方法でしょう(第117回参照)。この制度は、ボランティアを行うことにより、その活動を単位としてポイントを貯めて商品券などと引き換えができます。最終的に商品券に引き換えができるので、自身のやりがいにもつながります。
また、ボランティア活動を行うにあたり、社会福祉協議会や受入れ機関などの方ともつながっていきます。その中で自分自身が得意とする分野での活動になるので幸福度は高まりやすいのではないでしょうか。
ボランティア活動以外でも地域にはさまざまな活動があります。
例えば、町田市では65歳以上の高齢者向けに、各地域の社会資源をまとめた資料を冊子にして案内しています。
この冊子は、地域にある「通いの場」(介護予防につながるグループ・施設)や生活の役に立つ団体などの情報を、一覧にして紹介しています。
図書館や生涯学習センターをはじめとした各地で活動が行われているので、ご自身で一から探すとなると非常に手間がかかってしまうことも。ですが、この冊子をうまく活用すれば、さまざまな出会いにつながるのです。それをきっかけに、高齢者の暮らしが、さらにいきいきとしたものになることを目標としています。
また、包括支援センターの生活支援コーディネーターが情報を更新していますので行ってみたらもう活動していないなんてこともありません。
各取り組みについてもおおむね把握しているので、相談した際にご自身に合う、合わないなどアドバイスもしてくれます。
直接行くのは気が引けるという方は、地域の包括支援センターや市区町村の担当窓口などに相談してみるのも、地域とつながる一つのきっかけになるのではないでしょうか。
日本は諸外国に類を見ない速度で高齢化が進んでいます。
内閣府が発表した2022年版高齢社会白書によると、日本における65歳以上の人口は現在3,621万人余りで、総人口の28.9%を占めています。この数は、2042年には3,935万人でピークに達することが見込まれています。
その中で、自身の幸福度を高めていくためには地域や社会とつながり、関係を築いていくことが必要ではないかと思います。