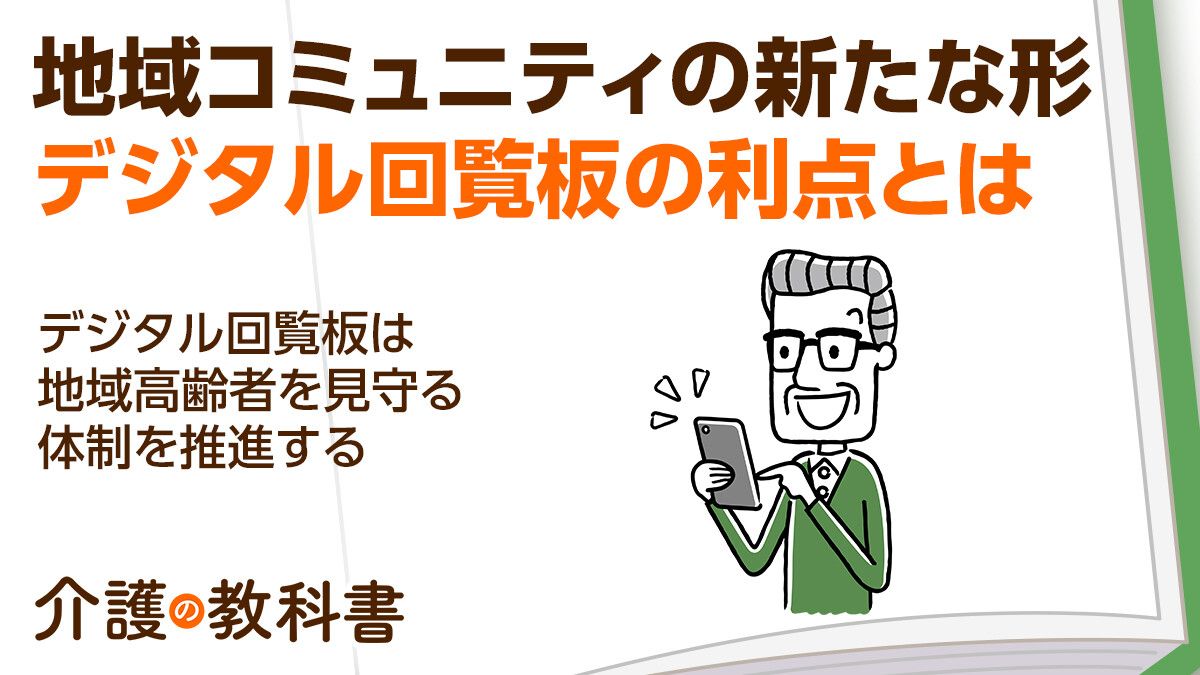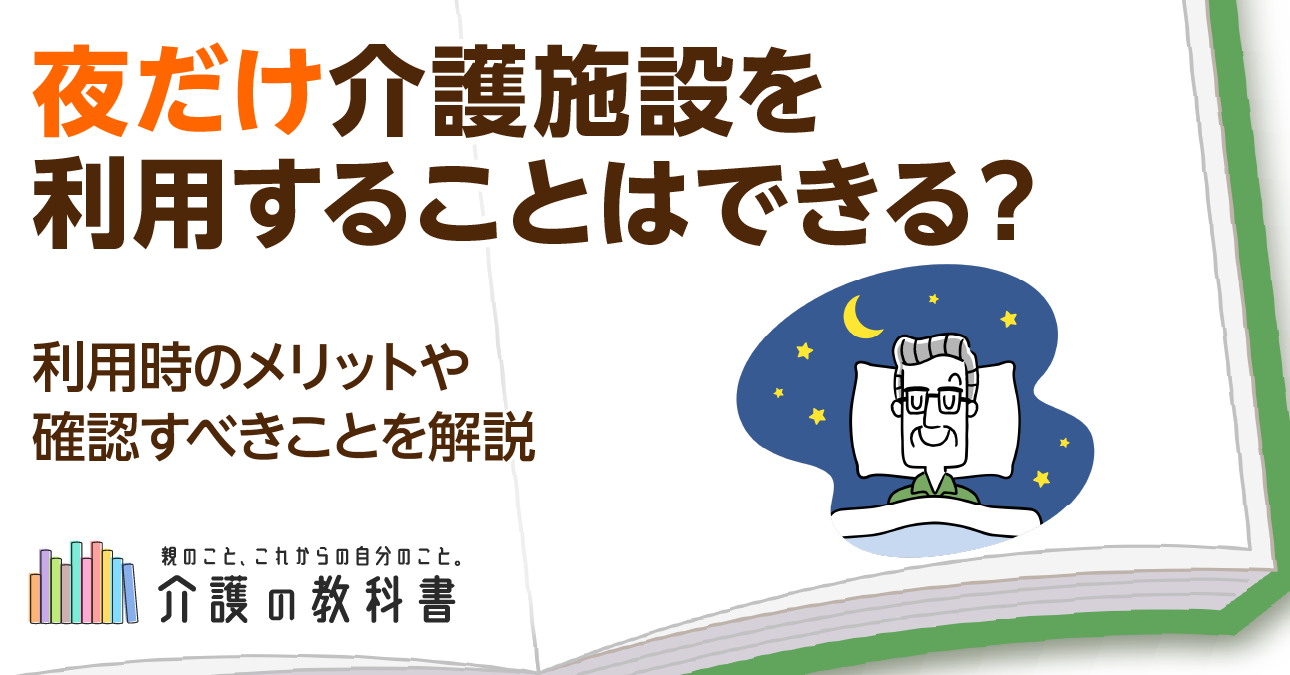みなさんは、デジタル回覧板をご存知でしょうか?文字通り、従来の回覧板をデジタル化したもので、地域の情報を伝えるツールです。
町田市では、2022年9月から東京都、小田急電鉄株式会社と連携する実証事業として、デジタル町内会「いちのいち」がスタートしました。東京都では町内会・自治会運営の効率化や未加入者の加入促進に向け、この取り組みを推進しています。
今回はこのデジタル回覧板について、町田市の事例を交えて考えていきます。
「いちのいち」の3つの機能
皆さんは町内会や自治会、回覧板と聞いて何を思い浮かべますか?
馴染みのある方から、馴染みもなく見たこともない方までいるかと思います。
私自身は住まいのマンションの自治会担当を務めたことがあり、自治会での毎月の清掃活動や年末年始の防犯見回り、回覧板をマンションの各階ごとに管理したりチラシについて仕分けしたりと手間がかかった記憶があります。良い経験でもありましたが、普段の仕事に加えてのことだったので、大変だったなあという印象を持っています。
町田市では、そんな大変な作業を効率化していく取り組みとして、デジタル町内会「いちのいち」を導入しました。
これまで紙媒体で行っていた地域の回覧や市からの町内会・自治会向け送付物を電子化し、スマートフォンなどで閲覧できるサービスを備えており、デジタル回覧板としての機能を備えています。
主な機能には次の3点があります。
- 1.回覧情報などの閲覧
- 市からの回覧の確認や町内会・自治会情報の投稿、閲覧ができる
- 2.コミュニティ
- 町内会・自治会内の班やサークルのグループをつくれる
- 3.カレンダー
- 町内会・自治会のイベント情報などをカレンダーで確認できる
今回は、その機能の中でも、特に①に注目したいと思います。
デジタル活用で地域のつながりをつくる試み
私自身でも調べていく中で、なぜデジタルなのか?という疑問が生まれ、今回担当の方からお話をお伺いしました。
その前に、町田市の町内会・自治会の加入率(2022年8月)についてみてみましょう。
| 年 | 加入率(%) |
|---|---|
| 2004年 | 60.2 |
| 2020年 | 50.3 |
| 2021年 | 48.9 |
| 2022年 | 47.6 |
統計が確認できる2004年は60%近い方が加入していましたが、2020年までに約10%下降し、2021年以降50%を下回っています。加入率が減少しているのは町田市だけではなく東京都、全国的にも同様です。
町田市内全体に311団体あり、内訳は以下の通りです。
- 町内会・町会:85団体
- 自治会:188団体
- その他:38団体
こうした団体の中でも構成される世帯が均一ではなく、加入世帯数が1,000世帯以上の団体は19団体。一方、50世帯未満の団体は41団体あり、一番少ない団体は6世帯と、大きいものから小さいものまで千差万別です。
町内会や自治会は、「地域でのつながりを大切にしながら、住民同士の相互扶助の理念を念頭に、その地域に住む住民同士が助け合い協力し合って、住みよい地域社会をつくる」ことを目的として自主的に組織された団体です。
こうした団体は、地域共生社会や地域包括ケアシステムにも大きく影響を及ぼす存在です。町田市での地域包括ケアシステムの推進に向け、今後強化すべき取り組みでも町内会・自治会などの地域資源との連携強化が挙げられており、その力に期待が寄せられています。

しかし、この数字だけ見ると地域のコミュニティとしての力が徐々に低下しているように感じます。
さらに、新型コロナウイルスの感染拡大が追い打ちをかけました。このウイルスが一番もたらした災いは、人と人とのつながりを断ってしまったことではないでしょうか。
今回紹介している「いちのいち」も、まさに新型コロナウイルスの感染拡大が一つのきっかけでした。町内会・自治会活動が制限され、また感染防止対策として、市からの回覧物についても、対面での接触や回覧物の仕分け作業時に、密になる状況などを避けなければならなくなりました。
また、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、会員の町内会・自治会離れが進み、町内会・自治会加入率が加速度的に減少しています。
その中で、新たな選択肢として、町内会・自治会未加入の方も参加できる仕組みとして、誕生したのが「いちのいち」です。
町内会・自治会情報に触れていない未加入者と町内会・自治会との接点を増やし、そのうえで町内会・自治会への加入や、地域コミュニティの活性化につなげていくことを目的にしています。
新型コロナウイルスで断ち切られたつながりを、デジタルを活用することで、地域に住む多様な方が選択してコミュニティとつながっていけるツールでもあり、この点が今までとは大きな違いです。これまでリアルでつながるしかなかった選択肢を増やすのではないかと思います。
地域住民や支援者もメリットが大きい
もう一つ特徴的なのは、町内会・自治会に加入していなくてもアクセスできるという点です。これまでの回覧板などでは、対象者はあくまで自治会・町内会の加入者でした。
それが誰でもアクセスできるようになったことで、地域の情報を知る機会が増えます(一部閲覧制限はあり)。そのため、これから町内会・自治会に加入しようかなと考える一つのきっかけにもなるでしょう。
この取り組みは、東京都の実証実験ということもあって、町田市では2022年10月現在約110の団体が加入。全体の約3分の1が参加していることになり、想像以上の反響がある状況です。
約2ヵ月でこの数なので、町内会・自治会の皆さんが待ち望んでいた部分と、行政の方の説明会の実施をはじめとした手厚い説明やサポートの結果だと感じています。
デジタルのプラットホームは行政が整備しますが、その運用の主役はあくまでも住民です。
デジタルに移行すると、一見高齢者やデジタルに慣れていない方が取り残されてしまうように思いがちですが、すべての紙が全面的にデジタルになるわけではなく、伝える媒体・伝える選択肢が増えたことは、地域においても喜ばしいことだと思います。
地域の情報や、防災情報などを伝える媒体は多岐にわたります。ときには紙、ときにはデジタル、あるいはその両者でもいいわけです。
私は、この取り組みが進んでいく中で、認知症の方の行方がわからなくなってしまったときなどに活用できるのではないかと個人的に考えています。
もちろん個人情報の取り扱いには十分に配慮したうえで、デジタル町内会「いちのいち」で情報発信を行い、地域の方のお力を借りて早期発見にもつなげられるのではないかと思います。
選択肢が増えたことは、誰にとってもメリットになると考えます。
新型コロナウイルスのような誰も想像していなかった事態で、生活は様変わりしました。これから、もしかしたら私たちの想定できない出来事で生活は様変わりする可能性があります。
そんな不確定な中ですが、人と人とのつながりをデジタルの側面からサポートできるような仕組みは大切ではないでしょうか。そんなツールをうまく運用できれば、地域のコミュニティをより強化していくことにもなります。デジタル町内会「いちのいち」は、地域の住民だけでなく、私たちのような支援者も役立つツールになる可能性を含んでいます。今後も注視していきたいと思っています。