静岡県浜松市は、市民の「健康寿命」や「幸福度」ランキングで何度も1位を獲得している自治体だ。2019年に「デジタルファースト宣言」をした後、「官民連携」をキーワードに、オンライン診療の実証実験をはじめとするデジタル化に関するプロジェクトを進めている。今回は鈴木康友市長に「まちのデジタル化による健康増進」についてお聞きした。
監修/みんなの介護
【ビジョナリー・鈴木康友】
「デジタルファースト宣言」で
デジタル活用による地域の活性化を

「人口減少・少子高齢化社会の到来やインフラの老朽化をはじめとした社会課題が深刻化する中、AI・ICT等先端技術やデータ活用などデジタルの力を最大限に活かし、都市づくりや市民サービスの提供、自治体運営に『デジタルファースト』で取り組み、持続可能な都市づくりを推進することを宣言します」
これが2019年10月に発表した浜松市の「デジタルファースト宣言」です。 「都市づくり」「市民サービス」「自治体運営」を3つの柱に、デジタル化を進めています。このうちの都市づくりにおいては、今年度策定中の「デジタル・スマートシティ構想」を中心に据えています。
デジタル・スマートシティ構想とは、データや先端技術を最大限に活かして、市民QOL(生活の質)の向上や産業の活性化、都市機能の高度化を目指すものです。デジタルの活用によって健康寿命の延伸や、交通の最適化、中小企業の生産性向上、農業への先端技術の導入を実現させていく予定です。
「デジタル・スマートシティ推進事業本部」を新設
浜松市では、デジタル化の推進のため、2019年4月に司令塔となる「デジタル・スマートシティ推進事業本部」を設置した。あわせて企業やNPO法人などが参画する推進組織「官民連携プラットフォーム」も発足。事業本部と分野間の連携や官民連携プロジェクトの促進などを行っている。2021年1月現在でパートナー会員11団体、一般会員103団体が参画している。
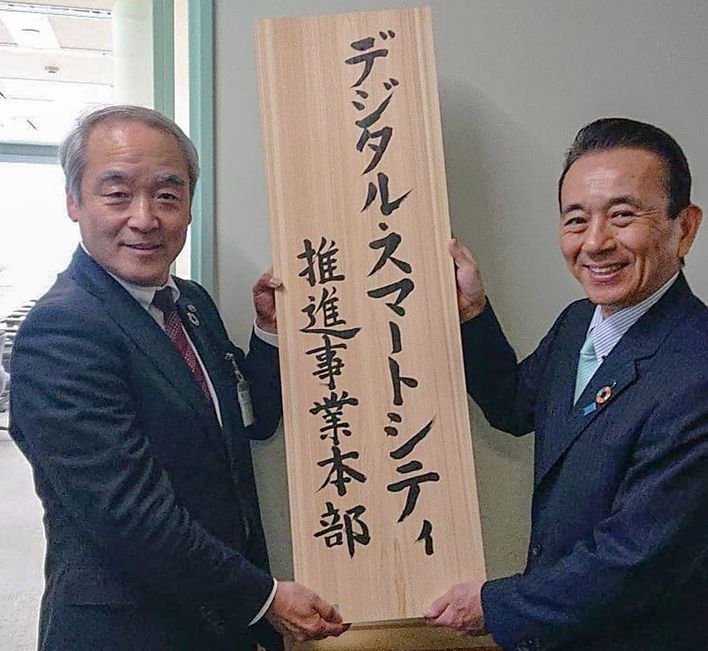
デジタル化の推進が検討されているのは、主に以下の9分野だ。
具体的には、「『予防・健幸都市 浜松』の実現に向けた官民連携」「ビッグデータを利用した生活習慣病等の予防・改善」「介護ロボットなどの活用による介護従事者の負担軽減」「AI などを活用した健診(検診)の受診率向上」などが挙がっている。
すでに市内では、民間の情報通信技術(ICT)などを活用した複数の実証実験プロジェクトが分野ごとに進行中だ。
緊急時に対応できる医療・介護サービスを開始
デジタル・スマートシティ推進事業本部が取り組む9分野のうち「健康・医療・福祉」には、後述する「浜松ウエルネスプロジェクト」のほか、災害や健康対策も盛り込まれている。
現在は以下のような取り組みが実施されている。
- LINE WORKSを使った災害時や新型コロナウイルス感染症対策に関する行政、医療関係団体、医療機関のネットワーク構築
- 避難所や医療機関の被災状況や、医療的ケア児者等の安否を収集、集計するためのクラウド型安否確認サービスの構築
- 認知症状により自宅に帰れず所在不明となった際に、あらかじめ登録した見守り協力者に情報をメール配信し捜索協力を依頼する「オレンジメール」
- ひとり暮らし高齢者等が緊急時にボタンひとつで自動的にコールセンターに連絡できる、緊急通報装置のレンタル
これらによって、緊急時にいち早く対応できる体制を整えている。
「春野医療 MaaSプロジェクト」が
医療や民間との連携によって実現した

デジタル・スマートシティ推進事業本部では、2020年度にオンライン診療の実証実験「春野医療 MaaSプロジェクト」を実施しました。
「MaaS(Mobility as a Service)」とは、次世代交通サービスのことです。移動診療車を使い、看護師が中山間地域である天竜区春野町に住む高齢者を訪問。情報通信技術(ICT)機器を活用して、診療所の医師が遠隔診療を行います。
またオンラインによる服薬指導、ドローンなどを活用した薬剤配送も実施しています。
この取り組みは、経済産業省のプロジェクトの指定を受け、地元の医師会やドラッグストアなどとの連携によって実現しました。
診療に使う端末機器は訪問する看護師が操作するので、高齢者が扱えない場合も問題ありません。オンライン診療は、過疎化と高齢化が急速に進む地域での生活の維持にも効果が期待されています。
看護師を乗せた移動診療車が自宅を訪問
「春野医療 MaaSプロジェクト」の実証実験が行われたのは、2020年10月下旬から2021年1月中旬までの3ヵ月間。看護師を乗せた移動診療車が、地域に住む10人の高齢者の自宅を訪問した。車内で血圧などを計測し、データを基にかかりつけの医師がオンラインで診断する。

服薬指導・薬剤配送については、以下の2パターンで実施された。
- 診療所の医師がオンラインによる服薬指導を行い、薬剤をドローンで配送
- 薬局の薬剤師がオンラインによる服薬指導を行い、薬局より自動車で配送
実験が行われた春野地区は、JR浜松駅から車で1時間ほどの場所にある。高齢化率は45.9%と高めだ。
運転免許証を返納するなどして移動が困難となる高齢者が増えているのは、同市の春野地区だけではない。全国的に買い物や通院が困難になる事態が予想されている。こうした中で、看護師のサポートによるオンライン診療・オンライン服薬指導や、薬剤のドローン配送は、今後も重要な役割を果たしそうだ。

看護師のサポートによってデジタル格差をなくす
社会のデジタル化は進んでいるが、高齢者を中心にタブレット端末やスマートフォンを扱えない層は少なくない。このような「デジタル格差」に対して、「春野医療 MaaSプロジェクト」のように、デジタル機器操作をサポートする人材を配置することで対応できる。
鈴木市長は、「各部局には、いろいろなことを『自分ごと』として捉えて対応するようにと伝えています」と話す。自分のこととして課題に取り組むことで、多くのアイデアが生まれる。
さらに官民連携のプロジェクトにおいて、行政と民間企業の間の「風通しのよさ」は不可欠だ。
「官民からいろいろな立場の人が関わるので、司令塔のような役割の『デジタル・スマートシティ推進事業本部』のような部署のほか、部局横断的なプロジェクトチーム(PT)を設置するなど連絡体制をとりまとめています」と鈴木市長。コーディネート部門がうまく機能している好例と言える。
「やらまいか精神」でまずはやってみる。
それが幸せに暮らせるまちづくりの秘訣に

浜松市では、2020年度に「浜松ウエルネスプロジェクト」をスタートしました。
これは、医療機関や大学・研究機関、地域内外の企業などの皆さんとともに、浜松市民の介護予防や健康づくりに向け、さまざまな社会実証事業や官民連携によるヘルスケア事業を推進していく新たな官民連携プロジェクトです。
実は、浜松市には、農業から工業まで自慢できるものがたくさんあります。全国ランキングからわかるように、市民の皆さんの多くが健康で幸せであることは特に自慢です。例えば「大都市別の健康寿命(厚生労働科学研究班調査)」では、2010年、2013年、2016年において男女とも全国トップとなりました。以前から、浜松市は「健康都市」として知られているのです。
さらに2018年の「政令指定都市幸福度ランキング(日本総合研究所)」でも第1位をいただきました。これらは、農業から、工業、サービス業まで産業が盛んで経済がうまく機能していることや、気候が温暖で過ごしやすいことなどが理由として考えられます。
浜松市民の「やらまいか精神」も特長です。やらまいか、とは「まずはやってみよう」という意味です。社会の変化のスピードが速く、価値観も多様化する中で、まずは小さく始めるスモールスタートやアジャイル(俊敏)型のまちづくりが求められます。これは「やらまいか精神」のDNAにつながるものです。
この「やらまいか精神」で市政に取り組んできた結果、市民の生活の質や幸福度が高まり、健康寿命が延びたとも言えるのです。浜松ウエルネスプロジェクトは、こうした強みをさらに伸ばしていくために始めたものになります。
「浜松ウエルネスプロジェクト」が始動
「浜松ウエルネスプロジェクト」は、「予防・健幸都市」という人生100年時代を見据えた新たな都市像を実現するための官民連携プロジェクトで、「浜松ウエルネス推進協議会」と「浜松ウエルネス・ラボ」という2つのプラットフォームをエンジンに、さまざまな社会実証事業やヘルスケア事業を展開している。

浜松ウエルネス推進協議会には、現在、地域の医療機関や大学・研究機関、金融機関、関連団体、地域企業など、約120社・団体が参画している。 また、経済産業省の「次世代ヘルスケア産業協議会」の地域版協議会にも位置づけられている。
事業としては、官民が連携し、生活習慣病予防や健康に関心の低い青壮年期の健診・検診受診率向上、地域企業の健康経営などを進めるほか、予防、運動、衣・食・住などに関わる民間企業のウエルネス・ヘルスケアサービスの創出や拡大などを推進、支援している。
他方、「浜松ウエルネス・ラボ」には、地域外の大手企業7社と地域の医療機関や大学が参画している。事業としては、市民の生活習慣病予防や認知機能の改善・介護予防、健康増進等に寄与する「浜松発」のさまざまな官民連携社会実証事業を行い、データやエビデンスを取得して蓄積している。また、医療機関が保有する大量の健診データの解析も行い、「大都市別健康寿命」第1位の所以などを明らかにしていく。
民間のアイデアでさらなるデジタル化を促進
浜松ウエルネス・ラボの取り組みとしては、2020年9月から、キリンホールディングスが認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)の方を対象とした健康食品摂取による認知機能改善効果の検証研究を開始している。
同年11月からは、SOMPOひまわり生命が、糖尿病予備群の方を対象に、デジタルを活用した血糖コントロール習慣の定着を検証。
さらに同時期から、キリンホールディングスとファンケルは、市民が抱えるストレス状態を「唾液」「嗅覚」「自律神経」などで科学的に計測する健康調査を実施している。

同年12月からは、第一生命保険が、健康増進アプリを活用した運動や食習慣の改善に取り組んでいる。
今後も参加各社がさまざまな官民連携社会実証事業を予定している。
鈴木市長は、「デジタル・スマートシティが目指す『市民のQOLの向上』に、ウエルネス分野が果たす役割は大きいと考えています」と意欲をみせる。 浜松市の行政と企業のさまざまなアイデアとのコラボレーションは、官民連携のモデルケースとしても参考になる取り組みだ。
※2021年1月13日取材時点の情報です



 この記事の
この記事の