撮影当時の関口監督の心境は?
母のことで頭がいっぱいだった私は、先人の母に対する適切な距離感にハッとさせられました
介護生活で大切にしていたことは、「普通の日常を送ること」でした。
当時、息子の先人(さきと)は小学5年生で、毎年シドニーの学校が夏休みになる12月に帰国して、5~6週間母と私と時間を過ごした後、シドニーの父親の元へ戻るというパターンでした。
動画の冒頭は、姪っ子も出てきますが、先人も姪っ子も良い意味で母のことを特別気にせず、当たり前のように受け入れていますよね。
一方、私は、母が大好物のカレーうどんを食べないことを気にしている!先人は、そんな私をちらりと見て上手に無視しています。
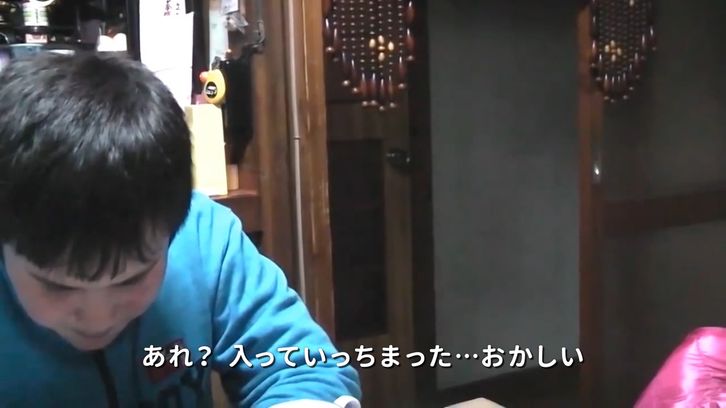
介護生活では、介護する側が、介護される側にフォーカスし過ぎてしまうことがありますよね。
このときの私もそうでした。母のことで頭がいっぱい。
しかし、先人の母に対する適切な距離感に「ハッ」とさせられて、改めて、日常生活の中で母とどう向き合ったら良いのか考えることができました。
そういった意味でも、「知らず知らずのうちに、先人に助けられていたんだなあ」と思います。
そのとき関口監督がとった行動は?
自室に閉じこもるようになった母を先人に任せていました。これも適材適所です
先人がシドニーから帰国すると、私は「娘」だけではなくて、「母」にもなります。
先人は当時、ピアノとテニスをやっていました。
昼間に地元のテニスコートで個人レッスンを受けていて、私もときどき練習を見に行きました。
この母親としての時間が、私の息抜きにもなっていたと思います。
そして、自室に閉じこもりがちな母のことは、先人に任せていました。
「小学生に母の心のケアを任せるなんて!」と思いますよね?しかし、これも適材適所です。
先人もごく普通に、母と一緒の時間をつくってくれていたと思います。
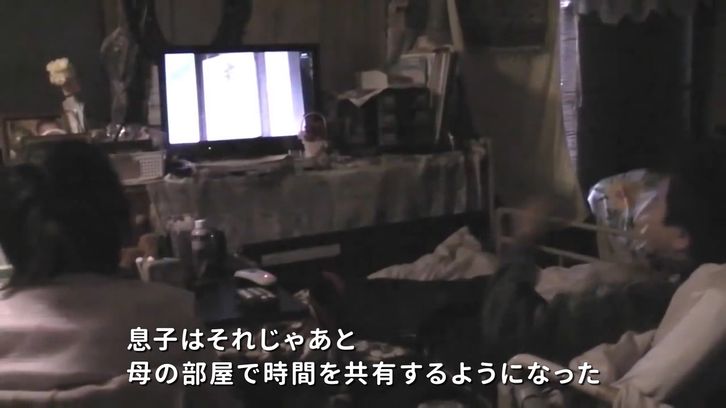
先人が、頻繁に機嫌が変わる母を動揺せずに受け入れられたのは、母からの揺るぎない愛を感じていたからでしょう。
また、私の助けになりたいという健気な気持ちもあったと思います。
母のことを先人に任せて、私はひたすらカメラを回していました。
関口監督から読者へ伝えたいメッセージは?
介護の息抜きは、上手に、しかも罪悪感を感じないようにしましょう!
飛行機に乗ったとき、乗務員から緊急の際の脱出方法の説明がありますよね(最近はビデオですが)。
その中で語られるのは、緊急の場合は、まず自分ファースト。次に子どもなど、一緒にいる人の手助けをする。
これは介護の基本でもあると思います。
まずは介護する側が健康でいられるように、自分の心身をチェックすることが、介護生活を続けていくうえでは必要だと思います。
例えば、お天気のいい日に外に出て散歩する。単に体を動かすだけでなく、自然に触れることが心の栄養にもなるのではないでしょうか。
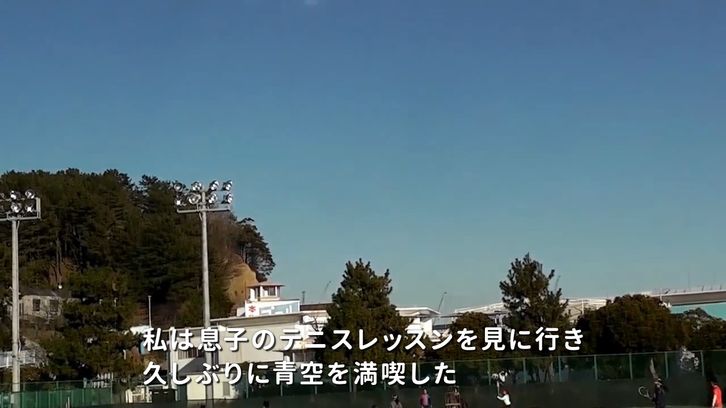
ただし、「自分ファースト」が行き過ぎてしまうと、ネグレクトになる可能性もあるので要注意です。
この境界線を見極めるのは、本当に難しいと思います。
私は、自分の気持ちや行動を客観的にとらえると同時に、母にも目を向けることを意識してきました。
自分ファーストと同時に母ファーストも意識し、<今日の自分>と<今日の母>を時差なく捉える。
そして<今日の自分>が<今日の母>に対応できそうもないと思ったらケアマネや、訪問看護師など、すぐ外に助けを求めました。
この判断は、母の介護期間が長くなるにつれてスピーディになっていきましたよ。
ネグレクトは、虐待です。
それを肝に命じ、母にも関心を向けながらケアをしてきました。



