撮影当時の関口監督の心境は?
介護は一人ではできないし、やるべきではない。抱え込まず、オープンにして行動する
私は、「毎アル」シリーズ第1作である「毎日がアルツハイマー」でも描かれているように、母の介護に関して知らないことやわからないことがあれば、すぐに地元の地域包括センターに助けを求めました。
当時からすでに、介護は一人ではできないし、やるべきではないとぼんやりと思っていたんですね。
母が一筋縄でいかない人物であることと、私が何事も一人で抱え込まず、オープンにして行動する性格である、というコンビネーションもあったと思います。
知らないことに対して聞いたり助けを求めたりすることは、ちっとも恥ずかしいことではない。
これは、私の人生におけるスタンスです。
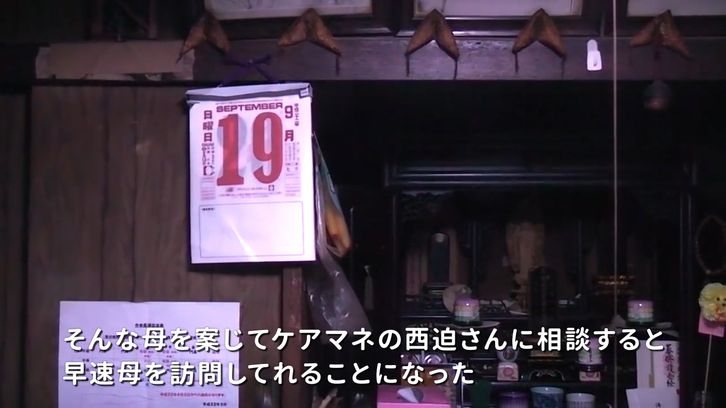
一方、母は一人で最後までやることにこだわるタイプで、わからないことや知らないことを自身で認めることはかなり厳しい性格です。
母と娘は、正反対ですよね。
この連載で書き続けていますが、介護される側の人の理解と同時に、介護をする側、つまり自身の性格も冷静に分析して理解していることが重要です。
この双方の性格の理解が基盤になってはじめて、辛くならない介護を考案することができると考えています。
そのとき関口監督がとった行動は?
感情的になる母は、映画のシーンとして最高の<絵>になる!だから、普段なら聞きづらいことを第三者の前で聞く
この動画でケアマネージャーの西迫さんを自宅に呼んだのは、以下の理由からです。
- ①西迫さんに母の現況を見てもらい、第三者の意見を聞く。
- ②娘の言うことは一切聞かない母なので、西迫さんから外出の提案をしてもらう。
- ③西迫さんの前で、あえて母に聞きづらい質問をしてみる。
つまり、この動画の西迫さんの訪問は、西迫さんご本人は知らずとも、いろいろとミッションがあったんですね。
ここで思いがけず私自身が得心したことがありました。
それは、西迫さんの<白々しいお世辞>のような褒め言葉が、母には効くということ。
これは、大きな収穫でした。

私は<西迫エフェクト>を学習し、この日から、母のことをもっと多く褒めるようにしました。
認知症初期の母は、いろいろとできていたことが記憶の混乱からできなくなり、内心は自信喪失になっていたのではないか。
だから、褒められればうれしいし、逆に自己防衛として身内の私に対しては、攻撃的になるのではないか。
そして何より、この感情むき出しの母が、映画のシーンとして最高の<絵>になる!
だからこそ私は、第三者のいる前で聞きづらいことを聞いてみようと思いました。
一体、母はどんな答えをするのか…。
私は、自分でカメラを回しているときは、常に映画監督です。
映画ができるかどうかは、どれだけ面白いシーンが撮れるかにかかってきますからね(笑)。
関口監督から読者へ伝えたいメッセージは?
相性の良い介護スタッフこそが鍵。問題を抱えたときこそ、自身の感情は脇に置き、理詰めで考える
在宅介護は、最初からスムーズにできれば何の問題もありません。
しかし、大概は何らかの問題を抱えることになると思います。
そのとき、どうするのか?
<ピンチはチャンス>と考えられるのか?
問題解決能力が自身になければ、どうすればいいのか?
私は自分自身の感情を脇に置き、理詰めで考えるようにします。
前回に書きましたが、もう1回!
<介護は愛ではなく理性でするもの>。
そして、自分自身が理性や理詰めで行動できないときこそ、介護保険につながっていることが大切で、介護の専門職と手を組んで<介護チーム>をつくることが必要です。
私はこの日の西迫さんと母の様子から、母と相性の良い介護スタッフこそが鍵だということを学びました。
介護スタッフ選びは、後日<オーディション>として進化していき、どんなときにも母と相性の良い人を選ぶという明確な基準を持つようになりました。



