本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
泉さんは、4月30日で任期満了(※)となります。まずは、「政治家引退後」のビジョンについて伺えますか。
※ 取材日:2月25日
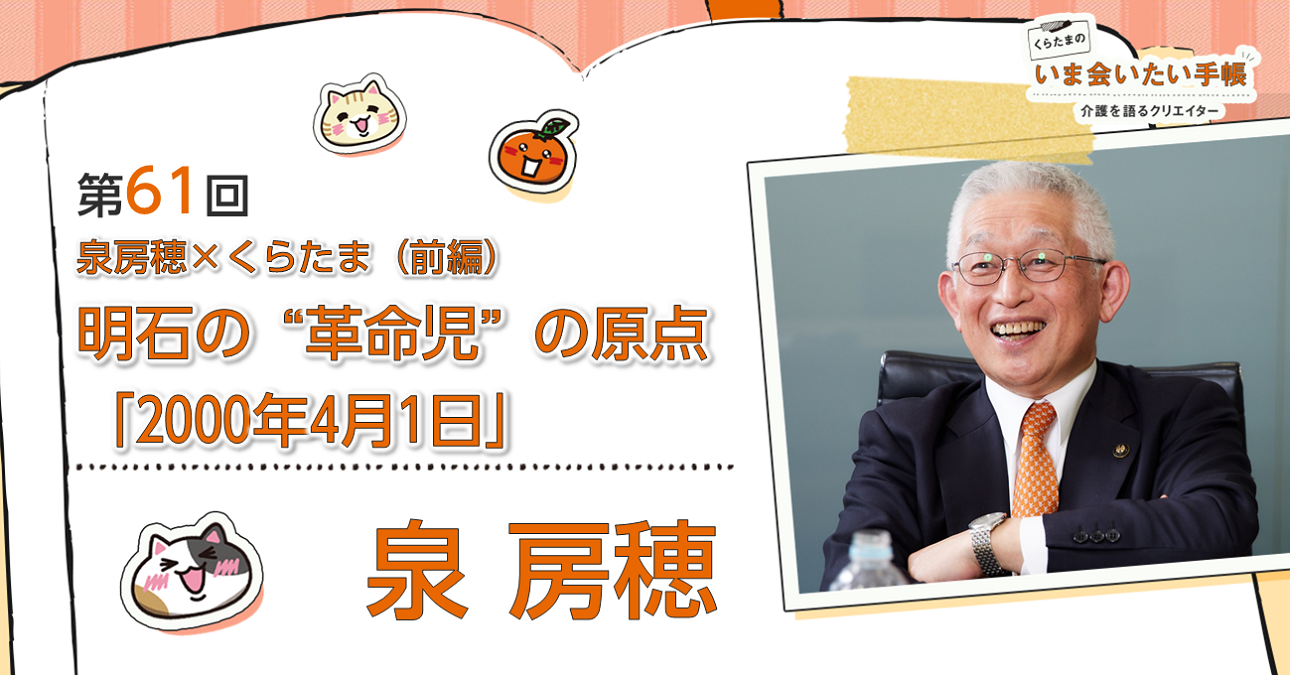
2023年4月30日。賛否両論を巻き起こしてきた泉房穂氏の明石市長としての任期が終わりました。10歳で社会への復讐を誓い、学生運動で目指した“革命”は、“美しい制度”と語る民主主義によって次々と実現。市長になる前から「市民のための政治」を誓っていた泉氏は、批判や脅しを受けながらも、その信条を曲げませんでした。市民から愛された政治家・泉房穂市長の”まちづくりの信念”をくらたまが聞きました。
市民の側に立つ施策で「やさしいまちづくり」を“現実”とした泉氏。思い切った改革を推し進める泉氏の原動力とは……。貧しい家庭環境で味わった苦渋や反対勢力との軋轢、「全国初」の施策の裏側など、ページをめくるたびに「人間・泉房穂氏」への理解が深まります。
 くらたま
くらたま本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
泉さんは、4月30日で任期満了(※)となります。まずは、「政治家引退後」のビジョンについて伺えますか。
※ 取材日:2月25日
 泉
泉こちらこそ、よろしくお願いいたします。しゃべり過ぎてしまうときがあったら、言ってください。
任期満了後の「選択肢」はいくつかあります。ただ、まずは国の政治が「ろくでもない」ので、国の政治をひっくり返すことは「せなあかん」と思っています。

 くらたま
くらたま早速(笑)。
 泉
泉幼い頃は、フランス革命のような「革命」を志していました。そんな自分が、革命に挫折して選挙に出ているんです。だから、選挙のような“民主主義制度”で社会を変えるなんて、忸怩たる思いも少なからずありました。
 くらたま
くらたま選挙は「妥協」なんだ。
 泉
泉民主主義制度なんて「やってられへん」から。自分たちの国は自分たちでつくっていくものです。特権階級のものではありません。
でも、日本は長らく自分たちの社会になっていないわけです。要するに、民衆が勝った経験がない。フランスにしてもアメリカにしても、自分たちで社会をつくってきているのに……。
 くらたま
くらたまそうですね。
 泉
泉鎌倉幕府や江戸幕府はもちろん、明治維新さえも「クーデター」です。だから、私は日本で初めての「革命」をやろうと思って、学生運動に没頭していたんです。負けましたがね。
 くらたま
くらたま「学生運動」が残っていた時代でしたか?
 泉
泉10年遅れの全共闘として、東大最後の全学ストライキを委員長としてやりました。機動隊とも対峙して。でも、予想どおり負けてしまい、責任を取ろうと退学届を出して明石に帰りました。
 くらたま
くらたま……どうなったんですか?
 泉
泉地元に帰って塾でも開こうと考えていたら、しばらくして敵の「親玉」から電話がかかってきました。「泉くん、みっともなくてもいい。帰ってきなさい」。「君にはまだ仕事がある。こんなところで終わっちゃいけない」と言われました。
 くらたま
くらたま敵の親玉はどなたですか?
 泉
泉当時の東大の学部長です。それで、「やむなく」東大に戻りました。
その後、社会から差別と貧困をなくしたくてNHKに入りました。でも、私が思い描いたような仕事はできず、やがてテレビ朝日へ。
ただ、そこでも、もどかしさを感じました。苦しんでいる方々の状況を伝えることはできても、解決のために、力を直接貸すことができなかったから……。
そんなとき、本屋で石井紘基さんの本を手にして、「大感動」したんです。
まだ20才だった私は、50才近くになりながらも、本気で世の中を変えるために立ち上がろうとしている人がいる事実に心からの感動を覚えました。そしてその感動そのままに手紙を送りました。 ~中略~ すると思いもよらず、すぐに返事がきました。そこにはなんと「お手紙ありがとう。ぜひ会って、話を聞かせてくれませんか」と書かれていたのです。驚くと同時に喜び勇んで、私は指定された喫茶店に出向きました。
(『社会の変え方』P40より引用)
 泉
泉そうして、石井さんの選挙を手伝うことになりました。私は、どうしても石井さんに選挙で当選してほしかったので、「テレ朝」を辞めて石井さんの応援に専念しました。 ……残念ながら結果は落選。そのときに石井さんから「君をこれ以上そばに置いておくわけにいかない。司法試験を受けて弁護士になれ」って言われたんです。
 くらたま
くらたま教育学部から司法試験ですか。
 泉
泉「君なら簡単に通るよ」と言われたんですけど、なかなか受からなくて……。「石井さんに完全に騙されたわ」と思っていました(笑)。そう言いながらも勉強を続けていったら、4年後、ようやく試験に合格できました。
でも、地元で弁護士になることを決めたとき「もう革命は無理やな」と。仕方ないから民主主義で生き抜こうと決意しました。市長になることに“狙い”を定めたんです。
 くらたま
くらたまそういった経緯だったんですね。
 泉
泉“妥協”の選挙ではあるけど、私の中では民主主義による革命のつもりでした。「有力者や政党を『全部』敵に回して勝つんだ」と誓っていましたから。

 くらたま
くらたまなるほど。市政にも革命への思いが表れていたのですね。
 泉
泉そう。でもね、市長選に出られること自体がありがたいんです。私のような人間が立候補できることは、歴史的に考えれば「すごいこと」です。金持ちでもなく、名家でもない私が、市長の立場に立てるわけだから。
おまけに、どんな「金持ち」も「貧乏人」も、等しく一票です。「こんな美しい制度、あれへんやん」と思いました。
「社会は自分たちが変えてもいいんだ」と考えられること自体も、昔ならありえなかったんです。
 くらたま
くらたま美しい制度という表現に泉さんの思いが込められていますね。
 泉
泉私は、20歳のときに経済学部から教育学部に転部したんですよ。そこで、ルソーの教育哲学に大きな影響を受けました。ルソーの思想は斬新だったんです、当時の社会背景を鑑みると。
17世紀後半のフランスは、絶対王政下にあったので国王の権力は揺るぎません。国王や貴族が華やかな生活を送る一方、民衆は貧しい生活を強いられていました。不平等な社会でも誰もが「社会は変えられない」と考えていたんです。そんな時代に「社会は民衆が変えてもいい」と発想の“大転換”をしたのがルソーです。
ちなみに、「子ども」という概念を発見したのもルソーです。それまでは子どもという概念はなく、全員「人」でした。中でも子どもは「中途半端な人」と考えられていたんです。
 くらたま
くらたま初めて知りました。
 泉
泉ルソーは学校の授業を1回も受けたことがないような人だったんです。当時は、今のように不登校に関する社会の寛容さもなかったので「どうかした人」だと見られていました。でも、固定観念に縛られていないから、発想が柔軟なんですよね。
女性や貧乏人、黒人の人権が軽んじられていた時代に、「それは違う」と唱えた。「東洋の日本人なる生き物やオランウータンにも権利はある」と主張した逸話が残っています。ちょっと行き過ぎた話ですが。
 くらたま
くらたまそれはそれとして、当時は革新的な発想だったんですね。
 泉
泉そう。私はルソーの思想に影響を受けているので、古い考え方や制度に縛られず「みんながハッピーになれるように変えていったらいい」と思ってきました。「ガラガラポンしたらええやん」という考えは、私の特徴のひとつだと思います。
 くらたま
くらたま明石市で子どものための政策に力を入れてこられた理由を改めて教えていただけますか。
 泉
泉「子ども」への取り組みばかりが目立っていますが、私が弁護士時代から力を入れていたのは、高齢者支援です。
 くらたま
くらたまそうなんですか!
 泉
泉話が遡りますが、明石で弁護士事務所を開設したのは、2000年4月1日のことです。私は、強い思い入れを持って、この日を開設の日に選びました。
 くらたま
くらたま介護保険制度がスタートした日ですね?
 泉
泉それだけではありません。成年後見制度がスタートした日でもあります。当時、介護保険と成年後見制度は、車における「両輪」だと言われていました。本人の判断力が低下している場合、誰かが介護サービスの利用手続きを支える必要が出てくるからです。
成年後見制度において、特に私が力を入れたのは「本人の意思の尊重」。相続のために高齢者のお金を残すのではなく、やりたいことのために使ってもらえるようにしました。
「メイク・ア・ウィッシュ」という難病の子どもの夢を叶える活動がありますが、私はその“高齢者版”をやりたかったんです。お年を召した方が亡くなる前に夢を叶える。ご本人の望みに合わせて、会いたい人に会ったり、行きたいところに行ってもらったり、もう一度美味しい物を食べてもらったり……。
そんな活動を、弁護士事務所で行っていました。この活動は「メイク・ア・ターミナル」と名付けられました。
 くらたま
くらたま4月1日が「やさしいまち明石」の原点でもあるんですね。
 泉
泉ええ。私は弁護士の中でも地域で1・2を争うぐらい後見人をしました。市長になった2011年時点でも、七人の後見人をしていたんです。五人のおばあちゃんの「息子がわり」と二人の子どもの「父親がわり」でした。
 くらたま
くらたまそうだったんですか。その後、その方々はどうなったんですか?
 泉
泉子どもたちは二人とも成人して“手”を離れました。五人のおばあちゃんは、みなさん亡くなられたので、私が骨を拾いました。
 くらたま
くらたまいつ頃から、そのような活動を?
 泉
泉2000年から家族全員で続けてきました。うちの子どもなんか、よう言ってましたもん。「パパ、うちの家っておばあちゃん何人おるの?たくさんいるね」って。
 くらたま
くらたま(笑)。やりとりが目に浮かびます。
 泉
泉当時、うちの子は、「孫」のような存在として「おばあちゃん」たちが入居する特養に行っていました。「おばあちゃん、長生きしてください」って文章を読んだことを覚えています。
 くらたま
くらたまほんとうのご家族みたい。
 泉
泉個人的にもそれほど高齢者支援に力を入れていましたから、明石市でも高齢者のための施策を打ち出しました。……ただ、言い訳をすると、「高齢者」への施策については介護保険の制度が「ガチガチ」で、明石市独自でやれることが少なかった。
反対に「子ども」は制度がなかったので、白紙のキャンパスに絵を描きやすかったんです。

 くらたま
くらたま「やさしいまちづくり」は、市長になる前から続けてこられたんですね。
 泉
泉47歳の市長選にそれまでの人生が「全部」入っています。例えば、1997年に私は弁護士になりましたが、自分の法律事務所の向いにNPOルームをつくって無料開放していたんです。
行政の代わりとなってNPOの団体を支援していました。不登校の子を支援する会や環境問題に取り組んでいる方々のNPOでした。会議室を提供し、一緒に印刷物の編集をして、配布もお手伝いしました。ポスティングも一緒にやりました。
そうやって市民活動支援を続けてきたわけです。だから、2011年に立候補したときには、たくさんの方々が集まってくれました。「ついに泉が立ち上がった!」という話なんですよ。小・中学校時代の友だちも「あいつ、子どものときから市長になりたいって言ってたけど、やっとそのときが来たか」って。
「つくり変える」ためには政党は邪魔なんです。業界の応援も「いらん」。市民のための政治が必要です。それを徹底したことが根付いていたんだと思います。
 くらたま
くらたま一貫した「闘い」なんだ。
 泉
泉18歳で東京に行ってからも、明石のことをずっと考えていました。地元の神戸新聞には地域版の明石版があります。――神戸新聞と言えば、私のこと叩いてるけど。まあええけど。
大学に行ってからも、その神戸新聞を送ってもらって、一日遅れで全部読んでいました。だから、私は全人類で明石に一番詳しい。
「どの大会で誰が勝ったか」まで見てきたんです。私は明石の良さと限界を知り尽くしているから政策が当たるんですよ。
 くらたま
くらたまなるほど。
 泉
泉昨日、今日の思いちゃうもん。10歳のときに「市長になる」と誓ってから、全力を傾けてきた。だから、ほとんどの施策は、すでに考えていたものです。状況を見ながらそれを「置きにいっている」だけですよ。
市長になったら、冷たい明石をやさしくできる自信があったんです。だから、そこに一生をかけようと思って生きてきました。国やほかのまちが「やさしい社会」を実現しなくても、明石から始める。ファーストペンギンとして成功事例を示す。そうすれば、いつか周りがマネしてくるだろうと思ったんです。
望外だったのは、市長を辞める前から「ご注目」いただいたことです。だって、私の活動は「死んでから評価されるかな」って思っていたから。
 くらたま
くらたま「時代」が正当な評価を下せないことが多々ありますから。
 泉
泉ええ。でも、一方で国民は不幸だと思いますよ。明石に転入者が激増しているのは、「冷たい社会」から逃げてきているわけですから。それだけ社会は崩れていってるんだと思います。

 くらたま
くらたま高齢者支援の取り組みについて伺えますか。
 泉
泉5年ぐらい前かな、今の厚生労働省の事務次官が局長になったときに明石に来てもらったんです。私は、認知症サポーター制度が「フリ」だけやっている制度だと思っていましたから。
だから、明石市で有償ボランティア化するモデル事業をしたいと話したんです。その後、話をつけて、実験的に明石で有償ボランティアによる制度を始めています。
認知症早期発見の取り組みにも力を入れています。認知症チェックシートを送ってもらった方に500円の図書カードをプレゼントしているんです。さらに、認知症の疑いがあり、病院で検査を受ける場合の診断費用は全額公費です。
 くらたま
くらたま検査を受けてもらえるように徹底サポートするんですね。
 泉
泉「病院に行きましょう」って声を掛けたら「金がかかる」ってなりますから。明石市はお金がかからない。もし、認知症と診断されたらタクシー券6000円もお渡ししています。加えて、2万円のサポート給付金も配る。それから、母子手帳のような形で「認知症手帳」をつくりました。これを使って情報共有をします。
ご家族のためには「宅配弁当券」20食分無料です。さらに、オレンジサポーターと名称を変更した明石独自の認知症サポーターのうち、ゴールドサポーターが10回無料で派遣されてヘルパーをする、「寄り添い支援サービス券」も配っています。「ショートステイ無料券」も配っているので、1泊2日はショートステイを無料で利用いただけます。
とにかく「みんなで支える」公助と共助を組み合わせた取り組みをしています。……全部、全国初のはず。
 くらたま
くらたま手厚いですね。
 泉
泉認知症サポーターだけではありません。明石は、成年後見センターをつくり、市民後見人を増やしていますが、有償です。 弁護士や社会福祉士と同じように汗をかいているのだから、市民だけ「ただでやれ」というのは間違いです。
日本は、“お上”には金を「ばらまく」くせに、“民”にはお金を出さない。……間違っています。明石市は、市役所の職員だけではなく、まちの市民も一緒になって子どもや高齢者を支えるコンセプトで運営しています。だからお金を払うのは当たり前なんです。
 くらたま
くらたまボランティア=無料というイメージが強いですよね。ちなみに、認知症チェックシートの目的は、認知症予防が目的なのですか?
 泉
泉いいえ。目的は「認知症になっても大丈夫なまちづくり」です。そのために、認知症を支える企業や市民団体を表彰するなどして、地域ぐるみで取り組んできました。 国が「推し進めたい」のは“予防”です。……こないだまで「共生社会」なんて言っていたくせに。
 くらたま
くらたま(笑)。
 泉
泉それから、日本が「ろくでもない」のは、高齢者のお金を子どもに回すかどうかの議論をしているからです。まさに「高齢者対子育て世代」の闘いを起こしている。
闘ったら両方が潰れますよ。そうじゃないんだ、と。明石市は、「ほか」から予算を持ってきて、「子ども」も「高齢者」も両方やるんです。
 くらたま
くらたまそもそもの発想を見直すことが必要ということですね。
 泉
泉明石市は「子ども」への施策の予算は倍にして、人員も3倍にしています。高齢者は、まだそこまでかけられていないけれども、集中的に取り組んでいます。
例えば、コミュニティバスも高齢者は無料にしました。それから、元気な高齢者の老人会的な活動を助成しつつ、要支援高齢者を支える費用も出すんです。
国のやり方は、“適当”に高齢者に「ばらまく」だけです。だからムダが出てしまう。そうして、その結果だけを見ているから「全部やめよう」となるんですよ。

 くらたま
くらたま明石市民も「やさしいまちづくり」に協力的ですね。
 泉
泉明石市が「強い」のは、中間支援組織を立ち上げたことも大きいのです。「足腰を強くしていった」わけです。
例えば、すべての小学校区に「こども食堂」をつくりました。この「こども食堂」の運営も行政がサポートしています。「あかしこども財団」という中間支援組織を立ち上げて、そこが手間暇とリスクを負うようにしたんです。行政は、市民が活動しやすいように応援する役割をしています。
 くらたま
くらたま「市民の側から考える」好例ですね。
 泉
泉市長への意見箱には、市民から毎週50通・100通のご意見が届きます。私は、全て読んで改善の指示を出しています。そこに書かれている特徴的なセリフは「こんなことを市役所に言っても聞いてもらえないので、市長さんに言います」なんです。「市長は市役所の代表ではなく市民の代表」という感覚を、多くの市民が持ってくれていると思います。
 くらたま
くらたま市民からの信頼が伝わるエピソードを伺いましたが、一方で「アンチ」の存在も気になります。
 泉
泉私のことを良く思っていない職員や議員は多いですよ。
 くらたま
くらたまこれだけ長く市長をされていても、まだ反感を持っている方がいらっしゃるんですね。
 泉
泉憎しみが強まっていってるもん。怒りが憎しみに変わっている状況じゃないですかね。「刺されたら」思い当たる人が何人もいますから。
それでも、思い切った改革には覚悟が必要なんです。市議会と市民の利益が対立したら、常に市民の側を取ってきました。市役所の慣習に反するとしてもです。だから、選ばれなかった側としては「なんで選んでくれないの?」となります。
「市民のため」という言葉はきれいやけど、職員には負荷がかかったり、リスクを負ったりするわけでしょう。定年間近になれば部長になれていた人が、なれなくなるということも起こりますから。
 くらたま
くらたまそうですね。
 泉
泉「うまみ」を感じていた人にとっては、一刻も早く市長を変えたい気持ちが強まりますよね。現に、市長一年目に公共事業を削減したときから、私の自宅ポストには「殺す」とか「天誅下る」と書かれた紙が投函され続けてきたんだから。
 くらたま
くらたま動物の死骸や汚物が玄関前に置かれるようなこともあったと、ご著書にありましたね。
 泉
泉ええ。当たり前のように「殺す」と言われ続けている12年です。それはもう激烈な闘いというか。……私が開き直っているから余計に腹が立つんやろうね。何をしても「堪えなくて」何をしても余計に予算を減らしていってるから。
当然、私自身にも恐怖はありますが、私には市民との約束がある。市民に選ばれた者の責任がある。何より子どものころに誓った、冷たい社会を変える使命がある。逃げ出したり、投げ出したりする選択肢など、最初から持ち合わせてなんかいないのです。悲壮な覚悟で市長の職を務め続けてきました。
(『社会の変え方』P338より引用)
 泉
泉反対勢力と闘いながらも、ゼロからイチをつくりました。でも、ほかのまちは、うちをマネすればいい。やりやすいと思いますよ。

 くらたま
くらたま「福祉関係者の賃金が安いのが納得いかない」というお話もご著書にもありましたね。
 泉
泉人に寄り添う仕事をされている方を安価で「こき使う」。人に寄り添わないところに高額な報酬を出す。これが今の社会の特徴です。どうかしていると思いませんか。
私は社会福祉士でもあるので「日本社会福祉士会の会長に立候補しないか?」と言われたこともありました。その当時から訴えていたことは、中学校の卒業文集に「将来の夢はソーシャルワーカー」と書きたくなる状況をつくることでした。
 くらたま
くらたま現状では難しいのではないでしょうか。
 泉
泉多分、なりたいのは医者と弁護士ぐらいやと。社会福祉士や介護士の仕事をしたいと書く人は少ないと思う。親も先生も暗に給与の話をするかもしれない。そんな社会はダメです。だからこそ、福祉職を多くの若者が目指したくなる仕事にせなあかんと言っています。
その話をしていた当時の調査では、社会福祉士の平均年収は250万だったんですよ。DV相談員の待遇は、国の基準で200万円〜250万円だった。今はもう少し上がっていますが。まさに「パート扱い」。そんな悩ましい相談の支援をする方に、それだけの金で「働けっちゅう国」なんですよ。間違っているでしょう。
ヨーロッパでは、弁護士や医師に負けず劣らず、ソーシャルワーカーは社会的地位のある職業です。年収も日本の倍を超える国もあります。人に寄り添い、継続的に支援を続けることは、高度でやりがいのある仕事だと認められているのです。日本で福祉にたずさわる人、たとえば社会福祉士をみても、その地位は弁護士や医師に比べて、明らかに低い。業務量は多いのに年収が低い。そんな環境では能力も十分に発揮できず、憧れの職業にもならない。そんな現状が、冷たい社会にさらなる歪みを生んでいます。
(『社会の変え方』P191より引用)
 くらたま
くらたま改善すべき点が多く残っていますね。
 泉
泉日本は、医者だけがびっくりするほど力を持っている国です。それは、不幸です。介護の大変さも「医者から見て『手間』がかかるかどうか」が基準になっていませんか。そうではなく、要支援の判断は当事者から見るんです。「個別」で見るんです。
 くらたま
くらたま今の介護制度に欠けている視点なのかもしれません。
 泉
泉例えば認知症だったら、「まだら」に症状が見られる状態のほうがしんどいんですよ。それにも関わらず、医者から見たらその状態は軽度なんです。
語弊がありますが、介護職からすれば要介護5の方が“ラク”です。もう完全に寝ているケースが大半だから。要介護5より要介護2のほうが、介護はしんどいんです。日本の福祉において「医者目線から本人目線への転換」は必要だと考えています。
 くらたま
くらたま制度それ自体を変えることは非常に難しいですね。
 泉
泉権限と責任と待遇はセットだから「社会福祉士を平均年収1000万の職業に育てなあかんわ」って“吠えた”んだけど、いまだに難しくてね。
だから、明石市では人に寄り添う専門職の待遇アップを実現しました。弁護士のほか、社会福祉士や臨床心理士など、人に寄り添う専門性を持った人材を全国から公募して正規職員として採用しました。非正規ではなく、正規化して平均年収700万、800万の待遇にしました。すると、第一人者の専門職の人が明石市の職員として全国から来てくれたんです。
 くらたま
くらたますごい。
 泉
泉「人」を増やすだけではなく、「質」を上げることにも取り組んできたのが特徴です。そうは言っても、明石市は人口30万人で予算規模2000億、正規職員は2000人です。それでも、兵庫県の29ある市の中の人口割合で、最も職員数の少ない市が明石市なんです。
 くらたま
くらたま人事についても改革を?
 泉
泉「なくても良い業務」に就いている職員には全員異動してもらいました。専門性を高めたうえで、少数精鋭化していったわけですよ。総人件費が20億円ぐらい浮きましたから。
 くらたま
くらたまそんなに浮くんだ!
 泉
泉それを市民への予算に回しました。
 くらたま
くらたまなるほど。
 泉
泉残業代についてもメスを入れました。「居座る」ようにして残業代を稼ぐケースが散見されました。だから、管理の仕方を変えました。部長や課長などの管理職の評価項目にして、残業に対するルールを厳格化。その瞬間に残業代が半分に減りましたから。それも数億円浮いたんです。こう考えると、税金なんかムダに使われているところだらけだと思いませんか。
 くらたま
くらたま否定はできません。
 泉
泉こういう取り組みをするだけでも、一気にお金は生まれます。だから、お金がないというのは嘘です。単に漫然とやっとるだけです。どこも痛みを伴わず「これまでどおり」をやろうとして、お互いに傷をなめあっているから金が動かない。
時代に応じたやり方にシフトすればお金は生まれます。
 くらたま
くらたまたしかに!泉さんは市民だけでなく、時代が求めているような方だと感じました。続いては明石の子どもたちについてもお伺いできればと思います。
後編に続きます

1963年、明石市二見町生まれ。元NHKディレクター・弁護士・社会福祉士・明石市市長。「5つの無料化」に代表される子ども施策のほか、高齢者、障害者福祉などに力を入れて取り組み、市の人口、出生数、税収、基金、地域経済などの好循環を実現。人口は10年連続増を達成。柔道3段、手話検定2級、明石タコ検定初代達人。