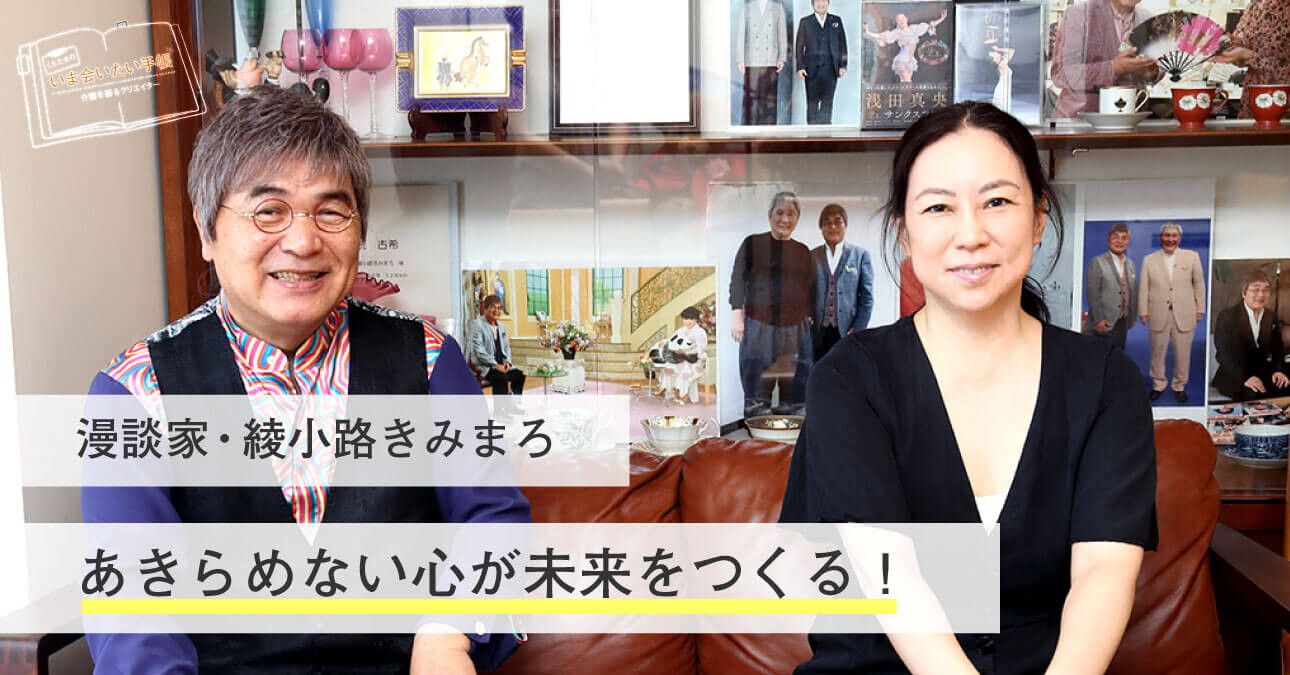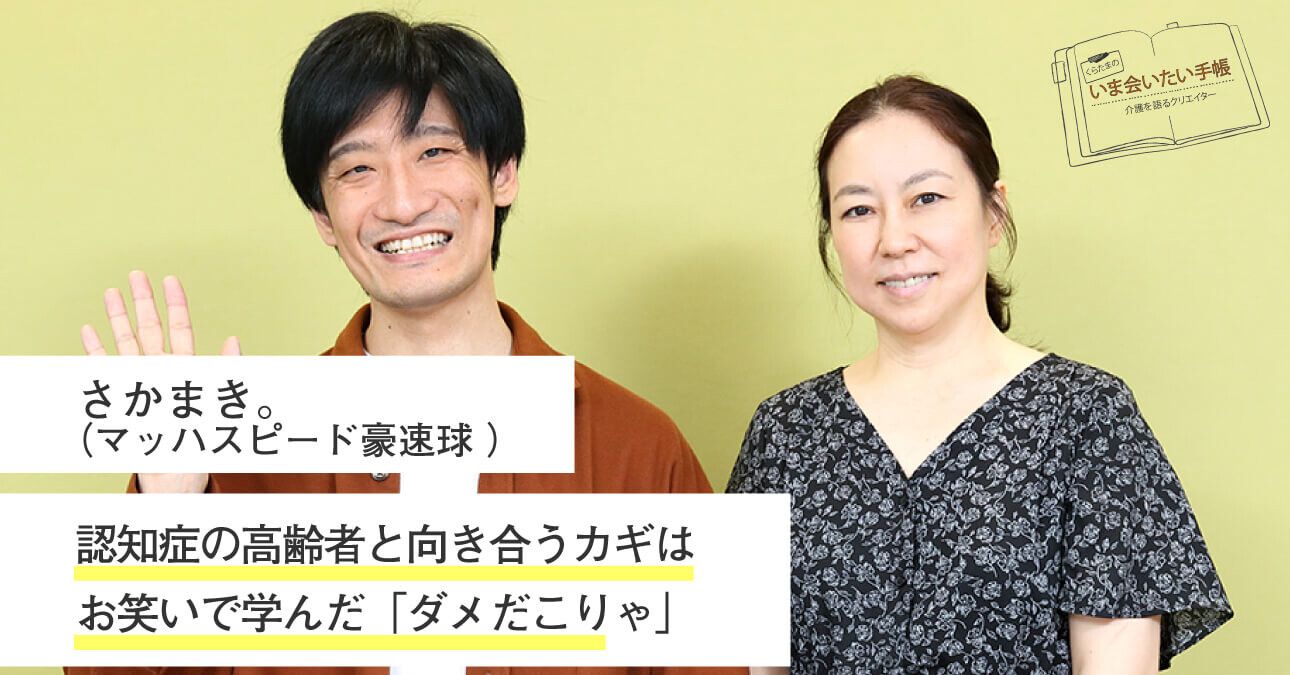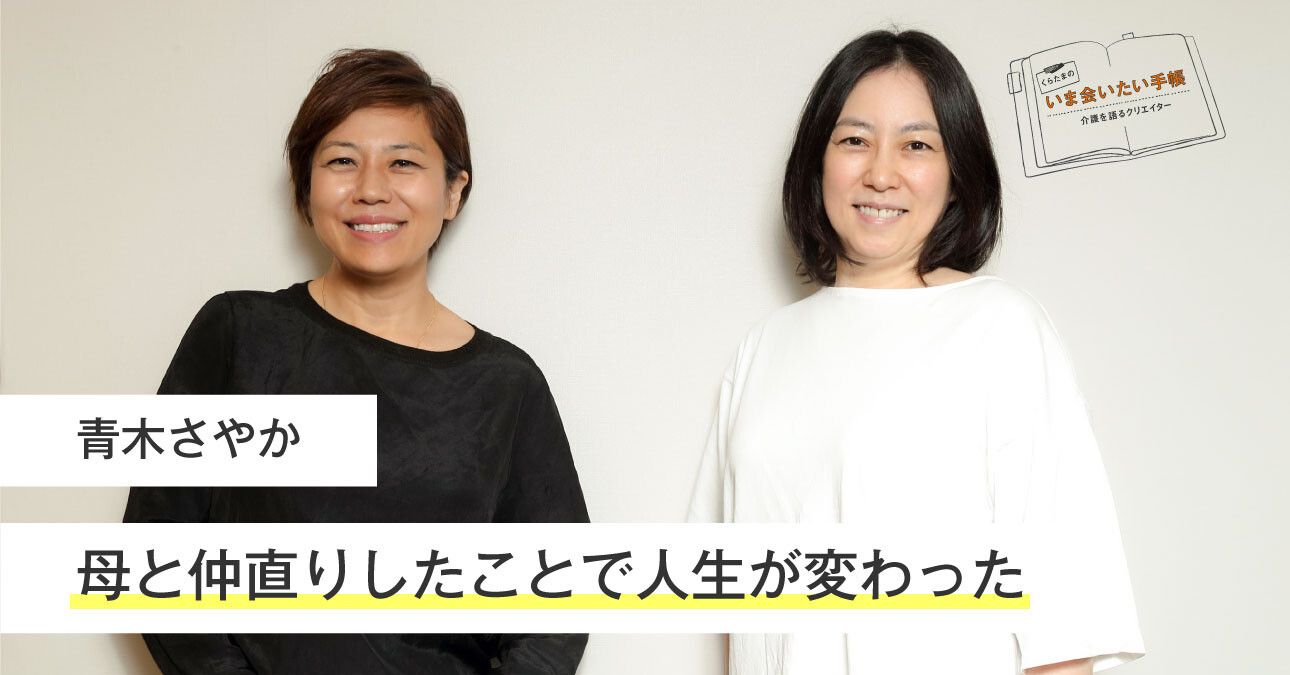きみまろさん、お写真よりも実物の方が若く見えますね。若さの秘訣は何ですか?
今回のゲストは漫談家の綾小路きみまろさん。中高年のアイドルとして"毒舌漫談"で一躍スターになったきみまろさんは、現在71歳。司会者を目指して上京した18歳から芸人を続けてきました。不遇時代のエピソードやブレイクのきっかけとなったサービスエリアでの物語、「きみまろを育てた立役者」と語る妻の存在まで、知られざるエピソードを漫画家くらたまが深掘りました。
- 構成:みんなの介護
毒舌漫談でありながら、中高年を中心に絶大な人気を誇る綾小路きみまろさん。本書の“きみまろ流人生哲学”に触れると、お笑い好きではなかった人をも虜にするきみまろさんの漫談の理由に納得。「人は最後までのぼり続ける」という考え方は、老いに対する新しい視点を与えてくれます。
中高年のアイドルへの道は新聞配達から始まった
 くらたま
くらたま きみまろ
きみまろ健康に良いと言われることを続けています。お酒は飲まないですし、エアロバイクなどの運動を習慣にしています。ペダルの重さを一番重くして1時間ぐらい漕ぐんです。舞台に立ち続けるためには、日々の体力づくりが欠かせません。
 くらたま
くらたますごいですね。長年お仕事への情熱を持ち続けていらっしゃいますが、キャリアのスタートについて改めて、教えて頂けませんか?。
 きみまろ
きみまろ司会業に憧れて東京へ出てきたのが18歳のときです。私は、鹿児島の片田舎の農村で育ちました。父は農家をしながら農耕馬の種付師をしていたんです。貧しいながらも愛情をかけて育ててくれました。
 くらたま
くらたま今のお仕事に繋がるきっかけって何だったんですか?
 きみまろ
きみまろ子どものころから、司会やスポーツの実況などを真似しては、友だちを笑わせるのが好きでした。父に連れられて行った子牛の競りのマネは当時の「18番」。面白い話をすることで人を笑わせることへの興味はその頃からありましたね。
当時は、司会者の玉置宏さん、宮尾たか志さん、高橋圭三さんらが人気を博した時代で、「ロッテ歌のアルバム」という歌番組での玉置さんの名台詞を練習しては、友人たちに見せていました。
 くらたま
くらたま司会業を目指すと言っても、何かツテがあったわけではないですよね?
 きみまろ
きみまろツテも知り合いもない。一人ぼっちでしたよ。住むところも仕事もなかったので、大学に通いながら新聞販売店の住みこみのバイトから東京での生活を始めたんです。
 くらたま
くらたますごいですね。そこから、どうやって司会業につながったのですか?
 きみまろ
きみまろ当時、北千住にある総合病院にも新聞を配りに行っていました。そこの病棟に、キャバレーの営業部長をしていた患者さんが3カ月ほど入院していたんです。
私はいつも予備の新聞を持って配達していたんですが、それをその方にあげて読んでもらっていました。同じ鹿児島出身ということもあり、だんだん仲良くなっていったんです。
ある日その方に「配達のバイトを辞めたいんですけど」って相談しました。すると「うちのキャバレーに来るか」って。そしてキャバレーのボーイをやることになりました。
人との縁は、特に大事です。結局、人生におけるさまざまなチャンスはすべて、人との出会い、人とのさまざまなご縁から生まれるものだと思うからです。しかし、損得の計算をしてしまうと、お世話になった人でも「もうこの人とは、つき合ってもメリットがない」と離れてしまったりするわけです。けれども、そういう人とのつき合い方というのは、他の人に対してもどこかそろばんをはじいているように感じられて、あまり信用されなかったりします。(中略)私は出会ったさまざまな人たちのおかげで、ここまで来られたと感じています。人間関係においては、損か得かなんてことは関係ないのだと思います。
(『人生は70代で決まる』P120より引用)
 くらたま
くらたま予備の新聞を配りに行くという行動がなかったら、その道は開いていなかったかもしれない…。
 きみまろ
きみまろ今思えば、全部他力本願でしたよ。そこから念願の司会業につながっていくとは思いもしませんでした。
 くらたま
くらたまきみまろさんは「人生は、縁と運と努力と体力」と仰ってきましたよね。
 きみまろ
きみまろ出会う方との間に縁がある。そして、運の波を感じながら努力を続ける。それによって人生が運ばれてきたと感じます。それらを土台から支えているのが、気力も含む体力!人生には、勢いと一緒に生きていくことが大事な時期もあります。
 くらたま
くらたま初めて司会の仕事をしたのはどんなタイミングだったのですか?
 きみまろ
きみまろ私が働いたキャバレーには、ショーの司会をしていた人がいました。ある日急にその人が仕事を休んだんです。
私はキャバレーの営業部長に「司会をやらせてほしい」と以前から言っていたので、そのとき「お前やってみるか?」ってなったんです。
1にも2にもなく引き受けました。普段から、ボーイをしながら司会者のセリフから学んだことをメモして、頭の中でシミュレーションをしていたんです。それをそのステージで発揮しました。
すると、会場は大いに盛り上がった。営業部長に「お前の方が上手いな」って言われて、翌日から私が司会を任されるようになったんです。
 くらたま
くらたままさに、縁と運と努力と体力のたまものですね。
オーディションに落ち続けた苦渋の下積み時代
 くらたま
くらたまでも、最初に手応えを感じられてからブレイクまで30年ぐらいの期間がありますよね。
 きみまろ
きみまろ日の目を見ない悔しさを、長年噛みしめていました。キャバレー回りをしていたとき、ビートたけしさんや片岡鶴太郎さん、亡くなられた星セント・ルイスさんと同じ舞台を踏んだこともあったんです。
彼らは売れていくのに、私には大きなチャンスは巡ってこない。テレビ番組出演のお誘いの声もかかりません。
「オレはダメだな」と自信をなくすことは、数知れず。「鹿児島訛りがあるからダメなのだろうか」と悩んだことも。でも、栃木訛りがあった東京ぼん太さんやゴテゴテの鹿児島訛りだった南州太郎さんもテレビに出ていた。訛りがあっても世に出られると、自分を励ましていましたね。
 くらたま
くらたまテレビ出演などのチャンスには、ご自分から手を上げられたこともあったのですか?
 きみまろ
きみまろオーディションもいろいろ受けていました。それも全部落っこちてしまう。 年下の審査員に「もう他にないの?」と言われたこともありました。紹介で行った笑点の“ネタ見せ”もダメでしたね。
芸の道で食べられなくなったときのために、学校に通ってあん摩マッサージ指圧師の資格も取りました。
 くらたま
くらたまさまざまな葛藤があったのですね。演歌歌手の司会もされていたとか。
 きみまろ
きみまろ森進一さんと出会って「僕の司会をやってみないか」と声を掛けてもらったんです。29歳の時でした。そして、森さんの司会を10年続けました。
その後、小林幸子さんの司会を4年。五代夏子さんを7年やり、そこでは、コンサートの進行などのほか、自分のコーナーがあって漫談をしていました。
トータルで20年ほど続けました。演歌歌手のステージに立っているうちに、私自身の漫談をお客さんにもっと見ていただきたいという思いが募っていきました。
 くらたま
くらたまつらい時期は、どんなことを支えにされていたのですか?
 きみまろ
きみまろ故郷を捨てて東京に出てきたので、これでは終われないという思いがあったのです。それに、マイク一つでお客さんを笑わせたい気持ちが募っていきました。今だから話せるのですが、心のどこかに、「私の漫談を絶対わかってくれる人がいる」という思いがありました。
忍耐も大事です。人生には、逆風が吹く辛いときや思い通りにいかないときがたくさんあります。そんなときは、今にきっとよくなると思って、じっと辛抱することです。自棄になったりしてはダメです。(中略)何があっても心を腐らせたりせず、真面目に一生懸命に努力をする。その積み重ねが、結果的に運を呼ぶという気がします。
(『人生は70代で決まる』P124より引用)
あとはお世話になった人たちに対しての恩返しですね。「まだやってるの?お前もなかなか売れないな」と言いながら、プロダクションの人が使ってくれるわけですよ。ブレイク直前の40代までそんな状況でした。
サービスエリアでのカセットテープ配布は苦肉の策だった
 くらたま
くらたまここからは、きみまろさんのブレイクに繋がった「伝説のカセットテープ」について伺えればと思います。サービスエリアで観光バスの運転手さんやバスガイドさんにご自身の漫談を録音したカセットテープを配られたんですよね。
 きみまろ
きみまろ自分の漫談をもっと多くの人に聞いてもらうためにはどうしたらいいのか悩んでいました。そして、ある日、閃いたんです!カセットテープに自分の漫談を吹き込んで配ろうと。
実は、観光バスに配る前に、老人ホームや中高年のいる美容室に配ってはどうかと考えました。でも、中高年は耳が遠いし、聞く気力もないだろうと。そして思いついたのが、観光バスに配ることでした。
観光バスはカセットデッキがあるし、バスガイドさんがいる。渋滞したときに流してくれるのではと思いましたね。それが当たったんです。
 くらたま
くらたまその時点でベテラン芸人さんですよね。いろいろなものを突き抜けた行動力だと思います。
 きみまろ
きみまろ今でもそうだけど、私はプライドが傷づくことはまったく怖くないんです。とにかくやってみないと「足跡」がつかない。そう考えて行動していました。でも怪しがられてバスの運転手さんと、もめたこともありました。それでも、今のように厳しく注意されることはありませんでした。
地元山梨のサービスエリアにも、全国から観光バスが来ていたんです。それを見るたびに心が高鳴っていました。
折しも、当時はバス旅行がブームだった。食べ放題のランチや桃狩りのために、全国から旅行客が来ていた。スーツケースにカセットテープをいっぱい入れて配っていました…。懐かしい思い出です。
 くらたま
くらたまカセットテープのデザインなども全部ご自分で考えたものだったのですか?
 きみまろ
きみまろ全部自分で考えていました。カセットテープの中にはめ込む紙の内容やデザインなど、それを印刷屋さんに持ち込んで印刷してもらいました。
そこには「このテープが欲しい方は、送料込みの税込2,000円でお届けします」と書いていたんです。そのとき考えた「きみまろ後援会」という事務所名と自宅の電話番号を添えて。すると、あれよあれよといううちに注文電話が殺到するようになりました。
あとで知った話なのですが、バスのお客さんが「このテープどこで売ってんの?」ってバスガイドさんに聞くらしいんです。
最初は片手で足りるぐらいの本数。それが2カ月たつと一日10本に。半年程たつと1日100本売れるようになっていた。最終的に1日400本ぐらいの注文が毎日くるようになりました。私の出演料よりもカセットテープからの収入が多くなった時もありました。
“漫談家・綾小路きみまろ”の成功の影に妻の支え
 くらたま
くらたま"カセットテープの成功"で、電話が鳴り止まない日々が続ていたのではないでしょうか。
 きみまろ
きみまろ着信音にしていた「森のくまさん」が一日中流れていました。とってもとっても電話が鳴るので、私と妻だけでは対応しきれずスタッフも雇うことに。私と妻は、毎日朝から晩までカセットテープを作りました。
 くらたま
くらたま夫婦愛を感じます。
 きみまろ
きみまろこれ以上つくれないというところまできていた頃、メジャーのレコード会社から声がかかってCDを出すことになりました。それが「爆笑スーパーライブ第1集!中高年に愛をこめて…」です。
2002年9月30日に発売されるやいなや、いきなりオリコンチャートのアルバム部門で47位。毎週順位が上がっていって、最終的には3位になりました。EXILEさんや浜崎あゆみさんと同じ時期にブレイクして順位を争っていました。
 くらたま
くらたまもし、カセットテープを配ろうと考えなければ。もし、きみまろさんが物おじする性格だったら…。漫談の歴史が変わっていたかもしれませんね。
 きみまろ
きみまろ私は中高年に支えられて生きてきたんです。それに、妻がずっと影で支え続けてくれた。妻にお金のことは全部まかせていました。
ブレイクした芸人は、経理をやってくれる人がいないと、税金が払えなくなって苦労すると聞いていました。
 くらたま
くらたま奥さんの力が大きいんですね。
 きみまろ
きみまろ私一人じゃここまで来ていません。人生丼勘定だから。そもそもブレイクしていないかもしれないし、破産していたかもしれない。本当に妻には頭が上がりません。
 くらたま
くらたまとても相性の良い奥様と巡り合われたんですね。
 きみまろ
きみまろ妻は、私のことを一番理解してくれています。漫談のネタも、よく妻に聞いてもらっています。こういうのをつくったんだけど、ちょっと聞いてと言って。
それに対して、妻は厳しく審査してくれます。それは面白くないとか、失礼だとかね。その上で、ギリギリ話せると判断したことを舞台で話しているわけです。
「よくおいでくださいました。そのようなお顔にお化粧されて」というネタがあります。これも、妻の助言によってぎりぎりのところで止めるようにしました。指を差したりはせず、誰とはなしに手を動かすだけにしておくとか。
前列の3・4列目ぐらいまでが被害者ですね。それでも嬉しいことに、私にいじられたいために前で見たいという方は多いです。
 くらたま
くらたま奥様はマネジャーのような役割なんですね。
 きみまろ
きみまろきみまろを育ててくれた立役者です。だから私も「恩返しをしないと」という思いがいつもありました。
 くらたま
くらたまファンの方々からはどんな声がありますか?
 きみまろ
きみまろありがたいことに、心のこもったお手紙をたくさんいただきます。私の舞台を見に来てくださる方は、普段はつらい思いをして過ごされている方も少なくなかったようです。
「つらいとき、とにかくきみまろさんの漫談のCDに救われています」とか。「なかなか笑うことがないので今日は来ました」とかね。そういうつもりでやっているわけではないのに、そんなお声をたくさんいただくんです。
「亡くなった主人が、ずっとあなたのテープを聞いていたので、お葬式ではあなたの漫談を流して送り出しました」とかね。少しは役に立ったと思うと嬉しいです。
 くらたま
くらたまたくさんの方を救われてるんですね。
どんな理由で亡くなるのかを知って最期を迎えたい
 くらたま
くらたま70代という地点から見ると、これまでの人生はどんなふうに見えますか?
 きみまろ
きみまろよくやってきたなと思います。50代までは、とにかく世に出たい一心でした。そして、世に出ることができたら、それを維持するための戦い。勢いに助けられながら生きてきたと思います。70代になると見える景色が違う。どんな出会いも出来事も、無駄なことは一つもなかったと思うんです。
人生100年とは言いますが、寿命は人それぞれ。今は、亡くなる年齢をある程度予想した上で、逆算して生きています。
 くらたま
くらたまこれからは、どんなふうに過ごしていきますか?
 きみまろ
きみまろ私はスウェーデンの高齢者が受けている介護や医療のあり方に憧れるんです。スウェーデンには、寝たきりになる高齢者が少ないでしょう?人に対してすごくやさしい国です。
介護については、国民が在宅介護の手厚いサービスを受けられる仕組みができており、自宅で可能な限り、自立した生活が送れるそうです。そのため、日本だったら確実に施設に入っているような認知症の高齢者でも、在宅介護を受けて自宅で生活しているといいます。(中略)スウェーデンにおけるこうした高齢者に対する介護や医療の在り方は、平均寿命世界一の超高齢化社会の日本が今後、参考にすべき点がたくさんあるような気がします。
(『人生は70代で決まる』P87より引用)
無理に団体行動をさせずに、一人でゆっくりする時間をつくってあげる。毎朝お年寄りの身なりを整えてあげる。そのようにして人権を尊重した接し方をされると、生きる力のようなものが出てくると言うんです。
ところが日本の高齢者の多くは”おしゃれ”の視点がない寝間着のような服を着て、車いすに乗って一日を過ごしています。
 くらたま
くらたま確かにそうですね。
 きみまろ
きみまろスウェーデンは、管だらけの無理な延命治療もしない。最期の時間は本人のしたい生き方をして終えていく。幸せに最期を迎える人も多いのではないかと思います。
実は、私の母は管をつけた状態で亡くなるまでの数年間を生きていました。そんな母の姿を見る中で、「このような状態を経験しないと、あの世に行けないのかな」と思っていました。だから私は、無理な延命治療を受けたいとは思わないんです。
理想はピンピンコロリ。でも、どんな理由で亡くなるのかはわかってから最期を迎えたいという思いがもあります。
 くらたま
くらたまピンピンコロリ憧れます。ちなみに、きみまろさんは、やり残したと思うことなんてあります?
 きみまろ
きみまろ私は、なかなか世に出られずに悔しい思いをしたけど、今振り返ってみらた大成功だと思います。世に出させてもらって、ブレイクさせてもらって、みんなに知ってもらうことができた。
 くらたま
くらたま間違いないですね。
 きみまろ
きみまろこれ以上望むのは欲だと思うんです。今こうしていれるのもおまけなんじゃないかと。今日こうやって出会えたことも奇跡みたいなもんだと思っています。だから出会いを大事にして、縁と運と努力と体力で、頑張っていきたいと思います。
 くらたま
くらたまきれいにまとめていただきました。さすがです!70代のきみまろさんの漫談がどんなふうに変わっていくのか、これからも楽しみにしています。
- 撮影:丸山剛史

綾小路きみまろ
1950年、鹿児島県出身。司会者を目指して上京し、1979年に漫談家としてデビュー。キャバレーの司会者として活躍したのち、演歌歌手の専属司会者へ。サービスエリアで配布した自作の漫談テープがきっかけとなり、2002年にCD「爆笑スーパーライブ第一集!中高年に愛を込めて…」をリリース。185万枚の売り上げを記録し、ライブやメディアで絶大な人気を誇る存在となる。コロナ禍でYouTubeチャンネルも開設し、新たな活動に取り組んでいる。