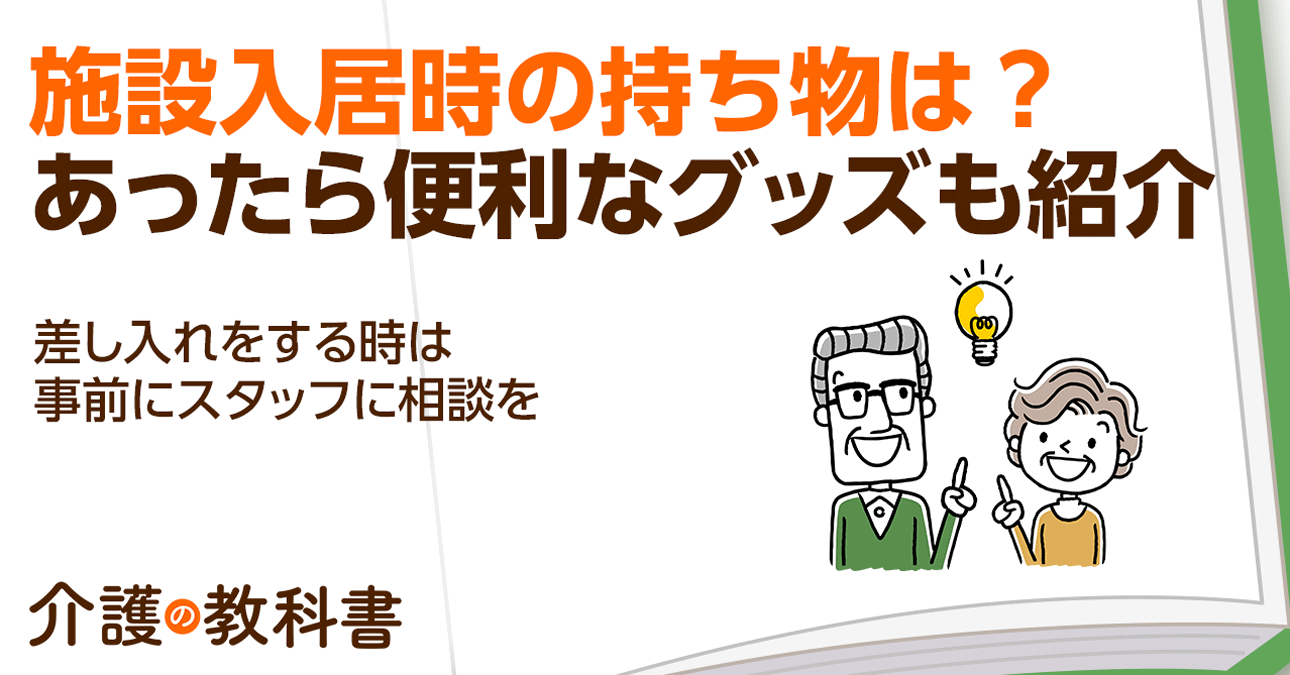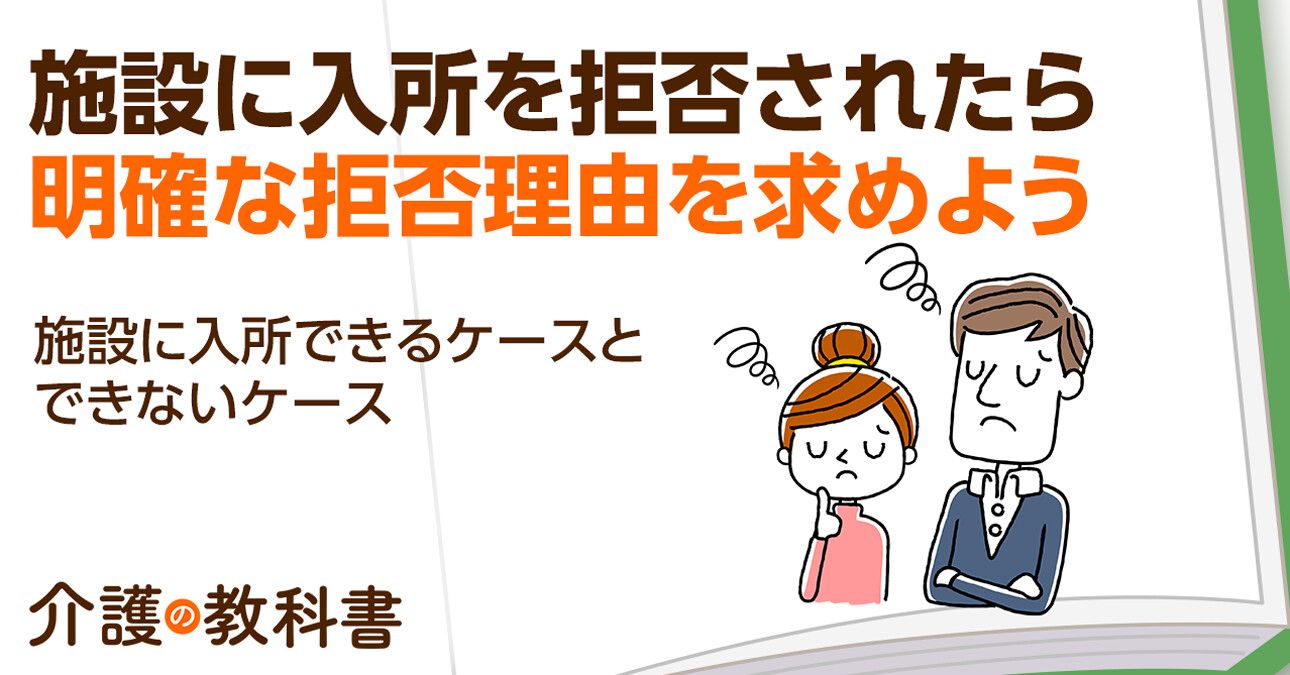皆さんこんにちは。株式会社てづくり介護代表取締役の高木亨です。
デイサービスに限らず、介護事業を営むうえで最も難しく重要なこととして、「従事者を守り育む一連の人事がほかの事業と大きく異なる」ということを理解する必要があります。
人が人を看る事業はほかにもありますが、例えば治療や教育といった、いずれも未来に向けた営みであり、人の生を見送る我々の営みはそうした「通常」の合理性と逆行しています。少なくとも、高齢者介護は、学校教育の範囲を大きく超えた倫理や哲学の領域を扱うと思っています。
今回は前回の1つ目に例として挙げた「職員の働きやすさを追求する」という点について、もう少し掘り下げて考察します。
人材は職員からの紹介で採用しよう
各種メディアでもすでに報じられていますが、介護職の人手不足は深刻な問題です。各事業所における介護サービスに従事する従業員の不足感は65.3%(『令和元年度「介護労働実態調査」の結果』を参照)に達している状況にあります。これを打開するため、既存の事業者も人材確保のために多くの労力とコストを掛けているのです。
この事実は、ちょっとやそっとの工夫で介護職員を安定的に雇用することが難しい状況であることを意味しています。国や自治体も介護職のイメージ向上や労働環境の改善に取り組んでいますが、不足した人材を同業他社間で獲得競争しているのが現状です。
介護職員の働きやすさに関しては、ほかの事業者がまねしようと思っても、そう簡単にはできないレベルまで高めておく必要があるでしょう。その入り口についても同様で、高い信用性が事業所側に求められます。「ハローワーク求人では人が集まらない」という状況であれば、その事業所の信用性は相当に低いと考えざるを得ません。
可能であれば、介護従事者はリファラル採用(職員に人材を紹介してもらう採用方法)が望ましいと言えます。現場をよく理解した職員からの紹介であるため、より適した方の採用が期待できます。

従事者の倫理観を養う
少し野暮ったい話にはなりますが、私が高齢者介護に強く惹かれるようになったのは、その行為に見られる「人間らしさ」です。私は高齢者介護が極めて特殊で人間的な支援であると考えています。
医療も教育も遠くはありませんが、基本的に人が人を看る場合、その方の人生が持つ未来への可能性を紡ぐために日々従事しています。しかし、高齢者介護は避けがたい「死」へと見送ることが生業です。高齢者介護が「福祉」とひとまとめにされてしまう1つの所以でもありますが、事業そのものがはじめから合理的とは言い難い性質を持っています。
「それがなんだ」とお思いになるかもしれませんが、この点は従事者がそれぞれに倫理観や哲学を構築するまでの間、介護事業者側は絶えず考え方を育み続ける必要があります。もちろん、そのためには諭し続ける側が延々と学び磨き続けていくことが求められるでしょう。
これらは事業としては1円にもなりませんが、非常に重要なことと考えます。研修でやったからそれで良いとか、繰りかえし伝えているとか、そんな安直なものではありません。常日頃からあいさつをするように、息をするように諭し、ときに議論を深めて、相互に高めあっていくことが大切なのです。なぜならば、たとえ一瞬でも倫理観や哲学が置き去りにされれば、高齢者介護事業は、福祉の風上にも置けない残酷な事件を「合理性に従って」起こしてしまいかねない、ハイリスクな一面を有しているからです。
利用者を大切にする従事者を守る事業者
高齢者を虐待、ときには殺害してしまう事件が起こるたびに介護業界には激震が走ります。
事件が起きてしまう大きな理由の1つとして、介護業界において、人権が最も疎かにされやすいのが従事者であるからだと思われます。介護保険法上、利用される高齢者については「弱者」としてわかりやすく説明されていますが、高齢者が引き起こすさまざまなカスタマーハラスメントについては十分な説明がありません。つまり、事業者側は何が何でも従事者を守る必要があります。
「従事者には利用者を大切に」と諭しながら、事業者側が実際に守るべきなのは従事者。それが揺らいではならない事業者側の基本でしょう。利用者を守るのは従事者であって、事業者が守るべきは従事者なのです。この点を違えた介護事業経営者がいる限り、不幸な事件・事故が生まれてしまいます。
「事業収入が少なく十分な手当てを払えない」「利用者確保で一杯いっぱいで従事者に手を掛けられない」といった、もっともらしい理由が「従事者に十分なケアを行えない言い訳」として言われています。しかし、従業員に心を配らない理由にはなり得ません。事業を営む者は「介護従事者がいなければ事業自体が成り立たない」「介護従事者の質がそのままサービスの質に直結する」事実を決して忘れるべきではないでしょう。

事業者には従事者の精神を支える人間性が必要
以前、「介護は精神労働である」と書かせていただきました。介護従事者は否応なく従事の度に精神をごっそりと削がれます。ただ、「そういう仕事」とひと言で片づけられないのが介護従事の難しいところです。
例えば、介護従事者が家で介護をしている場合、介護知識や技術に長けていても、まず間違いなく「在宅介護」は困難を極めることになります。どんな事業においても予定通りとはいかないでしょうが、ある程度想定はできるでしょう。ところが、介護の場合は予定通りにいかないのが常で、従事者の想定をはるかに超えてきます。「予定外」は利用者にとって何気ない言動であったり、一時の状態でも生じます。
予定通りに仕事が進まないことによる精神的ダメージは大きく、それが「常」であることのストレスはときに人を狂わせるほどと言っても過言ではありません。思った通りにならないのが介護である以上、介護従事者の上に立つ方々にはそうした従事者の精神を支えるだけの人間性が求められます。
組織体系が大きければ大きいほど、それに伴った人間性の大きさが求められる事業とも言えるでしょう。どれほど高度な介護知識と技術を備えていても、それを使う者が心を病んでいれば意味がないばかりか、人の命を危険にさえ晒しかねません。
高齢者介護は、通常の教育課程では得ることのできない深い人生観や高い倫理性、磨き上げられた哲学を必要とします。事業者には、知識や技術を育てること以上に人間性を育てることと、常日頃の精神のケアが重要になります。
不安ごとは日頃から解消されていく状況がベスト
当然、職場環境の整備と人材育成には多くのコストを充てる必要があります。今回のコロナ禍の影響もあって、これまで以上に介護従事者が抱える感染リスクに注目が集まりました。しかしケアを行う以上、もともとハイリスクであることに変わりはありません。
環境面や金銭面、制度面に掛けるコストは言うまでもなく重要です。さらには、職場でのコミュニケーションを円滑に保つための「コミュニケーションコスト」も大切になります。毎日のように生じる疑問点や問題点、不安に感じたことなどは常日頃から解消されていく状況が保たれることがベストと言えます。
「こんなことがあったがどうすると良かったか」「こんなことが考えられるがどうしていくべきか」など、指示するだけではなく互いに相談し合い、高められる状況と環境、そして事業者側の理解が必要です。

地域貢献や仕事を越えた学びの場、交流の場にまで橋をかけ、「事業者と従事者」、「雇用者と被雇用者」の関係ではなく、社会的人道的に支え合える関係性を構築する努力を惜しむべきではないと思います。「子育ては子どもを育てるばかりでなく、親も子どもに育てられる」と言いますが、介護事業に関しては事業側と介護従事者側も同様の関係が築かれるべきではないかと思うのです。