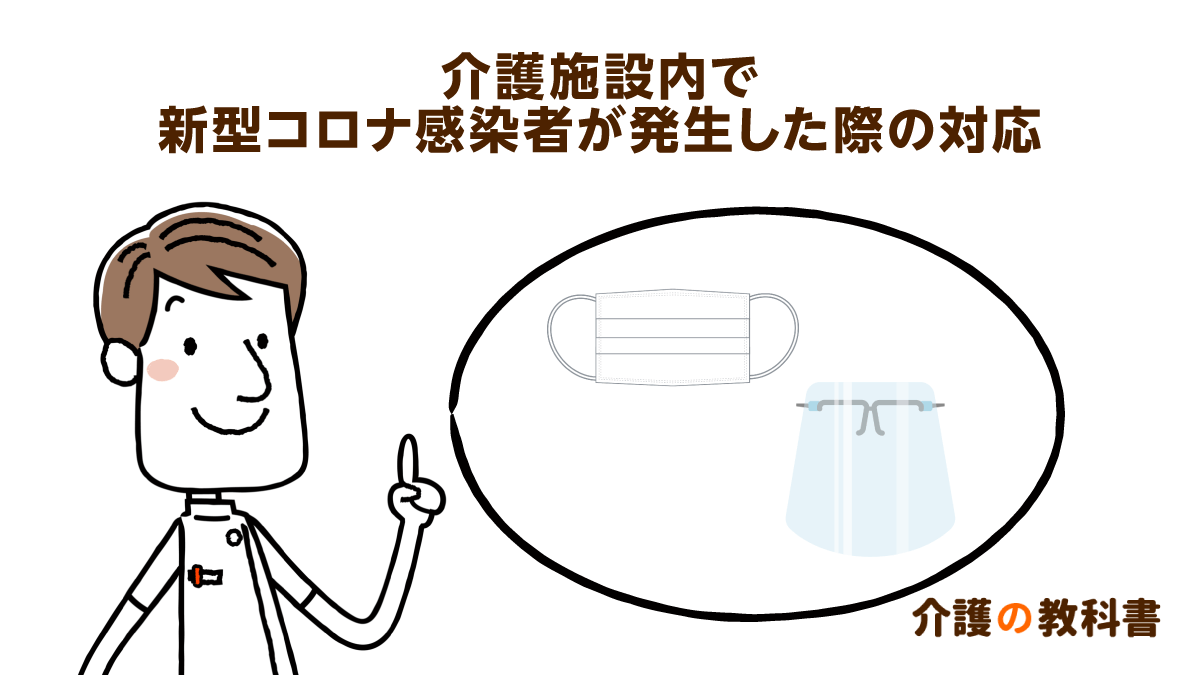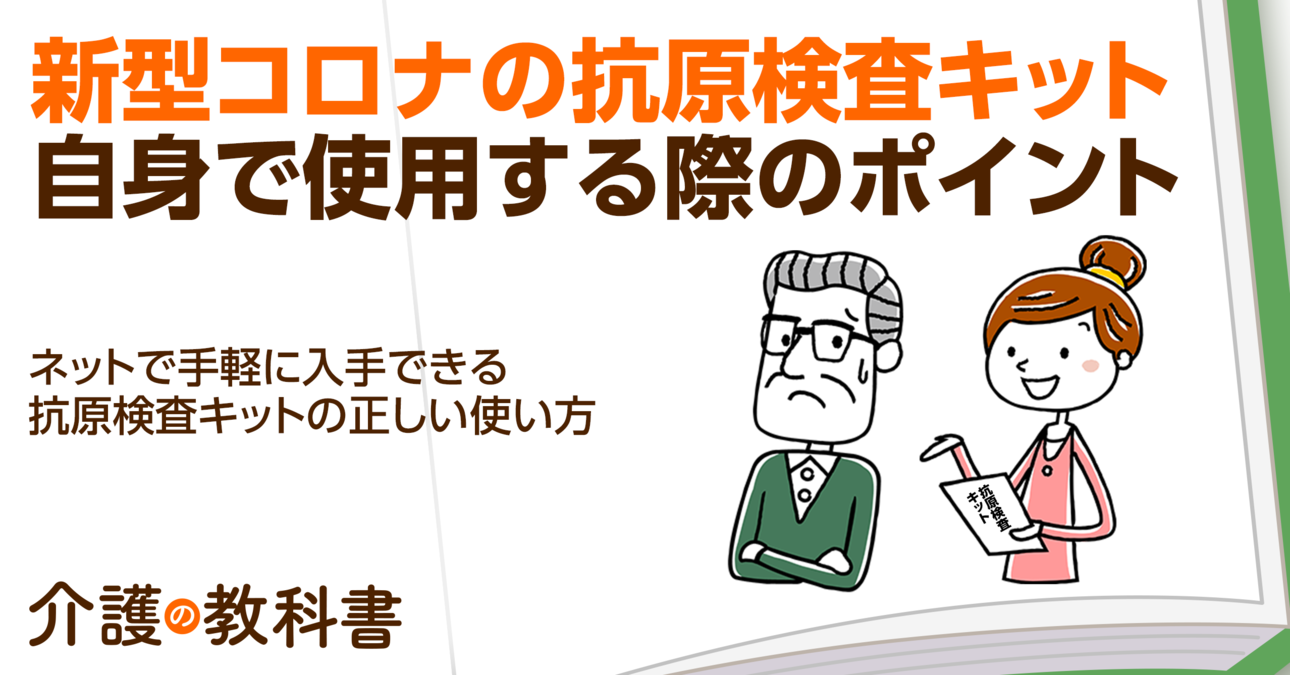特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。
新型コロナに伴う緊急事態宣言が、3月21日をもって解除されました。感染対策の緊張感も社会的には緩和傾向となっているとの報道もありますが、介護・医療現場は解除後もまったく変わらず、私たちは日々緊張感を持ち続けて利用者の方々に向き合っているのが現実です。
さらに、変異型ウイルスによる感染拡大の可能性もあるので、感染予防対策も力を緩めることはできません。とはいえ、どんなに感染対策を厳重にしてもクラスター(集団感染)が起きる可能性はあります。「いざ」というときに慌てふためき、「何をして良いかわからない」という混乱を防ぐため、今回は「介護施設内で新型コロナ感染者が発生した際の対応」についてお話しします。
感染防護具を脱ぐときも注意する
新型コロナの感染経路は飛沫感染と接触感染が主です。飛沫感染は、感染者のウイルスを含んだ飛沫が、介護者の目や鼻、口のいずれかから侵入することにより感染します。
そのため、感染者や疑われる利用者を介護・看護する場合には、不織布マスク(激しい咳込みがある場合はN95マスクを使用)やゴーグル(フェイスシールドなど)を着用しましょう。また、介護・看護においては利用者の体に触れることもありますから、接触感染を防ぐために、使い捨てプラスチック手袋やガウン、キャップなども着用してください。新型コロナの感染者とそれが疑われる利用者を介護・看護する場合は、「自分が感染しない」「周囲にウイルスを拡げない」ように、感染防護具を着用します。
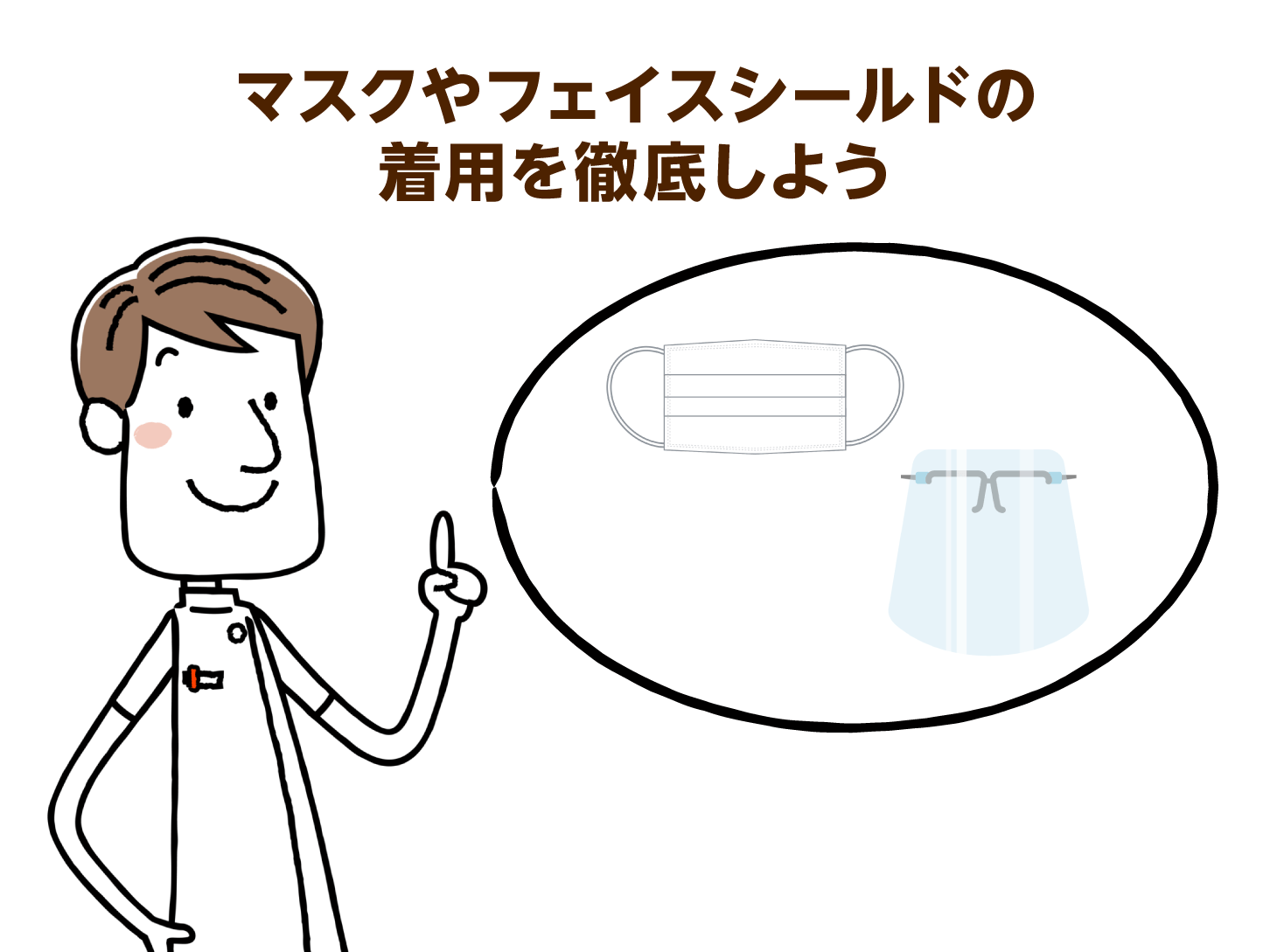
防護具の表面にウイルスが付着している可能性も…
一般的には、先述したような感染防護具を着用していれば安心と思われがちです。しかし、「安心=安全」ではありません。感染者や疑われる利用者を介護・看護した後につけていたゴーグルやガウンなどの表面には、ウイルスが付着している可能性があります。そのため、感染防護具を「安全に脱ぐ技術」が大変重要になるのです。原則としては、以下の順番で作業を行ってください。
- ガウン・手袋を外す
- シューズカバーを外す
- 手指衛生をする
- キャップを外す
- ゴーグル(フェイスシールド)を外す
- マスクを外す
- 手指衛生をする
このとき、表面に触れずに装備を外すテクニックが必要になります。難しいですが、これらの知識を習得するだけでなく、実際にできるようにならなければなりません。そのためには、トレーニングが必須となります。
野球に例えると、ヒットを打つためには「バットにボールを当てる必要がある」という知識はあっても、実際に当てることはなかなか難しいですよね。何度も練習をすることで打てるようになり、技術が磨かれるのと同じ原理です。
感染防護具をつける最大の目的は感染経路を遮断すること。安心感を得るために感染防護具をつけること自体を目的化しないように注意しましょう。
感染者と非感染者でエリアを分ける「ゾーニング」
新型コロナの感染者は医療機関での入院治療が原則ですが、感染者の増加による病床のひっ迫を理由に、医療機関に入院できない可能性もあります。そのため、施設で新型コロナの感染者が出た場合は、その方が施設で継続して生活することを前提に計画を立てておくための「ゾーニング」が必要です。この場合のゾーニングとは、感染者と非感染者の区分けを意味します。
方法と注意点
ゾーニングを実施するうえでの注意点として、まずレッドゾーン(感染者エリア)とグリーンゾーン(非感染者エリア)を明確に区別する必要があります。区別する際は、色つきテープやビニールシートなどを使用しましょう。このとき、レッドゾーンは可能な範囲で狭く設定してください。広く設定すると環境表面や機材類がその分汚染されてしまうので、職員における清掃や消毒の負担が増えてしまいます。

ナースステーション(職員室など)や感染者は出たエリア以外はグリーンゾーンとし、感染防護具の着用・脱衣場所は色つきテープなどで明確に指定します。防護具の着用場所には必要十分な感染防護具、脱衣場所には使用済みの感染防護具を廃棄する袋を準備して、感染防護具をその中に破棄してください。
| レッドゾーン | グリーンゾーン | |
|---|---|---|
| 場所 | 感染者や感染が疑われる利用者、 濃厚接触者(PCR検査結果前)などの居室 |
レッドゾーン以外の空間 |
| 人 | 感染者や感染が疑われる利用者、 濃厚接触者(PCR検査結果前)、 対応エリアの介護・看護職員 |
当該エリア職員以外 |
| 防護内容 | 原則として不織布マスク(またはN95マスク)・ プラスチック手袋・ガウン・ フェイスシールド・キャップ・シューズカバー |
不織布マスク |
| 用途 | 感染者や感染が疑われる利用者、 濃厚接触者(PCR検査結果前)の対応 |
左記以外の場所 |
レッドゾーン内で意識すべき6つのこと
- 1:利用者の行動制限
- 新型コロナの感染者が発生した場合、その方には個別隔離を実施し、個室内での生活を徹底させる必要があります。感染者のいるエリアは封鎖し、そのエリアの利用者は濃厚接触者とみなして素早く対応します。もちろん、基本は保健所の指示に基づいて対応を実施してください。
- また、レッドゾーン・グリーンゾーンで働く職員は、完全に行動を別にする必要があります。レッドゾーンを担当する職員は固定して、シフトを分けましょう。このとき、基礎疾患などで体調面に支障のある方や、妊婦の方などは考慮し、夜勤者が少なければ必要に応じて増員も行ってください。
- 2:環境整備
- レッドゾーンにおける環境整備に関してですが、接触の頻度が高い部分を中心にアルコールで清拭し清掃消毒を行いましょう。また、1時間に10分の頻度で換気も行います。
- 3:食事介助
- 新型コロナの感染者・疑われる利用者の食器は使い捨てのものを使用してください。
- 使い終わった食器や食物残渣物は感染性廃棄物として処理します。使い捨てできないものを部屋から持ち出す場合は、必ず袋に入れてください。食事を行う際は、まず対象者の手指を使い捨ておしぼりなどで消毒します。

- 4:排泄介助
- 排せつ介助については、原則として紙製品(オムツやパット類、使い捨て清拭)を使用し、使い終わったら感染性廃棄物として処理します。オムツやパット類は直接手で触れず、廃棄するときはごみ袋に入れて厳重に封をしましょう。
- ポータブルトイレを利用する場合は、中のバケツをオムツやビニール袋で覆い、尿や便が浸み込んだオムツは封をして、感染性廃棄物として処理します。使用後は洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)で消毒を行ってください。
- 5:衣類やリネン類の取り扱い
- 衣類に関しては次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)に30分浸し、洗濯や乾燥を行います。リネン類は次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)に30分浸して、ビニール袋を二重で密閉し、業者に出してください。
- 6:その他
- 利用者が鼻をかんだティッシュなどのゴミの処理は、ビニール1袋に入れて感染性廃棄物として捨てましょう。また、体温計などの器具は可能な限り利用者専用とし、介護者はケアの開始時と終了時に、石けんと流水での手洗いおよびアルコールによる手指消毒を実施してください。
事業所の状況に応じたマニュアルを整備
このように、新型コロナの感染者が出た場合には、ゾーニングの留意点や詳細をまとめたマニュアルを整備することが必須となります。厚労省などがマニュアルのモデルを公開していますが、事業所によっては環境も物品も人員も違いがありますので、所属する事業所に応じてマニュアルを整備すると良いでしょう。
筆者が勤務する施設でも、昨年4月に自作の「新型コロナマニュアル初版」を策定し、それから改定を重ね、現在「新型コロナマニュアル第10版」として現場で活用しています。マニュアルには、介護・看護職員が濃厚接触者となり自宅待機になってしまうことも想定し、職員の欠員が生じた際の応援体制などもマニュアルに盛り込むことが重要です。
早めに業務継続計画を立てよう
介護報酬改定に関する省令及び告示において、新型コロナや大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るために、業務継続計画の策定をする必要があります。介護施設では新型コロナ感染者が発生したとしても、当然事業を停止することはできません。そのため、業務継続計画を立てるとともに、必要な研修および訓練(シミュレーション)を実施しなければならないことも追記されました。
業務継続計画の中に盛り込まなければならない項目としては、以下の3つが挙げられます。
- 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保など)
- 初動対応
- 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有など)
業務継続計画の策定などには3年間の経過措置がありますが、いつ施設内で新型コロナの感染者が発生するかわからないため、早めに策定して取り組む必要があります。
「備えあれば憂いなし」
今回のお話が施設で働く皆さんにとって、少しでも参考になるとうれしく思います。