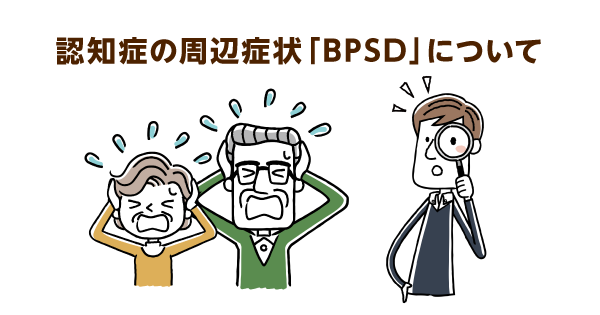こんにちは。特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。
今回は「専門職による暴言や暴力などの不適切ケアについて」をテーマに考えていきます。
介護職による暴言・暴力が起こった背景を深堀りする
私たち専門職は入居者・利用者の「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」支援することが仕事です。多くの専門職は、真摯に誠実に入居者・利用者に向き合い仕事をしています。ところが新聞やテレビで報道されるような“不適切なケア“が一部にあるということも事実です。
数年前に、ある介護施設において介護職員が複数の高齢者の方をベランダから転落させる事件がありました。その施設では、常日頃から複数の介護職員が利用者に対して暴言や暴力行為に至っていたことが明るみになりました。またほかの施設では、複数の職員が利用者に心無い言動を発している姿が隠しカメラの撮影記録によって発覚しました。高齢者の方の人生のラストステージの日々が「安心・安全」が担保されたものではなく、「恐怖と脅威」を感じる毎日となっているわけです。
施設内の常識が世間一般の常識と乖離するケースがある
このような不適切ケアの報道があるたびに私にはいつも考えることがあります。それは、「そのような行為をしてしまった職員が、この仕事に就いたときにどのような意識を持っていたのか」ということです。介護職として就職したときに「相手の心や体を傷つけよう」という意思や目的があったのだとすれば、対人援助の仕事をする資格はないと言えます。
ですが、不適切ケアを行った職員の中でも、この仕事に就いたときは「不適切ケアはしない、してはいけない」と強く心に持っていた方が圧倒的に多いのではないでしょうか。そのように強く心に持っていた人たちがこの仕事を続けるうちに、さまざまな要因によって“おかしなこと”に気づけなくなっていく…。自分が行っている不適切な行為が、世間一般から見たら非常識このうえない行為であると気がつかない…。
仕事に就いて間もないときは「これっておかしいな」と感じていたとしても、それが施設内で連続して行われていれば、「施設の中ではあり」というゆがんだ認識に変わるということなのです。

普段の無礼な言葉や強引な介助がやがて不適切なケアに発展
川の始まりを思い浮かべてみましょう。
大きな一級河川も、「ちょろちょろ」と流れ出る湧き水から始まります。湧き水が上流中流下流と海に近づくにつれて、流れが急になり、大きく・広く・深い川になっていくのです。
不適切ケアも同じだと思います。
無礼な言葉や子ども扱いするような言葉を毎日発していると、語気を強めた言葉を言うようになります。そして語気の強まった言葉を使うことが施設内で一般的になると、罵声や暴言が生まれてくるのです。
言葉だけではありません。少し強引な介助や不十分な言葉かけで相手を驚かせる介助が“普通”になれば「強引な介助」が生まれます。強引な介助に慣れてしまうと、アザや傷が残るほどの行為が生まれる可能性があるということです。いきなり罵声や暴言、暴力が生まれる訳ではないのです。
そのように不適切ケアを生み出さない、加速させないために、私たち専門職はどこに「目と意識」を向けたら良いのか。常日頃の「言葉」と「行動」に「目と意識」が向かなくなった時点で不適切ケアの芽は出始めているということです。
高齢者虐待防止法の5つの分類
2006年に高齢者虐待防止法が始まりました。この法律は、虐待を5分類に振り分けました。
- 1)身体的虐待
- 暴力的行為によって体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
- 2)心理的虐待
- 脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
- 3)性的虐待
- 本人が同意していない、性的な行為やその強要
- 4)経済的虐待
- 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
- 5)介護・世話の放棄・放任
- 必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしないなどにより、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること
介護の専門職ならこの5類型について認識されていると思います。
ここで私は「身体的虐待」と「心理的虐待」について焦点を当ててお話をします。
日本で最も発覚件数の多い「身体的虐待」
わが国で一番発覚件数が多い虐待は、「身体的虐待」です。
なぜ一番発覚件数が多いのか。それは証拠が残るからではないでしょうか。寝たきりで動けない・動かない方に不自然なあざや内出血がある。それを見た私たちは、「あれ、何でこんなあざや傷ができているのだろう」と思うわけです。そこから発覚するケースが多いのだと思います。
これは虐待と直接関係はありませんが、現場の介護専門職の方たちは、利用者の体や皮膚の状態に非常に敏感です。ただでさえ高齢者の方は私たちよりも体や皮膚の状態が弱くなっています。高齢者の方がご自身でベッド柵などにぶつけてできたと想定される、1センチメートル×1センチメートル程度のうっすらとした内出血も発見するほどです。
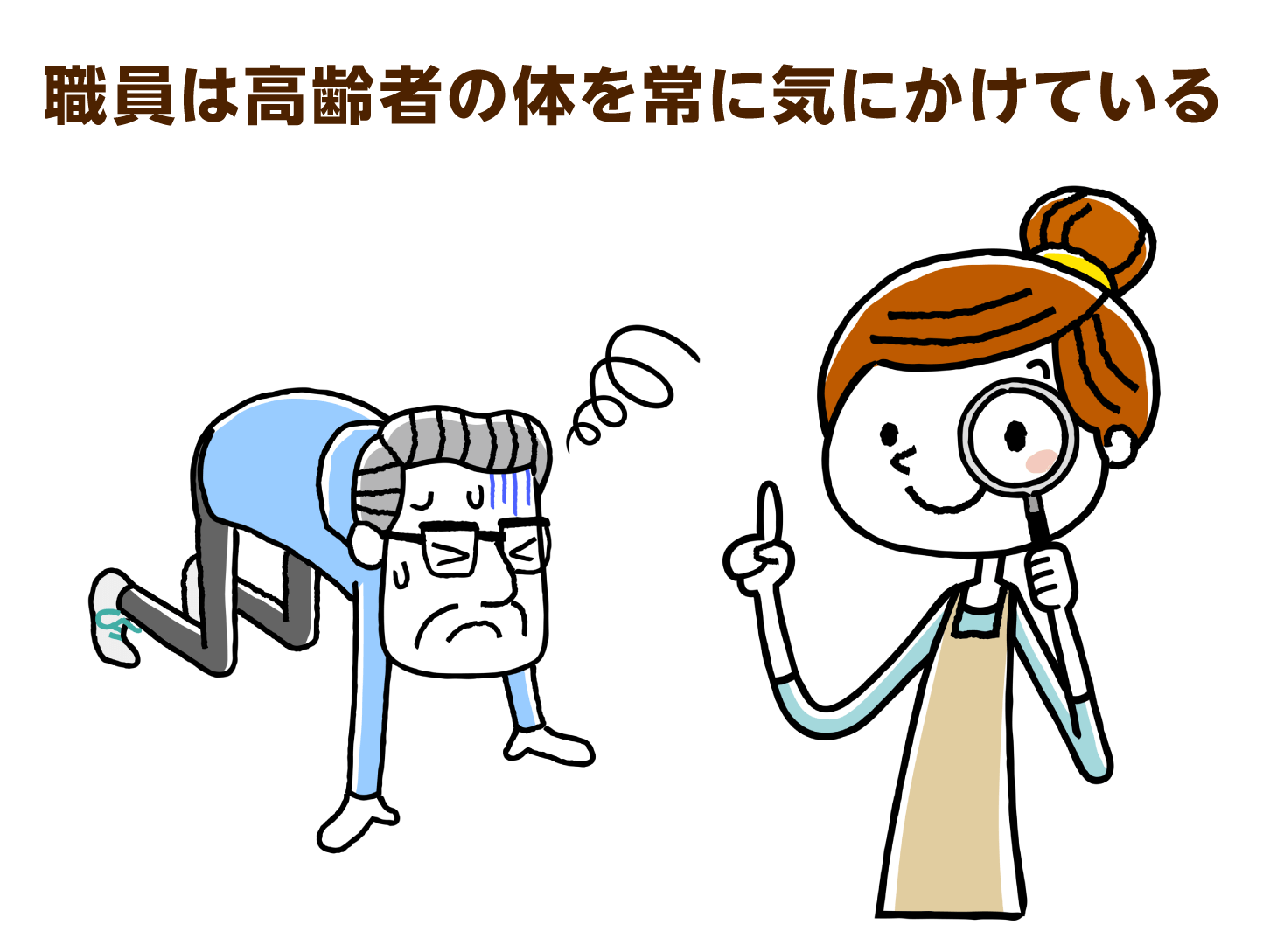
10年以上前のできごとです。私が働く施設のショートステイを利用し、自宅に戻られた認知症状態のAさんのご家族から私宛に電話がありました。
Aさんのご家族「髙橋さん、施設から戻ってきたら足に内出血ができていたんですけど。そちらから内出血について説明がないですが、何かあるんじゃないですか」
私たち職員はAさんが施設利用中、必死にかかわって向き合ったつもりでした。しかし家族に疑われてしまった。このときほど「疑われて介護はしたくない。疑われるのであれば介護はできない」と思った経験はほかにありません。そのようなできごとを経験されている介護専門職もいることでしょう。だから私たち専門職は、高齢者の体や皮膚に対していつも以上に目と意識が向くのだろうとも考えます。
このように目と意識が向いている状況では、通常身体的虐待が起きにくい状況とも言えるのです。
2番目に多い「心理的虐待」の発覚件数は上位と比較して圧倒的に少ない
わが国で二番目に発覚件数が多いのが「心理的虐待」です。言葉で相手を傷つける。身体的虐待と心理的虐待の発覚件数には差が大きくあります。しかし私の印象では、実態は両者の件数に大差はないのではないかと考えます。
ではなぜ差があるのか。それは、言葉には視覚できる形はなく、そして人は消えるものには目と意識が向きにくい。つまり、暴言を吐いたとしても、罪悪感などといった感覚が麻痺しやすく、無意識・無自覚に虐待を働いてしまうものだと思います。だからこそ私たち専門職は、自分たちが発する言葉や表現に意識を向けていく必要があると考えます。
【避けたい表現と行為】
- 指示・命令的な表現:「~してね」「ダメでしょ」
- ネガティブな表現:「汚い」「また失敗したの」
- 相手を否定する表現:「違うでしょ」「何でこんなことしたの」
- 自分主体表現:「危ないから座ってて」「寝ててください」
- 恐怖感をあおる表現:「病気が悪化しても知らないよ」「食べなきゃ明日の朝までご飯ないからね」
- これからする行為を言葉で伝えない:車椅子を急に動かす、何をするか伝えない
【望ましい表現と行為】
- 依頼・了承を得る表現:「~していただけますか?」「~しますか?」
- ポジティブな表現:「~しましょう」「~ならできます」
- 相手を受け入れる表現:「その通りですね」「~ということですね」
- 相手の立場や気持ちを配慮した表現:「いつでもおっしゃってください」「何がお好きですか」
- 安心感を与える表現:「すぐに行きます」「~良いと思いますよ」
- これからする行為を言葉で伝える:「今から食事です」「車椅子を動かしますね」
介護をされる人の生きる姿は介護をする人で大きく変わる
私たちの培った知識・技術・意識を駆使すれば、利用者の生きる姿をより良くできる一方で、利用者の暮らしの質を低下させることもできてしまう。私たちは専門職として自分自身の感覚が麻痺していないか省みていく時間をつくる必要があると考えます。