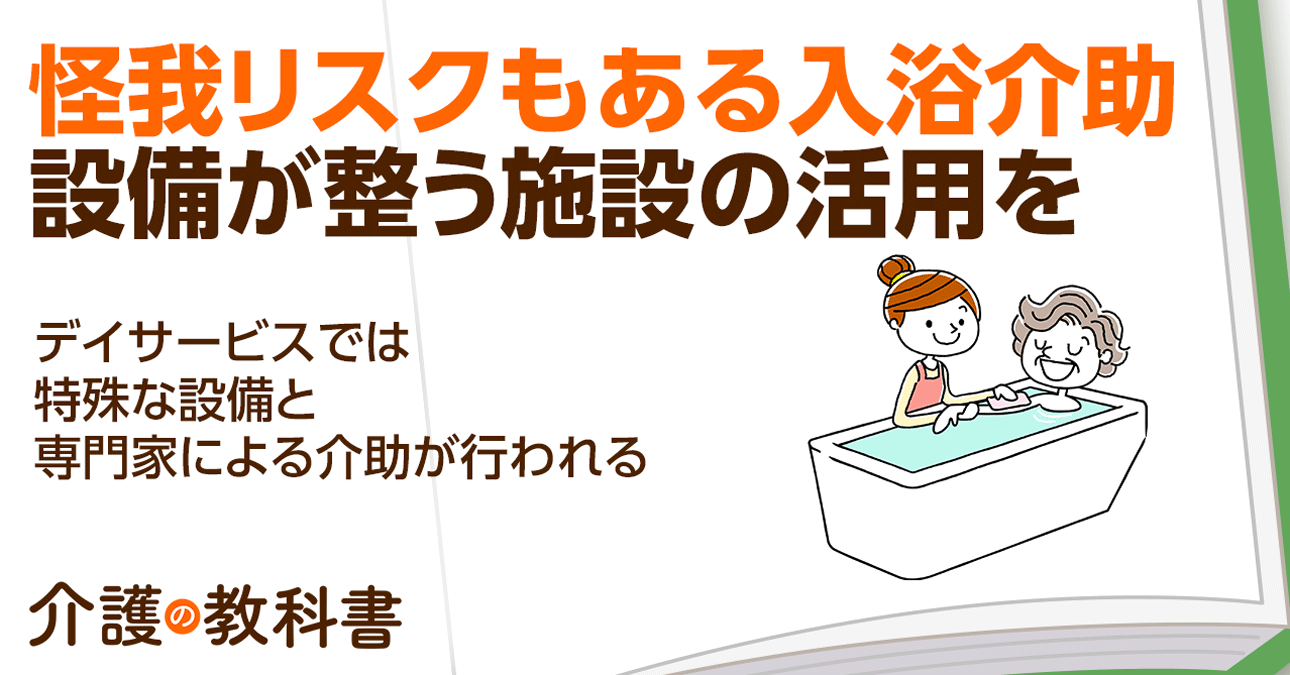こんにちは。ケアマネジャーの小川風子です。
介護サービスの利用者や介護施設の入居者に対する介護職員の暴力事件が、たびたびニュースで取り上げられています。いかなる理由があろうと決して許されるものではなく、厳しい処分を求められるのは当然のことです。
一方で、介護職員が利用者や入居者から暴力を振るわれる事例は、あまり表沙汰になりません。実際に介護職として施設などで働いていると、入居者からのハラスメントや暴言・暴力を日常的に目にします。おそらく現場を知らない方の想像をはるかに超えるほどではないでしょうか。
介護職の離職理由の一つでもある「利用者からの暴力やハラスメント」について、今回は施設入居者の例を基にお話しします。
入居者の暴力でありがちな「介護抵抗」
私は現在の職に就くまでに数回の転職を経ているのですが、介護施設で仕事をしたのは施設ケアマネを含めて合計6年ほどになります。その間、何回入居者に暴力を振るわれたかと聞かれれば、「数えきれない」としか答えようがありません。暴力的なのは一部の入居者で、そういった方は日常的に暴力を振るってしまいます。
「なぜそんな暴力を許すんだ」と思われるかもしれませんが、実はいつでも誰にでも見境なしに暴力を振るうというよりも、「介護抵抗」で暴れる方のほうが多いようです。
介護抵抗は、文字通り“介護に対する抵抗”のこと。認定調査でも、認知症の判断項目に挙げられているほどよくある症状になります。排泄介助や起床、更衣、入浴介助など、施設では体に触れる機会が多いのですが、そういった際に抵抗し、暴れたり噛んだりつねったり叩いたり蹴ったりされるのです。

介護抵抗されるからといって、こちらが介護をしないわけにはいきません。叩かれたからといってやり返してしまえば、入居者に怪我をさせてしまうかもしれません。結果として、生傷が絶えないこともしばしばです。
介護抵抗は、入居者にとって必要なことをしているのに、こちらが悪者扱いされて抵抗されるので、肉体的だけでなく、精神的にもつらいものがあります。
悪意のある暴力やハラスメントも発生する
介護抵抗は、以前から現場で問題視されてきました。しかしそれとは別に、悪意のある暴力や悪質なハラスメント行為をされることもあります。
私の印象としては、在宅介護の方が多いように思いますが、施設でも起こることがあります。例えば、以下のような例です。
- 何でもかんでも言いがかりをつけて威圧する
- すぐに暴力を振るう
- 攻撃的な物の言い方やセクハラ行為をする
こうした行為は、認知症や精神疾患の周辺症状の有無にかかわらず、悪意を持って行われます。
介護現場で暴力は「仕方のないこと」!?
介護職員と入居者の関係でなければ事件になるだろうというレベルの悪質な行為が、介護の現場では「仕方のないこと」として見逃されています。
介護職員が「相手は入居者だから仕方がない」と諦めてしまうケースもありますし、上司や管理職に訴えても、「入居者だから我慢しなさい」とか「それも仕事だから」と、抑えこまれてしまうこともあります。そのため、なかなか表には出てこないのです。
個人的には、介護抵抗も悪意のある暴力も、介護職員がつらい思いをするのは同じで、もっと世間に周知して職員を守る方法を考えるべきだと思っています。
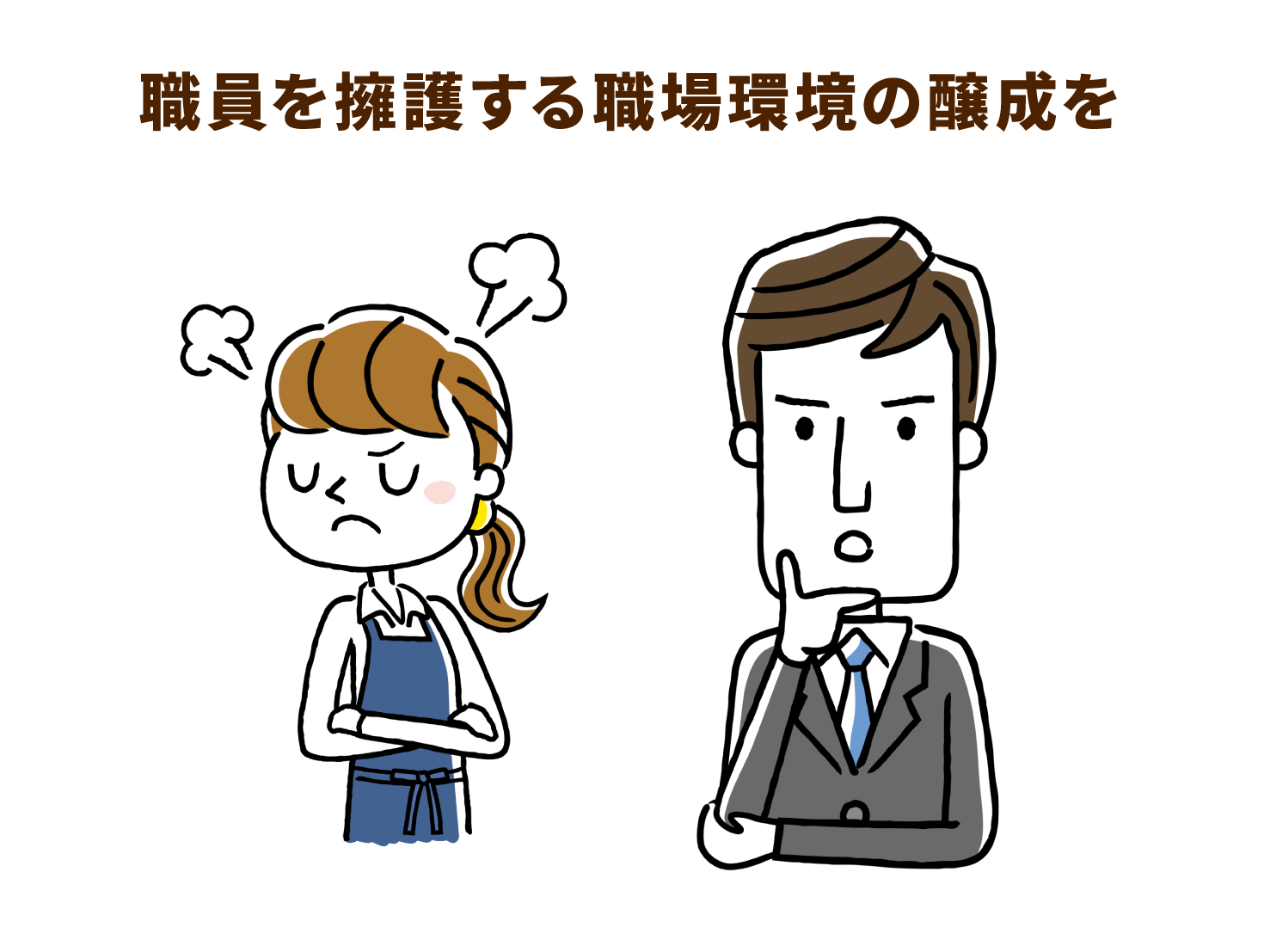
職員同士での情報共有と上司の態度を見極めることが大切
さて、ここまではありがちな事例をお話ししてきました。しかし、今回の記事では介護職員が「つらい思いをして働いているんだ」とアピールしたいわけではありません。介護職員の方に「自分の身を優先して守ってください」ということを伝えたいのです。
介護職として働く以上、悪意の有無にかかわらず、暴力やハラスメントの被害にあうことは避けられません。ですが、だからといって必要以上に我慢する必要はありません。
介護抵抗であれば、ある程度慣れてくると「この人はこの介護のときに手を出してくることが多いな」と予想できるようになります。予想できれば、比較的抵抗されることの少ない方法を職員同士で共有したり、複数人で介助して被害を最小限に食い止めるなどの対処ができます。
職員を変えると、ご本人の怒りの矛先が変わってうまくいくこともありますし、性別によって暴力を振るわれないこともあります。まずは職員同士で情報共有をして、いろいろと試してみてください。
悪意のある暴力やセクハラなどの行為がある人の場合は、複数人での介助が理想的。ですが時間帯によってはそうもいかないことがあります。
その際は、居室の扉を少し開けておくなど、何かあればすぐに逃げられるようにしておくと良いでしょう。殴られたり、度を越したハラスメントを受けてまで介護を続ける必要はありません。
こうした対応ができるかどうかは、施設の方針や上司の考え方で大きく変わります。介護職員への暴力問題で、最もネックになっているのは「介護職員ならそれくらい我慢しないとだめだ」という考え方や、それを職員に強要する施設のあり方だと私は考えています。
現在、私は居宅介護支援のケアマネとして働いていますが、施設のみならず、在宅の事業所でもこのあたりの差はとにかく大きいと感じています。問題を起こす利用者をすっぱり切ってしまう施設もあれば、現場の職員に我慢をさせる施設など対応はさまざまです。
身の危険を感じているのに、上司が親身になってくれないのであれば、その施設の考え方が間違っていると思っても構いません。実際、職員を守ろうと考えてくれる施設もたくさんあるからです。
環境が変わらないのであれば、転職するのも一つの解決策だと考えています。
入居者の人権ももちろん大切ですが、介護職員にも人権があり、守られるべきものであることを頭に入れておいてくださいね。