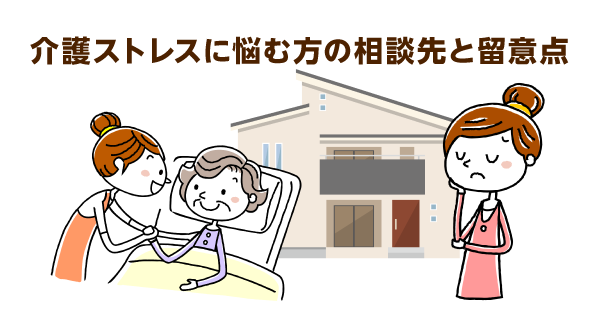皆さんこんにちは。医療と介護の連携支援センター長谷川です。
今回は「介護従事者が行う、医療依存度の高い方への支援」をテーマにお話します。
「介護従事者が行う非医療行為とは」「医療依存度が高いということはどのようなことか」 の2点についても説明します。
介護従事者が⾏う⾮医療⾏為は爪切りや口腔ケアなど
まず、「介護従事者が行う非医療行為とは」について説明します。
介護保険が施行された2000年から5年後の2005年に厚生労働省から出された通知「医師法第17条、歯科医師法第17条および保健師助産師看護師法第31条の解釈について」によると、医療行為ではないとされているものは次の通りです。特に薬を用いる行為や爪切りには注意が必要です。
非医療行為(2005年時点)
- わきの下や耳での体温測定
- 自動血圧計による血圧測定
- 新生児以外で入院の必要がない方へのパルスオキシメーターの装着
- 切り傷や擦り傷、やけどなどの応急処置および汚染時のガーゼ交換
- 軟膏塗布(褥瘡の処置を除く)
- 湿布の貼布
- 点眼
- 座薬挿入や点鼻薬噴霧の介助
- 一包化された内服薬の内服介助
- 口腔ケア(重度の歯周病などがない場合に限る)
- 耳かき(耳垢が完全に耳をふさいでいる場合を除く)
- パウチ内の汚物を捨てること
- 自己導尿を行う際のカテーテルの準備や姿勢保持
- 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸を用いた浣腸
薬を用いる行為
- 事前に本人や家族からの依頼がある場合に限る
- 使用する薬剤は医師からの処方薬であること
- 薬剤師の服薬指導や看護師からの指導をもとに使用する
爪切り
- 巻き爪や基礎疾患に糖尿病などがある方などは専門的な管理を必要とする
- ケアを行う中で医療行為か否か判断に迷った場合は、主治医やケアマネージャーなどにアドバイスや判断を仰ぐようにする

医療行為の線引が曖昧で、判断に困る状態が多発していた
なぜ、厚生労働省が上記を「医療行為ではない」と位置づけたと思われますか。
介護保険が施行されて5年が経ち、介護現場において上記の行為が数多く行われてきました。
介護保険施行開始時は、あくまでも上記の行為を行えるのは医療職員のみと限られていました。
ただし、介護保険事業所に必ずしも医療職員がいるとは限りません。
医療職員がいたとしても、配置人数は少なく、より重度な医療行為を行うことに優先度が置かれていました。
声高には言えませんが、その中で介護職は上記のような医療行為を介護保険開始当初は行っていました。
そもそも施設での介護や在宅介護に従事する介護職は、医療行為を行うことはできません。
しかし、高齢者や障がい者の介護現場では、医療行為にあたる行為とそうでない行為の線引きが曖昧なため、判断に困る状況が多発していました。
例えば、湿布の貼付や体温測定、血圧測定など。私たち自身も日常生活で当たり前に行う行為ですら、医療行為に含まれるのかどうか判断に悩みました。
そこで、現場が混乱しないように、上記のような形で厚生労働省は「原則として医療行為にはあたらない」と考えられる項目を具体的に示すこととなったのです。
その後、2012年には、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法などの一部を改正する法律」のもと、介護福祉士、および一定の研修を受けた介護職員などにおいて、たんの吸引や経管栄養が認められるようになりました。
ここで大事なのは、「医療行為ではあるが、一定の研修を行うことで実施可能となり、2005年の通知とは異なる」というとこです。
研修を行うことで実施可能な医療行為(2012年)
- たんの吸引(口腔内や鼻腔内、気管カニューレ内部)
- 経管栄養(胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養)

介護職員も医療行為が可能になった要因は「医療依存度が高い方」と「要介護者」の増加
このように日常的に行われることは、医療行為ではないことが明確になり、研修を受けることによって実施可能な医療行為についても明確化されました。
これまで医療行為は、あくまでも医師や看護師などの免許を有するものが「業」として行う行為のことを指していました。
介護職員も医療行為を行えるようになった要因としては「医療依存度が高い方の増加」と「要介護者の増加」が挙げられます。
「医療依存度が高い」とはどういうことでしょうか。
医療依存度が高い状態
- 吸引が必要
- 酸素療法や経管栄養、人口呼吸器装着、IVH(中心静脈栄養)、透析が必要な状況
- 医者にかかる割合が高くなっている
- 医療を施さなければ生活が困難
介護の現場で耳にする「介護度が高い」や「介護度が重い」という言葉に似ている印象でしょうか。
医療が発展していく中で、今までは医療機関で過ごされていた方が、病院と同じような環境や状況で自宅で過ごせるようになったり、在宅でも高度な治療が行えるようになりました。
そのため、介護を担う家族やサービス事業所は今まで以上に専門的な医療知識が必要になりました。なので、家族やサービス事業所の負担は増したように思います。
「医療依存度が高い方」が増加したことで、医療行為と非医療行為の線引きが明確化されたと感じています。

今後、医療依存度の高い方は増加する見込み
今まで以上に医療依存度の高い方が自宅で過ごす割合が高くなるということは、在宅で要介護者を支えるために必要なサービス自体に、医療的なケアや視点が求められることになります。
今までは、病院や施設で過ごされてきた方が自宅で過ごす場合、住環境の整備が急務です。そして、下記する医療依存度が高い方をサポートするサービスや施設は、要介護者が望む場所での生活を支えていくために欠かせないものです。
医療依存度が高い方をサポートするサービスや施設
- 訪問介護
- 訪問看護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
今後も、医療依存度の高い方は増加していくことが予想されています。今までは「退院できない」「施設でないと生活できない」と、自宅に戻ることをあきらめていた方の受け入れを行うためにも、介護従事者への支援は欠かせないと考えます。