今回の「みんなの介護座談会」は、高校時代からの友人関係にある介護経験者3名にお越しいただきました。「井戸端会議には不思議な力がある」。そんなお声も飛び出し、いろんなお話を伺いました。「ま、いっか」なエピソードは必見です。
この記事に登場するみなさんのプロフィール(敬称略)
60代。要介護1の実父(93歳)と要支援1の実母(87歳)と同居している。父は、デイサービスを利用しながら在宅介護中。母は要支援1がついているものの、家事などは自分でできるため、父の世話を手伝ってくれている。母は少しうつ傾向があり、神経質。介護自体の大変さもあるが、父と母のやり取りの間に挟まれるのも厄介に感じている。
60代。2年前、実父の死をきっかけに、ご主人と一緒に実母(87歳)の家に引っ越してきた。同居前は実父と実母の2人暮らしだった。母は歩行にふらつきがあり、伝い歩きで移動している。歩けなくなったことから家事などの意欲が低下。現在は母の食事づくりや掃除などをして世話をしている。要介護度はなし。
60代。3年前に義母の在宅を経験している。その時の要介護度は2。94歳で義母は亡くなる。介護のきっかけは転倒により骨折を繰り返したことだった。大腸がん手術も重なりADLが著しく低下。その後は、加藤さんとご主人が義母の家に通い、それ以外の時間は訪問介護サービスを利用しながら過ごしていたものの、ますます身体が弱り、ついに同居することに。
介護以外にも悩みは多い
みんなの介護(以下、―――) 「古くから」のご友人同士のみなさまにお集まり頂きました。お互いにとっては、“改めて”となってしまいますが、自己紹介をお願いできますか。

山田
山田です。94歳になる要介護度1の実父と要支援1の実母、夫の4人で暮らしています。
父は最近デイサービスを利用しているので、通院の付き添いをサポートしています。尿や便をときどき漏らしてしまうので、そういった対応もしています。あと、最近は薬の管理ができなくなってきていて……。薬の管理もしています。
要支援1の母はわりと「しっかり」しているので、私が仕事に行っている間は、父の食事の世話などをしてくれています。
「しっかり者」だというお母さんと一緒にお父さんの介護をしている山田さん。
通院や介護サービスの手続きは山田さんがサポートし、生活の補助はお母さんが近くでサポートしています。お母さんはお父さんと同じ部屋で過ごしているので、必然的にお母さんが介護に関わる時間が多くなるようです。
――― ありがとうございます。続いて森口さん、お願いできますか。

森口
森口です。以前は他県に暮らしていたのですが、2年前、実父が亡くなったことをきっかけに、実母が住む家に引っ越してきました。
当初は「しっかりしていた」母も、足が悪くなり足取りがおぼつかなくなってからは、外に出る機会がなくなって。……それをきっかけに家事への意欲もなくなってしまいました。今は、私が食事をはじめとした家事の世話や買い物に連れていくなどの生活全般のサポートをしています。
要介護度認定を2度申請するも介護度がつかず、介護サービスは利用せずに在宅でお母さんのサポートをしている森口さん。森口さんのお母さんは、歩行時にふらつきはあるものの、壁をつたいながらなんとか歩ける状態です。
――― ありがとうございます。最後に加藤さん、お願いできますか。

加藤
加藤です。私は過去の話となります。
6年前くらいまで、介護をしていた義母がいました。94歳で亡くなりました。介護のきっかけは、転倒により骨折を繰り返したことでした。大腸がん手術も重なって、身体が弱ってきた時期でした。
その後は、私と夫が義母の家に通い、それ以外の時間は訪問介護サービスや食事の宅配サービスを利用しながら過ごしていました。だけど、食が細かったこともあって身体がますます弱ってしまったことと、認知症も進行してきて「火のこと」が心配になってきて。結局、最後は同居することにしました。その時の要介護度は2でした。
私も夫も働いていたので、デイサービスに週5回通ってもらいながら、家にいる時は生活のサポートをしていました。
同居してから3年間、デイサービスを利用しながらお義母さんの介護をされていた加藤さん。ご主人は介護に協力的な方で、お二人で協力しながらお義母さんの介護をしていました。お義母さんはもともと食が細かったこともあり、食事面が一番大変だったといいます。
――― ありがとうございました。山田さんは、お母さまと一緒にお父さまの介護をされているとのことでしたが、ご自身のご負担はいかがですか。

山田
うーん…。ありがたい部分は確かにあります。こうやって今日座談会に来られたのも、母が家にいてくれて何かあったら連絡くれる安心感がありますからね。
私は短時間ですけど仕事をしているので、日中の父のご飯などの世話は母がしています。
ただ、母は母で本当に愚痴や文句が多くて…。母は要支援1で元気ではあるのですが、少しうつ傾向があって神経質なんですよ。

加藤
元気なお母さんから見ると、自分の夫が認知症であることにイライラするんだろうね。娘の山田さんから見る感覚とは違った感じで。

山田
そうかもしれない。この前は、母が脱いで洗濯機にいれた服をなぜか父が着ていたみたいで、怒り狂っていましたね。
私からすると「認知症なんだし、しょうがないでしょ」と思うことでも、母は許せないみたいで。
しかも父は、足が悪いながらも自転車には乗れるんですよ。だから近所の人からもぱっと見は元気そうに見えるようで。

森口
自分は家で苦労しながら世話してるのに、周りの人には元気そうに見えてたらそりゃ腹立つよね(笑)。

山田
そうなのよね。母は父の世話をして普段イライラさせられているのに、周囲から見て元気そうなのに時々腹が立つようなんです。私も私で、そんな母からの愚痴に毎日付き合わされるのも疲れるんですよ。
愚痴以外にも結構色々思うとこがあるみたいで、全てに口を出されると、それはそれで面倒なんです。
――― 特に「面倒だ」と思うことは、どんなことですか?

山田
例えば、病院にしてもデイサービスにしても、対応が気に入らないと簡単に『もう行くの辞めたほうがいい!』とか言うんですよ。その手続きとか面倒なことをやるのは私なのに。
「ま、いっか」は心のバランスを保つ秘訣
――― 山田さんも大変な思いをされたのですね。

山田
本当にそう!
だから、「もう好きにして」って感じで「ま、いっか」って思うようにしてるんです。良く言えば本人達の意思を尊重しています(笑)。
父のこともそう。尿や便を失禁したり、母が忘れていたことを何かと私のせいにしてきたり(笑)。つい最近なんかは「尿道に血液が溜まって尿が出にくい」っていうので、尿カテーテルを入れるようにしたんですが、それにも文句を言われて……。
まぁ認知症があるとはいえ、クリアな部分も多いからしょうがないんですけどね。そんなことばかりで、どっと疲れることもあるんですが、それも全て真に受けずに最後は『ま、いっか』で片づけるようにしています。
山田さんのお父さんが「生活しづらい」と言うことに対しては、心配して模索しながら試してみる山田さんです。でも、それに対してお母さんとお父さんから「文句」を言われると、自分のしていることまで否定されているように感じられ、“やりきれない”に気持ちになるそうです。しかし、それを真に受けすぎて自分の心が壊れないように「ま、いっか」と気持ちをリセットしてバランスを保っているそうです。
――― 森口さんのお母さまは要介護認定を2度申請し、要介護度が「つかなかった」とのことでしたが、当時の状況を詳しく伺えますか?
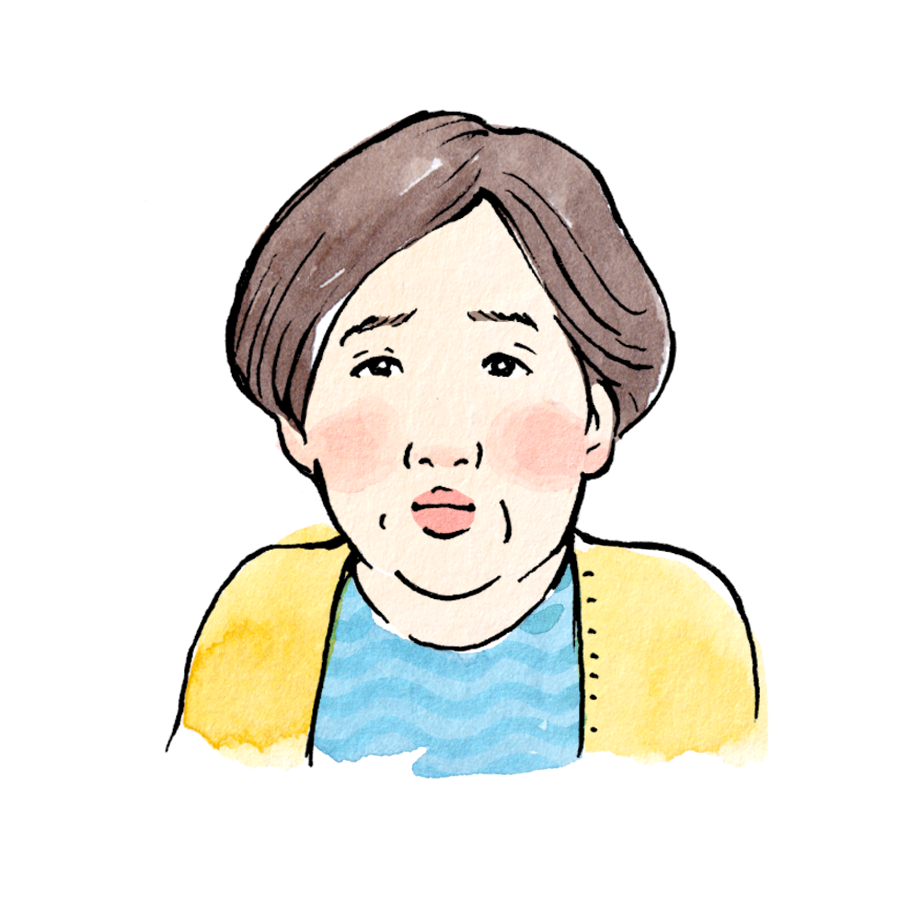
森口
はい。要介護認定を申請したきっかけは、家で閉じこもり気味な母をデイサービスに通わせて、外に出る機会を作ってあげたい思いからでした。
満足に歩くことができないことで、あらゆることに段々とやる気をなくしてしまったんですよね。本当に毎日テレビを見ているくらいしかすることなく、家事もやる気にならないみたいで、全然手を付けなくなってしまったのです。
でも最近、近所の人がデイサービスに行きだしたことをきっかけに、本人が少しデイサービスに興味を持ちだしたので、それで認定受けてみたんです。

加藤
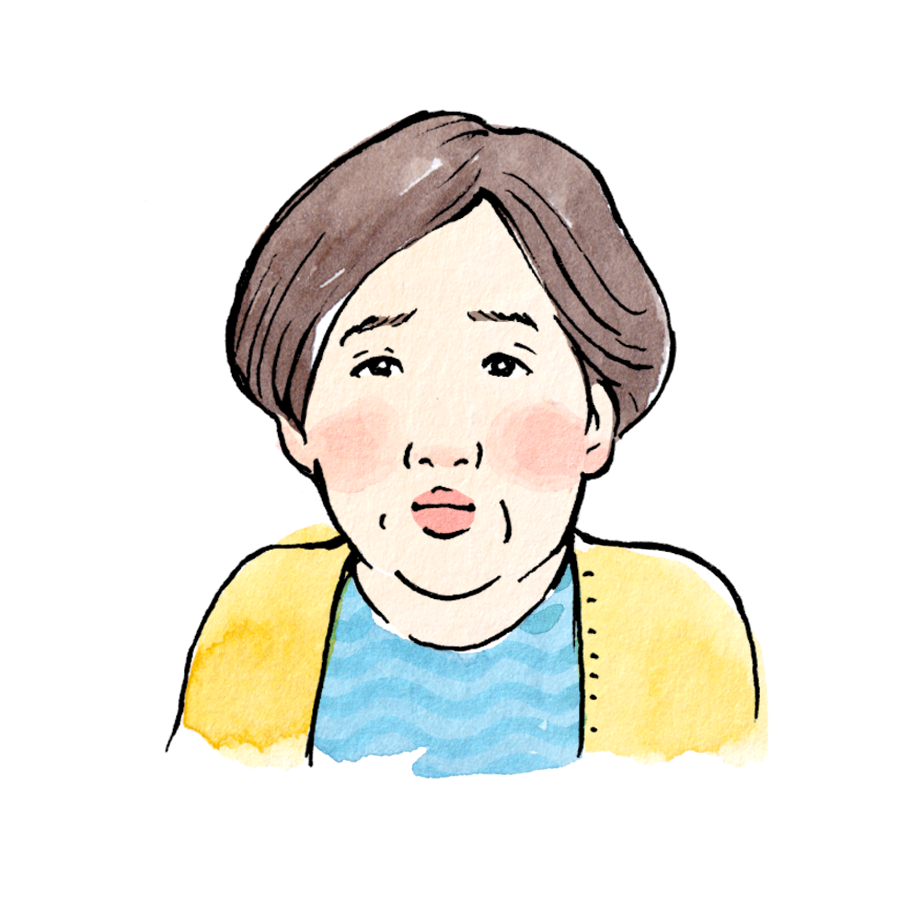
森口
それがさ、認定員の方が来てくださって、足がどこまで動くかとか寝返りを見てくれるんだけど、その時ばかりはすごくしっかりするのよ!
認定員さんに声をかけられると普段では考えられないくらいの反応と表情で「はいっ!」なんてはっきり答えちゃって。「しっかりした人」を演じようとするのよね。

山田
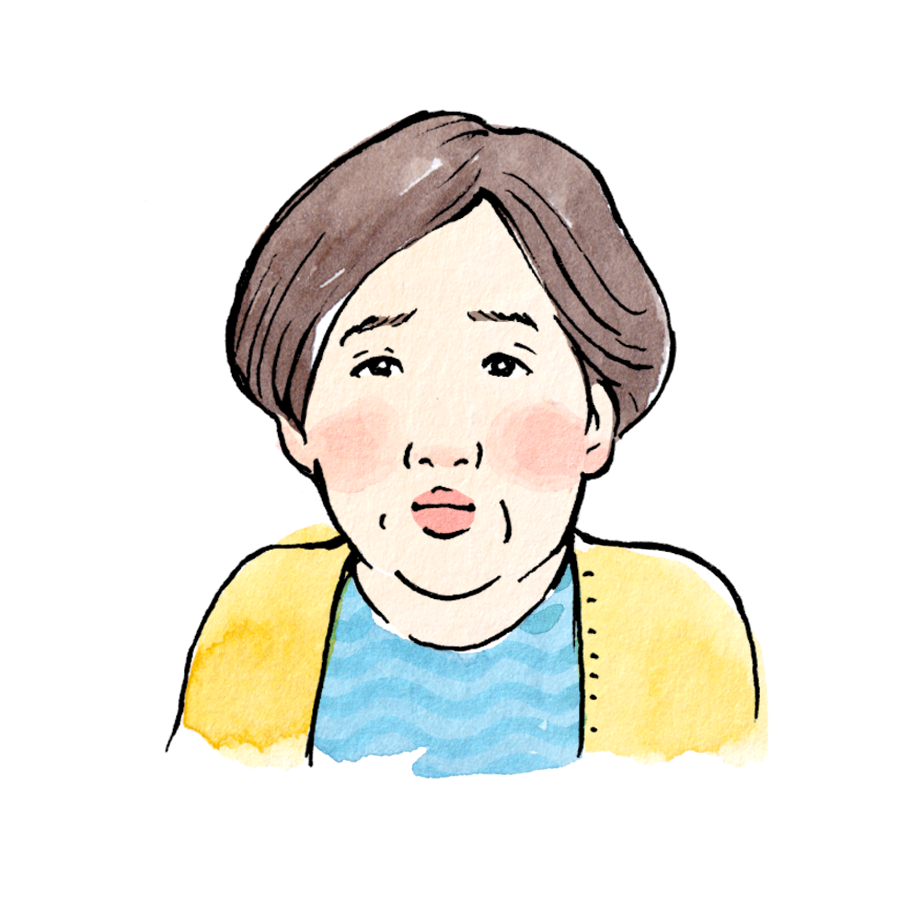
森口
いつもは上がらない足があがったり、聞かれたことに対しても全てはっきり答えたりしちゃってさ! 結局、要介護度がつかなかったんだけど、本人は「介護は必要ないって言われた」って、またそれを嬉しそうに話すわけ!

加藤
自分はしっかりしているって言われたみたいで嬉しいんだろうね。
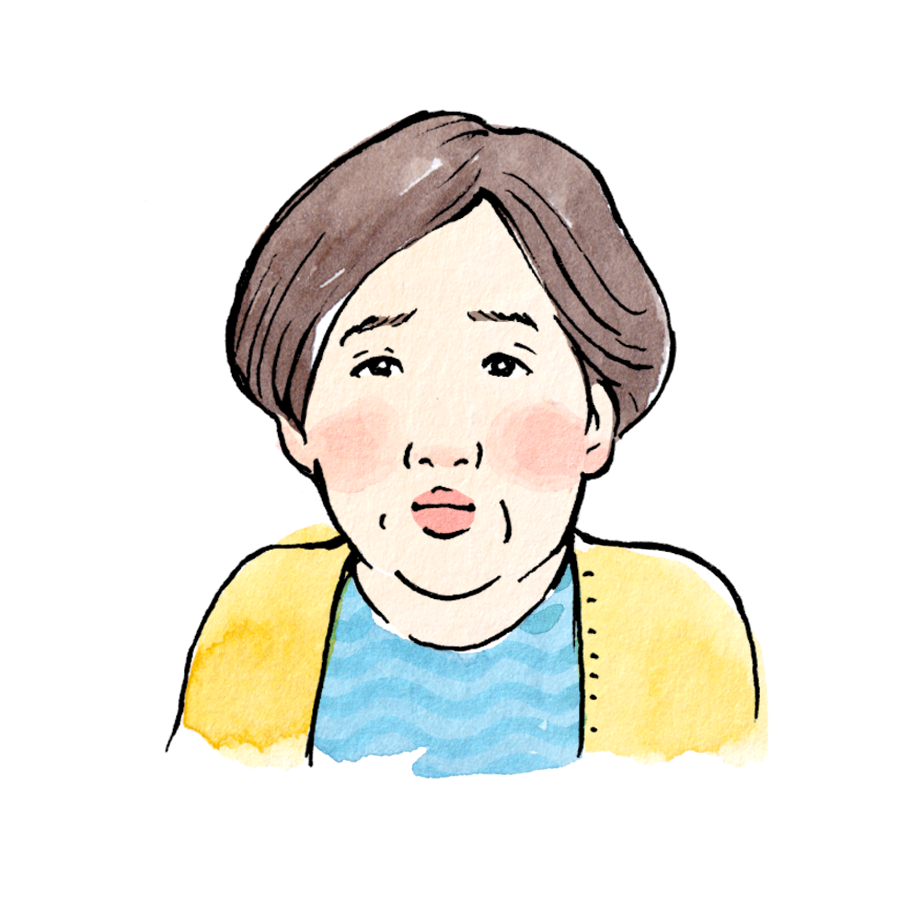
森口
たぶんそうだと思う。なんだかんだで、要介護度がつかないことで、自分のプライドを保ちたい気持ちもあるんだよね。
「介護家族には負担な介護の正論
――― 森口さんはお母さまとのご関係で、なにか他に感じられたエピソードはありますか?
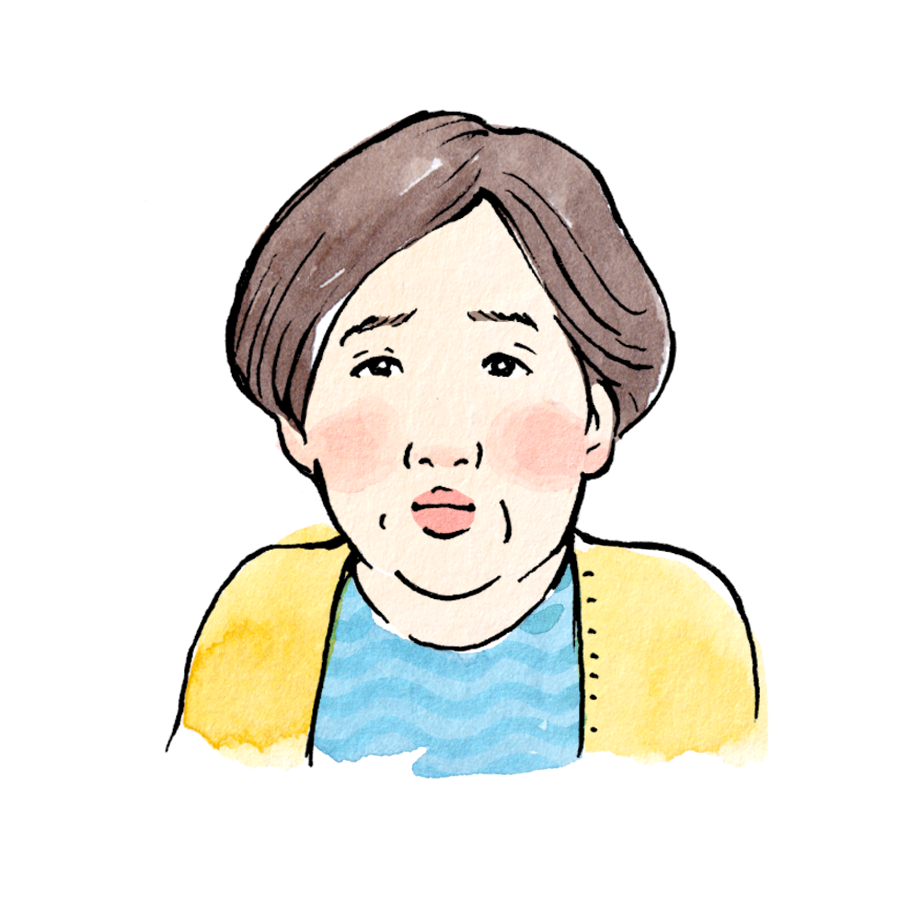
森口
あ、そうそう! つい最近の話だけど、スーパーに母と一緒に買い物に行ったのね。母がとても大きな山芋を買おうとしていたわけ。
それで、私、怒ったわけではないんだけど、驚いて思わず「え?!そんな大きいものいらないでしょ!」って大きな声で言っちゃったのよ。
それを見て、私が怒っていると勘違いした女性から「あなた、お年寄りには優しい声掛けが良いのよ」って言われちゃって。
聞けば、その方、介護士さんなんだって。「私、介護の仕事をしているから、お年寄りの接し方は知っているのよ。もっと優しく話しかけたほうがいいわ」って。
いつもしているやり取りも、「キツイ」と捉えられることがあるんだなと、その時は気をつけようって思った。
食べたいものを自分で選んでもらおうという考えで、週に数回、お母さんをスーパーにお連れしている森口さん。
介護士の方とのエピソードは「思い違い」があったようですが、介護士の視点では普段のやり取りが「キツくみられる」と知り、森口さんは反省したそうです。

加藤
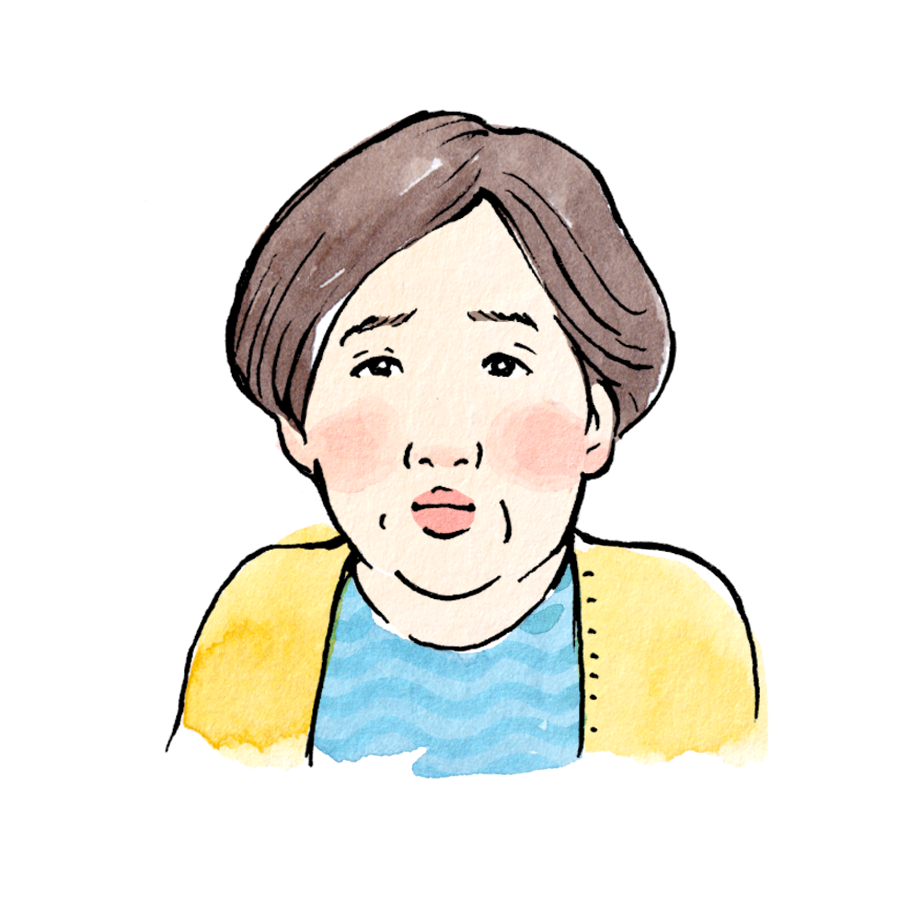
森口
「そうなんですね……」ってその時は反省したけど(笑)。でも、介護士さんが利用者さんに関わることと家族が関わることって違うからね。

山田
確かに、森口さんは明るいから真に受けないけど、それを言われた相手が切羽詰まった家族だったら悩んじゃうかもね。悪気なく言った言葉でも……。
その介護士さんの言うこともわかるのよ。でもさ、介護士さんがする「介護ケア」と私達身内がする「介護」は違うものね。そこは理解してほしいよね。親との関係性だって、昨日今日始まったものではなく長い間、色々な背景があって今に至るわけじゃない。
例えば、スーパーで子どもを叱る親だって、そこだけ切り取られたら「ひどい親」だけど、そこに至るまでに色々な理由があったのかもしれない。毎回同じことする子供にはやはりきつく叱るし。でもそれってその場だけ見たら周囲にはわからないもの。
だから周りの方も助言するなら、もう少し相手の背景を想像したりとか、慎重になったほうが良い時もあるのかもしれないね。
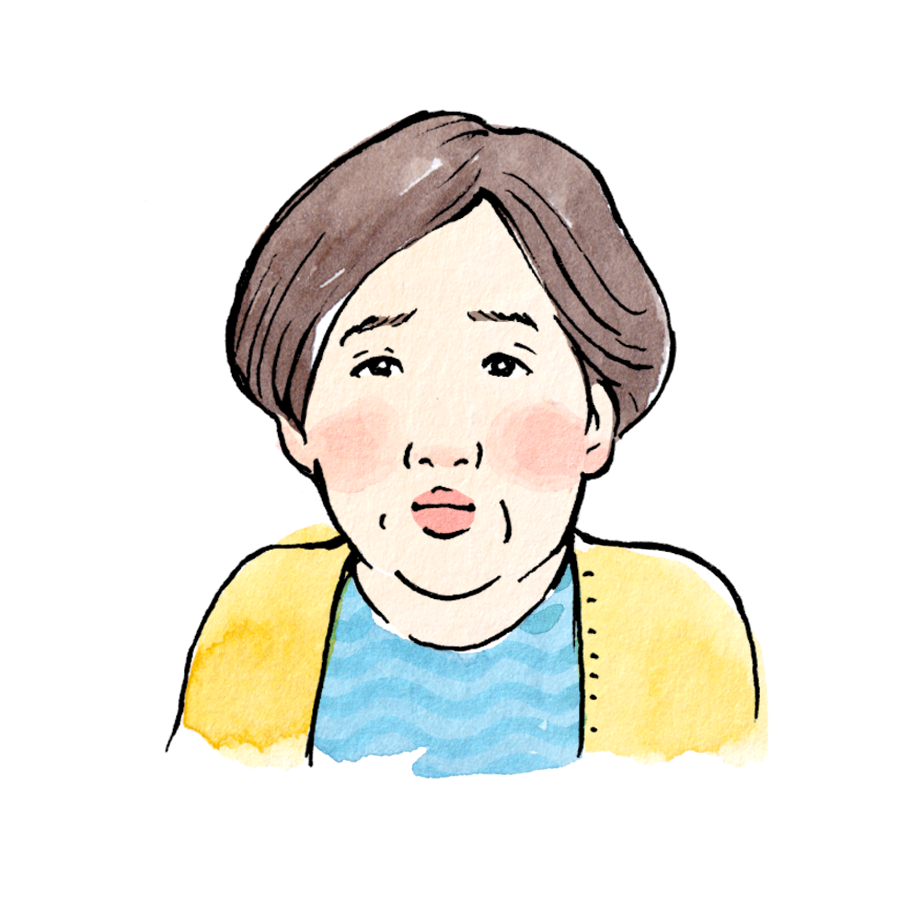
森口
そうそう。でもその話もそうだし、私も母と暮らすようになっていろんなことがあるけど、山田さんがさっき言ったように、どこかで『ま、いっか』って思うようにしてる。

加藤
――― みなさまの「ま、いっか」なエピソードがありましたら、もう少しお聞かせください。
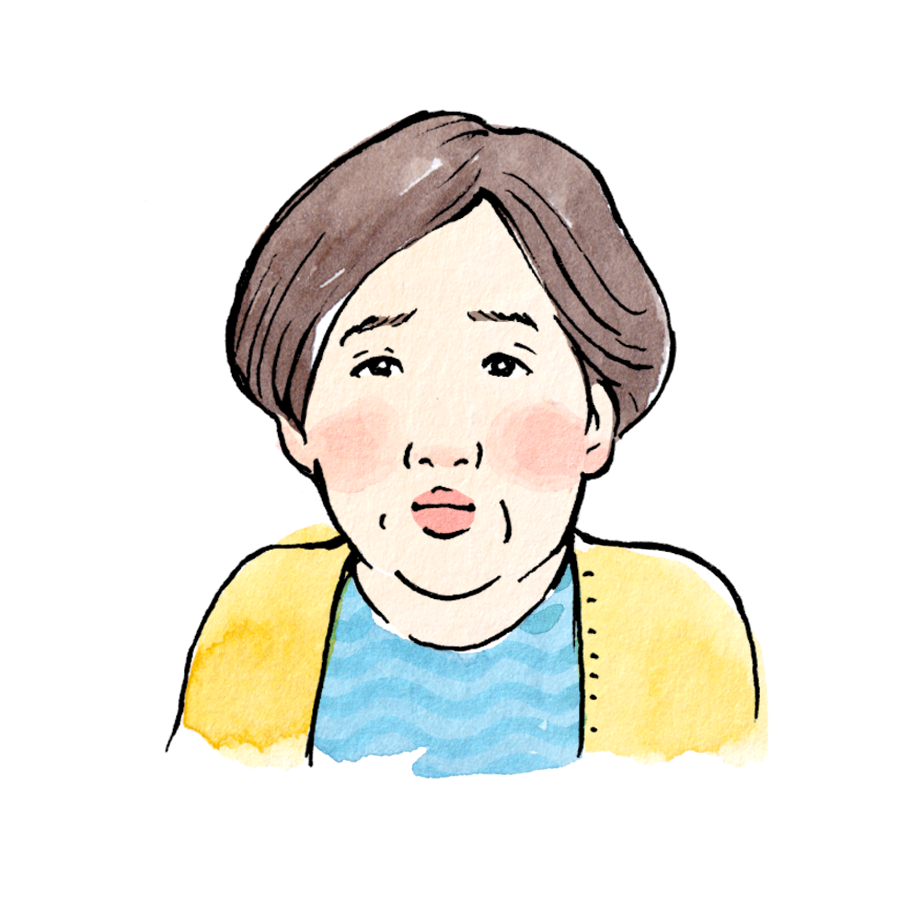
森口
私は母の「片付け」に対する考え方が苦手で……。私が片づけようとすると「それはダメ!」とか「あとからきたくせに」とかなにかと“いちゃもん”をつけて、片付けさせようとしないんです。最初は無理矢理にでも捨ててやろうと思ったんだけど、一緒に住むうちに「ま、いっか」って思うのも大事かなって。

加藤
ある程度理解してあげるほうが、こっちも精神的に楽だったりするしね。

山田
そうなのよ。自分までこだわっていると疲れちゃう! 私も我慢するわけではないけど、いちいち母や父と言い合わないようには工夫している。その工夫が「ま、いっか」って思うことなのかもしれない。
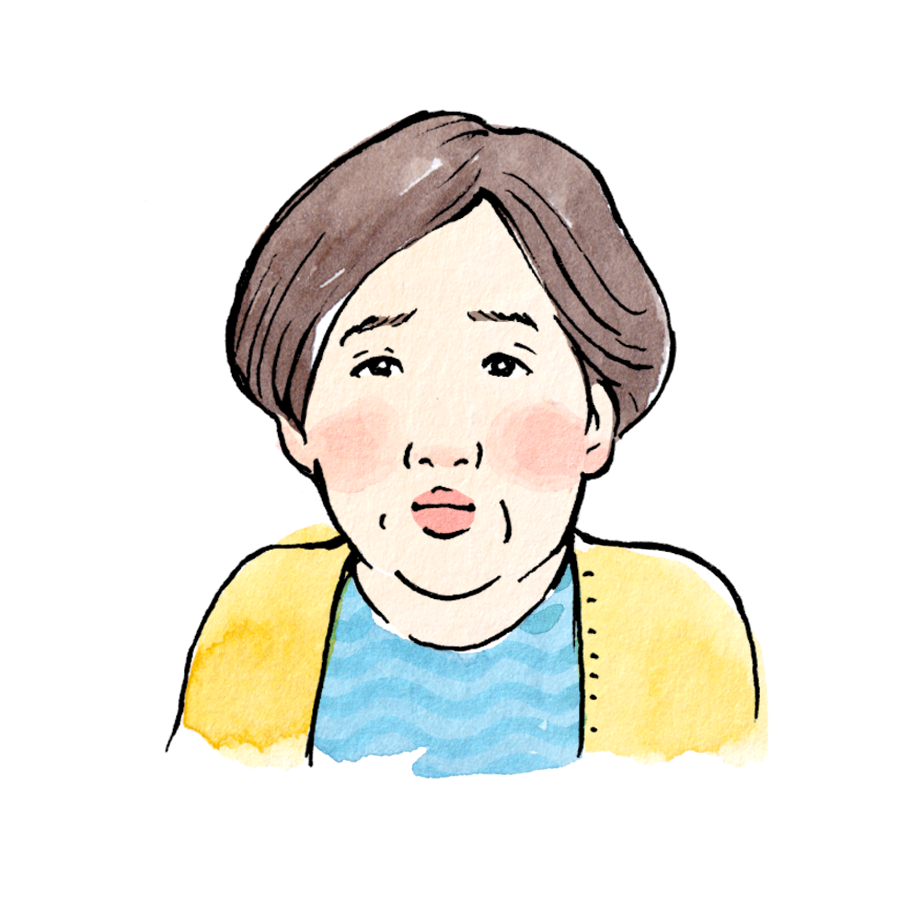
森口
だってもう長年生きてきた感覚を娘にあれこれ言われるのも嫌だと思うし、それで喧嘩になってもしょうがないじゃない。ある程度、こちら側が譲るっていうか……。なにもかも奪わず、本人らしくいられることが介護予防になるっていうこともあるしね。

加藤
私の夫は介護に熱心だったから、時々意見がぶつかることがあって。だけど、それも『ま、いっか』って考えるようにしていた。介護に協力してくれることはありがたいことだし、争いは無駄な時間になることも多いし。

山田
私はとにかく母と父の確執に「ま、いっか」かな。イライラすることもあるけど、そういう時はこうやって友達とお茶してあれこれ話すの。
介護の愚痴が言い合える友達の大切さ
――― 普段から「愚痴」を言い合う機会があるんですね。

加藤
愚痴が言える友達がいなかったら、はけ口がなくてストレス溜まりっぱなしだと思いますよ。みんな同級生だから、年代的に置かれる立場が重なるっていうのもあります。共感しやすいっていうか。
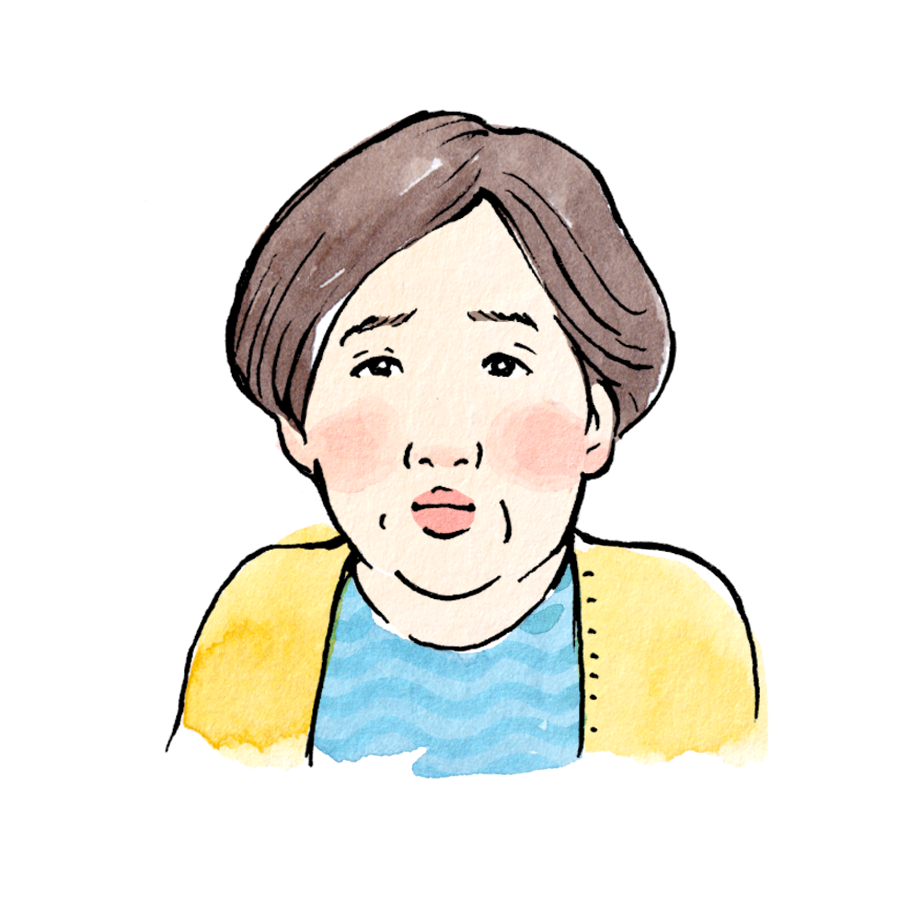
森口
みんなで話していると、イライラしていたこともいつの間にか笑いの「ネタ」になっていたりする。それで、スッキリして家に帰れるっていうね(笑)。
なにかあったら友達に話して最後は笑うことが一番! 深刻に考えすぎていたら、もたないわよ。友達の話で深刻なことは真剣に聞くけど、他は笑い合っちゃう! そのほうが「まぁたいしたことないか」って思っちゃうものね。

山田
介護って終わりがわからないものじゃない? だから、「解決策を考えよう」ってならないのよ。どっちかというと、置かれた今の状況をどう乗り越えようっていうか……。長期戦だからこそ、なんでも話せる友達って大事だと思う。
私の父と母の介護もいつまで続くかわからないけど、こういう時間があるうちは明るくいられる気がするわ。
――― みなさんのお話しぶりは、とても明るい印象です。

山田
おばちゃんがよく井戸畑会議をしていますよね。「なんの意味があるんだろう」って若い時は思っていたけど、いざ自分がこの歳になると女性が集まっておしゃべりすることに不思議な力があるのがわかるの。下手な本を一人で読むよりもよほどいい。会話の中で、これといった解決策なんてでるわけじゃないのよ。だけど、当事者同士であれやこれやと話しているうちに「あ、これってこういうことなのかも」ってふと、自分の中で解決できたりすることがあるの。
だから、深刻に悩んでいる方って、あまりそういう思いを人に言えなかったりするのもあるんじゃないかなって。
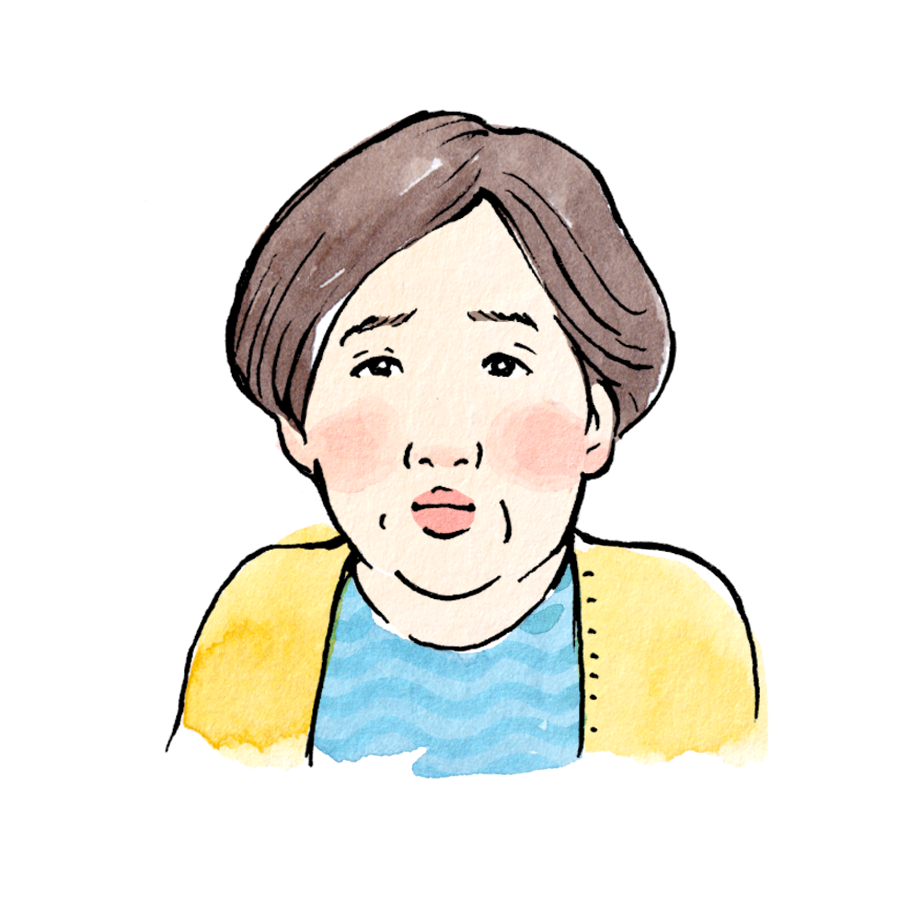
森口
今はネットとかでも、色々な人と繋がれるでしょ。近所に話す人がいなかったらそういう繋がりでとにかく誰かに吐き出すって大事かも。話しているうちに自分の気持ちが整理されてくることもあるものね。
人と人との繋がりによって介護の悩みや辛さを緩和していく。一人で抱え込まないことは大切なことであることをお話いただきました。
「ま、いっか」と切り替えたり、ご友人同士で愚痴を明るく話したりすることで、上手く乗り越えられるそうです。
からっと明るいイメージの3名でしたが、今の心境に至るまでには、苦労があったのかもしれません。
後編では、「介護のお悩み」についてお伺いします。

取材・文:中村 亜美
「みんなの介護座談会」へご参加頂ける方を募集しています
「みんなの介護座談会」は読者の皆さまに参加して頂く新企画です。皆さまの日々の介護に対する思いをぜひ座談会で語ってください。
以下のフォームより、ご応募をお待ちしております。
参加フォームはこちらをクリックしてください








 山田
山田 森口
森口 加藤
加藤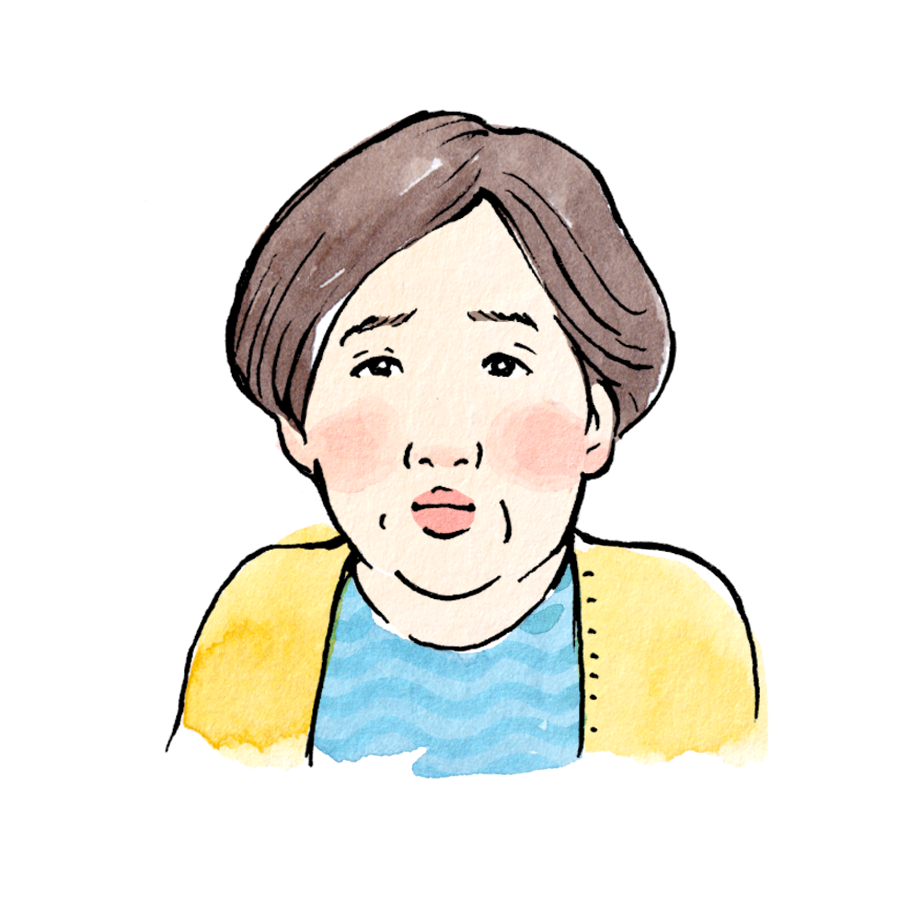 森口
森口 加藤
加藤