ご家族への「思い」があって介護職や介護に近しい分野でご活躍されている方々にお話を伺います。前編では、介護職の経験があるからこそ感じる「介護」の葛藤についてお話いただきました。後編では、介護をしたからこそ気づけたこと、介護で悩む方へのメッセージを聞きます。
この記事に登場するみなさんのプロフィール(敬称略)
元介護士。大学時代の恩師の言葉をきっかけに介護職へ。7年ほど高齢者施設に勤務。現在は総合スーパーで管理職として働く傍ら、予防医学を学んでいる。父の在宅介護を経験。
ケアマネジャー。息子の介護をきっかけにケアマネジャーへの転職を決意。重度の障がいを持つ息子と祖母の介護を母と行う。放課後デイや生活介護、訪問介護サービスも利用している。
介護施設の管理者。先天性脳性まひで生まれた兄と高齢の母と暮らしている。兄の力となるべく介護のノウハウを学ぶ目的で40代で訪問介護職に就く。
介護の「ストレス」
みんなの介護(以下、―――) 介護は“思いもよらぬ”ことが多いのではないでしょうか。「ストレス」を感じることはありますか。

天野
介護職をしていたときには、ストレスをあまり感じませんでした。あるとすれば……現場で自分が介護士として役に立てているのか、戦力として動けられているのか、利用者さんのために動けているのか、利用者さんのご希望に添えてるのか……といったストレスというよりも「悩み」はありました。
――― どのように悩みと向き合っていたのでしょうか。

天野
そうですね。車で通勤しているときに大好きな音楽をちょっと音量を大きくして、窓全開にしてかけたり……田舎で山道とかがあるのでできました(笑)。
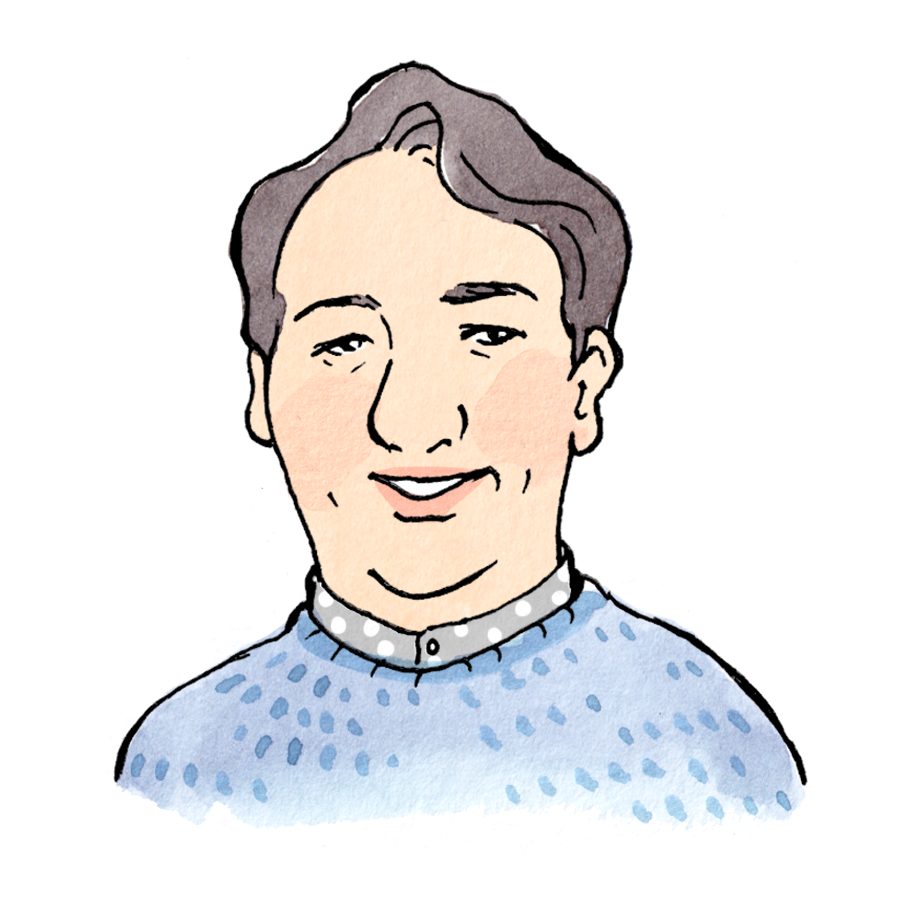
吉田
私はストレスがたまったときには、食べ歩きをしていますね。母と二人で食べ歩きするのが好きなんです。ストレスなくても食べ歩きしていますけど(笑)。おかげでどんどん太ってしまって。でも、食べることがストレス解消なんでしょうね。

白井
私は18年間、息子の介護をしてきています。「育児」なので、そんなにストレスは感じていません。強いていうとウチは犬を2匹飼っているのですが、その犬がですね、うちの息子が床に寝てるときにすペロペロと舐めるんです。
こっちは「何かあったらどうしよう!」とひやひやしますし、もう本当にビチャビチャになるし、息子も「止めて」って顔でこっちを見るのでそれがストレスといえばストレスですかね(笑)。
――― ご家族の介護とお仕事の介護の違いを教えていただけますか。

白井
そうですね。仕事と違って家族の場合は、“ちょっと”気を抜くところは抜けますよね。食事の際にも、仕事でしたら口の中に「綺麗」に運ぶことが普通だと思うんです。でも家族だとちょっとこぼしたり、ちょっとダラダラなったりしても「最後に拭けばいいか」って。
ただ“重い”のはきついですね。息子は身長159センチで体重が51㎏あるものですから、入浴介助や移乗動作の体の負担は大きいかな。それでも精神的なストレスとまでは至らないかな。
――― 家族だからこそ気を許せるのでしょうか。

白井
そうですね。仕事と家族とでは“視点”が違ったり、“丁寧さ”は変わります。それだけでなく、利用者さんの意思を確認しながら、その方の望んでいる介護をするというところが家族の介護とは違います。ざっくばらんにコミュニケーションを取りたい利用者さんだったり、丁寧な介護を求める利用者さんだったりと、色々なご希望があります。
“十人十色”なので仕事となるとモードが切り替わります。
介護をしていたからこそ気づけたこと
――― 介護を通じて“発見”されたことがありましたら教えてください。

白井
息子と外出するときは車いすなので、利用できるトイレやエレベーターについては、息子と一緒にいないときにも色々見るようになりました。
他にも障がい者の方が私の前を歩いてらっしゃったり、車椅子で困っていたりする方には手を差し伸べます。息子が障害を持っていたからこそ気づけた部分ですので感謝しています。
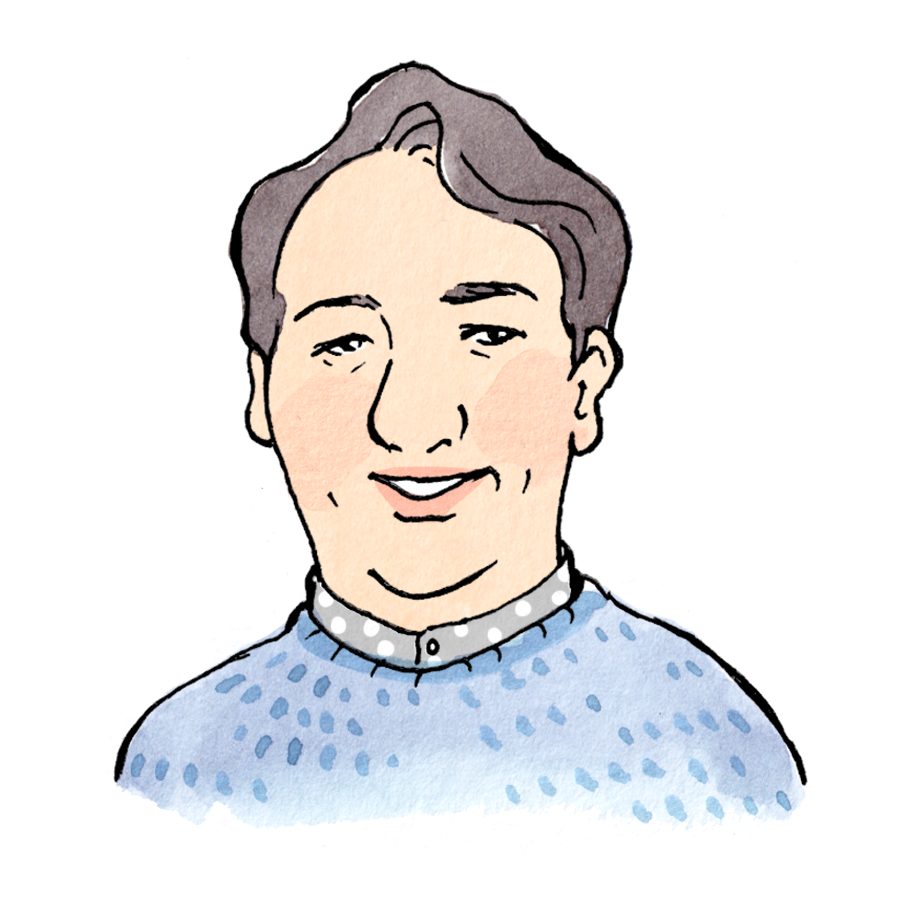
吉田
お答えになっているのかわかりませんが、介護の仕事に就いて皮膚の状況を見るようになりました。兄の支援をするようになったとき、首の周りに”ブツブツ“を見つけたんです。母に「首回りになんかブツブツあるけど」と言ったら「生まれつきなんだよ」と返ってきたんです。
支援していなければ気づくことはないじゃないですか。皮膚の状況に限らず、そういった「観察」みたいなのことは癖としてついてきたように思います。
吉田さんは仕事で介護をしているときも利用者さんの「皮膚の状況」を観察するようになったといいます。前日と「違い」があるようなときには声がけをして早めに診てもらうようにしているとのこと。
――― 天野さんはいかがでしょうか。

天野
私はガンで亡くなった父を看取っていますし、介護現場でも昨日話していた方の体調が急に悪くなって3日後にお亡くなりになられたという経験を何度もしています。看護師さんもそうだと思うんですが、「人が亡くなること」がすごく身近です。
人間っていつかは“平等”に死んでしまう、亡くなってしまう。そう考えると、何となく生きてる1日と、自分もいつか死んでしまったり、周りの人もいなくなっちゃったりすることを意識して過ごす1日では、充実感も全然違うと思うんです。
「人の死」を意識できるようになったことや、死生観ができたことは介護職に就いたからできた気づきで、すごく良かったなと思います。
――― 白井さんと吉田さんも介護されていた方の看取りをした経験がおありだと伺っています。

白井
私は父の看取りだけでなく、職場での看取りも経験しています。呼吸器をつけられた利用者さんでが亡くなられたことがあります。体が冷たくなってから器具を外すんですが、外すまでは胸が動いてる。最後の選択といいますか。呼吸器を付けたら「死ぬまで」付けていないといけないんです。呼吸器を付けないで亡くなるのかを選ばないといけないわけです。
呼吸器をつけるかつけないかで、感覚や考え方が変わってくると思います。私自身もこの仕事に入って初めて知ったので、呼吸器「ひとつ」付ける重要さや難しさを知りました。
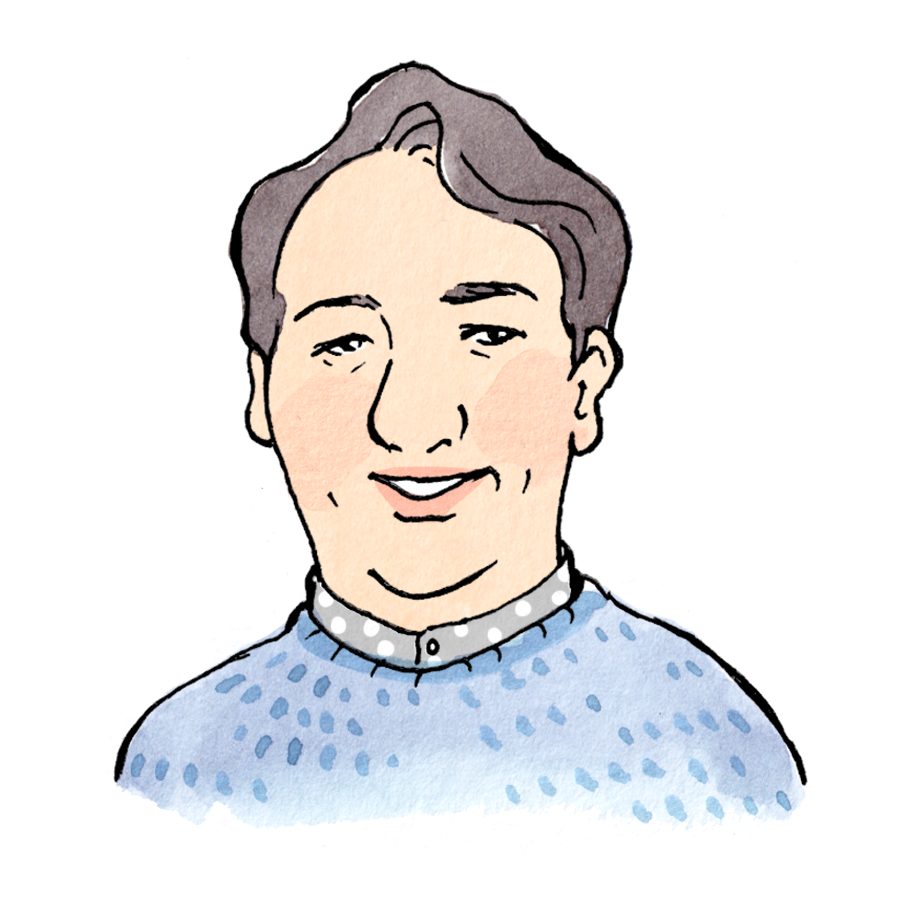
吉田
私の父は酒を飲み過ぎて肝臓が“やられて”亡くなっています。病院で看取りました。
利用者さんの看取りもしました。父もそうでしたし、利用者さんもそうですが、とにかくショックでしたね。「俺、こんな仕事をしてていいんだろうか」って思いましたし、「この先、やっていけるのかな……」っていうのはやっぱり考えましたよ。
父が死んだときは僕が手を握って息を引き取りましたけど、徐々にその親父の握る力が弱くなってくるんです。もう10年以上前ですけど、あの時の感触は今でも鮮明に覚えています。死ぬとわかっていましたが、呆然としました。
利用者さんの看取りを経験してずっと残っています。
一人で抱え込まずにみんなで支え合うのが大切
――― 本日はありがとうございました。最後に皆さんからお一言ずついただければと思います。

白井
子供の成長や子供の人生が私の生きがいです。私には3人の子どもがいるんですが、3人とも健常者だったらもしかしたら子供の人生が私の生きがいとは思わなかったかもしれません。一般的であれば、親元を離れて自立することがひとつの区切りなのかもしれませんが、障害の息子を持つことによって健常者以上に一緒に過ごす時間が長いんです。この先を想像しても離れることはないのかなとは思います。
子供の成長が私の人生そのものだし、生きがいになっているのかなと思っています。
お兄ちゃんとお姉ちゃんがいますが、いつかは親元を離れるでしょう。でも、吉田さんのところのように協力しあって弟の世話をする環境になると思います。ありがたいことにとても思いやりのある子どもたちに育ちましたし、家族の中にあの子がいたことで団結力が結構できたかなとも思います。
あの子が生まれたことに本当に感謝しています。障がい者が家族だからってマイナスのことだけじゃなく、本当にプラスのこともあるんだよということを最後に伝えたいな。
――― ありがとうございます。吉田さんもお聞かせいただけますか。
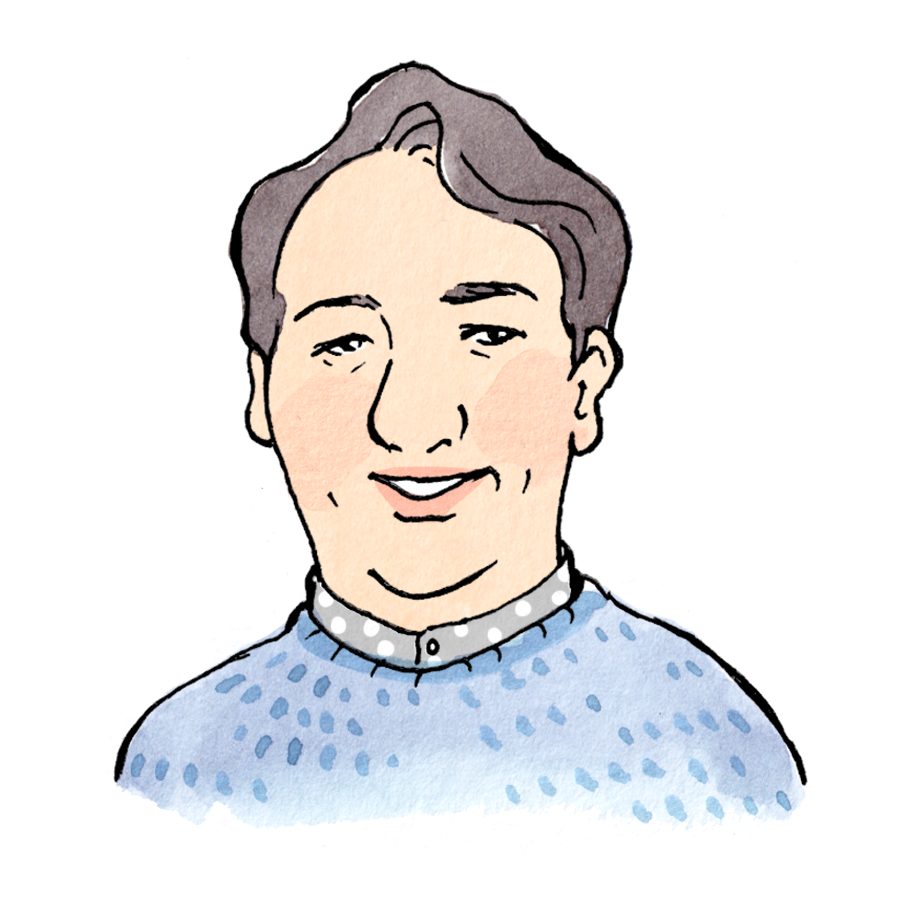
吉田
もし家族が介護を受ける状態になったら、まずは行政の方に助けを求めて欲しいです。自治体には障害福祉課というのがありますから、相談していただければ。新潟県で重度障がいの方がいれば私がお役に立てるかもしれません。
障がいをお持ちの方でも、高齢者の方でも、健常者の方だって1人では生きていけないと思います。だからみんなで支え合いながら生きて欲しいです。
みんなで支え合って生きていけるような社会になればいいなと思っています。……はい、私からは以上です。
――― ありがとうございます。天野さん、お願いいたします。

天野
一つの命は有限なので、いつか終わりが来るよというお話をさせていただきました。それは私自身もすごく感じているし、他の方にも1日1日を楽しんで過ごしてもらいたいなと思います。
「元気」だとなかなか意識しなかったりもするとは思いますが、もしかしたら急にパタンと倒れて病院に搬送されたりすることもあるかもしれません。交通事故で怪我をしてしまうこともあるかもしれない。
だから自分の健康や命について意識してもらえるような方を増やしていきたいと思って、今後も色んな方々に健康な身体作りや予防の大切さを伝える活動をしていきたいです。
――― 皆さま、本日は本当にありがとうございました。




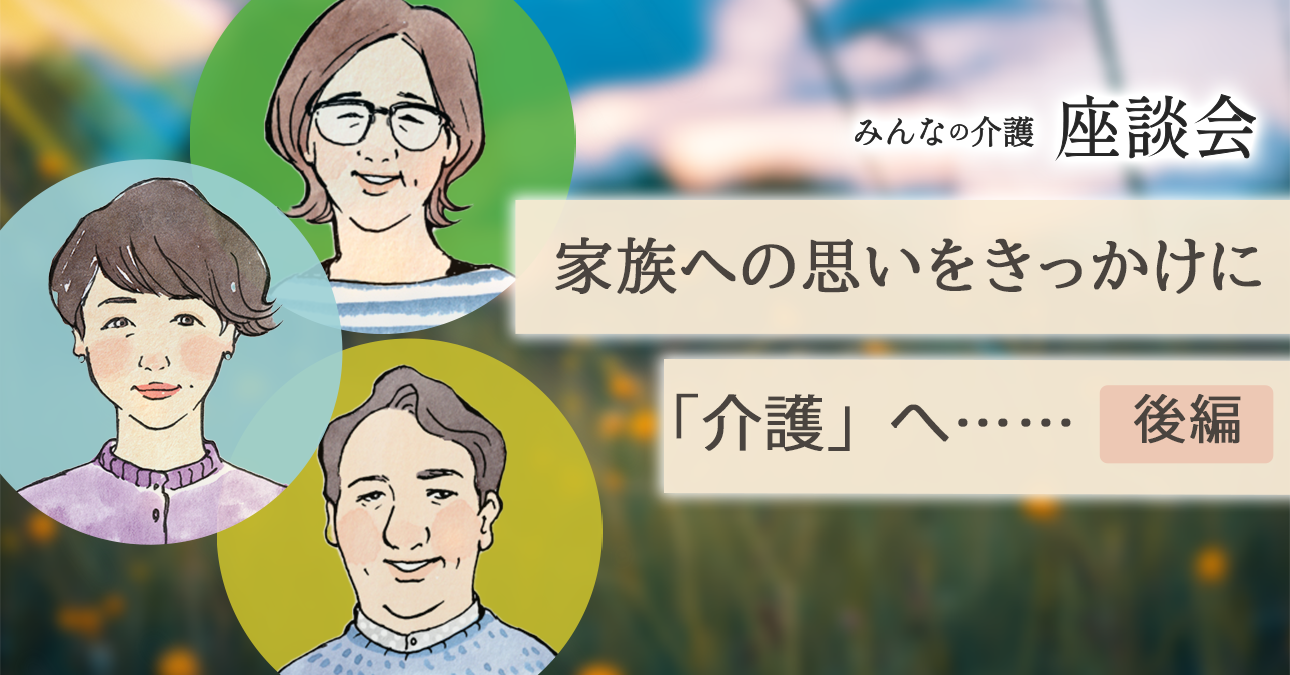


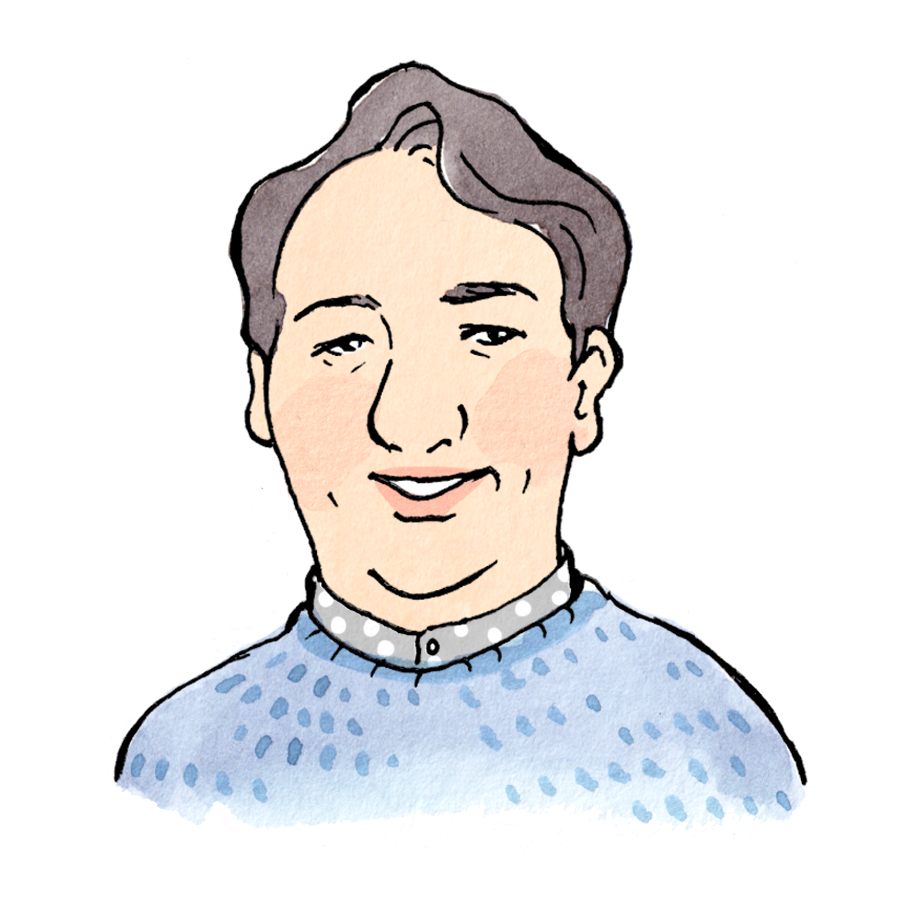
 天野
天野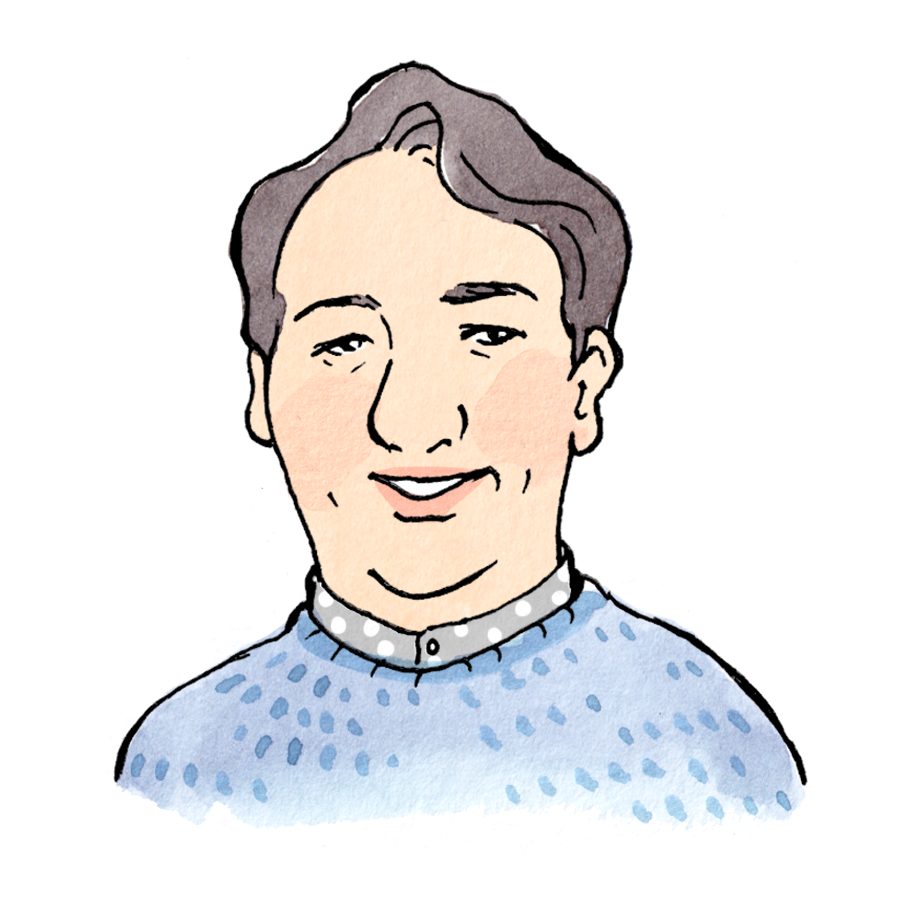 吉田
吉田 白井
白井