今回の「みんなの介護座談会」は、妻、娘、嫁とそれぞれ立場が違いますが、認知症となったご家族を介護したみなさまにお集まりいただきました。「認知症」といっても、その介護はひとそれぞれ。施設入所に対する考え方などを伺いました。
この記事に登場するみなさんのプロフィール(敬称略)
夫の介護のために介護離職。親子ほど歳の離れた夫が、健康診断で認知症の診断を受ける。判明当時は小学生と中学生だった子どもを抱え、働きながら在宅介護をすることに。夫の症状の進行は早く、暴力・暴言などからデイサービスやショートステイから利用を断られるようになる。在宅介護を続ける覚悟でいたが、過酷さが増す日々に、受け入れ可能な施設や精神病院を探す。2022年に入所先のグループホームが見つかる。現在は要介護3。
自営業。夫の転勤で東京へ転居。1年程経過したころから、地元・九州に住む母親に変化が出始める。転勤当初から頻繁に電話をしていたことで母親の異変に気付き、診断を受けたところ、アルツハイマー型若年性認知症と判明。東京←→九州の遠距離介護を続けていたが、父親を1年がかりで説得し、両親を東京に呼び寄せる。「通い介護」となるも、父親が限界を迎え、2016年に母親が特養に入所。現在、母親は発語も難しくなり、要介護5。
マンガ家。10歳以上年上の夫の姑が認知症になり、マンガ家の傍ら、在宅介護を約10年間続けていた。姑が車椅子生活になったことを機に、特養へ入所してもらったが、姑は半年後に入所先で死去。看護師免許を持っていることもあり、姑が施設に入所後、当時お世話になった現場の人たちへの「恩返し」も込め、グループホームで働き始める。グループホームでは、看護師としてではなく、現場のスタッフとして2022年まで働いていた。
「大変マウント」を取り合う家族会
みんなの介護(以下、―――) 前編では、家族が認知症だとわかったときの心境や在宅介護で大変だったことを伺いました。介護のお悩みを相談できるは、周囲にいらっしゃいましたか?

山下
九州から東京に両親を呼び寄せて、近くに住んでもらい通いの介護をする中で、二番目にお世話になったケアマネジャーさんがすごく親身になって、悩みを聞いてくださる方でした。私と年齢の近い女性で、母も“娘”のように接していました。
仕事上はNGなのかもしれませんが、個人的に仲良くなり連絡を取り合い、ご飯を一緒に食べに行ったり、母も連れて一緒にカラオケに行ったこともあります。
あと、同じ若年性認知症の親を持つ子ども世代の集いが立ち上がり、そこに参加して、情報を共有したり、グチを吐き出し合える仲間ができました。
子ども世代の集いは全国的に広がっていき、親が若年性認知症だとわかった方だけでなく、すでに見送った方まで、さまざまなメンバーがいるそうです。
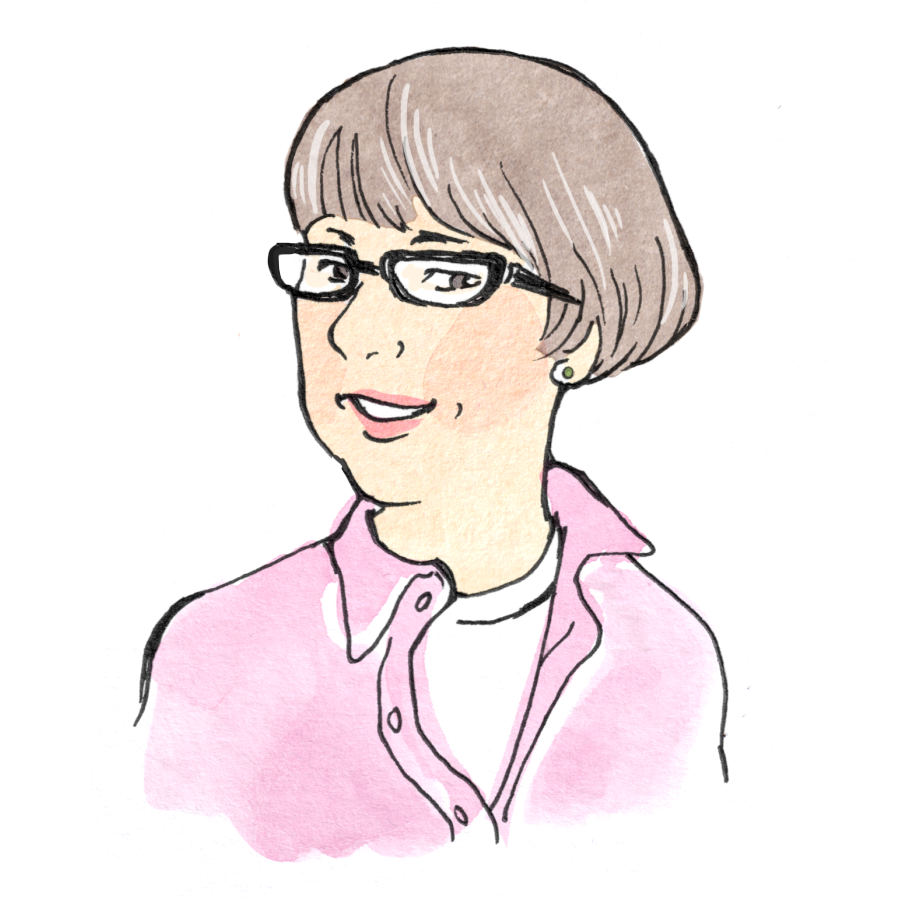
坂本
私は4コママンガを描いて発信することで発散したり。あとは地元の家族会に毎月参加していました。ただ、私よりも大変な思いをしている方ばかりで、「私は全然苦労していない」と思いながら帰る感じでした。
今回の座談会のように話を「回して」くださる方がいればいいのですが、あくまで私の感想ですが、家族会は話したい方だけが話し続けてしまったり、「私の方が大変だった!」と「大変マウント」を取り合うようなことがありましたね。
――― 「発言」が難しそうですね。
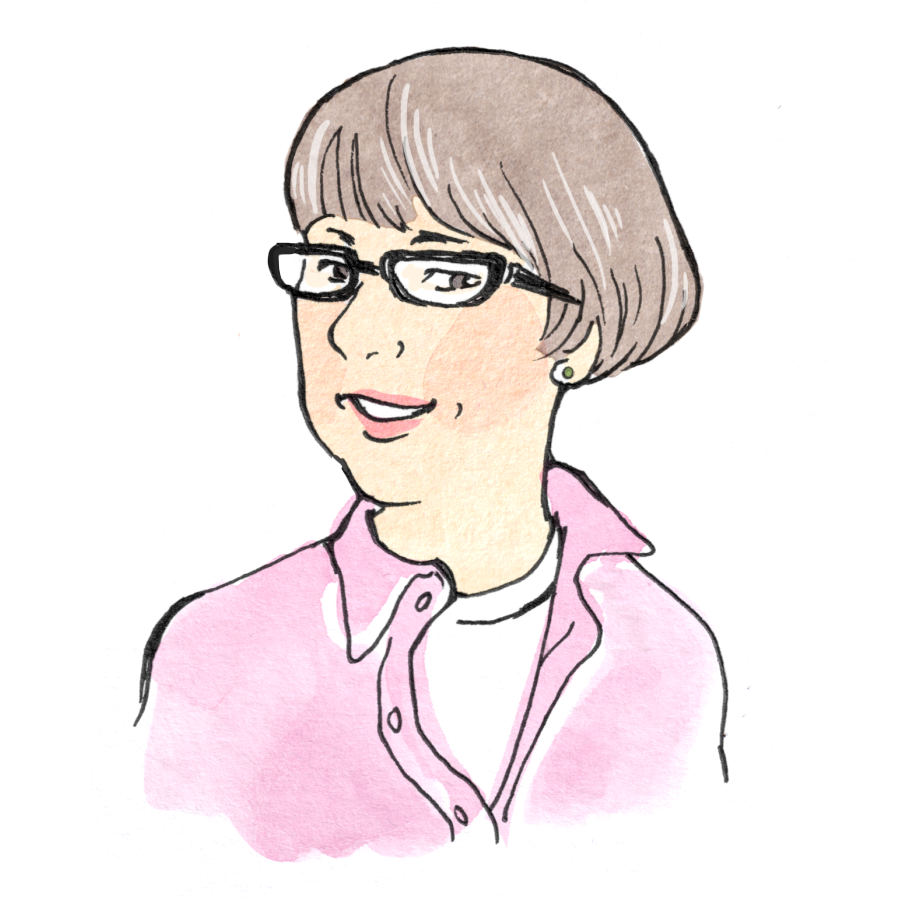
坂本
「ウンチまみれのオムツがトイレに捨てられていたときには……」などという強烈なお話を聞いてしまうと、姑はそういうことが一切なかったので話に入っていけなくて。ただ、そこで聞いた話はグループホームで働いていたときに、利用者さんが「あり得ない」場所で用を足すなど強烈なシーンに遭遇したときに、「あ、これ家族会で聞いた話だ」と驚かずに済みました(笑)。

小林
坂本さんがグループホームで働かれていたときの話ではないですが、夫が洗面台に便をしたときに、こちらとしてはそういったことがあるとすごく動揺するわけです。それをケアマネジャーさんに伝えると、「あー、みなさん、よく洗面台でされるんですよね」と。「よくあることだから大丈夫」というつもりでおっしゃっているのかもしれないけれど、暖簾に腕押しというか、「この方に相談してもなぁ……」という感じでした。
そのケアマネジャーさんもご家族の介護経験があるからいろいろな思いをもって働いている方ではあったけれど、ちょっとズレているというか……。
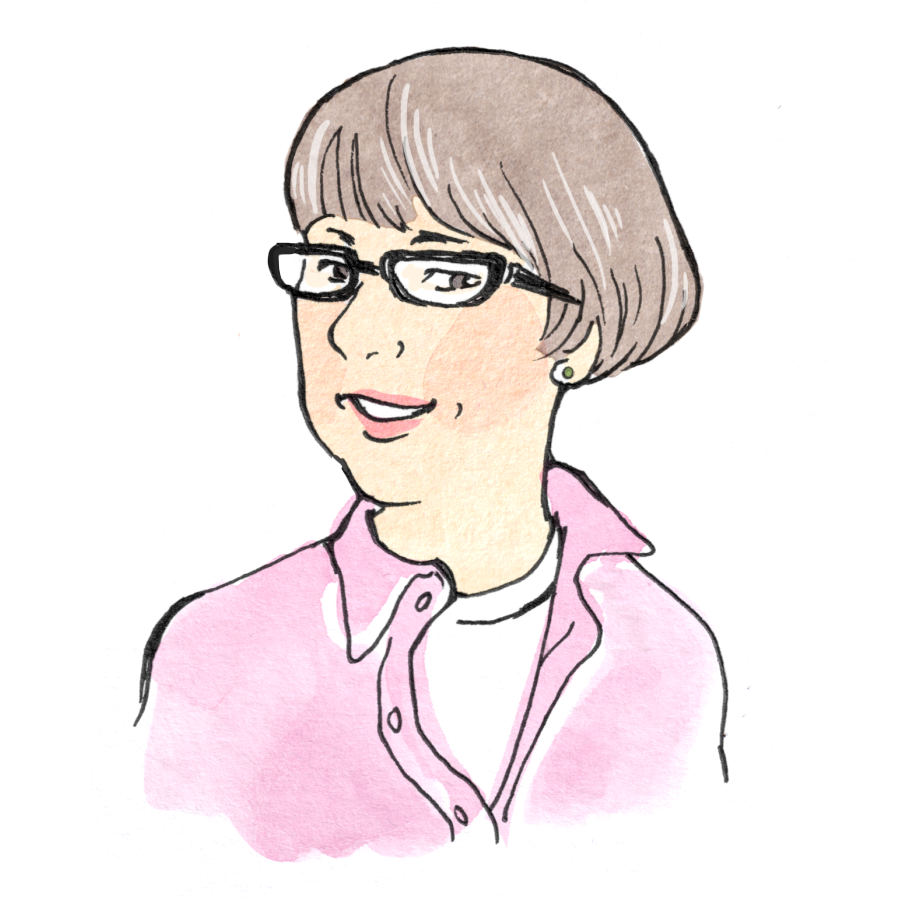
坂本
そうですよね。その「ズレ」が大きく感じてしまいますよね。

小林
あとは介護サービスを提案してくれるというよりは、こちらから「ショートステイを探してください」とか“刺激”を与えるようにして、お願いすることもありました。
介護経験のある友人に話を聞いてもらうこともありましたが、グチを言ってスッキリはしますが、それで私は救われなくて。「今、どうしたらいいのか」「どんなサービスがあるのか」など的確なアドバイスをくれる相談相手が欲しかったです。
介護で困ったことがあったら行政にメールを!
――― さまざまな介護の問題を提起していただきました。最後になりますが、介護をされている方へのメッセージをお願いできますか。

小林
在宅介護がつらくなったら、施設入所も考えて欲しいと思います。周囲の方は「やっぱり在宅がいいよ」と言うかもしれませんが、急に怒り出して、その原因がわからなかったり、そこらじゅうで「用を足す」ような状態では、こちらは常に緊張感の中で暮らすことになってしまいます。家族だけでの介護は無理です。
施設入所の費用が高いという問題はありますが、施設入所も頭に入れて、在宅にこだわらずに頑張り過ぎないで欲しいですね。
「入所して、ダメだったら退所したっていいじゃん」ぐらいの気持ちで申し込みだけでもしておくのはアリだと思います。私が在宅にこだわり過ぎてわかったことです。

山下
実際に母の特養への入所が決まったときは、「えっ、こんなに早く!」といろんな感情が入り混じりました。父も同じように思っていたのか、娘の前でも泣いていました。それでも、支えている父や私が母より深刻な状況になりかねないところだったので、「頑張らない介護」というのは大事だと思っています。
さきほどインスタグラムに届くダイレクトメールの話をしましたが、ご自身では支えきれずに、本当に大変で、“やっとの思い”で私にSOSを出しているように思います。そういったメッセージを拝読すると、「思い詰めていらっしゃる」方が多いという印象を受けます。どうか、ご自分の中だけにつらさを閉じ込めずに、メールでもなんでも、周りに助けを求めて欲しいと思います。
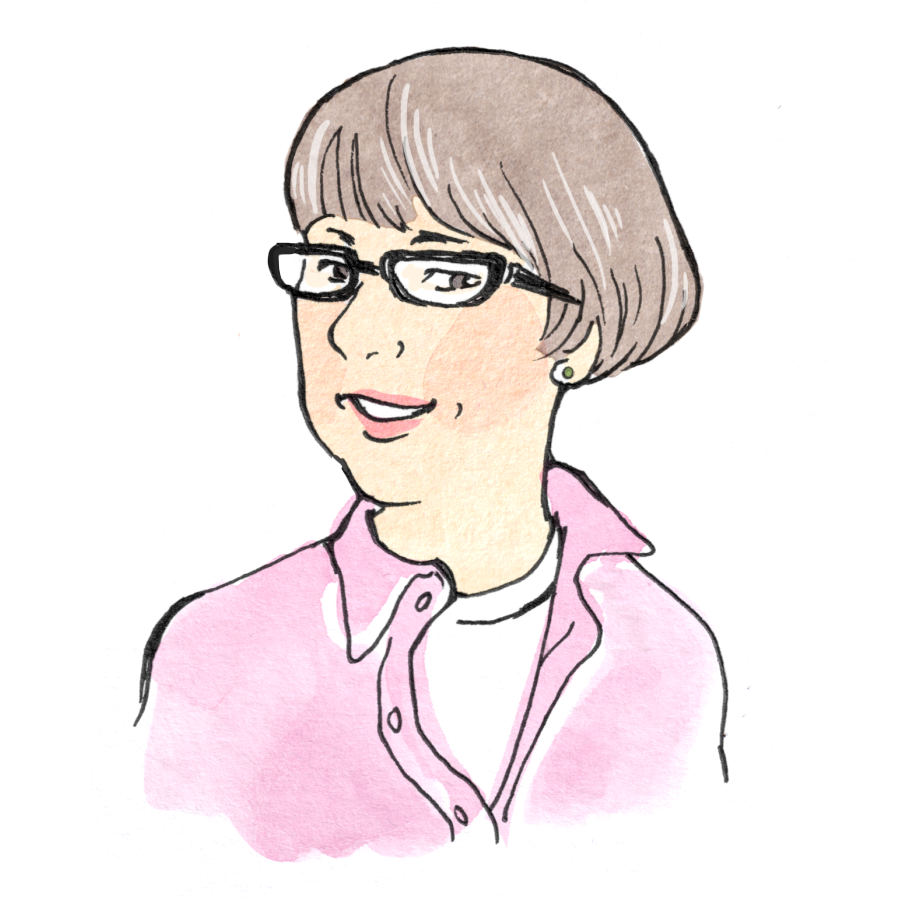
坂本
私は現場で働いていた者として思ったことがあって。働いている人は「ここの施設は最低だ」と辞めることができますが、利用者は「この施設は大丈夫かな」と思っても、ほかに空きがないと我慢してしまうことがあると思います。それはとても“しんどい”ことなので、利用者側もすぐに他に移ることができる状況になればいいなと思います。やはり施設と利用者の相性もありますからね。

小林
介護で困ったことがあったら、行政に意見を伝えることも大切です。電話だけでなく、意見が届いたというモノや記録が残る手紙やメールがいいそうです。みんなが「困っています」と発信していかないと、行政も困っていることの実態がわかりません。ですから、困ったことがあったらみんなで“ちょこちょこ”とでも行政に伝えていきましょう!
最後に非常に参考になる熱いメッセージをいただきました。介護の困り事を自分だけで抱えていては、状況が悪化してしまう可能性が大いにあります。“最初の一歩”は勇気が必要かもしれません。それでも、どんなに些細なことでも発信することが大切なのではないでしょうか。そのお声を「みんなの介護座談会」でもお聞かせください。

取材・文:岡崎杏里
「みんなの介護座談会」へご参加頂ける方を募集しています
「みんなの介護座談会」は読者の皆さまに参加して頂く新企画です。皆さまの日々の介護に対する思いをぜひ座談会で語ってください。
以下のフォームより、ご応募をお待ちしております。
参加フォームはこちらをクリックしてください







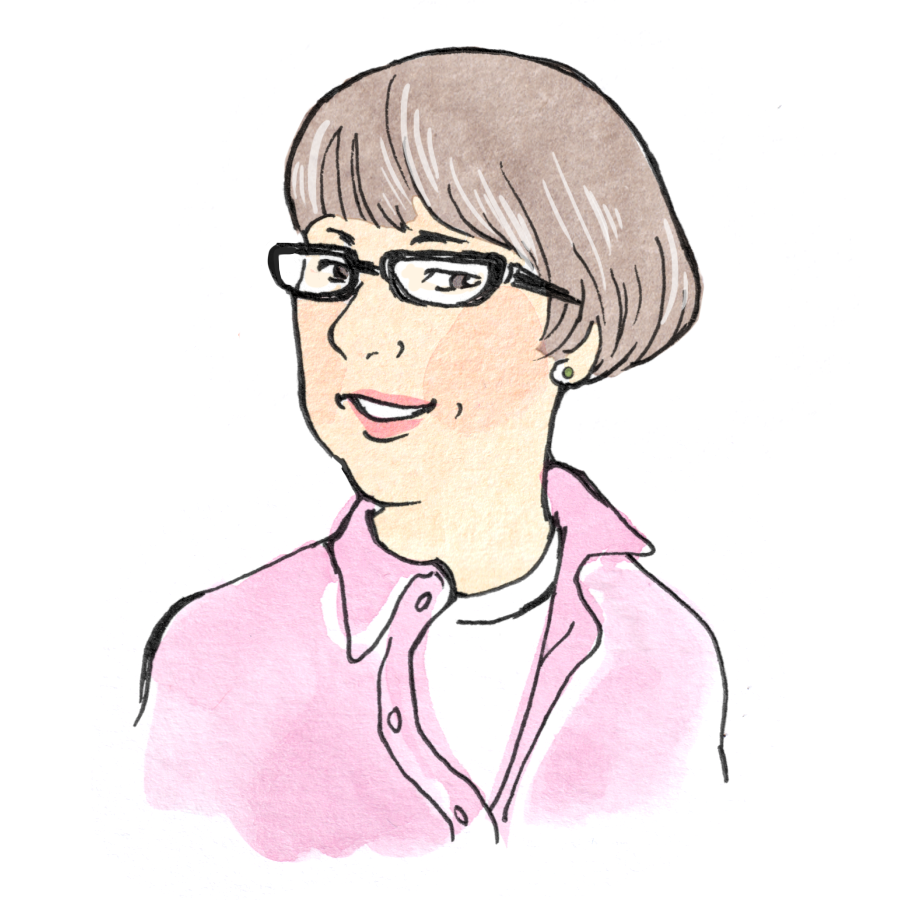
 山下
山下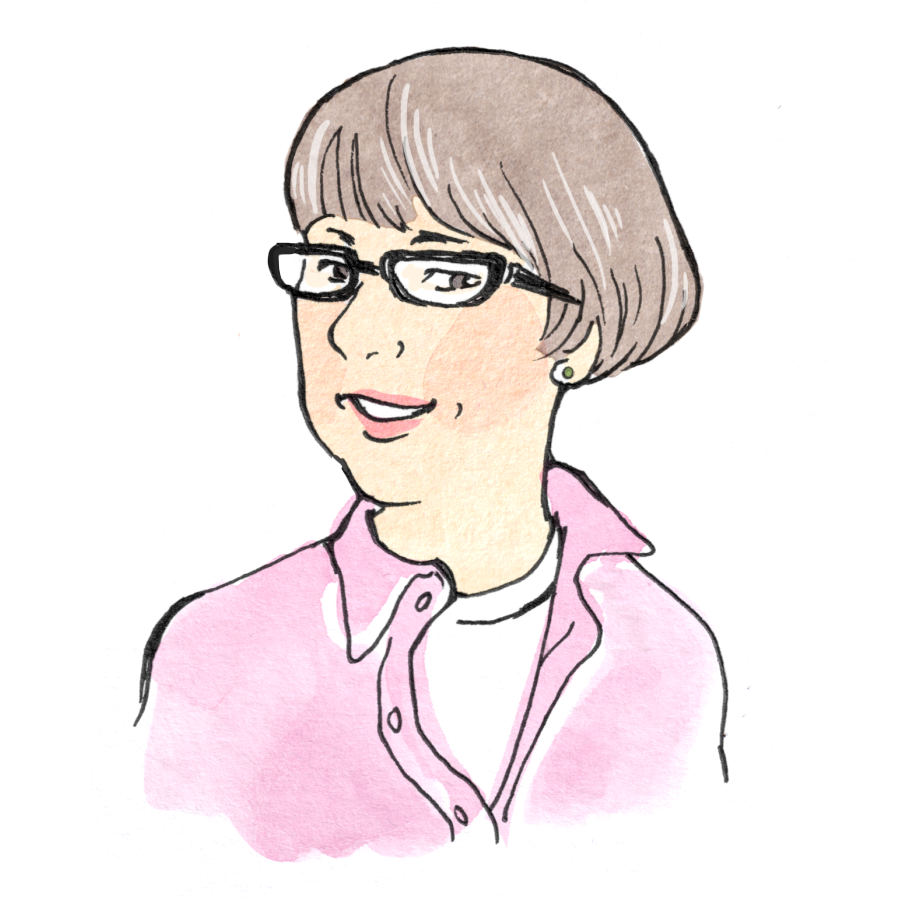 坂本
坂本 小林
小林