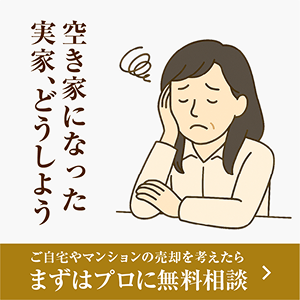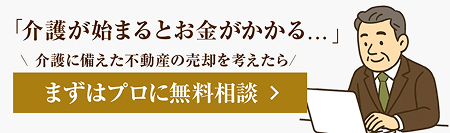稲葉剛「“貧しさは自己責任”という偏見と差別が路上生活者の命を奪う」
一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事であり、認定NPO法人ビッグイシュー基金共同代表、生活保護問題対策全国会議幹事、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科客員教授なども兼任する稲葉剛氏は長年路上生活者支援に携わってきた。現在は生活相談やシェルターの提供、仕事づくりといった生活困窮者の支援とともに政府への提言も行っている。1990年代から活動を続ける稲葉氏の原点には、どのような思いがあったのだろうか。
文責/みんなの介護
原点は、新宿ダンボール村の路上生活者支援
みんなの介護 稲葉さんは、長年路上生活者支援に携わって来られました。まずは、活動を始められた原点からお聞きできますか?
稲葉 私は、広島出身で親が被爆二世なんです。「私たちの社会で理不尽なことが起これば、声を上げるのが自然」という文化の中で育ち、学生時代から平和運動に参加していました。貧困問題にかかわり始めたのは、1994年頃からです。新宿ダンボール村の路上生活者支援がきっかけでした。
当時はバブル経済が崩壊した直後でした。東京・大阪・横浜・川崎・名古屋などの大都市部で、路上生活者の姿が目につくようになっていました。
彼らは、おもに建築土木現場で働いてきた50代~60代の日雇い労働者の方たちでした。バブル崩壊後の不況で仕事がなくなり、路上生活になってしまったのです。
1992年頃になると新宿駅から東京都庁舎に向かう地下通路にダンボールハウスが増え、新宿ダンボール村と呼ばれるようになりました。
多いときは、新宿駅西口周辺だけで300人ぐらいの路上生活者の人たちがコミュニティをつくって暮らしていました。
そんな中、私は東京都がダンボールハウスを強制撤去したという小さな新聞記事を見て衝撃を受けました。私たちの社会で何か地殻変動が起きつつあるような感じがしました。
そして、友人たちとダンボール村に住む方のお話を聞きに行きました。そこから炊き出しや夜回りなど、路上生活者支援の活動を始めることになったのです。
生活保護の「水際作戦」が今より激しく行われていた
みんなの介護 もう30年近く活動を続けて来られたのですね。路上生活者支援の活動の中でも特に稲葉さんが持っていた問題意識は何ですか?
稲葉 生活保護の利用に関する問題ですね。最後のセーフティネットである生活保護は、本来住まいがない方であっても権利として認められるべきものです。
しかし実際は、住まいがない人たちに対して差別的な運用がなされているケースがあります。いわゆる水際作戦です。役所の窓口に行っても何かと理由をつけて追い返される。そんな違法な運用が現在でも続いています。
私が活動を始めた90年代の半ばは、今以上に水際作戦が激しく行われていました。
みんなの介護 どのような状況だったのですか?
稲葉 路上生活者の方は、お体を悪くされている方が多くいます。
食事も一日一食とれればいい方だという方もいらっしゃいます。非常に過酷な環境での暮らしで、持病を悪化させて苦しんでいらっしゃる方が多い。
しかし、役所の窓口で「病院にかかりたい」と言っても職員に追い返される。「あなたはまだ働けるでしょう。日雇いの建築現場の仕事でも何でもやって自分のお金で病院に行きなさい」と言われてしまう。そんな対応が日常茶飯事でした。
結局、彼らは病院に行けないまま路上生活を続けざるを得なくなる。そして体調がどんどん悪化していって最後は路上で倒れて救急車で搬送される。
さらに救急車で搬送されても、路上生活者を病院もなかなか受け入れようとしない。そして、たらい回しにされた挙句に亡くなってしまう…。そのような悲惨な状況が起こっていました。
私も夜回りをしている時、ダンボールハウスで亡くなっている方を発見したことがあります。1990年代の後半は、新宿区内だけでも年間40~50人ぐらいの方が路上生活で亡くなりました。
私が学生の頃はバブルの真っ只中で、日本は世界第2位の経済大国だと言われていました。
その豊かであるはずの日本の、首都のど真ん中で、路上で人が亡くなっていく。しかも、病院にもかかることができず貧困によって命が奪われている。
その現状を知ったとき、私は非常にショックを受けました。この状況を何とか変えていきたいという思いで今日まで活動を続けています。

面白半分で行われていた「ケラチョ狩り」
みんなの介護 路上生活者の方は襲撃を受ける危険とも常に隣り合わせですよね。
稲葉 路上生活者が増えるに伴い、少年たちが集団で彼らをリンチして命を奪うような事件が多発しました。特に1990年代半ばから2000年代の初めにかけて、都市部ではほぼ毎年のように襲撃事件が起こっていました。
過去に少なくとも27人が死亡しています。また、ケガや物的損害など把握が難しい事件の件数はその何倍にものぼると推察されます。
こちらの記事をご参照ください。例えば、1996年に渋谷の代々木公園で野宿の男性が暴行されて殺された事件が起きました。少年グループはその暴力行為を「ケラチョ狩り」と呼んでいました。「虫けらを街から掃除する」という意味です。社会から目障りな存在とされている人たちを始末してやろう、というわけです。
少年たちがそのような考えを持ったのは、大人の影響を受けている部分が大きい。路上生活者の人たちを「クサい」「汚い」と言って排除し、子どもたちにも「ああいう人たちには近寄らないようにした方がいい」と教える。そうやって親や社会の意識を子どもにうつしてしまう。
「貧困は自己責任ではない」と知ってほしい
みんなの介護 根が深い問題ですよね。どのような対策を講じて来られたのでしょうか?
稲葉 事件現場に行って追悼会を開いたり、事件が起こった地域の住民の方たちと一緒に襲撃をなくすための方法を考える場を持ったりしました。
2009年からは、全国の路上生活者支援団体の関係者と学校の先生に協力いただき、学校で出前授業も行っています。
みんなの介護 それはどんな授業なのでしょうか?
稲葉 路上生活の当事者や経験者の方と学校に行って「路上生活者と人権」をテーマにお話をします。襲撃事件にかかわった生徒が通っていた中学や高校にも行きました。自治体の人権講座や教育委員会主催の研修会でお話しさせていただくこともあります。
また、近年は特にSNSでの発信に力を入れています。襲撃の原因になる差別や偏見をなくすためだけではありません。「貧困は自己責任じゃない」ということを社会に発信するためです。
SNSは簡単に発信できる反面、デメリットもあります。昨年、あるYouTuberが差別的な動画を自分のチャンネルにアップしました。路上生活者や生活保護の利用者たちの生きる価値そのものを否定する、ひどい暴言を吐いた動画でした。
それに対して、いくつかの支援団体で抗議声明を出すとともに、抗議のキャンペーンをSNS上で行いました。これには、多くの方々が賛同してくださり、最終的にご本人も過ちを認め、謝罪されることになりました。
私たちが恐れたのは、その動画が一つの差別扇動になって襲撃を煽ることにつながってしまうことでした。
ヘイトクライムを起こさないために、差別や襲撃は許されないということ、貧困は個人の責任ではなく、社会の構造の問題であるということを、折に触れて発信することが大切だと思っています。
撮影:横関一浩
稲葉 剛氏の著書『閉ざされた扉をこじ開ける 排除と貧困に抗うソーシャルアクション』(朝日新書)は好評発売中!
「大人の貧困は自己責任」という不寛容が日本社会を覆っている。日々の寝泊まりにも困り、生活に困窮している人々が自ら声をあげにくい風潮はますます強まっている。住居を喪失した人が失うのは、生活の基盤となる住まいだけではない。その果てにあるのは、生存そのものが脅かされる恐怖だ。20年以上、現場を見て歩いてきた社会活動家が「社会的に排除された側」からこの国を見つめ直す。
連載コンテンツ
-
さまざまな業界で活躍する“賢人”へのインタビュー。日本の社会保障が抱える課題のヒントを探ります。
-
認知症や在宅介護、リハビリ、薬剤師など介護のプロが、介護のやり方やコツを教えてくれます。
-

超高齢社会に向けて先進的な取り組みをしている自治体、企業のリーダーにインタビューする企画です。
-

要介護5のコラムニスト・コータリこと神足裕司さんから介護職員や家族への思いを綴った手紙です。
-

漫画家のくらたまこと倉田真由美さんが、介護や闘病などがテーマの作家と語り合う企画です。
-

50代60代の方に向けて、飲酒や運動など身近なテーマを元に健康寿命を伸ばす秘訣を紹介する企画。
-

講師にやまもといちろうさんを迎え、社会保障に関するコラムをゼミ形式で発表してもらいます。
-

認知症の母と過ごす日々をユーモラスかつ赤裸々に描いたドキュメンタリー動画コンテンツです。
-

介護食アドバイザーのクリコさんが、簡単につくれる美味しい介護食のレシピをレクチャーする漫画です。