産婦人科医・高尾美穂「50・60代はライフスタイルを見直す絶好のタイミング。人生を楽しみながら介護に向き合って」
ジェンダーレスなモヒカンヘアが印象的な産婦人科医・高尾美穂氏。診療活動のかたわら、NHK「あさイチ」をはじめ、多数のメディアから引っぱりだこの人気ドクターだ。女性が健やかに年齢を重ねるためのサポートをライフワークとする氏から、心と体が揺れ動く「みんなの介護」読者世代に向け、人生の後半戦を心地よく生きるためのアドバイスを伺った。
文責/みんなの介護
「みんなの介護」読者が知っておくべき女性の体の変化
―― 本日はお時間をいただきありがとうございます!先生のご活動を改めて教えていただけますか?
高尾 産婦人科医として「イーク表参道」で勤務しながら、「高尾美穂からのリアルボイス」という音声配信を行っており、日々をより良く生きるために女性のみなさんからの質問にお答えしています。
―― 産婦人科医である高尾先生が診療活動以外に女性のライフスタイル全般をサポートされているのは、どういった想いからでしょうか?
高尾 多くの女性に大切な情報を受け取ってもらいたい。そういった想いで活動しています。
女性の困りごとは、大きく2種類に分けて考える必要があります。
まずは「形やつくり」の問題。私の専門分野でいえば子宮筋腫ですが、いわゆる取り除けば治る類の病気ですね。産婦人科の外来診療では、やはりどうしても病気の治療が軸となります。正直、私自身も数年前までは、この分野にばかり目を向けていました。
けれど、世の中の大多数の女性が困っているのは、もうひとつの問題である「はたらき」の部分なんです。生理不順、PMS、更年期症状など、異常がはっきりと数値化されるわけじゃないけど、調子が悪い・すっきりしないといった曖昧な不調がみんなを悩ませている。
そしてこの「はたらき」の問題に対しては、医者にかからなくても自分でできる対処法がたくさんあります。だからこそ、情報を発信し続けています。
―― 「賢人論。」は40〜60代の方にも多く読んでくださっています。今回は、特にこの世代の女性にフォーカスしたお話を聞かせてください。
高尾 まず基礎知識として知っていただきたいのが、卵巣から分泌される「エストロゲン」という女性ホルモンについて。このエストロゲンは子宮に作用し、妊娠しやすい状態をつくる働きがあります。
10代前半で卵巣が成熟し、エストロゲンの分泌が増えると生理がスタートします。そして40代頃から急激に分泌量が減っていき、乱高下を繰り返しながら50歳前後で閉経を迎えます。
40〜60代女性というと、ちょうど閉経前後で体の不調を感じている真っ最中の方も多いかと思います。一方、つらかった更年期をすでに乗り越え、心身が安定した状況を楽しんでいる方もいらっしゃるかな。
いずれにせよ、エストロゲン値の変化に伴って、女性の心身が大きく変わることを実体験する世代ですね。
―― 先生は、このエストロゲンをはじめ、女性ホルモンに関する教育に注力されていますよね。
高尾 女性は男性と違って、生涯にわたりホルモンの影響にさらされ続ける生き物です。知識を身につけておいて損はありません。というより、ホルモンの波をうまく乗りこなすことこそが、女性が人生100年といわれる今の時代を健やかに生き抜くための最大のヒントとなります。
現在、日本人女性の平均寿命は約87歳。寿命が短かったひと昔前は「閉経=人生終盤」といったイメージでした。でも今は事情が異なります。生理のある10〜50歳までの40年間と、閉経後の40年間。閉経後の人生は「オマケ」じゃなくて、もっと心地よさを追求して生きていきたいですよね。
―― 閉経を迎えることで体に現れる変化について、具体的に教えてください。
高尾 妊娠準備以外のエストロゲンの役割は「コレステロール値を抑える働き」「骨量の維持」「しなやかな血管の保持」「肌や髪のツヤ・潤いなど美容面での影響」などが挙げられます。
たとえば、骨粗鬆症は高齢女性に多いでしょ?これは、閉経後はエストロゲン値がほぼゼロになるため、骨が脆くなるから。ほかにも、コレステロール値が上昇することで動脈硬化・心筋梗塞など、命に関わるトラブルを引き起こす可能性も高くなります。
また、筋肉や関節の動きを助けているのもエストロゲンです。健康寿命が損なわれる第一の原因は、自力歩行ができなくなること。介護予防という観点からも重要なホルモンです。
―― 閉経後の体の変化に対応するためには、投薬などの治療が効果的ですか?
高尾 もちろん、薬でコントロールするという選択肢もあるけれど、まずはセルフケア領域でできる予防法を実践してほしい。たとえば、運動習慣をつける、積極的に大豆を摂るなどです。自分の意識ひとつ行動ひとつで、リスクを抑えることができるものと知ってください。
―― やはりセルフケアができていない方が多いと感じますか?
高尾 現代の女性は、仕事・育児・介護・家事で忙しいあまり、自分の体への気遣いは後回しにしてしまいがち。「セルフケアが大事、生活習慣を改善しよう」なんて何十年も前から言われているし、みんな分かっていることなんだけど、そんなのやってる暇ないとかどうせ大して変わらないでしょと、なかなか取り組むにいたらない場合が多いんです。
そして結局、深刻なトラブルに直面してから、ようやく自分ごととして捉えるようになる。でも、そうなる前にできることはあるはずだよね・変えられる部分は多いはずだよねと伝えるのが私の仕事だと思っています。これからも何百回・何千回と繰り返し伝え続けますから、皆さんが自分にとってベストなタイミングで私の声を受け止めてくれれば嬉しいですね。
50・60代は「過渡期の世代」
―― 更年期前後の変化として、落ち込みやウツといった心の不調も出てくると聞きます。
高尾 エストロゲンは自律神経にも影響しますからね。ただ、それが理由のひとつでもあるんだけど、同じくらい人間関係というストレスが女性の健康に大きな影響を及ぼしていると感じます。
コロナをきっかけに2020年から「高尾美穂のリアルボイス」という音声番組を配信しています。番組内で、更年期前後のリスナーからの質問に答えていますが、体についての相談が一巡したあとは、もっぱら人間関係についての悩みばかり。女性が抱える体調の悪さというのは、心のもやもやみたいなものが理由の根底にあるんだなと改めて実感します。
―― 子どもの独立や親の介護など家庭環境が大きく変わる時期でもありますからね。
高尾 そうね。親との関係、それとパートナーとの関係性について悩んでいる人が多いですよね。
女性側は「恋愛→生殖→育児」といった目まぐるしい役割変化を経て、ようやく子育てを卒業したという気持ちが大きい。けれど50・60代の男性は、今の現役パパたちに比べて育児に積極的に関わってきたとはいえない世代です。だから、子育てが終わったことで、夫婦間における自分の役割が変わったという認識はあまり芽生えません。
この意識のズレが、女性の葛藤を生み出しているのは確か。「残りの30年40年を夫とともに生きることは考えられない」という気持ちになってしまうのですね。
―― 後半期の人生をストレスなく生きるためには、どういった準備が必要でしょうか?
高尾 自分を取り巻く環境を「心地よい状態」に変える心づもりをしておくこと。そのためには、経済的な自立は必須です。
2020年現在、50代女性の就業率は7〜8割。70・80代の方々と比べて、女性が働くことに対する社会の壁は低くなりました。自分の人生を自分でデザインしようと思うなら、自分で立って生活できる術を見つけておいた方が良いですよ。
その点、今もっとも大きな課題は男女間の賃金の差ですね。ただ、次の世代がメインになる頃には、この問題も解決に向かうのではないでしょうか。
―― 50・60代の皆さんはまさに「過渡期の世代」といえますね。
高尾 本当にそのとおり。ほかにも、これからは女性が自分で自分の体をコントロールすることがもっと一般的になると思います。
たとえば低用量ピルは、生理痛やPMS軽減の効果が期待できます。けれど50・60代が若い頃、ピルは未承認で身近な存在ではありませんでした。そのため、いくら自分の娘が生理痛に悩んでいても、ピルを勧めることってあまりなかったと思うんです。けれど、正しい情報を知る今の若い世代が親になったとき、ピルでの治療は当たり前のように選択肢に入ってくるでしょう。
医療面だけでなく、メインの世代が入れ替わるこの20年くらいで社会の空気感は大きく変わるんじゃないかな。そのためにも、私たちの世代が、次世代への橋渡しをしっかり行わないといけませんね。
閉経後のあなたには、次世代へつなぐ役割がある
―― 私はそろそろ更年期が見えてきた年齢なのですが、実際に閉経を迎えたとき「女じゃなくなった」とマイナスに捉えてしまわないかと心配です。
高尾 女性は年を取ると生殖能力がなくなる反面、男性の場合は機能が落ちるとはいえ、死ぬまでゼロにはなりません。そもそも、生物の生きる意義というのは「子孫を残すこと」。生殖能力を持たない生き物は、地球上にほぼ存在しないというのが自然界の法則です。
逆にいうと、閉経後の女性が「生殖能力を持っていない私は、なぜ生き続けねばならないのか」というテーマにぶち当たることは不自然ではないといえます。
―― この問いに対して、先生はどうお考えですか?
答えのひとつだと思うのが、ミツバチの社会です。ミツバチの働きバチはメスだけで構成されていますが、彼女らが産卵することは一生ない。何万匹ものメスたちの役割は、自分たちの遺伝子をつなぐことができる唯一の存在である女王バチに、良い形で繁殖できる環境を提供することなのです。
人間も同様に、閉経後の女性が生きる意味というのは、次世代が安心して子どもを産み育てられる社会を創造していくことなんじゃないかなと。年齢を重ねるにつれ、女性としての役割分担は変化していく。これをしっかり認識しておけば、閉経後の自分に自信喪失したり、無気力さを感じる事態は避けられるのではないでしょうか。
自分にとっての「快」とは何か。心地よく生きるためのヒント
―― 介護の世界には、男性介護士から入浴や排泄介助は受けたくないという「異性介助」の問題があります。婦人科医としてのご意見を聞かせてください。
高尾 一瞬の気恥ずかしさには目をつぶって介助を受けることと、清潔を保てない日々を過ごすこと。両者を天秤にかけて、自分にとってはどちらが重要なのかを考える。その上で選択するしかありませんよね。
外来診療においても、明らかな婦人科的な不調が見受けられるのに、内診がハードルで受診しないという方は一定数います。医師としてはもどかしい気持ちになりますが、優先順位は人それぞれ。他者が価値観を押し付けられるものではありません。
―― なるほど。どちらが正しいと決めつけるのではなく、選ぶのは自分ということですね。
高尾 介護問題に限らず、自分が何を望んでいるのかというポイントを最優先にできると、生きるのが楽になれます。私たちはどうしても常識や世間の目にとらわれて、頭が心を押さえつけがち。本当は心がどう思っているのかを自分なりに探してみると、おのずと答えは出てくるものだと思います。
「女らしさ」は誰のため?
―― 先ほどの“世間の目”というワードから、ぜひお聞きしたいことが。私自身、いくつになっても「女性らしくあらねば」といった言葉に囚われていると感じるのですが…。
高尾 あなたが思っている「女らしさ」というのが、誰を軸にした目線なのかを考えた方がいい。
たとえば、フェミニンな装いをすることや美容に気を遣うこと自体が「自分らしさ」の一部を形作っていると思うなら、周囲の視線や意見に左右されず、とことん理想を追求すれば良いと思います。でも、自分が「こうありたいから」じゃなく、他者からの評価を期待して「女らしくあらねば」という思考に陥っているなら、それはもう「自分らしさ」からは逸脱してしまってますよね。
自分はどういったスタイルで生きていきたいか。まず、ここをはっきりさせることです。
―― 外見的な「らしさ」だけでなく「良い母親」「賢い主婦」など女性には社会から期待される役割が多いとも感じます。
高尾 「子どもに手をかけなければ」「家の中はキレイな状態でなければ」といった言葉を「私は子育てに手をかけたい」「私は家中をキレイにしておきたい」に言い換えられるかどうか、が大事かな。
私たちって、都合の良い時だけ人のせいにしがちじゃない(笑)?誰だって、自分の子どもは素敵な人間に育ってほしいから、一生懸命子育てしているはず。決してやりたくないわけではない。でも、しんどい時や煮詰まった時はどうしても「やらされてる感」が強くなって、「〜ねばならない」といった表現を使ってしまうんですよ。
―― 今、自分が選んでいる行動は本当に望んでやっていることかどうかを知ることが、自分を解放する第一歩なんですね。
高尾 そう。同時に、人はさっき言ったような「都合の良い思考」に支配されてしまう場合もあると、知っておいた方がもっと良い。知っていれば、自分の状態を疑うこともできるでしょ?
それらも踏まえて自分の気持ちに正直になったとき「私はやりたくもない役割を課せられている」と感じれば、その役割を誰かに頼んだり手放してしまうといった選択肢を取ってもいいんじゃないでしょうか。
だいたいね、日本の女性には「100点満点を目指さないで」って声を大にして言いたいです。
―― 女性は頑張りすぎだと?
高尾 そのとおり。掃除だってね、多少ホコリがあったってどうにかなるものでもないんですから。私も以前は家事代行業者に頼むことにためらいがあったから、気持ちは分かりますけど、この国には「他人の手を借りるのは良くない」といった意識が根づいてしまっていることが、生きづらさを生んでいる。
育児だって介護だって、もっと誰かに頼って良いと思う。だからこそ、今の10代20代の若い子たちがメインの世の中になった時、彼女たちが自由に心地よく生きていけるよう、私たちの世代で社会を変えていきたいですよね。
言葉の力をあなどらないで
―― 「すべき」を「したい」に言い換えられるかなど、先生は言葉を大事にされているのが伝わってきます。
高尾 人は、潜在意識の中で言葉を選んでいます。だからこそ、他者と向き合う際には、ポジティブな感情を伝えたいという意識をベースに置く“癖”をつけておけば、自分の人生そのものも大きく変わっていくんじゃないかな。
私は「与える」「してあげる」といった言葉は使わないと決めています。代替できる別の表現があるならそっちを使う。その方が私にはしっくりくるから。
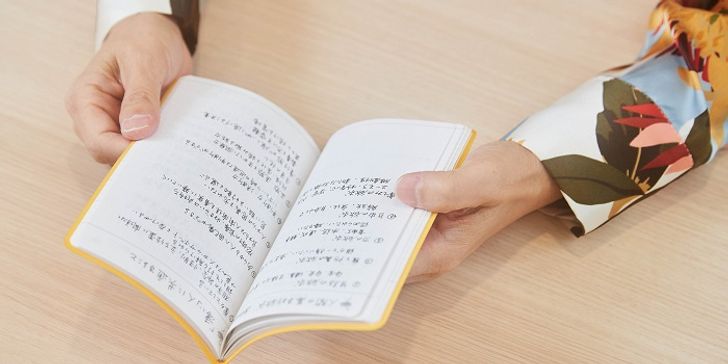 高尾先生の好きな言葉が記されたオリジナル手帳
高尾先生の好きな言葉が記されたオリジナル手帳
―― 言い回しひとつ変えるだけで、人間関係もうまくいったりしますもんね。
高尾 そうそう。たとえば夫婦間でよくあるのが、夫は「風呂掃除しといてあげたよ」とか言うわけです。ありがたいのは確かですが、そんな風に言われると妻は素直に感謝できないですよね。「風呂掃除したよ」でいいでしょ、「してあげた」って何よ、ってまたイライラの原因になってしまう(笑)。
―― この意識は、在宅介護で悩む人のマインドセットにも使えそうです。
ええ。今まさに介護を受けている後期高齢者の方々は、ひと昔前ほどではないにせよ「子どもが親の世話をするのは当然」といった感覚が無意識下にあるでしょうしね。それが態度や言葉の端々に出て、お互いの関係がこじれてしまう。とはいえ、古い時代の方々に、長年培ってきたその価値観を変えてもらおうと期待するのは難しいかもしれません。
代わりに、その親たちの介護をしている我々の世代が気をつけた方が良いなと思うのは、いずれ自分たちも誰かに面倒を見てもらう日が来るとイメージしておくこと。自分が「してあげている」ことだけにフォーカスしすぎないようにね。
毎日を楽しみ、介護だけの生活にしないで
―― 先生ご自身は、介護のご経験は?
高尾 2018年から夫が重度のギラン・バレー症候群を患っており、現在も療養中です。日々の生活に特殊な支援機器が必要だったり、私も仕事があるため、付きっきりで看病するのは難しく、今は夫とは離れて暮らしています。
だからこそ思うのは、誰かの介護をする状況にあったとしても、介護者自身が自分の人生を楽しむことを忘れないでほしいということ。友人と外出するとか、趣味の時間を持つとか、毎日を楽しめている中の一部に介護や看病がある。そんな生活であれば継続できるだろうし、望ましいですね。
「大事な人に介護が必要になりました。私が全力でケアをします」これももちろん美しい姿であるけれど、もしも何かを犠牲にしたり無理をしたりしていると感じるのであれば、背負い込んでいる環境を少しづつでも変えられるように動いてみるのもひとつの選択だと思います。
―― 介護するだけの存在にならないように、ですね。
高尾 昭和生まれの私たちって、自分ひとりで何でもできることが良しとして育てられてきた世代です。でも本当は、誰かに頼る能力はものすごく大事。どの人にどの部分を頼れるかっていう選択肢を持てることは人生の財産です。
―― ご自身が介護を受ける立場になっていくことについては何かイメージされていますか?
高尾 これからの時代、最期まで家族に面倒を見てもらえる人は少数派になります。特に私は、老後は確実に自分で何とかしなきゃいけない。友人同士でシェアハウスを借りて、助け合いながら暮らそうなんて話しています。
パートナーとともに生きていくことを選択した人も、夫婦という関係性にあぐらをかくのではなく、血のつながりがないからこそ、ちょうど良い塩梅で配慮し合える関係になれるとベスト。所詮は他人なんだから分かり合えない部分があって当たり前、くらいの感覚を持つことが、より良い介護のあり方にもつながっていくような気がします。
これからの自分は今の自分がつくるという意識を
―― 高尾先生は「老い」そのものについてはどう捉えていますか?
高尾 年齢を重ねることって、捉え方次第でポジティブにもネガティブにもなりますよね。私にとって「老い」の最大のメリットは、経験値が増えていくこと。良い経験も残念な経験もそれぞれに積み重ねた結果、若い時よりも考え方に断然深みが出ています。
あと、年を経るにつれて自分のキャラもエッジが効いてきます。もちろん頑固になっちゃうパターンもありますが、「自分らしさ」や「自分が何をしたいのか」といった点が明確になって、生き方やスタイルがはっきりしてくる。
女性って、誰かと比較することで、苦しんだり不安を感じるパターンが多いんですよ。でも、自分の個性や強みがはっきりしてくれば「私はこういう人間だから」と前向きに開き直ることができます。
それに、年齢なんて数字にしかすぎませんよ。同じ70歳でもフルマラソンを走る人がいれば、介護施設で寝たきりの人もいますから。
―― 見た目も中身も全然違う70歳が出来上がる時代ですしね。
高尾 戦後間もなくに生まれた層には情報がありませんでしたから。これを実践しておけば、年をとっても元気に過ごせるよという有益な知識がそう簡単には得られなかったから、同じ世代であれば健康状態にそこまで大きな偏りは出ていません。
でも現在は、医学的根拠に基づいた予防策がたくさん立証されています。たとえば、85歳以上の日本人の約55%が認知症を患っていますが、正しい対策をしていれば発症が抑えられる病気なんです。
今の50・60代が85歳になった時、認知症患者が55%よりも低い数字にもっていくことが私たち医療従事者の目標ではないでしょうか。だから繰り返しになりますが、セルフケアがすごく大切だと伝えたい。
―― この記事を読んでいる誰もが、手遅れではないということですね。
高尾 全然!むしろ、体にも環境にもいろんな変化が現れはじめて、ようやく自分の心身そのものを「我がこと」として意識できるようになるのが50・60代です。逆にいうと、20年30年後の自分の姿を決めるのは今の自分であるということ。自分のライフスタイルを見直す絶好のタイミングですよ。
やっぱりね、年をとると手放すことも諦めることも増えてくるのは事実です。でも、自分で納得して手を離したのなら、それは自分が選んだ道だと胸を張って言えるでしょう?前向きに開き直る部分を持ちつつ、自分らしい生き方を追求していきましょう!
撮影:熊坂勉
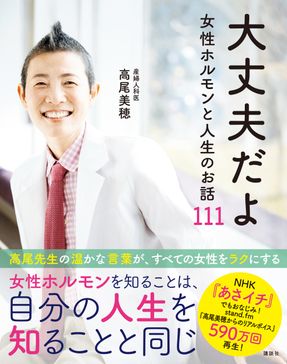
高尾美穂氏の著書大丈夫だよ 女性ホルモンと人生のお話111(講談社)は好評発売中!
生理、更年期、閉経、心の不安など、女性が人生で直面する悩みの多くには、実は女性ホルモンが深く関係している。女性の体と心を振り回す女性ホルモンとうまく付き合い、自分の人生を自分でデザインしていくためにどうすべきか。女性たちから絶大な支持を集める産婦人科医・高尾美穂が、111の処方箋を温かな言葉で語る。生きるのがラクになる知恵が詰まった1冊。
連載コンテンツ
-
さまざまな業界で活躍する“賢人”へのインタビュー。日本の社会保障が抱える課題のヒントを探ります。
-
認知症や在宅介護、リハビリ、薬剤師など介護のプロが、介護のやり方やコツを教えてくれます。
-

超高齢社会に向けて先進的な取り組みをしている自治体、企業のリーダーにインタビューする企画です。
-

要介護5のコラムニスト・コータリこと神足裕司さんから介護職員や家族への思いを綴った手紙です。
-

漫画家のくらたまこと倉田真由美さんが、介護や闘病などがテーマの作家と語り合う企画です。
-

50代60代の方に向けて、飲酒や運動など身近なテーマを元に健康寿命を伸ばす秘訣を紹介する企画。
-

講師にやまもといちろうさんを迎え、社会保障に関するコラムをゼミ形式で発表してもらいます。
-

認知症の母と過ごす日々をユーモラスかつ赤裸々に描いたドキュメンタリー動画コンテンツです。
-

介護食アドバイザーのクリコさんが、簡単につくれる美味しい介護食のレシピをレクチャーする漫画です。











