撮影当時の関口監督の心境は?
母の気持ちを理解して受け入れ、トイレットペーパーへの固執にとことん付き合う!
2019年の現在から振り返ってこの動画を見ると、改めて母の認知症初期の難しさがよくわかりますねえ。
いわゆる<まだらボケ>であった母は、意志強固にして頑固!
そんな母の苛立ちや怒りの感情の爆発の前に、私は無力感を感じていました。
以前も書きましたが、母の認知症というより、母の性格と対峙する毎日でした。
本人の「こんなはずはない」という気持ちが手に取るようにわかりながらも、私にはその気持ちを上手に慰め、おさめることができなかった…。
特に母のトイレットペーパーへの固執は、母の尿失禁が背景にあり、デリケートかつ重大な問題だったのです。
プライドの高い母ですから、尿取りパッドや紙パンツへの移行なんてトンデモナイ!
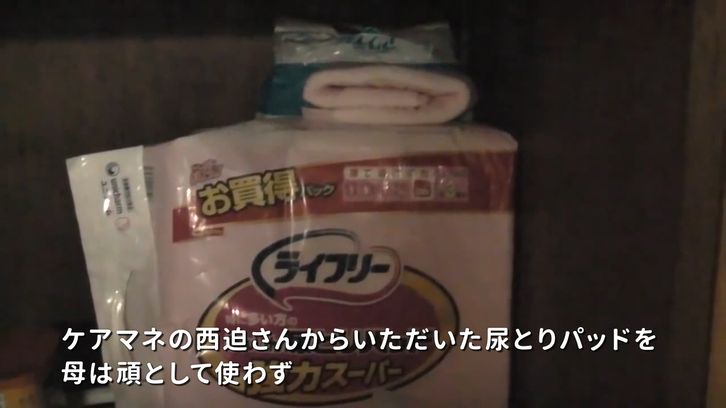
この時点で私は、そんな母の気持ちを理解して受け入れ、トイレットペーパーへの固執にとことん付き合うことにしました。
認知症ケアは、介護者である私の視点や考え方一つで、まったく違う景色が立ち現れる…。
そんなことを理解し始める第一歩でしたね。
相手を変えることは不可能。そうであれば、自分がどのように考えを改め、状況を分析し、計画を立てて行動をするのか。
そんなことを深く考えさせられるキッカケになった<ありがたい>トイレットペーパー事件でした。
そのとき関口監督がとった行動は?
母に気づかれれば、怒りを買う。だから、気づかれないように<母を見守る>
取りあえず、母に気づかれないように<母を見守る>ことにしました。
母に気づかれれば、怒りを買う。
本人は如何せん<見守り>が必要だとは思っていない訳ですから。
そんなスリリングな母と娘の状況でした。
当時、大人の3輪車で出かける母を慌てて撮影したことを鮮明に覚えています。

なぜ鮮明だったかと言えば、カメラのレンズを通して見える光景(自分で小型カメラを持って撮影)は、裸眼で見るよりも記憶に留まりやすいからです。
カメラのフレームの中の母の行動や言動は、映画のシーンとして使うかも知れないという意識の高まりから、メンタル・ノートに焼き付いてしまうんですね。
母は3輪車の運転もおぼつかない!ふらつきが出ている?
私が即座に決断したのは、私も自転車に乗って、母の後を追うということです。
母は、私が追い越しても気づかない。母を待ち受けて撮影しても私の存在に気づかない。
それだけ彼女の頭は、トイレットペーパーでいっぱいだったのでしょう。
母の記憶がまだらであることの素晴らしさは、スーパーマーケットに到着し、トイレットペーパーさえ購入すれば、落ち着きを取り戻し、あたかも私がずっと一緒だったと思ってくれるということでした。
だから、買い物終わりに、母の大好きな珈琲を一緒に飲もうと誘えたのです。
そして、ビデオカメラを出して母のそんな様子を撮影しようとしたら、母ははじめてビデオカメラを叩いた!
私の反応はというと、母よりもカメラの方が大事だと思い、即座に撮影をやめましたね(笑)。
関口監督から読者へ伝えたいメッセージは?
まずは<認知症を恐れない>ことがステップ1。正しく理解すれば、むやみに絶望することもないのです
この連載も16回目になりました。
改めてここで強調したいのは、介護する側の心構えです。
今の日本では、どうしても認知症を大変な病気だと考えてしまうと思いますが、まずは<認知症を恐れない>ということが大事なのではないでしょうか。
これが、ステップ1だと思います。
家族が認知症を発症しても絶望しない。
正しく理解をすれば、むやみに絶望するようなこともないのです。
ただし、自分の固定概念や主観からの脱却が強く求められますので、そこのところをどのように自覚し、行動するかによって介護の負担がまったく変わってきます。
都立松沢病院の齋藤正彦院長は<認知症を体験する>という表現を使われます。
<認知症を治す>という考え方ではありません。
認知症のご本人やご家族が体験している苦悩や、悲しみ、不安を医療者や介護の専門職がいかに共感を持って感じることができるのか。
そして、認知症の本人だけではなく、家族に対してもどのように適切なサポートができるのかを考えていらっしゃるそうです。
私の連載は、母の数々のエピソードに対して<私はどう感じて考え、分析し、行動したのか>ということに尽きます。
深刻になってする介護は、介護される本人を追い詰めてしまいます。
介護に必要なのは、愛よりも理性であり、科学。
これからもそんな事例を書いていきますね。
今日は大晦日、激動の2019年が終わろうとしています。
介護には年末年始も関係ありません。
でも、どんな日でも太陽が昇らない日はありません。
皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください。
平和を強く祈念して。



