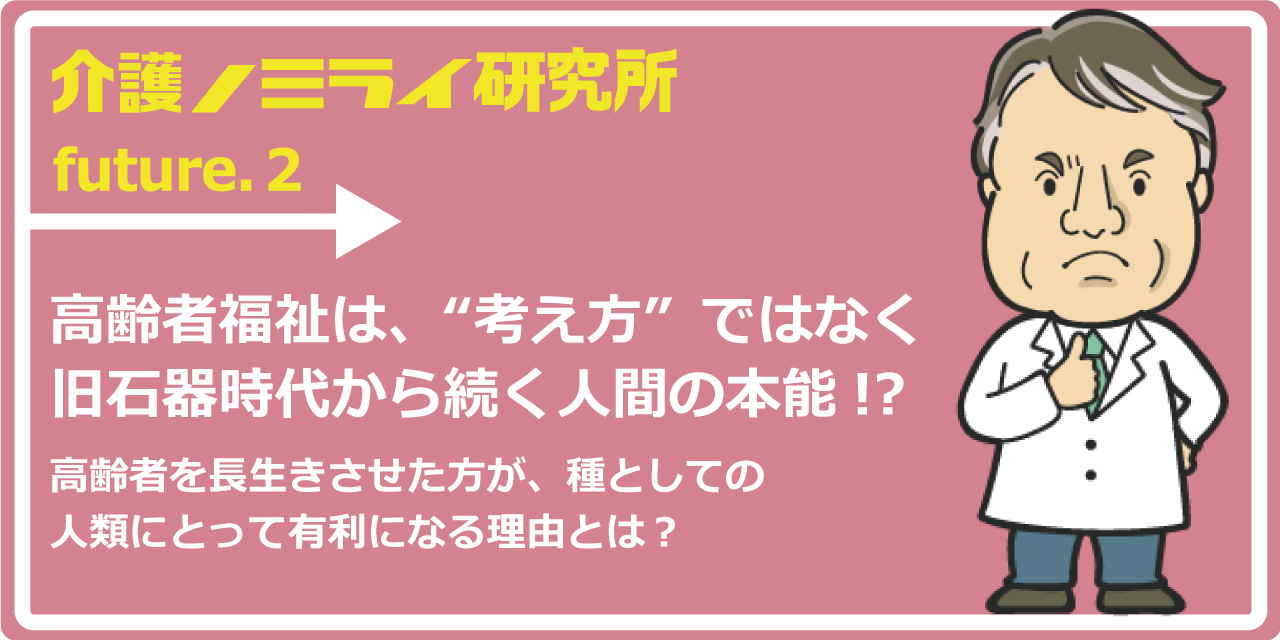連載第1回「弱者への自己責任論の強要は間違い!?」では、進化論の前提である、生物が子孫を「過剰生産」するという事実について考えました。ここから、社会的弱者の「自己責任」を(過剰に)問うことの間違いについて、指摘しています。
急速に発展しているかに見える科学技術は、その発展の方向性に問題があります。このままでは、人類の大量死滅を避けることはできません。そうした背景を受けて、今回は、なぜ、介護の未来を考えることが大事なのかについて、考察を進めてみようと思います。
誰もが素晴らしい才能の持ち主…だけれど、
遺伝子がすべてアクティブになっていないから
その才能が発揮できていない!?
美容整形で著名な、高須クリニックの高須克弥院長は、自分の恋人に整形手術をすることを拒否しているそうです。その理由として、高須院長は「人は欠損に恋をする」と言っています。欠損とはつまり、不完全と言い換えても良いかもしれません。これは、進化や遺伝子という側面から考えても、とても鋭い指摘です。
一般には、特定の才能がある人に対して「そういう遺伝子を持っている」と言い方をすることが多いでしょう。数学の才能、音楽の才能、サッカーの才能、プログラミングの才能、そして外見の美しさ…この世界は、なんて不公平なのかと嘆いた経験は、誰にでもあると思います。
ただ、こうした不公平は、遺伝子のあるなし「だけ」で決まっているわけではありません。実は、誰もが、こうした様々な才能をつかさどる遺伝子を持っている可能性があるのです。ただ、そうした遺伝子がアクティブ(表現型)になっていないだけかもしれません。

実際に、最新の進化論(エピジェネティクス進化論)による発見が、この可能性を強く示唆しています。
こうした最新の研究によれば、個々の遺伝子には、メチレーション(メチル化)と呼ばれるカバーがかかっています。このカバーがはずれている遺伝子だけがアクティブな状態にあり、特定の才能だけが開花するという仕組みになっているようなのです。
そして、カバーであるメチレーションは、特定の経験がトリガーとなって外れるようになっていると考えられています。残念ながら、トリガーとなる経験の具体的な中身については、まだ解っていません。これがわかれば、私もイケメンになれるはずなのですが…。
人は「不完全」を好きになる生き物
欠損の組み合わせ=あなたの魅力?
さて、私たち人間の遺伝子には、700万年の人類史を勝ち抜いてきた特徴が記録されています。おそらくは、40億年以上にわたる生命の歴史もまた、そこにあるでしょう。そうした膨大な遺伝子のうち、どの遺伝子をアクティブにさせるかを、このメチレーションが決めているわけです。
現在の自分というのは、自分の遺伝子が持っている可能性の「ほんの一部」によって、表現されているかもしれないということです。おそらくは、アクティブになっていない遺伝子のほうが多いはずです。
そう考えたとき、個性とはすなわち、高須院長が言う「欠損」のことに他なりません。比喩ではなく、本当に「欠損」させられている可能性が高いのですから。
個性とはすなわち、個体間の「欠損」の違いなのです。勉強が得意ではない、運動が得意ではない、鼻が低い、足が短い…そうした「欠損」のパターン(組み合わせ)は、自分独自のものです。そして、その「欠損」を好きになってくれる相手がいたからこそ、私たちの遺伝子は、今日まで残ってきたということは、忘れてはなりません。
そもそも、好みが異なるということは、それぞれの個体が魅力的に感じる「欠損」が異なるということでもあります。こうした好みの違いによって、進化論が述べるところの多様性が担保されていきます。
自分の「欠損」に関する悩みも多いものです。しかし、そうした「欠損」の組み合わせが、むしろ生存戦略上の強みなのです。
完璧な人間こそモテない?
特定の才能×特定の環境=1番モテる
「すべて」の遺伝子がアクティブな状態を理想と考える人もいるでしょう。完璧にあこがれてしまうのは、私だって同じことです。しかし、こうした「あれも、これも」という考え方は、経営学(戦略論)によって否定されています。「選択と集中」こそ、競争優位の源泉なのです。
「すべて」がアクティブな状態では、結局のところ、器用貧乏に陥ります。特に、ただ1人の相手を見つけるという競争には(何世代にもわたる長期的な競争には)勝てません。これはいわば「ボタンの多いリモコン」のようなものだからです。
進化論では、種の多様性が、特定の環境に適応できる可能性を(偶然)高めるという考え方をします。そして種の多様性は、これまで考えてきたような才能の「欠損」によって表現されているというのが、最新の進化論です。そして、具体的にどのような「欠損」が有利になるかは、環境によって異なるという点は、とくに重要です。
たとえば、歴史上の偉人と呼ばれるような人の個性も「欠損」で表現されています。特定の才能をもっていた人物が、特定の環境にいたから、偉人になれたわけです。しかし、それと似た「欠損」を持つはずの偉人の子孫たちは、必ずしも偉人にはなれていません。時代によって、適応すべき環境も異なるからです。
繰り返しになりますが、これは、個人の運命は、遺伝と環境によって決まるということを意味しているでしょう。
逆にいうなら、遺伝子からしても、どのような「欠損」のパターン(個性)が、特定の環境においてもっとも有利であるかは判断できないのです。だからこそ生物は、その種の中でランダムに「欠損」のパターンを生み出し続けています。多様性によって、チャンスをつかむ個体が「偶然出てくる」ことに賭けているということなのでしょう。
現代社会が求める新しい価値観。
ヒューマニズムの思想に代わる◯◯ismとは?
自然淘汰は、こうした「欠損」が環境に適応していない個体に対して起こります。それは、連載第1回でも指摘したとおり、自己責任ではありません。そうではなくて、子孫の「過剰生産」を前提とした、遺伝子の生存戦略なのです。
ここまで話を進めれば、特定の環境から脱落者が出てしまうのは、生物であれば仕方のないことであることが理解できるでしょう。そして社会福祉は、こうした脱落者に対するセーフティーネットとして機能してきました。
一般には、社会福祉は、崇高な倫理観をもった人類が生み出したものと信じられています。不運にも脱落者になってしまった個体に対して救いの手をさしのべるのは、人類だけだと考えられてもいるでしょう。これが、人類を「ヒューマニズム(人類中心主義)」という方向に走らせた、ひとつの根拠でもあります。

「ヒューマニズム」というと、なんだか良いことのように感じられるかもしれません。しかしこの背景にあるのは、他の生物よりも、人類のほうが上位にあるという傲慢です。この傲慢から、人類は、他の生物を支配しても構わないというロジックを組んでいます。
これは、神を信じられなくなった人類が、自らを自然の支配者として位置付けるための思い上がりなのです。
誰もが、動物園や水族館に閉じ込められている生物、ペットとして売られていたり、食べ残され続ける生物について「なにかが間違っている」と感じたことがあるはずです。
私たちはしかし、そこに「ヒューマニズム」という思想を持ち込むことで、それに目をつぶってきました。それでも「ヒューマニズム」に生物学的な根拠などありません。
そんな「ヒューマニズム」を正当化させているのが、社会福祉の存在であるという点は、とくに重要です。社会福祉の崩壊が怖いのは、それが、人類から「ヒューマニズム」という幻想を奪うからです。
そうなったとき、人類は、他の動物を殺害することと、他の人類を殺害することの差異を見失います。私はこれが、立派な人物でさえ、いざ戦争になると、他者の殺害をためらわなくなることの背景だと考えています。
利他性こそ人類の文化?
原始的かつ最強の生存戦略である理由…
「ヒューマニズム」が幻想であることを認識してしまうとき、戦争のリスクは極限まで高まります。とくに、親類縁者(生物学的には特に血縁)を見捨てざるを得ない状況は、人類をして「ヒューマニズム」への絶望をうながします。
そして介護は、多くの個人が、親族への「ヒューマニズム」が発揮できなくなる可能性の高いイベントなのです。介護の未来と、戦争のない平和な世界は、直結しているわけです。
しかし、連載第1回でも考えたとおり、短期的には社会福祉の崩壊は避けられそうもありません。そうなると、戦争を避けるためには、ヒューマニズムという幻想に変わる何かが必要になってきます。
これこそ、現代社会があたらしい価値観を求めて迷走している背景だと、私は考えています。

なお、こうした時代には、お手軽でスピリチュアルな解決策に期待が集まりやすい傾向があります。社会福祉の充実こそが保守本流であるにもかかわらず、です。
たとえば、三国志の時代(およそ100年で人口の86%が消滅した)にも、スピリチュアル・ブームがありました。史実としての曹操は、社会福祉を考えながら、スピリチュアルを売るインチキ商売の取り締まりに苦労しています(詳細は拙著『曹操 ― 乱世をいかに生きるか』PHP研究所をご参照ください)。
そもそも、人類が理性によって築いてきた(と信じている)社会福祉というのは「ヒューマニズム」のような幻想によって支えられているのでしょうか。単に、環境の収容能力が都合よく成長していたことによって、自然淘汰が(あまり)急激には起こらなかっただけとも考えられます。そのほうが、生物学的にはありそうなことです。
ここにこそ、実は希望があります。まず、おそらくは、社会福祉というのは同胞を助けるという利他性によって支えられている本能です。人類はこれを「ヒューマニズム」の根拠としてきたのですが、利他性というのは思想ではありません。利他性は、アリにも見られるようなかなり原始的な生存戦略であり、本能なのです。
他の生物にも見られる特徴なのですから、この利他性によって「ヒューマニズム」は正当化されません。しかし人類が、利他性をその生存戦略の中心にしてきたことは、旧石器時代の人類の研究などから、事実であると考えられています。
人類は、他の生物よりも上手に利他性を活用してきたと考えられるのです。それが社会福祉だと考えたとき、見えてくる世界が違ってきます。
高齢者福祉は人類だけの本能だった!?
人間の本質に迫れば見えてくるものとは
社会福祉は、自然淘汰からの脱落者(運が悪かっただけの個体)を守るように作用します。それによって、人類の遺伝子はより多様な状態で、より長い期間生き残ることが可能になります。こうして、多様性を維持することは、環境の変化に(偶然)適応する個体が生まれる確率を高めるでしょう。
人類は、かつては、6~7種類はいたことがわかっています。しかし今では、私たち(ホモサピエンス)だけ、ただ1種類が生き残っています。この原因も、ホモサピエンスが備えている利他性をベースとした社会福祉であるとしたとき、利他性が持っている進化論上の意味がスッキリしてきます。
アリの場合もまた、自己犠牲的な利他性によって集団を守ります。この本能によって、絶滅を逃れ、自然淘汰を生き残ってきました。
お互いの存在を大切にすることには、進化論上の合理性があるということです。しかし、人類とアリのような生物の利他性の間には、大きな違いがあります。それが、高齢者福祉の存在です。
そもそも、人類以外の生物で、子供を産めなくなった高齢の個体が生存できるという哺乳類は(ほとんど)存在しません。
しかし人類の女性の場合は、閉経後も寿命が続くという点が非常に奇妙なのです。ここには、なんらかの適応がある可能性が高いのですが、いまのところ多くの議論が続いています。

日本には、高齢になった女性を山に捨てるという「姥捨山」という伝説があります。一部には、そうしたことも本当にあったのでしょう。
しかし、人類全体の統計としてみたとき、この伝説は人類の特徴ではありません。人類史において、食糧難のとき「口べらし」として殺されてきたのは、高齢者ではなくて子供です。少子化もまた、社会が、まだ生まれてくる前の子供を殺しているようなものだとしたとき、この事実は強調されてきます。
生存や生殖の危機がある場合、子供がまずその犠牲になるというのは、生物の設計でもあります。同種の個体間における子殺しは、人類以外の他の生物にも頻繁に見られることです。
人類社会における子供の虐待問題も、生物の本能という視点から考えてみる必要もあると思います。子供の虐待と貧困に相関があるというのは、生物学的には自明とも言えることなのですから。
社会福祉の崩壊は、これからの人類に
何をもたらすのか?という想像力が必要
念のために強調しておきますが、私は、子供を殺すことや虐待を正当化しようとしているのではありません。そもそも私たちが「悲しい」と感じることが、生物学的に正しいというのはあり得ないと考えています。そうではなくて、そうした「悲しい」ことを減らすためには、本能について理解する必要があるという立場です。
さて、そんな人類の遺伝子が、他の生物とは異なり、高齢者(とくに女性)の生存を支持しているという事実は、かなり不思議です。
不思議ではありますが、高齢者の生存を維持したほうが、種としての人類にとって有利になる(なんらかの)理由があるのは間違いなさそうです。そう考えるのが、進化論を考えるときの大切な視点でもあります。
たとえばこれを「儒教があるから」とするのは、正しくありません。むしろ「なぜ人類の遺伝子は、儒教のような考えを生み出すのか」といった、その背景にある、進化論上の合理性を探る必要があります。
同様にして、社会福祉(特に高齢者福祉)が崩壊することは、生物としての人類になにをもたらすのかという想像力が、いまこそ求められているのです。
とはいえ、高齢者福祉の背景に、進化論上、どのような合理性があるのかは、いまこところ科学では解明されていません。そこで、あくまでも推測にすぎませんが、連載第3回となる次回は、ここについて、経営学(戦略論)の視点から考えてみようと思います。