介護現場の“ワンオペ夜勤”解消を目指して…介護・福祉を支えるエッセンシャルワーカーの声
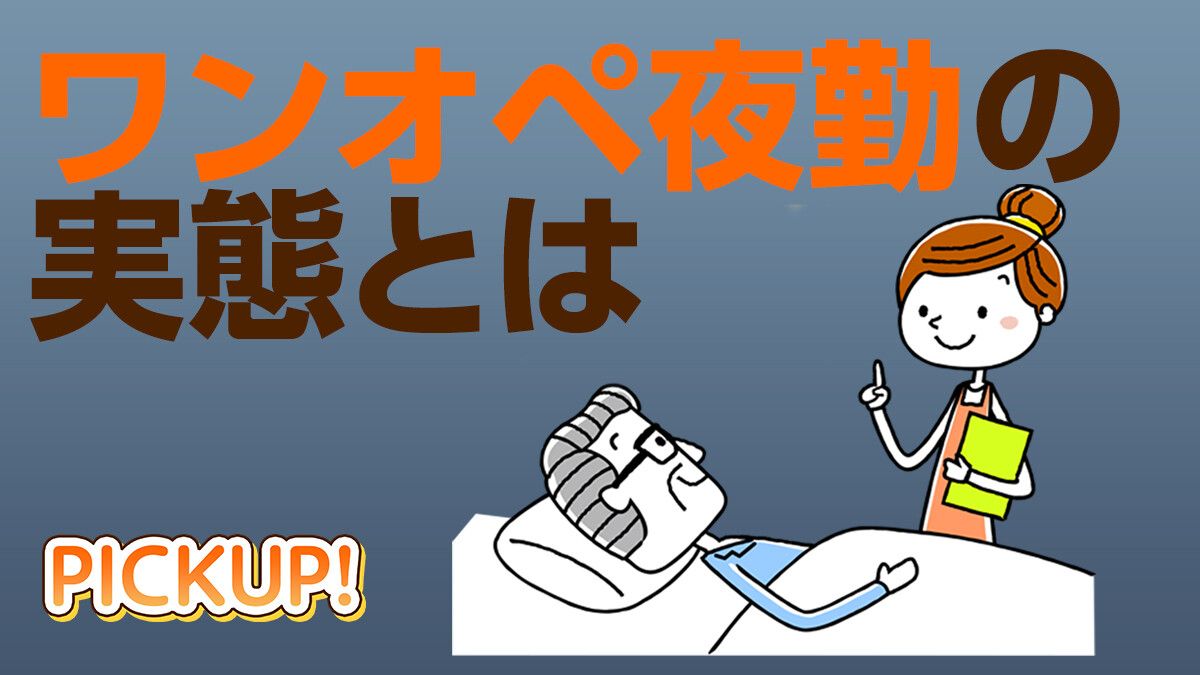
介護現場の“ワンオペ夜勤”解消を目指して、4万人の署名が集まる
2022年11月11日、介護職員らの労働組合が、施設での1人夜勤を行う「ワンオペ」をなくして複数配置を前提とするよう求める要望書を、4万人超の署名を添えて厚生労働省に提出しました。
組合側は要望書の中で、介護施設において夜勤のワンオペが多いこと、夜勤職員の責任が非常に重いことを指摘。
ワンオペでの夜勤時、介護職は事故を起こさずに過ごすことで頭がいっぱいとなり、そのストレスの大きさから退職につながるケースがあることも言及しています。
ワンオペの負担軽減策としてはICT(情報通信技術)の活用に近年注目が集まっています。例えば、人感センサーなどを居室内に設置することで、介護職の見守り業務の負担を軽減するといった方法です。
しかし、要望書の中では、ワンオペによる負担の大きさはICTの活用では必ずしも軽減できないと指摘しています。実際、センサーなどが異常を検知しても、現場で対応するのは介護職自身となるため、「一人で対応する」という重圧は避けられないからです。
“ワンオペ夜勤”とは?
ワンオペとは「ワンオペレーション」を略した言葉で、夜勤を1人体制で行うことを意味します。
夜勤業務は一般的には、夕食後の歯みがきや寝巻への着脱介助などの就寝準備に始まります。そして、就寝時間後は、1~2時間おきにすべての部屋を巡回する安否確認を行いながら万一の急変の際などへの対応に備えます。
加えて、夜中には呼び出しがあれば居室に駆けつけて排泄の支援もその都度行います。
そうした安否確認と排泄介助などのケアをしながら、介護記録の作成と館内の掃除などを実施する必要があるのです。
そして、何より負担が大きいのは、夜勤の最後に待ち受ける起床介助です。
入居者は5時頃から目が覚め、それに合わせて排泄介助を望む呼び出しが増えてきます。“ワンオペ夜勤”の場合には、10人から数十人の入居者のケアを手早く行わなければなりません。
さらに、起床介助が終わると、朝食の準備を行います。夕食時と同じく、食事の配膳、介助、片付け、服薬管理を実施。朝食が終わるころには、日勤の人が出勤するので、引継ぎを行ってようやく“ワンオペ夜勤”が終わります。
“ワンオペ夜勤”、当事者の声
利用者の健康・事故のリスクに対して一人で対応しなければならない責任は大きく、“ワンオペ夜勤”は日勤より遥かにストレスが大きいものです。
全国福祉保育労働組合東海地方本部と愛知県医労連が実施した夜勤実態アンケート(2021年9/1~10/31調査)には、現場からのこんな声が寄せられました。
・コールが重なって、対応しきれない事が毎回ある
・看護師が1人なので、急変者が複数でると、対応できない
・センサー使用患者が同時になった時。優先順位を考えたり走って別フロアへ行かなければならない
・ナースコールが何件か重なる時があり、朝では5~6件重なった時は恐怖を感じる
(介護・障害職場の夜勤実態アンケートまとめ「夜勤に関して、あなたのヒヤリハット事例を教えてください」より編集部抜粋)
この他、ストレスから利用者の方に怒りをぶつけてしまいそうになるという悲痛な声も複数見られました。
“ワンオペ夜勤”の根本的解決に必要なのは「介護人材の確保」
この問題を解決するためには、実際に夜間に複数配置を行うために十分な人員を確保することが不可欠です。
介護サービスの利用者にとっても、現場の働き手にとっても、国・行政のさらなる対応が必要となりそうです。





