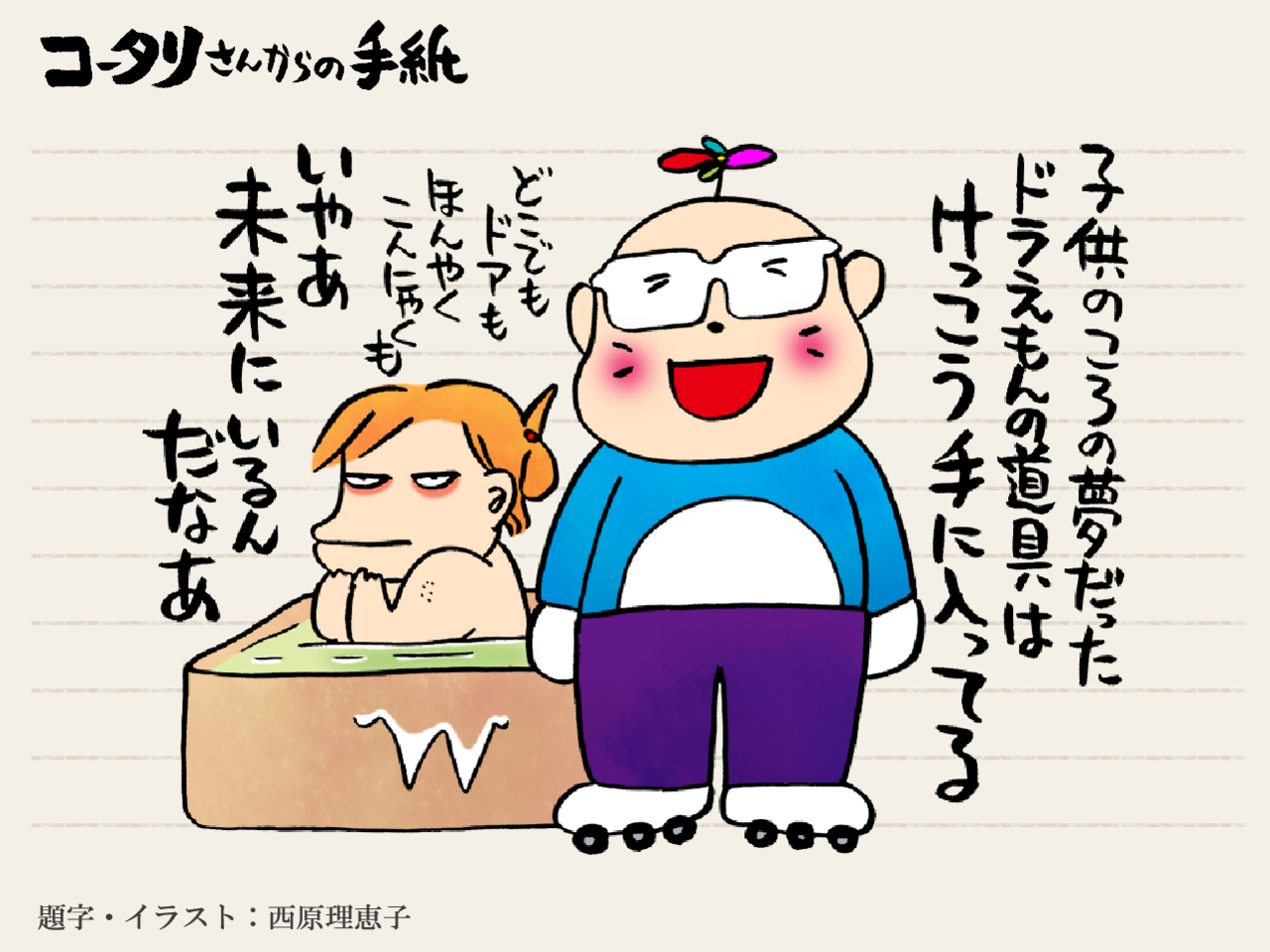全国で緊急事態宣言が解除されたが
もとどおりの生活に戻ったわけではない
全国で緊急事態宣言が解除された。それでもまだまだ新型コロナウイルス感染症の流行前のような生活に、戻ったわけではない。
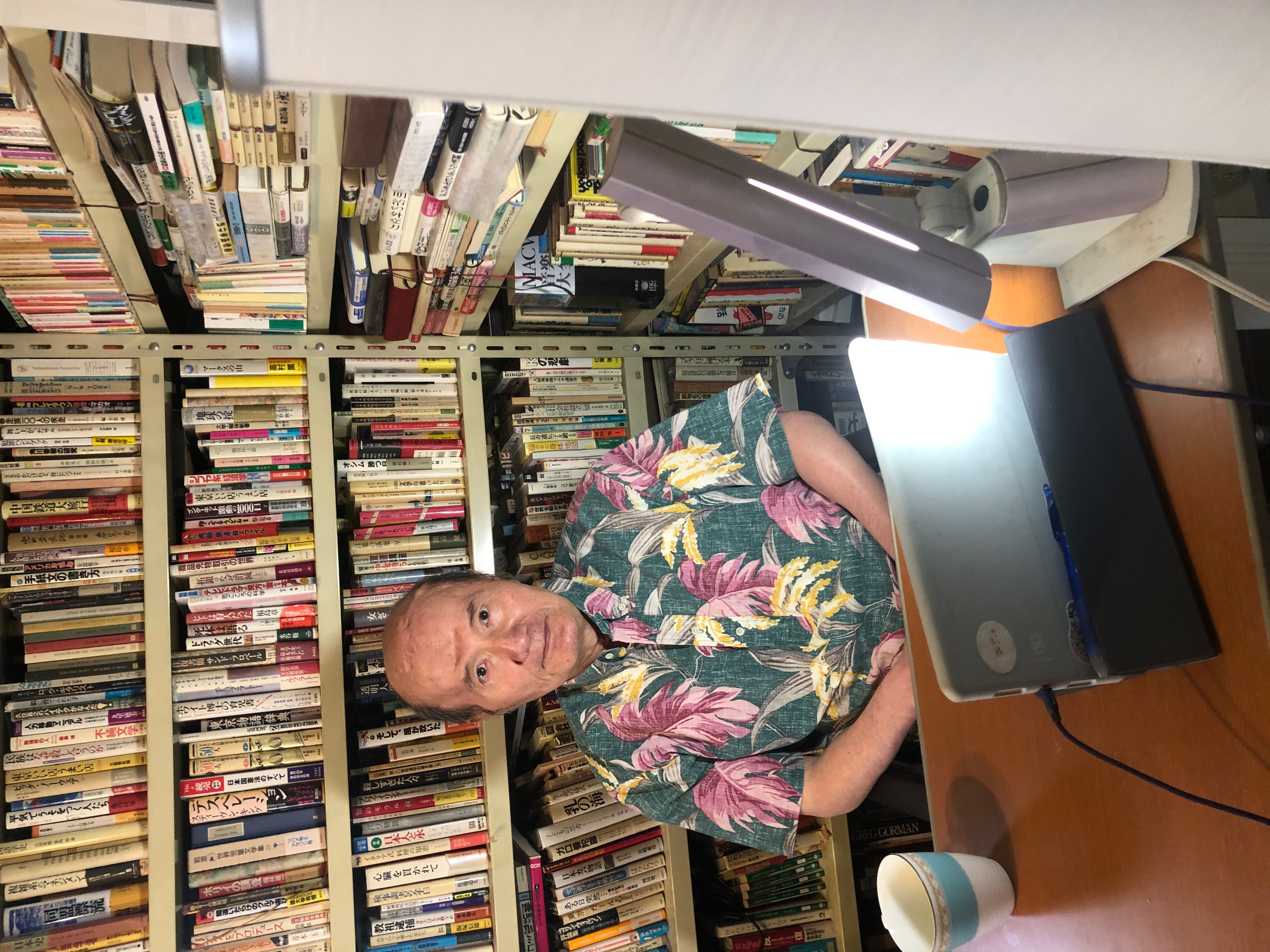
感染を防ぐために最善の注意を払っていた外出自粛期間が明けても、どこまで以前の生活に戻って良いのか、誰もが悩むだろう。国や自治体のガイドラインがあったとしても、「果たしてそれで本当に大丈夫なのか」と思うだろう。
もちろん、飲食店が従来のように夜中まで営業するのは賛成だし、映画館や文化施設が早く再開することを望んでいた。知り合いの高齢者たちの中には、「1歩も外出てないよ」とか「買い物は3日に1度だけ」なんて話している人が多い。
電話で話すと「1週間ぶりに人と話した」「久しぶりに買い物に出たら転んで病院に行った。きっと足腰が弱くなったのよねえ」なんていう話も聞いた。これも「コロナの負の出来事」だよなあと思う。
「コロナの負の出来事」に直面しているのは、高齢者だけではない。経済が回らなくて困っている大人たちもいるし、家での仕事が逼迫した人や、学校に行けない子どもたちの健康面や学力低下も心配だ。「コロナで失ったもの」を挙げるときりがない。
しかし、良いか悪いかは別問題として、「コロナのお陰で、ほんの少し発展したよなあ」と思うこともある。「オンライン関係の活用」だ。いつもは外で集まったりして行っていたことを、オンラインで行う流れが進んでいる。
「オンライン診療」や「オンライン⾯会」が広がる
対面時よりも会話の数が増える!?
TVで観たものには、「オンライン結婚式」なんていうのもあった。大きな式場に集まっているのは、新郎新婦とその両親だけ。
披露宴会場に設置された機材でその場を映し出し、全国にいる親戚や友人などと中継を結ぶ。全員で20人強の参加者だったが、式場にいる本人たちと同じ3段重のような料理を自宅でいただけるそうだ。
皆家にいて、正装でパソコンや携帯の前に座っている。乾杯の音頭もケーキカットも行う。思い出のVTRも流す。新郎新婦の姿を生で見られないということ以外ほとんど普通の結婚式と変わらない。パソコンやテレビモニターの画面越しではあるが、参加者全員が会話できていて、普通の披露宴よりも参加者とたくさん話せている。
地方にいるおじいちゃんやおばあちゃんは「会えないのは寂しいけれど、一緒に祝えるとは思っても見なかったのでうれしい」とのこと。そりゃそうだ。
そのほかにも「オンライン診療」や「オンライン面会」などが話題になっている。「オンライン法事」や「オンライン葬式」なんてのまで見かけた。
新型コロナウイルスの影響で医療機関は大変混乱していた。そんなときは、「慢性的な症状に処方されるいつもの薬などをもらいに、病院に行くのはどうなのか?」と考えるだろう。もし、家にいながら、TV電話などで診察をしてもえて、処方箋を出してくれるのなら大助かりだ。
病状の変化に心配のある人には向かないが、「3ヵ月に1回診てもらって、薬をもらいに行ってるんだ」というような人達向けに、あってもいいサービスかもしれない。
触診がない分、対面診察よりは誤診が心配かもしれない。しかし、対面より聞きやすいとか、事前にメールで問い合わせしておけることや、病院まで出向く手間がないなど、メリットもある。
デジタル化が進んだけれど
古き良き時代が戻ってきたようにも思える
百貨店も開いていなかった期間は、オンラインの買い物なんていうのも、もちろんありがたかった。
緊急事態宣言の間にも不幸もあったし、結婚した若者もいた。贈り物をするとき、普通だったら「銀座にでも行ってデパートでなにかを」ということになるんだろうが、外出自粛期間中は、インターネットで購入して届けてもらった。
近所のスーパーも時短営業になった。午前中にホームページから商品を頼んでおけば、夕方までに届けてくれる。電話での注文もOKだそう。84歳になる義父は「なんだ御用聞きか」と言った。
昔は、近所の酒屋さんが「御用聞き」をしてくれたと言う。「サザエさんの三河屋さん」だね。酒屋さんには瓶ビールに味噌や油を注文して、ついでに魚屋さんに寄って「秋刀魚を5尾買ってきて」なんて頼んでいたそうだ。
どうしていたかというと、「今日は何かありますか?」と裏木戸を開けて、御用聞きが毎日来ていたと言う。氷屋さんが氷を届けに来たり、豆腐屋さんが豆腐を売りに来たりもする。
野菜だって、産地から担いで売りに来ていたそうだ。「だからおばあちゃんが1人で留守番していても困らなかった」と言う。ボクの子どもの頃の時代の話だ。
妻の実家は、都内の住宅街にあったが、近くの中華屋やそば屋の出前は当たり前にあって、鰻や喫茶店、とんかつ屋なども出前をしてくれていたと話していた。
まるで「Uber Eats」のようだ。時代が変わって、デジタル化が進んだ。しかし、やり方こそ変化したものの、古き良き時代が戻ってきたようにも思える。
インターネット上で
人と人がつながる
新型コロナウイルスの影響で行き場がなくなった食品や、給食用の食材が、破格値でインターネットで売り出されていた。
普段は購入しないような高級食材から規格外で普段なら出回らない野菜なんかも、「お助け」という名目で売られていた。普段から、売り出せば良いのにと思ってしまう。
インターネットと流通網が発展した現在、全国の食材をどこにでも届けることができる。コロナ禍で、いつもと違う出前を取ってみたり、食材を注文してみたりした人も少なくなかったと聞いた。
それに、何と言ってもリモートワーク。インターネットでつながっていれば、自宅からでも通勤していたとき同じように仕事ができてしまう。もちろん、会社にいるときとは環境などが違うかもしれない。しかし、やり方を工夫することで意外とできてしまうことに気づいた企業も多い。日本中の活動が停滞しているときに、パソコンの中で、人と人がつながる。
もう何十年前からリモートワークをしているようなボクも、新型コロナウイルスの流行下でリモート会議をさせていただいた。
ボクは喋れないから、だいたい皆の話を聞いている。「神足さんはどう思います?」なんて質問されれば、部屋の離れたところにいる妻を、PC上の相手が「あきこさ~ん」なんて呼んでくれて、僕の意思を伝えるべくアシストしてくれる。
聴覚障がいの方用に、相手が話している言葉を、そのまま文字に起こせるアプリなんていうのもある。高齢者も、そのようなテロップ機能があった方が言葉がわかりやすいようである。
ハイテクと高齢者たちの
相性はとても良い
東京大学の登嶋健太さん率いる「シンロウジン」というグループがある。普段は外になかなか出られないお年寄りや障がいを持っている方々、入院中の人々に世界中の景色や、自分の家の周りをVR映像で見てもらう活動をしているグループだ。その映像を撮るのは、平均年齢70歳以上の元気な高齢者。
まだ30代の登嶋先生に教えてもらいながら、施設に映像を届けに行くこともある。毎週日曜日に渋谷のQWSというところで会議や活動をしていた。
3月中旬頃からは、その活動もストップした。その代わり、毎週日曜日にZOOM会議をしている。マウントディスプレーで皆でVR旅行に行ってみたり、ZOOMの使い方を考え直したりする。ハイテクな高齢者たちだ。

いつも思うのだけれど、こうしたハイテク名物と高齢者の相性はとても良い。高齢者だから無理だろというのは、想像力に欠けた人が考えることだ。先入観がないと、物事がすんなり受け入れられる。
新型コロナウイルスの影響で、外出が困難になった高齢者たちに、会話と外の空気感をお届けする良いチャンスとなった。
「コロナ騒動」では、ほとんどがつらいことばかりだったが、それを乗り越えるために「ちょっとこれは良かったかも」というものを挙げてみた。
「コロナ騒動」で急速に進んだリモートワークやオンラインの様々な取り組み。良いものは残して、さらなる時代の進歩に備えなければ。
新型コロナウイルスの流行をきっかけに「外出できない時間」や「リモートワーク」を体験した人たちが、今まで眠っていた身近なハイテクを取り入れる時がきた。