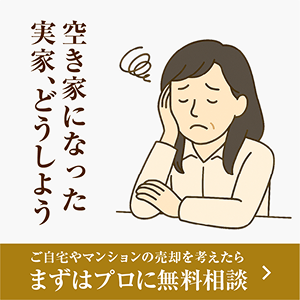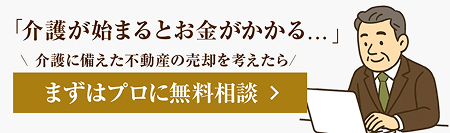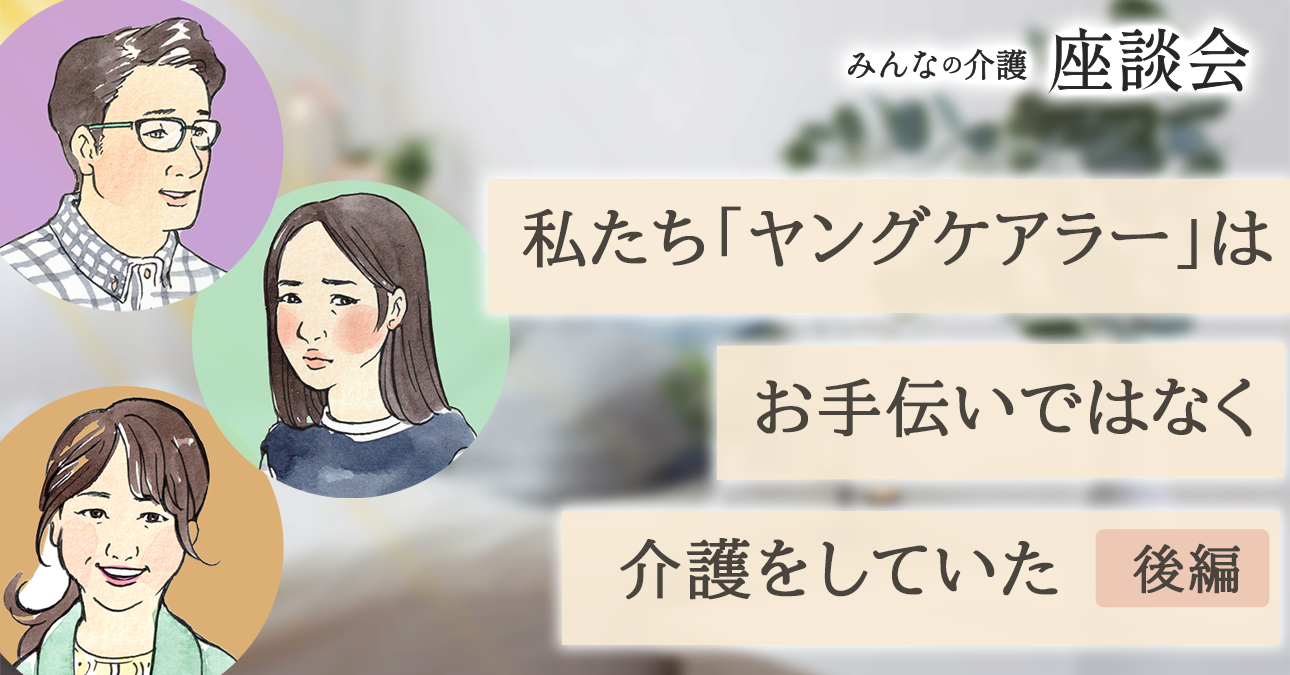
介護当事者の“本当の気持ち”を語らう「みんなの座談会」。前編では、ヤングケアラー・若者ケアラーにならざるを得なかった状況、同世代に感じていた“ギャップ”についてのお話を伺いました。後編では、ご家族での立場が弱く、反対意見もあった中で施設入所に至るまでの経緯について伺います。
この記事に登場するみなさんのプロフィール(敬称略)
高校生のときに母親がくも膜下出血で倒れて、要介護5の寝たきり状態に。
学校や仕事の後に母親の病院に通い続ける日々を送るなか、山本さんは結婚、出産し一児の母となる。その後、母親が約20年間の入院生活の末に他界。その後、父親にパーキンソン症候群の症状が見られるようになり、実家への通いの介護をしていた。症状の進んだ父親は2022年に特別養護老人ホームに入所。
大学生のときから、母方の祖父の介護を担う。父親は亡くなっているため、働く母親に代わり「学生ならば時間があるだろう」と周囲から促される形で祖父の介護をすることに。大学院に進学するも学友や教師からは介護に対する理解を得ることができず、大学院を中退。就職先で祖父の介護で得た経験を活かそうとしたが上手くいかず、転職。その後、祖父は他界。現在は福祉関係の資格を取得し、福祉関係の仕事をしている。
大学生のときから、母方の祖母の介護を担う。両親に聴覚障害があったため、事業をしていた祖父母が親代りとなって中村さんを育ててくれた。中村さんが小学生のときに、祖父と父親が他界。中村さんをサポートし続けた祖母に、中村さんが大学在学中に認知症の症状が見られるように。初めは祖母の事業のサポートをしていたが、そのうちに一人で生活全般の介助を担うようになった。その後、祖母は特別養護老人ホームへ入所し、最期を迎えた。
施設入所という大きな壁
先が見えない在宅介護に限界を感じるようになったみなさんは、施設入所について考えるようになりました。ただし、施設入所にあたり、ご自身だけでなくご家族にも「さまざまな思い」があるようです。
みんなの介護(以下、―――) 前編では、施設入所の申し込みをしている最中に、おじいさまが亡くなってしまったお話も井上さんから伺いました。当時のお話を伺えますか。
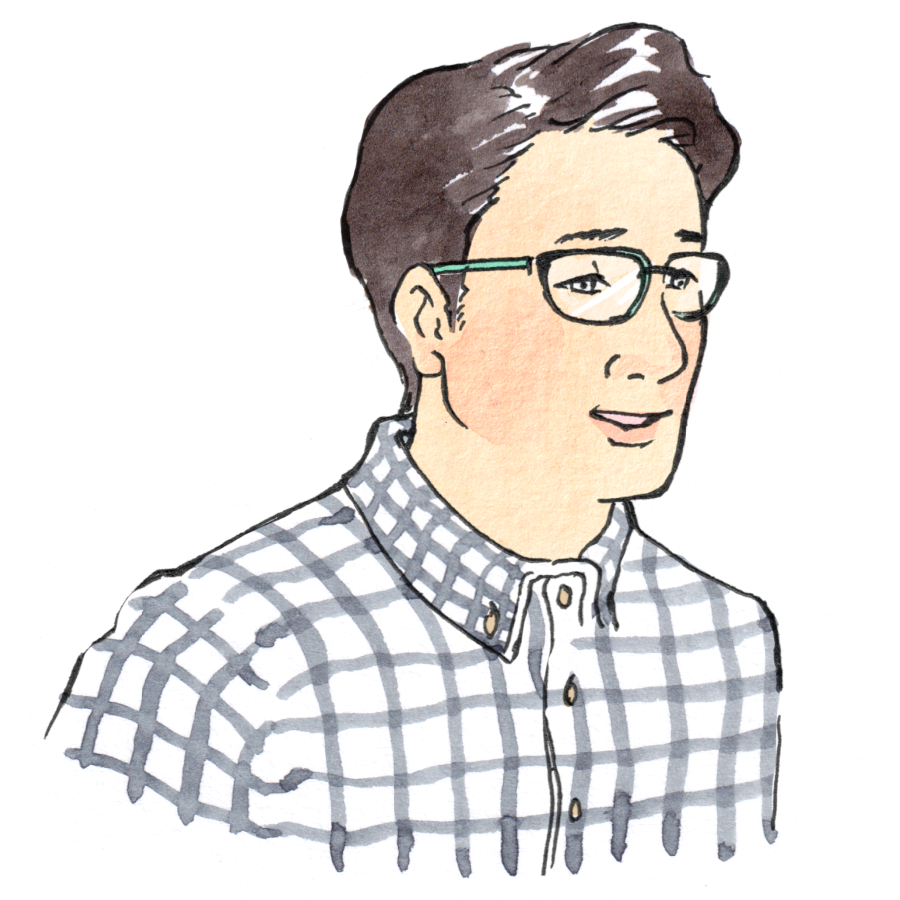
井上
祖父が亡くなる半年前ぐらいに、特別養護老人ホームの申込をしていました。でも、同居家族がいることで入所判定基準の点数が低く、入所できないまま時間が経過し、家で看取りました。
私は早い段階から祖父の施設入所を希望していましたが、母は「祖父が家族のことを忘れたら入所させたい」と、話を進めることが難しかったんです。
さらに、「口は出すけどお金は出さない」という親戚の方から、「学生で暇なヤツがいるならば、そいつが介護すればいいのでは?」と言われたこともあるそうです。
ヤングケアラーや若者ケアラーの悩みのひとつには、家族内で立場が弱いことがあげられます。学生であれば金銭的に自立していないことも多く、“社会人”として働いていても家族を支えるほどの経済力がある方は一部です。現実問題として「言い返すことが難しい」という問題があるようです。
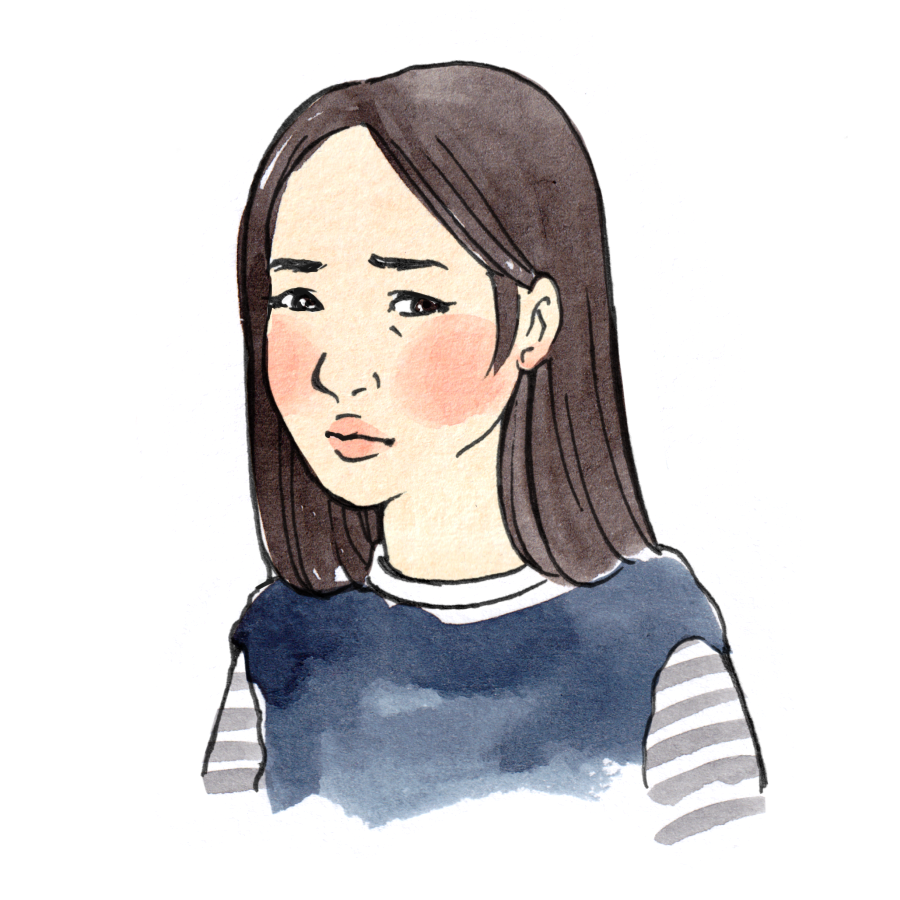
中村
私も同じでした。そろそろ祖母に施設へ入ってもらいたと思っていても、家族の賛同がなかなか得られませんでした。
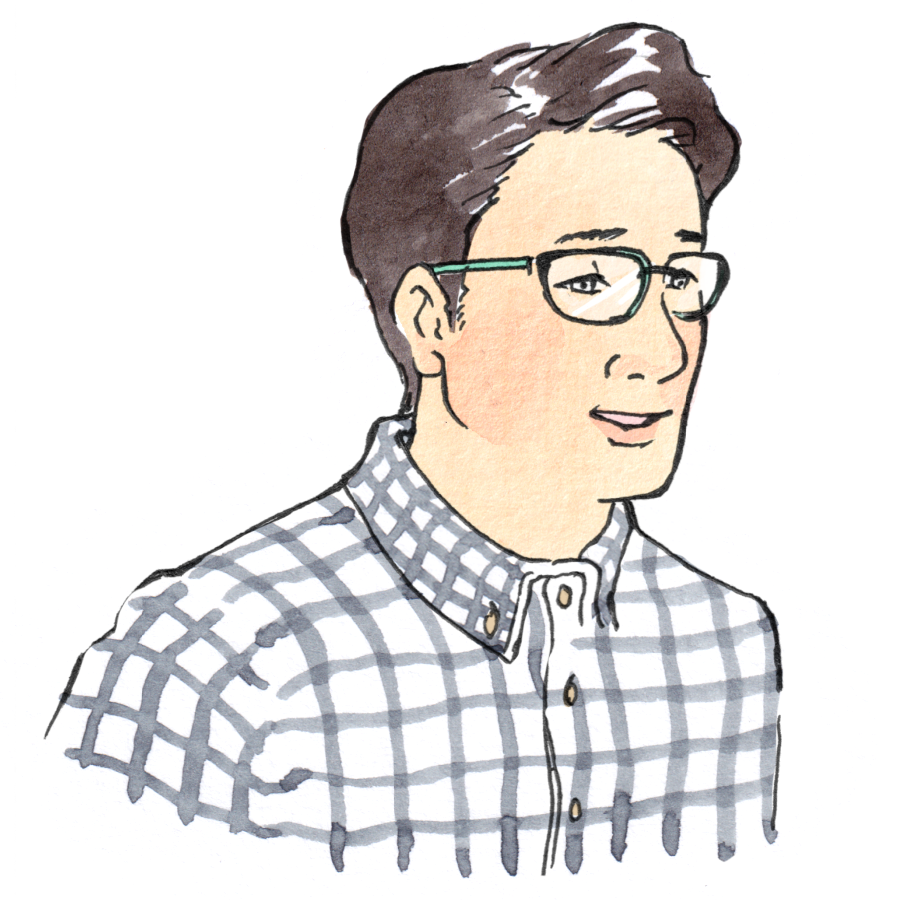
井上
でも、施設の相談員の方からは「施設に入ったからといって、介護が終わるわけじゃない。それも介護の一つの形だと思って、申し込みだけでもしてみては」とアドバイスをいただきました。
それまで入所の話を聞き入れてくれなかった母も、“専門職”の方の言葉ですんなりと納得したんですよ。そのときは、専門職の方の声掛けというのは力があるなあ、と思いました。
――― 中村さんは、おばあさまが施設へ入所するときに「葛藤」はありましたか。
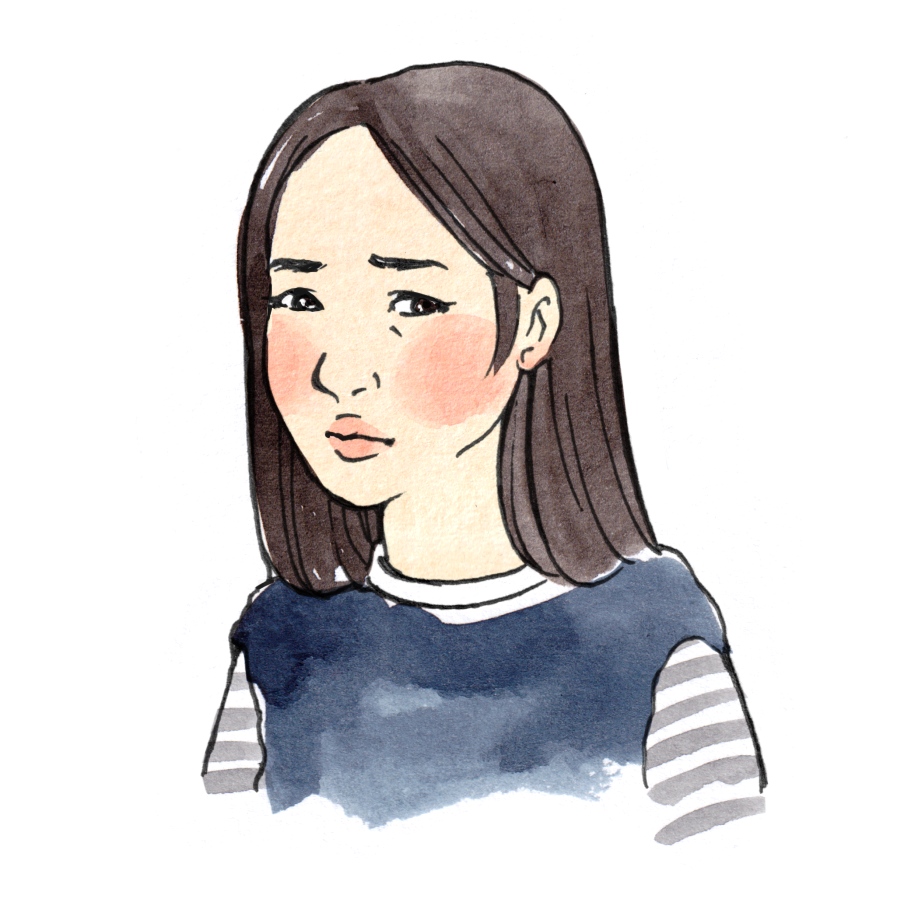
中村
家族の反対があっても私の持病が悪化する心配もあったので、祖母の特養の申し込みに踏み切りました。そのときに来てくださった調査員の方が私に向かって「あなたの人生も大事なんだから、おばあさんを施設に入れることに罪悪感を持たなくていいですよ」と言ってくれたんです。
あの言葉がなかったら、祖母を施設に入れたことにずっと罪悪感を持ち続けていたと思います。
調査員の言葉によって、中村さんは「私が考えていたことは、別におかしなことではないんだ」と自信が持てたそうです。そして、祖母が施設へ入所したら「自分の人生を生きるために私は働く」と、周りの方々に宣言しました。
井上さんや中村さんのように、職員の言葉が介護における転機に繋がることがあります。
――― 山本さんのお父さんは、昨年、施設に入所されたと伺っております。
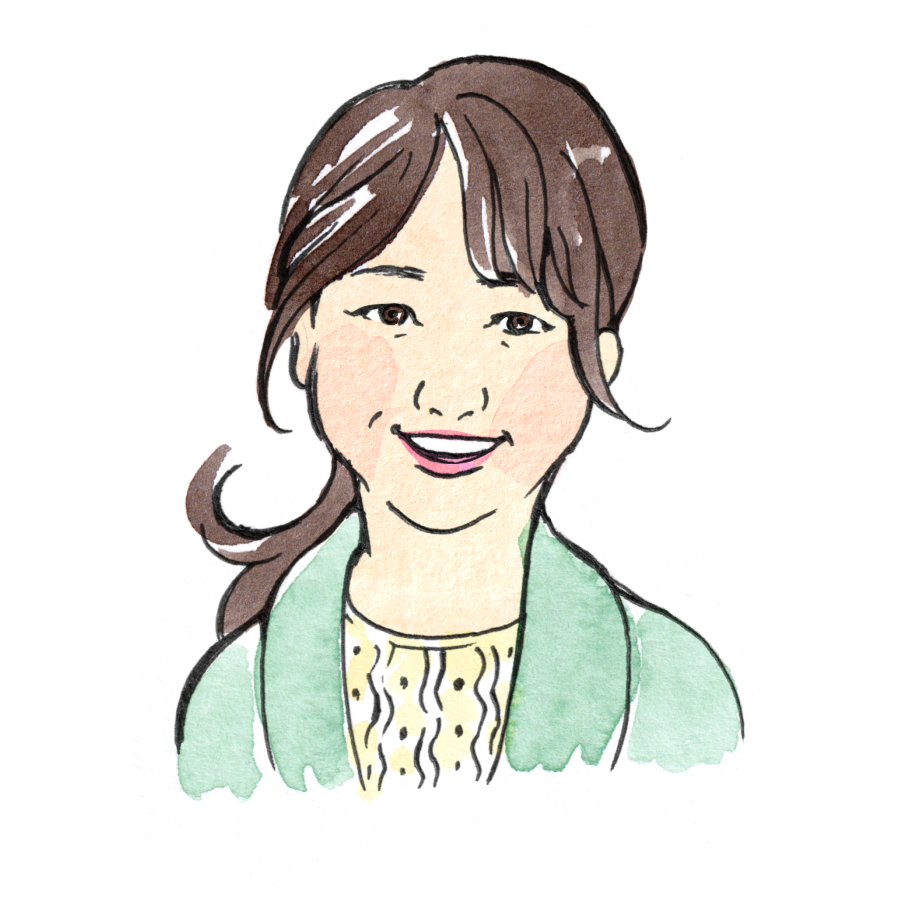
山本
母のときの経験もあって、「在宅介護が大変になったら施設にお願いしよう」と父が要介護状態になったときから考えていました。
ママ友が「私が介護しなくちゃ」とか、「今は元気だけど、旦那さんの親が倒れたら私が介護するのかな」と言ったりしているのを聞くと、「家族が介護をするもの」という価値観が根強いと感じます。でも私は「介護サービスをどんどん使って周りに助けを求めていかないと! 家族だけで抱え込むのは絶対良くない」と思っています。
割り切ったつもりでいた山本さんも、施設に入所された直後のお父さまから「こんなところに入るなんて、人生の終わりだ」と言われて心を痛めました。
しばらくすると、施設の職員さんたちの人柄なども分かってきて、会話を楽しんだり、環境にも慣れてきたりしたようで、いまはそこまで悲観的になっていないそうです。
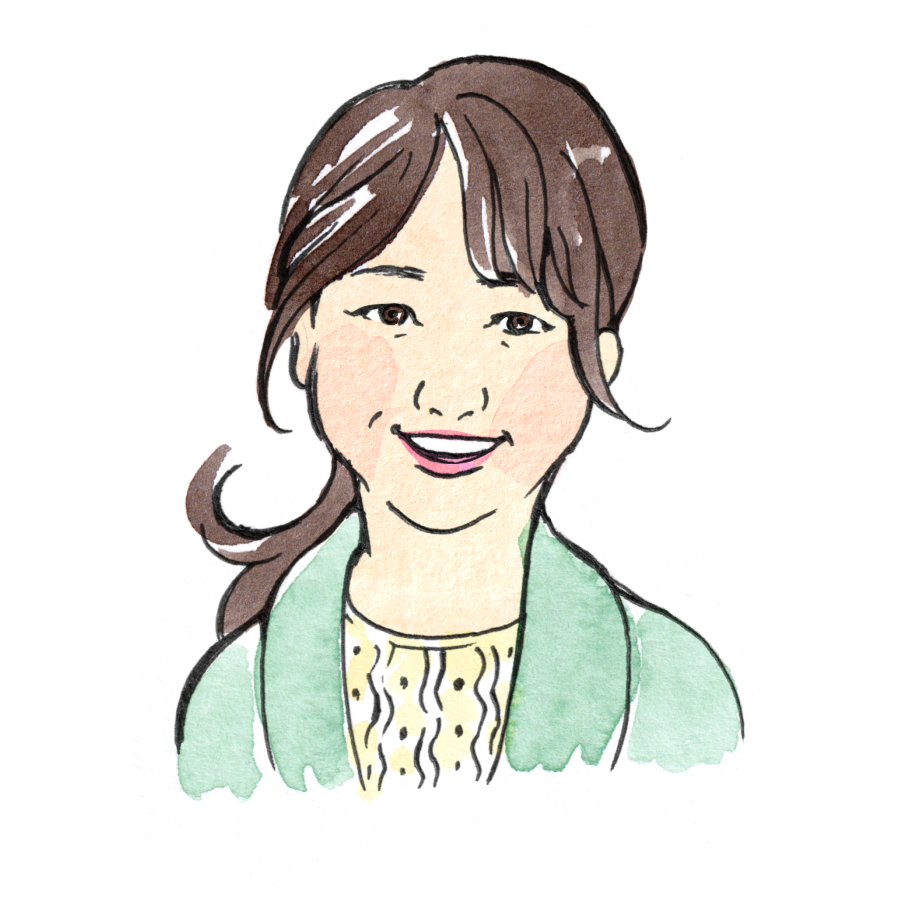
山本
ただ、父が入所した施設に対して要望というか、もう少しだけ配慮して欲しいことがあって……。父は認知症ではなく、パーキンソン症候群の薬の影響で幻覚がすごいんです。それに対して父が何かを言ったら「あら、今日も幻覚が見えて煩わしいですね」などと共感する言葉がけをしてもらえれば、父も安心すると思います。でも施設の職員さんは「はい、はい」とか「また言っている」と流してしまうようです。
父はそれが「分かってもらえなくて悲しい」言っています。施設のスタッフを介護の「プロ」としてリスペクトしています。でも「心のケアのプロではないんだな」と思うことがありました。みなさん多忙そうで、そのあたりの要望をしづらい現状もありますし。
学校に心理カウンセラーがいるように、施設にも心のケアの専門員がいてもいいくらいだと思います。そのあたりをもう少し介護業界全体として配慮してもらえるようになったらいいですよね。
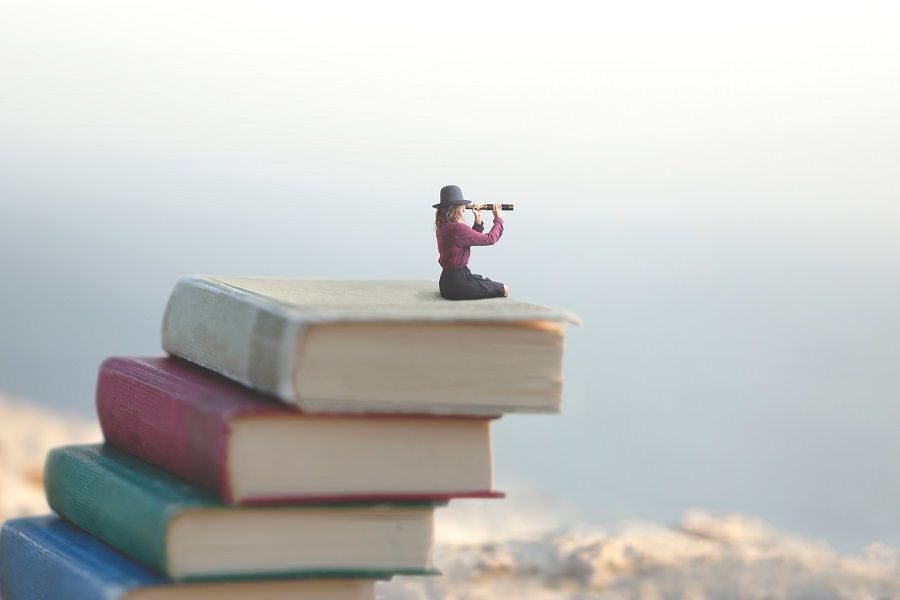
こんな介護サービスがあればいいのに……
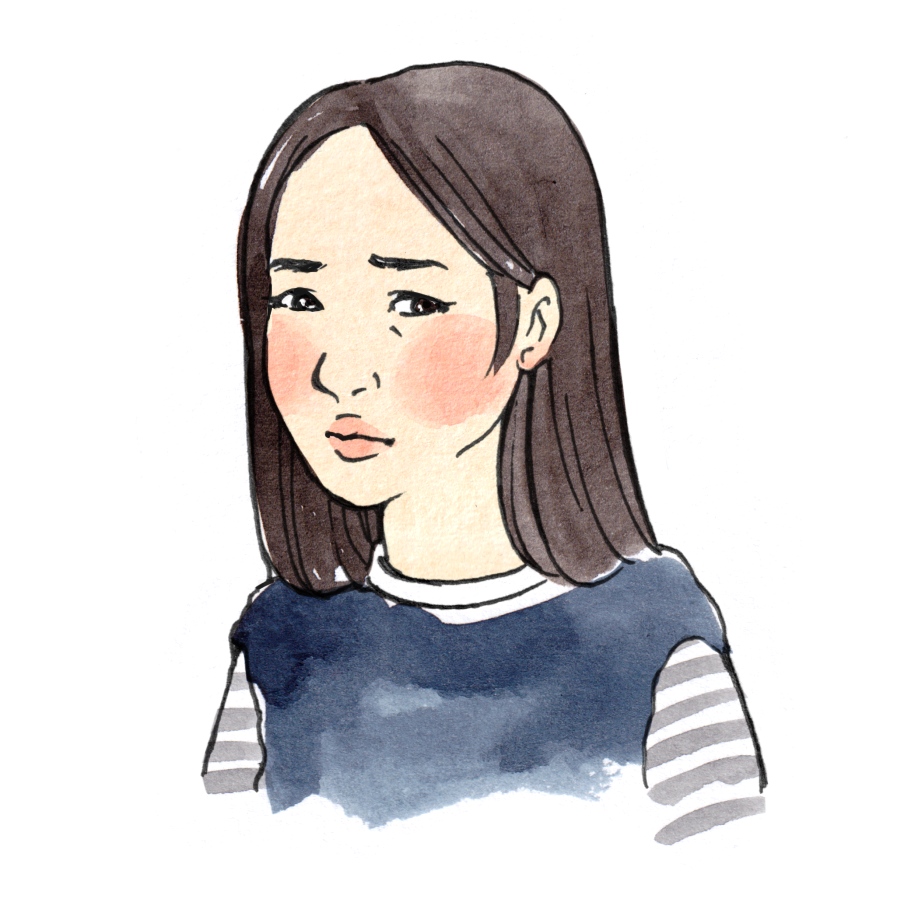
中村
そのあたりの配慮は、介護の仕事の一環として対応してもらえたらありがたいですよね。
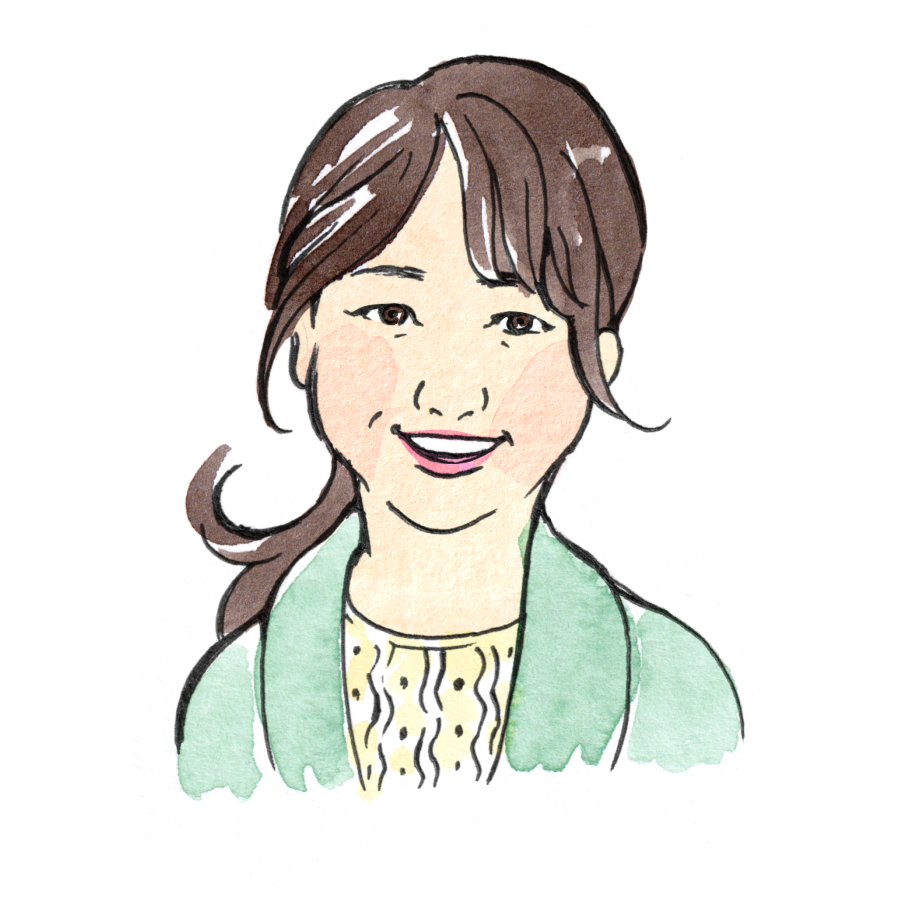
山本
父への対応という点では、在宅介護のときから、できれば身体的なお世話だけでなく、『話し相手』になってくれる方がいて欲しかったです。父は幻覚による不安を常に抱いていました。事情を知っていただいたうえで、精神的な面で頼れる専門の方がいたら、父はもっと穏やかにいることができたのではないかと思います。
――― 井上さんは介護サービスに望んでいたことはありましたか。
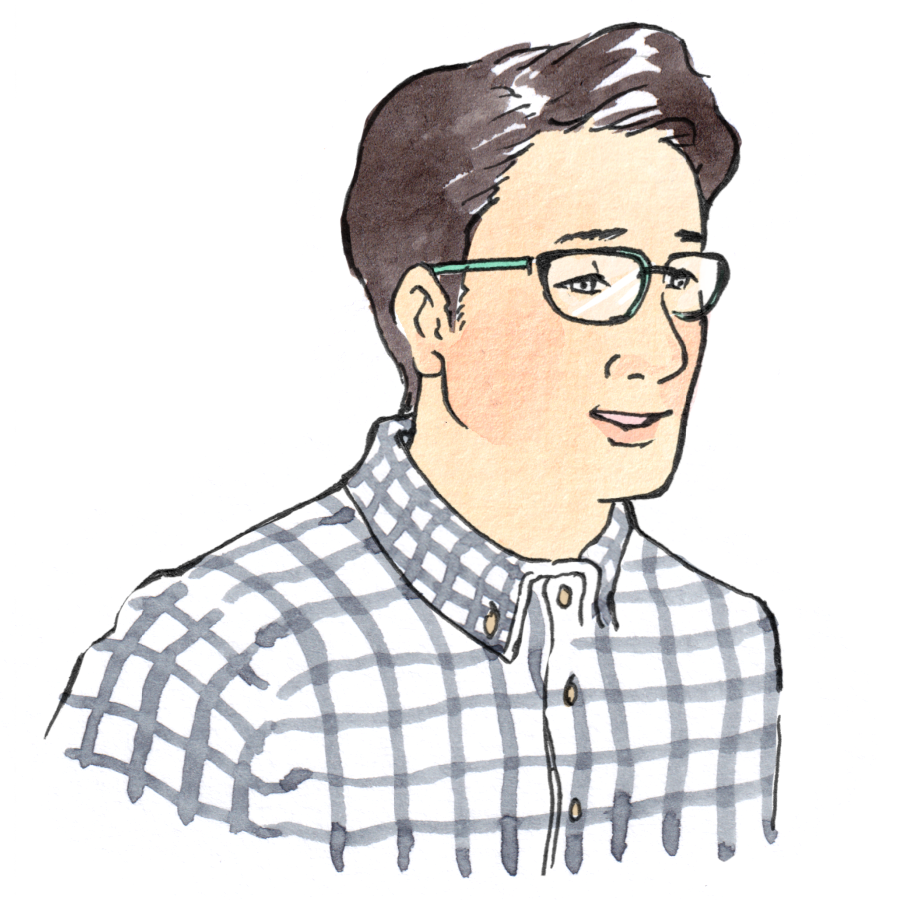
井上
そうですね。祖父はショートステイを利用することがあったのですが、そちらは
3ヵ月前から予約しないといけなくて。「
レスパイトすることが大切」だとよく言われていますが、そんな先の予定がわからないのでどのようにお願いすればいいか難しかったですね。そのあたりがもっと柔軟性を持って対応してもらえたら、ありがたかったです。
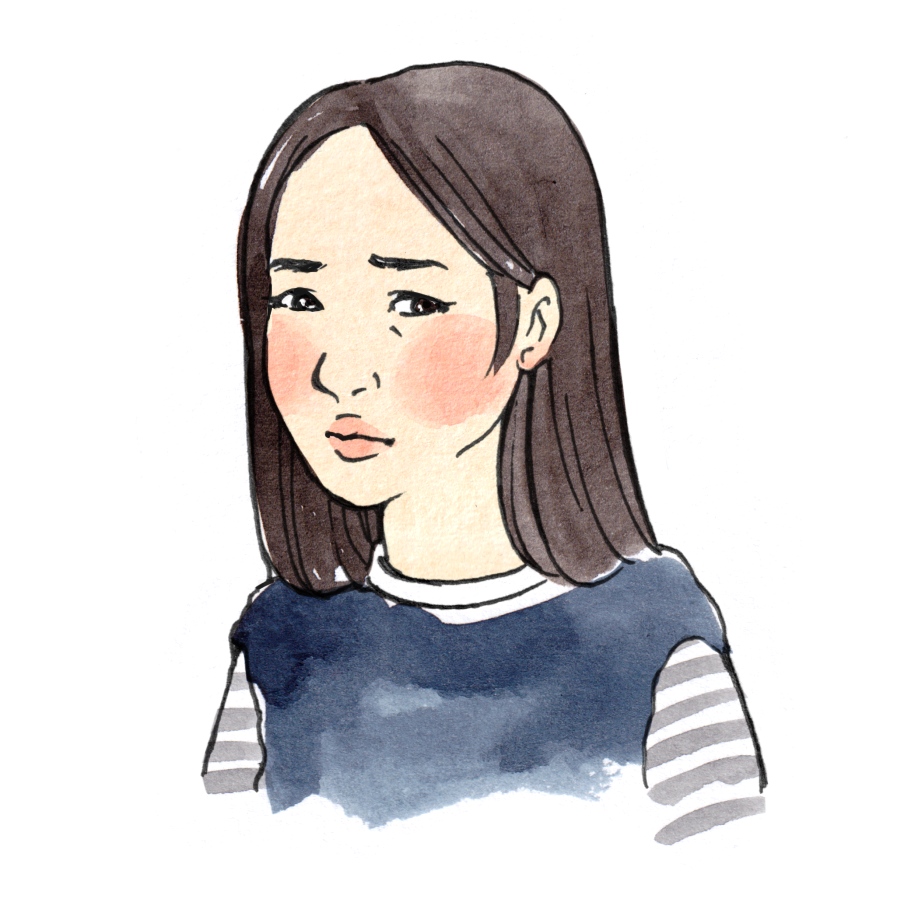
中村
要介護の方への介護サービスはもちろんですが、介護する人へのケアが欲しいとずっと思っていました。
介護経験者同士が支え合う会のようなものはたくさんありますが、公的なサービスとしては存在していないようです。そのあたりを考えると、介護保険があるとはいえ、結局は家族の善意に寄りかかっている制度だと感じてしまうことが多々ありました。
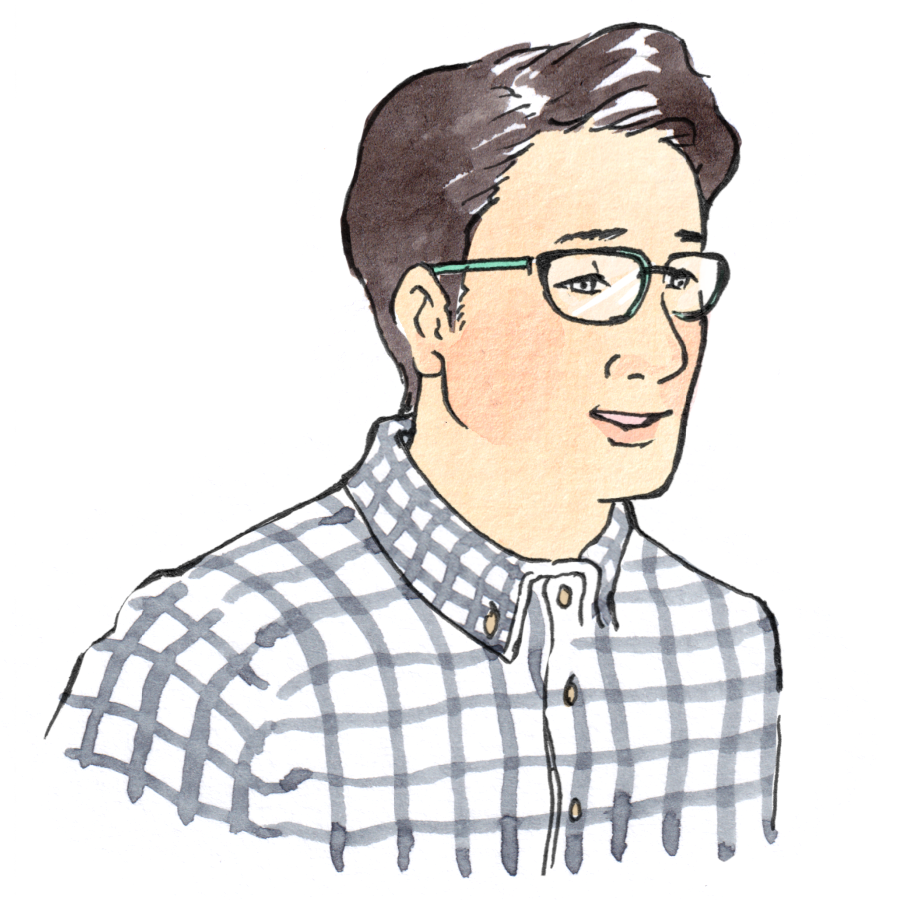
井上
確かに、介護保険で使えるサービスにはそういったものがほぼない。
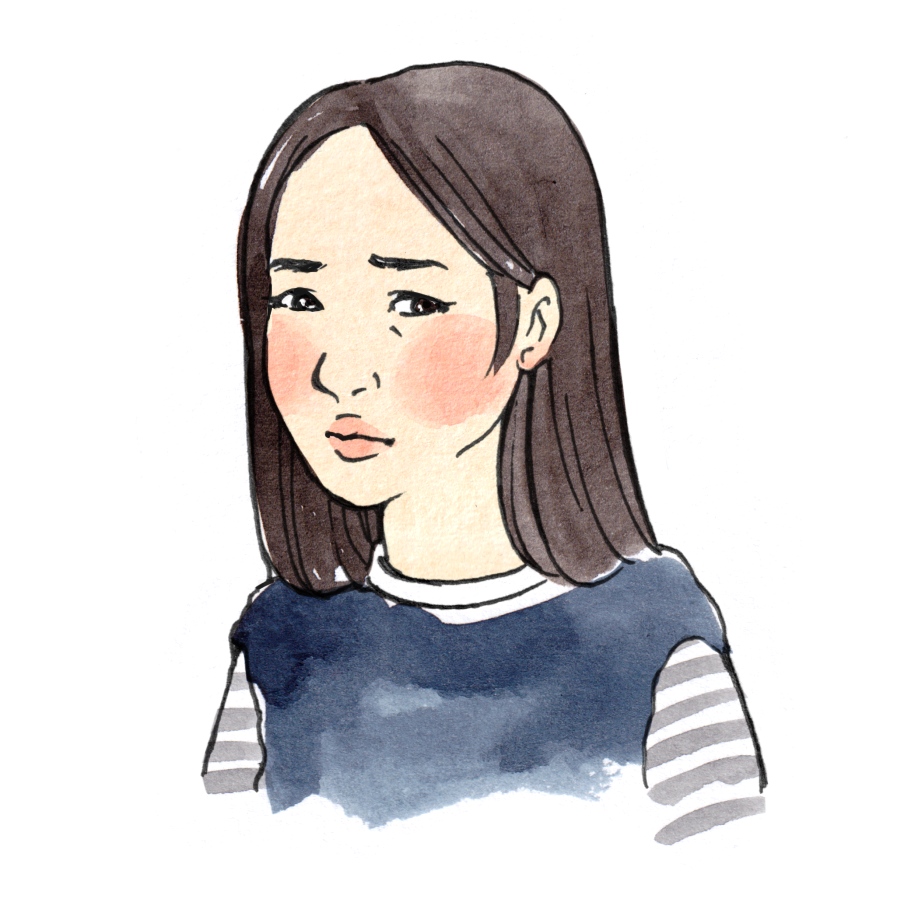
中村
介護する人だってロボットではないわけだから、気分的なものであったり、身体的な休息が欲しいときもあります。だけど、それを公的に支える制度は私が祖母の介護を終えてしばらく経っても、おざなりになったままというか、そういう視点が抜けたままですよね。
「介護経験」は履歴書に書けない!?
――― 在宅介護で大変だったことを教えてください。
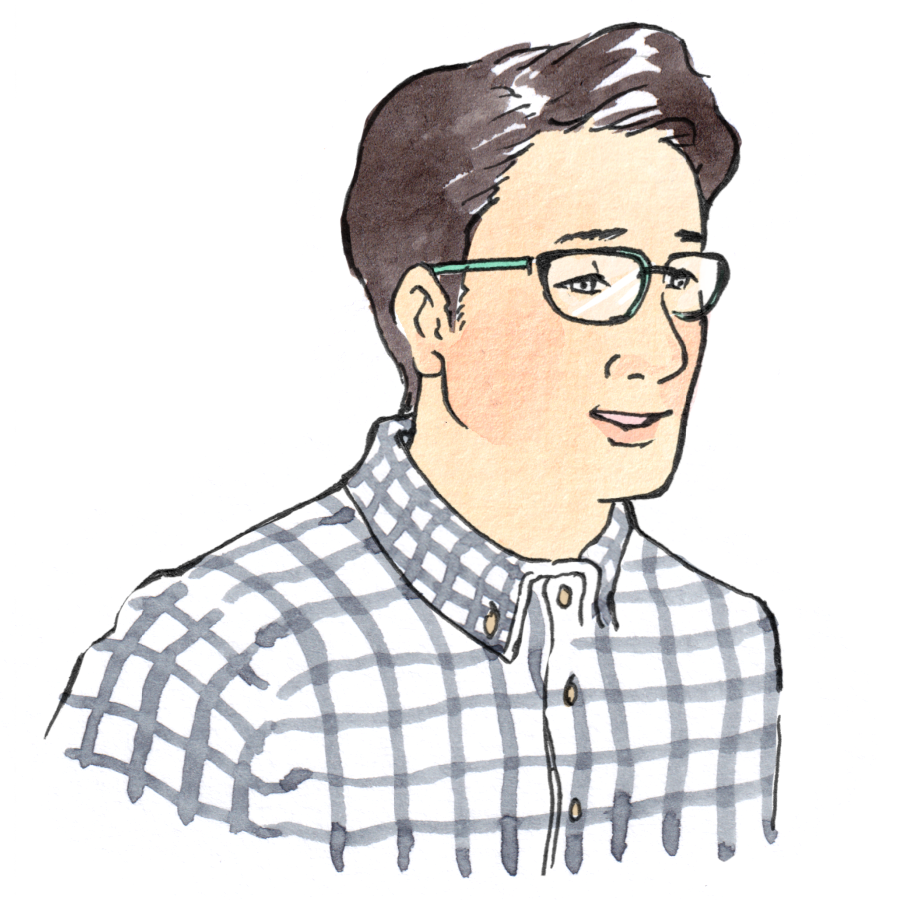
井上
学生の時分から家族の介護をしていると、社会に出るのが「遅れてしまう」ことがあります。自分もそうでしたが、その理由に「介護経験」は履歴者に書けないと思っていたからです。でも、若者雇用対策のカウンセラーの方に「介護経験」も履歴書に書いてもいいと言われました。
そのあたりの評価や理解があれば救われる人がいると思います。
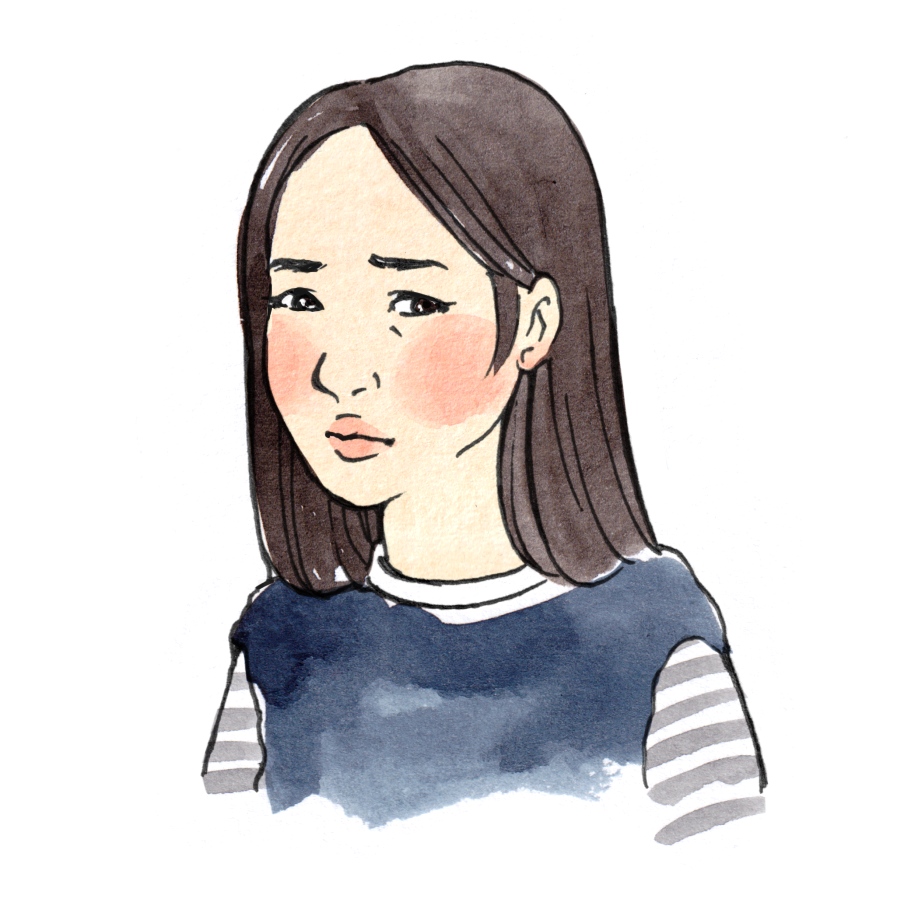
中村
「介護経験」って、履歴書に書いてもいいんですね!? どんなに介護を頑張っても、周りからは「頑張っているね」と言われるくらいで、善意を搾取されているような気持ちがありました。
だからといって、すべてを放り投げて、自分の人生を突き進むほどの勇気もなく、今後の人生の計画が立てられないというのは一番の不安だったのを覚えています。
――― 将来に大きな不安を抱いてしまうことも、「若者ケアラー」の悩みの一つですね。
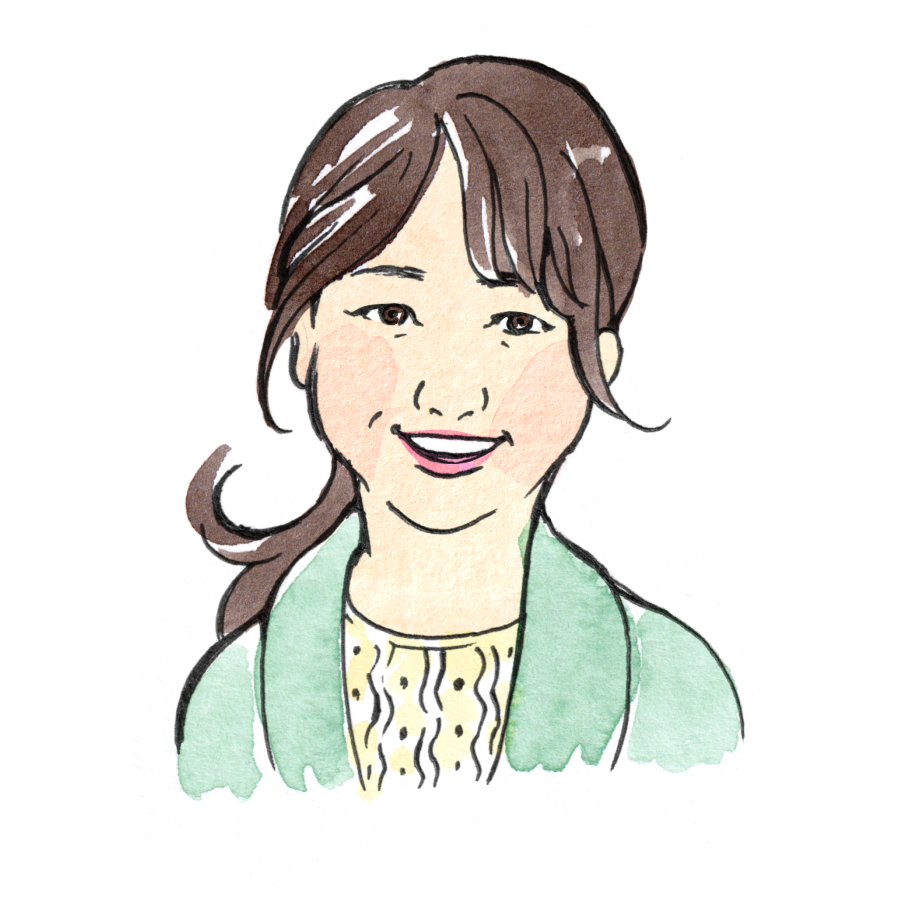
山本
他にも「もどかしいな……」と感じたことがいくつかあるんです。
――― ぜひお聞かせください。
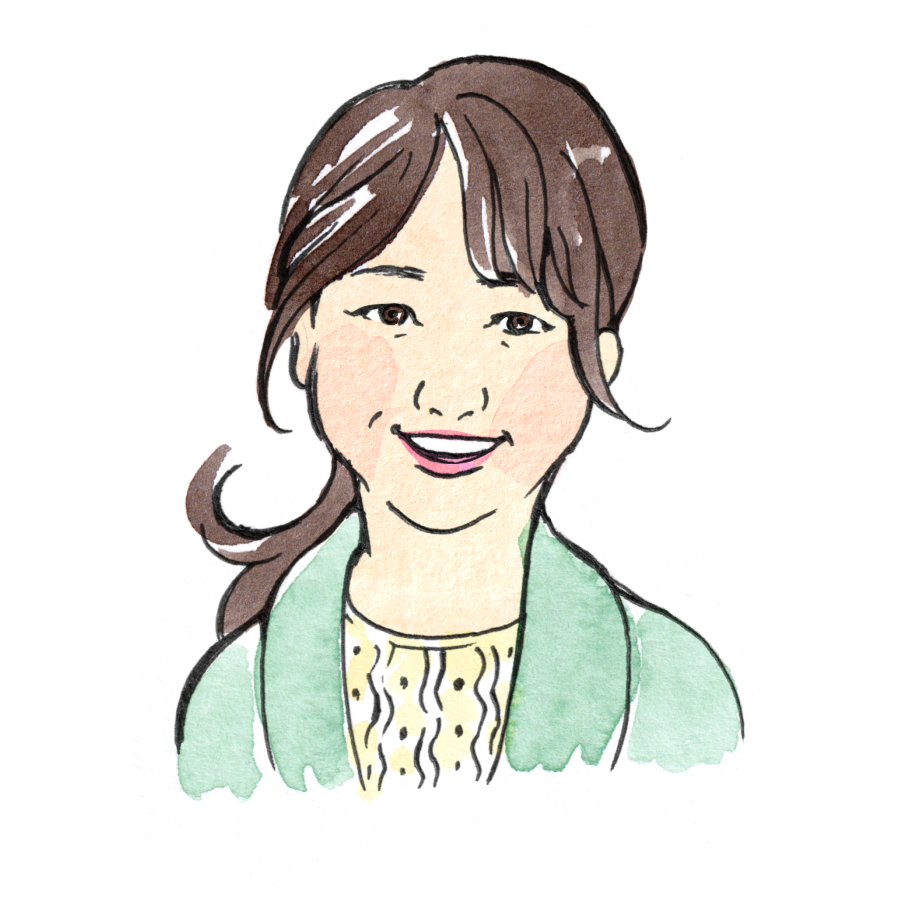
山本
父の在宅介護をしていたときは、訪問ヘルパー、訪問リハビリ、入浴介助などさまざまなサービスを利用していたのですが、コロナ禍なのにそれに関わる人たちが全員実家に来て、会議をするんです。
オンラインで済むような内容でも、その場で紙の書類に何度もサインが必要だったり、IT方面の対応が進んでいないようでした。各所から別々に電話がかかってきたりして調整するのが兄には本当に大変そうでした。
――― それは大変でしたね……。
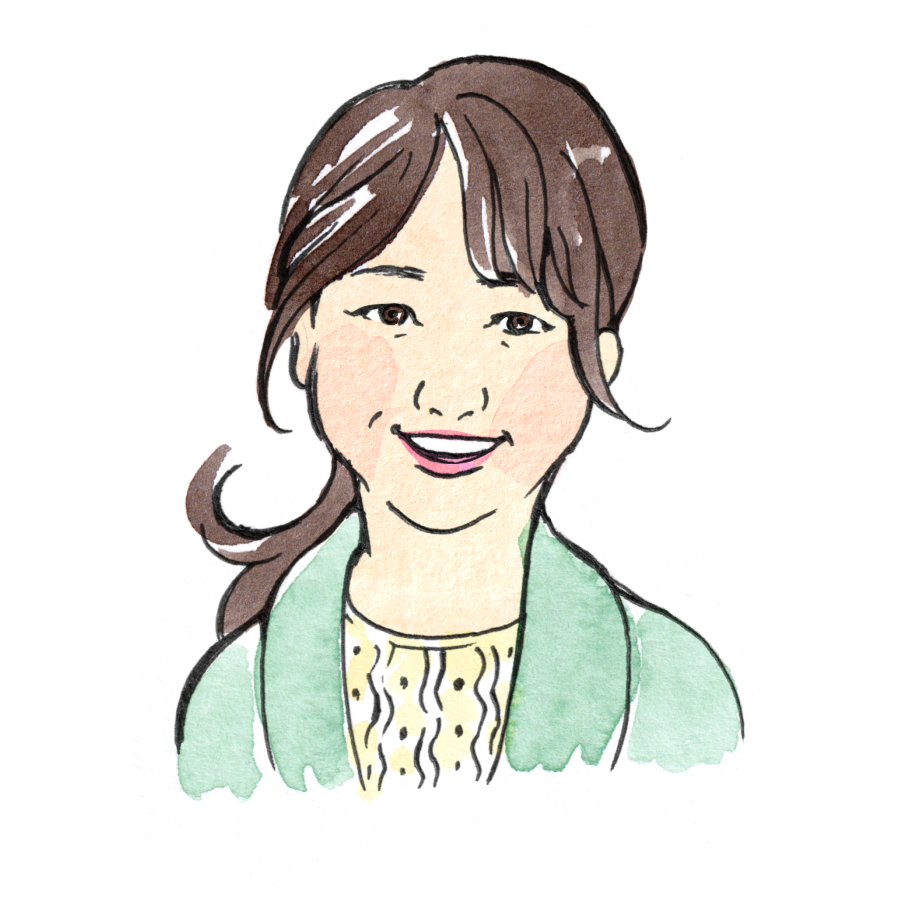
山本
もう一つありまして。施設に入所する前は、訪問ヘルパーさんに掃除と食事作りをお願いしていました。介護サービスは父のためのものなので「決まった範囲」のサービスしかお願いできず、実家で飼っている猫のトイレ掃除をしてもらうのはNGでした。
せっかく頻繁な通い介護をしなくて済むように環境を整えたのに、猫のトイレを掃除するためだけに実家に行かなければならず、もどかしかったです。
猫も大切な家族ですが、疲れてしまって「今日は休みたいな……」と思うときなどに、オプション料金がかかっても猫のちょっとしたお世話も頼めたら安心感が大きかったと思います。あとは、介護のためにかかる交通費の補助があれば気持ちもまた違ったと思います。
飼い主が要介護状態になったら、ペットのお世話は難しくなります。対策を考えておくことは、ペットにとっても重要なことです。
山本さんは、10代での介護経験を経て、今はお父さんの介護に“突入”しています。お母さんの経験があったからこそ、お父さんに対しては介護サービスを積極的に利用する方針になれたそうです。
もし、また家族の介護をすることになったら
――― 井上さん、中村さんは「来たるべき」介護についてはどのように考えているのでしょうか。
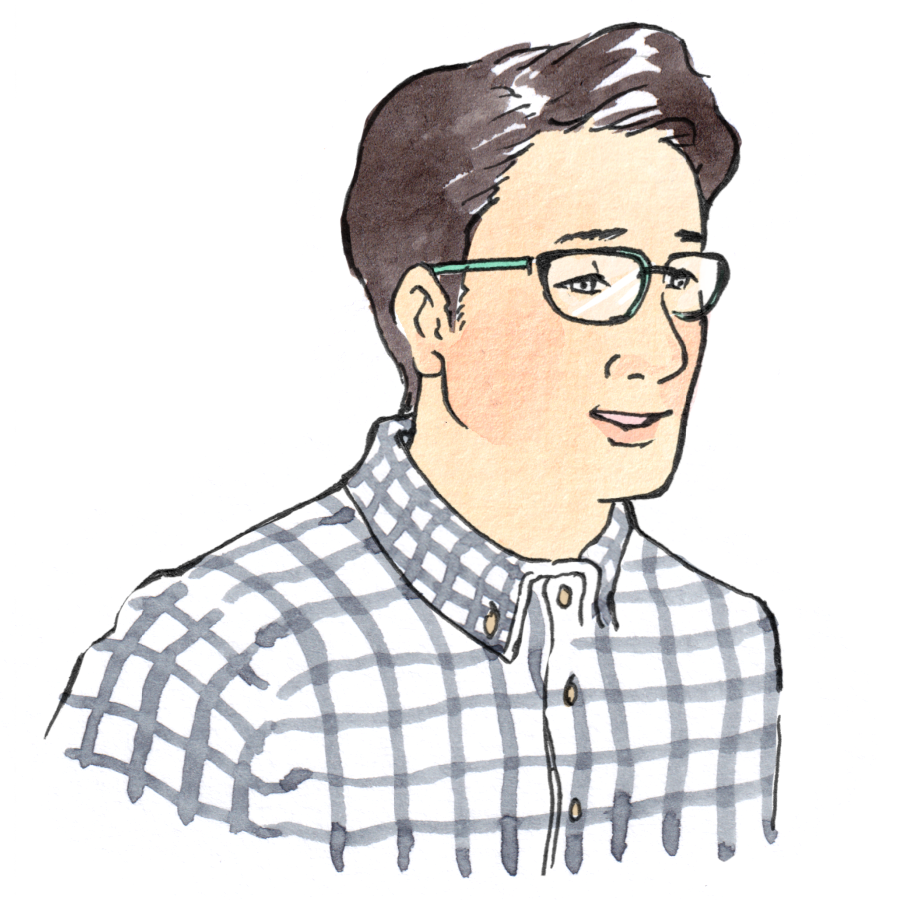
井上
“2周目”は妻の両親や私の母の介護になると思うのですが、母のことに関してはすでに妹たちとも話をしています。 祖父の介護をして思ったことなのですが、介護経験がなかったり、意外にも専門職の方から「家族ができるならば、家族が介護すればいいじゃん」といったことを「軽い」調子で言われたことがあります。
そういう言葉は別に聞かなくていいと思います。一度経験としているからこその図太さをもち、割り切ることが重要だと考えています。「自分はこれ以上は無理」という線引きをして、自分の生活は守っていきたいと思っています。
井上さんは、ご自身にも介護が必要になる可能性がゼロではないため、そのための備えを今からしているそうです。
――― 中村さんはいかがですか。
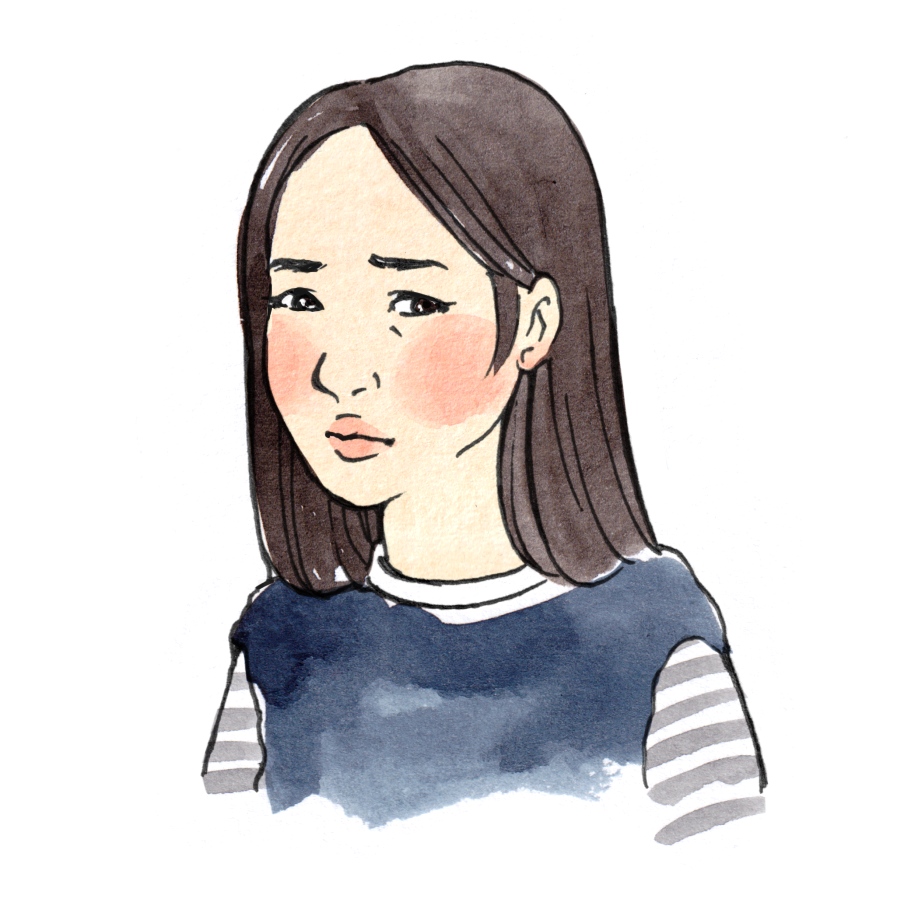
中村
実は……すでに母がいろいろなところの調子が悪く、介護に「片足を突っ込んでいる」状態で。まだ早いと言う人もいるかもしれませんが、今年中には介護保険の申請をしようと考えています。
というのは、私の持病が悪化して、現在、透析をしているため、母に対して祖母のときのような“無理”ができません。まだリストアップなどはしていませんが、祖母のときの反省を踏まえて、ギリギリまで我慢をするのではなく、施設入所も見据えてお互いにベストな道を探っているところです。
祖母の介護から、「自ら発信しないと誰も助けてくれないことを悟った」という中村さん。以前は人の顔色ばかり窺う性格でしたが、“2週目”の介護がやってきたら、少し図々しくなって周りを巻き込むつもりだとか。祖母の介護は「性格が一変するほどにすごい経験だった」と言います。
――― 山本さんはすでに“2周目”ですが。
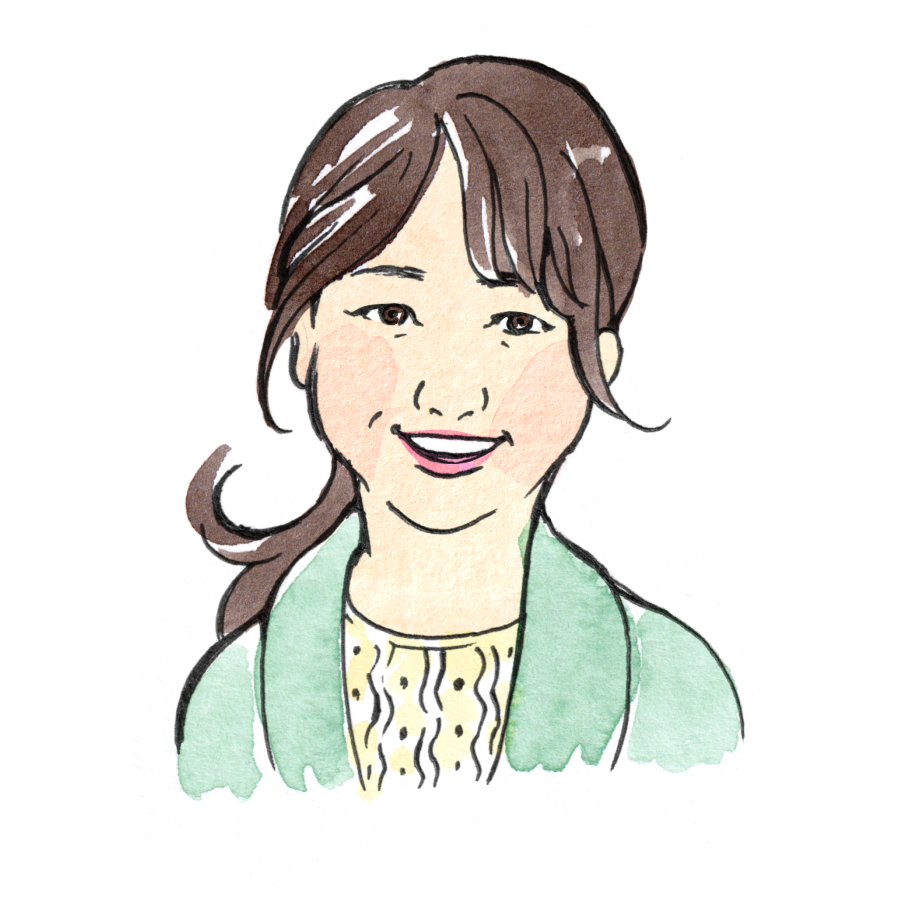
山本
はい。介護って相手によって全然違うから、母と父の介護はまったく別のものです。在宅介護の父の方が大変だと思いました。
やはり、介護のプロなどの外部の人や施設を上手に「利用」して、絶対に一人で抱え込んではダメというのは最初から思っていましたね。
山本さんはご両親の介護を経験したことで、育児で大変なことがあっても、「子どもは成長していく未来がある」と思い、あまり落ち込んだりしなくなったそうです。
――― 井上さんも今はお父さんになられて育児をされているそうですね。
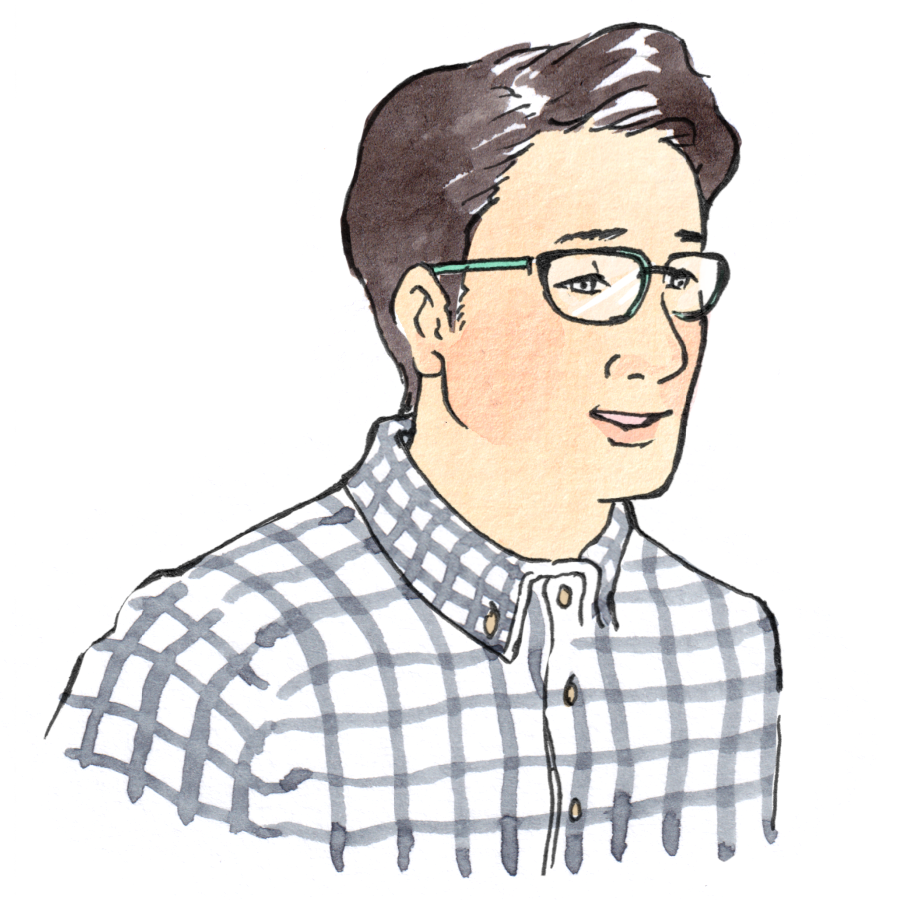
井上
確かに、育児より介護の方がしんどかったというのはありますね。
世間的にも介護を理由に「早退します」というよりも、育児の方が「それはしょうがないね」となります。同世代の経験者が圧倒的に多いし、想像しやすいのもあると思います。
妻は育児でいっぱいいっぱいになることがありますが、介護のときから一歩引いて見るようなところがあって、妻のグチを客観的に聞き流せるスキルのようなものも介護のおかげで身につきました(笑)。

「当事者」から「当事者」へのメッセージ
――― ヤングケアラーや若者ケアラーも含めて、介護をされている人にメッセージをお願いします。
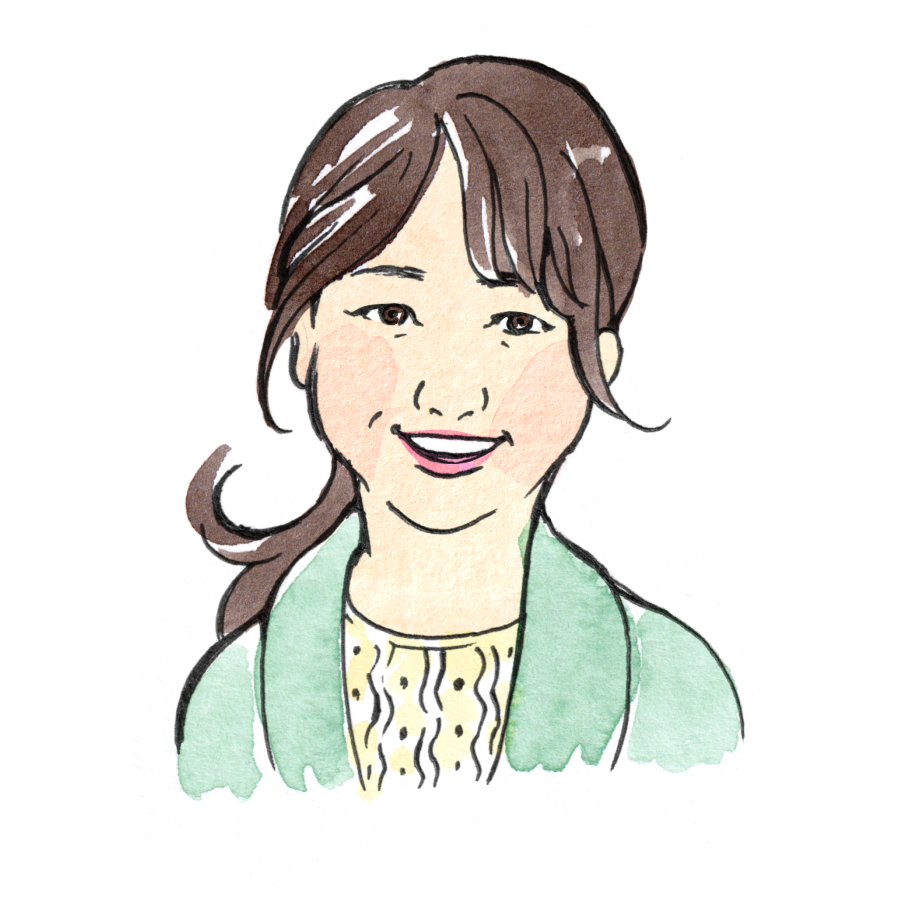
山本
今、ヤングケアラーがメディアで一種の「ブーム」になっているようなところがありますが、母が倒れたころにもそういう動きがあったら救われていただろうなと思います。とにかく、人と繋がることで道が開けていくことがあるので、SNSなどを活用して仲間を探していって欲しいですね。
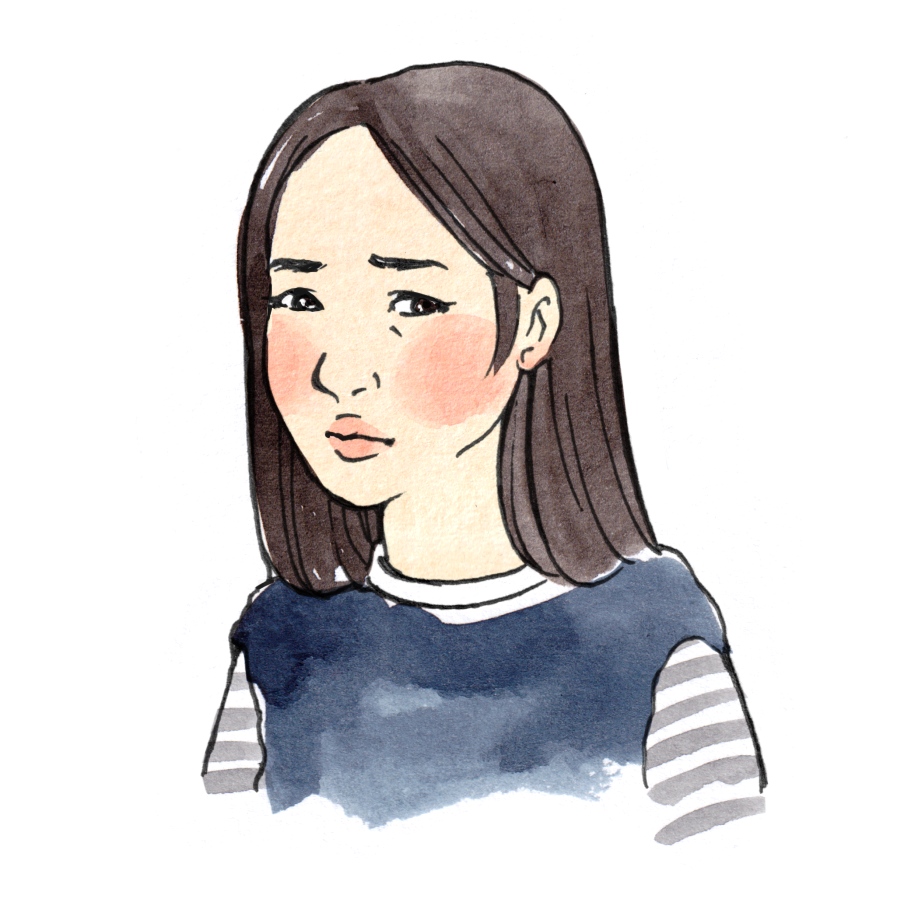
中村
ヤングケアラーをはじめ、自身が置かれている状況が「お手伝いなのか、介護なのか」を認識できていない当事者がいます。そういった方が、「自分は介護している」と認識してもらうにはどうしたらいいのかを考えたときに、自身の生活に何かしらの違和感があれば、それをおかしいと認識して、心の扉を閉めずに助けを求めて欲しいです。
そうでないと、自分の未来も家族の未来もなくなってしまいます。誰に助けを求めたらいいかわからなかったり、話したくない方には、私も含めて経験者などができることを考えていきたいです。
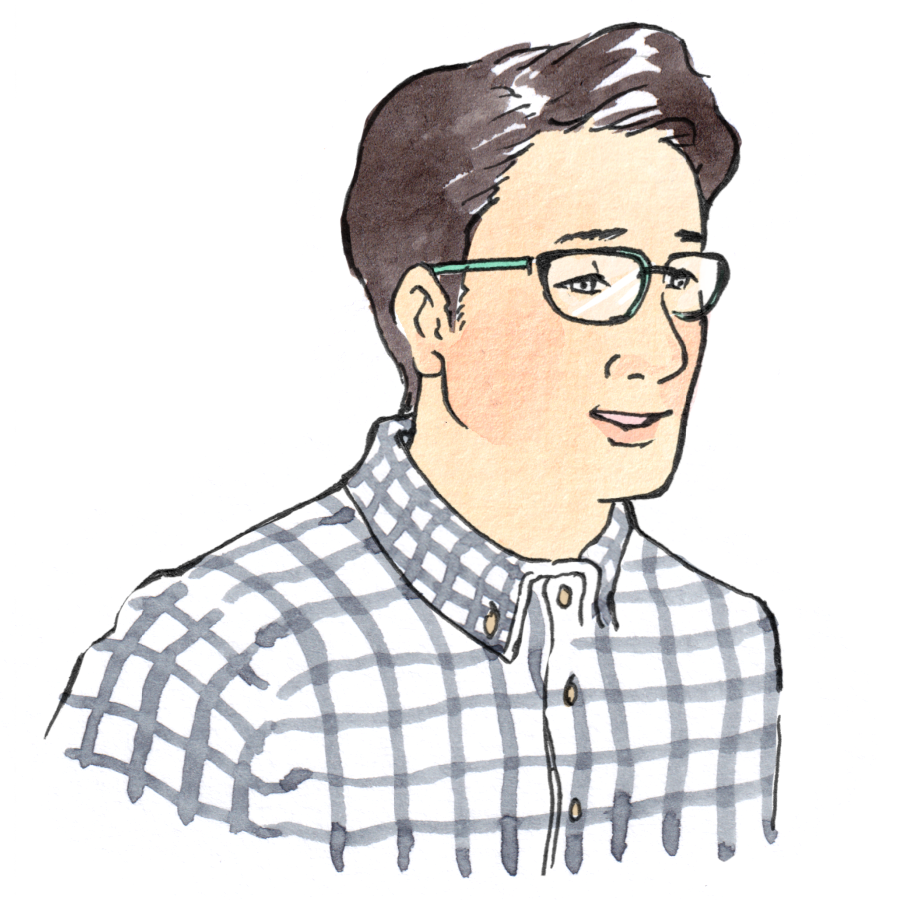
井上
介護生活において、「自身がどうしていきたいか」という答えは自分の中にしかないのではないでしょうか。
他者や居場所に過剰な期待を持ってはいけませんが、自分の中の答えを見つけるために、人との出会いや心が穏やかになる居場所を探すことは大事だと思います。そのためのチャンレジは諦めずに続けてください。
ヤングケアラーや若者ケアラーは、経済的にも、年齢的にも、家族の中では弱い立場になってしまいます。それゆえ「お手伝い」という言葉で片付けられて、自身が介護をしているという認識を持ちづらい現実があります。だからこそ、周りが彼らの存在を見つけ出して、彼ら自身の人生に希望を持って歩んできるようなサポートをするべきなのかもしれません
取材・文:岡崎 杏里
「みんなの介護座談会」へご参加頂ける方を募集しています
「みんなの介護座談会」は読者の皆さまに参加して頂く新企画です。皆さまの日々の介護に対する思いをぜひ座談会で語ってください。
以下のフォームより、ご応募をお待ちしております。
参加フォームはこちらをクリックしてください
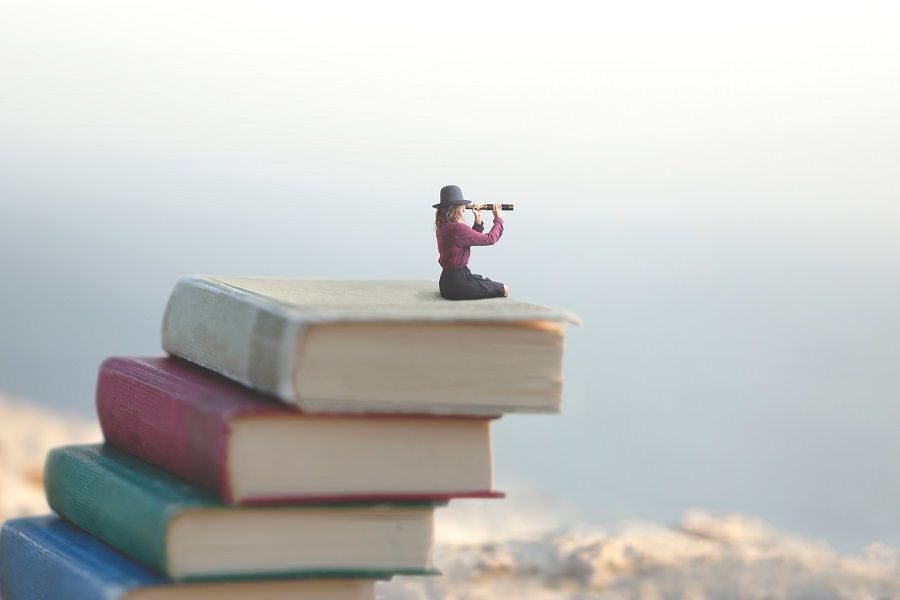




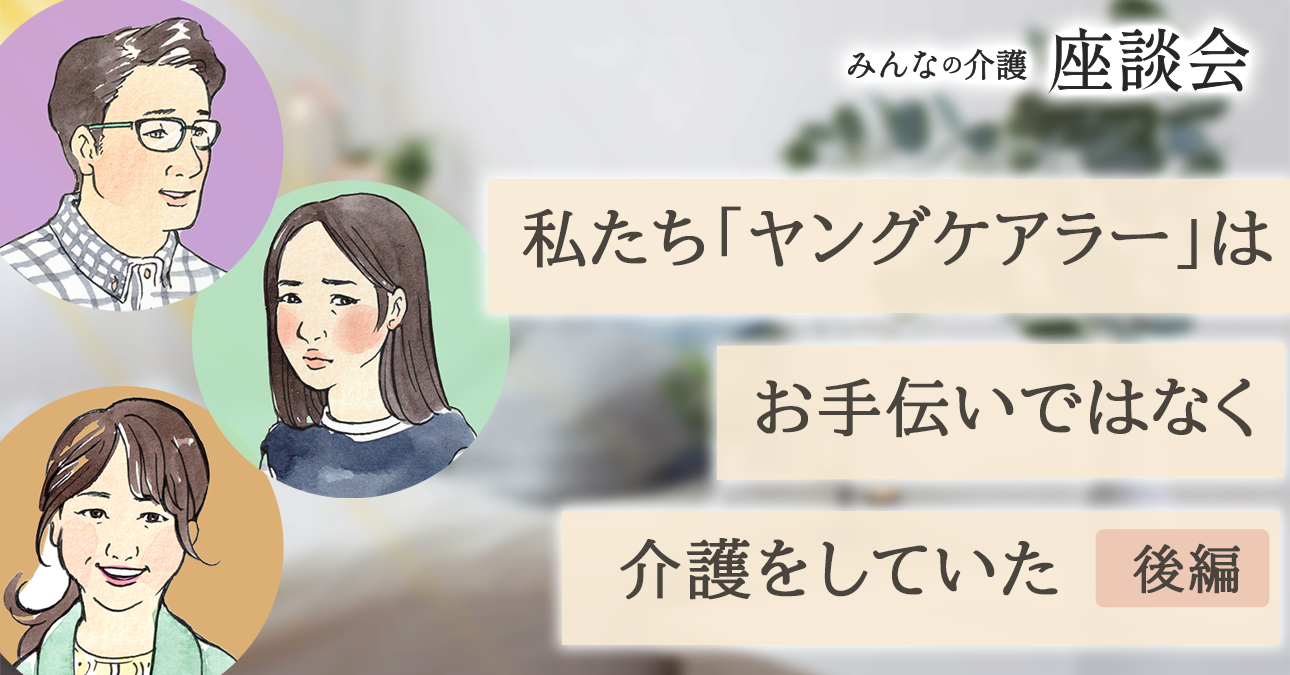

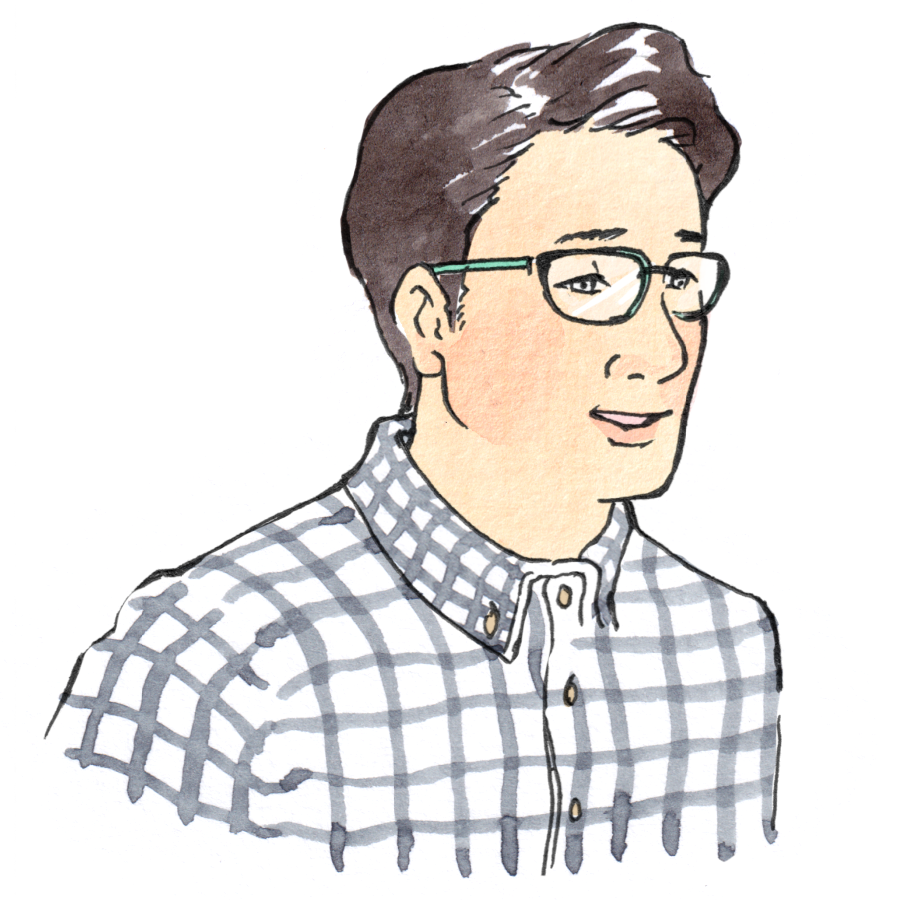
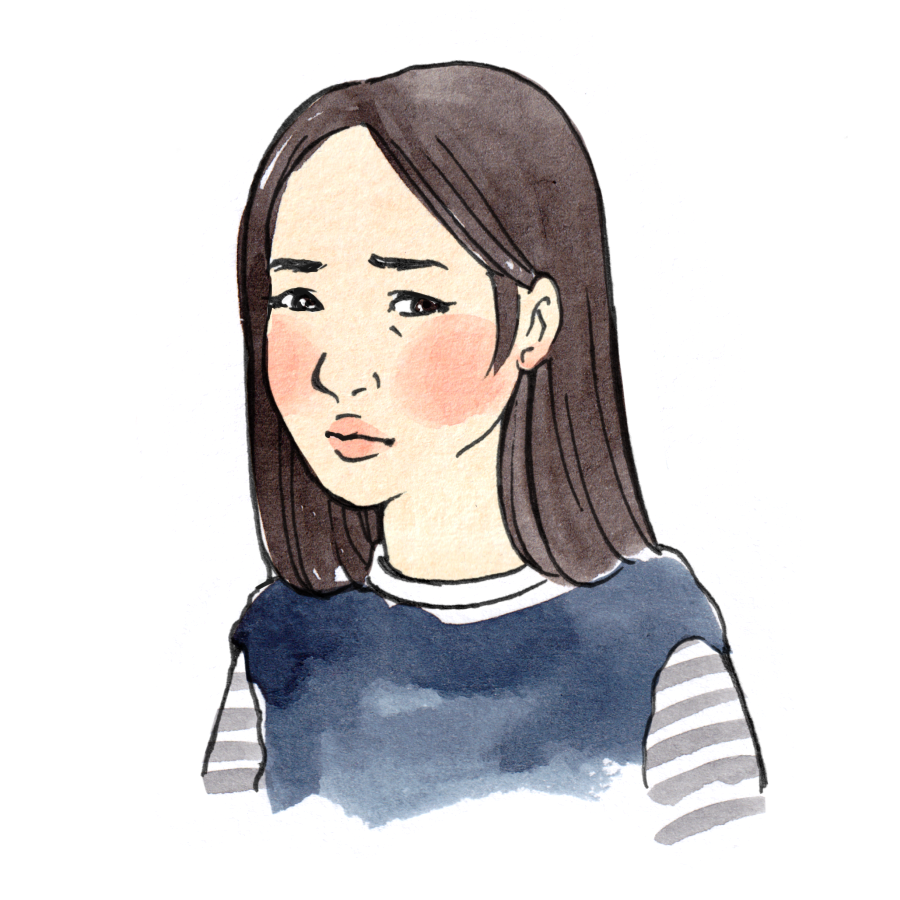
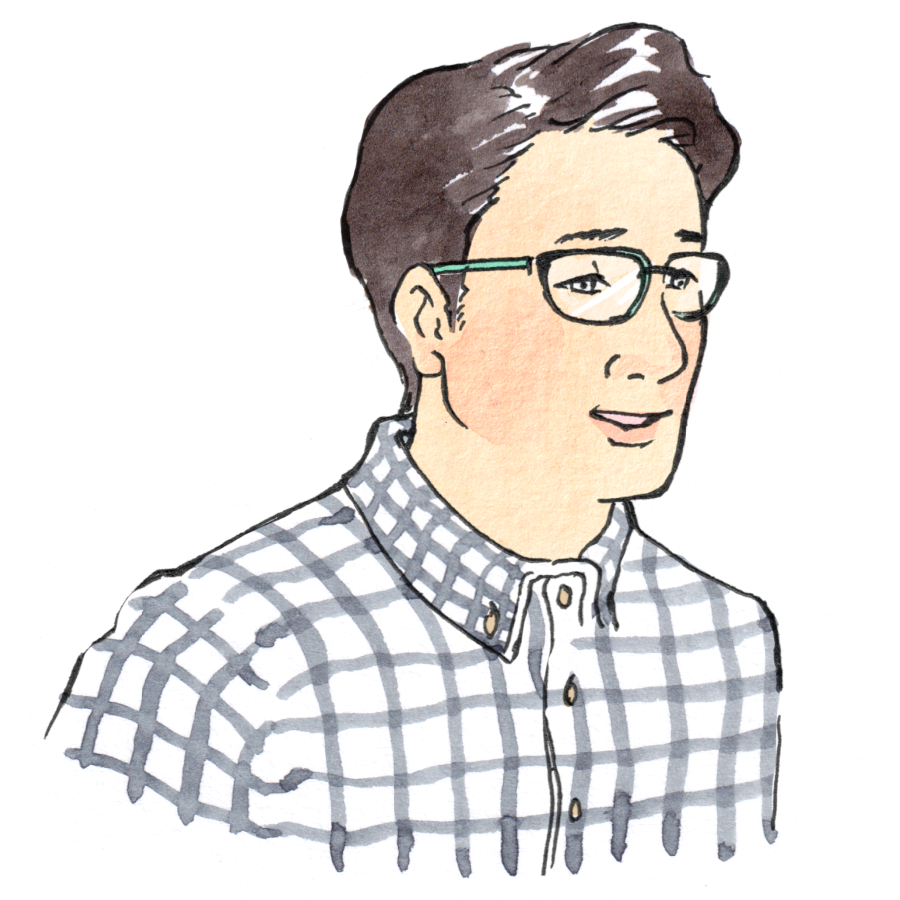 井上
井上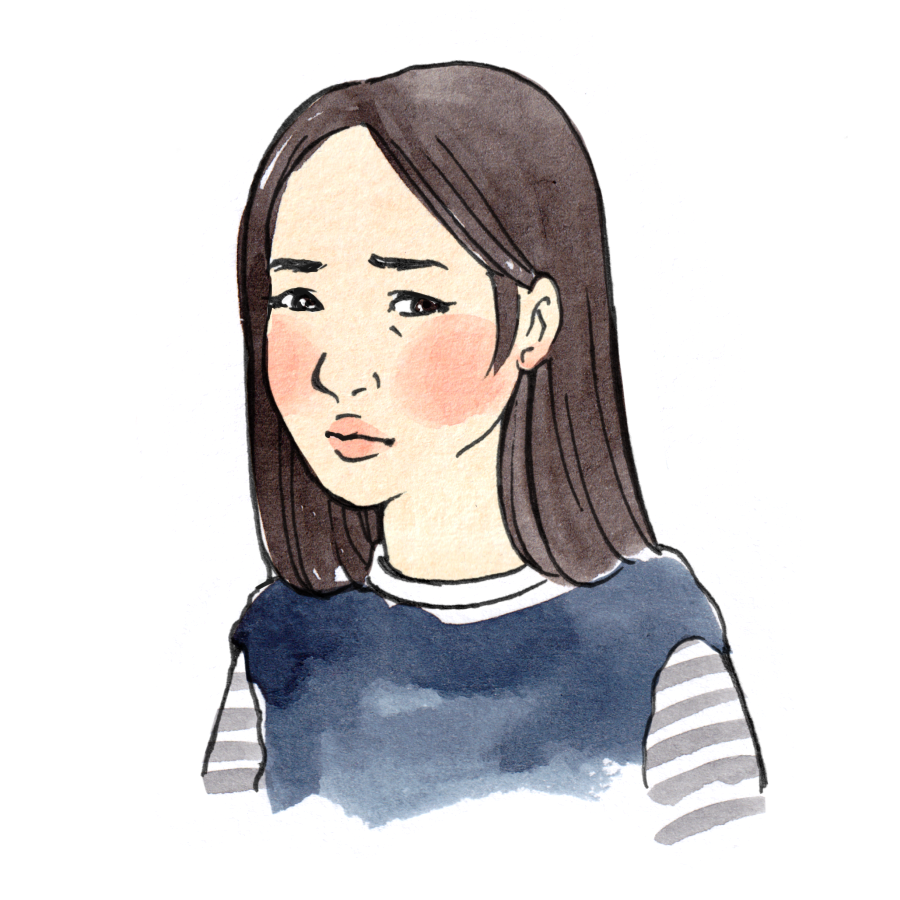 中村
中村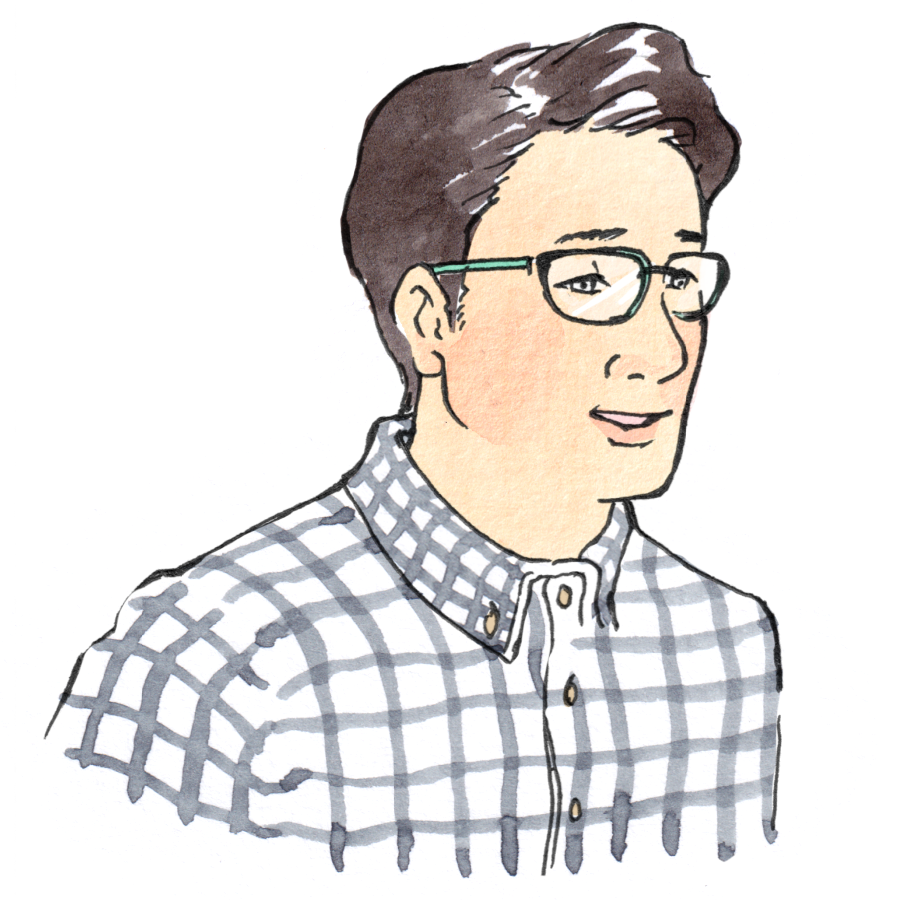 井上
井上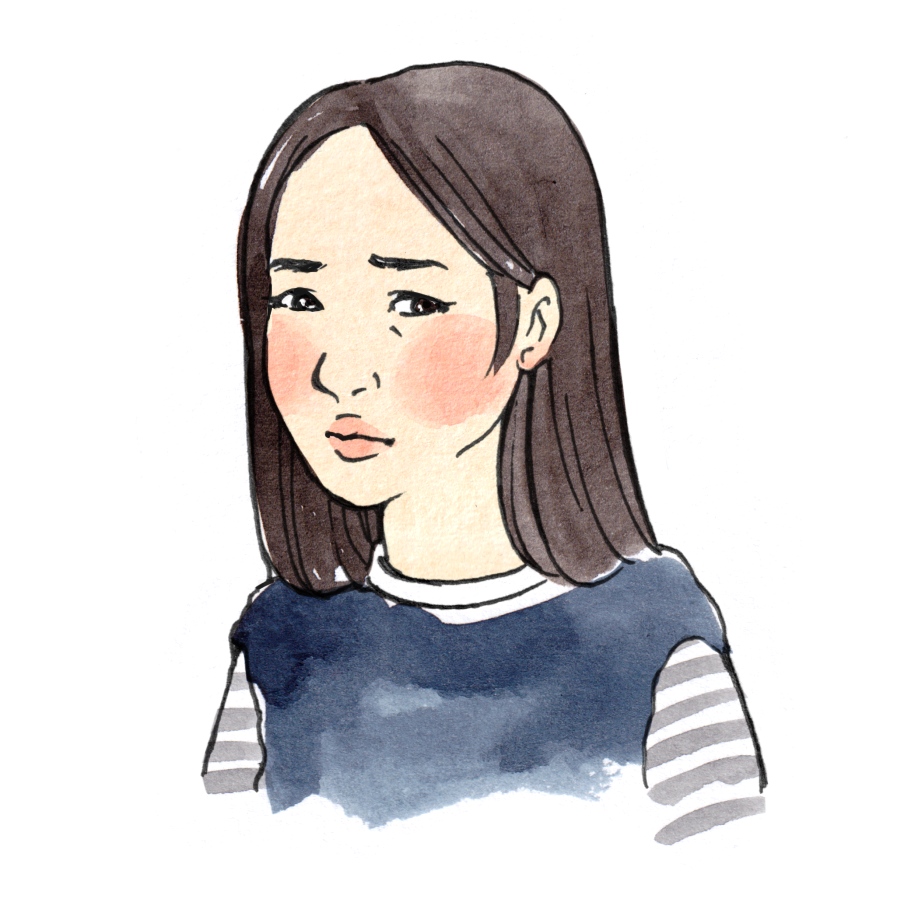 中村
中村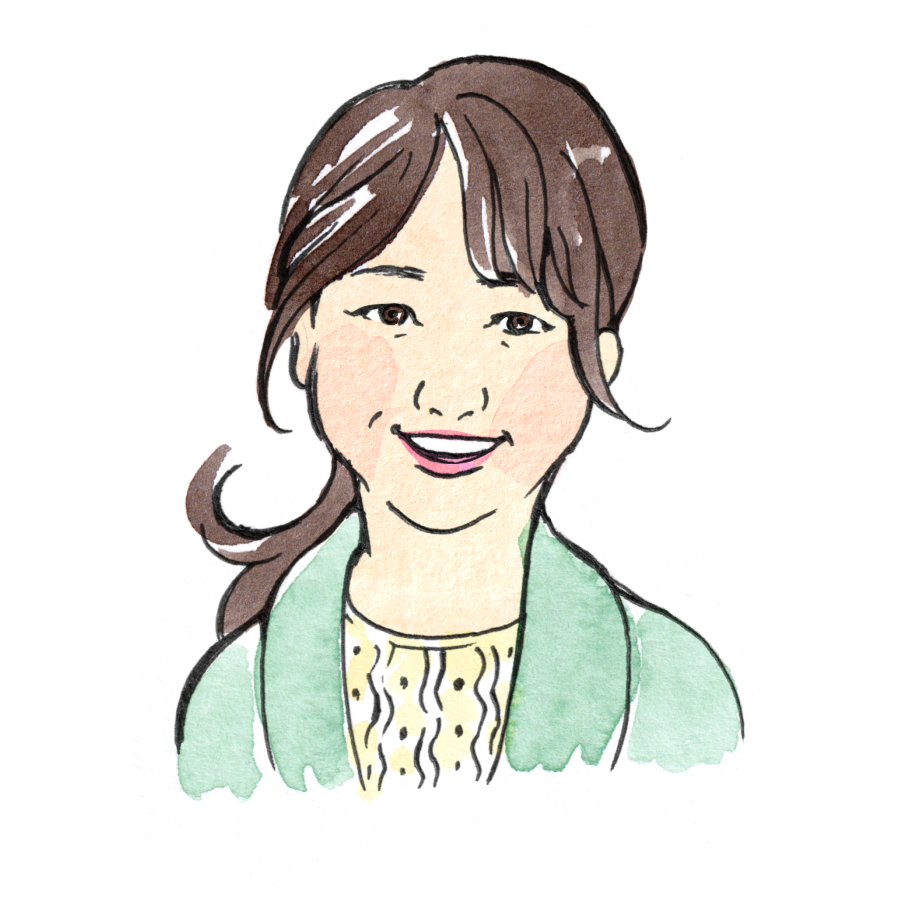 山本
山本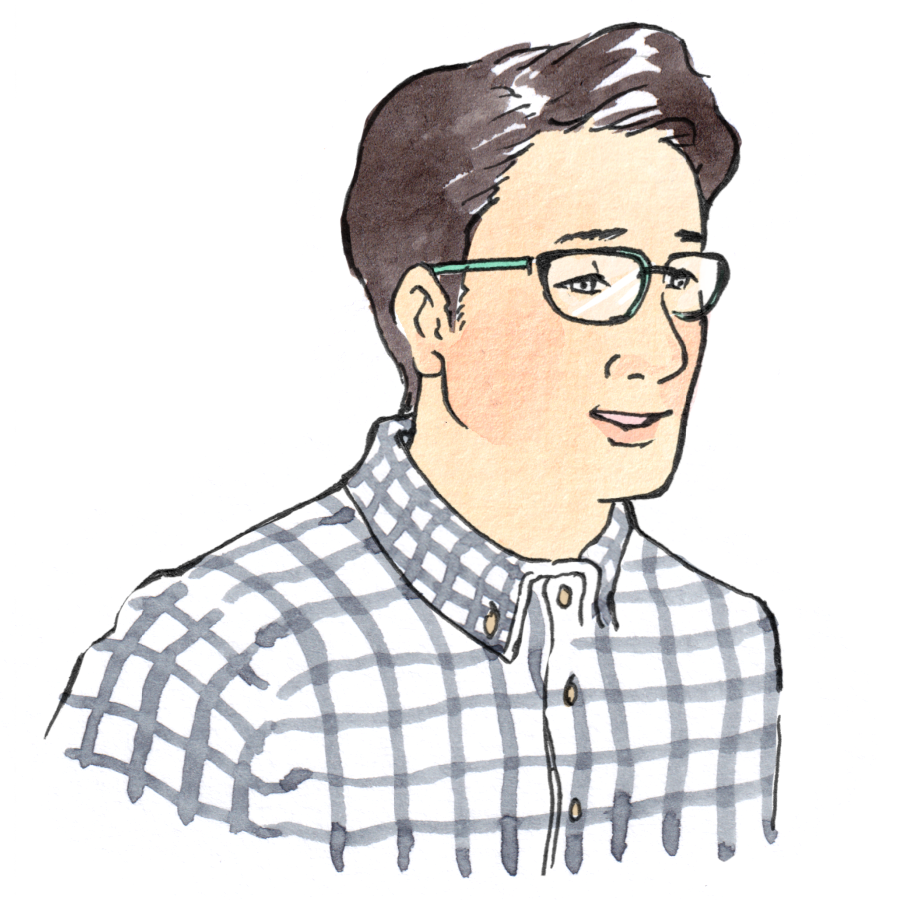 井上
井上