介護当事者の“本当の気持ち”を語らう「みんなの座談会」。今回は、ヤングケアラー・若者介護者として10代もしくは20代前半から家族の介護にかかわってきた3人にお話しを伺いました。
この記事に登場するみなさんのプロフィール(敬称略)
高校生のときに母親がくも膜下出血で倒れて、要介護5の寝たきり状態に。
学校や仕事の後に母親の病院に通い続ける日々を送るなか、山本さんは結婚、出産し一児の母となる。その後、母親が約20年間の入院生活の末に他界。その後、父親にパーキンソン症候群の症状が見られるようになり、実家への通いの介護をしていた。症状の進んだ父親は2022年に特別養護老人ホームに入所。
大学生のときから、母方の祖父の介護を担う。父親は亡くなっているため、働く母親に代わり「学生ならば時間があるだろう」と周囲から促される形で祖父の介護をすることに。大学院に進学するも学友や教師からは介護に対する理解を得ることができず、大学院を中退。就職先で祖父の介護で得た経験を活かそうとしたが上手くいかず、転職。その後、祖父は他界。現在は福祉関係の資格を取得し、福祉関係の仕事をしている。
大学生のときから、母方の祖母の介護を担う。両親に聴覚障害があったため、事業をしていた祖父母が親代りとなって中村さんを育ててくれた。中村さんが小学生のときに、祖父と父親が他界。中村さんをサポートし続けた祖母に、中村さんが大学在学中に認知症の症状が見られるように。初めは祖母の事業のサポートをしていたが、そのうちに一人で生活全般の介助を担うようになった。その後、祖母は特別養護老人ホームへ入所し、最期を迎えた。
10代や20代前半でも家族の介護をせざるを得ない状況に
みんなの介護(以下、―――) 学生という立場でご家族の介護を担う「ヤングケアラー」「若者ケアラー」だったみなさまにお集まりいただきました。
どのような経緯でご家族の介護を担うようになったのかお話いただけますか。
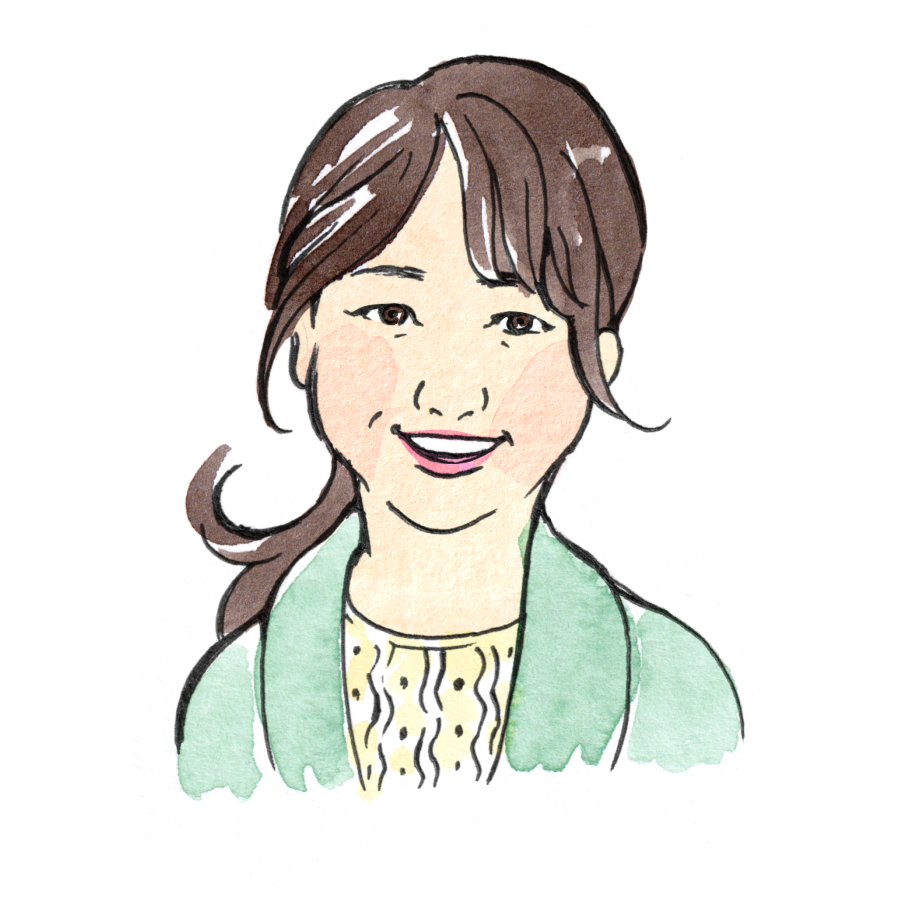
山本
山本です。17歳のときに、母がくも膜下出血で倒れてから、寝たきりの状態になりました。倒れた日に救急車で運ばれてから亡くなるまで約20年間、母は入院生活を送りました。なので、在宅介護をされていたみなさんとは少し違うのかもしれませんが、学校の帰りなどに病院へ行ってお世話をしていました。最初から最後まで、母は要介護5でした。
母を見送ったあと、前立腺ガンのほかにも持病のあった父がパーキンソン症候群に。要介護3の認定を受けました。父と同居している兄は、仕事で留守になることが多いので、介護サービスを利用しながらの約3年間、実家へ通いの介護をしていたのですが、2022年に父は特別養護老人ホームへ入所しました。
高校生のときにお母さんが倒れて以来、家事や病院でのお母さんのお世話を学生ながらにしていたという山本さん。当時は「ヤングケアラー」という言葉も存在しません。
お母さんが入院している約20年の間に、山本さんは結婚、出産をして1児の母になりました。現在、お父さんの介護とお子さんの育児を担う「ダブルケアラー」として、"2周目”の介護生活を送っています。
――― ありがとうございます。井上さん、お願いできますか。
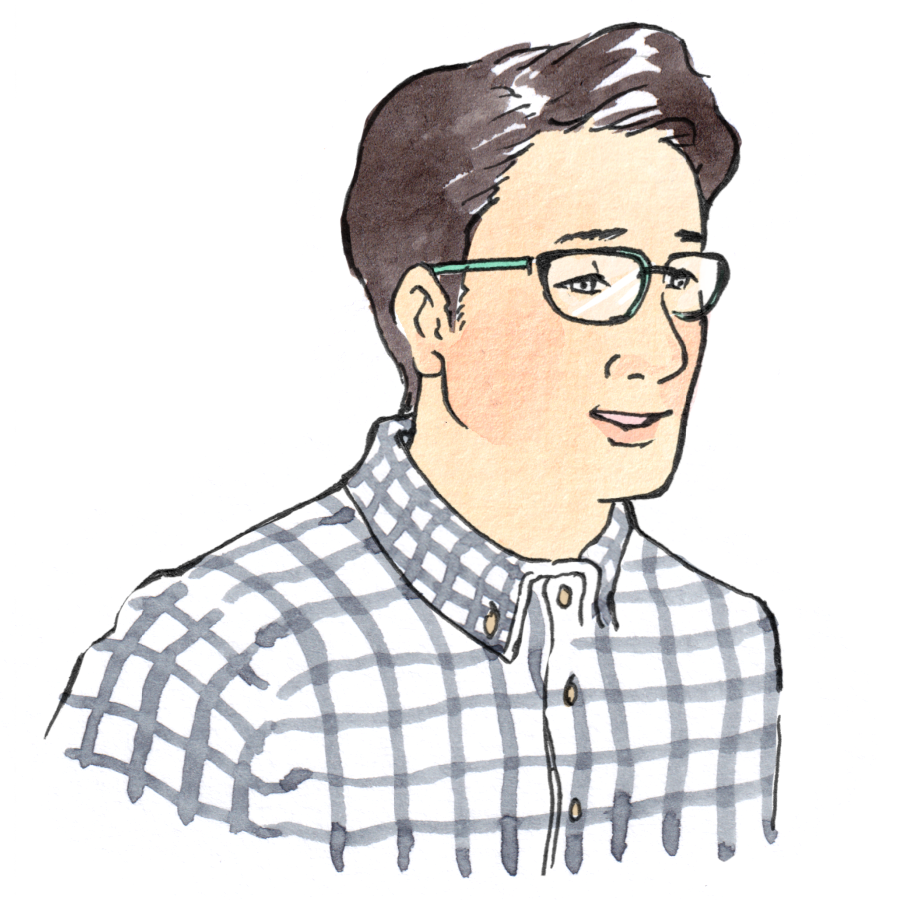
井上
井上です。大学4年生のときに、母方の祖父に認知症のような症状が見られるようになりました。母は働いていたので、もしその母が介護の負担から倒れてしまったら、私が2人の面倒を看なくてはならなくなります。「2人のお世話は無理だ」と思ったので、母の“手伝い”をするという認識で、祖父の介護に携わるようになりました。
大学に在学中から、研究者に興味があったので大学院への進学を考えていました。大学院生であれば、大学院に通いながら祖父の介護を自宅で続けられるとも思っていました。
ところが、私が大学院に進学したころから祖父の昼夜逆転生活が始まってしまって……外に出ようとして「毎晩」転倒したり、変なものが見えると騒いだりするので、その対応をする私は夜に寝ることができなくなりました。結果、大学院には寝に行くような生活になってしまいました。
お祖父さんはレビー小体型認知症だったそうです。最初は要介護1でしたが、しばらくすると要介護3に。井上さんを特に悩ませたのは、お祖父さんの深夜の幻覚や幻聴。対応がどんどん大変になっていった井上さんは、介護と学業の両立が難しくなってしまいました。
約10年の在宅介護の日々で、お祖父さんの施設入居をお母さんに強く「お願い」したそう。でも、お母さんや親戚の方々が難色を示し、結局、最後には施設の申込みこそしてくれたものの、入所する施設が決まる前にお祖父さんは亡くなってしまいました。
――― ありがとうございます。中村さんもお聞かせいただけますか。
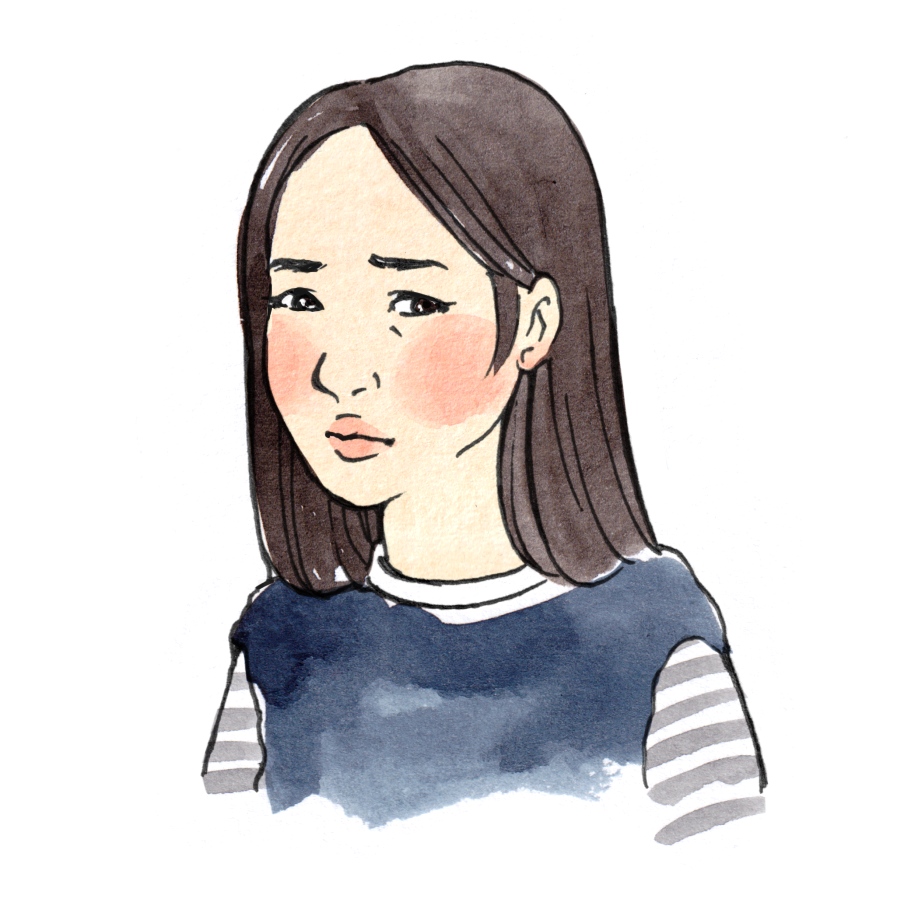
中村
中村です。両親が聴覚障害者なので育児の上で難しいこともあり、幼いころから実家の隣に住む祖父母が親代わりとなってくれていました。祖父は私が小学2年生のとき、父は小学6年生のときに病気で他界しました。祖父母がやっていた事業は祖母が引き継いでくれたので、母や私、年の離れた妹の生活の面倒をみてくれました。
祖母は、おかしな言動がみられるようになる1年くらい前に介護認定を受け通院介助サービスを使い自立した生活をしていました。
ところが、言動が怪しくなり、そのうちに歩行も困難になりました。さらに認知症が進行して、寝たきりの生活になってしまったのです。
それからの約4年間、祖母が特養へ入所するまで、介護サービスをほぼ利用せずに、私が1人で祖母の在宅介護をしていました。
家庭の事情や自身を取り巻く環境から、孫の立場で介護を担うことになった井上さんと中村さん。二人とも大学生かつ、20代前半ということで、同世代の方々との大きなギャップを感じていたそうです。
「ヤングケアラー」は周りのからの助言が受けにくい!?
――― 介護保険の申請をされた際に、介護や医療の関係者の方からのアドバイスはなかったのでしょうか。
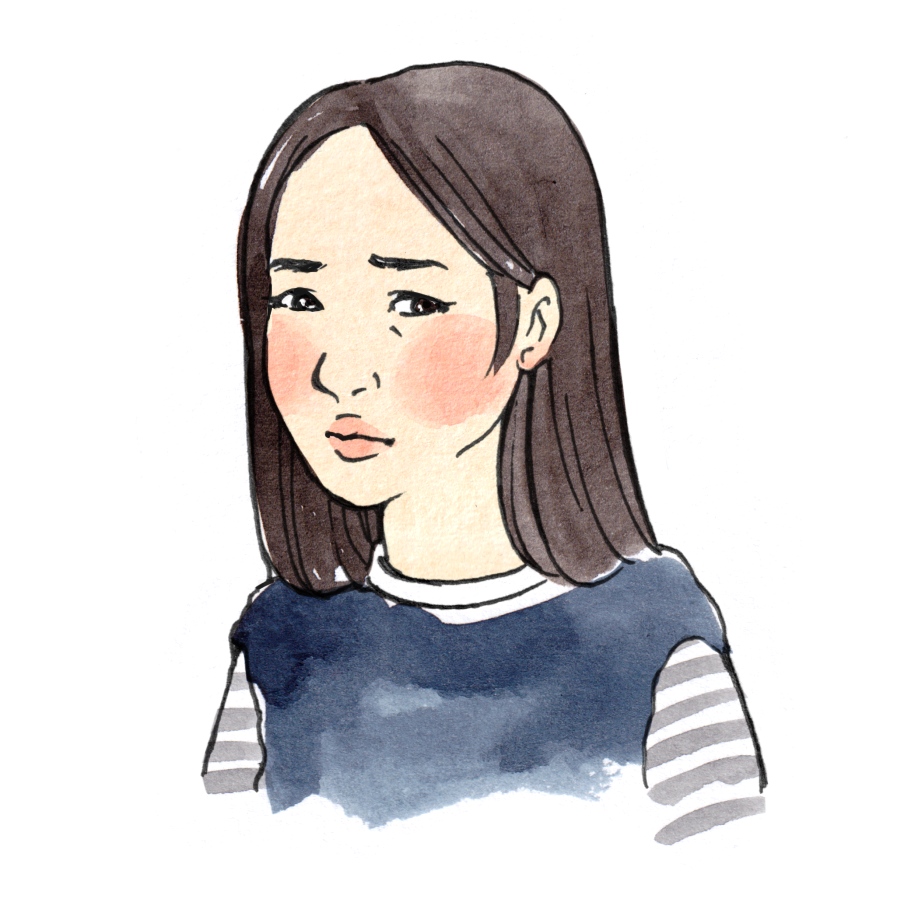
中村
言ってくれていたのかもしれませんが、私がそれを受け取れなかったのかもしれません。それだけでなく、自分が本当に困ったときに頼れる人が浮かびませんでしたね。
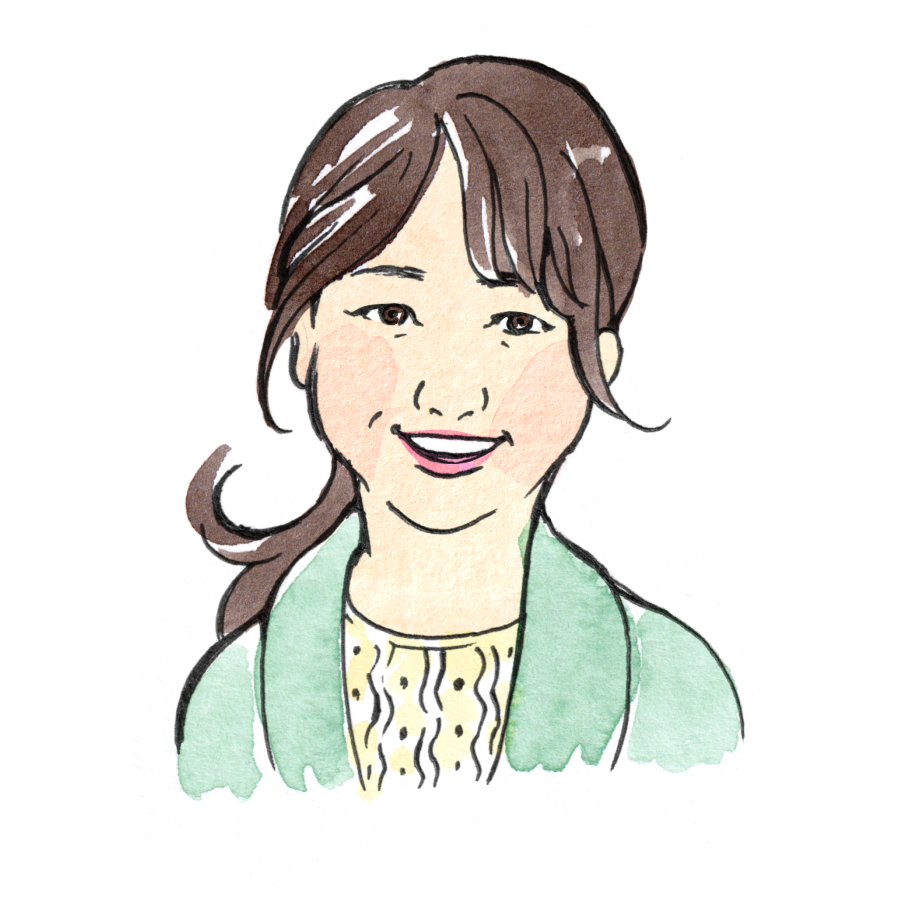
山本
いわゆる「ヤングケアラー」として母を見ていたときには、倒れたその日から入院だったので、頼るとするならば病院の看護師さんや介護士さんだったと思います。でも、「あなたが来るとお母さんが喜ぶわよ」と言われたりしたので、「はい、頑張ります」と言うしかなくて。ですから、心理的なことを相談するチャンスがありませんでした。
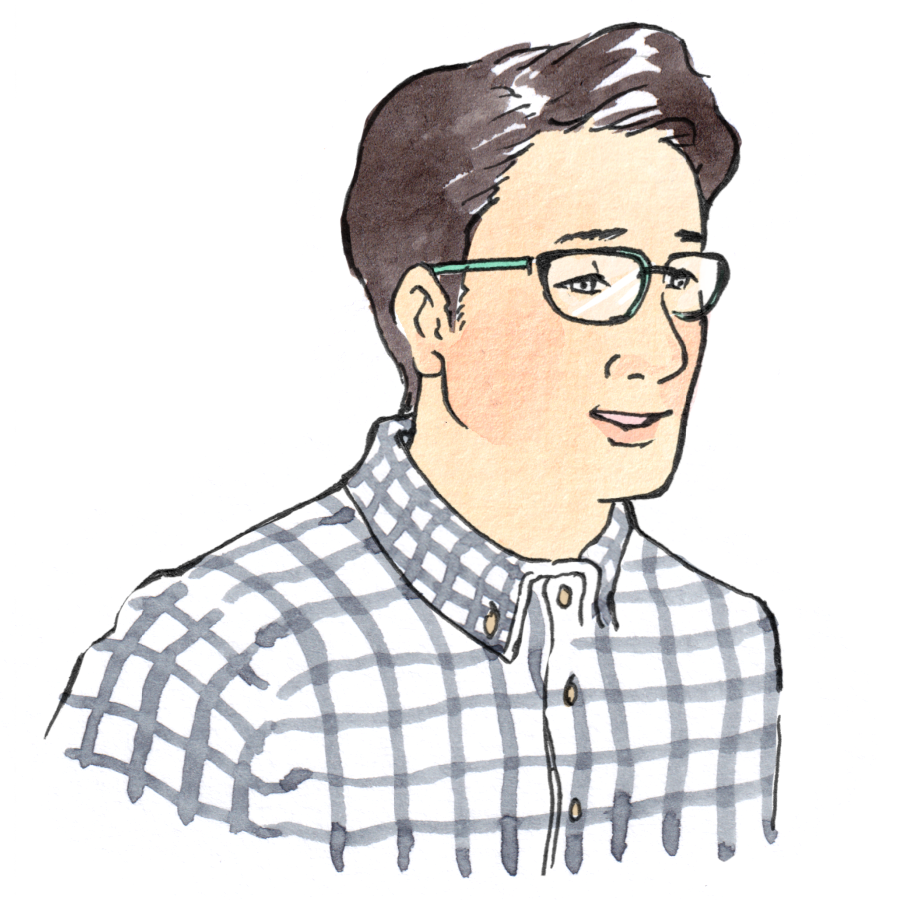
井上
私の場合、介護申請などの手続きは母がやっていたので、専門職の方と関わる機会があまりありませんでした。
それでも、家で偶然"接触”した専門職の方からは「お孫さんも関わってくれるから安心ね」と言われたり、「お手伝いしてくれるなんて、えらいね」と言われたことがありました。
そう言われてしまうので、「自分のやっていることはお手伝いなんだ」としか思えなく、「自分は介護をしている」という認識をするまでに時間がかかりました。
――― 井上さんはどのようなことをきっかけに、ご自身が「お手伝い」ではなく「介護」をしていると認識できたのでしょうか?
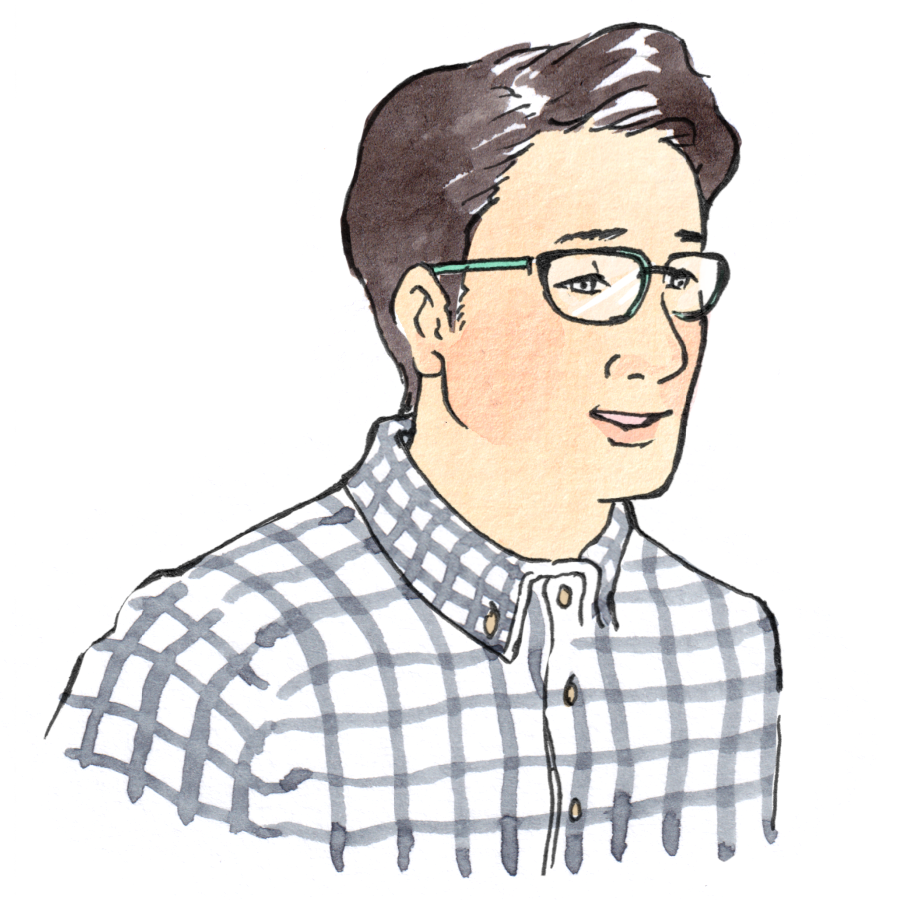
井上
新聞で「男性介護者の会」のことを知り、参加したんです。そこでは50代が「超若手」と言われていましたが(笑)。
ただ、「君のやっていることは介護だよ」と、初めて参加した日に言われました。そこで「介護をしている」という自覚ができて、「ここでならみなさんに相談することができるのではないか」とも思いました。
私にとっては、世代が違えどもその会の方々のほうが同世代よりもいろいろと話しやすかったです。それまで同世代に話しても望むような反応は得られなかったし、やれ結婚したとか、就職したとか、旅行に行くとか……そんな話を聞くのがつらかったので。
それよりも利害関係やしがらみがなく、"お父さん”のようなの方々と話すことが私には合っていたようです。
大学院を辞めて就職はしたものの、家での介護と会社の往復くらいしかやることがなかった私にとって、第三の居場所が出来たという感じでした。
――― お二人にとっての「第三の居場所」はありましたか。
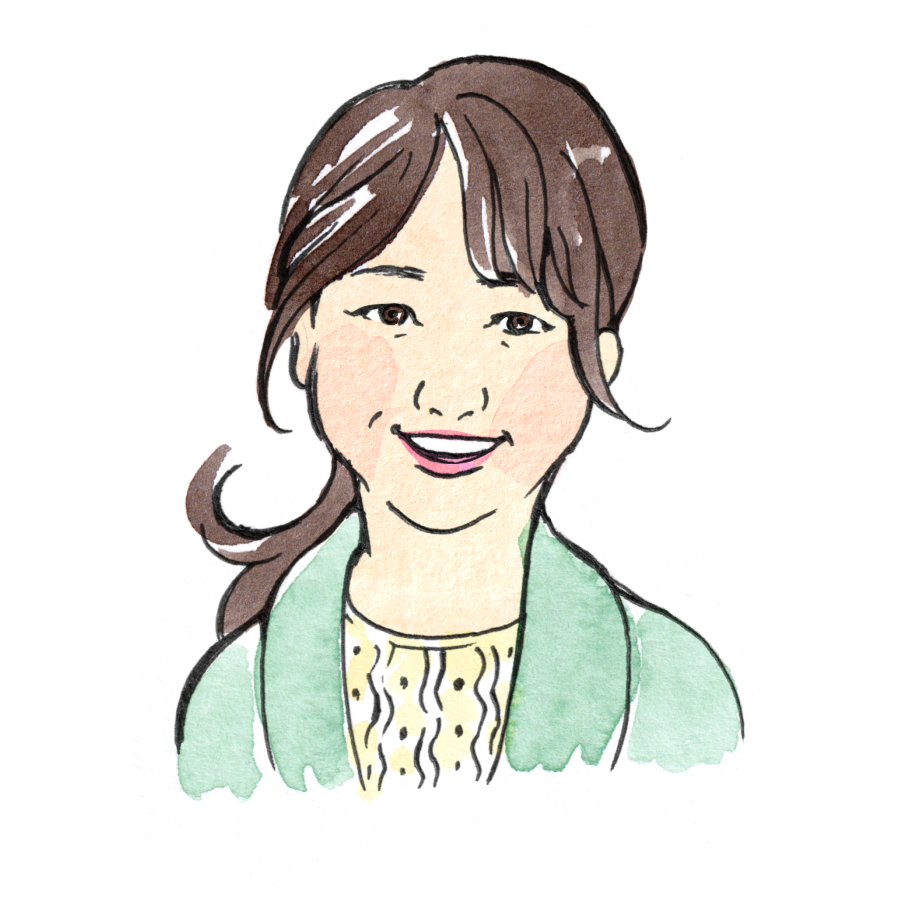
山本
SNSでご家族を介護している方々のコミュニティーを見つけました。そこに集う方々は「もうしょうがないから今の状態を楽しんじゃおう」と明るく介護をしている感じの方々で。その"ノリ”に救われた感じがありました。
ただ、同世代は"現場”の方しかいませんでしたが。オフ会も開催されて、そこに参加したことで介護仲間との横のつながりができていきました。
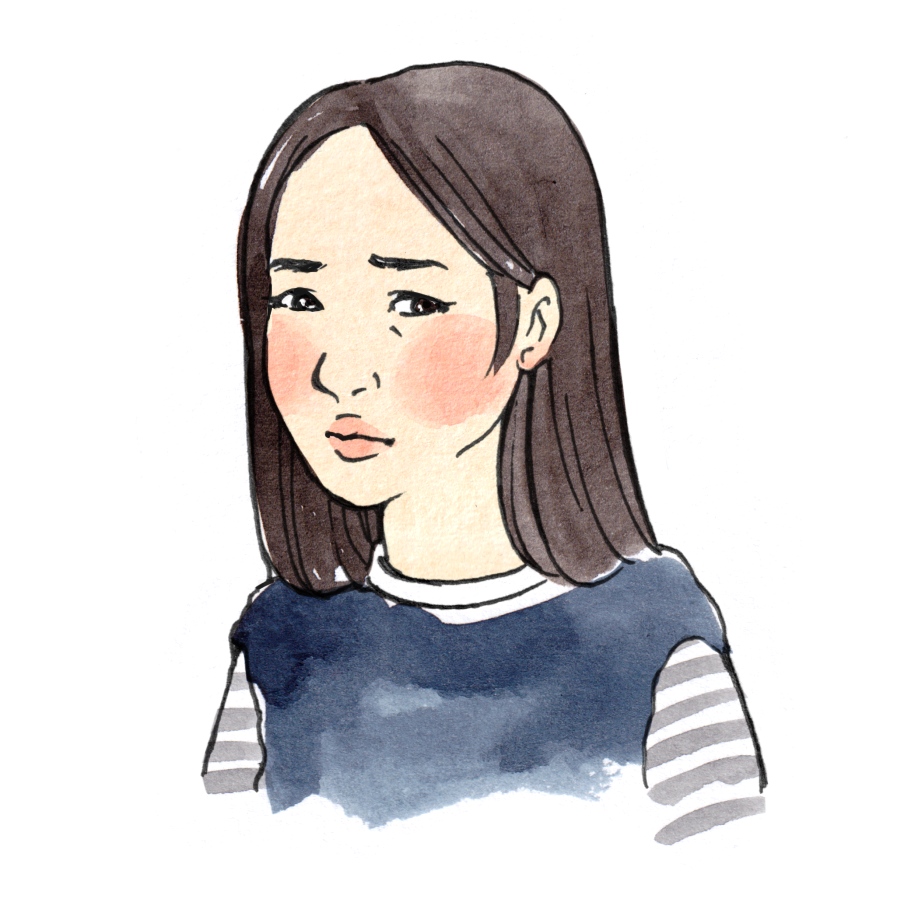
中村
私はそういった会にも一切参加していなくて……そもそも、そういった会があることすら知りませんでした。当時はネット環境も不十分だったので、誰とも繋がることができずに社会から孤立したような思いでした。世界が狭くなり、「こんな生活をしているのは自分だけだ」と思い込んでいたのかもしれません。
それでも、私の状況を知っている友人が、同世代で介護をしている方を紹介してくれました。その方と出会うまでは、20代から介護をしている方に出会ったことがないし、話しても私の思いは伝わらないと心を閉ざしていましたね。でも、その方とは共通点があるし、自身の介護の知識や体験から掘り下げて話をしてくれることが、すごくうれしかったのを今でも覚えています。
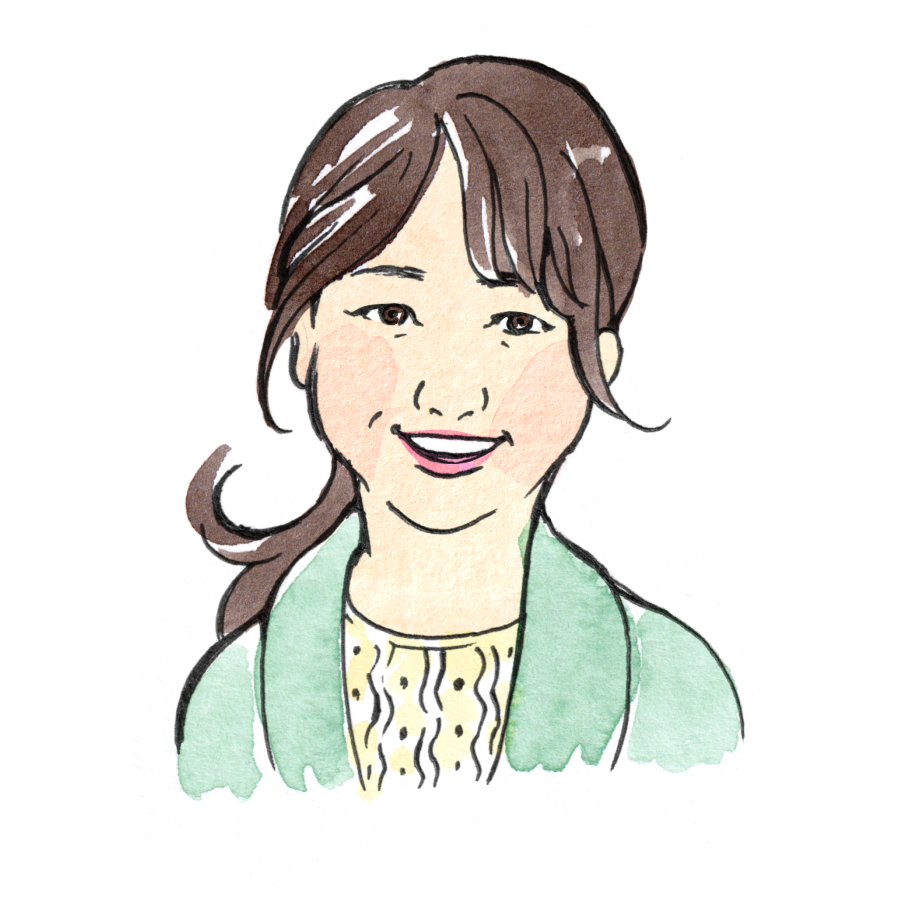
山本
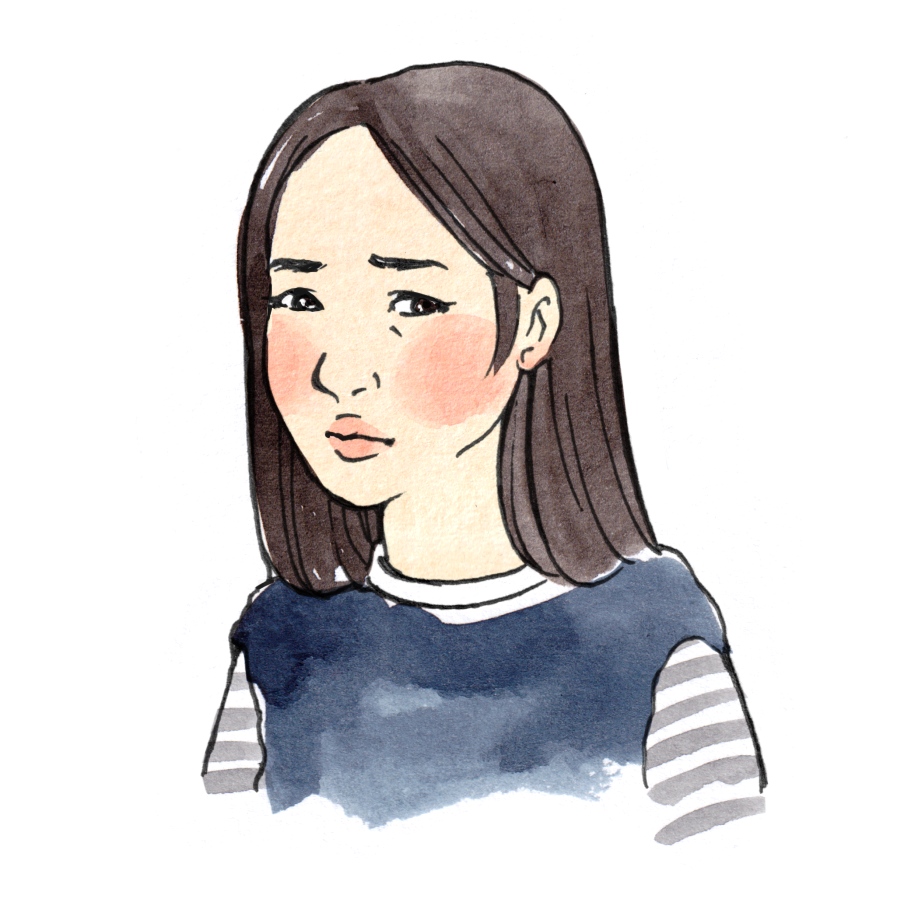
中村
当時の私は、介護サービスは使わずにほぼ一人で祖母の在宅介護をしていたのですが、その方に「なんでもっと介護サービスを使わないの!」と言われて、それがきっかけで施設入所も含めて、介護サービスの利用を考え始めました。
――― お話いただいたような出会いがなかったら、みなさんはどうなっていたと思いますか。
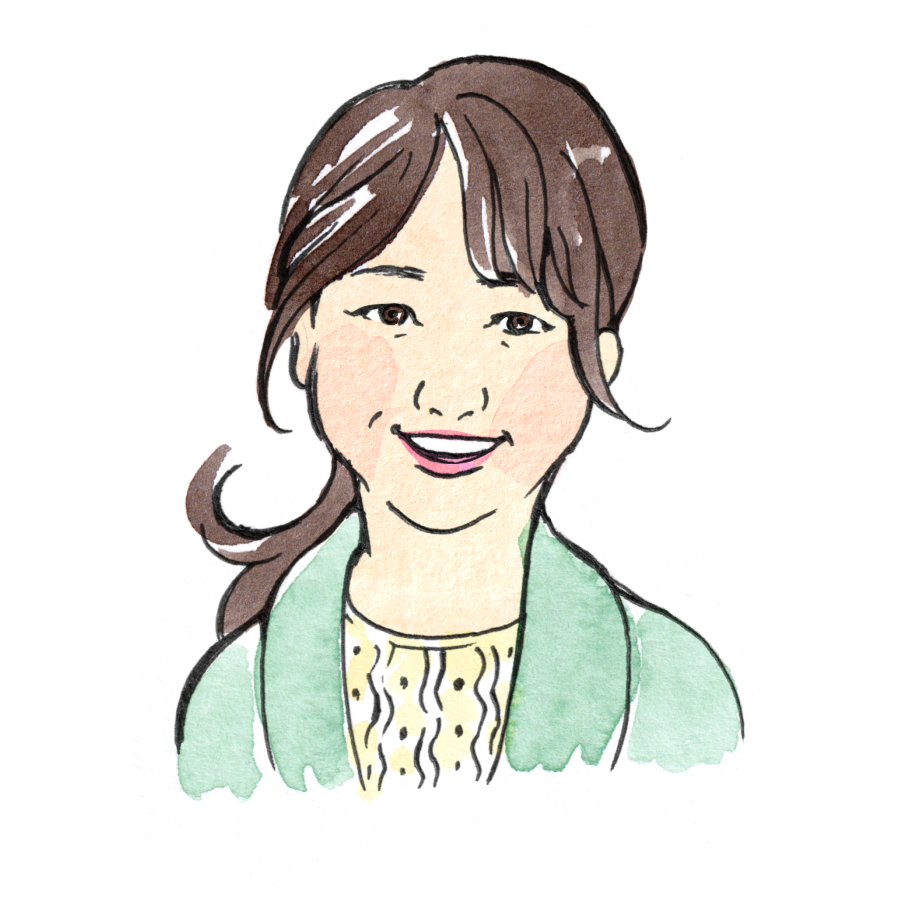
山本
ずっと探し続けていたとは思います。それでも見つからなかったら、「誰も私を理解してくれない」と卑屈になっていたと思います。
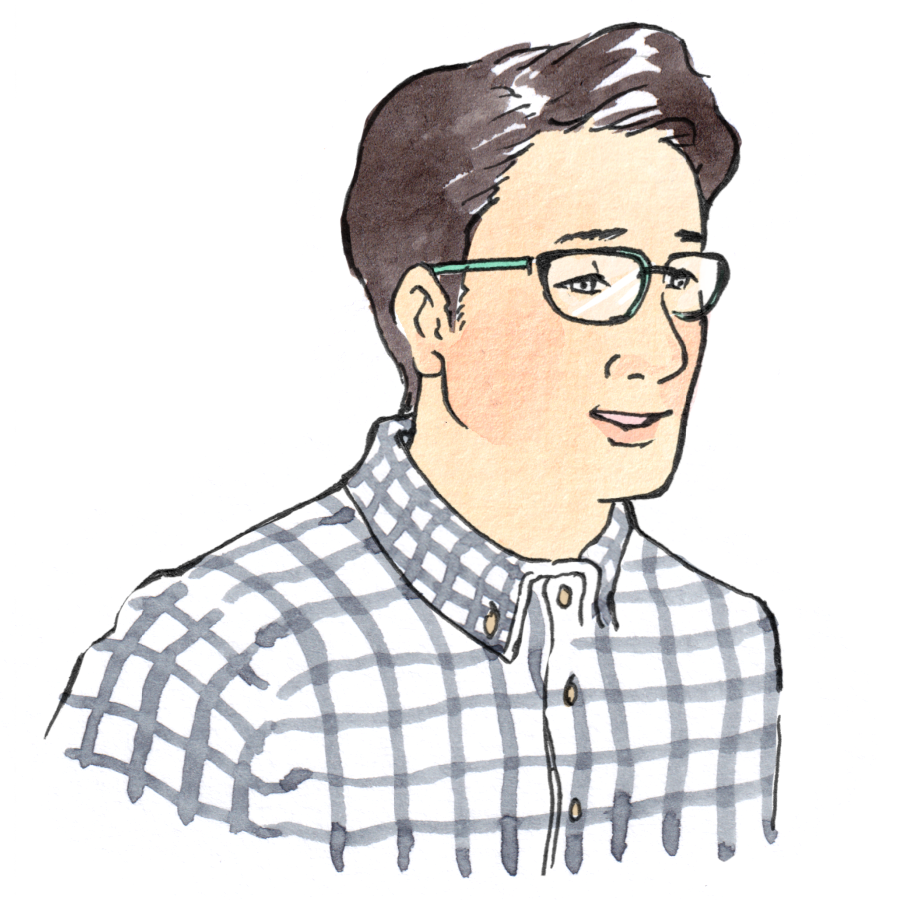
井上
私は大学院を辞めたときに、人生を立て直そうと思い、自分が嫌だと感じる環境を全部放り投げたんです。そのタイミングで「男性介護者の会」との出会いがあったり、若者の雇用対策のカウンセラーさんから「あなたがやってきたことは履歴書に書けることではないか」と言われたりして、前に進むことができました。
だから、ご縁というか、人との出会いや自分を理解してもらえるコミュニティーというのは非常に大きな力になると思っています。
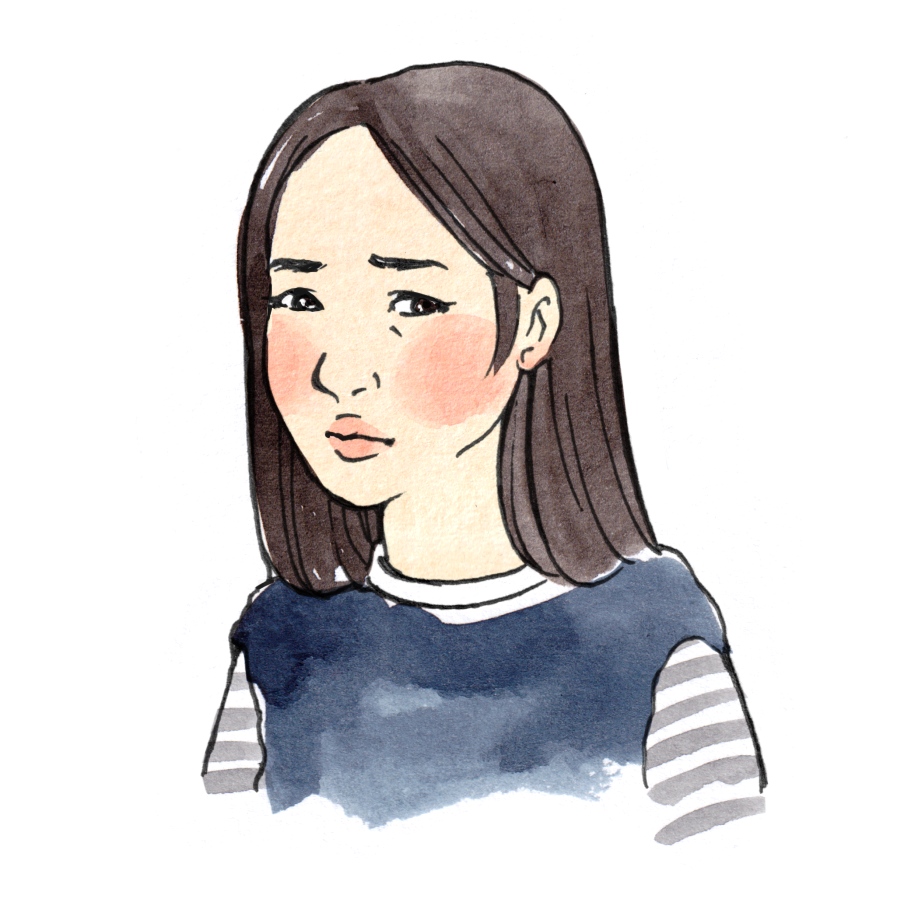
中村
心を開いて、初めて祖母について話ができたときの感動は今でもしっかり覚えています。
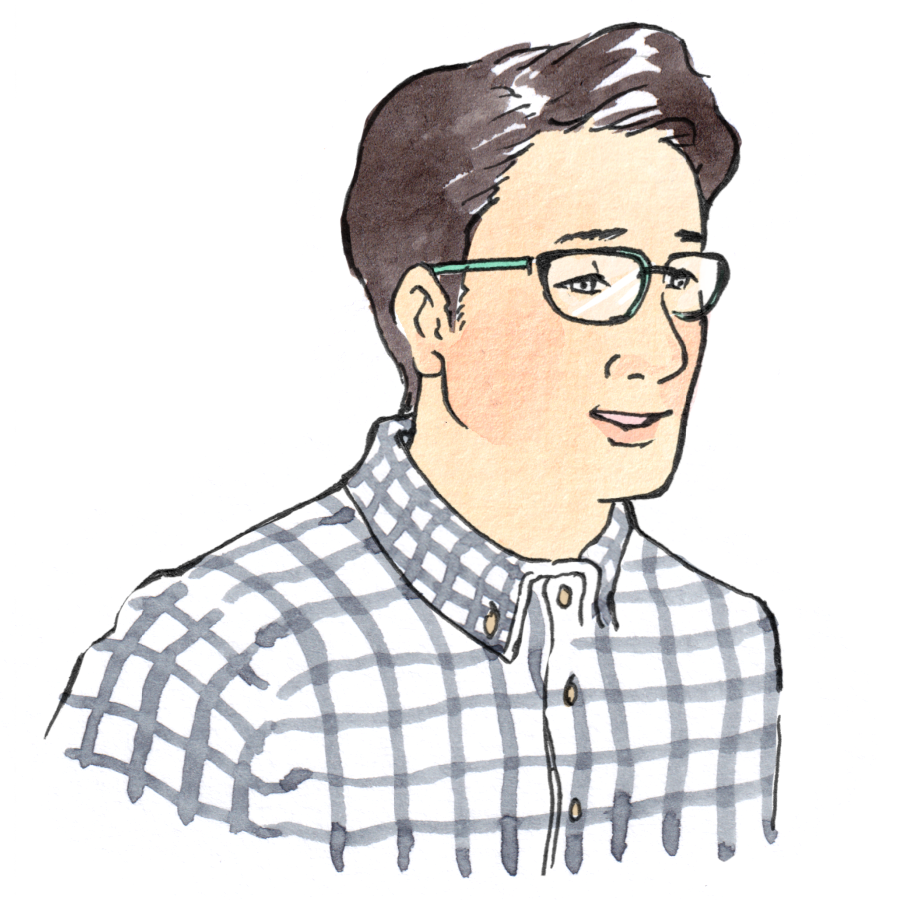
井上
大学院に通いながら祖父の介護をしていたころから、私のような人の現状を変えるような取り組みがしたいと考えるようになりました。
ただ、自分1人で動こうにもその方向性がわからないままで。それが、人生を立て直そうと動き出したことで、転職して、福祉に関する資格を取得するなど、方向性が定まり自分のやるべきことが見えてきました。
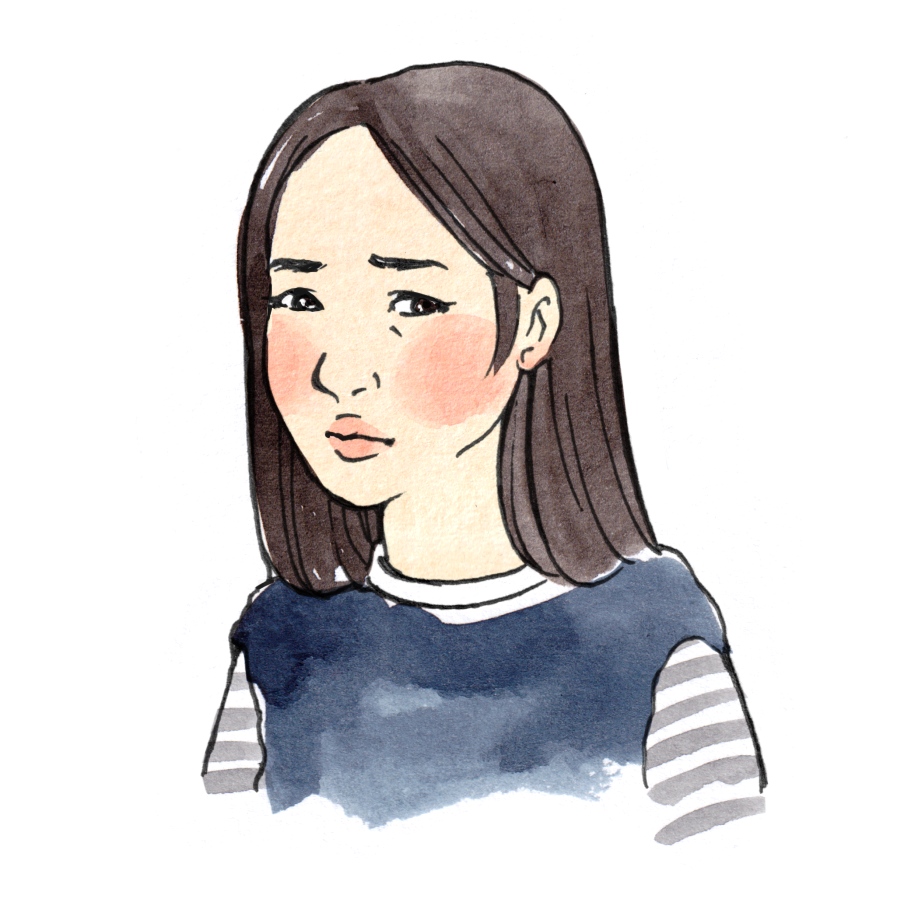
中村
もし、祖母の介護を自宅でし続けていたら、破滅的な終局を迎えていたと思います。同世代の介護経験者の方のお話は、すべて納得がいくというか、腑に落ちることばかりだったんです。そうやって、若い方が介護をするという「現実」を理解した上でどうすればいいかを伝えてくれる方に出会えるのとそうでないのとでは、雲泥の差があると思いましたね。

自分の存在がだんだんと消えていく……
――― 在宅介護で大変だったことを教えてください。
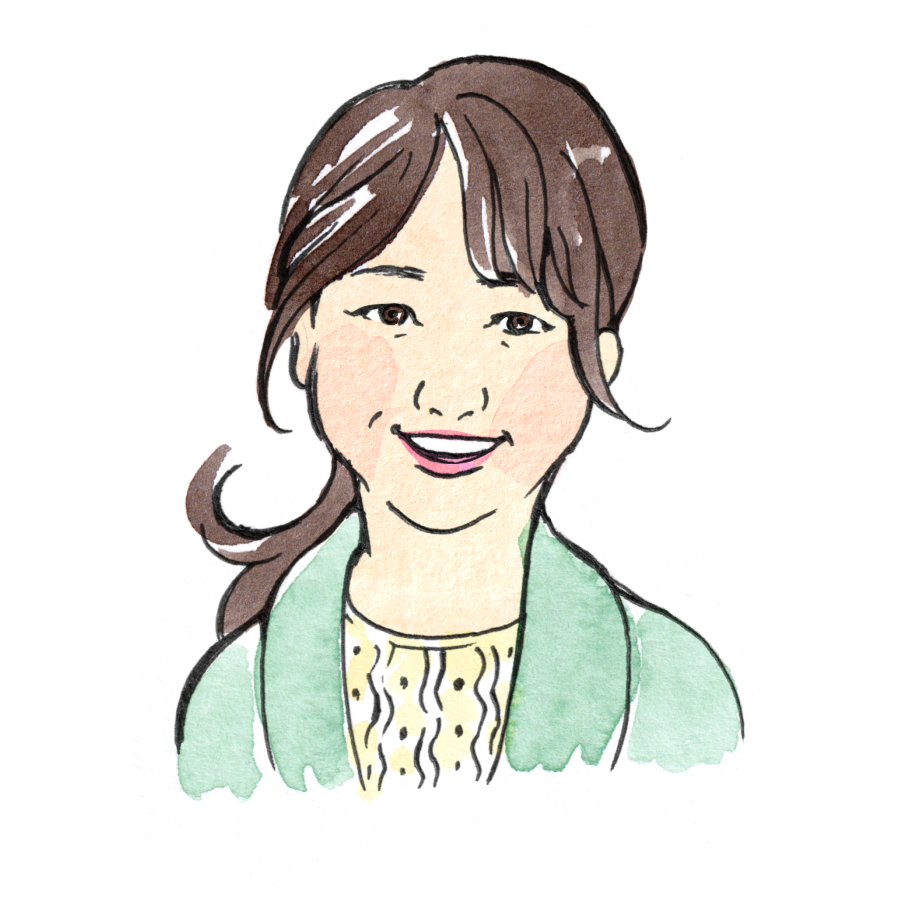
山本
父の在宅介護の話をさせてください。パーキンソン症候群で足元が不安定なため、私が見ていないところで、いつ転ぶかわからないのが常に不安でしたね。あとはストレスのはけ口というか、兄が「おやつオバケ」と呼ぶほど、大量に甘いものを食べてしまうんです。食べ過ぎて吐いたり下痢をするほど食べるのですが、その対応って余計な「仕事」というか。
……あとはときどき実家に帰ってくる兄が、そんな父を怒鳴ったりして、親子関係が最悪で。兄と父は同じ家にいるはずなのに、それぞれが私に電話をかけてきてグチるんです。父と兄のクッション代わりとなって、私が2人の話をまとめて、それぞれに電話を掛け直すという。
――― 井上さんはおじいさまをご自宅で見られていた際、いかがでしたか。
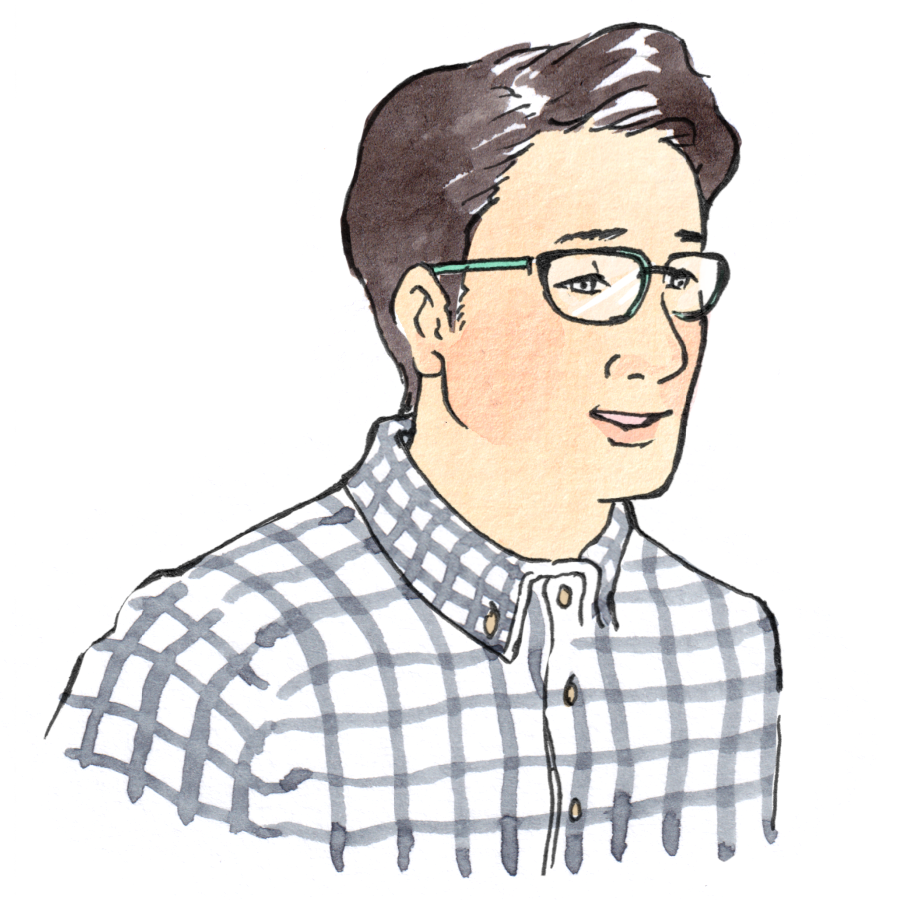
井上
夜中に祖父が家から出ようとするので、玄関に鈴をつけておいて、それが鳴るたびに飛んで起きていくとか、本人が動き回っていた最初の半年くらいが一番しんどかったです。
実は介護自体が大変だと思ったことがなくて。祖父の介護のせいで行動範囲が狭まって、自分のスケジュールがどんどん真っ白になっていくというか、自分の存在がだんだん消えてくような感覚がつらかったです。
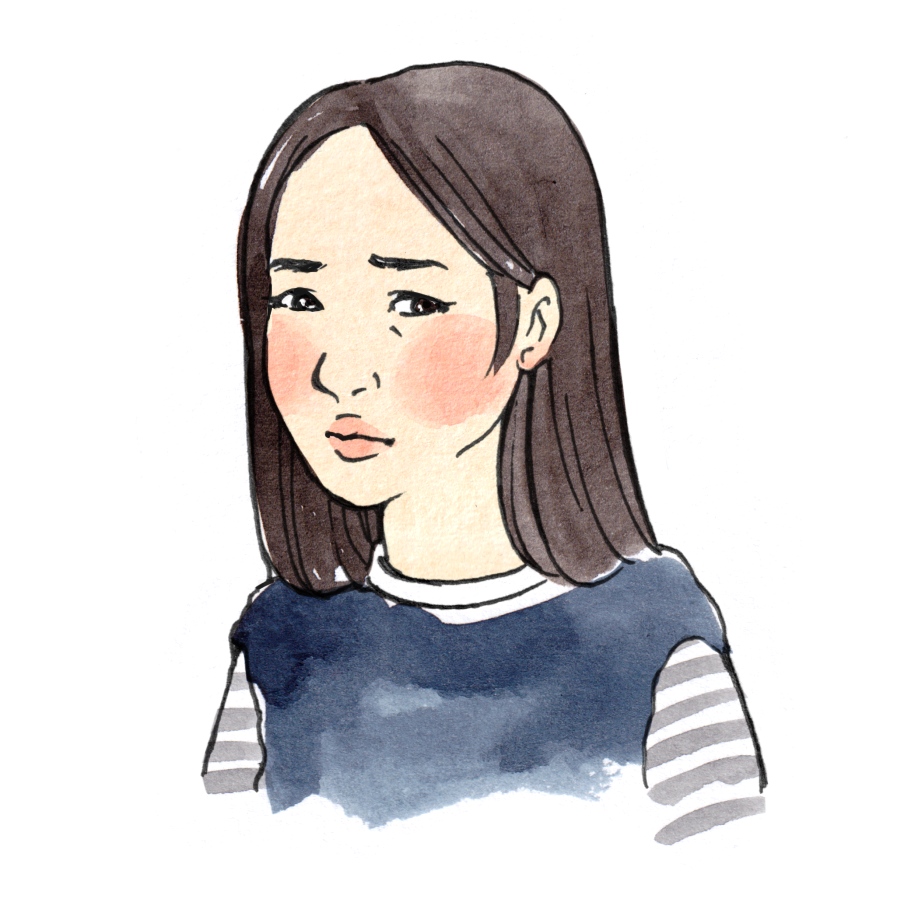
中村
私も祖母が一人で動けたころはいつ転ぶか分からないので、常にハラハラしていました。疲れると隣の自分の家に帰って、数十分休んだら、また祖母の家に戻るのですが、その間に祖母が転んでいたりするので全然気が休まりませんでした。
一人で動けなくなってからは、移動するたびに重い身体を支えて介助しました。昼夜逆転してしまったので、夜中の2時3時まで様子を見て、寝付いたら自分の家に帰れます。朝、祖母のところに行くと布団に粗相をしているので、それらを片付づけるのも大変でしたね。
とにかく休むことができないので、若いからある程度続けられたと思うのですが、精神的にも肉体的にも常にギリギリな感じでした。
中村さんは、今であればプロに頼ることの重要性がわかると言います。しかし、当時はギリギリな状態でありながら、ご家族の反対があったり、家に"他人”が入ってくることに抵抗を感じて、訪問ヘルパーなどの介護サービスをお願いしなかったそうです。
後半では、施設入所に対する葛藤やそれを乗り越えたきっかけ、若いからこそ、2周目となる介護を再びすることになったときの心構えなどについて伺います。
取材・文:岡崎 杏里




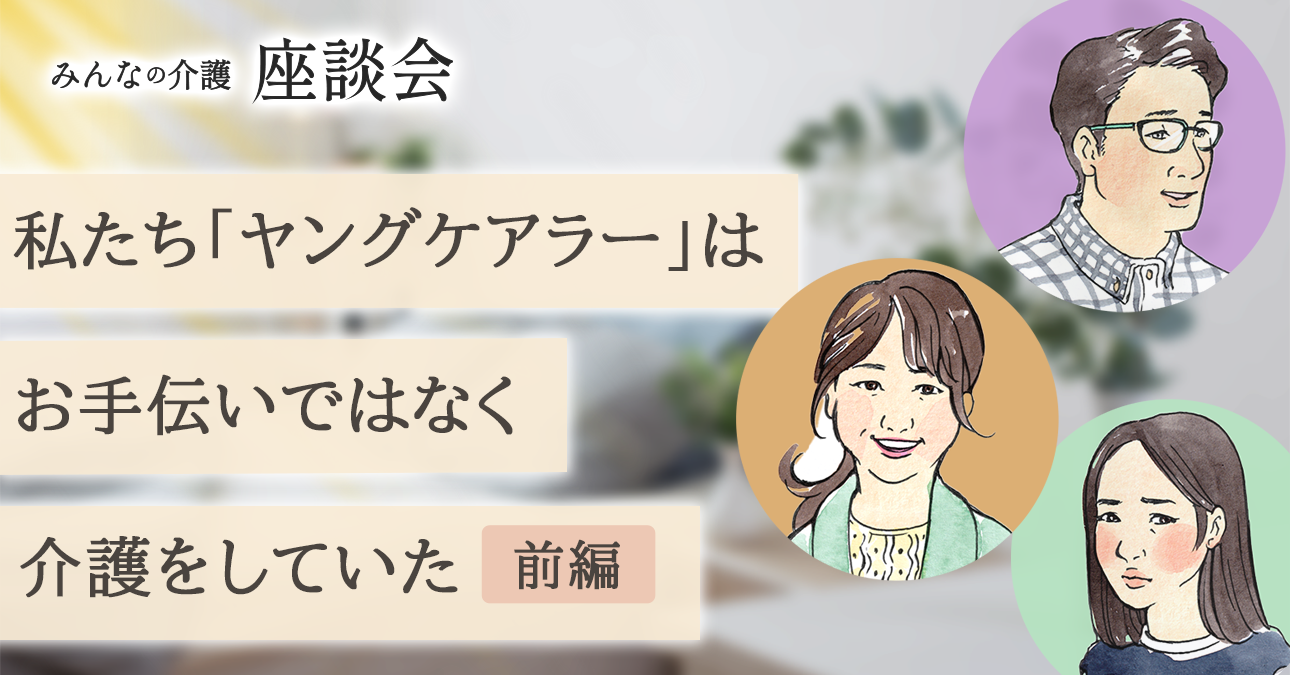

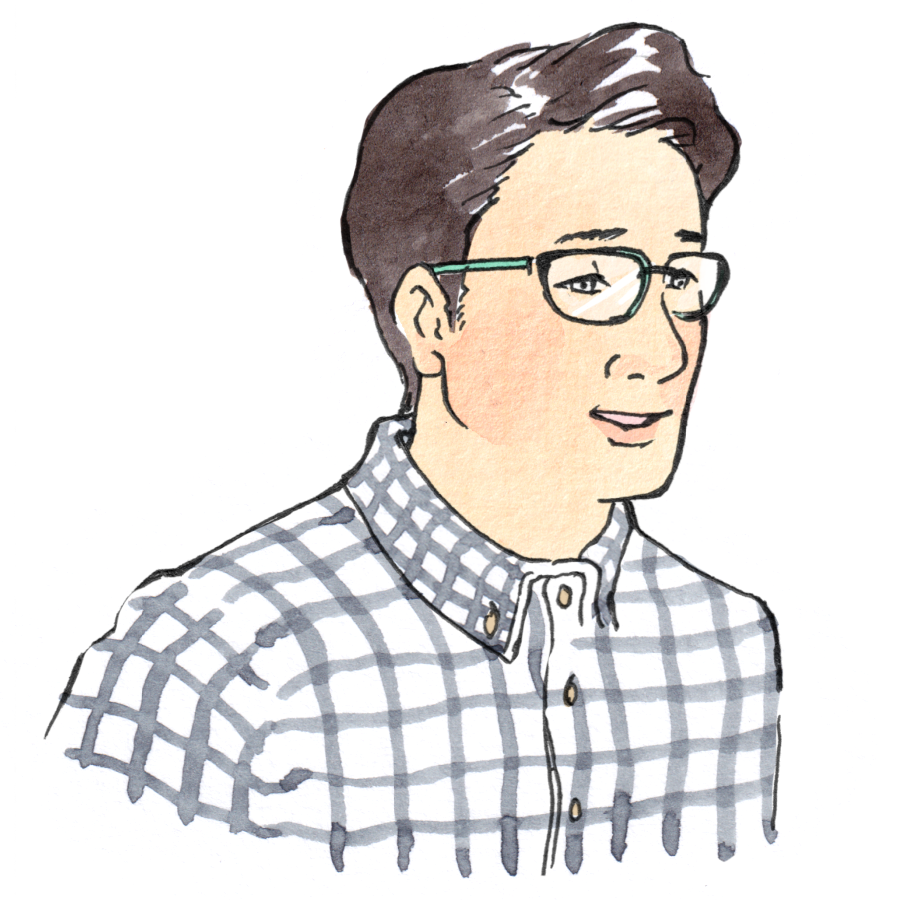
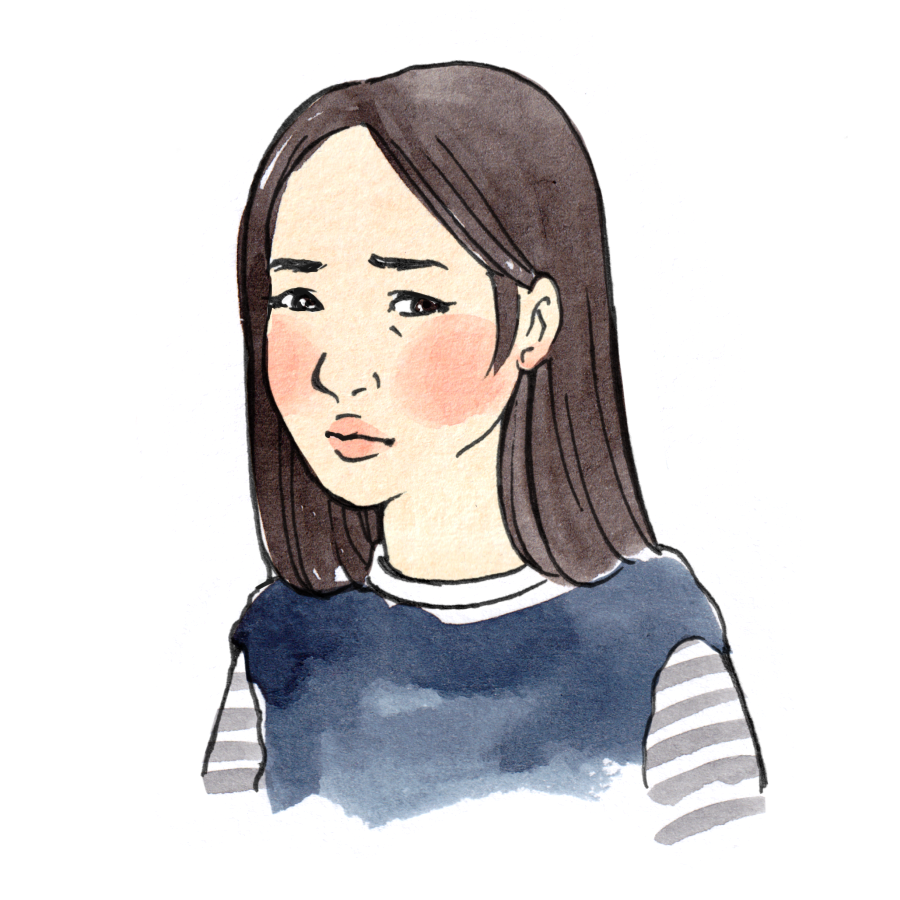
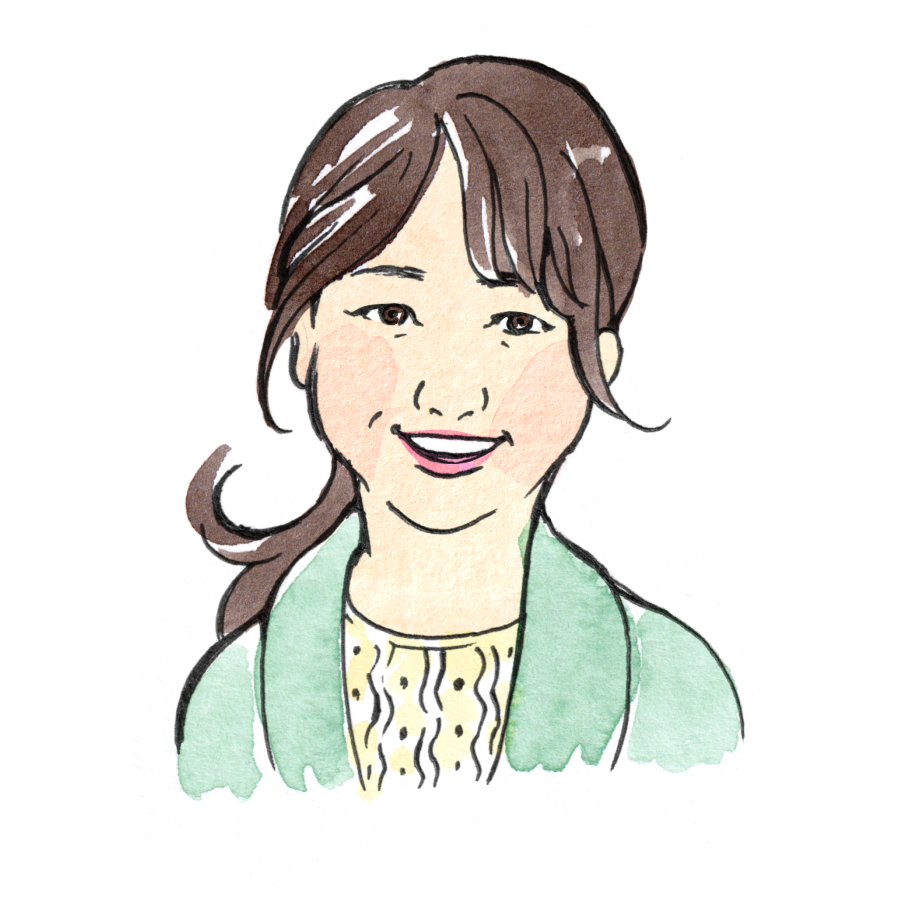 山本
山本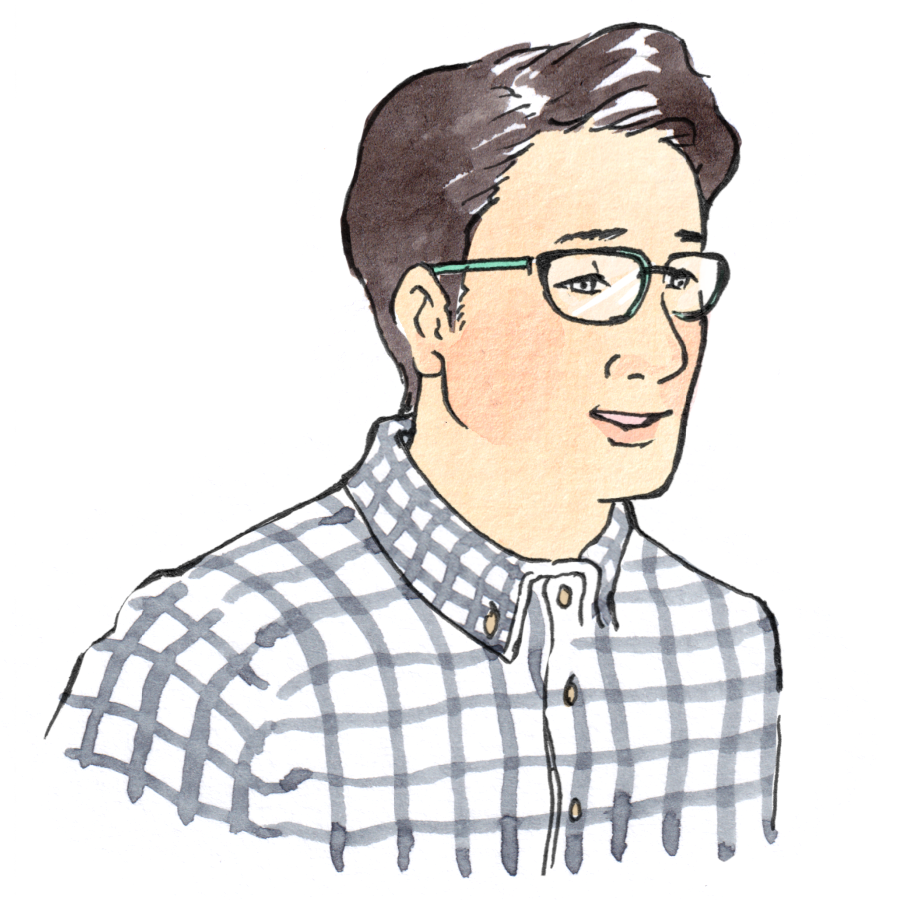 井上
井上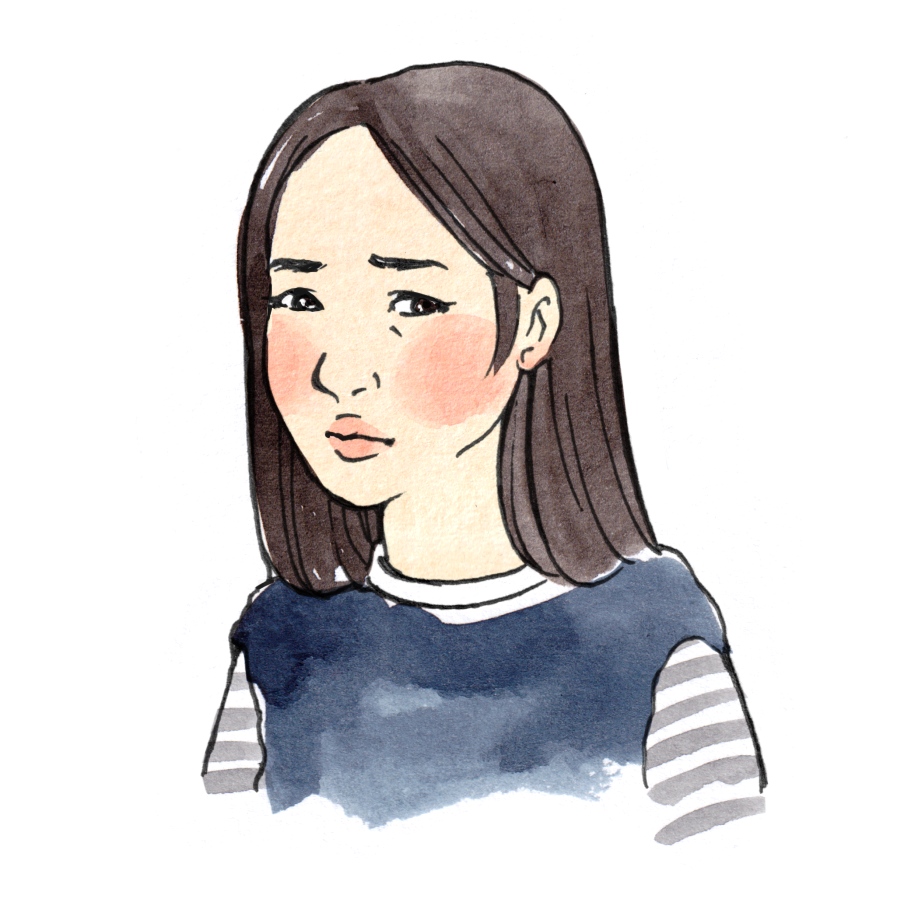 中村
中村