今回は「ママ友」による介護座談会です。親を介護するママさん、孫として介護に参加していたママさん、通いの介護をするママさん……介護の距離感についてのお話を伺います。
「ママ友」の介護座談会
みんなの介護(以下、―――)
本日は「ママ友」の皆様にお話を伺います。まずは、自己紹介をお願いできますか。
――― 吉野さん、お願いできますか。
――― ありがとうございます。最後に杉浦さん、お願いします。
――― みなさま、ありがとうございます。小西さんの介護のお話をベースに、皆様のご意見をお伺いするような形で進行させて頂きます。
介護を意識した日
――― 小西さんがお母さまの介護を意識され始めた頃のお話をお伺いできますか。
―― 認知症に対するご理解があったのでしょうか。
認知症が「痴呆」と呼ばれていた時代に
―― 吉野さんは祖父母の在宅介護をされていたと伺いました。当時、認知症の症状は見られなかったのでしょうか。
――― 当時のご家庭の雰囲気を伺えますか。
認知症への対応
――― 当時は認知症への誤解もあったと想像するのですが、「支援」という発想は経験則で理解されていたのでしょうか。
―― お母さまの介護で大変だったことはどのようなことでしょうか。
子どもの介護体験の話
――さきほど、孫世代とのかかわりについてのお話を吉野さんから伺いました。小西さんのお子さまは介護に対してどのような思いなのでしょうか。
―― どのような反応が?
――孫世代と祖父母世代が介護について理解を合わせることの難しさを感じます。
――詳しくお聞かせください。
「ママ友」の皆さんの真っ直ぐな意見。学びの多いお話でした。後編では吉野さんの入所のお話に迫ります。

「みんなの介護座談会」へご参加頂ける方を募集しています
「みんなの介護座談会」は読者の皆さまに参加して頂く新企画です。皆さまの日々の介護に対する思いをぜひ座談会で語ってください。
以下のフォームより、ご応募をお待ちしております。


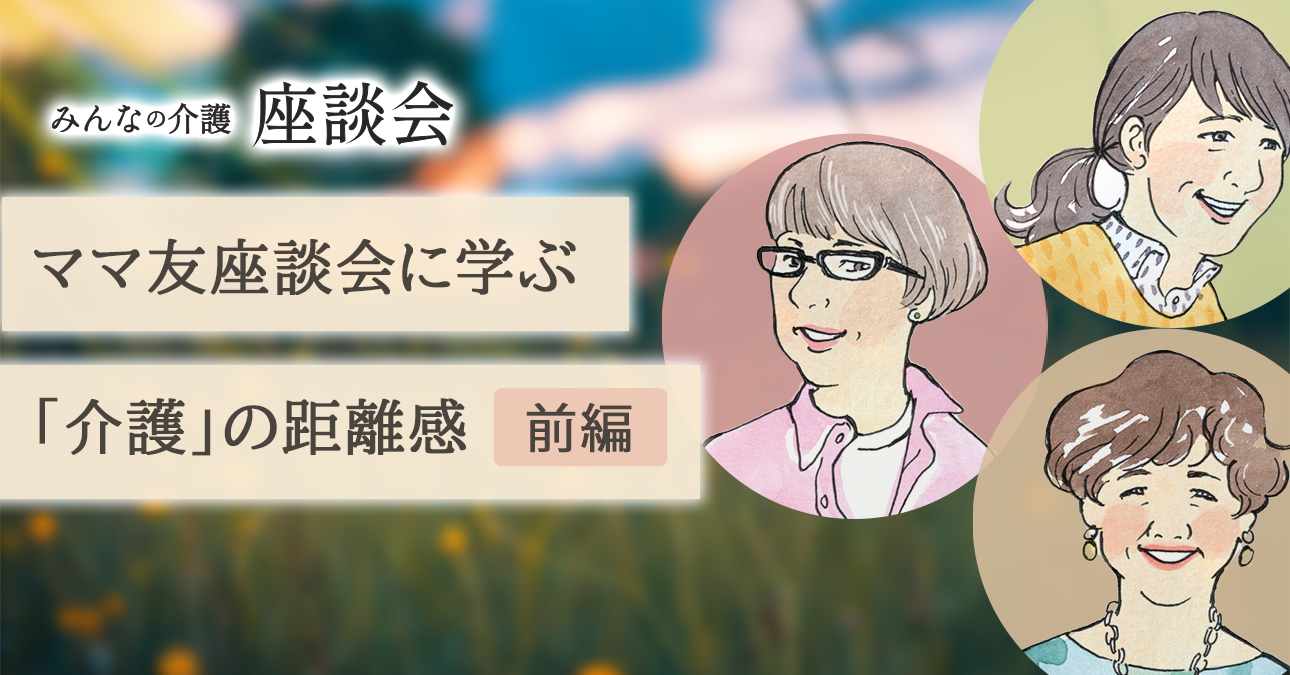


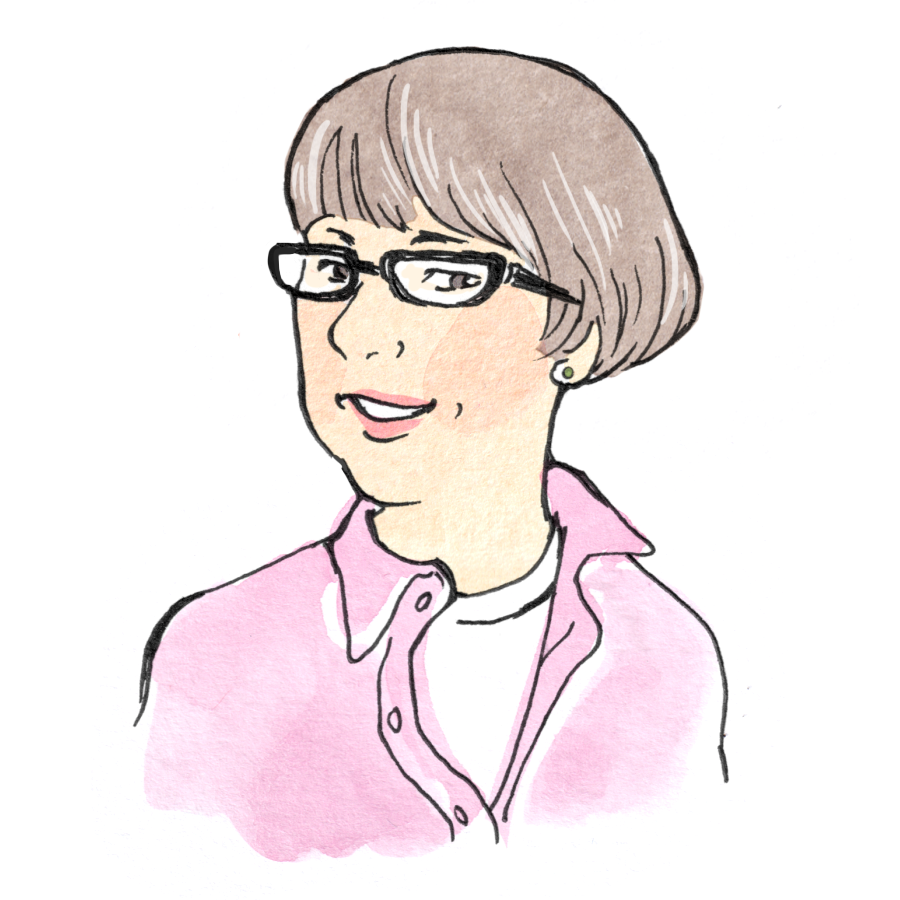
 小西
小西 吉野
吉野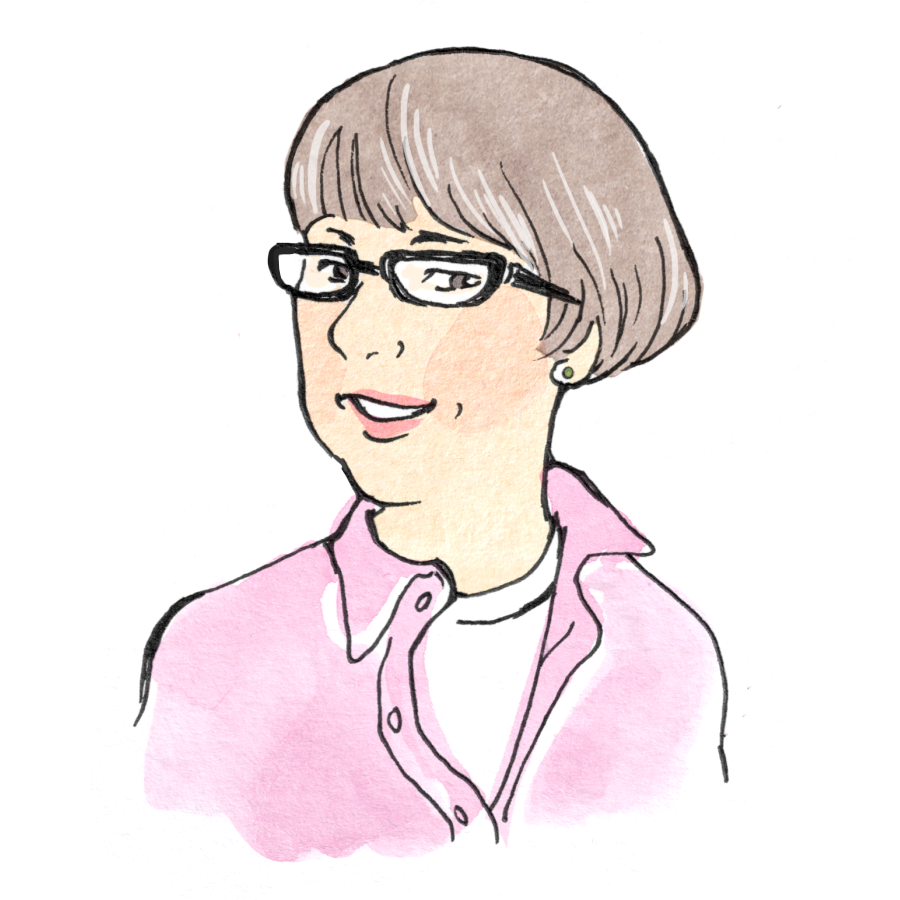 杉浦
杉浦