今回はある姉妹とその従妹による座談会です。前編では、老人ホームの入所の是非について意見を交わします。「5名」の家族の介護経験があるという藤堂さんを中心に、プロによる介護と在宅介護について語らいます。
この記事に登場するみなさんのプロフィール(敬称略)
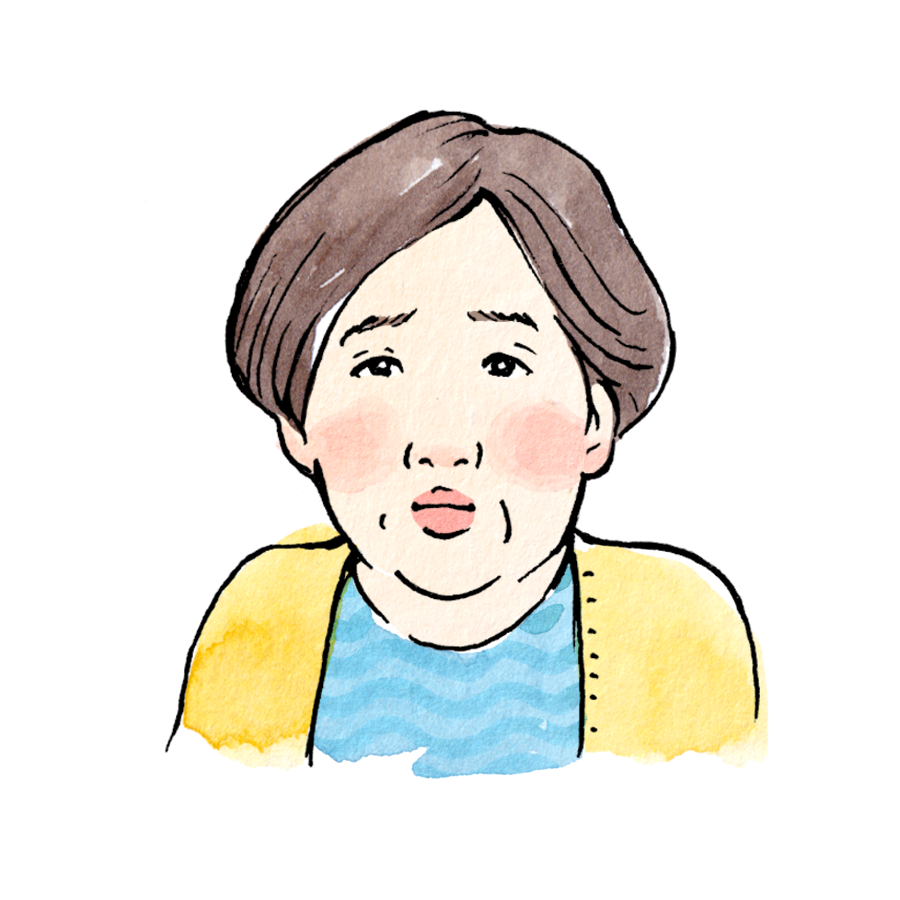 田崎 ミホ(仮)
田崎 ミホ(仮)
 田崎 ヨウコ(仮)
田崎 ヨウコ(仮)
 藤堂 ミキ(仮)
藤堂 ミキ(仮)
60代主婦。認知症の実母(要介護3)がグループホームに入所している。長女として自宅で一緒に暮らしたいと考えているが……。
60代主婦。義母の在宅介護を10年以上経験。義母が亡くなってからは、同居する孫の面倒を見る毎日に。姉が実母と暮らすことには否定的。
20代前半から家族の介護に携わる。人生で5人の家族の介護経験を持ち、老人ホームへの家族の入所経験もある。老人ホームでのプロのケアを目の当たりにし、プロにしかお願いできないことを学ぶ。
グループホームの入所の是非
みんなの介護(以下、―――) 本日は田崎ご姉妹とその従妹の藤堂さんにお話を伺います。まずは自己紹介をお願いできますでしょうか。
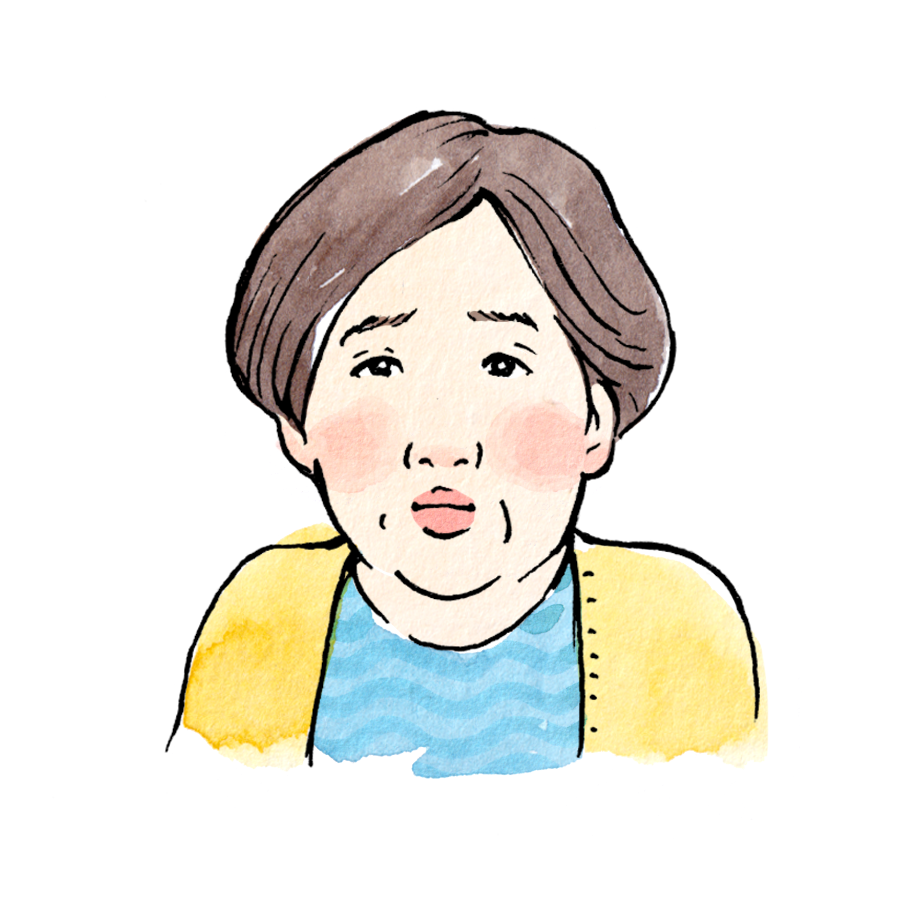
田崎(姉)
田崎ミホと申します。本日は旧姓の田崎家の姉としてお話させていただこうと思います。
要介護3の認定を受けている実母が3年前からグループホームに入所しています。面会に行く度に認知症の症状がひどくなっているような気がして、本当は自宅に“引き取りたい”のですが……。
――― ありがとうございます。グループホームの入所についてのお話は、後ほどお伺いできればと思います。続いてヨウコさん、お願いできますか。

田崎(妹)
妹の田崎ヨウコです。もう亡くなってしまいましたが、義母の介護を10年以上しておりました。
姉同様、面会制限が解除されてからは、毎日のように実母のグループホームに顔を出すようにしています。
――― ありがとうございます。それでは、藤堂さんお願いします。

藤堂
藤堂です。これまでに5人の在宅介護だけでなく、家族の老人ホームへの入所経験もあります。二人よりも経験だけは豊富なので、体験談から学んだことをお話させて頂ければと思います。
――― みなさま、ありがとうございます。早速ですが、田崎さんのお母さまがグループホームに入所されるまでのお話をお伺いできればと思います。
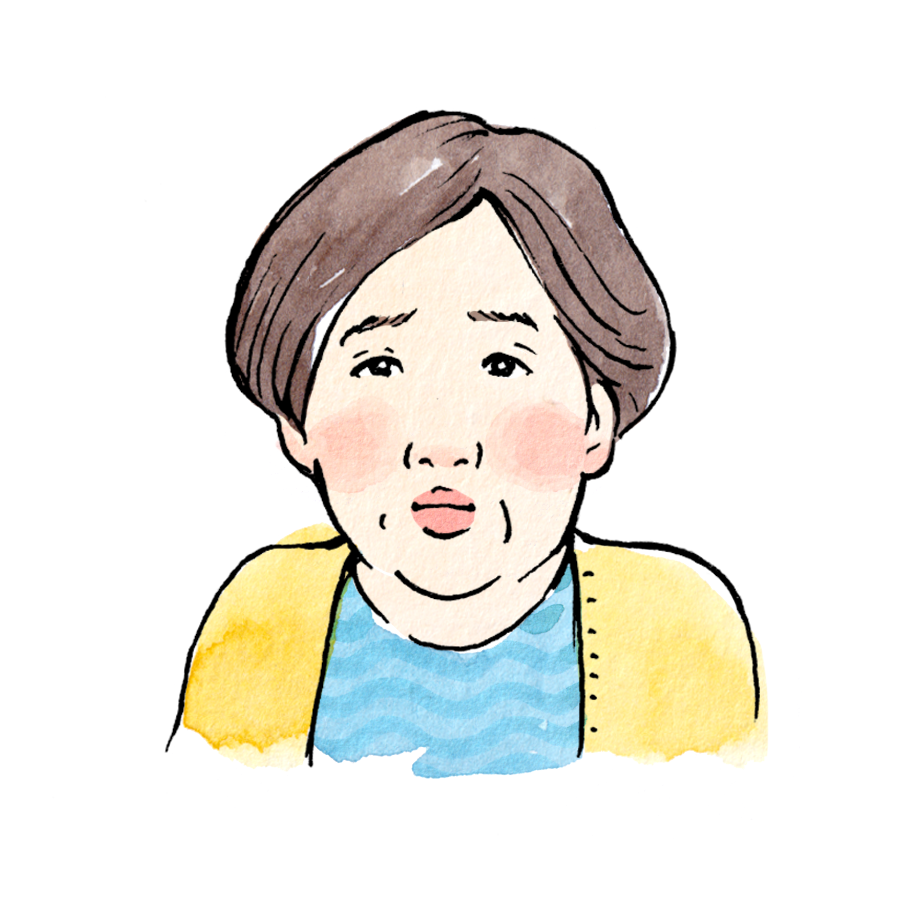
田崎(姉)
10年前に父が亡くなったんです。父は自宅で自転車の修理店を営んでいたので、母もその手伝いをしていました。
母にとって父は人生の全てだと言っても過言ではないというか……。父が亡くなってから、認知症の症状が少しずつ見られ始めるようになりました。いまでも「お父さんはどこ?」と言っているけれども、認知症は始まった当時からいつも言っていました。

田崎(妹)
お父さんが亡くなってからは、独居だったことも原因かもね。私たちのお母さんは本当に“テキパキ”した人で……。親戚一同が私たちの家に集まるようなときも一人で切り盛りしちゃうような人でした。
お父さんが亡くなった時期は、私たちの子どもが就職や進学で地元を離れた時期でもあったから張り合いがなくなったことも関係があるのかも。

藤堂
おじちゃんの三回忌のときに久しぶりにキミエさんに会った時、白髪が増えていて「元気ないなあ」って思ったんだよね。
よく覚えているのが、割烹着を着て「すき焼き」や「揚げ物」の調理をしてくれたキミエさんのこと。誰に対しても「おもてなし」精神があったよね。認知症とは「遠い」ところにいたというか……。
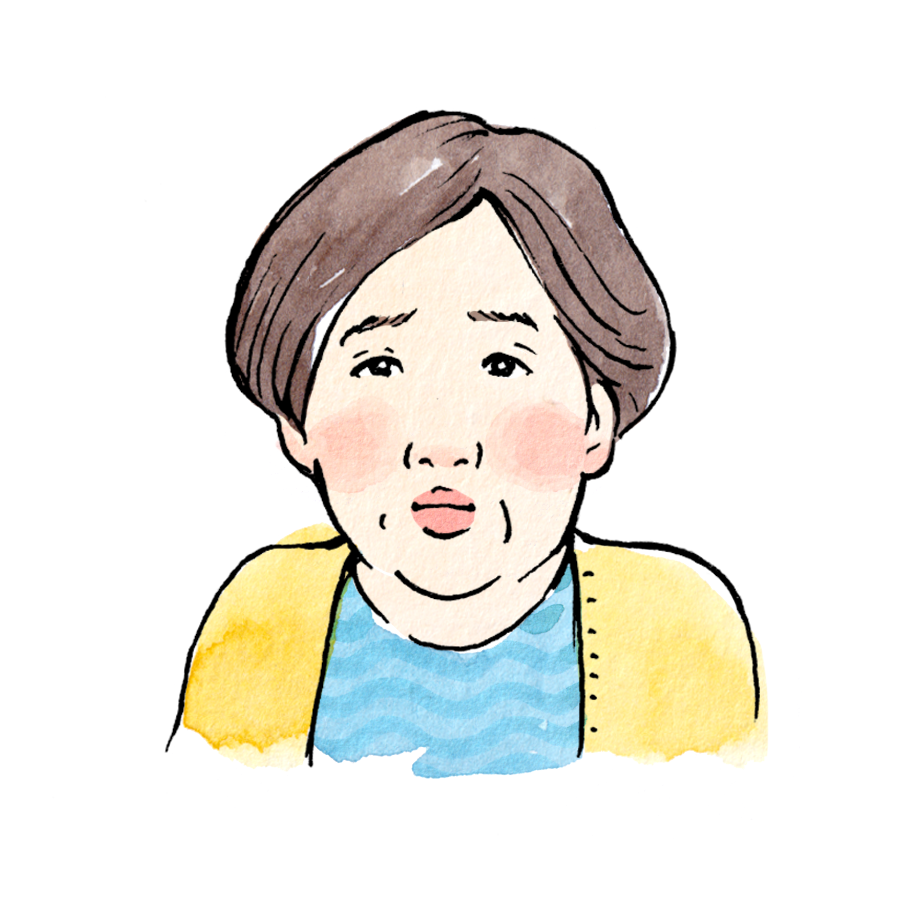
田崎(姉)
そうそう。グループホームでもね、よくわかっていないんだけれども、ご飯の時間なんかになると、率先して入居者の皆さんにお声がけしているみたい。

田崎(妹)
グループホームに入所してもう3年にもなるのかあ。コロナ禍になる前だもんね。コロナ禍で外に行く機会も減ったもんね。
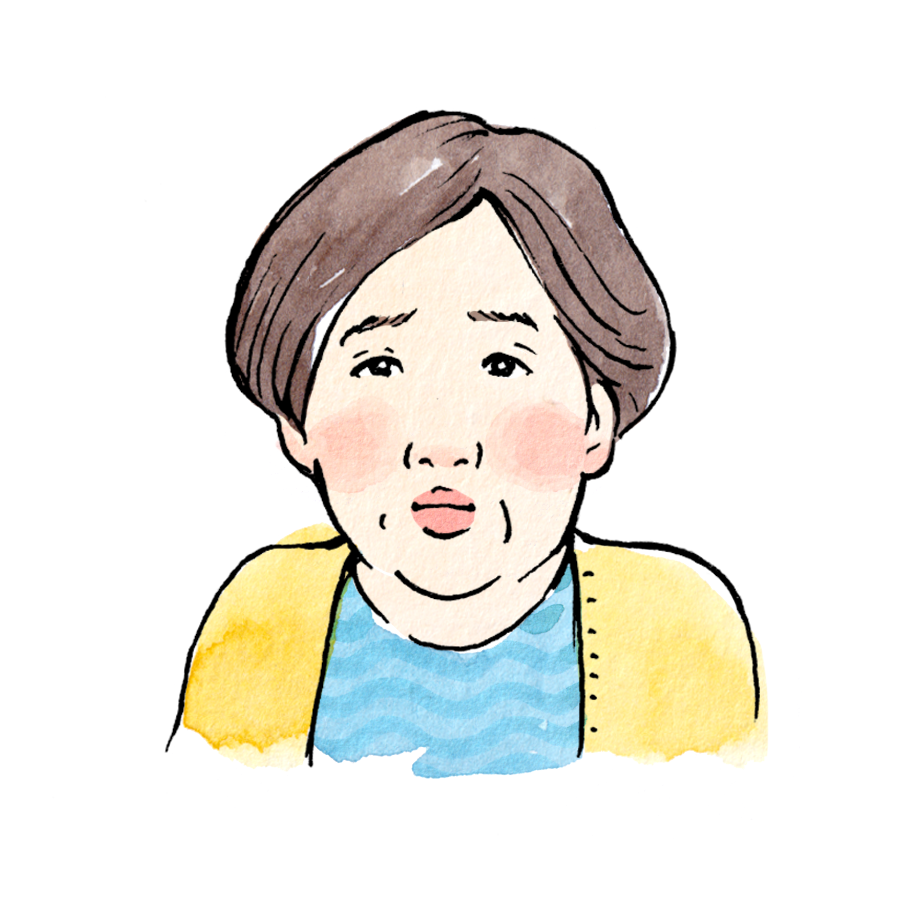
田崎(姉)
うん。デイサービスには時々言っていたけれども、人と接することが日常ではなかったから。
コロナ禍になって、私の自宅で一緒に暮らすことも考えたのですが、母としても父と暮らした家から出たくないということもあって、独居を続けたんです。
ただ、だんだんと深夜の「一人歩き」や一人での買い物が難しくなり、包括センターに相談して……という流れです。

田崎(妹)
姉の夫、義兄が持病を抱えていることもあって、姉の負担がさらに増えることもあって入所の手続きを二人で進めたんです。
相談事

藤堂
少し言い方が冷たく感じられてしまうけれども、認知症になるといつも辛いという状況でもないと思うんだ。本人も多分わかっていないことも多いし、自分が潰れる方がよっぽど大変なことも分かって欲しいかな。
それにグループホームの方々は認知症の方と接するプロだから。そこは忘れないほうが良いよね。

田崎(妹)
うんうん、疲れ切ったお姉ちゃんを見るのは、みんなも辛いからね。

藤堂
義母の友人から「自分を守るのは自分だよ」って言われたときに“はっ”としたんだよね。
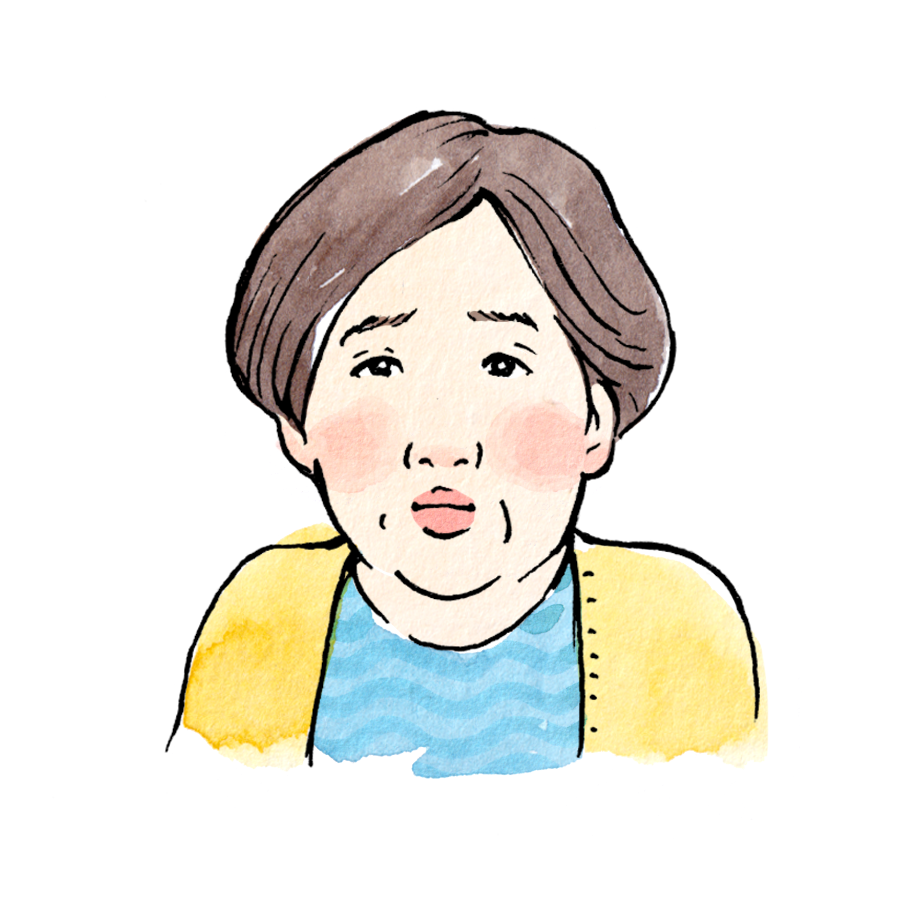
田崎(姉)
そうだね。介護をしているときって“視界”が狭まっているから。

藤堂
そう言われたときに、自分の中で切り替えた。一生懸命やっていても、自分が倒れたら「誰が介護をするんだ」って。それで頼れるサービスは使った方がいいんじゃないって切り替えた。

田崎(妹)
サービスを利用せずに終わっちゃう方々だっているもんね。

藤堂
頼ることに越したことはないと思う。やっぱり家族とプロでは介護の質が違うから。「見る」ことと「看る」ことは違う。精神的なケアだけで十分だよ。
――― 介護に対して不満やストレスはどのように発散すべきだと思いますか。

藤堂
私は「右から左」に流しちゃう。深く考えていないわけではなく、当時勤めていた会社の社長も、時間の融通をきかせてくれたりしたのもありがたかったなって思う。だから、ストレスの発散の原因をどういう風に作らないかを考えたほうが良いと思います。
それでもストレスは溜まるから、息子のサッカーの試合をよく見に行ったかな。元気に頑張っているところを見ると、私も頑張ろうって気持ちになれた。

田崎(妹)
私の場合は、義母の介護をしていたときには、本当にもう「嫌んなっちゃう!」って思ったタイミングで義母が介護施設に入ったんだよね。だから、当時も「こんなもんだったか」って感じだったかな、私は。まあ、大変だったけど。
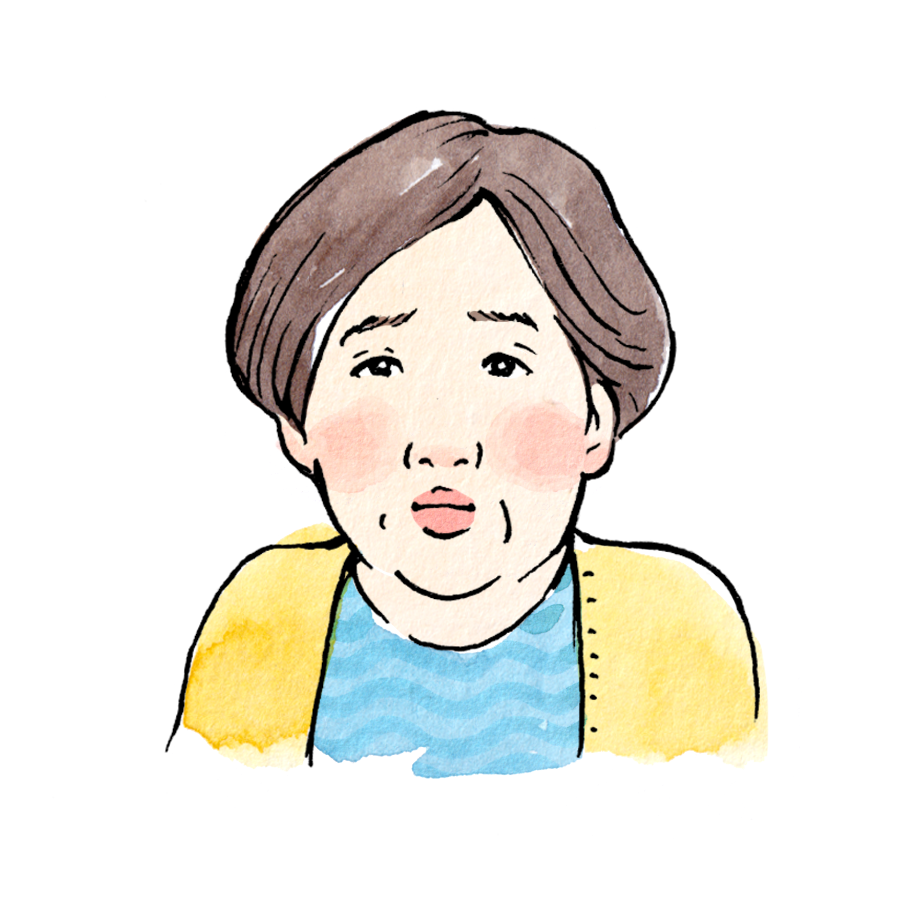
田崎(姉)
「こんなもんか」っていうのがすごいよね。この一言にヨウコの性格が表されていると思う。

田崎(妹)
そうかな。私はどちらかというと、自分で解決しちゃうのかも。ミキちゃんは介護についてよく相談されるんじゃない?

藤堂
そうだね。話すよりも聞く方が多いかな。
私もね、お母さんが「早すぎた」から。で、パタパタって、本当に。自分の子供の手が離れて、介護が始まって……あ、ちょっと待って。そうだ、私、伝えたい話があって…。
藤堂さんの「伝えたい話」とは……? 後編では5人の介護をした藤堂さんの介護経験を聞きます。

「みんなの介護座談会」へご参加頂ける方を募集しています
「みんなの介護座談会」は読者の皆さまに参加して頂く新企画です。皆さまの日々の介護に対する思いをぜひ座談会で語ってください。
以下のフォームより、ご応募をお待ちしております。
参加フォームはこちらをクリックしてください



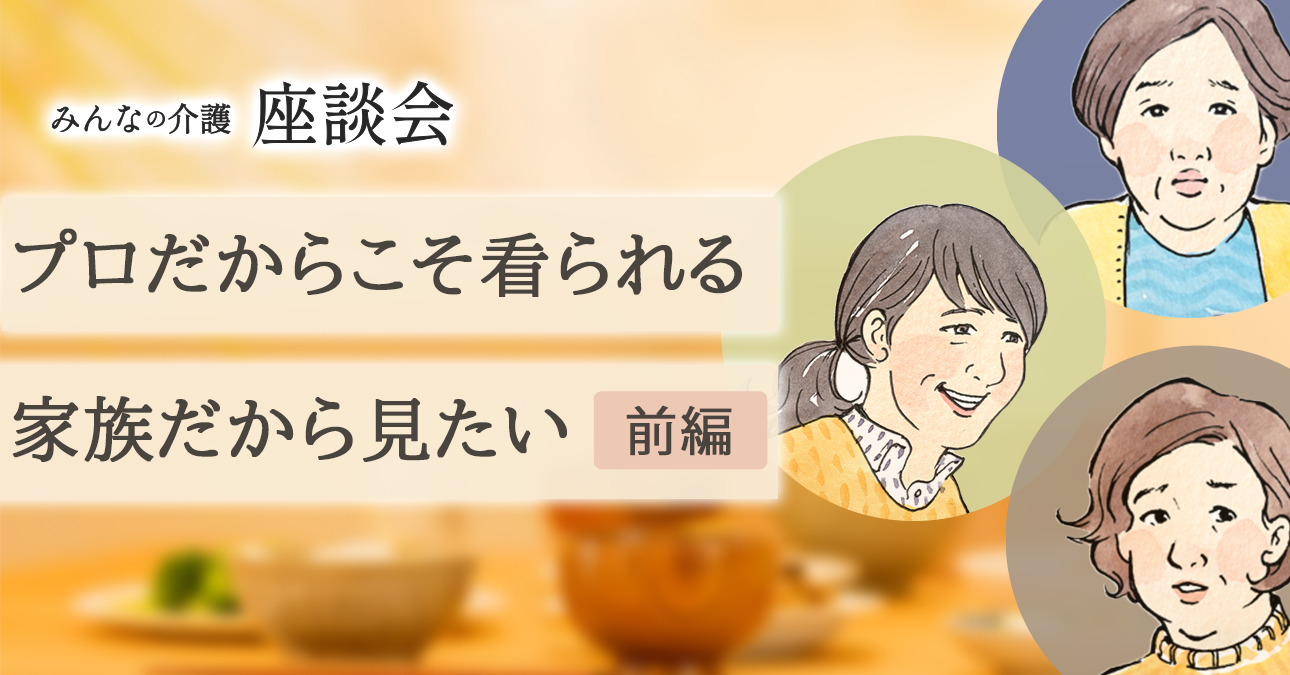
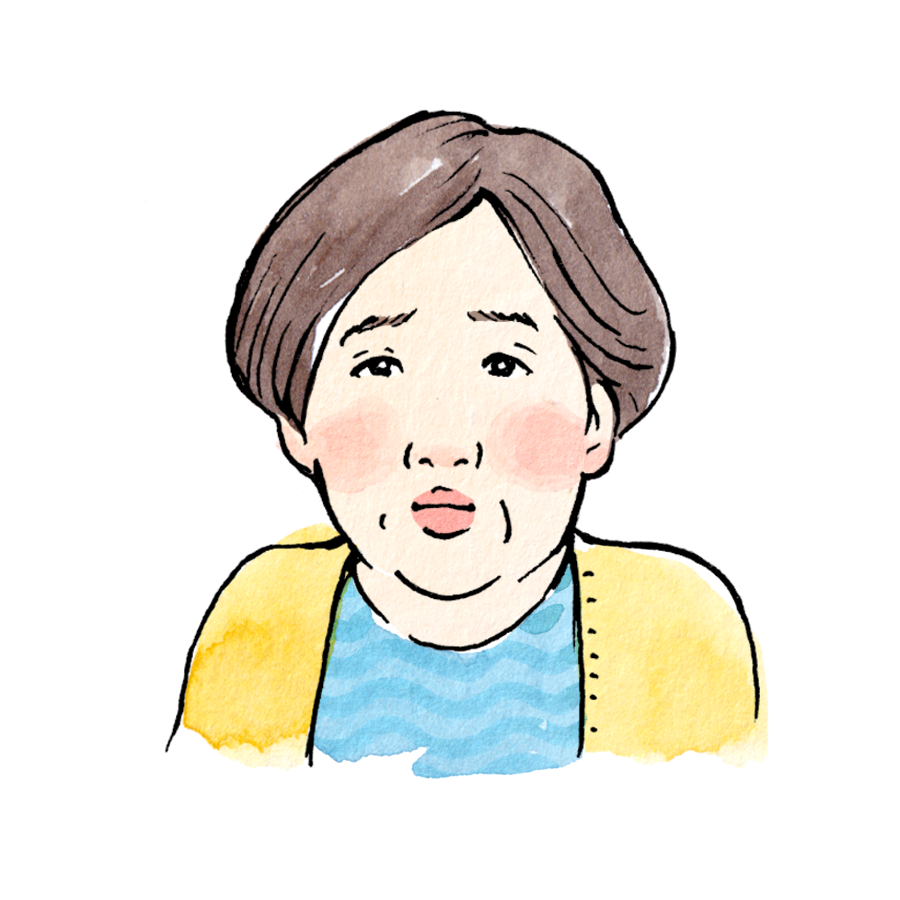


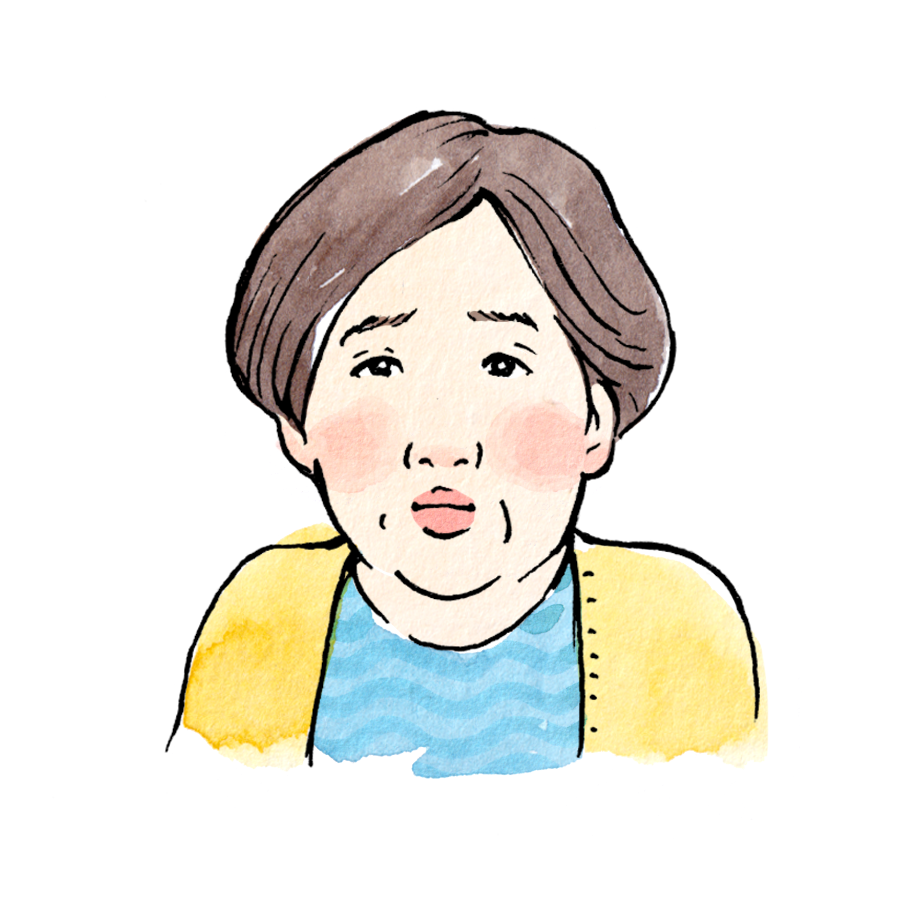 田崎(姉)
田崎(姉) 田崎(妹)
田崎(妹) 藤堂
藤堂